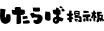レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
YOU、恥ずかしがってないで小説投下しちゃいなYO!
-
どんどんこーい。
-
見上げた空、蒼の彼方にある太陽の光が差し込んで、思わず目を逸らす。
―――刹那、視界の片隅へ煙を上げながら遠くへ落ちていく飛行機。
俺の視線はそこに釘付けになった。
蘇る、悪夢。蘇る、出来事―――
俺は走り出していた。
なだらかな岡を越え、鬱蒼と繁る密林を抜け……俺が着いたのは、狭い砂浜だった。
岩陰に隠れ、辺りを伺い見る。
目の前に広がる光景は、あまりにも自分の遭遇した事故と似ていた。
竹を割ったように真っ二つの飛行機。
燃え上がる、海面。
砂浜に打ち上げられ、動かない人々。
思い出す、血まみれの両親。
動かない、人々。
泣き叫ぶ、幼い頃の自分。
ズズン…と飛行機の一部が弾けた。
腹にまで響くようなその音に、俺は過去の自分を重ねていた。
確かあの時も、同じように……
「お母さん! お父さぁん……あああああぁぁん……」
そう、彼のように泣いたんだ。
砂浜に独り立ち尽くして、動かない塊を見つめながら。
-
俺自信、極度の対人恐怖症みたいな感じだったんだと思う。
もう何年も会っていないヒトから、俺は逃げ出そうとした。
……そして、迂闊に岩陰から出た自分を呪ったんだ。逃げようとしたけど、足が震えて立てなかった。
なんせ今の俺はもう、人間じゃ無いようなみてくれだから。
……だからこそ、驚いたんだ。
「お兄ちゃん、手伝ってくれる?」
少年はこんな姿の俺に怖じけづく事なく話し掛けてきた。
それどころか、まだ小学生位だろうに、両親の『死』を受け入れていたんだから。
「これでよし、と」
落ちた枝と蔦で作った即席の十字架に手を合わせる。
神様はいつだって非情で、子供にばかり試練を与えるのだ。
俺が同じように手を合わせると、少年はしゃくり上げ始めた。
唇を食いしばり、必死に我慢しようとしているみたいだけど、やはり零れる、溢れる。
俺は自分の過去を思い出していた。こんなに、強く泣けていただろうか。
慣れない暑さと環境は辛くて、焼け焦げた人の肉の臭いに嘔吐した。
あの頃の俺は誰もいないこの場所で、真っ暗な夜を歩いた。
……でも今は、俺がいてこの子がいる。
俺は、一人ではなくなったのだ。
-
俺は何がしてあげられるあだろう?
不謹慎ながら彼が来てくれて、よかった。
でも俺には、彼にしてあげられる事はここでの生活を教える事だけだった。
「君……名前は……?」
ようやく鳴咽の治まった彼に尋ねると、彼は振り返って口をパクパクと動かした。
―――刹那、喉を押さえ、困惑の色が広がる。
「お兄ちゃん、手伝って」
それが、俺の聴いた最初で最後の彼の言葉だった。
-
燦々と照り付ける太陽が川面にキラキラと輝き、俺はその川面に穴を開ける。
水しぶきが上がって、俺は獲物を魚籠に入れる。
ガサガサという音が背後に響き、そこから現れる小さな影……
オイオイ、そんな笑顔で手を振られてもなんだかなぁ……
コイツは葉月って名前らしい。
女みたいな名前だけど、実際は男。意外と筋肉質のイイ身体してるんだ。
葉月が居着いてから……というか、事故に遭ってからもう2年が過ぎた。
その間俺はコイツに寝床と食事を与え、共に生活をしている。
どういう事か、事故の処理にくる人間はいなかった。
3日、現場で待ち続けても来なかったのだ。
葉月の言葉は還る事は無かった。
親が目の前で死んだんだ。当たり前かもしれないが、あまりにも酷いだろう。
大好きな歌を唄う事も赦されず、こんな地に放り出されてしまったのだ。
不幸中の幸い、という言葉が正しいかはわからない。
けれど、俺がこの島にはいる。
小さな島だけど、食うに足る食料はあるし、何より俺が久しぶりに会う人を放っておける訳が無いのだ。
-
ちょうど1年くらい経った頃だろうか。葉月は、狩りに着いてくるようになった。
森を駆け、海を駆け、それはまるでアイガモの親子のように。
そして、生活する術を吸収していった。……けど、何故か料理はからっきしだった。
「おわっ!? だから違うって! これは……こう。今みたいにやると手が危ないから、な?」
……言った傍からこれだ。
全く、先が思いやられる。
……何だかこんな話ばかりだと俺が大変な思いをしてばかりだと思われてしまうかもしれない。
でも、それは間違いなのだ。
実際は、俺の方が助けられている。これだけは、間違いない。
人の住まない孤島、そこでの生活は独りで、辛く、寂しいものだった。
今となっては自分の庭のような島も、何処にも人はいない。
……けど、彼は来た。たとえ、どんなカタチであっても。
そして俺は独りではなくなった。
虚空に消える独り言ではなく、話を聞いてくれる相手ができたのだ。
そして何より、彼はよく笑った。
朝日を見る。ご飯を食べる。新しい事を識る。月を見る。星を見る。
笑うのだ。眉尻を下げて、目を細めて、優しく、優しく―――
そして、葉月の笑顔につられて笑う、俺がいた。
一緒にいて、優しい気持ちになるなんて初めての経験だ。
俺は与えてばかりいた訳ではなく、与えられてもいたのだ。
-
―――コンコンッ
葉月が俺を呼ぶ音。木の棒を、打ち合わせる音。
声を失った彼の、唯一の伝達手段だ。たいていは、ごはんが出来上がった時。
………といっても、焼き上がりを見ているだけだけど。
今日は魚と山菜の蒸し焼き。
名前も知らない木の大きな葉っぱで、名前も知らない魚や山菜を包んで、火にかけたもの。
食える山菜を見分けるまでは大変だった。
キノコは特に。何度も腹を壊したし、死にかけた事もある。
でも、だからこそそれが今に活きて、俺達の糧となっている。
「いただきますっ!」
俺の声が響く。葉月も、同じく口を動かす。
手を合わせ、親指で箸を挟むポーズもいつの間にか真似されている。
なんだかそれが可愛くて、俺もつられて笑顔になる。
「うまいな!」と言うと、葉月も笑顔で頷く。それが何よりも嬉しくて、また笑顔になった。
-
とある三日月の夜。やけに明るい夜だった。俺と葉月は、浜辺まで出掛けた。
砂浜に二人で寝そべって、呆と空を見上げた。満天の星空というのは、こういうことなんだろう。
果てしなく綺麗で、底知れなくて、どことなく恐ろしい……世界には俺独りだという風に考えてしまう。
独りの恐怖。喋る相手が、感情を表す対象がいないという恐怖。
果ての無い宇宙をさ迷うように、自分が生きているという証を見つけられない世界。
寒くなんかないのに、寒気がした。葉月が、幻だったりしたら―――
不安を拭うように横を向くと、葉月と目があった。
同じような事を考えていたのだろうか、それとも両親の事を思い出していたのだろうか。
彼は目を潤ませ、そっと俺の腕を取った。
人のソレではないような、毛むくじゃらの腕。ゴツゴツして、傷だらけの腕。
それを彼のしなやかな指先が、擽るように撫でて、絡まった。
上手く表現は出来そうに無い。朧がかる頭の片隅にある懐かしい記憶。
『人に触れる』という事は、存在を確かめるという事なんだと気付かされる。
俺の手の平に、葉月が頭を乗せた。
温かくて、少し重くて、髪が指に絡まる。ただそれだけの事なのに、ひどく安心して、とても心地良かった。
俺はやんわりと微笑む葉月の頭を撫で、もう一度空を見上げた。
夜空があまり好きではない俺だけど、葉月と一緒なら好きになれる。そう思った。
「綺麗だな…」
一人言のように呟くと、葉月は頭を退けて、俺の手を握った。
ゆっくりと、優しく握られる感触。
「綺麗だね…」
そう、聞こえた気がした。
-
すっかり砂浜で寝こけてしまった俺は、葉月に突かれて目を覚ました。
頬や二の腕を悪戯をするようにつつく葉月は、起きた事に気付くと『おはよ』と口を模った。
頭を掻きながら欠伸をしていると、今度は肩を叩かれた。
砂浜を指差し、葉月は俺にこんな事を聞いて来た。
『もしも僕が女の子になったら、どうする?』
それは勿論、言葉ではなくて文字。葉月の、唯一何かを誰かに伝える手段だった。
独特の丸い文字だ。
「女に? まぁなるわきゃないけど、そーだな……」
目を閉じて、考える。
女……この島に来てしまってからは、生きている女には会っていない。
もしも葉月が女だったら俺は、どうしたんだろう―――
そこまで考えて、また肩を叩かれる。
くりくりとした大きな目で、俺と地面を交互に見ている。
地面に目が移ったところで、葉月はまた何かを書き始めた。
「ん? お…よ…め…さ…ん…に…し…て…く…れ…る…? ……は? え? 嫁? 俺の?」
男にこんな事言われて狼狽する俺はどうなんだろう。
ちょっと自分が情けなくて、俺は肩を落とした。
葉月は、未だに目を輝かせて返事を期待しているようだ。
-
仔犬が尻尾を振りながら、餌を待つように。
そんなたとえがよく似合っていた。
「葉月、ある訳ないだろ」
そう言っても、葉月は俺の腕を掴んで離さない。
ぶんぶんと首を横に振って、それはさながらだだをこねる子供のように。
「んー……ま、有り得ないが……葉月なら、喜んで」
俺がそう言った瞬間の葉月の表情の変貌ぶりは凄かった。
つぼんでいた朝顔が咲くように、笑顔が零れた。
洞窟に戻ると、葉月は『正』の数を数え始めた。
彼がこの島に来て以来、初めて電源を入れた『ケータイ』という道具と見比べながら。
その姿を見ながら、ぼんやり俺も考える。俺はもう何年、何日ここにいるんだろう。
もししっかりと記していたならば、と考える。正確な年齢なんて知る術も無かった。
記していたとしても、恐らくその『正』の数も物凄いものになっているだろう。
1年365日、年に73個の『正』が増えていく事になる。おそらく、500個は越えるのだから尚更だ。
-
―――ツンツン
狩って来た獲物(猪)の干し肉を作っていると、葉月につつかれた。
振り返ると、何やら屈託の無い笑みを浮かべて立っている。
葉月は俺の腕をくいくいと引っ張っている。
どうやら連れていきたい場所があるみたいだ。
「ん? しっこ?」
取り敢えずからかってみると、ほっぺをふくらませてジト目で見られた。
「わかったわかった、そう怒るな」
頭をくしゃくしゃと撫で、俺は立ち上がる。
今日はどこに連れてってくれるんだろうか。
葉月はすっかり慣れた足取りで林を駆けた。
もう2年以上もここにいるんだから当たり前といえばそうだけど、最初は大変だったのだ。
突然親を失い、声を失い、彼に残ったのは小さなバッグと自分の身体だけだった。
この島で暮らしていく知識も体力も持ち合わせてはいなかった。
辛そうに山道を歩く葉月を見て何度も背負おうとしたが、彼はそれを頑なに拒んだ。
―――多分、解っていたのだ。
俺を見て、何日経っても救助が来ない状況を見て、生きるには強くなるしかないんだ、と。
当時11歳だった葉月だが、頭が良かったのだ。
勿論勉強がどうだかは解らない。でもそんなものここでは関係ない。
要は、どうすれば生きられるか。自分は今どんな状況なのか。
それをありのままに捉えられる奴なのだ。
-
俺の手を引きながら、おそらくあの浜辺への道無き道を進む。
碧い海の中のような木漏れ日が、俺達を包んでいる。
カラッとした暑さは心地良く、遠くで鳥が鳴いている。
葉月の背中を追いながら、また思い出す、あの頃。
あの小さな背中は、縮こまって丸まっていた背中はもう無かった。
今目にうつるのは、しなやかに一回りも二回りも大きくなった男の背中だった。
この密林を抜けて、顔面岩を過ぎて岩場を少し下る。そうすると、もう海だ。
遠浅の、比較的波の穏やかな浜。葉月は何か伝えたい事があると、必ず俺をここに連れてくる。
もちろん住家にも平たい岩と炭という代用品はあるんだけど、余程ここが好きなのだろう。代用品は、あまり使われなかった。
葉月は漂着物を一通り漁ると、砂浜に腰をおろした。
少し離れた場所にいる俺に小石を投げる。
手招きと自分の隣をポンポンと叩くジェスチャーで、俺は葉月のもとへ向かった。
俺が隣に座ると、葉月は持っていた木の棒で砂浜に文字を書き始めた。
ウキウキと、踊るような手つきで何かを真剣に書いている。
「えー…何々? あ…と…1…ね…ん…? …ん? 何があと一年なんだ?」
葉月は一度俺の顔を見てニッコリと笑い、再び書き始めた。
「1…5…さ…い…? おぉ、15歳の誕生日って事か? もうそんなになるのか……」
-
複雑な、気持ちだった。
この島で暮らし始めて、俺は自分の歳を数えるのを止めた。
祝ってくれる人もいない。誕生日なんて、死へ一歩近付くだけの話だった。
口には出さないが、誰かが救助に来てくれるかどうかもわからないのだ。
無駄な考えは捨てて、今とこれからを生きる事だけを考えて生きて来た。
……でも、葉月はそんな希望を捨てずに、今も生きている。
このまま、ずっとこの島で暮らさなければならないかも……そんな事は、言える訳がなかった。
突然俯いた俺の顔を、葉月が覗き込んだ。
眉をハの字にして、心配そうに俺の腕を掴んだ。
「……心配…してくれたのか?」
葉月は小さくコクリと頷くと、何かを走り書いた。
『どうしたの? どこか痛い?』
小動物のようなつぶらな瞳をパチクリさせながら、また覗き込んでくる。
この優しい子に心配かけてちゃいけないな……
俺は鼻もとを手で擦りながら、不機嫌そうな顔で、葉月を睨みつけた。
硬直する葉月。何故か目には涙が浮かんでいる。
俺はそのままの顔で鼻を啜り、言った。
「……くしゃみが出そうで出ないって、気持ち悪くね?」
寄せては返す、波の音が響いている。
-
……ひっ!
葉月の身体が、僅かに揺れた。
……ひっ…ひっ……
顔に腕を当て、しゃくりあげる。
うん、泣かせてしまうとは予想外だ。
『驚かせんなよなー!』ばちーん!
くらいなモンだと思ってた俺が、今度は狼狽する番だった。
結局、泣き止むまで待つしか出来なかったけど。
「……なぁ、悪かったって」
まだ鼻をぐずりながら、顔を上げない葉月の頭を撫でる。
随分情けない姿だが、気にしない。
独りになってしまうのが、今は何より恐ろしいから。
やっと顔を上げた……と思ったらジト目のまま、棒を踊らせる。
「……う……わかったからそんな目で………ん? せ…き…に…ん…と…る…? わかった、何でもするよ」
葉月は一瞬、何かとても嬉しそうに目を見開いた。
すると、身体を翻し、反対側に何かを書き始めた。
-
こういう時、覗くとしこたま怒られるのを俺は知っている。
以前『ケータイ』とやらを覗こうとしてかなり怒られた。
……複雑なお年頃、ってヤツだろうか。
そんなくだらない事を考えていると、葉月はいつの間にか俺を見ていた。
まだ薄赤い目を擦りながら、手でジェスチャーを送ってくる。
どうやら『見ろ』ってことみたいだ。
「ん? どれどれ……」
俺は立ち上がって、葉月の身体の陰になってる部分を覗き込んだ。
【ぼくと いっしょう いっしょにいて】
「…………プッ」
思わず吹き出した。あ、睨まれてる。
だって、何を真剣に書いてるのかと思ったら、あんまり可愛い事を書いてあるんだもんな。
また頬っぺたを膨らませながらポカポカ叩く葉月の手を制しながら、俺は謝った。
-
「あーすまんすまん。わかったよ、約束する。ずっと一緒だ。―――ほれ!」
小指を差し出して、指切りをする。
メロディーも何も無い、ただ指を絡めて揺するだけの約束。
……なのに、葉月の顔は晴れ渡った。
ニコニコと何度も何度も腕を振る。
時俺は、聞いておくべきだったんだ。気付いておくべきだった。
何故そんな、ある訳がない例え話をするのかということを―――
-
指切りの約束から幾らかの月日が流れて、それでも俺と葉月の生活はなんら変わりは無かった。
変わった事と言ったら、葉月が髪を切らなくなった事くらいだ。
以前は短く切り揃えていたのに、葉月はそれを拒むようになったのだ。
今ではもう、肩甲骨に届かんばかりに伸びている。欝陶しくはないのだろうか?
葉月の声は、未だ戻らない。
すっかり元気を取り戻して、もう俺がいなくても島中を歩き回れるくらいだというのに。
やはりあの丘へ葬った両親の事を、どこか引きずっているんだろうか?
だとしたら、この島にいる限り、葉月に安息は訪れないのだろうか。
隣に眠る葉月を起こさないように外に出て、星空を見上げる。
あの幾千幾億の星々のどれかが葉月の両親なのだろう。
俺はそのまま座り、暫く星空を眺めていた。
-
「ねぇ、早くこっちにきて…」
誰の声だろう? 誰が俺に話し掛けてるんだ?
声のする方は、霧がかって霞んでいる。
自分の手先も覆われるような視界の中、俺は声だけを辿って走った。
「こっちだよ、はやくぅ…」
瞬間、微かに見える黒い影。
俺は手を伸ばし、それに触れた。
辺り一面を覆っていた霧は晴れ、現れたのは久しく見ない、人…
女性が、微笑んでいる。
困惑するしか出来ない俺に、女は言った。
「……もうすぐ、逢えるよ」
何の事だかわからない。
でも何だか、見たことのあるような笑みだ。
女はそのまま踵を反し、深い霧の奥へと消えていく。
彼女が一歩踏み出す度、霧は濃くなる。
追い掛けたくとも体は動かず、問い掛けたくても声が出ない。
霧は段々と濃く、深くなっていき、遂に視界から女は消え―――
-
蒼い、空が広がっていた。
そうか、空を見たまま寝てしまったのか。
俺は背中の土を掃うと、川へと下りた。
葉月が採って来たらしい山菜を洗っている。
「おはよ、採って来てくれたのか?」
葉月は立ち上がり、振り返って言葉の代わりに笑顔で応えた。
俺も笑顔で応え、顔を洗うと、隣で葉月は髪を洗い始めた。
葉月の髪は少し癖のついた直毛で、光に透かすと赤く見える。
そういえば、夢の中の女も似たような―――
ないない、変な事考えるのは止そう。葉月が変な事ばっか言うから考えちまうだけだ。
ブンブンと頭を振ってその思考を振り飛ばすと、頭から水を被った。
葉月は俺を見て、はしゃぎながら髪の水気を抜いていた。
今日も焼け付くような太陽が惜しみなくその力を差し込む。
俺は頭をガシガシと掻いて気合いを入れるのだった。
-
「葉月、そういえばなんで"お嫁さん"なんだ? 葉月は男が好きなのか?」
俺はデリカシーがないらしい。葉月にひっぱたかれた。
デリカシーってなんだろ。旨いのかな?
まぁそれはさておき、葉月がご機嫌ななめのようですよ。
ほっぺを膨らませたまま、ジト目攻撃が始まったりね。
で、決めた。貢ぎ物で機嫌を取る。んでしっかり謝る。
……ということで、俺は浜辺に向かって歩き出した。
目的のモノを見つけた頃には、大分陽が傾いていた。
目的は、珊瑚の欠片。以前見つけたモノは、墓に供えてある。
まだ葉月には見せたことがない、俺の両親の墓。一応俺なりに考えて決めた。
無事仲直り出来たら、明日は葉月に両親を紹介するんだ。
―――でもまぁ、そううまくはいかないものらしく、食糧を調達して帰る頃には暗くなっていた、と。
火の側には葉月が食べたらしい魚の骨が残ってて、本人はもう寝てた。
ちょっと涙が出た。
-
葉月の笑顔が見れないのがこんなに辛いなんて思わなかった。
まぁ自業自得なんだけど。
そんなこんなで肩を落としながら、俺は捕って来た鳥の血抜きをして夕食の準備をする。
鳥は明日のために取っておいて、蒸した山菜と保存用の肉で終了。と、思いきや。
魚籠には魚が残っていた。平石には『食べて』との書き置き。
またちょっと涙が出て、それがまた妙に美味くて、心まで温まった。
満足しながら床につこうとした時だった。
何気なく撫でた葉月の頭がやけに熱い。
顔も赤く、息も荒くなっている。
普通なら風邪だと思うのだが、あまりの高熱に俺は狼狽した。
水を汲み、ボロボロの布切れを濡らして額に乗せてもすぐに温まってしまう。
苦悶の表情を浮かべる葉月の手が、何かを求めるように宙をさ迷う。
こんな時、何も葉月を苦しめなくてもいいじゃないか。
俺は葉月の手を取り、必死で葉月に呼び掛ける。
「葉月っ! おい葉月ぃっ!!」
洞窟に虚しくこだまするのも気にせず、俺は呼び続けた。
―――そして、俺は目を疑ったんだ。
葉月の手が、肩が、身体が、縮んでゆく―――
しなやかな筋肉は見る間に衰え、男らしい骨格が、筋張った身体が丸みを帯びてゆく。
髪は更に伸び、それは既に身長と変わらない程の長さになっていた。
―――俺はまた、夢でも見ているのだろうか?
そう思える程、不可思議な現象。
目の前で、有り得ない事が起こっていた。
-
葉月は翌朝には目を覚ました。
―――何故だろう。
もう前の彼の面影は無くなってしまったはずなのに、彼女は彼で、彼は彼女だった。
当たり前といえばそうだろう。突然彼の心が消えてしまう訳ではないのだから。
暑い陽射しも昨日と変わらなくて、あの砂浜も昨日と変わらなくて、でも少しだけ変わったもの。
俺と彼の、彼女の会話。そしてある意味での関係だった。
「おはよう」
俺が笑いかけると彼も笑って、身長ほどもある髪を手に取ってまた笑った。
「知ってたから、あんなコト言ってたのか?」
彼は、笑って頷いた。俺はつられて笑いそうになるのを堪えて、言った。たどたどしくではあるけれど。
「何で、女になる? 今の人は、そう生まれてくるのか? それともお前は―――」
人間では、ないのか? そう言いかけて、口を押さえる。
人間でない訳が無い。今まで、一緒だったのだ。3年もの間、片時も離れずに―――
『多分、僕が生まれたすぐ後位からかな。ある事が起き始めたんだ』
勝手が違う、といった様子で葉月は砂浜に文字を綴る。
何かを思い出しながら、それは記憶を手繰り寄せるように続けられた。
-
葉月は翌朝には目を覚ました。
―――何故だろう。
もう前の彼の面影は無くなってしまったはずなのに、彼女は彼で、彼は彼女だった。
当たり前といえばそうだろう。突然彼の心が消えてしまう訳ではないのだから。
暑い陽射しも昨日と変わらなくて、あの砂浜も昨日と変わらなくて、でも少しだけ変わったもの。
俺と彼の、彼女の会話。そしてある意味での関係だった。
「おはよう」
俺が笑いかけると彼も笑って、身長ほどもある髪を手に取ってまた笑った。
「知ってたから、あんなコト言ってたのか?」
彼は、笑って頷いた。俺はつられて笑いそうになるのを堪えて、言った。たどたどしくではあるけれど。
「何で、女になる? 今の人は、そう生まれてくるのか? それともお前は―――」
人間では、ないのか? そう言いかけて、口を押さえる。
人間でない訳が無い。今まで、一緒だったのだ。3年もの間、片時も離れずに―――
『多分、僕が生まれたすぐ後位からかな。ある事が起き始めたんだ』
勝手が違う、といった様子で葉月は砂浜に文字を綴る。
何かを思い出しながら、それは記憶を手繰り寄せるように続けられた。
-
『15才か16才までに、エッチしないと女の子になる病気……というよりも現象?』
何だそれは? そんな事ある訳……無い、とは言えずに、俺は押し黙った。
現に目にしてしまったのだから、本当にそんな事が有り得るのだ。
俺が世界から隔離された後で、そんな世界になってしまっていたのだ。
『原因は不明。性転換率80%強。おまけに僕は―――』
葉月は、ためらいつつも続きを書き出した。
信じられないような言葉が、そこには並べられていた。
『ずっと、人を好きになれなかった。親に管理されるような生活で、どんどん笑えなくなってった。
外に出るのは学校の時だけ。僕は与えられた課題と練習をこなす、親の叶えられなかった夢を叶える道具。
反抗は許されずに、縛られた毎日だったんだ。
学校でもね、友達なんて一人もいなかったよ。当たり前だよね、一番楽しい休み時間に、僕は楽譜と睨めっこだもの』
彼は、彼女は笑った。
でもそれは俺の見ていたいモノではなく、困ったような、寂しそうな笑顔。
俺が思うに、彼女はなまじ頭が良いがためにがんじがらめになってしまったんだろう。
親が喜ぶには、怒られないには、叩かれないには、どうすればいいんだろう?
友達が欲しいのに、一緒に遊びたいのに、なんという不器用な求愛行動なんだろう。
-
俺は胡座をかいて、葉月を膝の上に載せた。
前とは違う感触と、伸びた髪がくすぐったい。
俺は彼女の髪を手で梳きながら、そっと肩に手を回した。
小さく、小さくなってしまった彼女は何かを書き、俺の腕に手を添えた。
『もっと強く……』
折れてしまいそうな葉月の身体を、俺は包み込むように抱きしめた。
何だか変な感じだ。あんなに固かった身体が、吸い付くように俺の肌に重なっている。
始めて味わう感触だ。もっと、もっと、もっと……ずっと、触っていたいような。
しばらくして葉月は身じろいだ。
俺が放すと、彼女はぷはっと息を吐いて何かを書き、俺を見上げた。
『お兄ちゃん、名前、なんてゆーの? ほんとに今頃だけど』
う、そうか。葉月には聞いたくせに名乗ってなかったか。
スマンスマン、と頭を掻きながら、指で砂浜をなぞる。
熱い砂の下から、湿った砂が見えた。
「俺は『旭』あさひ、だ」
-
呼ばれることの無い名前を、俺は何年振りに口にしただろう。
親から貰った大事な名前も、この島で暮らすのには全く使う必要が無かった。
いや、名前を忘れようとしていたのかもしれない。
昇る陽を見る度、名前を呼んでくれた両親の顔が思い出されるのだから。
両親で一つ、思い出した。
葉月が女になったゴタゴタの内に忘れていたけど、彼女に紹介しようと思ってたんだ。
「葉月、俺の親、見てみるか?」
葉月は驚いたように目を見開いた。
生きてるの? この島にいるの? そう言いたげに、目をキラキラと輝かせている。
顔が少し小さくなったせいだろうか、一際目立つ両の目で俺を見据えている。
「スマン、生きてはないんだ。 期待させちまったか?」
葉月はプルプルと首を横に振った。髪が遅れて顔に纏わり付いている。
シュンとした様子で、彼女は砂浜をなぞりだした。
『ゴメンね、わかってるはずなのに、つい…』
-
社会から離れた場所で生活するのに必要なのは、脳天気さと適度なバカさだ。
勿論運動神経だとかサバイバルの知識もあれば役立つ。
でも先ず必要なのは前者である。
幾ら後者があろうとも、人の死や孤独に苛まれれば弱るし役に立たない。
頭の良さも人を思いやる気持ちも、時としては辛いモノになってしまうのだから。
「バカ、気にしちゃないよ。そら、行こうぜ」
俺は葉月を引っ張り上げて立たせると、腰布を叩いて砂を落とした。
彼女の背筋は丸まっていて、傍目にもまだ気にしていると判る。
まったくそこまで気にする事ないじゃないか……
俺は彼女の腋に手を差し込み、高々と抱え上げた。
手に当たる柔かい毛と肉の感触と、軽くなってしまった重みを感じながら。
-
深緑の森の中は微かに湿り気を帯びていて、鬱蒼とした雰囲気は小鳥達が掃っていた。
俺達はその愉しげな歌声と共に、獣道を進んでいる。
「葉月、身体は何ともないのか?」
歩を止めて振り返ると、葉月は笑顔で何かを書き出した。
微かに肩が上下し、長い髪が所々背中に張り付いてしまっている。
小中学生並の身体では、やはり体力もそれなりに落ちてしまっているようだ。
『ちょっと、ゆっくりにしてもらえるとうれしい』
やっぱりそうみたいで、上げた顔は汗が頬を伝っていた。
思えば歩幅も速度も元のまま……
そっか、と頭を掻いたところで体力が回復する訳もないのだ。
「んー……そっち向いて、脚開いてみ?」
怪訝な表情で振り返る葉月は、おずおずと脚を開いた。
瞬間、俺は葉月の股に頭を突っ込み、そのまま持ち上げる。
『………!……!!』
「おわっ!? こら、暴れんなって!」
どうやら肩車はお気に召さないようだ。
力いっぱい足をジタバタされた揚句、頭を叩かれた。
散々な抵抗の後、結局は頭を抱えるようにしがみつく事で落ち着いたらしい。
肩を掠める葉月の髪がくすぐったいけど、これなら多少は休めるはずだ。
「あと10分くらいだから、我慢な」
返事の代わりに髪が縦に揺れた。
頷いているのだろう。俺はゆっくりと歩を進めた。
-
赤や黄の果物をかじりながら進むと、森の出口が見えた。
俺が【お爺さん】と勝手に呼んでいる枯れかけた目印である樹は、前と変わらずそこにあった。
森を抜けた先は菜の花に似た花の咲く丘だ。
一面に広がる背の低い花達は、年中風に揺られて蜂や蝶と共存していた。
この丘の端……大きな岩が突き出た場所に俺の父さんと母さんが眠っている。
「よ……っと。葉月、花取って来てくれ。なるたけ綺麗なの」
葉月を降ろした俺は葉月にそう頼んで、岩へと向かった。
葉月は髪を揺らしながら、花畑を走り回っている。
岩は髭のような草に囲まれていた。
花が生い茂り、草木は豊かにその葉枝を揺らす。
そんな自然の中で唯一人の造り出した鉄の板のようなもの。
不自然な、昔の俺に造ることが出来たやっとの墓標。
文字の部分は錆びてしまっているが、【お父さん お母さん】と書いてあるのは読み取れた。
ここに来るのはいつぶりだろうか。
辛いことばかりでろくに訪れる事も出来なかった。
いや、ここに来る事自体、辛いことだったのだ。
冷たい、動かない、もう笑わない両親を思い出すから。
思い出の中の両親はいつも笑ってて、俺の名前を呼んで、優しくて、温かくて……
-
ポン、と肩を叩かれて俺は我に返った。
振り返ると、葉月が花を抱えて立っている。
「お、あぁ……サンキュ。ここに供えてくれ」
葉月は花を置くと振り返り、俺の頬に手を当てた。
……どうやら泣いてしまっていたらしい。いい大人が恥ずかしい話だが。
『どんな人たちだったの?』
葉月は俺の隣に座り、そう尋ねてきた。
どうしてだろう。また目の前がぼやけてきたんだ。
誰かにそんな事を聞かれるのは初めてだった。
自分でもうろ覚えな親の顔は、思い出せば思い出すほど溢れてきて止まらない。
怒られたり、励まされたり、微笑みかけたりしてくれた。
元気だった頃の思い出が、言葉に出来ない程溢れた。
『うらやましいなぁ……』
葉月は俺の肩に頭を添わせながら、そう書いた。
聞いた感じだと、俺の親の話は自慢話にしか聞こえないような話なのだ。
『ね、ボクみたいなのでもちゃんとした親になれるのかな?』
葉月はどんな気持ちでそう綴ったのだろう。
俯いたまま、顔を上げようともせずに。
-
どう答えればいいのだろう。
そんな事は考える暇もなく、俺は思ったことを口にしていた。
「"なれるか"じゃなくて"なる"んだろ。親に。今から悩むと疲れるぞ」
ふと、葉月の頭から震えが伝わって来た。
何事かと目を向けると、お腹を抱えて笑っている。
「な、なんだ? なんか変な事言ったか?」
元気付けようと、というかほぼ考え無しでの発言でここまで笑われるとは思っていなかった。
葉月は目を擦りながら、必死に笑いを押さえようとしている。
『悩んでるのが馬鹿らしくなっちゃった。ね、そろそろ戻ろ』
葉月はそう言って立ち上がり、何本かの花を摘んだ。
「葉月、それ持って帰るのか?」
駆け寄って来た葉月は大きく頷き、俺をしゃがませ、肩に飛び乗った。
何だか存外気に入っているようで、足がピコピコ動いている。
やれやれ、と俺は立ち上がり、帰路に着いた。
来る時感じていた妙な抵抗みたいなものは、もう感じなくなっていたんだ。
-
「元々一人だったんだ。 そんなに心配すんなって」
自分の発した言葉の筈なのに、それはただの強がりでしかなかったのだ。
………葉月がいなくなって、何年が過ぎただろう。
そう、葉月は喋れなかったし、独り言のようなものだったと思ってもう諦めよう。そう考えようとした。
笑って送り出したことを今更後悔したりなんかして、俺は改めて自分の女々しさを知った。
―――あれは、確か2年前だろうか。俺の両親の墓参りをしてすぐの事だった。
船が、近くを通り掛かったのだ。小さな小さな漁船。待ち続けた筈の、救助。
俺達はボロボロになったシャツを旗代わりに、精一杯それを振り、祈り続けた。
頼む、見てくれ……!
誰か、気付いて……!
その時、思った。神様は、いるのだ。
徐々にこちらに向かって来る船では、恰幅の良い船員が手を振っている。
でも、俺は―――
『帰れるの?』
葉月は素直に嬉しそうに砂浜に文字を書いた。
その笑顔が嬉しくて、でも切なかった。だって、俺は―――
「葉月、お前は一人で帰るんだ」
-
「・・・?」
何を言っているのか解らない、と言ったように、葉月は首を傾げた。
―――そんな顔しないでくれよ。 決心が鈍っちまうだろ?
長い、永い、俺のこの島での生活。
爪はいつの間にか硬く鋭く発達し、体毛もヒトのそれとは思えない程に覆われていた。
進化。 退化。 どんな言葉で表せるかどうかなんて、俺には解らなかった。
………けれど一つだけ、ハッキリと解ることがある。
俺は、世界から取り残されているのだ。
諦めてしまっている、と言われてしまえばそうかもしれない。
怖いのか、と言われてしまえばそうかもしれない。
「葉月……」
だから俺は、葉月にしっかりと、言わなければならない。
この島で俺と暮らした日々を。
この島であった数々の出来事を。
この島で見つけた悠久とも言える時間を、お前は手放さなければいけないんだ、と―――
「俺は、友達も、親戚も、住むところも、覚えちゃいない。 でもお前は違う。 そうだろ?」
葉月の肩がピクリと震えて、目に涙を一杯に浮かべて、顔を上げる。
反論も何も、出来やしない。葉月の腕(声)は、俺が封じているのだから。
-
「俺はこんなだ。もうヒトじゃない。でもお前は違う。そうだろ?」
幾ら葉月が身じろいだとしても、幾ら腕を振り払おうとしても、俺は葉月を放しはしない。
【お兄ちゃんはヒトだよ】
【一緒に帰ろう】
そんな言葉、聞きたくないんだ。葉月は、一番言って欲しい事を言ってくれるから。
「俺はもう、離れすぎたんだ。それに―――」
葉月は、下を向いて動かない。
俺は、そんな葉月に話し続ける。
葉月が来てからの日々が、頭を過ぎった。
声を、失ってしまった事。
魚を捕るのが、徐々に上手くなっていった事。
塩辛い料理を二人で食べた事。
星を見た事。
喧嘩した事。
森を駆けた事。
女になった事。
葉月が笑っていた事―――
-
「……はァ……」
何度目かわからない溜め息が、零れ落ちる。
全く情けない事に、この溜め息がここ2年間の癖になりつつあるのだ。
葉月は元気にしているのだろうか?
何故俺も一緒に帰ると言わなかったんだろうか?
俺の事はもう、思い出になってしまったんだろうか?
全て自業自得だってのは解ってる。
自分の弱さが、今へと繋がってしまったのだ。
あの時も、こんな空だったっけ。
葉月の乗った船が、大きな入道雲の方へと消えていったのだ。
俺は岩場の陰で、遠ざかっていく船を見つめていた。
―――と、思い出すのも段々と辛くなってきた。
もう、葉月はいないんだ。洞窟に帰って、飯でも食って、寝てしまおう。
俺は高台から降り、ゆっくりと洞窟へと戻っていった。
西日が、全てを紅く染めていた。
-
『お兄ちゃんへ
色々と言いたいことはあるけど、今はやめておきます。
まず、今までありがとう。こんな私を見捨てないでくれて、本当にありがとう。
このメモは、ちゃんと読んでもらえるかな?
お兄ちゃんの事だから、薪代わりになっちゃわないか心配だけど、時間が無いから簡単に書くね。
またね! 葉月』
「……?」
重ねられた薪の奥に隠されていた小さい紙切れには、あの丸文字で手紙が書いてあった。
色々あるという言いたい事を、全て聞きたかった。
一度でいいから、名前を呼んで欲しかった。
ずっと二人で、暮らしていければよかった。
本当はもう、救助なんて待ってはいなかったのに―――
『帰れるの?』
あの言葉と瞳の光が無ければ、俺は引き止めてしまったのかもしれない。
葉月のやりたいようにさせてやりたかった。それがもし、自分と道を分かつ事になっても。
……俺は葉月の足枷にはなりたくないから。
-
自分でも酷く、矛盾を感じた。
放したくないのに、放す。 待っていない救助を、喜ぶ。
言い難く複雑な気分だ。まるで操り人形のように、自分が自分ではない感じ。
思い通りに動いてはくれないこの身体は、誰のものなのだろう。
燦々と降り注ぐ太陽に手を翳して、俺は今日も変わらず獲物を狩る。
何も変わらない、ただ葉月のいた時間が夢なのだ。そう自分に言い聞かせながら。
終わり?
久々にどっちつかずのエンドだと思った。
-
ずっと気になっていた無人島物語…ハッピーエンドになると思ってたのに…
「またね」の最後のメモを書いてるときの葉月たんがカワイソス
だがGJ!
-
【―――行き。TS、69便にお乗りのお客様、7番搭乗口までお越し下さい】
私は、人の波を掻き分けるように7番搭乗口へと向かった。
何て事は無い。まだ時間には余裕があるのだけれど、万が一にでもあの人に見つかる訳にはいかないから。
「えっと、7番7番……あったぁ♪」
『7』と書かれたプレートを見つけた私は、子供のようにはしゃいだのだろう。
やっと…やっと、会えるのだ。ずっと会いたかった、けど会えなかった、お兄ちゃん。
この3年間、それだけを目標に過ごして来た。
朝日を見る度に、瞼の裏にはいつもあの風景が浮かんだ。
時は八月。太陽は全てを焦がすかのように照らし、私の心は焦がれる。
夏の暑い日々を好きになったのも、やはりあの島を思い出すからだろうか。
日本の暑さとは違う、カラッとした空気。一年を通しての強い陽射しが心地良い、南国。
今でも鮮明に思い出せる澄んだ満天の星空は、私の一番のお気に入りの場所……
「……く様……お客様、どうぞ」
「……ぇ? は、はいィッ!」
危ない危ない。楽しみすぎて行けなくちゃ元も子もない。
私は検査ゲートをくぐり、手荷物を受け取ると、そそくさと廊下を急いだ。
-
廊下の窓からは、これから乗る飛行機が見えた。
既に乗り込んでいる人達がいて、親子連れのお客さんがいるのも―――
不幸中の幸い…とでも言うのだろうか。私は飛行機を恐れたりすることは無かった。
両親の死とそれっぽっちの事。些かバランスの悪いものだけれど、私ににとってはとても大事な事……
こんな事を考えちゃう私を、お兄ちゃんは叱るのかな。
でも、私は―――……
「葉月ちゃん!」
「!? 江藤さん……」
ゲートの向こう側から、あの人が顔を覗かせる。
額に大粒の汗を浮かばせ、肩を上下させている。
当然だろう。自ら担当している私が、突然姿を消したのだから。
「葉月ちゃん……どこに行くつもり? 明日からの予定はどうする…」
「ごめんなさい。私、行かなくちゃ……」
「契約だってある! 社長にも、スタッフにも……皆に迷惑がかかるのよ?」
「……ちょっと、お墓参りに行くだけだから……」
「葉月ちゃん……」
ちょっと、だなんて嘘―――
ごめんね、江藤さん。
私は、それでも行かなきゃ。
-
恩を仇で返すなんてしたくはなかったけど、もう引き返せない。
私はこの道を選ぶのだ。
自己中心的だと言われても、無責任だと言われても―――
機内のアナウンスが響く。
私は徐々に流れ始める景色を見つめながら、3年間を思い出す。
失ったはずの声が、少しずつ戻って来た事
私を慕ってくれる人達がいた事
私を大事に想ってくれた人がいた事
勝手だけれど、全てを捨てて、私は私の道を行く。
私の中でのあそこでの日々が、今も色褪せる事なく残っているから。
これで、やっと―――永かったなぁ………
もうすぐ―――もうすぐ、会えるんだ。
雲の上から見る海は碧くて、空は蒼くて……
私は、再会に胸を躍らせていた。
-
「HAHAHA! ……しかし、ホントにいいのか?」
「えぇ、お願いします」
ゆっくりと、滑るように、船は岸を離れ、私は遠くを見つめた。
おじさんが変わってなくてよかった。
彼は、お兄ちゃんの事を唯一知っている人だから。
船を出してくれたおじさんは、3年前、私をあの島から連れ出してくれた人だった。
それだけでなく、帰国の手続きやそれまでの宿など、私に世話を焼いて下さった方なのだ。
そして今も秘密を守り、今回の私の暴挙にも目を瞑り、あまつさえ私を島へ渡してくれようと言うのだ。
おじさんにはお礼をしても足りないくらいの恩がある。
『お礼をすることが出来ないのが悔しくて申し訳ない』
と言ったら、
『あの島じゃなかったら気付けなかった。礼なら空に向かって笑ってやりな』
と言われてはぐらかされてしまった。
……懐かしい匂いだ。
おじさんの漁村を少し離れただけだというのに、もうあの島の匂いがする。
潮風と、太陽と、海鳥の鳴き声。
焼き付くような暑さと海の碧さは、私のいたあの頃と少しも変わってはいなかった。
「ハヅキ、見えて来たぞ」
おじさんの声に、指差した方向に、私は目を奪われた。
ああ……ああ―――私は、帰って来たのだ。
-
「じゃあ、ホントにこれで………ありがとうございました!」
「あぁ、必要なモンがあったらまた持って来てやっからよ」
「いえ、そんな……そこまで迷惑掛けるわけには―――」
「そうか。俺の親切は迷惑、か……」
「いえ、決してそういう訳では――!」
「―――なら、有り難く受け取れよ?」
「おじさん……」
「じゃあ、またな!」
幾つかの会話が終わるや否や、おじさんは帰って行った。
どこまでお人よしなのだろう。私は、海に背を向けて歩き出した。
あの洞穴で、あの川原で、お兄ちゃんは今日を生きているのだろうか。
海岸からの林を抜けると、私がいた頃よりも幾らか草が増え、それだけの月日の経過を感じる。
生きるためだけに狩り、生きることを楽しんだ私達。
笑って、怒って、冗談をいって……そんな事を思い出しながら歩いていると、私の目にあるものが飛び込んで来た。
古ぼけ、交差した二つの墓。そして―――毛むくじゃらの背中。
会ったら最初に何を言おうか考えてた。私はアドリブが利かないから、頭の中でずっと整理してた。
―――けど、意味が無いことだったんだ。一目見ただけで、私の足は駆け出していた。止まらないんだ。
お兄ちゃんが私の方を振り向いて、私は地面を蹴る。両腕を広げたお兄ちゃんが、私を抱き留める―――
「ただいま!」
おわり
-
最後の最後にsage忘れる俺は死ねばいいのにorz
-
いつの間に…
ハッピーエンド ありがとう♪
-
泣いた
-
いつも初菜の傍に居て、ずっとあの笑顔を見ていたい。そう思っていた。
彼氏・彼女の関係じゃなくても、友達でも良い。ただの知り合いでも良い。
俺は、彼女が笑っていてくれればそれで良かった。
―――彼女の幸せが、何であるかも考えないままに。
……思えば俺の自己満足だったのだろう。
彼女を想った気持ちも、彼女を突き放した行いも。
『なんで付き合ってくれなかったんですかッ! 抱いてくれなかったんですかッ! 私は、私が、どれだけッ――!』
―――喉元に、突き立てられるのだ。
あの時彼女が仄見せた真実の顔は、俺にその事実を教えてくれた。教えて、くれたんだ。なのに俺は―――
知って欲しかった。自分がどれだけ彼女を想っていたかを。
―――そのわがままで、彼女がどう思うかなんて考えないまま。
だから、俺が、いなくなるしかないと思った。
逃げたんだ。
「「あ……」」
ゆっくりと瞼を、長い睫毛を持ち上げた彼女と視線が交わる。
彼女の傍に、俺は居ても良いのだろうか?
裏切った。逃げ出した。そんな、泣かせてばかりの俺なのに―――
-
「……あー、えっと、だな、まあ言いたい事は色々あるけど、さ」
沢山の言いたい事がある。それは彼女に言いたかった事。
謝りたかった。許しを請いたかった。疑問をぶつけたかった。……お礼が、したかった。
彼女の投げ掛ける視線は、全てを見透かされるくらいに真っすぐで、揺らがない。
―――太陽を見つめるみたいに、彼女が眩しくて見ていられないんだ。
そしてその光はあたたかくて、ガチガチに固めた俺の心を、融いてしまうんだ……
「……ありがとう、はーたん」
止まらない。俺を形作っていたもの。心よりも早く、身体が動いてしまう。
俺はソファに腰掛ける彼女を、そっと抱きしめていた。
「……えぐっ……ふぇっ……ふぇぇぇぇぇんっ! ……良かった、ひっく、本、っく、当に、良かっ――! うあっ、よかった、ひぐっ、よかっ……!」
細い肩は小刻みに震えて、抑え切れなくなった鳴咽が溢れ出した。
俺はこんなにも、想われていたんじゃないか。
だからこそ、あんなに必死に俺を急かしてくれていたんじゃないか。
自分はなんて、馬鹿なことをしてしまったんだろう。
愛しさと失望が混じった複雑な感情は、やがて溶け合って拡がっていく。
もう彼女と一つになることが出来ない俺は、こうやって頭を撫でる事しか出来ないけれど……
「……ん、よしよし」
彼女の両の手が俺の腰に回って、少しずつその手に力が入ってゆく。
一つにはなれなくても、この距離でいい。
なれないからこそ、彼女に縋り付くのだから。
-
いつからだろう。
俺の中で初菜が特別な存在になっていて、子猫のように寄り添ってくる彼女を、愛おしく思い始めたのは。
…いつからだろう。
彼女の姿を目で追うようになったのは。
……いつからだろう。
彼女が俺を好きになってくれたのは。
こんなに近くにいる彼女を、俺は泣かせてばかりだ。
そしてこんな事が無ければ、これからもずっと、彼女を泣かせ続けたんだろう。
今の俺が傍にいる限り、彼女は俺に前の俺を重ねてしまうのだから。
「―――初菜」
はっきり、させなくちゃならない。
俺が彼女に突き付けるしかないのだ。
「色々気付いてやれなくて、ごめんな」
彼女の震えが、止んだ。
まだ顔は上げてくれないけど、俺は話を続ける。
「男じゃなくなっちまって、ごめんな。自分勝手で……ごめん」
俺の胸に額を擦りつけるように、彼女は頭を首を振るった。
その姿が『コゲさんは悪くない』そう言ってくれているようで、堪らない愛しさが込み上げる。
どれだけ力を込めても、今の俺では前みたくは出来ないけれど……
-
「……俺さ、多分これからも変わってっちまうよ。変わりたくなんかないけど……なんだかそんな気がするんだ」
多分、そんなに遠くない未来にそうなるであろう話。
俺はもっと女らしくなって、いつか自然に女として過ごすようになってしまうだろう。
変わってしまった今、俺の身体は意思とは関係なしに、子孫を殖やす準備を整えている。
苦しくて、悔しくて、でもどうしようもなくて……
噴き出すように、湧き出すように、俺は行き場の無い感情を吐き出した。
「……なんで女体化なんかあるんかなぁ? なんで、この歳なんかなぁ…… な…んで……俺、た…だ……はつ…なを……」
途切れ途切れになる言葉を紡ぎながら、力が入らなくなる膝を何とか奮い立たせた。
幼少以来感じた事がなかった鳴咽が、止まらない、止められない……
酷く、自分を無力に感じた。
もしかしたらあまり変わりは無いのかも知れない。それこそ、元からそうだったというのもあるだろう。
けど、こんなにやる瀬ない悲しみと悔しさを感じるのは初めてだった。
人の持つ適応力というのが、はっきりとした敵意を持って襲い掛かって来るのだ。
なまじ脳天気で適応力があるばかりに、俺は彼女をおいてきぼりにしてしまったのだから。
「……ごめんな。 泣いてもどうしようもないよな」
半ば自嘲気味にそう言うと、涙を拭って彼女を放した。
俺はもう、彼女の為に生きる。そう、本気で考えていたんだ。
バカな俺なりに、彼女の為に出来る事をしていこう。
彼女の笑顔だけでも―――せめて見ていられるように、と。
-
またアクセス規制に巻き込まれた\(^o^)/
-
ややこしく、遅くなったけどはーたんとのリレーの続き投下完了。
最近有名所きてるか本スレで聞いてもスルーだし俺はもうダメかもしれんね
携帯でしかも何故かまとめに規制喰らってる俺としてはこのリレーだけでもまとめて頂けると幸いです。
-
怒涛のラッシュに初菜さんどころか俺が泣いた。これの続きを……俺に書けと……
何というプレッシャー、これは間違いなく圧倒的じゃないか
-
コゲさんGJ!
本スレがコテ雑みたいだから入りにく過ぎて困る
-
コゲタン (o^ー')bグッジョブ
-
今年こそは、今年こそは、と毎年思うこの季節。 例外に洩れず、今年も僕は同じ道を辿っている。
慣れっこだと思っていた一人ぼっちの塾からの帰り道が、高校に上がっただけだというのに、やけに切なく思えた。
街の其処彼処に見られるクリスマスカラーの所為だろうか。 それともいつもより多いペアの人並みがそう思わせるんだろうか。
どちらにしろ僕は、煌びやかなイルミネーションを共に眺める人も居ずにただ下を向きながら道の端を歩いていた。
「いらっしゃいませ〜! ただいまお安くなっておりますよ〜! いかがですか〜!」
ちょうど商店街の終わりに差し掛かった頃だっただろうか。 ありがちな売り文句を発する聞き覚えのある声が聴こえてきた。
何となく気になって道の向こう側を見てみると、少し寂れたようなケーキ屋さんの前にサンタの衣装に身を包んだクラスメイトがいた。
同じ学校の同じクラス。 ただそれだけの関係の僕と彼女。 そして僕の家のクリスマスをケーキで祝う習慣は中学校で終わった。
今まで一言二言しか言葉を交わしたことも無いんだし、声を掛ける必要も無いだろう。 僕は見て見ぬふりを決め込んで、家路を急いだ。
「あら、おかえり。 いとこの祈美ちゃん来てるわよ、ってことでケーキ買って来なさい!」
玄関に並ぶ見かけないブーツは誰のものだろう、という疑問はすぐに母さんに解かれ、それと同時に僕はまた、来た道を戻ることになった。
バッグを剥ぎ取られ、三千円を握らされながら家を出ると、さっきよりも少しだけ暗く、寒くなっているような気がした。
それは僕の気のせいだという事にしたんだけれど、さっきよりも白い息が長く続いていたのだけは、はっきりとわかってしまったんだ。
すれ違う男女の波を掻き分けるように進んで、一番家から近いケーキ屋さんの前へ着いた。
さっきクラスメイトが売り子をしていたブースはもう無くなっていて、僕は何故か、少しだけホッとしていた。
-
「いらっしゃいませ〜」
店内に入ると、疲れた顔をした店主らしき人に出迎えられた。 余程疲れているのだろうか。
先程店先に出されていたテーブルが、そのまま店内に収容されている。 その上には売れ残ったケーキが二つ……
僕はその残ったケーキに手を伸ばして、店主の方を振り返った。
店主は、レジの精算なんかをしていたのだろうか。 レシートの束を持ちながら、空いている方の手を顎に当てた。
「あの、コレお幾らですか?」
「それかい? そうだな……もう閉店だし、残っても困るしな。 半額でいいよ」
こんな交渉が出来るのも、いい意味で大型店と違うところなのだろう。 勿論店主の度量によるところも大きいんだろうけど。
それならば、と僕は母さんから預かったお金をポケットから取り出した。 それと同時に、店の奥から階段を駆け下りるような音が聞こえた。
「修ちゃんそれホント!? じゃあ俺もう一個買う!」
唖然とした、ってのは良くある事だと思っていたけれど、不意打ちもいいところだ。
店の奥から出てきたのは、帰ったのだろうとばかり思っていた、クラスメイト―――
「中原さん…」
「泉君…」
「ん? 知り合いかい?」
目が合って硬直する僕と彼女を不思議そうに見ている店主。
クラスでは大人しい彼女の意外な一面を目の当たりにした僕は、僕たちの関係すら説明出来ずにいた。
-
月が雲の向こう側に薄らと見える朧月夜。 言葉もなく薄暗い路地を歩く僕は、何も言わない彼女の後ろを歩いていた。
ただ彼女の足音と時折吹く冷たい風だけの世界。 何故僕はこうして彼女に連れ出されたのかもわからないまま、彼女の吐く白い息を目で追っていた。
「泉君さ…家、近くなの?」
「え? うん…ここから、10分くらいかな」
「ふーん…そっか…」
ふと彼女が立ち止まった交差点で、二人でただ空を見つめながらやり取りする、短い会話。
家族の事とか、部活の事とか、そんな話題だけだったけど、それでも何も話さないよりはまだ、幾分か気が楽だった。
「中原さんの事も、聞いていい?」
「つまんなくてもいいなら、ね」
「何で…女体化した事、学校では隠してるの?」
「……やっぱ、気付かれる、よね…」
特に意味はなかった。 悪気もなかった。 ただ、無神経だったんだ。
でも僕がその事に気付いたのはもう彼女が顔を顰めた後だった。 信号の光が赤から青に変わって、彼女はまた歩き出した。
僕は後悔の念に囚われながら、開いた距離を少しでも縮めようと彼女の後を追った。
「……最初はね、っていっても中学の時なんだけど、男の時と変わりなく過ごしてたんだ」
ポツリ、ポツリと、彼女は口を開いた。 ちょうど公園の入り口で、彼女はベンチに腰かけた。
僕は近くの自動販売機で温かい飲み物を買って、彼女に手渡した。 昔からある、ココアだ。 彼女は少しだけ笑顔を見せて、缶を両手で覆った。
-
「…でも、やっぱり男の時と同じようにはいかなかったんだ。 体力も、人の見る目も、親も、全部に僕はもう男じゃないって教えられたんだ」
冗談混じりに、笑いながら、彼女は話を進めた。 眉をハの字に垂らして、肩を竦めて見せた。
でも僕には、どうしても彼女が無理をしているように思えて仕方がなかったんだ。 だって―――
「だから、今はもう言葉遣いも直して女の子としてやっていこうって決めた。 たまに戻っちゃう時もあるけど、ね」
―――これじゃあ、彼女が周りとの関係を拒んでいるようにしか見えないじゃないか。
こんなに、本当はこんなに明るくて楽しい人なのに、きっと本当は僕なんかよりもずっと友達が多いはずなのに。
……僕はこの時、考えていなかったんだ。 この後の僕の発言がどれだけ脆いものかを。
「じゃあ、僕とまず始めてみようよ。 多分、ホントの中原さんは自分で考えてるよりずっと、素敵な人だよ」
「え? ……何を?」
「うん……改めて言うのは何か恥ずかしいけど、友達、かな」
街灯の微かな灯りの下で、芯から凍えるような寒空の下で、彼女が笑った。
照れたような、ぎこちない微笑。 でもそれは僕の心を揺らすのには十分すぎるほどの可愛さで―――
「……よろしくね、泉君」
「…う、うん…」
小さな偶然が重なった、お世辞にも聖夜とは呼べそうもない夜。
クリスマスケーキの売れ残りにも、福はあるのかなぁ、と思わずにはいられなかった。
おわり。 半端だなぁ、と思った。
-
ネタは同じクリスマスネタだというのに圧倒的なクオリティの差に俺涙目wwwwwwケーキうめぇwwwww
コゲタソ乙!
-
色々反感かいそうなのでこっちにコッソリ投下。
「ウフフ……さぁ、顔をお上げなさい? 伏せてしまっては折角の美貌が拝見出来ませんわ?」
猿轡も手錠も首輪も…妖しく黒く光る様は、私の心を、想いを高ぶらせるばかりだった。
先程までお茶を共にしていたクラスメイトが、声にならない声を上げ、悶える。
涙を浮かべながら、必死になって拘束を解こうとしている。 それは、叶わない事なのだけれど―――
「無駄ですわ! 今の貴方は私のモノ……私の許し無しに、戒めは解けません」
彼女が暴れる度、ガチャリ、ガチャリと鎖が音を起てる。
天井から伝うその戒めという名の私の想いは、文字通り彼女を縛っている。
―――いや、これは我慢できなかった私の我が儘のカタチなのだろう。
金があれば何でも出来る。 そんな私の嫌いなはずだったモノを、今は私の意思でふるっている。
所詮私も、そういった腐った人間だったのだ。
「……お嬢様、準備が整いました」
「ありがとう。 下がって頂戴…」
侍女を下がらせ、愛しい愛しい彼女の身につけているものを全て剥ぎ取る。
まだ誰も汚したことのない白磁の肌が露となり、私は自制をするのも限界になっていた。
桜色の胸の先端も、その控え目な茂みの奥の秘裂も、全てを目茶苦茶にしてしまいたい―――
「もう、一人ではシたの?」
首筋を指でなぞりながら耳元でそう囁くと、彼女は悶えながらも首を横に振った。
前までの逞しさは微塵も無く、そこにいるのはか弱い女の子。
私の一挙一動に反応せざるをえない、彼『だった』人。
「じゃあ……」
私は彼女の茂みを掻き分k(省略されました。 やはり自重は大事だと思います)
-
(省略されました・・全てを読むにはここを押してください)ってあるから
wktkして押したのに・・・押したのにぃっ!
-
チクチョー モニターが凹んだぜwwwww
-
壁│Д゚)…ダレモイナイ!?シンサクトウカスルナライマノウチ!
てことで、本スレは規制に巻き込まれてるんでこっちに投下します。
良かったら読んで欲しいな(・∀・)
-
タイトル:『これって兄妹(きょうだい)?』
いつの頃かお互いに引かれ合い、そして結ばれた二人の物語…
それは時に甘く、時に切なく、時に悲しい…
普通ではない二人のちょっとした恋愛劇。
ある休日。物語の主人公である二人が一緒に遊んでいました。
弟思いの兄、兄思いの弟。近所でも評判のとても仲の良い兄弟でした。
それは二人が大きくなってからも続きました。
兄が高校生、弟が中学生の頃に…ある事件が発生しました。
それは世界中にパニックを引き起こしました。その事件に巻きこまれた人々は恐怖、あるいは悲惨な事態に発展していってしまいました…
その事件とは…
-
『 童 貞 の 女 性 化 』
それはある年齢を越えた童貞の男子が突然女性へと変貌していくという奇病。
発症率は驚異の87.6%。発症する時期は完全には解明されいていない…。
発症を抑える為には脱☆童貞を行えば良い訳だが、そう簡単に行くわけではない。
話を主軸の二人に戻します。結果として兄は男性のままでした。
しかし、二人の周辺では女性化した男性が多くおり、男女比がとんでもないことになっていました。
各国政府はこの事態を重く受け止め、なんとか歯止めをかけようと様々な政策・立法を実行、施行していきました。
…という長い前振りはここまで。ココから本編となります。(全10話前後予定)
長いよ! と言いたい方はレスで「休日(ryまで読んだ」とでも書いて下さいw
ではでは、本編のはじまりはじまり〜。
-
第1話 目覚める恋心
あの事件から2年が経過し、ある程度の落着きが戻っている。
でも、兄の友人や僕の友達にも『女性化』している人がいる事に変わりは無い。
そして、研究が進んで発症する条件が浮かび上がってきた。
1.童貞である事
2.年齢が満15〜17歳以内である事
3.上記年齢の誕生日前後1ヵ月で発病する事
その他にも多数の未確認条件があるみたいだけど、有力なのはこの3つ。
ボクはもう3以外は当てはまってる…それに誕生日もあと1ヶ月と少しで来てしまう。
「はぁ…どうなっちゃうんだろ」
ベットの上で一人呟く。それは部屋の中で反響し、そして消える。
暗い気持ちの上に一人でいるには寂しすぎるし、なんだか泣いてしまいそうになる。そんな時、
「おーい、飯できたぞ、め…って、ゆう坊、なーにそんなに暗い顔してんだよ?」
「な、なんでもないよ」
「ふーん、まぁいいや。冷める前に食おうぜ」
「うん」
優しい声と笑顔でボクを呼んでくれる兄、「浩之」。ちっちゃい頃から「ヒロにぃ」って呼んでる。
「ゆう坊」というのはボクのあだ名。名前が「悠馬」なのでそう呼ばれてる。
-
両親は共に健在だけど、仕事の都合上家にいない事が多いので、ヒロにぃとボクで家事を分担してやっている。
今週はヒロにぃがご飯当番で、掃除・洗濯がボクの当番。
得意料理はボクが和・洋、ヒロにぃは中華。レパートリーが違うので飽きは来ないけど、ヒロにぃの中華はその辺の
お店の物より美味しい。ボクは逆にまずくは無いけど、飛び抜けて美味しい訳でもないっていう極々平凡な感じ。
「ほれ、今日は青椒肉絲と炒飯だ」
「わぁい」
「明日は何がいい?」
「んーとね…酢豚!」
「お、いいねぇ。まかせろ」
「お願いね?」
「はいはい。そんじゃま、食うか」
「うん、頂きます」
見た目通り、凄く美味しかった。…うん、これも今度またリクエストしようっと。
夕飯を食べ終わった後、二人でお笑い番組を見て、お風呂に入って、おやすみを言って、そのまま布団の中へ…
嬉しさと、明日への希望を胸に秘め、そのまま眠りについた。それが最後の夜だとは知らずに…。
ただ…ボクは今になって思う。辛い事もあったけど、本当に良かったと…。
-
『 次 回 予 告 ! 』
誕生日まであと『1ヶ月と少し』。二人の運命の輪は静かに廻りだした…
ひっそりと、だが確実に物語は時を刻んで行く…
次回、『これって兄妹(きょうだい)?』
第2話 ボク…女の子になっちゃった!?
「ど…どうしよう!?ヒロにぃ!!」
「さて、どーしたもんか」
-
てな感じです。描いてて訳わかんなくなったのは秘密だw
期待してくれる方いたらうれしいッス。
んじゃ、続き書いてきますわ〜ノシ
-
乙!!
俺も年末に回線を光に切り替えたんだが、
本スレ規制食らってた…orz
-
うはwwwww
こっちかあ
+(0゜・∀・)+ワクテカ+
-
あげ
-
やっぱり規制されてるし・・・いい加減本スレに書きたいのぅ…
-
規制されてるのでこっちに
武井「貧乳っ娘になって乳首をいじめられる」
真樹「は?」
武井「いや、昨日そういう安価をもらっちまってな」
真樹「……ふぅーん」
武井「っつーワケで、早速安価を実践に移そうと思うのだが」
真樹「ちょっと待て。まさか対象は俺じゃなかろうな?」
武井「お前以外に誰がいるよ?」
真樹「いやいやいや。俺は確か貧乳って設定はなかったはずだぞ。スク水になった時も『発育した胸が云々』って描写されてたはずだ」
武井「そんなもん安価をしてくれた人の熱い想いと読者の切実な願いと作者(と書いて神と読む)の何か色々があればちょちょいのちょいよ」
真樹「なんか最後のが一番デカい気がするんだが……」
武井「まあ諦めろ」
真樹「断固拒否するっ!」
武井「そう邪険にするなよー、これでもかなり折れてる方なんだぜ?」
真樹「あ?」
武井「本当だったら中学生時代の真樹のトラウマになった事件を書こうとしてたんだぜ?」
真樹「……最悪だな。『安価:再会』の例のシーンだけでも気分悪くした人がいたってのに」
武井「げろしゃぶは隠れSだからな。ついヒロインにそういう事をしたがる傾向にあるな。あのシーンでも本人は『ちょっとソフトにしすぎた』っつってたしな」
真樹「あれでか!?」
武井「ま、そんなこんなで……」
真樹「ん?」
武井「やらせてもらいます!」
真樹「うわ!? ちょ、待てーーーっっ!!!」
-
どさり、と真樹は尻餅をついた。
かなりの勢いだったので、下が布団だったのは幸いだった。
「おいっ! 武井」
尻餅をつかせた張本人の名前を呼ぶ。
しかし武井はじっと真樹を見つめるばかりで返事をしてこない。
「いきなり何するんだよ」
「温泉宿に男女二人で泊まって、他にナニするってんだよ」
「お、お前なあ……」
非難しようとするが、その前に武井の手がスルリと真樹の浴衣の合わせに侵入してくる。
「お、おい!」
ひやり。
「わひゃっ」
武井の手が予想以上に冷たく、真樹の口からはへんてこな音が漏れてしまう。
「真樹、お前何も付けてないのかよ…」
「なっ、なに呆れた顔してんだよ! いいだろっ、別にそんなの付けるほどの大きさでもねーんだし!」
「でも、付けてないと形が崩れるって言うぜ?」
「元男な俺にとっちゃ別に悲しくも何ともないね」
「俺が悲しくなるだろ?」
「え?」
突然のその言葉に咄嗟に反応できず、よって次の武井の行動もすんなりと受け入れてしまった。
――ちゅ。
実際にはそんな音がしたわけでもないのだが、武井は真樹の唇に自分のを重ね合わせてきた。
「〜〜っ!!」
血液が一気に頭に昇り、思考が一瞬止まりかける。
「うわ、わ……!」
わたわたと意味不明の踊りを踊り始めた真樹は無視して、武井は合わせに突っ込んだ手を大きく開く。それと連動して真樹の浴衣は呆気なくはだけた。
-
頼りない電光の下に、真っ白な真樹の肌があらわになる。
全体的に肉付きが足りなく、とくに胸囲などは同世代の女の子より、一回りほど下の女の子と比べても足りないのではないかと思わせるものだ。少年といっても通用するかもしれない。
「見るなよぉ……!」
慌てて前を隠そうとするが、その手を武井に掴まれてしまう。
そのまま、もう片方の手で真樹の胸を撫でてきた。
「あ…っ」
思わず声が漏れる。
「何すっ……」
さわさわ。
「あぅ!」
さわさわさわ。
「っい………、お前……んっ……ちょっ……とぉ!」
掴んだ真樹の手から力が抜けるとみるや、その手も真樹の胸をいじくる事に使い始める。
両手で刺激を与えられ、真樹は我慢できずに仰向けになる。それと同時に、彼女の長い黒髪が放射状に広がる。
「貧乳は感度がいい、ってホントだったんだな」
「うるせ……え!?」
きゅう、と乳首をつままれる。
「さっきまでまっ平らだったのになあ」
「っんだと!?」
「今はもう、つまめるぐらいに“立て”ちゃって」
武井がゆっくりと手を離すと、小さくも自己主張している自分の二つの突起が見えた。
顔が真っ赤になっていくのが、鏡をみなくても分かる。咄嗟に顔を背けた。が、
「……はうっ!?」
自分の胸元に湿った生暖かい物が触れてきた。
慌てて視線を戻すと、武井がベロで乳首を舐めていた。
「おいっ! いい加減にしろよ!?」
「やだ」
それだけ言うと、また真樹の乳首を飴か何かのように舐め始める。
-
「ほんとに……んぁ! ……ダメだって言って……んんー!」
抑えようにも、口からはいやらしいあえぎ声が漏れてくる。
それが自分の発したものだなどと真樹は信じられなかった。
片方の乳首は舌で弄ばれ、もう片方は指で弄繰り回されている。爪でツンツンとつついたり、ピンと弾かれたり、クリクリと捻られたり、きゅうっと引っ張られたり。
その度に真樹の体は敏感に反応する。
「あうっ……あん! ……や、も……きゃ」
次第に体全体の筋肉が弛緩してきて、口もだらしなく開きっぱなしになる。
「あっ、あっ、あっ、あっ、あっ……!」
武井が真樹の乳首を甘噛みする毎に、真樹は空高く上り詰めていく気分になる。
脳みそなどとっくに溶けてしまっているのだろうと思った。
「変……だよっ……俺っ…武井っ…なんか……だめっ!」
思考が。視界が。
白一色に塗りつぶされて。
そして……。
―――ちゅんちゅん。
気がつくと、いつもの自分の部屋のいつもの布団の中で真樹は目を覚ました。
服もいつものパジャマだ。浴衣などではない。
胸も、あの洗濯板のようなものではなく、しっかりとした双丘を形作っている。
「……夢、か」
なぜか安堵感より先に、寂寥感が襲ってくる。
そして。
「うわぁ! 濡れてるうう!?」
小さな神社に、驚愕した少女の叫び声が響き渡った。
-
おしまいです。
別にわざわざこの二人にこじつけなくても、まったく別物の短編として書いてもよかったんだけど、こうなりました。
はやく規制解除されねーかなー…。
-
GJ!
-
GJ!
-
「えーっと、東口ってこっちだよな……?」
土曜日の新宿駅。多くの人で賑わっており、至る所に人がいる。
「人多いな……、うぜぇ」
つぶやく俺。人ごみが大嫌いという性格は、自分の書く小説の主人公にも反映されていたりする。
今日は某巨大掲示板のとある物書きスレッドのオフ会ということで、普段めったに来ない新宿になど来てしまっている。
そしてやっとの事で東口にたどり着く。
時間は既に、集合時間の1時を少し回ってしまっていた。
「確か集合場所からの写メが、掲示板にうpされてたよな……」
眼鏡をかけてもなお悪い視力を頼りに、写真と実際の場所を照合しながらフラフラと歩いていく。
すると改札口の脇に、数人の男女がたむろしていた。
(あれか……?)
見知らぬ人に声を掛けるなんて、自分としてはかなりの勇気のいることだったが、意を決する。
「えと、あの……オフ会の人たち……ですか?」
“何の”オフ会なのかは、もし間違っていたら恥ずかしすぎるので口に出せなかった。
「あ、はい。そうですよ」
そのうちの一人が、にっこりと微笑んで返してきてくれた。
(うわぁ、なんつー明るい笑顔をしなさるんだコノ人はっ!)
はっきり言って日陰者としての自覚がありまくる俺は、こういう『陽』の人に弱かった。
-
それから30分ほど待ったが、俺の後に新たに来る人はいなかったので、早速昼食をとりに新宿の街へと繰り出した。
しかしさっきから気になっているのだが、メンバーの中のとある男性が、ずっと同じ女性にばかり話しかけているのだ。
すらりとした感じのその女性。恐らくは20を過ぎたか過ぎていないか、くらいだろう。めちゃくちゃ綺麗だ。まあ、男なら夢中になるのも仕方ないのだろう。
だが、先ほどの笑顔の素敵な人が、その男性にときどき蹴りを入れていたりする。どういう関係なんだ?
お店につき、席の準備のため少し待機室で自己紹介などをした。
先ほどの女性は吉良の介さん(男性だと思っていたので驚いた)、吉良の介さんにばかり話しかけていたのがアニヲタさん(他の人には目もくれていなかった)。
他にも、憧れの06dさんなども来ていた。dさんが自己紹介した時などは、皆感心したり驚いたりしていた。
そして、笑顔の素敵な兄貴はヒロアキさんだと言う(アニヲタさんとは前からの知り合いとのこと)。
順々に自己紹介して行き、俺の番になる。正直これから食事だというのに、コテトリを口にするのは憚られたが仕方が無い。
「俺は、げ……げろ……」
そこまで言った所で皆察してくれたようだ。「あー、はいはい。あの人」とか言ってくれたりしている。皆のヌクモリティに感謝である。
せっかくのしゃぶしゃぶだったのだが、小食のため俺はほとんど食べる事ができなかった。
食事が始まっても、アニヲタさんは吉良の介さんにばっかり話しかけていた。まあ、吉良の介さんも嫌そうにはしていないのだし、良いのだろう。
と思ったら、すぐ隣から舌打ちしたような音が聞こえた。隣にはヒロアキさんが座っているのだが、まさかね……。
-
次に、カラオケに行った。
俺はカラオケは好きだ。だが、初対面の人たちの前で大声を張り上げるのも恥ずかしい。
こうなったら初っ端からリミッターを外すしかない、と自分を奮起させる。
あえて他の人が引きそうな曲目ばかりを選び、出せない音程をごまかしつつ叫びまくる。
他の事には一切目が行かなかった。
しばらくして気がつくと、アニヲタさんと吉良の介さんが居なかった。
「あれ? あの二人は……」
言いかけたところで、当の二人が部屋に戻ってくる。心なしかアニヲタさんが消沈していた。
いや、『心なしか』なんてものじゃない。さっきまであんなに吉良の介さんに話しかけていたのに、今では曲のリストに視線を落として黙々と字を追っていたりする。しかも時折ぷるぷる震えていたりする。
俺だけじゃなく周りもアニヲタさんの変貌振りには気がついていたようだったが、そこに突っ込むような野暮ったい人はいなかった。
ただ、どこからともなく笑い声が聞こえてきた気がした。
五時も過ぎ、解散という流れになった。
今日という日を大切な思い出にしようと心に誓い、昼ごろより酷くなった人ごみの中をビクビクしながら帰っていった。
-
ごめんなさい。
「とある日のお話」を読んだら、自分も書きたくなってしまって……。
えーっと、一応このお話はフィクションですよ?
本当に昨日はお疲れ様でした。またの機会にお会いしましょう。
-
新参ですが小説を投下しようと思う
なんでここなのかって?
本スレに投下する勇気なんて俺には存在しないからさ
-
本スレに投下して欲しいけど、ここでもいいよ!
wktkしながら待ってる。
-
現在ちょくちょく原稿を進めている段階
この異常なノロさも本スレに投下しづらい要因さ(汗
-
(´∀`)人(´∀`)ナカーマ
-
此処の小説ってまとめに載せたらアウトかな?
もう、書けないんだったら、まとめに徹しようと思うんだ
-
別に大丈夫だべ!
もしくはここのやつを本スレに再投下するとか?
-
本スレおちてるからこっちに投下
あと久し振り
『女体化VS女装』
例年より遅咲きの桜の花びらが少し強めの風に飛ばされ、舞い散っていく。
俺はそんな光景をただボンヤリと眺めていた。
そろそろ学校に行かないと遅刻になりそうだが、この風景を見ずに学校に行くと人生を損しそうなくらいに綺麗な景色だった。
……わかっているさ、これが言い訳にすぎないくらい。
でも学校には行きたくない。
別に連休明けだからダルいとかじゃないんだ。
……連休の初日に女体化したからなんだ。
-
女体「よし、今日は学校休m」
??「何言ってんのよ!」
女体「うおっ!」
聞き慣れた声と共に背中に衝撃を感じ、前のめりになってしまう。
女体「バカ姉貴、鞄で殴んなよ」
俺は後ろを振り向き、不意打ちの主を軽く睨む。
だが、腕を組んで偉そうにしている姉貴は怯むことなく、逆に俺を睨み返してきた。
姉「あんたがバカなこと言ってるからでしょ!」
そんなこと言われても、この格好はさすがに嫌だ。
姉「ほら、早く学校行くわよ!」
俺は姉貴に引きずられ、学校に行く羽目になった。
-
ようやく覚えた通学路を10分ほど引きずられ、学校に着いた。と同時に襟首を離してもらえた。
姉「んじゃ、あたしは自分の教室に行くから、今日一日頑張りなさいよ〜ウケケ」
姉貴はムカつく笑い方で笑いながら、自分の教室へと行った。
ちなみに俺が1年生で姉貴が3年生だ。どうでもいいか。
女体「さて、帰るk」
??「あら? 見かけない顔ね」
姉貴とはまた違った意味で聞き慣れた声にうんざりしながら声の聞こえた方を向く。
そこには俺と同じ、女生徒用の制服に身を包んだ男がいた。
-
そいつは一見すると、どう見ても女にしか見えなかった。
でも男だ。いわゆる女装というやつだ。
こいつが女装をしているのには、ちゃんと理由がある。
この世界には童貞のまま15歳になると、16歳になるまでの1年間の間に、女体化するという面倒な仕組みになっている。
とはいえ、女体化確率はせいぜい全対象者の40〜50%くらいだ。
そして、女体化すると必然的に金が必要になってくる。例えば、制服が必要な学校の生徒なら、制服を男子用から女子用に変えなくてはならない。
-
そんな訳で女体化した者のいる家庭には国から特別援助金が出るのだが…
女装「転校生の人?」
目の前の女装野郎は女体化したフリをして、特別援助金をもらっている。
しかも、こいつが男だと気づいているのは俺だけという最高に面倒な状況だ。
まあ、特別援助金のことについては家が貧乏だから黙ってやることにした。
女装「ちょっと、何か喋りなさいよ!」
あ、無視して解説してたが、何も反応しない俺に半ギレしている。
-
女体「んだよ、うるせーな」
女装「っ…!」
女装は絶句している。が、それも一瞬の事ですぐに反論してきた。
女装「うるさいって、あんたが転校初日で緊張して上手く喋れないだろうからって、話しやすい空気にするように配慮した私の気遣いがわからないの!?」
俺が転校生だと思われていることや話しやすい空気を作ったとか、つっこむべきところはあるが、こまめに1つずつ指摘するのも面倒なので、それをまとめて否定する一言を言う。
女体「それは違う」
-
女装「な…な…!」
女装は言い返そうとしていたが、言葉が見つからないようだ。
女体「んじゃ、先に教室行ってんぞ」
こいつに構って遅刻するのもしゃくなので、教室に急ぐ。
そして、時間ギリギリで俺が教室に入った途端、教室内の視線が一斉に俺に向けられた。
女体「うっ…」
俺は大量の視線に怯む。
そりゃ知らない女が教室に入ってきたから、おかしく思うのは解るけどさ…なんでこうも機敏に反応出来るかな。
-
大量の視線を浴びながら、自分の席に学生鞄を置く。と共に
「「「ええーーーっ!!」」」
教室内の全員がタイミングを見事にシンクロさせた絶叫を響かせた。
「そこの席って確か男子だったよね!」
「え!じゃあ女体化したの!?」
「すごく可愛くない?」
「だよね〜!」
「元からこんな顔だった?」
「違うんじゃない?」
「ハァハァ」
「ちょっとでもイケると思ってしまった俺オワタ」
「心配すんな!俺もだ!」
「俺も!」
「オレも!」
「僕も!」
「あたしも!」
「うはwwwwktkrwwwwww」
-
俺に関する様々な話題が飛び交う中、女装も教室内に入ってきた。
女装「うわ!なに、この騒ぎ!」
教室に入ってきた女装がびっくりしていた。
女「あ!遅いね、遅刻だよ!」
女装「ちょっとアクシデントがね…それより、何の騒ぎよ、コレ」
女「うちのクラスで女体化した男子がいるんだけど、すっごく可愛くなったんだよ〜!」
女装「へぇ〜誰?」
女「ほら!あそこの席に座ってる子だよ!」
女装「ふぅん……!(あの席って!てかアイツは!)」
女「どうしたの?石鹸水で溶いた洗剤を飲んだような顔して」
女装「な…なんでもない」
-
女体「(うるさいなぁ…)」
騒がしい教室内に、俺の機嫌は少し悪くなる。
女装「あ〜ら、お・は・よ・う!」
女体「んぎゅ」
いきなり上から女装がもたれかかってきた。重い。
女体「とりあえずどいてくれ」
女装「なんでよ」
女体「重いから…痛い痛い痛い。なぜ殴る」
女装「不思議そうに言うなっ!当然でしょ!」
なんでだろう。さすがに女相手に言う気はないが、あいつは男だから平気だと思ったのに…
|
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板