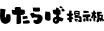レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
( ^ω^)文戟のブーンのようです[3ページ目]
-
≪とりあえずこれだけ分かっていれば万事OKなQ&A≫
Q.ここってどんなスレ?
A.お題に沿った作品を指定期間内に投下
投票と批評、感想を経て切磋琢磨するスレ
Q.投票って?
A.1位、2位とピックアップを選ぶ
1位→2pt 2位→1pt で集計され、合計数が多い生徒が優勝
Q.参加したい!
A.投票は誰でもウェルカム
生徒になりたいなら>>4にいないAAとトリップを名前欄に書いて入学を宣言してレッツ投下
Q.投票って絶対しないとダメ?
A.一応は任意
しかし作品を投下した生徒は投票をしないと獲得ptが、-1になるので注意
Q.お題はどう決まるの?
A.前回優勝が決める。
その日のうちに優勝が宣言しなかった場合、2位→3位とお題と期間決めの権利が譲渡されていく
Q.使いたいAAが既に使われてる
A.後述の「文戟」を参照
詳しいルールは>>2-9を参照してください!
また雰囲気を知りたい方は
スレ1
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/21864/1531744456/
スレ2
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/21864/1533540427/
へGO!!
-
麻婆豆腐が、食べたかった。
香辛料とにんにくの効いた餡と、豚のひき肉が
よく絡んだ木綿の豆腐を、熱々のうちにかっ込んでしまいたい。
しかしわざわざパウチを買って、料理をする気力などない。
かといって、スーパーやコンビニの惣菜も嫌だ。
一度か二度食べてはみたものの、あんなの
麻婆豆腐とは言えない、ただの辛いあんかけ豆腐だ。
ひき肉の旨味や脂によって引き立つ豆板醤の辛さで、額に汗をかきたい。
だから俺は、中華街へと向かった。
地下鉄特有の長ったらしい清潔な
下水のような道を行き、歩くこと五分。
南口へと通じる階段を登れば、
もうすぐそこには真っ赤な門が待ち構えている。
華やかな提灯の下、練り歩く観光客を、
俺は幽霊のように間をすり抜ける。
途中、栗だの肉まんだのの客引きに
声を掛けられるが、まったくもって無視を決める。
ほとんどの飯店では、輸入物の冷凍食品を扱っていて、
どこで食べてもおんなじような味しかしないのだ。
(´<_` )(もうこの街には、本物の料理人なんて一握りしかいない)
ふやけた小麦の甘さと湿気た竹の臭いが、憎悪を掻き立てる。
偽物の中華の臭いは、酷く耐え難い苦痛をもたらす
ので、俺は逃げるように細い路地へと飛び込んだ。
表の喧騒とは違い、こちらは本国に近くなる。
易占、漢方、按摩、鍼灸、輸入食品店。
埃と誇りの混じった胡乱な臭いと、それに染まった店番の男たち。
どいつもこいつも喧嘩っ早くて、荒々しく、
つっけんどんだが、おかげで邪魔な観光客は寄りつかなくなった。
-
( ・∀・)「やあ、兄山の」
見知らぬ男が、懐っこく手を挙げる。
前掛けの屋号からして、おそらく酒屋なのだろう。
だが、俺は酒を飲まない。
( ・∀・)「あれ?」
近付いてきた男は、ようやく違和感に気付いたらしい。
( ・∀・)「兄山じゃない?」
(´<_` )「赤の他人だぜ、俺は」
男の視線は、俺の右耳へと注がれていた。
俺は耳环を開けていて、若竹色の、安い翡翠をぶら下げている。
対して兄山は、装身具の類を一切付けない。
しかしそれを抜きにすれば、俺たちはよく似ていた。
( ・∀・)「そうだよねぇ、そうだ、そうだ」
納得した男は、大人しく引き下がる。
こうして間違われることはしょっちゅうで、
しかしいつまで経っても慣れることはない。
思わず苦笑しながらも、さらに路地の裏へ足を進める。
店の裏側に位置するここは、人気がなく、
代わりに生ゴミが山脈のように連なっており、
壊れた雨樋からは、ぼたぼたと水が溢れ出している。
おそらく二階以上の店では、
店仕舞いの清掃が行われているのだろう。
足早にそこを通り抜け、またまた細い道へと身をよじる。
するとようやく、看板のない飯店に出くわした。
傾きかけているビルの一階をぶち抜いた
その店は、さながら遺構のようである。
はたして俺の他に誰がいるのだろう。
いつもそう思うのだが、奇特な店には奇特な客が集まるものだ。
-
(´<_` )「麻婆豆腐炒飯」
戸を引きながら叫ぶと、たったの四席しかないカウンターの奥から、
( ´_ゝ`)「よぉ、弟者」
明るい声が掛かり、その手前には、
/ ,' 3「……」
荒巻老人が、ラーメンを食べている。
さらにその隣では、テレビを
見ていたらしい娘が、席を立つところだった。
ノパ ー゚ノゞ「……」
カウンターを占領していたガラクタ――安いライターや
古い雑誌、菓子の空き箱などを、娘が移動させた。
ぽっかりと空いたカウンターの上は、油か何かで
艶めいており、極力触らないことを心がけて、俺は席についた。
(´<_` )(壊れてやがる)
柱状の席は、ガタつきが酷く、
おそらくつなぎ目が馬鹿になっているのだろう。
少しでもバランスを崩せば、ひっくり返るに違いない。
狭い店内には壁にもみっちりと物が積まれていたりするので、
そこに頭をぶつけた日には、解脱すること間違いなしだった。
( ´_ゝ`)「久しぶりだな」
苦心しながらケツに力を入れている俺に、兄者――兄原、兄山、兄野、
兄木、兄藤、兄水、兄口……、偽名は様々だった――が話しかけて来る。
彼は、例の他人である。
この店の常連にしては珍しく饒舌で、人懐っこく、
俺のことを弟と呼び、妙に気にかけてくれるお人好しだが、
やはり彼も異常に満ちている。
( ´_ゝ`)「食うか?」
オーダーメイドのスーツを着こなす伊達男の前には、一斗缶が
一つ聳え立っており、その中には愛玉子がたゆたっているのが常だった。
嘘か真か、俺にはまったく判断がつかないが、
週に一度、兄者はこれを食べないといけないらしい。
-
( ´_ゝ`)「要らないか」
返事のない俺に、兄者は苦笑して、
業務用のレードルを手に取り、一合はよそえるそれで、
音を立てながら甘酸っぱい檸檬のシロップを口にする。
隣では、張り合うように荒巻老人がラーメンを啜っていた。
爺さんは、普通のホームレスで、中華街と公園を練り歩き、
アルミ缶を拾っちゃ売り拾っちゃ売りを繰り返している。
そうして稼いだ日銭のうち、百円を払い、ラーメンを食べている。
具材はいたってシンプルだ。
玉ねぎの皮に人参のヘタ、キャベツや白菜の芯に、腐りかけの焼豚やら、
麺の切れ端――店主曰く、ここは製麺所らしい――が、荒巻老人の生活を支えている。
歯が二本しかない老人は、くっちゃら、
くっちゃら、と、だらしなく、下品にメシを食っている。
それでも歯磨きの代わりになるから、
屑は体にいいと、店主はホラを吹いていた。
( `ハ´)「お待ちどぉ」
噂と感慨にふける俺の前に、噂の店主がやって来た。
カウンターを占領する丼の中には、真っ赤な豆腐に、
ごろごろと入ったネギと粗みじんのにんにく、
ニラの青さが引き立つ刺激的な臭いが立ち込めている。
(´<_` )(これだよ、これ)
ヒビの入った蓮華をひっ掴み、盛られた山を切り崩せば、
卵と蒲鉾の紅白が目立つ炒飯が、赤に塗りたくられていく。
ないまぜになった土砂を、口の中へと
放り込めば、待ちわびた舌が旨味を享受する。
ほかほかの餡が絡まった炒飯は、噛まずともするんと飲み込める。
俺は、噛みごたえのある食い物が大嫌いだった。
ここの麻婆豆腐は、木綿のくせに柔らかくって、
だけども絹のようにぼろぼろと崩れることはない。
口どけなめらかに豆の味がして、
後からじゅわっと辛さとにんにくの風味がガツンと鼻に抜け、
鶏ガラと胡椒の効いた炒飯が混ざって、えも言われぬ幸せを、
脳の髄から、背骨の端まで、性行のように、味わうことが出来るのだ。
-
(´<_` )(最高だ)
がっつく俺に、兄者は目を細めて眺めている。
( ´_ゝ`)「よかったなぁ、弟者」
一方的に送られてくる慈愛に、俺はようやく頷いた。
兄者との付き合いは、ここ以外では何もない。
彼が何をしているのか、俺は知らないし、逆に彼も、
俺がどんな仕事をしているのか、興味すら持っていないだろう。
一見裕福に見える彼の高尚な苦悩だって、
凡人の俺にはとうてい理解できない類だろう。
けれどもその空白が、俺は愛おしい。
深く知ってしまえば、喪失感はいっそう強くなる。
そうして痛い目を見たことが、今までに何度あったことだろう。
(´<_` )(ああ、辛い)
上乗せされていく唐辛子の辛さに、身体中が火照り出す。
舌はビリビリと痺れ、花椒特有の
酸味が効いた熱っぽさに唸りながら、
黒いスウェットの袖を引き延ばした。
額に浮き出た汗は、そこはかとなく
にんにくの臭いがにじみ出ているようだった。
/ ,' 3「あんまり辛いと、ケツいわすだろう?」
珍しく呟いた老人に、これまた珍しく、俺も頷いた。
あまりの辛さに、無関心さを装う暇がなかったのだ。
/ ,' 3「朝鮮の刑務所で飯食ってた頃を思い出すよ」
(´<_` )「へぇ」
/ ,' 3「捕まったわけじゃないよ」
びろんびろんに伸びた麺をつまみながら、老人は語る。
-
/ ,' 3「戦後人手が足りなくって、頼まれてさ。
仕方ないから看守として残ったってだけよ」
(´<_` )「へぇ」
話半分、冗談五割、まじめに
受け取るほど、俺はバカじゃない。
それになんたって、麻婆豆腐が一番だ。
蓮華を舌の代わりに皿を舐め回し、
一滴も餡が残らないように、腐心する。
その背後から、乱雑に戸が開く音。
「兄原だな?」
真後ろから掛けられた言葉は、
カウンターの奥へと向けられたものに違いない。
実際そうに違いなかっただろうに、
豆腐の滓をすくい取る俺の肩に、手が食い込んだ。
_
( ゚∀゚) 「テメェがそうだろう?」
(´<_` )「え?」
チラと視線を送れば、当の兄者は背を向けており、
荒巻老人はラーメンをすすり、
鍋を振る音が響く厨房へと、看板娘の背中が吸い込まれていく。
つまり誰も俺の無実を証明する輩はいないので、呆けているヒマはなかった。
-
_,
( Д ) ,"・,。「ゴパッ――」
秒速三一五メートル。
九×一八ミリのマカロフ弾が、喉から脳天へと直撃。
マカロフPMの有効射程距離は五十メートルで、
ゼロ距離で射殺したというのに、奴の頭蓋は丈夫だったらしい。
脳みそを豆腐のように散らすこともなく、ただ首からゴボゴボと、
豪雨のように血が降り注ぎ、黒いスウェットへと染み付いた。
どふ、
と音を立てて、男は床へ転がり、
それを見届けて、銃を懐へとしまった。
( ´_ゝ`)「悪いね、弟者」
/ ,' 3「南無三」
ニヤニヤとニタニタの中間のような笑みを
浮かべる兄者の横で、老人は十字を切った。
なんだか仲間外れにされたような心地になり、俺は嫌悪を露骨にした。
ノパ ー゚ノゞ「――」
カウンターから、無口な女が飛び出した。
ほとぼりが冷めた頃にやって来るのは、いつものお決まりだった。
四肢をビクつかせる男の首を掴み、
彼女は厨房の奥へと消えていく。
(´<_` )「帰る」
会計を済ませようとするも、満腹なはずの胃の腑は、
ギチギチと締め付けられるように痛んだ。
不意にやってくる仕事っていうのは、いつだって不愉快なものである。
-
( ´_ゝ`)「マスター、紹興酒と、彼に麻婆豆腐炒飯を」
厨房に向けられた言葉に、俺は虚を突かれる。
( ´_ゝ`)「奢るよ」
(´<_` )「どうして?」
( ´_ゝ`)「あれは、俺の客だった」
後頭部を掻き毟る兄者は、ヘラリと笑う。
( ´_ゝ`)「弾だって高いだろう?」
違いない、と俺は頷いた。
命を張っているわりに給金は安すぎる上に、
年々規制は厳しくなるばっかりで、入手するのも楽ではない。
(´<_` )「おぶ」
顔面に投げつけられたおしぼりは、無愛想な女からだ。
顔と手を拭くと、ねっとりと血が絡みついた。
/ ,' 3「あーあ、やだね」
ぶつくさと文句を言う荒巻は足を持ち上げて、
それから間もなく床へとお湯がぶちまけられた。
どうも女は、店を掃除するらしい。
ぐじぐじにお湯を吸いこもうとする靴を引き上げて、俺は席に着く。
(´<_` )(日本のヤクザは礼儀正し過ぎる)
わざわざ名前なんて聞かずに、ズドンと
撃っちまえば、助かったのはアイツの方だったろうに。
(´<_` )(訳わかんねえ店だな)
一体俺は大事にされてるのか、そうでないのか。
混乱している鼻に、辛味の効いた匂いが行き着いた。
もうじき、料理がやって来るだろう。
-
蛇に耳环と藪から棒に、のようです《了》
.
-
( ^ω^)「>>220ここめっちゃすきだお」
-
>>241
( ^ω^)「おつだお!これまた読み応えのある良作だったお」
-
('(゚∀゚∩ 良作がいっぱいですが先に投下させてもらうよ!
-
ざわ…
ざわ…
(-_-) 授業終わりの五分前、教室内は何だか落ち着かない雰囲気に包まれている
(-_-) それもそうだ、もうすぐ昼飯の時間なのだ
(-_-) 教師はそんな俺達生徒の気持ちには気付いていないのか熱心に教科書を読み上げている
(-_-) だが、それは俺の耳には届かない
(-_-) 何故なら……
(-_-) 腹が……
(-_-) 減った……
(-_-) ……からだ
(-_-) 俺は今猛烈に腹が減っている、目の前に座る女のツインテールがチョココロネに見えるぞ
ξ゚⊿゚)ξ ←目の前に座ってるツインテールの女
(-_-)■ それにこの香りつき消しゴムが何か物凄く美味しそうに感じる
(-_-) 俺はもう、限界だ
( ^ω^) じゃあこれで今日の授業は終わりだお!ちゃんと復習して来るんだお!
チャイムが鳴り始める僅か数秒前、教師は授業の終わりを告げた。そしてチャイムが鳴り始める。
(-_-) 今だ。もう俺を、俺の腹を縛るものは何も存在しなくなった。そう、俺は自由なのだ
(-_-) いざ行かん、昼食と言う至福の楽園へ
-
(-_-) ぼっちのグルメー屋上編ーのようです
-
俺は周りの喧騒には目もくれず席を立ち、屋上へと向かう。
北校舎の屋上、そこは俺が入学した時から入り口の鍵が壊れている為立ち入ることが出来る「食」という
神聖な儀式を執り行うのに適した場所なのだ。
(-_-) 暑すぎず、寒すぎず、風も強くなく日差しも強すぎではない。今日は最高の屋上ランチ日和だ
(-_-) 誰かと食事を食べないのかって?それはどう考えても愚問
(-_-) 食事をする時、それは誰にも邪魔をされてはいけない。一人で静かに、でも自らが満足するものを満足するまで味わう
(-_-) それが食事という神聖な儀式なのだ
(-_-) え?人と話しながら食べる?そんな……そんな行為は食事を愚弄する犯してはいけない禁忌の一つだ。
(-_-) 食事をする時は心を落ち着け精神を目の前の食材にのみ傾ける。それがものを食べて生き永らえる人間として最低の礼儀だ
(-_-) 人の視線が気になって、誰かと話すことで精一杯で、何か悩みがあって……そんな時には幾らおいしいものを食べた所で味は分からず、その行為はただの栄養摂取にしかならない
(-_-) これは絶対にあってはいけないことだ。だから俺は食事をする時は必ず一人で、目の前の食材にのみ意識を向けて最大の感謝と共に頂くようにしているのだ
-
(-_-)▲▲ そんな今日の俺の昼食はこれ、登校中に買った某コンビニのおにぎり計二点だ
(-_-) これだけ食に関する御託を並べていてそれで食べるものがコンビニおにぎりwwwと思われた方、それは完全に甘いとしか言いようがない
(-_-) いや、甘すぎる!サトウキビよりも、合成甘味料よりも甘い!
(-_-) 確かに自分で作った自家製のおにぎり、それは素晴らしいものであるし俺の大好物でもある
(-_-) 素材に拘れるし自分の好きな量、味と調整も自由自在だ
(-_-) だがコンビニおにぎりという存在もまた長い歴史と携わった人々の知恵と努力、汗と涙の結晶なのだ
(-_-) どんな状況でも新鮮なパリッとした海苔を、よりご飯に合うおかずを、より高品質で低価格で、そんな崇高な存在を馬鹿にするとは何事か
(-_-) ああ、腹が待ちくたびれたとクレームの嵐だ
(-_-) ほら、待っていてくれ。今食べるから
(-_-)▲ うん……うん……
(-_-) あぁ……まるで砂漠に水が吸収されていくかのように体が満たされていく
(-_-) そう、俺は、いや人間は食事をすることで生き、食事をする為に生きているのだろう……
これからも俺のグルメは続く。そこに旨いものがある限り、そして命ある限り。
-
ξ゚⊿゚)ξ 何あいつ一人で頷いてるのよ?面白そうだからつけて見たら勝手に屋上なんか入ってるし、そこで優雅にぼっち飯して楽しんでるし……
ξ゚⊿゚)ξ 変なの
<END>
-
>>213
なんだこの記号
-
ミセ*>ワ<)リ「やほやほっ! ミセリだよ!」
ミセ*゚ー゚)リ「今月から二学期も始まったし、いっちょやりますか!」
ミセ;゚д゚)リ「――ってみんななんで夏休みに文戟してんのぉ!?」
ミセ;゚д゚)リ「やっべっ! 出遅れた感満載じゃん!」
ミセ;;゚〜゚)リ「むむむ〜っ! 今から全員倒しちゃうんだからね!」
ミセ*>ワ<)リ「それじゃあアタシの作品をミンナ見ろぉ〜〜〜〜〜〜ッ!!」
-
足跡で作ったフレームでは?
構成の話だったらこうだと思う
。(句点)→ 。。
゚(半角半濁点)と●→ ゚●゜←゜(全角半濁点)
-
投下と被ったかすまん
-
トランスチューブターミナルの方角から、
天蓋の光学ディスプレイが、にわかに曇りの様相を呈してきた。
人工的な青空を模したカラーが、
黒と灰の混ざりあった靄に切り替わっていく。
光学ディスプレイは一見天蓋を隙間なく覆い尽くしているように見えるが、
互いの辺には若干の隙間があり、
そこからスプリンクラーにより人工的な降雨が再現される。
デルタ・コンプレックスは絶えず工業地帯からの有害な排煙が大気を汚しており、
こうやって定期的に大気汚染物質を雨に吸着させ、
更に地下にある処理施設へ流すのだ。
.
-
僕はくたびれた合皮の鞄から、色あせた"緑《グリーン》"の折り畳み傘を取り出す。
近くを清掃しているボットを横目に、早々にそれを広げた。
全てのボットは監視業務を兼任していて、
常にこの地下都市に住む市民を見張っている。
偉大なるコンピューター様が管理なされている完璧な社会で、
愚かにも雨に濡れ、
自身の体調を崩す要因を作り出す愚鈍な市民など存在しないのだ。くそったれ。
工業地帯から自身のクリアランスである緑の居住地区に出る。
画一的なデザインのアパルトメントが立ち並んでいるので、
しっかりと標識を見ないと現在自分がどの通りを歩いているのか分からなくなる。
チェス盤の様に整理され尽くした美しい街並みといえば聞こえがいいが、
実際はコピー&ペーストで記号化きった無機質な空間と言わざるを得ない。
更にこの場所をせせこましく感じさせるのは、
屋根の上を走る"輸送道路《トランスハイウェイ》"だ。
自動運転の輸送車が時間を問わず走り回るせいで、
その騒音と排ガスにこの街は常に溺れている。
輸送車も、市民のクリアランスに合わせて色分けされていて、
それぞれに配給される物資が詰め込まれている。
頭上で鳴る、タイヤが荒れたアスファルトを転がる音を聞きながら、
僕はゆっくりとかぶりを振った。
.
-
思うのは、"人工食糧《レーション》"のこと。
完璧な栄養素と機能性を兼ね備えたコンピューター様の最高傑作と名高いソレ。
裏を返せば栄養素と機能性以外の全てが切り捨てられており、
味は無く、食感は砂粒を握り固めたような劣悪なものだ。
もちろんそれに文句の一つでもいえば、間違いなく反逆者として処刑される。
だから僕ら下級市民は皆、文字通り味気ない生活を"享受させて頂いている"訳だ。
最近は舌も胃も、人工食糧を受け付けなくなって来ていて、
こっそりと職場の産業廃棄物に混ぜて捨てている。
同僚から痩せたことを悟られないように、
仕事着にソファから抜いた綿を詰め、着膨れするようにして誤魔化している。
しかしそれも、次の医療ボットによる定期検診で間違いなく看破されるだろう。
単純なもので構わないから何か味があれば、少なくとも飲み込むに足るのでは、と
誰に言うでもない愚痴にも似た提案が、あぶくのように湧いては割れた。
やがて、その不満も洗い流すように雨が降る。
傘膜に当たる雨粒が跳ねる音は、存外嫌いじゃない。
あと数分もすれば雨脚は更に強まるはずだ。
その前に家に入らないと、傘を差したくらいではずぶ濡れ必至だろう。
僕は少し早歩きになると、傘と雨で視界の狭まった世界で、
居住地区に走る送電ケーブルに無造作にぶら下げられた標識を睨むように進んだ。
.
-
――カァ……ァアン。
ふいに、硬質な反響音が聞こえた。
丁度、金属を壁か何かに打ち付けたような音だ。
僕はその音の方向に顔を向ける。
大通りと大通りの間にひしめくアパルトメント達の隙間。
インフラ配管や室外機が絡み合う、薄暗い路地裏に、それは居た。
――最初は、人間だと思った。
室外機の一つに腰掛け、壁を背もたれにして、濡れているのだと。
傘を忘れて、少しでも雨を避けるためにそうしているのか、
はたまた、この管理社会に疲れ切って頭の狂った"偏執狂"であるのか、
どちらにせよ、お近づきになっても僕の得になる事は無いだろう。
傘に入れてやる代わりに金を巻き上げることも考えたけど、
あいにく今の僕の生活に、
そもそも金を使うような時間が無いことを思い出して思わず笑いが出た。
.
-
だからだろうか、なんとなく、その人影に近寄った。
何か助けになれば、なんて良心からじゃない、
単純に先程の音の出処が気になっただけだ。
もし何かしらの異常があるなら、
"端末《ターミナル》"からコンピューター様に報告するのが市民の義務だ。
傘の柄を首と肩で挟むように支え、
空いた両手を使って合皮鞄から"光線銃《レーザーガン》"を取り出す。
もし、かの人影が当方の予想通り狂人であり、こちらに襲いかかってくるようであれば、
迷わずに引き金に手をかけ処刑出来るようにする準備だ。
もう一度、あの音が響く。
距離をつめる度に、
雨のカーテンの向こう側にボヤケていた輪郭がはっきりしてくる。
.
-
どうやら女のようだ。
肩口の下辺りまで伸びた黒髪が、水を吸って艶めいた輝きを放っていた。
その女は、室外機に腰をかけながら、ゆっくりと前後に揺れている。
そして、自身の後頭部をアパルトメントの壁に打ち付ける時に、あの金属音が響いていたのだ。
間違いなく、狂人の類だろう。
僕は光線銃の銃口を、その人影に合わせるように持ち上げる。
その時、女が前後に揺れるのを止め、首だけをゆっくりとこちらに向けた。
――顔の半分が、無かった。
正確には、彼女の顔面の右頬から額までの皮膚が剥がれていたのだ。
そして、鉛色に鈍く光る金属の頭蓋骨と、
剥き出しのセンサーアイが雨粒を纏うように晒さている。
.
-
(´・_ゝ・`)(自律人形か……)
一見すると異様な姿に一瞬あっけに取られるも、すぐにその考えに思い至る。
人型ボットの所有は"藍《インディゴ》"以上の階級にのみ認められた特権であるが、
おおよそ、そこでの仕打ちに耐えかねて逃げてきたのだろう。
最新鋭の自律人形は擬似的な感情を有するものがあると聞いたことがある。
そして、既にこの"疑似的"という修飾語が曖昧なものになりつつあるほどに進歩している、とも。
(´・_ゝ・`)(どうしようか。この場合の対処は頭に入ってないなぁ)
狂人で無いことに安堵しつつも、この事案をどうすれば良いかという次なる課題が出てきてしまった。
自身より上の階級の持ち物である事は確かであり、安易に破壊することは出来ない。
しかしながら、これを端末から報告すると、この自律人形を逃した藍様は、
コンピューターから『自身の持ち物もロクに管理できないマヌケ』の名のもとに処刑されるだろう。
そうなったら、その後の逆恨みが怖い。
処刑されても記憶を引き継いだ"予備《クローン》"が即生成される。
それがこの地下都市の良いところであり、くそったれのその2だ。
.
-
そんな僕の逡巡を尻目に、その女型自律人形は微笑んでみせた。
人の相貌を残している左の眦を下げ、口角を少しだけ上げる。
その瞬間、強まった雨が僕の突き出した光線銃に当たって、水滴が跳ねた。
避ける間もなく、その水滴は僕の口内へ侵入した。
大気汚染物質を含んだそれは、単純に健康に悪いだけでなく、
その味も糞を煮詰めたみたいに最悪なものだ。
大抵の場合、口に入った時点で反射的に吐き出そうとえづいてしまう程に。
しかし、そうはならなかった。
それどころか、僕は今まで感じたことの無いほどの幸福感に包まれていた。
僕の舌の上を走る、柔らかな布で撫でられたような心地よい快感。
一瞬で口内全部に広がった快楽の波は、余韻を残すように何度も寄せては返した。
思わず銃を落として口元を押さえてしまう。
それは吐き出すとは真逆の行為で、つまり僕はこの口の中の"コレ"が逃げないようにしたんだ。
何が起きたのか分からなかった。
.
-
「美味しいですか?」
少し掠れたような、ハスキーに寄った声がして、
僕は口を押さえたまま、声の方向にピントを合わせる。
自律人形が、こちらを見ている。
そしてもう一度、同じ抑揚で、こう言った。
(◎、`*川「――美味しかったですか?」
その時、僕は理解した。
今僕が感じているこれは、"味"なのだと。
今まで一度も感じたことのない、未知のもの。
僕の階級では、その知識のみは開示されていた。
甘い、酸っぱい、しょっぱい、からい、苦い。味というものはこの5つの組み合わせから成り立つと。
でも実際には人工食糧以外を口にする機会の無い僕たちは、
苦い以外の4つに関しては、予備が尽きるまで知り得なかったはずのものだ。
それを今僕は、体感しているのだと。
.
-
それからもう一つ理解したことがある。
眼前で微笑む自律人形は、ただの汎用ボットじゃない。
こんな機能を持っているのは、最上階級"紫外《ウルトラヴァイオレット》"専用のアレ以外あり得ないんだ。
(´・_ゝ・`)「――"美食人形《グルマヌカン》"……」
僕の言葉に続くように、人形は口を開く。
(◎、^*川「さぁ、"ご主人様《マスター》"、お次は何をお召し上がりになるの?」
.
-
(´・_ゝ・`)Strawberry On The――のようです(//、`*川
.
-
********************************************
あれから一週間経った。
僕は彼女を家に持ち帰っていた。
痛々しい程に破れていた顔面の人工皮膜には、
使う機会もなく余らせていた配給の包帯を巻き付けた。
大気汚染物質を吸着した人工毛髪は丁寧に洗ってやり、
同じように身につけていた古めかしい給仕服も洗濯してやった。
そこまですると、もはや生身の人間と見分けがつかない。
包帯で顔半分を覆っているのは若干気味が悪いが、
あいにく僕には修復の技術が無いので、そこはお互い我慢することにした。
.
-
――美食人形。
人間の脳髄に作用する感応波を発することで、
本来なんの味もない人工食糧に特定の味付けをすることが出来る。
更に、共に食事を楽しむという空間の演出づくりの為に
会話機能と上等な擬似感情を有する。
当然とんでもない高級品であり、最上階級以外は所有を許されない。
それは単純に高価であるというだけじゃなくて、
下級市民に余計な探究心を抱かせないための措置という意味合いの方が強い。
文字通り『味をしめた』市民は、他の美味を追求したがるだろう。
そこに付随して、本来その階級では開示されていない情報までも嗅ぎ回るようになり、
いずれは立派な反乱分子に成長するに違いない。
コンピューター様はそう判断したのだ。
だからほほ全ての情報開示が許されている紫外階級のみに、
嗜好品として与えられるのだ。
.
-
(´・_ゝ・`)「……これで僕も小悪党から、立派な大悪党だな」
(//、`*川「あら、ご主人は小悪党でしたの?」
(´・_ゝ・`)「そうさ。皆多かれ少なかれ、規律に違反してる。
善良なる完璧な市民なんてどこにもいやしないのさ」
(//、`*川「"悲観主義《ペシミスト》"ですの?」
(´-_ゝ-`)「そうじゃないよ。息苦しい中で、なんとか楽しく生きるのが人間ってこと」
(//、`*川「それがいいですわ。さぁ、今日は何をお召し上がりになりますか?」
(´・_ゝ・`)「『甘い』、がいいな。甘いのが一番好きだ」
(//、^*川「あらあら、ご主人はお子様みたいなことおっしゃるのね」
そう言って彼女は口元に手を当てながらクスクスと笑うと、
戸棚からパッケージされた人工食糧を取り出す。
それを開封した後、きちんと清潔に洗われたプラスティックの白皿に丁寧に並べていく。
.
-
以前はパッケージから直接貪るだけでだったけど、
今は彼女にこうやってお膳立てしてもらう。
曰く、(//、^*川『盛り付けも、美食の一部ですわ』
実際、そう言われると少し美味しそうに見えるから不思議だ。
僕は彼女がテーブルの向かいに腰掛けるのを待ってから、皿に手を伸ばす。
(//、`*川「あら? いただきますはないんですの?」
(´・_ゝ・`)「おっと、すまない」
(´-_ゝ-`)「――いただきます」
(//、^*川「どうぞ、召し上がれ」
左目を柔らかく閉じ、歌うように彼女は言う。
それが絵になるくらい美しくて、
僕は手を伸ばしたまま彼女を見つめる。
.
-
(//、`*川「……? どうしましたの? 味付けを変えます?」
(;´・_ゝ・`)「ううん、そうじゃないんだ。そうじゃ、なくて」
(//、`*川「思いっきり辛いのがお好みですの?」
(;´・_ゝ・`)「ちょ、ちょっとそれは勘弁」
(//、^*川「ふふふ」
さすが、という言い方でいいのだろうか。
彼女との会話は楽しい。
人工食糧を摘んで、口の中に放り込む。
とても落ち着く子守唄が、じんわりと脳髄に染みていくような、
柔らかな羽毛で頬を撫でられるような、そんな幸福感がゆっくりと体全体に行き渡る。
『甘い』は、優しい。
だから好きだ。
残念ながら、食感までは変えられないので、
口の中にはザラついた感覚が残ってしまう。
それでも以前の無味無臭の固形食とは比べようも無いほど美味だった。
.
-
(´・_ゝ・`)「――君はなぜ、あの日あの場所にいたんだい?」
(//、`*川「ほら、ご主人。こぼしてますわ」
(;´・_ゝ・`)「おっと、ごめんね」
(//、`*川「後でお掃除しますわね。……それで、あの日のことですね」
(´・_ゝ・`)「うん。君のことがもっと知りたいんだ」
(//、^*川「あら、うれしいですわ」
彼女はそう言って微笑んだけど、
その前に一瞬悲しむような表情になったのを僕は見逃さなかった。
(//、`*川「すごく、すごく単純なお話ですの」
(//、`*川「私、"廃棄処分品《ジャンク》"として捨てられる予定でしたの」
(´・_ゝ・`)「なんでまた。こんなに素晴らしいのに」
(//、^*川「そう言っていただけて光栄ですわ」
(//、`*川「でも、現実は型落ちモデルですのよ」
(//、`*川「私、『P-20xx』モデルは旧型ですので、再現できる味に限りがありますの」
(//、`*川「それで、つい最近『T-20xx』という最新のモデルがロールアウトされまして」
(//、`*川「私はお役御免、廃品回収の自動走行車に詰め込まれて、処理施設行きになるところでしたのよ?」
(´・_ゝ・`)「それは、また……」
.
-
(//、`*川「とっても『苦かった』ですの。それから『しょっぱかった』……」
(//、`*川「だから私、トラックの荷台から飛び出して、
そのまま、この地区の上を走る輸送道路から飛び降りましたの」
(;´・_ゝ・`)「随分と無茶をするなぁ」
(´・_ゝ・`)「顔は、その時に?」
(//、`*川「そうですわ。輸送車から飛び出した時にハイウェイを長く転がったんですの」
(;´・_ゝ・`)「聞いてるだけで、肝が冷える」
(//、-*川「――逃げたかったんですの、『苦い』から」
(//、-*川「『苦い』のは嫌ですわ……」
彼女は自分の肩を自分で抱いてみせる。
そのままキュウと小さくなるように顔を伏せて、
膝を抱えるように足を椅子の上に乗せた。
先程から彼女が口にする『苦い』や『しょっぱい』などの味の表現は、
どうやら彼女の感情を意味するらしい。
『苦い』は恐怖、『しょっぱい』は悲しみだ。
.
-
僕は立ち上がると、テーブルの向こう側に手をのばす。
そのまま彼女の黒髪に触れ、優しく掻き回す。
人工毛髪特有の過度な指通りの良さを感じながら、何度も、何度も、撫でた。
(´・_ゝ・`)「僕は、君を捨てたりしないよ」
(//、-*川「……ホントですの?」
顔は、上げない。
膝と膝の間に顔をうずめるようにしながら、
拗ねるように彼女はそう言った。
(´・_ゝ・`)「ホント。約束する」
(//、-*川「……『約束は、破るためにするものだ byレーニン』ですわ」
(;´・_ゝ・`)「君のデータベースは随分危険な方向に偏ってないかい?」
(//、^*川「気の所為ですわ」
やっと顔を上げた彼女は、僕をからかうみたいに笑ってみせた。
.
-
そのまま彼女は続ける。
(//、`*川「それを言うと、ご主人も随分と博識ですわね」
(//、`*川「私が監視ボットでしたら階級を逸脱した知識の所有の名目の下、即処刑ですわよ?」
(´・_ゝ・`)「ははっ、怖いことを笑顔で言うなぁ」
(´-_ゝ-`)「仕事柄、そういう知識に触れる事が多いんだよ」
(//、`*川「終ぞお聞きしませんでしたけど、ご主人は何のお仕事をされてますの?」
(´・_ゝ・`)「"焚書士"だよ」
(//、`*川「焚書――ですの?」
(´・_ゝ・`)「まぁ、本に限った話じゃないけどね」
(´・_ゝ・`)「この都市の規律を乱し、治安を害する有毒図書を探して、燃やしてしまうのさ」
(//、`*川「本――なんてこの都市にまだあるんですの?」
(´・_ゝ・`)「ある場所には、ね」
(´・_ゝ・`)「さっきも言ったけど、市民たちは多かれ少なかれ規則を犯しているものだ」
(´・_ゝ・`)「軽く叩いただけでホコリが舞う、そんな奴らばっかりさ」
(//、`*川「それでも、随分骨の折れる作業に思えますわ」
(//、`*川「市民の皆様だって、許可なく図書を保有していれば
処刑されることが分かっているでしょうから、必死に隠しますわよね?」
(´-_ゝ-`)「そうだねぇ……」
(´・_ゝ・`)「――でも、あいにく僕の鼻は特別製でね」
(´・_ゝ・`)「古くなった紙の匂いや、色褪せたインクの香りなら、100m先でも嗅ぎつけられる」
(//、`*川「すごいんですのね」
(´・_ゝ・`)「まぁ、これもバレたら処刑間違い無しの特殊能力だけどね」
(//、`*川「綱渡り稼業ですのね」
.
-
(´・_ゝ・`)「それで、知識の話だけどね……」
僕は彼女の頭の上に乗せっぱなしだった手を離すと、
ベッドが置かれた部屋の隅へ向かう。
簡素な組み立て式のスプリングベッドと、その隣に小さなキャビネット。
僕はそのキャビネットの上に掛けられていた、題名のない風景画の収まった額を外す。
その下からは、ダイヤル錠が付いた金庫の扉が顔を覗かせる。
(//、`*川「まぁ」
彼女は僕の背中に感嘆の声を投げる。
ちょっと得意になりながらダイヤルを右へ左へひねると、
カチリという錠の外れる音がして、金庫の扉が少し浮いた。
そのまま取っ手に手を掛けて扉を引くと、中からエタノールに似た揮発臭が漏れる。
そこには、僕の数百冊に及ぶ蔵書が収納されていた。
(´-_ゝ・`)「これが、僕が小悪党たる所以さ」
(´・_ゝ・`)「市民から回収した図書で、気に入ったものがあれば、こうやってこっそり持って帰ってきちゃうんだ」
(//、`*川「ご主人はお持ち帰りが得意ですのね」
.
-
言いながら、彼女は椅子から立ち上がりこちらに歩み寄る。
僕の肩越しに金庫の中身を見ると、
背表紙に書かれた作者名を読み上げていく。
(//、`*川「『トルストイ』『モンテーニュ』『ゲーテ』『トマス・モア』『韓非子』……随分節操の無い――
あら、『手塚治虫』もありますのね」
(´・_ゝ・`)「中身で選ぶこともあれば、表紙で選んだりもするからね」
(//、`*川「『国富論』『我が闘争』……確実に処刑ものですわねぇ」
(´・_ゝ・`)「僕の他には君しか知らない」
(´・_ゝ・`)「だから『約束』」
(´-_ゝ-`)「もし僕が君を捨てるようなことがあれば、君はこのことを何処へなりと報告すればいい」
僕がそう言うと、やや間があってから
後ろから抱きしめるように腕が回される。
人工被膜の下には薄いながらも弾性の強いケイ素クッションが内蔵されているので
自律人形といえど、柔らかい感触がする。
(//、-*川「そんな『しょっぱい』こと仰らないで。泣いてしまいますわ」
彼女にそんな機能が備わっていないことは分かっていたけど、
それでも僕は回された腕に、自分の手を重ねた。
(´-_ゝ-`)「分かった。もう二度と言わない」
.
-
僕がそう言った瞬間、壁に備え付けられた時計からアラームが鳴った。
出勤時間が来たのだ。
(´・_ゝ・`)「ごめん、もう行かないと」
(//、`*川「そう……ですのね」
僕の背中から、彼女の柔らかさが遠ざかる。
彼女に向き直る前に、
僕は一冊の本を金庫から引き抜き、そのまま彼女に手渡した。
(´・_ゝ・`)「これ、きっと面白いから読んで見てよ」
(//、`*川「『オスカー・ワイルド』……?」
(´・_ゝ・`)「そう。彼の短編集」
(//、`*川「お好きなんですの?」
(´^_ゝ^`)「割とね」
玄関脇のポールハンガーに掛けられた緑のコートと羽織ると、僕は家を出た。
扉が閉まる直前に聞こえた『いってらっしゃいませ』は嬉しそうに弾んでいたように思う。
.
-
********************************************
仕事からの帰り道、コートの裏の四角い感触を胸に感じながら、
僕は彼女の言葉を思い出していた。
『再現できる味に限りがある』
裏を返せば、僕の知っている5つの味以外にも
その範囲の限りであれば再現出来るということなのではないだろうか?
僕も、この本を手に入れるまで思いつかなかった。
味、とは単に味覚を刺激するものという意味ではない。
それぞれの味が混ざり合って、それが『料理』となる。
"美食人形《グルマヌカン》"だ。その機能を有していると考える方が普通だ。
なんで気づかなかった?
決まってる。
その思考に行き着くまでの情報が、僕の階級には圧倒的に足りなすぎた。
だが今は違う。僕は知ってしまった。
否応にも足が早まる。期待感に心臓が早鐘を打つ。
緑階級の居住区画に戻り、標識の確認もせずに大通りを突っ切る。
もし間違えて自分の家以外に入ってしまえば、家宅侵入罪で即処刑な訳だが、
今の僕には、そんなことどうでも良かった。
足が覚えている距離感に任せてずんずんと進み、自宅の扉を勢いよく開いた。
.
-
(*´・_ゝ・`)「ただいま!」
僕はその言葉と同時に、後ろ手で扉にロックを掛ける。
厳重に二重のチェーンロックまで施して。
(//、`*川「おかえりなさいませ、ご主人様」
(//、`*川「そんなに血相変えて、なにかありまして?」
(*´・_ゝ・`)「君に聞きたいことがあるんだ!」
(//、`;川「は、はぃ?」
僕は足早に彼女に歩み寄ると、両肩に手を乗せて目を見開く。
言いたい言葉があるけど、息切れと、うまい説明が見つからなくて
パクパクと二度三度口を開いては閉じてを繰り返してしまう。
それが自分でもじれったくて、地団駄を踏みたい気分に駆られる。
(//、`*川「大丈夫ですよ、落ち着いてくださいな」
そんな僕の内情を察したのか、彼女は優しく語りかける。
以前僕がそうしたように、僕の髪に指を通す。
冷たい彼女の指の感覚は、僕の頭の芯を冷静にさせた。
目を瞑り、深呼吸をする。
出来るだけ、シンプルに伝えよう。そう思う。
それだけ決めると、僕はゆっくりと瞳を開いた。
そして彼女に告げる。
(´・_ゝ・`)「君に、料理をしてほしいんだ」
(//、`*川「ぅん?」
.
-
しまった、シンプル過ぎた。
僕の言葉の真意が汲み取れないまま、彼女は小首を傾げる。
その拍子に、しなやかな黒髪が包帯の下辺りに揺れて、
なんだかとても艶めかしい。
もう一度、今度はもう少し情報を添加して説明する。
(´・_ゝ・`)「君は以前『再現できる味に限りがある』と言っていたね」
(//、`*川「……ええ、言いましたわ」
(´・_ゝ・`)「それは、"五基本味"しか再現できないってことなのかな?」
(//、`*川「――それとも、もっと複雑な」
(´・_ゝ・`)「"料理"の中で限りがあるってことなの?」
(//、`*川「そ、れは……」
僕が彼女を家に招いて初めて、言い澱む。
その顔は迷いであり、怯えであり、恐れであり、哀れみでもあるように思えた。
彼女の表情の根底にあるものにすぐに合点がいく。
僕は彼女は次の言葉を紡ぐより早く、再び話を切り出した。
(´・_ゝ・`)「クリアランス違反……ってこと?」
(//、-*川「――そうですわ」
.
-
単純な話だ。
今までの彼女との会話の中で、僕からクリアランス違反の話をすることはあっても、
彼女から新しく知り得る様な情報を開示されたことは一切なかった。
それは彼女の思いやりだ。
あるいは単にロボットしての原則従っているのかもしれないが
ともかく彼女が僕をご主人様と呼んでいるということは、
少なくとも僕の立場を危うくするような行為は一切出来ないということなのだろう。
味の話も、再現も、僕が僕のクリアランスで知り得る範囲である
"五基本味"の中だけで行われてきた。
美味人形の存在だって、
そういうものが上流階級にはあるという事は下級市民にも開示されている。
だが、そこまでだ。
この世界に"五基本味"以外の味があり、
それらを組み合わせて更なる美味を生み出せるという事は
最上階級でしか知り得ない情報だ。
本をくすねて、クリアランス外の情報を持つ僕ですら
何故か遠いおとぎ話のように思っていた。
だから現実にしようなんて一度も考えなかった。
.
-
でも、事情が変わった。僕は手に入れてしまったのだ。
(´・_ゝ・`)「……これを、見てほしい」
僕はコートの裏側に隠していた一冊の本を彼女に見せた。
残る左目を大きく見開いて、彼女は僕の顔と本とを交互に見た。
(//、`*川「――料理のレシピ本」
(´・_ゝ・`)「そう。もう僕は知ってしまった」
(´・_ゝ・`)「料理というものは、物語の中だけの存在じゃない。現実に作り出せるものなんだって」
(´・_ゝ・`)「……答えてほしい」
(´・_ゝ・`)「君は、料理の味を再現、出来るの?」
しっかりと、彼女の瞳を見据える。
人工角膜の向こうにセンサーアイがうっすらと見える。
そのピントが収縮と拡散を繰り返し、小さくカシャと音を立てる。
そして、一度目を閉じると
僕の胸に頭を埋めるように寄りかかりながら、腰に手を回してくる。
しっかりと密着した状態で、彼女は僕の質問に答えた。
(//、^*川「――出来ますわ。貴方がそれを、望むなら」
その声は、音響装置を通して出ているはずなのに、震えている様ように聞こえた。
.
-
僕はレシピ本を普段食事に使用しているテーブルの上に置くと、あるページを開いた。
本来ならば燃やすべきこの本を、懐に入れてしまった一番の理由がそこにある。
(´・_ゝ・`)「僕は、コレが、食べてみたい」
そう言って指さしたレシピのタイトルは、【Strawberry sponge cake】
見開きの右ページは原材料と制作の工程表が、
左のページには、完成品と思われる料理の写真がカラーで掲載されている。
おそらく数百年以上前、まだ人類が地上に暮らしていた核戦争以前の産物だ。
僕はこの写真の中の料理に惹かれてしまった。
三角柱の形は、おそらく円形の一部をカットしたものだろう。
海綿質の柔らかな層の間に、白いクリームが挟まり、
赤い果実の断面が見えている。
層の上部にも、クリームがたっぷりと飾られていて、
その頂点に血液のように昏い紅色をした果実が輝いていている。
味も食感も全くの未知。
しかし僕の脳髄に直接響くように、この料理を食べたい衝動が広がる。
写真を見ているだけで、口内に唾液が溜まっていく。
なるほどコンピューター様の見立てはまったくもって正しかった訳だ。
一度味をしめてしまえば、その先の人間の欲望に歯止めはない。
僕は本来ならば、仕事終わりにダストシュートにまとめて放り込むはずの本の束から
レシピ本だけを抜いて、懐に隠し家まで持って帰った。
そして彼女に味の再現をこうして頼むに至るのである。
.
-
(//、^*川「これはまた、随分とお可愛いものを」
先程までの震えた声と不安の表情をすっかり消して、彼女は笑う。
どうやらこの料理は男性市民が口にするのは恥ずかしい類のものらしい。
(´・_ゝ・`)「この料理を知ってるのかい?」
(//、`*川「これは、『スイーツ』と呼ばれる菓子類ですわ」
(´・_ゝ・`)「菓子……」
いくつかの図書にその言葉が出てきたのを思い出す。
ちょっとした空腹を満たすための、甘い料理という説明だった気がする。
なるほど写真をよく見てみれば、確かに横に添えられたフォークと大きさを比べると
それほど食いでのある料理では無いらしいことが分かる。
(//、`*川「旧時代に、女性が好んで食べたモノですわよ」
(;´・_ゝ・`)「そ、そうなのかい? でもこんなにキレイなものに、男も女もないさ」
ロマンチストですのね、と彼女はもう一度口元に手を添えた。
その笑みが終わると、彼女は僕に背を向けて、
人工食糧が保管されている戸棚の前まで歩む。
そしていつもの食事の準備と同じ様に、皿の上にそれを盛り付けると、
テーブルの上、開かれたレシピ本の隣に置いた。
.
-
(//、^*川「きっと写真を見ながら食べたほうが美味しいですわ」
(//、`*川「さぁ、おすわりになって」
そう言って手のひらで椅子を指し示す。
僕はその申し出に素直に従う。
ほぼ着席と同時に人工食糧に手を伸ばしたけど、
ふと彼女の方を見ると、じっと僕の顔を見つめていたので、
なんとなくもう一度尻の居所を調節してから、「いただきます」と言った。
(//、^*川「はい、召し上がれ」
いつものやり取りをこなすと、彼女は満足したように両手を広げた。
先程よりも少し冷静な気持ちに引き戻された僕は、
無性に緊張しながら、再度皿の上に手を伸ばした。
この緊張の中には、『期待を裏切られたらどうしよう』という後ろ向きのものも含まれてしまっている。
定型のあいさつによりニュートラルに引き戻された思考が、もしもの保険をかけはじめているのだ。
それでも僕は欲求に抗うことが出来ない。
指の先につまんだ人工食糧も、いつもよりも重量がある気がしてならない。
震える指先を口元まで運ぶ。
一瞬彼女を見る。
笑っている。
それにひどく安堵を覚えて、僕は一気に口に放り込んだ。
.
-
(*´・_ゝ・`)「――っ!!」
突き抜けるような爽やかな刺激が、口の中で爆発した。
おそらくは酸っぱいに近い味なのだろうけど、全く嫌じゃなくて、
むしろいつまでもその中に溺れていたいと思わせるような、晴れやかなものだった。
その余韻もつかの間、次に現れたのが、まるい甘み。
それはいつも口にしていた単純な『甘い』とは全く違う質感を持っていた。
きめ細かく、かつ重厚なそれが、
行進するみたいに舌の上を縦横無尽に駆ける。
ゆっくり丹念に編み上げられた極上の織物のような、
軽いはずなのに質量があると錯覚してしまう上品な味。
その2つが続けざまに発現したあと、最高の波が遅れて到着する。
甘いと、酸っぱいの混ざりあったその味は、心臓の奥の奥まで到達したみたいで、
僕の胸は一気に苦しくなる。
なんだこれは。
服の上から心臓に手を当てる。大きく脈打っている。
今までの都市生活で感じたことの無い感覚。
それがこの味で想起させられているんだ。
例える言葉が見つからないまま、その味覚の奔流に身を任せる。
甘い、酸っぱい、甘い、酸っぱい。
苦しい。胸が。締め付けられる。
でも決して嫌じゃないんだ。嫌なんかじゃない。
.
-
――ポタ。
胸を押さえる僕の手の甲に、ほのかに温かい水滴が落ちた。
(´;_ゝ;`)「――あ」
僕は、泣いていた。
美味しい、なんて言葉だけじゃ何ページ書いたって足りない。
この味が説明出来ないように、自分の感情にも正しい意味をもたせることが出来ない。
僕は嗚咽を漏らさないように、むりくりに微笑みながら彼女を見る。
(//、-*川「いいんですのよ。本当に美味しいものを食べたら、人は涙を流すものですの」
彼女の冷たい指先が、僕の頬を走る涙の跡に触れた。
そして親指でゆっくりとそれを拭う。
僕は咀嚼を止めることも出来ないままだったけど、
彼女は何度も何度も僕の頬を撫でた。
それが嬉しくて、ありがたくて、涙の方も止まることが無かった。
.
-
(//、-*川「知っていまして?」
そう彼女は僕に投げかけたけど、
返答を求める問いかけじゃないことはすぐに分かった。
そのまま彼女の言葉に耳を傾ける。
(//、`*川「今ご主人の口に広がる味を『甘酸っぱい』っていいますの」
(´・_ゝ・`)「あふぁふっはい……」
(//、^*川「ふふっ、お口にものを入れたまましゃべるのはお行儀がよろしくありませんわ」
(´・_ゝ・`)「むぐ……」
(//、`*川「この『甘酸っぱい』には、前時代、変わった意味合いがありましたの」
(´・_ゝ・`)「――それは、なんだい?」
(//、`*川「……」
(´・_ゝ・`)「……」
.
-
(//、^*川「――ふふっ」
(//、^*川「ひ・み・つ、ですわ」
(;´・_ゝ・`)「……なんだい、それ」
(//、^*川「でもね、ヒントを差し上げます」
(//、`*川「もし、今、私が擬似的に模倣しているこの感情に名前をつけるなら、きっと」
(//、^*川「とっても『甘酸っぱい』ものになりますの」
(;´・_ゝ・`)「……わからん」
(//、`*川「往々にして、殿方とはそういう生き物ですわ」
(//、^*川「さぁ、まだまだたくさんありますわ。残さず召し上がってください」
彼女はそれだけ言うと、頬杖付いて、僕の顔を眺めるようにした。
頭の中には彼女の言ったヒントが飛び回っていた。
それでも彼女のススメ通り、更に手を伸ばしているうちに、ゆっくり記憶の底に消えていった。
.
-
すっかりと平らげる頃には、すでに明日の仕事に支障が出てしまうほどの時間が迫っていた。
一つ一つをあまりに大事に食べすぎたらしい。
僕は少し焦りながらも、ごちそうさまと、それから彼女への謝辞を忘れなかった。
その言葉に、彼女は微笑みだけで返すと、皿をテーブルから取り上げ、流しへと向かった。
(´・_ゝ・`)「あ」
瞬間、口の中にザラつく無味の感覚が蘇った。
食事が終わったので、彼女の感応効果が切れたのだ。
その不快な質感に思わず声が漏れた。
彼女は首だけでこちらを振り返ると、
(//、`*川「どうか、しましたの?」
と言った。
(;´・_ゝ・`)「うん、ちょっとね」
僕はそれを返すのが精一杯で、コップの中の濾過消毒水を流し込んだ。
それで口の中の砂粒みたいな感触はとりあえず喉の奥へしまい込むことが出来た。
.
-
(´-_ゝ-`)「きっと『本物』なら、こんなことないんだろうな……」
意識せず零れた自分の言葉に気づいて、慌てて口を覆った。
そんなことで、発言を取り消せるわけでもないのに。
恐る恐る彼女の方を見る。
先と変わらない様子で洗い物を続ける後姿に、僕は胸を撫で下ろした。
間違っても言っちゃいけない言葉だった。彼女に対してあまりにも失礼な――。
人間の欲望に際限がない。
やはりそれは正しい。
手際の良い洗い物の音に耳を傾けながら、僕は自責と自制の念を、今一度深く心に刻んだ。
.
-
********************************************
それから僕は定期的に、彼女にレシピ本から味の際限を頼んだ。
カレーに、ハンバーグに、唐揚げなんていうのも食べた。
どうやら僕の味覚は前時代でいうところの『子供』に相当するものらしくて、
そういうものばかり頼む僕に、彼女はいつも微笑んだ。
全部美味しかった。
そしてやっぱりそのどれもがそれ以上の言葉で飾ることが出来なかった。
僕は仕事に行く前に、必ず彼女に本を一冊渡す。
家に戻ると、大抵彼女はソファに腰掛けて、その本を読んでいた。
食事の話題は必然的にそれら本の内容に関してだった。
あれが面白かった。コレはイマイチだった。
この登場人物が好き。こいつは嫌い。
この会話も、当然今まで誰ともしたことが無かった。
だから凄く楽しくて、僕はいつまでも彼女とこうしていたい想いに捕らわれる。
美味しい料理と、素敵な友人。
たったこの2つで人生がどれほど豊かになるのか、
この都市の市民の何人がこのことを知っているのだろうと思うと、
やはりここが哀れな囚人共の牢獄でしか無いことを嫌でも再確認させられた。
.
-
――その日も、雨が降っていた。
濡れないように細心の注意を払いながら、帰路につく。
デルタ・コンプレックスの天候と昼夜には一定の規則がなく、
コンピューター様の思いつきでコロコロと切り替えられる。
中でも劣悪なのが、雨と夜の組み合わせだ。
ただでさえ視界の悪い雨の日に、夜の帳が降りる。
これは完璧に区画整理された居住区画で目的地にたどり着く確率を格段に下げる。
間違った部屋に入れば処刑対象なので、
こういう日は誰も外出したがらないし、仕事を終えた市民はそのまま仕事場で朝を迎えるか、
ある程度の覚悟の下帰宅するかのいずれかを選択しなければならない。
家に帰らない選択もリスキーで、
例えばそのまま朝を迎えた直後にコンピューター様からのトラブルシューティング依頼が来たりすると、
風呂に入る間もなくブリーフィングに出席することになる。
そうなると、その後に待ち受ける"清潔度チェック"でとんでもない目にあったりもする。
全くもって質の悪い――
.
-
そんなことを考えていると、雨の向こう側に人影を見た。
暗くて視界も悪かったので、一瞬見間違いかとも思ったが、
確かに左右に揺れるように進んで行く姿を見つけた。
傘を差していない代わりに、
撥水加工のされたレインコートを羽織っているようだ。
この区画を往くにはあまりにも命知らずな速度で、
半ば駆けるように大通りの角を曲がっていった。
あの曲がり角の先には僕の家がある。
胸騒ぎがして、僕も歩を早めた。
.
-
(´・_ゝ・`)「ただいま」
(//、`*川「あら、おかえりなさい」
彼女はいつもどおりソファに腰掛け文庫本を読んでいた。
僕が扉を開けると同時に本を閉じて、僕の方に歩み寄る。
その時、一瞬なにかに躓くようによろけはしたが、
すぐに体勢を立て直す。
(//、^*川「ごめんなさい、昼間ワックスを掛けたので滑りやすくなってるんですの」
そう笑いながら、濡れて肌に張り付いた僕の仕事着を脱ぐのを手伝ってくれる。
……なにも変わったところはない。
自分の取り越し苦労に胸を撫で下ろしながら、
それでも一応確かめずには居られなかった。
(´・_ゝ・`)「――今日、君、外出とか……した?」
(//、^*川「あら、いやですわ。私これでも逃亡者ですのよ?」
僕が冗談を言ったと思ったのか、彼女は肩を震わせて笑う。
その笑い声にどこか無機質なものを感じながらも、
僕はそれ以上追求することが出来なかった。
僕の彼女に対する疑念が悟られるのも嫌だったし、
それ以上に、この先に踏み込むことの出来ない壁のものに僕は気圧されていた。
いつも通りの美味しい食事と、楽しい会話。
でも僕はそれに集中できずにいた。
それでも、その内情を知られないように僕は努めて明るく彼女と話した。
.
-
――僕は、間違っていたし、正しかったと知る頃には、取り返しがつかなくなっていた。
.
-
その日は大捕物を終えた後で、酷く疲れていた。
有毒図書を所有する"赤《レッド》"階級の市民がミュータント能力を持っていて、
しかもそれが透明になる事ができるなんていう、こと逃亡に関して実に厄介な代物で
追跡と捕縛に予定の数倍以上の時間と人員を割かれたのだ。
しかもその有毒図書というのも、前時代のポルノ雑誌で
一部の職員を除いては、脱力と同時に座り込んでしまうほどの下らなさだった。
珍しいことに、今回の事案に参加した焚書士には明日の特別休暇が与えられ、
その誰もが一日中睡眠でも取ろうという漠然とした決意を胸に帰宅した。
(´・_ゝ・`)(意外とこういう時にトラブルシューティングの指令が入ったりするのが人生なんだよなぁ)
僕は捻くれた考えを抱きながらも、工業区画を抜けようとする。
爪'ー`)「ダンナ」
聞き覚えのない嗄れた声と共に、僕の合皮鞄の端が掴まれた。
咄嗟に、僕は鞄から光線銃を引き抜くと、振り返りざま声の主に突きつけた。
.
-
爪'ー`)「おっとっと、止めてくださいよ。怪しいものですが悪人じゃねぇ」
(´・_ゝ・`)「……物取りなら、相手が悪かったね」
爪'ー`)「知ってますよ。結構噂立ってますぜ、歴戦の焚書士だって」
――なるほど、どうやらコイツは"土竜《ジムグリ》"の類らしい。
普段はコンピューター様の監視の目が届かない通気口や、
地下都市の更に地下を走る下水管の中を住処にしていて、
機密情報の売買や、違法物資の流通、闇市の経営などを生業としているアウトローの総称だ。
(´・_ゝ・`)「僕は、君を知らないけど」
僕は無造作に構えていた銃の先を、
しっかりとそいつの眉間に合わせながら返す。
『僕の特別製の鼻』のことを知られたのであれば、
この場で処刑する必要があった。
この手の輩は情報を元手に強請りも集りもやる。
そして骨の髄までしゃぶり尽くされて気が狂った同僚を一人知っている。
爪'ー`)「怖いなぁ……こわい、こわい」
ひっ、ひっ、と粘ついた笑いに肩を震わせる土竜に、嫌が応にも眉間に皺が寄る。
ただでさえ不愉快な悪臭をその身に纏ったコイツに、馬鹿にされている気分になる。
もう面倒くさいから、いっそ引き金を引いて帰ってしまおうか。
.
-
そこまで考えた僕に勘付いたのか、土竜は早口に話しだした。
爪'ー`)「いえね、ダンナにはお世話になってやすもんで、一度ご挨拶と思いましてね」
(´・_ゝ・`)「……?」
(´・_ゝ・`)「もう一度言うよ。僕は君を知らない」
爪'ー`)「いやいや、姿形は知らなくても、存在はご存知でしょ?」
(´・_ゝ・`)「そりゃ君らみたいな溝鼠がこの辺りを寝ぐらにしてるのは知ってるけど」
爪'ー`)「え、いや、そうじゃなくてですね」
爪'ー`)「……ありゃりゃ、こりゃおかしいな」
(´・_ゝ・`)「なんだい、一人で合点しないでくれ」
爪'ー`)「もしかして、ダンナからの依頼じゃないんですかい?」
(´・_ゝ・`)「だから、何が」
爪;'ー`)「……マジですかぃ」
爪;'Д`)「こりゃ、まずい」
そこまで言って、土竜の顔から笑みが消え、額の皺に汗が浮かんだ。
同時に僕の胸中には暗雲が立ち込める。
フラッシュバックするように、あの雨の夜、レインコートの後ろ姿が脳裏を過った。
.
-
爪;'ー`)「……怒らないで聞いてくれやすか?」
土竜の言葉は、急に媚びるような声色に変わった。
本当ならは逃げ出すのがセオリーなのだろうが、
こうも至近距離で光線銃を突きつけられてはそれも出来ない。
だから逃走から、哀願、命乞いにシフトさせるといった様子だ。
(´・_ゝ・`)「内容による」
僕はそれだけ返すと、話の続きの催促をするように顎をやった。
爪;'ー`)「先に言っときます。
アッシは武装なんかは一つも持ち合わせておりやせんので、いきなりZAP、ZAPは無しにしてくださいね」
そう言うと、土竜は身にまとった襤褸切れの内側に手をやった。
そして戻ってきた手に握られているのは、
何処かで見覚えのある、金属の球体だった。
.
-
(;´・_ゝ・`)「――センサー……アイ?」
爪;'ー`)「……てっきり、借金にでも困ったダンナが、
自分の自律人形にパーツを切り売りさせているもんだと」
(´・_ゝ・`)「――いつからだ」
爪;'ー`)「さ、三ヶ月ほど前になりやす」
――丁度、あの日の辺りじゃないか。
僕が彼女に料理の再現を頼んだ、あの日から。
(´・_ゝ・`)「今まで、どんなパーツを買った」
明らかに怒気を孕んだ僕の声に、土竜は一層身を縮こませながら答える。
爪;'ー`)「基本は内部パーツです。"調律器《ハーモニクサー》"、"平衡維持装置《スタビライザー》"……」
爪;'ー`)「それから服で隠れる部分の人工被膜と、その下のケイ素クッションも頂きやした」
(´・_ゝ・`)「それで、今日はその、センサーアイか?」
爪;'ー`)「い、いえ、コレは初日にお売り頂きやした」
爪;'ー`)「包帯で隠れている部分だから、いらないって……」
爪;'ー`)「あまりに上等品だったんで、こうして肌身離さず持ち歩いてるんです」
.
-
(´・_ゝ・`)「それじゃ、今日は――」
爪;'ー`)「……それが、そのう――」
(#´・_ゝ・`)「サッサと言えッッッ!!!!!!」
僕の放った怒声は、工場の軋むような駆動音をかき消すように広がる。
剥き出しの鉄骨や金属の壁に反響して、その語尾が間延びする。
爪;'Д`)「きょ、今日が最後だって……」
爪;'Д`)「『闇市で材料が揃う』って――」
もう一度襤褸切れの中に差し込まれた手が、一際大きな金属の塊を掴んで戻ってくる。
機械に疎い僕にだって分かる。
それは、
彼女の命そのものじゃないのか。
(´・_ゝ・`)「"主電源装置《メインパワーセル》"……」
爪;'ー`)「だいぶイカれてやしてね、あと数ヶ月も持たないって代物でした」
爪;'ー`)「それでも、あっしはそれだけは止したほうがって言ったんですぜ?」
爪;'ー`)「でも予備電源があるからって……、あと数時間でいいって……」
.
-
穴が、空いたような、気がした。
足元に、ぽかんと。
昏く、深く、悲しく、寂しい。
虚無であり、虚脱であり、悔恨であって、絶望だった。
(´・_ゝ・`)「あ、あ……ぁ――」
自分がどんな顔をしているのか分からないけど、
土竜の反応でなんとなく察しがついた。
酷い、顔なのだろう。
爪;'Д`)「あ、あっしこんな稼業で、もう"予備"がありやせんで……」
眼の前の溝鼠が吐く、汚物にも似た言葉は耳に入れど聞いていなかった。
ただただ彼女の笑顔と、美味しい料理と、
そしてあの日僕が言ってしまった言葉が、繰り返し頭の中をかき乱す。
爪;'Д`)「ひっ、ひぃいッ!」
そんな僕の隙を付いて、土竜は反転すると一目散に駆け出した。
その背中に光線銃を浴びせる気力すら、今の僕には無かった。
(´・_ゝ・`)「……そうだ」
急がなくては。
奴が言っていたじゃないか。
あと、もって、数時間だと――
.
-
僕はこの仕事を始めてから何年も使い古した合皮鞄を放り投げた。
少しでも身軽になりたかった。
そして、一秒でも早く、彼女の下へ辿り着きたかった。
重い、足が重い。
苦しい、胸が苦しい。
熱い、目頭が熱い。
嗚呼、今の僕の感情を、彼女風に表現するなら、きっと『苦い』がお似合いだ。
.
-
(´・_ゝ・`)「ただいま」
家に入る前は、あんなにも纏まらなかった思考が
玄関ドアを開けた瞬間にクリアになった。
(//、^*川「おかえりなさいませ」
それはきっと、彼女がいつものように微笑んでくれたからで、
だからこそ僕は、いつも通りで居なきゃいけないって、そう思ったんだ。
部屋の明かりはすべて落とされていて、
いつも食事に使っているテーブルの上だけが仄かに光を放っていた。
(´・_ゝ・`)「今日も大変だったんだ」
僕は言いながら、コートを脱ぐ。
彼女はそれを受け取ると、ポールスタンドに掛けた。
(//、`*川「毎日お疲れ様ですわ」
言いながら、よろける。
そうだ、彼女の中に平衡維持装置はもう無い。
机の上の明かりを頼りに、僕らは向かい合って座る。
.
-
中心には、真っ白の皿の上に、あの日写真で見たとおりの、あの菓子が盛られていた。
底辺に丸みを帯びた、二等辺三角形の三角柱。
一番下に、薄い黄色の海綿層。
その次は美しく光を反射する白い滑らかな層。
赤い果実の断面は、肉眼で見ても分かるくらいに瑞々しかった。
その上にもう一度海綿層があって、その上にはクリームが丁寧に、均一に塗られていた。
最後に、クリームで作られた飾り器がデコレートされていて、
その上に、紅く熟れた果実が、一際素晴らしい芳香を放ちながら、乗っていた。
その脇には蝋燭が立てられ、小さな燈が灯っている。
(*´・_ゝ・`)「わぁ、美味しそうだなぁ」
渦巻く『苦い』も『しょっぱい』もおくびにも出さず、
僕は柔らかに微笑む彼女にそう言った。
(//、^*川「どうぞ、召し上がれ」
いつもと、同じ、彼女の声音に、僕は、すぐにでも、泣き出してしまいたくなる。
.
-
(´-_ゝ-`)「頂きます」
一度手を合わせ、目を瞑る。
目尻から、すうと、熱いものが流れ落ちた気がする。
皿の横に添えられた金属製のフォークを手に取る。
悟られるな、震えを。
彼女は"美食人形《グルマヌカン》"。
僕はそのご主人様なのだ。
食事は、楽しいものでなくてはならない。
フォークの先が、緩慢に皿へと向かう。
心臓が、痛い。
.
-
(//、`*川「……私」
その静謐な空気を割いたのは、意外にも彼女の方だった。
フォークの位置はそのままに、彼女を見つめる。
(//、`*川「大好きなお伽噺がありますの」
唐突に。
(//、`*川「一番最初にご主人からお借りした『オスカー・ワイルド』の短編集」
そこまで聞いて、僕は、もう一つの過ちに気がついた。
喉の奥が、痛い。
(//、`*川「素敵なお話でしたわ」
(//、-*川「私も、こんな風に生きたいって思いましたの」
ああ、止めてくれ。
僕は、君に、何もしてあげられていないのに。
(//、-*川「私も、あの『幸福な王子』みたいに、誰かの幸せのために、そう、思いましたのよ」
(//、-*川「もうすぐ尽きる命ならば、せめて、誰か、愛する人に――」
.
-
(//、`*川「――ねぇ、ご主人」
(//、`*川「今」
(//、^*川「幸せですか?」
.
-
微笑む。
あの日見た、雨に濡れた彼女の顔。
同じように微笑んでいた。
廃棄処分寸前で逃げ出し、『苦くて』『しょっぱくて』、
それでもその中で僕に笑いかけてくれた。
なぜ、僕だったの?
幸せか、だって?
そんなの、
そんなの――
(´^_ゝ^`)「――幸せだよ」
.
-
この後にも、いっぱい、たくさん言葉を紡ごうとしたのに、何一つ出てこなかった。
そのかわりに、一気に僕の双眸から涙が溢れた。
みっともなく、嗚咽を漏らしながら、フォークを握っていない方の手でズボン生地を握りしめた。
(//、^*川「――召し上がれ」
彼女はもう一度そういう。
僕は涙でぐしゃぐしゃになりながら、フォークを生地に沈ませ、一角を削り取る。
想像通りの柔らかな質感と彼女の肌の思い出が重なる。
喉はこんなにもひりついているのに、
僕はそれを口に運ぶという行為を止められなかった。
食べたかった。
彼女の与えてくれた『幸福』を。
一つも残さず、全て、キレイに。
舌の上に乗せられた、その切片は、あの日再現された味と寸分違わないもので、
しかし食感が伴っているだけで何倍もの美味に感じられた。
(´;_ゝ;`)「ふぉいひぃよ……」
これが、僕の精一杯だった。
僕には、これしか、無かったんだ。
.
-
(//、^*川「あらあら、ものを口に入れたままお話しては駄目なんですのよ?」
いつか聞いたセリフも、何もかも、すべてが、幸福の為に。
(//、-*川「でも、今日だけは、もっと言ってくださいまし」
(´;_ゝ;`)「ふぉいひぃ……」
(//、-*川「もっと」
(´;_ゝ;`)「ふぉいしい」
(//、-*川「もっと……」
(´;_ゝ;`)「おいしい」
(//、-*川「もっと――」
(´;_ゝ;`)「美味しい、美味しいよ」
.
-
(//、^*川「――ふふっ」
(//、`*川「私も、私にとって」
(//、-*川「貴方との生活は」
(//、^*川「とっても『美味しい』ものでしたわ――」
もぐ、もぐ。
(//、`*川「――ご主人は、お好きなものは最後に食べるんですのね」
もぐ、もぐ。
(//、`*川「ねぇ、その果実。それが『甘酸っぱい』んですの」
もぐ、もぐ。
(//、`*川「あの日の答え、教えて差し上げますわ」
もぐ。
(//、-*川「『甘酸っぱい』っていうのは――」
ごくん。
.
-
****************************************
_、_
( ,_ノ` )「馬鹿野郎、随分な場所におっ建てやがるじゃねぇか……」
店に入ってくるなり、男はそうこぼした。
厚手の合皮で出来たロングコートを着ていても筋肉質な体つきである事が分かる。
(´・_ゝ・`)「コートは入り口のポールにでも掛けてください」
僕はそれだけ言うと、コップに氷と水を注いで、カウンターの上に乗せた。
_、_
( ,_ノ` )「おいおい、俺は客じゃねぇぞ」
(´・_ゝ・`)「入り口からご入店いただいた以上、誰もお客様です」
_、_
( ,_ノ` )「変わったやつだな。このご時世に料理なんてよ」
(´・_ゝ・`)「好きなんです。それじゃ駄目ですか?」
_、_
( ,_ノ` )「この地下都市で、他人のために何かやることに意味なんてねぇだろ」
(´-_ゝ-`)「食べてくれた人が、美味しいって笑ってくれれば、それで」
_、_
( ,_ノ` )「やっぱりあんた、変わりもんだ。もしくは筋金入りの"偏執狂《パラノイア》"だ」
(´-_ゝ-`)「……そうかもしれませんね」
男はそれに答えることはせずに、お冷の乗ったカウンターの前に座る。
光線銃は手にしていない。
.
-
_、_
( ,_ノ` )「闇市で買った天然素材で作った、前時代の美食を振る舞う……ねぇ」
(´・_ゝ・`)「ちょっとしたコネクションがね」
_、_
( ,_ノ` )「土竜あたりか?」
(´・_ゝ・`)「まぁ、そんなとこです」
_、_
( ,_ノ` )「これだけの規模とメニューだ。金もかかるだろうに」
手元のメニュー表を開きながら、男は顎を撫でる。
(´-_ゝ-`)「焚書士時代に、ちょっとね、色々」
_、_
( ,_ノ` )「言わなくても大体分かるよ。蔵書のたぐいは闇市でも人気の品だ」
(´・_ゝ・`)「それで、お客様、今日は何をお召し上がりになりますか?」
_、_
( ,_ノ` )「だから、俺は客じゃね――」
(´-_ゝ-`)「"反乱分子《レジスタンス》"に正義の鉄槌を下す、勇敢なトラブルシューター様、ですか?」
_、_
( ,_ノ` )「――もういい」
(´・_ゝ・`)「さ、ご注文を」
_、_
( ,_ノ` )「……分かんねぇよ。俺のクリアランスに開示されてる情報じゃ、どれが美味いのか分からん」
(´^_ゝ^`)「どれも美味しいです」
_、_
( ,_ノ` )「――それじゃ、お前のオススメをくれ」
_、_
( ,_ノ` )「美味かったら、見逃してやる」
-
(´・_ゝ・`)「……それじゃ、これなんていかがですか?」
僕は、彼の手からメニューを受け取ると、あるページを開いた。
_、_
( ,_ノ` )「……なんだこの、三角形。黄色と白と赤って、本当に食い物か?」
(´・_ゝ・`)「味は、保証しますよ」
_、_
( ,_ノ` )「ほぉ……どんな味なんだよ」
(´-_ゝ-`)「――大変失礼ですが、お客様、恋人がいた経験はおありですか?」
_、_
( ,_ノ` )「なんだ藪から棒に。それと味が関係あるのか?」
(´・_ゝ・`)「大いに」
_、_
( ,_ノ` )「恋人なんて、コンピューター様が管理しているこの社会で、持ってるやつのほうが異常だぜ?」
.
-
(´・_ゝ・`)「それじゃ、きっと、この味は」
(´^_ゝ^`)「お気に召すと思いますよ」
_、_
( ,_ノ` )「なんだそりゃ」
(´・_ゝ・`)「だって、その味は――」
(´・_ゝ・`)Strawberry On The――のようです(//、`*川 【了】
.,
-
うおおおぉぉおつ!おつ!好き!
-
ミセ*>ワ<)リ「っしゃぁっ!! どやぁっ!!」
ミセ*>ワ<)リ「初めて"デミペニ"使ったけど、いいねっ! いいねでしたっ!」
ミセ;゚д゚)リ「ってもぉこんな時間!?」
ミセ;゚д゚)リ「明日もしご――」
ミセ;゚〜゚)リ「学校早いのにぃ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っ!!」
ミセ*>ワ<)リ「夜更かしは美容の大敵だからもう寝るねッ!」
ミセ*>ワ<)リ「それじゃ皆、ちゃんと読んでねぇ〜〜〜〜〜〜〜〜っ!」
.
-
爪;'ー`)y- 「今日、夜遅くまで仕事があるんだ」
爪'ー`)y- 「帰ってきたら投下すれば、セーフだよな?」
爪'ー`)y- 「今回も力作ぞろいで読み応えあったぜ。残りも楽しみだ」
-
投下するよー
-
(0)
安らぎを得られる時間とはどこだろう?
熱した頭で椎名は思考に耽っていた。
睡眠を回答にする人間はそれなりにいそうだ。
確かにそうだなぁと共感を持てる。
食事や入浴を回答にする人間もそれなりにいそうだ。
羨ましいというよりは妬ましい。
不特定多数に敵意を向け、椎名は手を真っ直ぐに伸ばした。
長方形の鏡に触れ、水蒸気を軽く拭う。
傷を抉る行為だった。既に不快なものを見ているというのに。
それでも止める事は出来なかった。
数秒もしない内に自身の全体像が露わになった。
シャワーに打たれ続けている女が、棒切れのような脚で立っている。
(#゚;;-゚)「はぁ……」
今日も椎名は醜かった。
.
-
(1)
ミセ*゚ー゚)リ「おーい、起きてますかー」
(*゚ー゚)「……え? ああ、うん」
ミセ*゚ー゚)リ「どうしたん? 寝不足?」
教室の机に身を預けていた椎名に、芹沢が声を掛けた。
(*゚ー゚)「いやさ、つい遅くまで机に向かっちゃって」
丁度大学受験を控えている時期だ。
誤魔化すためのカードはすぐ手元にあった。
ミセ;゚ー゚)リ「真面目だねー……しぃちゃんは。
私なんて駄目だよ、快眠続き」
(*゚ー゚)「そんなことないよ。ただちょっとブレーキが効かなくなっただけ」
椎名は立ち眩みを覚えながら帰り支度をした。
-
ブレーキが効かなくなった、というのはあながち嘘でも無い。
いわゆるやけ食いというやつだった。中々合格ラインを越え切れない。
そんな焦燥がストレスの種になり、手軽な発散方法を作ってしまった。
ここ半年ほどの椎名は就寝時間が遅くなっていた。
置かれている状況から、両親もどちらかと言えば応援する側だ。
時折夜食まで運んでくれるのだから感謝以外無かった。
しかし、食事に安らぎを見出しすぎてしまったのはこれが原因かもしれない。
ついには自ら買い溜めをし、菓子パンを摂取する毎日。
気づいた時には体重計の一の位が上がっていた。
-
ミセ;゚ぺ)リ「んー、昔の感覚で買っちゃうと太る気がするんだよねぇ」
帰路の途中で寄ったコンビニで、芹沢は食べ物を物色していた。
(;*゚ー゚)「昔って、半年も経ってないでしょうに」
ミセ*゚ー゚)リ「いやーハタチで人生折り返しって言うでしょ?
あれは嘘だねきっと。多分部活やめたら折り返しだよ。
もうあっという間。あーあ、そろそろ私もおばちゃんかぁ」
(;*゚ー゚)「その理屈だと部活入ってなかった私はどうなるの?」
ミセ*゚ー゚)リ「えっ、まあ長生きすんじゃない?」
(;*゚ー゚)「雑だなぁ……」
椎名は棚から適当にメロンパンを取り、芹沢も悩む事に飽きたのか同じものを取った。
-
会計を終え、店を出た二人は既に封を開けていた。
値段なりの味を楽しめる程度の話に花を咲かせ歩く。
椎名は今だけを考えるように努め、いつも通りの日常を過ごした。
やがて当たり前の別れが訪れる。
芹沢の影が完全に遠ざかると、張っていた気が瞬く間に緩んだ。
-
駅のトイレに駆け込み、無理やり嘔吐した。
良くない行為だとは分かっている。なのに体重が気になってしょうがない。
多分病気なのだろうが、通院する時間も勉強に当てたかった。
加えて親にこんな事を言いたくはない。根本的に椎名は見栄を張る人間だった。
可否はともかくとして、椎名は高校を卒業するまで意地を通し続けた。
途中から胃の中身が自然と上がってくるようになった。それでも醜態を晒さないように努めた。
その結果、逃げた。
ほとんど生活の体を成していない一人暮らしを始めた。
死ぬ気で入った大学では単位をかき集めるのが精一杯だった。
キャンパスライフという幻想はあっという間に崩れ去った。
.
-
(2)
椎名は夜が好きだ。
唯一の安寧である眠りが取りやすい時間だ。
しかし、それはそれで虚しかった。
どこに救いを求めているのか、という問いの答えが見えてしまいそうだから。
ただ、夜が好きな理由はもう一つあった。
こうして外に出る際に誤魔化しやすいのは大きな利点だ。
着こなせもしない標準サイズのニットを身に纏いながら、目的地へ足を進めた。
-
相も変わらずに毒々しい。
向かっていた場所に到着した椎名は少したじろいだ。
常時クリスマスシーズンを迎えているような外装だ。
寒色と暖色を詰め込んだ蛍光色のライトが目に差す。
防音しきれないノイズが耳を突き刺す。隣接する歩道の隅で騒ぐ学生で頭が痛い。
椎名は少し身を縮こまらせながら、ライブハウスの中へ入った。
ドリンク券と水で割ったようなビールを交換し、客席の後方に立つ。
ステージ上の明かりに近づいて姿が照らされるのは嫌だ。
熱狂に乗るのも難しい。なんとか場に溶け込めそうなのはこのポジションだった。
苦労の対価として楽しみが見合うのかは分からない。
それでも好きなバンドが近くに来たのだから聴きに来ようと思った。
-
多分、椎名が高校生ならのめり込まない演奏が始まった。
その理由は大人になったからでもなんでもない。
メジャーなものが受け付けなくなってしまっただけ。
そんな、中学生まで退化しているような笑えるものだった。
別に人との違いを作るために聴いている訳ではない。
寧ろ違いなんて作りたくなかったのに、ここに収まってしまった。
もう愛の言葉は聞きたくない。
今の椎名には到底重ねる事が出来ない。
結局、あなたとか君なんてどこにもいないのだから。
-
目が巻き髪で隠れているボーカルが気だるい生活を歌う。
椎名がリピートしている曲だった。聴衆は静かに熱狂している。
なのにどうしてだろう、鳥瞰してしまう自身に気がついた。
ここに集まったファンは似たような思いを抱いているはずなのに、疎外感を覚える。
分かっている。一ミリ単位も狂いがない共感なんて無い。
分かってはいるのに、結局全員他人なんだなと、当たり前の事が胸を重くさせる。
私は何を求めに来たのだろうと、椎名はノイズを聞き流し続けた。
-
(,,゚Д゚)「姉ちゃん一人かぁ? 俺と遊ばねぇ?」
俯きながらライブハウスから出ると、一人の男に絡まれた。
顔を上げて分かったが、キャッチという格好には見えない。
恐らくは椎名と同じような年代の学生だった。
半端に茶色が混じった髪をした男は、如何にも酒気帯びといった様相だ。
普段なら軽く断って人混みに逃げるという選択肢もあった。
だが、その日の椎名は無視をしてフラフラと歩くしか無かった。
(,,゚Д゚)「おい聞いてんのか!」
(;*゚ー゚)「……っ!」
-
後方から男に手首を握られた。
チークや服なんかでは誤魔化せない、椎名の中身だった。
(,,゚Д゚)「……は?」
気の抜けた声が聞こえる。
椎名は男を振り払い、足早に去っていく。
(,,゚Д゚)「……きっしょ」
背中に突き刺さった言葉を拭い去る事は、椎名にとってはあまりにも困難だった。
.
|
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板