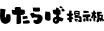レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
( ^ω^)文戟のブーンのようです[3ページ目]
-
≪とりあえずこれだけ分かっていれば万事OKなQ&A≫
Q.ここってどんなスレ?
A.お題に沿った作品を指定期間内に投下
投票と批評、感想を経て切磋琢磨するスレ
Q.投票って?
A.1位、2位とピックアップを選ぶ
1位→2pt 2位→1pt で集計され、合計数が多い生徒が優勝
Q.参加したい!
A.投票は誰でもウェルカム
生徒になりたいなら>>4にいないAAとトリップを名前欄に書いて入学を宣言してレッツ投下
Q.投票って絶対しないとダメ?
A.一応は任意
しかし作品を投下した生徒は投票をしないと獲得ptが、-1になるので注意
Q.お題はどう決まるの?
A.前回優勝が決める。
その日のうちに優勝が宣言しなかった場合、2位→3位とお題と期間決めの権利が譲渡されていく
Q.使いたいAAが既に使われてる
A.後述の「文戟」を参照
詳しいルールは>>2-9を参照してください!
また雰囲気を知りたい方は
スレ1
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/21864/1531744456/
スレ2
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/21864/1533540427/
へGO!!
-
('(゚∀゚∩ なんだか凄いことになってるね…
('(゚∀゚∩ どんどんクオリティも上がってて怖いんだよ…
('(゚∀゚∩ いつか潰されないかとか 、まあ僕は自分の作品を頑張って書くだけだよ!
-
(・∀ ・)「いっちばーん」
(・∀ ・)「とーかするぞ」
(・∀ ・)「あ、そうだ」
(・∀ ・)つ【閲覧注意】
-
( ・∀・)「いただきます」
一人きり、部屋の中でモララーは手を合わせる。
誰もいないからといってマナーをおろそかにするような教育を受けていない彼の所作は美しく、
お手本のような箸使いであった。
彼自身がこしらえた夕飯はわかめの味噌汁と魚の煮付け、
出汁巻き卵とほうれん草のおひたし。
そして白米。
絵に描いたような日本の朝食であり、
夕飯として出されると少々物足りなさを感じる者も多いかもしれない。
しかし、後は眠るだけのこの時間。
腹を満たす必要性は薄く、
健康面を考えるのであれば質素に見える程度が丁度良いのだ。
箸で卵焼きを割れば出汁が溢れ、
ほうれん草を噛めばしゃきしゃきとした音が鳴る。
テレビの一つ、ラジオの一つもついていない部屋は静かで、
モララーの食事の音だけが静かに響いていた。
( ・∀・)「ごちそうさまでした」
ゆっくりと時間をかけて彼は皿を空にする。
-
( ・∀・)「今日も美味しいご飯だった」
風呂に歯磨き、明日の準備。
寝るための準備を整えつつ、モララーは呟く。
気に入りの品種を大きめの炊飯器でふっくら炊いた白米には甘みがあり、
丁度いい火加減の出し巻き卵は硬すぎず柔らかすぎずの加減を守っていた。
他の料理に関しても同様で、
どれも満足のいくものを作れたと自負している。
だが、世間はいつも彼に言うのだ。
( ・∀・)「一人でも味気なくないのになぁ」
親元を離れて早数年。
一人暮らしにはすっかり慣れた。
平日にする料理も、
休みの日にまとめて行う家事も、
始めこそ戸惑いや失敗もあったけれど、
今では問題なくスムーズに行うことができている。
不便など一切ない、と言えば嘘になるが、
現状にモララーは充分満足していた。
けれど、周囲は彼をそう見ない。
-
会社の上司や同僚、パート達は休憩時間や始業前、
飲み会の席にたまたま出くわした電車の中で口を揃えて言うのだ。
「独り者は寂しい」
「食事が味気ないだろう」
何がだ。
モララーはいつも思っている。
しかし、できた男である彼は、
己の考えが少数派であることを理解しており、
人間関係において同調は非常に有効であることも知っていた。
( ・∀・)「そうですね。ボクにも良い人が見つかるといいのですが」
人好きのする良い笑顔を顔に貼り付け、
同じ言葉を繰り返す。
中身の伴わぬ薄っぺらなそれは、
今のところ誰かに見抜かれることなく過ごせている。
( ・∀・)「わっかんないなぁ」
寂しい、という感情は、
比較的理解の及ぶ範囲であった。
家族と暮らしてきた十数、あるいは二十数年。
周囲にあった自分以外の気配や物音が消えるというのは、
確かに違和感を覚えるものである。
-
その違和感を「寂しい」と形容することに疑問はあるが、
漠然とした理屈が見出せるのならば受け入れることもできた。
ならば味気なさはどうだろうか。
( ・∀・)「誰かがここにいたって、ボクの料理の腕前は変わらないし、
使う材料も変わらない。
だったら誰と食べたって一緒だろうに」
学生時代にいた恋人という存在も、
職場の同僚も上司も、
彼の味覚に何らかの変化をもたらしはしない。
両親に関しては検証を行ったことがないので憶測になってしまうが、
おそらくは彼らと共にレストランに行ったところで、
一人で同じ場所、同じ料理を食べた時と同じ感想しか抱けないだろう。
( ・∀・)「小学校の時なんて大変だったもんな」
洗い物を終えたモララーはしみじみと呟く。
いつ思い返してもやらかした、としか思えない時代が彼にもあった。
( ・∀・)「家庭環境の違いであそこまで浮くかね」
塗れた手を拭き、肩を回す。
これで今日の仕事は終わりだ。
残すところは眠るのみ。
-
目覚まし時計をいつもの時間にセットし、
モララーは布団の中へ入り込む。
閉じられた瞼に浮かぶのは、
遠巻きに見られている幼い己の姿だった。
( ・v・)「どーしてみんなといっしょに
ごはんをたべないといけないの?」
「せんせー、もららーくんへんだよ」
「いっしょにたべなくないなら、
お前どっかいけよ」
( ・v・)「……だって」
彼が大勢との食事に楽しみを見出すことができず、
舌の上に乗る料理へ振りかけられた目に見えぬスパイスを感知できぬ理由の一つに、
生まれ育った家庭環境というものがある。
モララーの両親は善良であったし、
夫婦仲が冷え切っていたわけでも、
地の底を這うような家計でもない。
共働きではあったが母親はいつもモララーのために暖かい食事を用意してくれ、
仕事に忙しくしつつもたまの休みになれば父親は子供と共に出かけ、
習い事がしたいと言えば教室に通わせてくれる、
誰から見てもわかりやすく幸せな家庭であった。
ただ一つ。
食事と共にする習慣がないことだけが、
世間から外れていただけ。
-
鍋やテーブルに用意された食事を温めるのはいつものこと。
出来立てを食べるときは母がずれた時間にとるのがモララーにとっての日常であった。
( ・v・)「うるさいなぁ……。
ボクはひとりでごはんをたべたいのに」
何が好きか、一口欲しい、
他愛もない雑談、騒がしい周囲というのは、
彼にとって非日常でしかなかった。
周囲から浮いた状態は中学を卒業するまで続き、
その間に人との関わり方をよくよく学んだモララーは、
遠くの高校へ入学することで新たな人生をスタートさせた。
大勢で囲む食事の美味さを理解できぬことで支障を感じたことはない。
一生をかけて望まねばならぬ疑問点ではあるが、
思考をめぐらせることを苦に思わぬモララーにとって、
些細かつ難解な疑問というものは人生の友も同然。
世間体のために隠さねばならぬ事項ではあれど、
唾棄し、絶望するようなモノには成り得ない。
成人して数年んが経つ今も過去の実験、検証の結果を元に思考を働かせている。
機会があれば両親や、全くの他人との食事というものも試してみるべきだろう。
好奇心の尽きぬ人生は素晴らしい。
モララーは己の奇異性に感謝すらしていた。
-
彼に転機が訪れたのは、上司に勧められた見合いの席についたときだった。
川 ゚ -゚)「初めまして。素直クールと申します。
友人にはクーと呼ばれています」
( ・∀・)「……」
お辞儀と同時に艶やかな髪が肩へ流れてゆくのを目にし、
思考は瞬きほども時間をかけずして消え去った。
髪だけではない。
落ち着いた声も、ちらりと見えた青をわずかに垂らした黒の瞳も、
細身の体によく似合う服装も、頭を下げるその所作さえ、
モララーの思考を押しのけ、心や脳の全体を占領してしまう。
川 ゚ -゚)「あの……?」
(;・∀・)そ「あ、はい!
すみません。少し、ぼーっとしてしまいまして」
相手からの無言に、クールと名乗った女性は戸惑いの表情を浮かべる。
窺うような声に正気を取り戻したモララーは、
一言謝罪を入れ、自身の紹介へと移っていく。
( ・∀・)「私は良野モララーと申します。
本日はこのような場を用意していただき、光栄です」
川 ゚ -゚)「こちらこそ。いつまでも独り身の私を心配し、
母が都合してくれたのですが、あなたのような人と会えるのであれば、
もっと早くに見合いというものを受け入れても良かったかもしれません」
-
片手では数え切れぬほどの女性と付き合ったことのあるモララーであるが、
今ほど感情が揺れ動いたのは生まれて初めてのことであった。
( ・∀・)「それで――」
川*゚ -゚)「ふふ、それ、本当に?」
いつになく会話は弾み、
出される食事も質の高さが窺えるもので、
実に良い時間を過ごすことができた。
( ・∀・)「よければ、また今度、
食事でもご一緒できればと思うのですが」
川 ゚ -゚)「奇遇ですね。私もいつ言い出そうかと考えていたところです」
過去の女性達と遊びで付き合っていたつもりなどないが、
クールと出会い、脈打つ心臓を鑑みるに、
あれらは全て本気の恋ではなかったのだろう。
恋や性交渉というものへの好奇心からあの関係はきていたに違いない。
この歳で初恋か、と思わないわけではなかったが、
それ以上にモララーは浮かれていた。
交換した電話番号とメールアドレスと携帯電話に打ち込むわずかな時間に幸福感を覚えるなど、
昨日までの自分に告げたところで信じないに決まっている。
-
川;゚ -゚)「遅れてしまってすみません」
( ・∀・)「いいえ。私も今きたところです。
それに、予定の時間から十分も過ぎてませんよ」
川 ゚ -゚)「たとえ一分であろうと遅刻は遅刻です」
眉を下げるクールに優しい言葉をかけ、
モララーは雰囲気が良いことで有名な店へ彼女を案内する。
既婚者の同僚もこの店を現在の奥さんとのデートに利用しており、
店員、料理、雰囲気、共に非常に良い、という評価をしていた。
顔も知らぬ不特定多数の意見とよく知る人物からの太鼓判があるのだ。
初デートの場所としては申し分ない。
( ・∀・)「二名で予約していた良野ですけれど」
木目調の扉を開ければ、
なるほど、ほの暗い店内にある光は炎を連想させる淡さと落ち着いた色味をしており、
店内にいる者の顔を優しく照らしている。
粗をぼかすと同時に、血色を良く見せる効果は、
恋人、もしくはその候補を連れてくるには最適なものであった。
流れるクラシック、店内に作られた細い水路を行く水の音。
瑞々しい観葉植物と半分個室のように区切られた席は、
同僚やネット上で絶賛されるに相応しいものである。
-
川 ゚ -゚)「モララーさんからのメール、
いつも楽しみにしてるんです」
( ・∀・)「それは嬉しいですね」
川 ゚ -゚)「つい話が弾んでしまって、
長話になってしまうのが申し訳ないな、と」
( ・∀・)「私は構いませんよ。
でも、そうですね。
もしも良かったら、次からは電話をしても良いですか?」
川*゚ -゚)「……もちろん」
クールの頬がわずかに赤く染まる。
照明による錯覚かもしれないが、
弾む調子を押さえ込んだような声を聞けば、
モララーの目が場の雰囲気に騙されているわけではないことは明白。
メールのやりとりは続けていたけれど、
直接顔を合わせたのは二回目だ。
展開が速すぎるだろうか。
否、モララーはひと目見たときから彼女に恋をした。
始まりが早かったのであれば、
続きが同様であるのは必然のはず。
勝機がないわけでもない。
( ・∀・)「……そしてできれば、
敬語もやめていただきたい」
-
他人としてではなく、恋人として。
それがまだ早いのであれば、
心が揺れ動く友人として。
モララーはクールの心に居座りたかった。
川*゚ -゚)「わかった」
小さく頷いた彼女に、モララーは安堵の笑みを返す。
( ・∀・)「良かった。
断られたらどうしようかと」
川 ゚ -゚)「そんなはずがないだろ?
もし断るなら、そもそもここにだって来ていない」
人によっては冷たく感じるかもしれないクールの言葉選びも、
モララーからしてみれば自分に素直かつ落ち着いた好印象にしかならない。
川 ゚ -゚)「電話やメールだけと言わず、
また美味しい料理も食べたいしな」
テーブルに置かれているのは、
トマトとキノコをふんだんに使ったパスタだ。
フォークを用いて口元に近づければ、
ハーブとトマトの芳醇なさわやかさが鼻腔をくすぐる。
-
口に含めば優しい酸味と共に、
キノコの味わい深さが広がり、舌先を楽しませてくれる。
前菜として出されたズッキーニーのオイル漬けも中々のものであったが、
パスタも予想を外さぬ美味さである。
次に出てくる肉料理への期待も高まるというもの。
( ・∀・)「これは次も良い店をリサーチする必要がありそうだ」
川 ゚ -゚)「次はキミの馴染みを知りたいものだが」
( ・∀・)「ここほどの料理は出てこないよ」
川 ゚ -゚)「普段の食事が知りたいんだ」
( ・∀・)「だったらいずれはボクの手料理も振るわないとだね」
川 ゚ー゚)「楽しみにしているよ。
勿論、私の手料理も食べてもらうことになるけど」
( ・∀・)「わお。最高だね。
その日が今から待ち遠しいや」
会話が弾む。
食が進み、アルコールが喉と胃を心地良く焼いていく。
見合いの席での料理も大そう美味しいものだったが、
この店も相当に質が高い。
二人で二万程度で良いのか、と本気で悩んでしまう。
-
初デートでこれほどの料理を出されてしまっては、
次回からの店選びはどれほど大変だろうか。
わずかな不安がモララーの脳裏をよぎるが、
きっとクールは見知った居酒屋の料理でも笑んでくれることだろう。
彼女を美化しているわけではなく、
極普通に生きている中で、これだけの料理をこの価格で見つけることは難しい。
そのことを理解し、高すぎるモノを望まぬだけの賢明さをクールは有している。
ブランド品を買い与えなければ満足せぬ豚のような女ではないのだ。
川 ゚ -゚)「今日も楽しかった」
( ・∀・)「ボクもだよ」
川 ゚ -゚)「……帰ったらメールをしても?」
( ・∀・)「ボクから送るかもしれない」
川*゚ー゚)「待ってる」
( ・∀・)「走って帰らないと」
川*゚ー゚)「競争でもしようか?」
( ・∀・)「怪我をしたら大変だ。
ゆっくり帰ってくれ」
-
二人は頻繁に連絡をし合い、
日常の中に週末のデートが組み込まれるようになった。
ショッピングでは互いの服や持ち物を選びあい、
気になっていた映画を鑑賞し、
コンサートや展覧会にも赴いた。
最後に行く食事の場所は交互に選び、
新しい店の発掘やオススメを紹介しあった。
( ・∀・)「……おかしい」
周囲から揶揄される程度には楽しく、充実した日々だ。
金曜になれば目に見えて浮かれ、
デートの日は一日を通して幸福感に満たされる。
別れた次の日には恋しさを覚え、
メールに電話にとクールの存在を確かなものにしようとした。
だが、満たされた生活の中、
モララーに一つの疑問が生まれる。
( ・∀・)「あの店はボクがよく利用してた店だ。
味は悪くないが、あそこまでではなかったはず」
週明けの月曜日。
自分で作った夕飯を口に入れつつモララーは思い悩む。
-
昨日、クールと食事をした店は、
馴染みとまでは言わずとも、
それなりの頻度で利用していた居酒屋だ。
悪い味ではないが特別美味いわけでもない。
変わったメニューがあることが気に入っていただけで、
その他に特筆するべきところはないような店だったはず。
( ・∀・)「……どうしてあんなに美味しかったんだ」
舌の上で広がった旨み、
歯ごたえから脳髄に伝わってくる味、
鼻から胃へ落ちてくる香り。
どれをとってもモララーの知るものとは違っていた。
料理人が変わったのか、と思い、
さりげなく厨房へ目をやりもしたが、
そこにいる禿げ頭は数年前からちっとも変わっていない。
使う食材が変わったのであれば大々的に宣伝を打つだろうし、
調理方法がここ最近で変わったにしても味の違いが劇的だ。
( ・∀・)「一体全体、どういうことだ」
自分の周りで、自分の理解が及ばぬことが起きている。
良い方向への変化であるため、不気味とまでは思わないけれど、
モララーの好奇心を刺激して有り余るほどの事態ではあった。
-
( ・∀・)「まずは落ち着いて前提を考えよう」
食事を終え、風呂に湯を溜めながら考える。
( ・∀・)「いつからこの異常は起きているのか」
頭の中だけで思考を完結させるのは賢いやりかたではない。
周囲に人がいない状態であるのならば、
思考を整理し、状況を再認識させる効果を期待し、考えを声に出していくべきだろう。
( ・∀・)「不明。ボクが認識しだしたのはここ数週間。
仮に数週間前からの異常であるとするならば、
その期間に何があったか」
記憶を掘り起こし、過去へと飛ぶ。
( ・∀・)「仕事の成績が上がった。
外食の回数が増えた。
クールと出会った」
明日の準備に手を動かし、
一つ一つ心当たりをあげていく。
( ・∀・)「ふむ。外食回数が増えたことで、
ボクの舌の好みが変わった……?
いいや、そうだとすれば年単位の変化になるはずだ」
-
ならば、とモララーは言う。
( ・∀・)「クールさんと出会ったことが原因だと仮定すると」
テーブルに置いていた携帯電話が震えた。
数回のバイブレーション。
メールを受信したのだろう。
( ・∀・)「彼女と話すことに集中するあまり、
味へ意識が向いていない……?」
散々に言われてきた、
誰かと共に食べる食事は美味しい、などという選択肢は最初から除外されている。
積み重ねてきた検証の結果が、
他者と食べる食事に変化はない、と結論付けていた。
クールは素晴らしい女性だ。
愛おしい存在でもある。
しかし、共に食事をする人間は味に変化をもたらさない。
決定的な要因を見つけぬ限り、
モララーは己の出した結論を覆すつもりはなかった。
( ・∀・)「あるいは」
携帯電話を手に取る。
クールの名前が画面にポップアップされていた。
-
ネットで見つけた可愛い動画の話に並び、
次に行く予定の店を見つけたこと、
残業で疲れたことが書かれており、
文末はおやすみなさい、という言葉で締めくくられている。
( ・∀・)「……彼女がいることで生まれるポイント」
返信を打ちながらも思考の半分が帰ってこない。
店に人間にも変化がなく、
他人が味に変化を及ぼさないのであれば、
要因はクールという人間にあるのではないか。
思い出されるのは、クールの艶やかな黒髪。
風に揺られたそれは、隣にいるモララーへ甘く優しい匂いを運ぶ。
笑顔は柔らかで愛らしく、普段は大きく、笑うときは細められる目は水分をたっぷり含んでいて美しい。
言葉を紡ぐ唇は弾力があり、初めてのキスをした際は夢中になってしまった。
( ・∀・)「そうか」
また明日、と付け加えたメールを送信し、
モララーは天啓を得る。
( ・∀・)「彼女は特別なんだ」
気づいてしまった。
好奇心が背を蹴りつける。
-
川 ゚ -゚)「お邪魔します」
( ・∀・)「何もない家だけでくつろいでてよ」
悩みに結論を打ち出して数週間。
モララーは初めてクールを自宅に招待した。
二人の関係は既に恋人未満を脱しているが、
時間の都合や互いの興味関心の都合で自宅訪問は後回しにされていたのだ。
川 ゚ -゚)「キレイな部屋だ」
( ・∀・)「物がないだけだよ」
川 ゚ -゚)「いいや、埃もないし、細かなものもきちんと整理されている。
日頃からちゃんと家事をしている人間の部屋だ」
( ・∀・)「そう褒められると恥ずかしいなぁ……」
本棚にしまわれている本の話や、仕事の話。
テレビをつけて番組に対する感想などを言い合っていれば、
時間はあっという間に過ぎていく。
( ・∀・)「もうこんな時間か」
外を見れば夕日が半分以上地の底へと沈みこんでいた。
もう間もなく世界は夜になる。
川*゚ -゚)「……今日は、泊まっても?」
-
クールの荷物はいつものポーチではなく、
大き目の旅行鞄だった。
恋人が自宅へ招待してきたのだ。
泊まりを想定するのは当然だろう。
( ・∀・)「一つ、話をしても?」
川 ゚ -゚)「ん? あ、あぁ、勿論だとも」
予想外の返しに言葉を詰まらせながらも、
彼女は是と応える。
( ・∀・)「ボク、人と食べるご飯に特別な美味しさとか感じたことがなかったんだ」
川 ゚ -゚)「そうなの、か?」
( ・∀・)「うちの家はみんなでご飯を食べる習慣がなかったからかな。
成長した今でも誰かの存在が食事をより良いものにしてくれるって感覚がなかった」
それがキミと出会って変わった。
モララーは優しい声色で言う。
( ・∀・)「よく行く店の料理があんなに美味しく思えたのは初めてだった」
川*゚ -゚)「ふふ、それは良かった」
クールは笑む。
当然だ。
恋人からキミは特別な存在だ、と言われて嬉しくならない女はいない。
-
( ・∀・)「たくさん考えた。
どうしてキミとならあの料理も、あの料理もどれもこれも美味しくなるんだろうって」
川*゚ -゚)「それは私だからこそ、か?」
( ・∀・)「その通り!」
モララーは両手を大きく広げ、
ソファに座っていたクールを抱きしめる。
( ・∀・)「キミが傍にいるだけで、
ボクの脳も舌もすっかり変わってしまう」
川*゚ -゚)「おいおい、どうしたんだ急に」
( ・∀・)「嬉しいんだ!
キミと出会えて。
新たな可能性に出会えて!」
川*゚ -゚)「……私も、嬉しいよ。
モララーと出会ってから、楽しいことだらけだ」
( ・∀・)「ありがとう。
キミという存在をボクは無駄にしない」
川 ゚ -゚)「それってどういう――」
クールの言葉が止まる。
背後から、鋭い冷たさが体内に入り込んだ。
-
川 ゚ -゚)「モ、ラ……?」
( ・∀・)「近くにいることで感じられる香りがボクの嗅覚を刺激した。
柔らかな肉体がボクの想像力をかきたてた。
世界で一番美味しいものがそこにあったから、
前菜まで美味しく感じられたに違いない!」
クールを抱きしめた右手には大振りのナイフが握られており、
彼女の背に突き立てられている。
モララーは一言を発するごとに刀身をより深く埋めていく。
川 ゚ - )「モッ……!」
( ・∀・)「わかるよ。キミの言いたいことは。
ずっとキミといれば、ボクは以前よりずっと美味しいものを食べ続けられる。
殺してしまうなんてもったいないよね」
でも、我慢できない。
常と変わらぬ表情と声で彼は言う。
( ・∀・)「好奇心が止められないんだ。
前菜まで美味しくしてしまうようなキミの体は、
一体どれほど至高なんだい?
味わいたい。世界最高を」
暖かい血がクールの服を、モララーの手を汚し、
黒のソファを伝って床まで侵食していく。
-
( ・∀・)「髪までちゃんと食べるからね」
川 - )「――ぁ」
柄まで埋まり、クールはか細く空気を吐いて力を失う。
鼓動の音が止まった。
( ・∀・)「よい、しょっと」
血抜きもしなければならないが、まずは死体を冷やさなければならない。
傷口から入り込んだ最近により、血液が腐ってしまう前に。
モララーはクールの体を抱き起こし、
先んじて溜めていた浴槽の氷水へと彼女の体を放り込む。
透明な水が赤く染まり行くのを確認しながら、
彼は次の作業の準備をしていく。
( ・∀・)「数日にわけて食べよう。
冷凍する分と、燻製にする分と、たたきと、煮込みと焼きと」
鼻歌混じりに道具を揃え、
とうとうクールの解体が始まった。
血を抜き、皮を剥いで部位を分け、肉を削ぐ。
何分、初めてのことであるため、全てを完璧にこなすことなどできるわけもなく、
赤が浴室に撒き散らされるが、モララーは気にも留めない。
充満していく鉄錆びにも似た匂いが彼の腹をくすぐって仕方がないのだ。
今の彼にあるのは食への探究心のみ。
-
( ・∀・)「いただきます」
解体という重労働を終えたモララーは、本日の夕飯に肉を並べた。
新鮮な肉を軽くあぶり、たたきにしたものと白米を前に、手を合わせる。
キレイな箸が一口サイズの肉をつまみ、
タレも何もつけぬままモララーの口へと運ばれた。
まずは食材そのものの味を確かめねばなるまい。
(*・∀・)「あぁ……。
これは、素晴らしい」
深い味わい。
舌の上でとろける感覚。
鼻にまで昇ってくる香り。
どれをとっても至上であった。
(*・∀・)「いかんな。箸が止まらない」
肉は有限だ。
クールは細身の女性であったため、
得ることができた量もそう多くはない。
欲望のままに箸を進め続け、
調理をしてゆけば、瞬きの間に至高の肉は消えてしまうだろう。
自制心を取り戻すためにその時を想像してみるが、
何とも耐え難い飢餓感に襲われてしまった。
-
( ・∀・)「キミほどの女性にはもう二度と会えないんだろうなぁ」
暗い外の世界へ目をやり、モララーは心底残念である、と言葉を零す。
一時の幸福が終わってしまえば、
残されるのはあの味気ない料理達だけ。
また共に食事を楽しめるような人間に出会えるとも思えない。
( ・∀・)「……やっぱり、ちょっともったいなかったかな」
皿の上に残された最後の一切れを突き、
ひと匙の後悔にふける。
( -∀-)「だけど、仕方ないよね」
だって。
( ・∀・)は好奇心に勝てないようです
了
-
(・∀ ・)「すぺしゃるさんくす! >>135」
(・∀ ・)「いや、悪かったな、ってはんせーしたからさ!」
(・∀ ・)「せめてオレ様がちゃんと書いてやろうって思って!」
(・∀ ・)ノシ「おれいはいらないぞ!
とーぜんのことをしたまでだ!」
-
開幕ぶっぱでなにしてくれとんねん!
-
('A`) (俺がこの文戟って企画で一番驚いたのは)
('A`) (俺以外の奴の筆の速さな)
('A`) (一体どうなってるんだ…)
-
(;"ゞ)「ホラー終わったから出てきたけどまだ続いてんじゃねえか! ふざけんな!」
(;"ゞ)「俺の短編で流してやる! 閲覧注意なんて流してやるからな! くっそ!」
-
「どうぞ、これを」
ことり、と音を立てて、デレちゃんは白い粉の入った小さな小瓶を机に置いた。
大きさは彼女の親指とほぼ変わらないから、それほど大きくはない。
「……それにしても、よかったのかお?」
「なにがですか?」
きょとんとした表情はツンと双子だとは思えないほど柔和だ。
それを彼女は自分には可愛げがない、なんて気にしていたことを思い出した。
「デレちゃんひとりで来て。おじさんとおばさんも来るものだと思っていたんだけど」
「お父さんとお母さんは、家で待ってます。大勢で押しかけても迷惑だろうし、って。それに……」
言い淀んで、デレちゃんは小瓶に視線を落とした。
かつて姉にそうしていたように、助けを求めているかのようだった。
「あんまり内藤君には重く考えないでほしいから、って言ってました」
「そう、かお」
-
そんな気遣いをされても、いまさらだ。僕はもうツンと約束をしてしまった。
そして、彼女の家族は僕にその約束を守らせようとしている。
そこに僕の意思はあるようで、実はないということを本当の意味で知っているのは、僕だけだ。
「はい……そんなことしたって、大した気遣いにもならないのに」
「よく分かってるおね」
「まあ、はい……だからわたしだけはまわりくどいことはなしにしようと思いました」
デレちゃんは小瓶をそっと、僕の目の前に差し出す。
ところどころ小さな固まりの混じった中身は粉っぽく、石灰を思わせる。
「内藤君……食べてください。できるなら、わたしの目の前で」
まっすぐに言い放ったデレちゃんの瞳は、力強く僕を捉えて離さない。
似てないと言われていた姉妹だけど、そんなことはないと僕はずっと思っていた。
例えば、真剣なときの表情はツンもデレちゃんもそっくりだ。
「……食べてあげてください。お姉ちゃんを」
眼前に置かれた小瓶に視線を落とした。
デレちゃんとそっくりな表情で、ツンの遺灰が僕を見つめている気がした。
-
君は僕とひとつになりたいようです
-
僕とツンは家族ぐるみの付き合いがある幼馴染で、そして恋人同士だった。
特に昔から大きな病気もせず、健康に暮らしてきたツンが突然体調を崩したのは、去年のことだった。
悪性の腫瘍がツンの体を蝕んでいるのだと、彼女の家族から伝えられた。
そして、それをツン本人には知らせていないことも教えられた。
ステージはどの段階なのか、手術はするのか。
勉強して身に着けた知識を、僕は次々に彼女の家族にぶつけてみた。
だけど、色よい返事は戻ってこなくて、それがツンの病状の重さを嫌でも僕に悟らせた。
僕は少しでもツンの生きる力になりたくて、毎日病院に通い詰めた。
その日あった些細なことひとつでも話した。世界から彼女を切り離させないために。
だけど、僕はそのうちそんな生活に嫌気がさすようになった。
とうとうツンは何か察したらしく、見舞いに来た家族や僕につらく当たるようになった。
元々男勝りでがさつなところはあったけど、無意味に周囲に当たり散らすような子じゃなかったはずなのに。
ツンがどんどん変わっていってしまう。日に日に病状が悪化していくのが分かってしまう。
それでも何でもないように笑顔を張り付けて彼女の前に立たなければならない。
いつしか僕は見舞いに行くたびに泣いて帰るようになっていた。
僕の足はツンのいる病院から遠ざかろうとしていた。
もういっそ、お互いに綺麗な思い出のままで終わった方が幸せな気すらしていた。
そんな考えが頭を埋め始めたころ、デレちゃんから連絡があった。
ツンが、ふたりきりで話したいことがある、と。
-
「ねえ、ブーン。あたし、死ぬよね」
約束の日、約束の時間。
ふたりきりの病室に入って開口一番、ツンは僕にそう尋ねてきた。
「……」
「もう、平気な風に取り繕わなくていいよ。正直に答えて。覚悟はできてる」
「……たぶん、そうだと思う。おじさんたちもツンの病状のこと、あまり話そうとしてくれないし」
「……そっか」
ふう、とため息をついて、ツンは窓の外へと顔を向けた。
そこにはかろうじて枝に繋がった葉なんてない。
冬になってすっかり枝だけになってしまった木だけがそびえ立っていた。
「……あたし、まだ生きたいんだけど」
「……」
「ちっちゃいころ、あんたのお嫁さんになるって約束もしたのに、叶わないままとか……」
-
「ごめん……ツン」
「……なんであんたが謝るし泣くのよ」
「……ごめん」
「もう……」
残していく方と残される方。いったいどちらが辛いのだろう。
そんな仮定は無意味だ。どっちも同じくらい辛いに決まっている。
それなのに、僕ばかりが泣いて情けない限りだった。
「……ブーン。ちょっとやってほしいことがあるんだけど」
まだ泣き崩れて顔を上げられない僕に、ツンが優しい声で語りかける。
僕にできることならなんでも、と滲んだままの視界のまま、顔を上げた。
「……抱きしめて」
そう言ってツンは、桃色のパジャマのボタンをひとつひとつ外していく。
やがて、何回かだけ見た一糸まとわぬ上半身が露わになる。
かつての姿は見る影もなく、やせ細ったそのシルエットに、また視界が滲む。
-
「ブーンも上脱いで。そしたら抱きしめて」
言われるがままに上の服を脱いで、傍らに放り投げる。しわになるかなんて気にしなかった。
そして、ベッドに腰かけると、両手を広げて待ち構えていたツンの体をそっと抱きしめた。
「……」
「……」
無言の時間が過ぎゆく。その中で僕はいろんなことを考えていた。
ツンの体から女の子特有の柔らかさが消え失せてしまったこと、代わりに現れた骨の感触のこと。
骸骨のようになってしまっても、それでもまだ胸は息を吸うたびに膨らんではしぼむこと。
僕の体温よりは冷たいけど、その体には確かに温もりがあること。
僕とは違うテンポで、彼女の心臓は確かに鼓動を刻んでいること。
僕の胸の中で、ツンという人間は確かに生きているということ。
「……ブーン、あったかい」
「ツン……体が冷えるからそろそろ」
「あんたがこうしてくれてればあったかいから、大丈夫」
-
ツンがそんなことを言うものだから、僕はお言葉に甘えてもう少し彼女を抱きしめていようと思った。
「ブーン」
「何だお?」
「あたし、生きたい……生きたいけど、無理なんだよね」
耳元で聞こえるツンの声は、濡れていた。
「……」
「でも、せめて、ブーンと一緒にいたいよ……ずっと……ずっと……」
「……僕もだお」
「……だから、ひとつだけお願い、聞いてくれる?」
「……うん」
「――」
-
「あたしの遺灰を食べて」
デレちゃんはあの日の約束をなぞるように、呟いた。
ツンとデレちゃんがやっぱり似ていないことを、僕は心から神様に感謝した。
「お姉ちゃんとふたりきりで会ったあの日、そう言われて、内藤君は約束しましたよね」
「……うん」
「お姉ちゃんの遺言書にも、内藤君に遺灰の一部を食べてもらうよう書かれていました」
「うん……」
「さあ……食べてみてください。舐めるでも、水で飲みこむでも、何かにかけるでも……なんでもいいです」
僕は小瓶を手に取って、まじまじと眺めてみる。
遺灰がどんな味がするかなんて分からないけど、食べるなら簡単だ。
栓をしているコルクを抜いて、指先に遺灰をつけて舐めとれば、それで終わりだ。
それだけのことで、ツンも、彼女の家族も、みんな救われる。
愛する人へ託した最後の望みが叶う。
-
だけど。
「……ごめん。僕は、食べない。食べられない」
「……どうしてですか?」
デレちゃんが机の上に置いていた拳をぎゅっと握りしめた。
小刻みに震えるほどに力が込められているのが見て取れる。
「お姉ちゃんと約束したんじゃないんですか」
「確かに僕はあの日、ツンと約束した。君を食べるって」
「だったら!」
「嘘をついた。僕は初めから、約束を守るつもりなんて、なかった」
デレちゃんは目を丸くしたそのあとで、眉間にきゅっとしわを寄せた。
その眼差しに込められているのは、怒り。
大好きな姉との約束を破り、故人の想いをないがしろにした、僕への怒りだ。
-
「少しだけでいいから、僕の話に耳を傾けてほしい」
「……わかりました」
デレちゃんは拳をほどいて、膝の上に置いた。
大きく深呼吸しているのは、いったん冷静になるためだろう。
「……どうしてですか? 約束を破ろうなんて、どうして……」
「……あの日、僕はツンを抱きしめた。ふたりとも裸になって、抱きしめ合った」
「なっ……!」
「上半身だけだお。そこら辺はきちんとわきまえてるから、安心してほしいお」
「はあ……」
少し顔を赤くしたデレちゃんは、額に張り付いた髪の毛を整えながら相づちを打つ。
わきまえているのか、と言われたらいまになって思うと自信がないけど、納得はしてくれたようだ。
-
「僕は、ツンとひとつになんてなりたくなかった」
「それはどうして、ですか?」
「……ひとつになる、っていうのはどういうことだと思う?」
「……ずっと一緒にいられる。そういうことだって、お姉ちゃんの遺書に書かれてました」
「……その前提自体が間違っているんだお」
「どういうことですか?」
「ひとつになるっていうことは、僕の中にツンが溶けて消える。そういうことだお」
「……」
「一緒にいるっていうのは、ふたりじゃなきゃできないことなんだお」
「ツンを抱きしめたときに、僕はそれに気付いたお。僕たちはどれだけ近づいてみても他人なんだ、って」
-
「他人だから僕はツンを愛せた。僕と隔てられた他人だからこそ、自分を嫌いになりそうなときでもツンを愛していられた」
「……永遠でなくても僕の傍らにツンがいてほしい。そう思えることこそ、僕からのツンへの愛情なんだお」
「だから、僕はツンに自分の遺灰を食べてほしいって言われたとき、断ろうかと思ったお」
「でも、僕とひとつになりたいと思えることがツンから僕への愛情なんだとしたら、それを断るのは違うと思った」
「……それで、嘘をついた?」
「そうだお。例えツンを裏切ることになったとしても、僕はあのときツンの想いを否定するのは違うと思ったんだお」
「……傲慢ですね。それを聞いてわたしがどんな気持ちかわかりますか?」
「分からないお。どれくらい怒っているのかなんて」
「でも、これは僕とツンの問題だお。例え家族とはいえ、そこに入り込む余地なんて与えさせないお」
「ツンはひとつになりたかった。僕はそれを約束した。僕はふたつでありたかった。だから約束を守らなかった」
「ツンはもういない。世界のどこにも。だから、僕が裏切ったなんて知る由もない」
「ツンは僕が約束を守ると信じて逝ったし、僕は約束を破ることで自分の意志を貫いた」
「僕たちふたりはお互いの願いを守り抜いた。それでこの話はおしまいだお」
-
僕はそう言って話を締めくくると、そっと小瓶に手を伸ばす。
小瓶の行く先はデレちゃんの眼前。彼女はその一連の動きをただ目で追うだけだった。
「だから、僕はこれを食べない。だから、僕はこれを受け取れない」
「……そう、ですか」
「いま言ったこと、全部ご両親に話してくれて構わないお。そのうえで、これをお返しするお」
デレちゃんは小瓶を手に取り、雨に濡れた子犬でも見るような目でそれを見つめた。
彼女はいま何を思っているのだろう。僕への怒りか。ツンへの憐れみか。
「……内藤君の考えは、よくわかりました」
「それはよかったお。それじゃあ、ご両親によろしくお伝えくださいお」
「ええ、でも……その前に」
「え?」
-
デレちゃんは手に持った小瓶をもう一度、僕の目の前に置いてみせた。
受け取らないという意思表示はしたはずだ。それなのにどうして。
「食べなくてもいいです。でも、これは受け取ってください。両親には、わたしが適当に話をつけておきます」
「いや、受け取れないお。食べないならちゃんと遺骨と一緒に」
「内藤君、お姉ちゃんとふたつでありたいって言いましたよね?」
「確かに、言ったけど……」
「これは紛れもなくお姉ちゃんです。そして、この瓶のふたを開けなければ、お姉ちゃんはどこにも行きません」
「何があったって、この瓶が内藤君とお姉ちゃんを隔てます。ふたりはずっと、ふたりのままです」
「それって、内藤君がお姉ちゃんと一緒にありたいと願った形じゃないですか?」
「……そんなの、屁理屈だお」
「ええ、屁理屈です。でも、内藤君の言い分だってそうです。だから、わたしも屁理屈を貫かせてもらいます」
「……」
-
「食べない代わりといってはなんですけど、この遺灰は内藤君がずっと持っていてください」
「なにがあってもなくさないで、これを見るたびにお姉ちゃんのことをいつも思い出してください」
「内藤さんはお姉ちゃんとひとつにならなくてもいい」
「お姉ちゃんは内藤君の記憶の中で生き続けられる。内藤君とひとつになれる」
「どうですか? これもお互いの願いを守ったことになりませんか?」
「……まいったな」
そんな困ったようなことを言いつつも、僕は笑っていた。
笑いながら、泣いていた。
「……じゃあ」
「……受け取るお。ご両親には説明よろしくお願いしますお」
「……はい!」
-
結局、遺灰を受け取ることとhなり、デレちゃんは満足げに家路についた。
ひとり家に残されて、僕はもう一度ツンの遺灰と向き合うことになる。
彼女は相変わらず何も語らない。金色の紙も、青い瞳も、すべて鈍い白の中に溶けてしまった。
「……ツン」
「……僕たち、ずっとじゃないけど」
「……一緒にはいられないけど」
「これからも、そばにいられるよ」
机の上に置かれた遺灰を、そっと手に持った。
そして、あまりに軽くなってしまった彼女を封じ込めた小瓶に、僕はそっと口づけた。
【了】
-
( "ゞ)「……」
( "ゞ)←ところどころ直したいところが見つかった顔
-
>>187
( ^ω^)「うわぁ……(ドン引き)」
( ^ω^)
( ^ω^)
( ^ω^)「うわぁ……(超ドン引き)」
(;^ω^)「クオリティ高いのがまた……」
(;^ω^)
(;^ω^)「うわぁ……(超サイヤドン引き)」
(;^ω^)「乙だお!」
-
>>208
( ^ω^)「おつだお!」
(;^ω^)「デルタはテーマの取り込み方が滅茶苦茶綺麗で凄いお……」
-
(-@∀@) 「いろんなたべものがあるんだなあ」
(-@∀@) 「投下だよ」
-
( ゚∋゚) 「来たか・・・」
(,,゚Д゚) 「急にどうしたんすかゴラァ」
_
( ゚∀゚) 「サークルについての話があるって言うから来たけど」
( ゚∋゚) 「今日、『アセとナミダ・・・そして男のための筋肉サークル』の皆に集まってもらったのは他でもない」
( ゚∋゚) 「日々男と筋肉について研究している我らが協議しなければならないことができた」
(゚Д゚;,) 「ジョルジュ先輩、ここってただの筋トレサークルじゃないんすか?」
_
( ゚∀゚) 「あー、ギコは今年から入ったから知らないのか」
_
( ゚∀゚) 「これはこいつの発作みたいなもんだからほとんど無視していいぞ」
( ゚∋゚) 「こら、静かにしろ。今からお前たちに世紀の大発見を発表するんだぞ」
_
( ゚∀゚) 「まあまあ、本題に入ろうぜ」
( ゚∋゚) 「うむ、いいだろう」
-
。。 。。. 。。 。。. 。。
゚●゜ 。。 ゚●゜ 。。. ゚●゜ 。。 ゚●゜ 。。. ゚●゜ 。。
゚●゜ .゚●゜ ゚●゜ .゚●゜ ゚●゜
( ゚∋゚)の男の料理〜チーズケーキ編〜
。。 。。. 。。 。。. 。。
゚●゜ 。。 ゚●゜ 。。. ゚●゜ 。。 ゚●゜ 。。. ゚●゜ 。。
゚●゜ .゚●゜ ゚●゜ .゚●゜ ゚●゜
-
( ゚∋゚) 「・・・というわけだ」
_
( ;゚∀゚) 「いやどうゆうわけだよ」
( ゚∋゚) 「どうと言われてもなあ」
( ゚∋゚) 「アイキャッチにあるとおりだぞ」
( ゚∋゚) 「さすがのジョルジュも驚きが隠せないか・・・」
_
( ;゚∀゚) 「いやいやいや」
_
( ゚∀゚) 「( ゚∋゚)の男の料理〜チーズケーキ編〜」
_
( ;゚∀゚) 「さすがにこれだけじゃぁ何一つわからんぜ」
( ゚∋゚) 「男は多く語らないからな」
_
( ;゚∀゚) 「それにしたって限度があるだろ!」
_
( ;゚∀゚) 「これだけのために大学の大会議場を貸し切りにしたのかよ」
(,,゚Д゚) 「というか、よく3人しかいないサークルに貸してくれましたね・・・」
-
( -∋-) ハァ
( ゚∋゚) 「どうやら俺もお前も男としてまだ未熟だったようだな」
( ゚∋゚) 「仕方ないから語ってやろう」
(゚Д゚,,) 「なんで俺たちまで悪いことになってんすか」
_
( ゚∀゚) 「知らん」
( ゚∋゚) 「いいか?落ち着いて聞いてほしい」
( ゚∋゚) 「俺が今から言うことはまだ完全に決まったわけじゃない」
( ゚∋゚) 「それをみんなに決めてほしいんだ」
_
( ゚∀゚) 「うるせえなあ、とっとといいやがれ」
( ゚∋゚) 「それもそうだ、男らしくスパッといこう」
( ゚∋゚) 「俺は・・・」
( ゚∋゚) 「チーズケーキは男の料理だと思うんだ」
-
_
( ゚∀゚) (,,゚Д゚) (゚∈゚ )
_
( ゚∀゚) (,,゚Д゚) (゚∈゚ )
_
( ゚∀゚) (゚Д゚,,) (゚∈゚ )
_
( ゚∀゚)σ (゚Д゚;,) (゚∈゚ )
(,;゚Д゚) 「ええっと、一体どういうことですか?」
(;゚∋゚) 「なんと、まだ伝わらないだと」
(,;゚Д゚) 「ええ、まあ、はい」
( ゚∋゚) 「まさかここまで男が拒絶する話だったなんて・・・」
(゚Д゚,,) 「そういう問題なんすか?」
_
( ゚∀゚) 「こいつの筋肉しか入ってない頭の中ではそうなんだろうな」
_
( ゚∀゚) 「ほっとくのも面倒だしどうしてそう思ったか始めから話してくれよ」
-
( ゚∋゚) 「始めからとなるとギコもいるしあの事件から話さないといけないな」
(,,゚Д゚) 「あの事件?」
( ゚∋゚) 「ああ、あの悪名高い『チーズフォンデュ中毒事件』のことだ」
_
( ;゚∀゚) 「あれかあ」
(゚Д゚,,) 「あれ?ジョルジュ先輩知ってるんですか」
_
( ;゚∀゚) 「まあな」
_
( ゚∀゚) 「確か去年の夏のことだっけ?」
( ゚∋゚) 「確かそのくらいだったか」
( ゚∋゚) 「昼頃にジョルジュから電話が来たのが事の始まりだ」
( ゚∋゚) 「電話に出てみると『チーズフォンデュくおうぜ』」
( ゚∋゚) 「そう言なり聞き返す暇もなく電話が切れてしまった」
-
( ゚∋゚) 「その後5分も立たずにジョルジュはやってきた」
( ゚∋゚) 「手にはでかいビニール袋を下げていたな」
(゚Д゚,,) 「ずいぶん急じゃないっすか?」
_
( ゚∀゚) 「そりゃあクックルの家に向かう途中に電話したからな」
( ゚∋゚) 「そうだったのか・・・道理でやってくるまでが早かったわけだ」
( ゚∋゚) 「袋の中を見てみると鶏肉やら野菜やらが入っていた」
( ゚∋゚) 「それと大量のチーズ」
(,,゚Д゚) 「ジョルジュ先輩やる気満々じゃないっすか」
_
( ゚∀゚) 「一生に一度あるかないかくらいだからな」
_
( ゚∀゚) 「全力でやらなきゃ損だぜ」
( ゚∋゚) 「そういうわけで料理をつくることになったんだ」
-
( ゚∋゚) 「しかし、いざ料理を始めようとしたら問題が出てきた」
(,,゚Д゚) 「問題?」
( ゚∋゚) 「ああ、俺もジョルジュもチーズフォンデュがどんなもんか知らなかったんだ」
(,,゚Д゚)
._
(゚∀゚ )
(゚Д゚,,) 「全力はどこ行ったんすか」
._
(゚∀゚ ) 「時間が・・・足りなかったんだよ・・・」
( ゚∋゚) 「その男らしい行動力。俺は好きだぞ」
_
( ;゚∀゚) 「このバカやろう何おぞましいこと言ってんだよ」
(,,゚Д゚) 「┌(┌^o^)┐ホモォ...」
-
/_⌒ヽ ノノノノ
( ゚∀゚.) (゚∈゚_) <その後チーズフォンデュのことを
/´ ⌒ヽ、ユッサユッサ /⌒ ) チーズで煮込む料理と勘違いした俺たちは
ユッサユッサ 〈 イ i |_∧ .ミイ // 鍋のなかの煮え立ったチーズに
⊂二\ \ _.| | ゚Д)<がああああ | (( 生肉を放り込む暴挙に出た。
/⌒⊂二二// ̄ ) .| ))
| ノー-|ヽ(i_,.ノ ̄ ,ノ | //
| / | トー'´⌒ヽ、__/^i .| ノノ
ノ ) ヽ 人 ヽ_.__..__/ .|ノノ
(__,./ `ヽ___,.ノ´ (____`) .彡ヾ
( ゚∋゚) 「見た目はさながら地獄の釜の中のようだったよ」
( ゚∋゚) 「しかし、据え膳食わぬは男の恥」
( ゚∋゚) 「そこに料理が・・・しかも自分が作ったものとなると食わねばならぬ」
_
( ゚∀゚) 「貧乏性とも言うな」
( ゚∋゚) 「ほぼ生の鶏肉を食った俺達は腹痛を起こし救急車のお世話になった」
_
( ゚∀゚) 「チーズって意外と火を通さねえんだよ」
/_⌒ヽ ノノノノ
( ゚∀゚.) (゚∈゚_) < さすがの俺もあの時は
/´ ⌒ヽ、ユッサユッサ /⌒ ) ダメかと思ったね
ユッサユッサ 〈 イ i |_∧ .ミイ //
⊂二\ \ _.| | ゚Д)<謝る、謝るから | ((
/⌒⊂二二// ̄ ) 許してください | ))
| ノー-|ヽ(i_,.ノ ̄ ,ノ | //
| / | トー'´⌒ヽ、__/^i .| ノノ
ノ ) ヽ 人 ヽ_.__..__/ .|ノノ
(__,./ `ヽ___,.ノ´ (____`) .彡ヾ
-
_
( ゚∀゚) 「全く、あん時はひどい目にあったぜ」
(,,゚Д゚) 「いやあ、俺もひどい目に会いましたよ」
_
( ゚∀゚) 「お前は自業自得ってやつだ。反省しろい」
(,,゚Д゚) 「了解でございます」
( ゚∋゚) 「全く。後輩に当たらず俺に全てをぶつければいいのに」
_
( ゚∀゚) 「何を言いやがる。気持ち悪い」
(,,゚Д゚) 「クックル先輩に勝てないのに勝負を挑むわけないっすよ」
_
( ゚∀゚) 「なんだあ、また関節技喰らいたいか?」
(,,゚Д゚) 「ひえっ、勘弁して下さいよ」
(,,゚Д゚) 「あ、ああそうだ。そんで、話はお終いですか?」
( ゚∋゚) 「何だ、本題を忘れたのか」
( ゚∋゚) 「しょうがないやつだ。思い出させてやろう」
-
ノノノノ
くらえ必殺レス番指定キック!!> (゚∈゚ )
(ミ_(⌒\ヽ
>>213(≡ ̄ ̄三\⌒ノ ノ )
 ̄ ̄ ̄\ 彡) ノ―
_ \_ノノ ―
/ _ ヽ ..∧_∧ / / ≡=
( ゚∀゚).. .( ,,゚Д゚) / ノ
( ∪ ∪. (∪ ∪ /ノ_―(⌒
と__)__) と__)__) .ミ/= ( (⌒
-
(,,゚Д゚) 「あー、そういやチーズケーキの話でしたね」
_
( ゚∀゚) 「俺もすっかり忘れていたぜ」
( ゚∋゚) 「やれやれ、忘れてしまうとは情けない」
_
( ゚∀゚) 「アイキャッチから9スレもかかってるからな」
(,,゚Д゚) 「忘れても仕方ないっすよ」
( -∋-) 「全く、お前らというやつは・・・」
(,,゚Д゚) 「ともかく、やっと本題に入るわけですね」
( ゚∋゚) 「そうだな、やっと話せる」
( ゚∋゚) 「例の事件の翌日、ジョルジュより早く退院した俺はあることに困っていた」
(,,゚Д゚) 「また問題ですか」
( ゚∋゚) 「そう、有り余るチーズをどう処理しようかという問題だ」
-
(゚Д゚,,) 「そんな大量に買ったんすか」
_
( ゚∀゚) 「500gのピザチーズを7袋くらい買ったんじゃねえかな?」
( ゚∋゚) 「チーズフォンデュに使ったのはそのうち2袋だけだな」
(,,゚Д゚) 「そりゃ困ってしまいますね」
( ゚∋゚) 「だから俺はチーズを大量に使う料理を探した」
( ゚∋゚) 「そこで出会ったのがチーズケーキだったのだ」
_
( ;゚∀゚) 「やっとチーズケーキの話だぜ」
(゚Д゚,,) 「長かったっすね」
_
( ゚∀゚) 「じゃ、チーズケーキの話もしたことだし俺達はこれで」
(,,゚Д゚) 「おつかれさまでした〜」
-
.../⌒ノノノノ⌒ヽ
(ミ (゚∈゚ ) ミ) <まあ待て
.(ギコ )\/(ジョル) お前たち
∨∨ ∨∨
.ノ /
.( \/ヽ
.\ ) )
.///
.`ヾ ヽミ
-
( ゚∋゚) 「大切な話はこれからだ」
_
( ゚∀゚) 「ちくしょう」
(,,゚Д゚) 「諦めましょう」
( ゚∋゚) 「ところでお前ら。チーズケーキを作ったことはあるか?」
_
( ゚∀゚) 「あるわけねぇよ」
(,,゚Д゚) 「お菓子って面倒くさそうですしね」
( ゚∋゚) 「そう思うだろう。俺もそう思っていた」
( ゚∋゚) 「しかし、事実は違っていた」
(,,゚Д゚) 「へー」
_
( ゚∀゚) 「ほーん」
-
( ゚∋゚) 「チーズケーキの作り方は簡単だ」
( ゚∋゚) 「必要なものはチーズ、砂糖、小麦粉、卵、牛乳」
( ゚∋゚) 「まず、牛乳を温めてチーズを溶かす」
( ゚∋゚) 「このときチーズを刻んでおいたら溶かしやすいぞ」
( ゚∋゚) 「そのまま他の材料をぶっこんでかき混ぜる」
( ゚∋゚) 「砂糖と小麦粉はレンゲ3分の1くらいがちょうどよかったと思う」
( ゚∋゚) 「だいたい混ざったら耐熱容器に入れてオーブントースターに入れる」
( ゚∋゚) 「あとはいい感じになったら完成だ」
( ゚∋゚) 「どうだ、簡単だろう」
_
( ゚∀゚) 「いい感じってなんだよ」
( ゚∋゚) 「そこは男のさじ加減だ」
(,,゚Д゚) 「大さじとかじゃなくてレンゲってのが先輩らしいっすね」
-
( ゚∋゚) 「お前たちこれを聞いた上でチーズケーキをどう思う?」
(,;゚Д゚) 「ええと、意外と簡単っすね」
( ゚∋゚) 「そう、その通り」
( ゚∋゚) 「これだけ適当に作れるのだ」
( ゚∋゚) 「男の料理と言っても良いのではないか」
( ゚∋゚) 「しかしスウィーツを男の料理と呼ぶのは少し抵抗がある」
( ゚∋゚) 「これが本当ならばまさにコペルニクス的展開だ」
( ゚∋゚) 「俺は何が正しいかわからなくなってしまったのだ」
( ゚∋゚) 「そこで同じ男であるお前たちに意見を聞きに来たんだ」
(,,゚Д゚) 「で、この質問に戻って来るんすか」
_
( ゚∀゚) 「やっと初めの話なのか」
-
( ゚∋゚) 「で、どうなんだ」
(゚Д゚,,) 「ジョルジュ先輩どうします?」
_
( ゚∀゚) 「死ぬほどどうでもいいな」
_
( ゚∀゚) 「別に男の料理でも良いんじゃないか」
(,,゚Д゚) 「ということらしいですよ」
( *゚∋゚) 「そうか。やはりそうか」
( *゚∋゚) 「また新しい男の発見がまた一つ・・・」
( -∋-) 「俺もまだまだだな」
( ゚∋゚) 「よし!お前ら、今月は『男の料理強化月間』とする!!」
( ゚∋゚) 「料理を作る中で男を見つけるのが活動内容だ」
( ゚∋゚) 「新しい男のあり方をともに見つけようではないか」
(゚Д゚,,) 「ここって筋トレサークルっすよね?」
_
( ゚∀゚) 「もう知らん!!」
( ゚∋゚)の男の料理〜チーズケーキ編〜【了】
-
(-@∀@) 「投下終了だよ」
(-@∀@) 「ぜひ作ってみてね『男チーズケーキ』」
-
(´・_ゝ・`)「なんておいしそうなんだ……」
(´・_ゝ・`)「今度作るとしよう」
(´・_ゝ・`)「僕も男飯に続こうかな」
-
ピアス
蛇に耳环と藪から棒に、のようです
.
-
麻婆豆腐が、食べたかった。
香辛料とにんにくの効いた餡と、豚のひき肉が
よく絡んだ木綿の豆腐を、熱々のうちにかっ込んでしまいたい。
しかしわざわざパウチを買って、料理をする気力などない。
かといって、スーパーやコンビニの惣菜も嫌だ。
一度か二度食べてはみたものの、あんなの
麻婆豆腐とは言えない、ただの辛いあんかけ豆腐だ。
ひき肉の旨味や脂によって引き立つ豆板醤の辛さで、額に汗をかきたい。
だから俺は、中華街へと向かった。
地下鉄特有の長ったらしい清潔な
下水のような道を行き、歩くこと五分。
南口へと通じる階段を登れば、
もうすぐそこには真っ赤な門が待ち構えている。
華やかな提灯の下、練り歩く観光客を、
俺は幽霊のように間をすり抜ける。
途中、栗だの肉まんだのの客引きに
声を掛けられるが、まったくもって無視を決める。
ほとんどの飯店では、輸入物の冷凍食品を扱っていて、
どこで食べてもおんなじような味しかしないのだ。
(´<_` )(もうこの街には、本物の料理人なんて一握りしかいない)
ふやけた小麦の甘さと湿気た竹の臭いが、憎悪を掻き立てる。
偽物の中華の臭いは、酷く耐え難い苦痛をもたらす
ので、俺は逃げるように細い路地へと飛び込んだ。
表の喧騒とは違い、こちらは本国に近くなる。
易占、漢方、按摩、鍼灸、輸入食品店。
埃と誇りの混じった胡乱な臭いと、それに染まった店番の男たち。
どいつもこいつも喧嘩っ早くて、荒々しく、
つっけんどんだが、おかげで邪魔な観光客は寄りつかなくなった。
-
( ・∀・)「やあ、兄山の」
見知らぬ男が、懐っこく手を挙げる。
前掛けの屋号からして、おそらく酒屋なのだろう。
だが、俺は酒を飲まない。
( ・∀・)「あれ?」
近付いてきた男は、ようやく違和感に気付いたらしい。
( ・∀・)「兄山じゃない?」
(´<_` )「赤の他人だぜ、俺は」
男の視線は、俺の右耳へと注がれていた。
俺は耳环を開けていて、若竹色の、安い翡翠をぶら下げている。
対して兄山は、装身具の類を一切付けない。
しかしそれを抜きにすれば、俺たちはよく似ていた。
( ・∀・)「そうだよねぇ、そうだ、そうだ」
納得した男は、大人しく引き下がる。
こうして間違われることはしょっちゅうで、
しかしいつまで経っても慣れることはない。
思わず苦笑しながらも、さらに路地の裏へ足を進める。
店の裏側に位置するここは、人気がなく、
代わりに生ゴミが山脈のように連なっており、
壊れた雨樋からは、ぼたぼたと水が溢れ出している。
おそらく二階以上の店では、
店仕舞いの清掃が行われているのだろう。
足早にそこを通り抜け、またまた細い道へと身をよじる。
するとようやく、看板のない飯店に出くわした。
傾きかけているビルの一階をぶち抜いた
その店は、さながら遺構のようである。
はたして俺の他に誰がいるのだろう。
いつもそう思うのだが、奇特な店には奇特な客が集まるものだ。
-
(´<_` )「麻婆豆腐炒飯」
戸を引きながら叫ぶと、たったの四席しかないカウンターの奥から、
( ´_ゝ`)「よぉ、弟者」
明るい声が掛かり、その手前には、
/ ,' 3「……」
荒巻老人が、ラーメンを食べている。
さらにその隣では、テレビを
見ていたらしい娘が、席を立つところだった。
ノパ ー゚ノゞ「……」
カウンターを占領していたガラクタ――安いライターや
古い雑誌、菓子の空き箱などを、娘が移動させた。
ぽっかりと空いたカウンターの上は、油か何かで
艶めいており、極力触らないことを心がけて、俺は席についた。
(´<_` )(壊れてやがる)
柱状の席は、ガタつきが酷く、
おそらくつなぎ目が馬鹿になっているのだろう。
少しでもバランスを崩せば、ひっくり返るに違いない。
狭い店内には壁にもみっちりと物が積まれていたりするので、
そこに頭をぶつけた日には、解脱すること間違いなしだった。
( ´_ゝ`)「久しぶりだな」
苦心しながらケツに力を入れている俺に、兄者――兄原、兄山、兄野、
兄木、兄藤、兄水、兄口……、偽名は様々だった――が話しかけて来る。
彼は、例の他人である。
この店の常連にしては珍しく饒舌で、人懐っこく、
俺のことを弟と呼び、妙に気にかけてくれるお人好しだが、
やはり彼も異常に満ちている。
( ´_ゝ`)「食うか?」
オーダーメイドのスーツを着こなす伊達男の前には、一斗缶が
一つ聳え立っており、その中には愛玉子がたゆたっているのが常だった。
嘘か真か、俺にはまったく判断がつかないが、
週に一度、兄者はこれを食べないといけないらしい。
-
( ´_ゝ`)「要らないか」
返事のない俺に、兄者は苦笑して、
業務用のレードルを手に取り、一合はよそえるそれで、
音を立てながら甘酸っぱい檸檬のシロップを口にする。
隣では、張り合うように荒巻老人がラーメンを啜っていた。
爺さんは、普通のホームレスで、中華街と公園を練り歩き、
アルミ缶を拾っちゃ売り拾っちゃ売りを繰り返している。
そうして稼いだ日銭のうち、百円を払い、ラーメンを食べている。
具材はいたってシンプルだ。
玉ねぎの皮に人参のヘタ、キャベツや白菜の芯に、腐りかけの焼豚やら、
麺の切れ端――店主曰く、ここは製麺所らしい――が、荒巻老人の生活を支えている。
歯が二本しかない老人は、くっちゃら、
くっちゃら、と、だらしなく、下品にメシを食っている。
それでも歯磨きの代わりになるから、
屑は体にいいと、店主はホラを吹いていた。
( `ハ´)「お待ちどぉ」
噂と感慨にふける俺の前に、噂の店主がやって来た。
カウンターを占領する丼の中には、真っ赤な豆腐に、
ごろごろと入ったネギと粗みじんのにんにく、
ニラの青さが引き立つ刺激的な臭いが立ち込めている。
(´<_` )(これだよ、これ)
ヒビの入った蓮華をひっ掴み、盛られた山を切り崩せば、
卵と蒲鉾の紅白が目立つ炒飯が、赤に塗りたくられていく。
ないまぜになった土砂を、口の中へと
放り込めば、待ちわびた舌が旨味を享受する。
ほかほかの餡が絡まった炒飯は、噛まずともするんと飲み込める。
俺は、噛みごたえのある食い物が大嫌いだった。
ここの麻婆豆腐は、木綿のくせに柔らかくって、
だけども絹のようにぼろぼろと崩れることはない。
口どけなめらかに豆の味がして、
後からじゅわっと辛さとにんにくの風味がガツンと鼻に抜け、
鶏ガラと胡椒の効いた炒飯が混ざって、えも言われぬ幸せを、
脳の髄から、背骨の端まで、性行のように、味わうことが出来るのだ。
-
(´<_` )(最高だ)
がっつく俺に、兄者は目を細めて眺めている。
( ´_ゝ`)「よかったなぁ、弟者」
一方的に送られてくる慈愛に、俺はようやく頷いた。
兄者との付き合いは、ここ以外では何もない。
彼が何をしているのか、俺は知らないし、逆に彼も、
俺がどんな仕事をしているのか、興味すら持っていないだろう。
一見裕福に見える彼の高尚な苦悩だって、
凡人の俺にはとうてい理解できない類だろう。
けれどもその空白が、俺は愛おしい。
深く知ってしまえば、喪失感はいっそう強くなる。
そうして痛い目を見たことが、今までに何度あったことだろう。
(´<_` )(ああ、辛い)
上乗せされていく唐辛子の辛さに、身体中が火照り出す。
舌はビリビリと痺れ、花椒特有の
酸味が効いた熱っぽさに唸りながら、
黒いスウェットの袖を引き延ばした。
額に浮き出た汗は、そこはかとなく
にんにくの臭いがにじみ出ているようだった。
/ ,' 3「あんまり辛いと、ケツいわすだろう?」
珍しく呟いた老人に、これまた珍しく、俺も頷いた。
あまりの辛さに、無関心さを装う暇がなかったのだ。
/ ,' 3「朝鮮の刑務所で飯食ってた頃を思い出すよ」
(´<_` )「へぇ」
/ ,' 3「捕まったわけじゃないよ」
びろんびろんに伸びた麺をつまみながら、老人は語る。
-
/ ,' 3「戦後人手が足りなくって、頼まれてさ。
仕方ないから看守として残ったってだけよ」
(´<_` )「へぇ」
話半分、冗談五割、まじめに
受け取るほど、俺はバカじゃない。
それになんたって、麻婆豆腐が一番だ。
蓮華を舌の代わりに皿を舐め回し、
一滴も餡が残らないように、腐心する。
その背後から、乱雑に戸が開く音。
「兄原だな?」
真後ろから掛けられた言葉は、
カウンターの奥へと向けられたものに違いない。
実際そうに違いなかっただろうに、
豆腐の滓をすくい取る俺の肩に、手が食い込んだ。
_
( ゚∀゚) 「テメェがそうだろう?」
(´<_` )「え?」
チラと視線を送れば、当の兄者は背を向けており、
荒巻老人はラーメンをすすり、
鍋を振る音が響く厨房へと、看板娘の背中が吸い込まれていく。
つまり誰も俺の無実を証明する輩はいないので、呆けているヒマはなかった。
-
_,
( Д ) ,"・,。「ゴパッ――」
秒速三一五メートル。
九×一八ミリのマカロフ弾が、喉から脳天へと直撃。
マカロフPMの有効射程距離は五十メートルで、
ゼロ距離で射殺したというのに、奴の頭蓋は丈夫だったらしい。
脳みそを豆腐のように散らすこともなく、ただ首からゴボゴボと、
豪雨のように血が降り注ぎ、黒いスウェットへと染み付いた。
どふ、
と音を立てて、男は床へ転がり、
それを見届けて、銃を懐へとしまった。
( ´_ゝ`)「悪いね、弟者」
/ ,' 3「南無三」
ニヤニヤとニタニタの中間のような笑みを
浮かべる兄者の横で、老人は十字を切った。
なんだか仲間外れにされたような心地になり、俺は嫌悪を露骨にした。
ノパ ー゚ノゞ「――」
カウンターから、無口な女が飛び出した。
ほとぼりが冷めた頃にやって来るのは、いつものお決まりだった。
四肢をビクつかせる男の首を掴み、
彼女は厨房の奥へと消えていく。
(´<_` )「帰る」
会計を済ませようとするも、満腹なはずの胃の腑は、
ギチギチと締め付けられるように痛んだ。
不意にやってくる仕事っていうのは、いつだって不愉快なものである。
-
( ´_ゝ`)「マスター、紹興酒と、彼に麻婆豆腐炒飯を」
厨房に向けられた言葉に、俺は虚を突かれる。
( ´_ゝ`)「奢るよ」
(´<_` )「どうして?」
( ´_ゝ`)「あれは、俺の客だった」
後頭部を掻き毟る兄者は、ヘラリと笑う。
( ´_ゝ`)「弾だって高いだろう?」
違いない、と俺は頷いた。
命を張っているわりに給金は安すぎる上に、
年々規制は厳しくなるばっかりで、入手するのも楽ではない。
(´<_` )「おぶ」
顔面に投げつけられたおしぼりは、無愛想な女からだ。
顔と手を拭くと、ねっとりと血が絡みついた。
/ ,' 3「あーあ、やだね」
ぶつくさと文句を言う荒巻は足を持ち上げて、
それから間もなく床へとお湯がぶちまけられた。
どうも女は、店を掃除するらしい。
ぐじぐじにお湯を吸いこもうとする靴を引き上げて、俺は席に着く。
(´<_` )(日本のヤクザは礼儀正し過ぎる)
わざわざ名前なんて聞かずに、ズドンと
撃っちまえば、助かったのはアイツの方だったろうに。
(´<_` )(訳わかんねえ店だな)
一体俺は大事にされてるのか、そうでないのか。
混乱している鼻に、辛味の効いた匂いが行き着いた。
もうじき、料理がやって来るだろう。
-
蛇に耳环と藪から棒に、のようです《了》
.
-
( ^ω^)「>>220ここめっちゃすきだお」
-
>>241
( ^ω^)「おつだお!これまた読み応えのある良作だったお」
-
('(゚∀゚∩ 良作がいっぱいですが先に投下させてもらうよ!
-
ざわ…
ざわ…
(-_-) 授業終わりの五分前、教室内は何だか落ち着かない雰囲気に包まれている
(-_-) それもそうだ、もうすぐ昼飯の時間なのだ
(-_-) 教師はそんな俺達生徒の気持ちには気付いていないのか熱心に教科書を読み上げている
(-_-) だが、それは俺の耳には届かない
(-_-) 何故なら……
(-_-) 腹が……
(-_-) 減った……
(-_-) ……からだ
(-_-) 俺は今猛烈に腹が減っている、目の前に座る女のツインテールがチョココロネに見えるぞ
ξ゚⊿゚)ξ ←目の前に座ってるツインテールの女
(-_-)■ それにこの香りつき消しゴムが何か物凄く美味しそうに感じる
(-_-) 俺はもう、限界だ
( ^ω^) じゃあこれで今日の授業は終わりだお!ちゃんと復習して来るんだお!
チャイムが鳴り始める僅か数秒前、教師は授業の終わりを告げた。そしてチャイムが鳴り始める。
(-_-) 今だ。もう俺を、俺の腹を縛るものは何も存在しなくなった。そう、俺は自由なのだ
(-_-) いざ行かん、昼食と言う至福の楽園へ
-
(-_-) ぼっちのグルメー屋上編ーのようです
-
俺は周りの喧騒には目もくれず席を立ち、屋上へと向かう。
北校舎の屋上、そこは俺が入学した時から入り口の鍵が壊れている為立ち入ることが出来る「食」という
神聖な儀式を執り行うのに適した場所なのだ。
(-_-) 暑すぎず、寒すぎず、風も強くなく日差しも強すぎではない。今日は最高の屋上ランチ日和だ
(-_-) 誰かと食事を食べないのかって?それはどう考えても愚問
(-_-) 食事をする時、それは誰にも邪魔をされてはいけない。一人で静かに、でも自らが満足するものを満足するまで味わう
(-_-) それが食事という神聖な儀式なのだ
(-_-) え?人と話しながら食べる?そんな……そんな行為は食事を愚弄する犯してはいけない禁忌の一つだ。
(-_-) 食事をする時は心を落ち着け精神を目の前の食材にのみ傾ける。それがものを食べて生き永らえる人間として最低の礼儀だ
(-_-) 人の視線が気になって、誰かと話すことで精一杯で、何か悩みがあって……そんな時には幾らおいしいものを食べた所で味は分からず、その行為はただの栄養摂取にしかならない
(-_-) これは絶対にあってはいけないことだ。だから俺は食事をする時は必ず一人で、目の前の食材にのみ意識を向けて最大の感謝と共に頂くようにしているのだ
-
(-_-)▲▲ そんな今日の俺の昼食はこれ、登校中に買った某コンビニのおにぎり計二点だ
(-_-) これだけ食に関する御託を並べていてそれで食べるものがコンビニおにぎりwwwと思われた方、それは完全に甘いとしか言いようがない
(-_-) いや、甘すぎる!サトウキビよりも、合成甘味料よりも甘い!
(-_-) 確かに自分で作った自家製のおにぎり、それは素晴らしいものであるし俺の大好物でもある
(-_-) 素材に拘れるし自分の好きな量、味と調整も自由自在だ
(-_-) だがコンビニおにぎりという存在もまた長い歴史と携わった人々の知恵と努力、汗と涙の結晶なのだ
(-_-) どんな状況でも新鮮なパリッとした海苔を、よりご飯に合うおかずを、より高品質で低価格で、そんな崇高な存在を馬鹿にするとは何事か
(-_-) ああ、腹が待ちくたびれたとクレームの嵐だ
(-_-) ほら、待っていてくれ。今食べるから
(-_-)▲ うん……うん……
(-_-) あぁ……まるで砂漠に水が吸収されていくかのように体が満たされていく
(-_-) そう、俺は、いや人間は食事をすることで生き、食事をする為に生きているのだろう……
これからも俺のグルメは続く。そこに旨いものがある限り、そして命ある限り。
-
ξ゚⊿゚)ξ 何あいつ一人で頷いてるのよ?面白そうだからつけて見たら勝手に屋上なんか入ってるし、そこで優雅にぼっち飯して楽しんでるし……
ξ゚⊿゚)ξ 変なの
<END>
-
>>213
なんだこの記号
-
ミセ*>ワ<)リ「やほやほっ! ミセリだよ!」
ミセ*゚ー゚)リ「今月から二学期も始まったし、いっちょやりますか!」
ミセ;゚д゚)リ「――ってみんななんで夏休みに文戟してんのぉ!?」
ミセ;゚д゚)リ「やっべっ! 出遅れた感満載じゃん!」
ミセ;;゚〜゚)リ「むむむ〜っ! 今から全員倒しちゃうんだからね!」
ミセ*>ワ<)リ「それじゃあアタシの作品をミンナ見ろぉ〜〜〜〜〜〜ッ!!」
-
足跡で作ったフレームでは?
構成の話だったらこうだと思う
。(句点)→ 。。
゚(半角半濁点)と●→ ゚●゜←゜(全角半濁点)
-
投下と被ったかすまん
-
トランスチューブターミナルの方角から、
天蓋の光学ディスプレイが、にわかに曇りの様相を呈してきた。
人工的な青空を模したカラーが、
黒と灰の混ざりあった靄に切り替わっていく。
光学ディスプレイは一見天蓋を隙間なく覆い尽くしているように見えるが、
互いの辺には若干の隙間があり、
そこからスプリンクラーにより人工的な降雨が再現される。
デルタ・コンプレックスは絶えず工業地帯からの有害な排煙が大気を汚しており、
こうやって定期的に大気汚染物質を雨に吸着させ、
更に地下にある処理施設へ流すのだ。
.
-
僕はくたびれた合皮の鞄から、色あせた"緑《グリーン》"の折り畳み傘を取り出す。
近くを清掃しているボットを横目に、早々にそれを広げた。
全てのボットは監視業務を兼任していて、
常にこの地下都市に住む市民を見張っている。
偉大なるコンピューター様が管理なされている完璧な社会で、
愚かにも雨に濡れ、
自身の体調を崩す要因を作り出す愚鈍な市民など存在しないのだ。くそったれ。
工業地帯から自身のクリアランスである緑の居住地区に出る。
画一的なデザインのアパルトメントが立ち並んでいるので、
しっかりと標識を見ないと現在自分がどの通りを歩いているのか分からなくなる。
チェス盤の様に整理され尽くした美しい街並みといえば聞こえがいいが、
実際はコピー&ペーストで記号化きった無機質な空間と言わざるを得ない。
更にこの場所をせせこましく感じさせるのは、
屋根の上を走る"輸送道路《トランスハイウェイ》"だ。
自動運転の輸送車が時間を問わず走り回るせいで、
その騒音と排ガスにこの街は常に溺れている。
輸送車も、市民のクリアランスに合わせて色分けされていて、
それぞれに配給される物資が詰め込まれている。
頭上で鳴る、タイヤが荒れたアスファルトを転がる音を聞きながら、
僕はゆっくりとかぶりを振った。
.
-
思うのは、"人工食糧《レーション》"のこと。
完璧な栄養素と機能性を兼ね備えたコンピューター様の最高傑作と名高いソレ。
裏を返せば栄養素と機能性以外の全てが切り捨てられており、
味は無く、食感は砂粒を握り固めたような劣悪なものだ。
もちろんそれに文句の一つでもいえば、間違いなく反逆者として処刑される。
だから僕ら下級市民は皆、文字通り味気ない生活を"享受させて頂いている"訳だ。
最近は舌も胃も、人工食糧を受け付けなくなって来ていて、
こっそりと職場の産業廃棄物に混ぜて捨てている。
同僚から痩せたことを悟られないように、
仕事着にソファから抜いた綿を詰め、着膨れするようにして誤魔化している。
しかしそれも、次の医療ボットによる定期検診で間違いなく看破されるだろう。
単純なもので構わないから何か味があれば、少なくとも飲み込むに足るのでは、と
誰に言うでもない愚痴にも似た提案が、あぶくのように湧いては割れた。
やがて、その不満も洗い流すように雨が降る。
傘膜に当たる雨粒が跳ねる音は、存外嫌いじゃない。
あと数分もすれば雨脚は更に強まるはずだ。
その前に家に入らないと、傘を差したくらいではずぶ濡れ必至だろう。
僕は少し早歩きになると、傘と雨で視界の狭まった世界で、
居住地区に走る送電ケーブルに無造作にぶら下げられた標識を睨むように進んだ。
.
-
――カァ……ァアン。
ふいに、硬質な反響音が聞こえた。
丁度、金属を壁か何かに打ち付けたような音だ。
僕はその音の方向に顔を向ける。
大通りと大通りの間にひしめくアパルトメント達の隙間。
インフラ配管や室外機が絡み合う、薄暗い路地裏に、それは居た。
――最初は、人間だと思った。
室外機の一つに腰掛け、壁を背もたれにして、濡れているのだと。
傘を忘れて、少しでも雨を避けるためにそうしているのか、
はたまた、この管理社会に疲れ切って頭の狂った"偏執狂"であるのか、
どちらにせよ、お近づきになっても僕の得になる事は無いだろう。
傘に入れてやる代わりに金を巻き上げることも考えたけど、
あいにく今の僕の生活に、
そもそも金を使うような時間が無いことを思い出して思わず笑いが出た。
.
-
だからだろうか、なんとなく、その人影に近寄った。
何か助けになれば、なんて良心からじゃない、
単純に先程の音の出処が気になっただけだ。
もし何かしらの異常があるなら、
"端末《ターミナル》"からコンピューター様に報告するのが市民の義務だ。
傘の柄を首と肩で挟むように支え、
空いた両手を使って合皮鞄から"光線銃《レーザーガン》"を取り出す。
もし、かの人影が当方の予想通り狂人であり、こちらに襲いかかってくるようであれば、
迷わずに引き金に手をかけ処刑出来るようにする準備だ。
もう一度、あの音が響く。
距離をつめる度に、
雨のカーテンの向こう側にボヤケていた輪郭がはっきりしてくる。
.
-
どうやら女のようだ。
肩口の下辺りまで伸びた黒髪が、水を吸って艶めいた輝きを放っていた。
その女は、室外機に腰をかけながら、ゆっくりと前後に揺れている。
そして、自身の後頭部をアパルトメントの壁に打ち付ける時に、あの金属音が響いていたのだ。
間違いなく、狂人の類だろう。
僕は光線銃の銃口を、その人影に合わせるように持ち上げる。
その時、女が前後に揺れるのを止め、首だけをゆっくりとこちらに向けた。
――顔の半分が、無かった。
正確には、彼女の顔面の右頬から額までの皮膚が剥がれていたのだ。
そして、鉛色に鈍く光る金属の頭蓋骨と、
剥き出しのセンサーアイが雨粒を纏うように晒さている。
.
|
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板