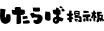レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
中・長編SS投稿スレ その2
-
中編、長編のSSを書くスレです。
オリジナル、二次創作どちらでもどうぞ。
前スレ
ttp://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/9191/1296553892/
-
読んだ感想だよ。
ガス帯をテレサの超能力で吹き飛ばせたのは良い。テレサ自体がガトランティスと単身で渡り合えるチートだし。星爆弾、波動砲のコンボで大帝戦死もまあ良い。
ガス帯の消滅、軌道変更と巨大戦艦の撃破はテレサでも本気で当たらなければならなかった。地球艦隊の波動砲の一斉砲撃が本気テレサの惑星爆弾と同じ。
惑星都市は描写を見る限り、拡散波動砲でもイチコロだろうけど巨大戦艦は正直、波動砲では火力不足で効く気がしない。
テレサが波動砲の発射に合わせ能力一点集中で巨大戦艦の装甲に穴でも開けたのだろうか。
-
ここは投稿スレです
感想は専用の感想スレがあるのでそちらに書きましょう
-
提督たちの憂鬱支援SS 中編版――「リバティベルが鳴る日には」
プロローグ
――西暦1962年4月 日本帝国 帝都東京 日比谷公園
「老けましたね。嶋田さん。」
「そういうお前もな。辻。」
帝都東京。
この地球でも最強といわれる国家の中心は、杜である。
鬼門に靖国神社を配し、かつて天海大僧正が作り上げた霊的な防御機構をも取り込み、恐れ多いところを中心とした衛星軌道を配したこの都市は、発展の真っただ中にあった。
皇居が南面する東京駅の周辺は超高層ビルの建築ラッシュであるし、明治時代以来営々と年を重ねてきた霞が関の官庁街は化粧直しを施され、1930年代のモダニズムから明治時代の赤レンガ街に色彩的には近づきつつある。
しかし、この都市の――世界最大の海洋である太平洋とインド洋をその実質的な支配下におく超大国の中心は微動だにせず、今も日本人の帝国とそれに次いで世界の(当然だろう。日本帝国は「日本人のための」国なのだ)安寧を祈っている。
あの太平洋の戦い以前に比べて主上にかかる負担は減っており、たまにはこうして昔の臣下を呼んで世間話をする時間があるのは結構なことだと嶋田は思った。
その帰りしな、いつも寄る公園の屋台で一服していると、彼の周囲には、何人かの学生が集まり、彼にサインをねだってきた。
先ほどまでは快くそれに応じ、引退したとはいえ帝国の政界に絶大な影響力を持つ嶋田を取り込もうとやってきた野心のある政治家を(わざわざ歩いてきてやったという態度が丸出しだった)面前で一喝し震えあがらせていたが、予定通りそこへ辻がやってきた。
彼は、周囲を騒がせてしまったことをガーデンテラスで談笑する人々に詫び、辻と向き直った。
友邦であるインド連邦産のアッサムにミルクをたっぷり入れた嶋田は、二重橋を横目に一服した。
彼は「神崎将人」だった頃から煙草は苦手であり、こうした紅茶を好んでいたのだった。
その点でドイツのヒトラー元総統から「国際嫌煙学会」への協力を要請されて苦笑いしたりするが、現在の彼は基本的に自由人という扱いだった。
「なに、俺は史実では80年代まで生きるらしいからな。せいぜいお前の目をぬって暇を堪能するさ。」
「それは重畳。この資料をお渡ししても問題ない程度にお暇ということですね?」
嶋田は、にやりと笑う辻に、露骨に溜息をついてみせた。
「お前な・・・。」
口を開きかけた嶋田は、辻の様子が少し変わっていることに気づく。
いつもの黒さが少しだけあせ、何か思いつめているようだ。
この表情を辻が見せたのは、もうずいぶんと前――あの衝号の一件以来だった。
「どうした?帝国は問題多いながらも発展している。核兵器管理体制はしつこいくらいに万全。国際防疫に関しては先日西ナイル熱の封じ込めに成功したばかりだろう?まさか東米で何かあったのか?」
嶋田は、周囲を素早く見渡す。
彼の周囲を固めている特殊警備課の警護官たちはわざわざ自分の彼女と談笑するようにして自然さを演出し、話を聞こえないようにしている。
周囲200メートルのクリーニングは済んでいるはずだ。
「いえ・・・少し昔のことをね。今回お渡しする資料に関することです。」
「お前がその言い方をするということは、俺に昔話を聞かせるつもりなのだろう?」
嶋田はあえておどけてみせた。
やれやれ。これから山本のところに寄るつもりだったが・・・あいつの孫だくさんの相手は少し待ってもらわねばならないらしい。
「では、これを・・・。」
辻が差し出した冊子の表題には、こう書いてあった。
「リバティ・ベル計画に関する調査報告書 閲覧厳禁」。
-
――西暦1943年3月 北米大陸 カリフォルニア市
フランクリン・D・ローズヴェルトは、温かな日差しの中ゆっくり深呼吸していた。
元大統領である彼は、崩壊したアメリカ合衆国の様子に心を痛めてはいたが、あの大恐慌の収拾にあたった日々に比べれば体調はすこぶるよかった。
妻のエレノアとはじめたオレンジ農園は紆余曲折の末に軌道に乗りなかなかの評判だったし、だからこそこの混乱する西海岸経済の中にあって彼は安定した老後を過ごせていたのだった。
だが、そんな彼の平穏な日々はつい一昨日唐突に終焉を迎えた。
だからこそ彼は久々にスーツに袖を通してオレンジ園の真ん中で客人を待つということをしていたのだった。
「閣下。」
「グルー君か。」
ローズヴェルトは笑みを浮かべた。
元駐日大使であり、現在はカリフォルニア政権と呼ばれる西海岸諸州のゆるやかな同盟の外相をつとめるジョセフ・P・グルーがそこにいた。
彼の横には、東洋人の男性がいる。
ローズヴェルトに珍しい切手(最近再独立を宣言したタンヌ・トゥヴァのものだった)を送ってきて以来の付き合いである男、岩崎久弥だった。
日本を代表する財閥の総帥である岩崎は、日本政府から特使としてこのカリフォルニアにわたってきていたのだった。
日本人にいささか偏見のあったローズヴェルトが得た、はじめての日本人のペンフレンドでもある。
「やあ。久しぶりですな。」
年上である岩崎をローズヴェルトはにこやかに迎えた。
「閣下。急に御用とは。」
ローズヴェルトの顔が曇った。
あの恐ろしい――計画。
それについて彼に話さねばならない。
でなければ、彼や、彼をはじめとするアメリカ合衆国国民は、永遠にあの悪夢を恐れ続けなければならないのだ。
自由の鐘が鳴らされる時、合衆国は・・・いやその残骸は人類の悪夢を凝縮した存在になってしまうだろう。
それを避けるためには、ローズヴェルトは悪魔とでも手を結ぶ覚悟だった。
それが、実質的な「最後のアメリカ合衆国大統領」となった彼の責務だと、彼は考えていたのだから。
――同日 旧イリノイ州 シカゴ近郊 海軍作戦本部
廊下の落書きを見ながら、ジョセフ・F・エンライト「大佐」は暗儂たる思いにかられていた。
先ごろまでこのシカゴを支配していた旧連邦軍臨時第2軍が実質的に崩壊して2週間あまり。
現在は「五大湖同盟」を称する旧イリノイ州軍の残党がアメリカ合衆国非常事態軍政指揮本部を名乗ってこの都市を維持しているが、その実態たるやごろつきとなんら変わりがない。
春だというのに気温が10度を下回りみぞれが降る天候状況の中で、「連邦陸軍」はケンタッキーへの侵攻とロッキーを越えて西海岸を「併合」する準備にいそしんでいるらしい。
かつては大学の講堂だったこの場所は、現在も続くわけのわからない「内戦(シビル・ウォーⅡ)」の中で爆撃を受け、下卑た落書きを残した同盟の兵士もろともずたずたになった後のままだ。
まったく、一時的にしろノーフォークを回復し、停止されたはずの鉄道網を一部とはいえ掌握しているのが奇跡のようなものだった。
-
「ルメイ閣下。いらっしゃいますか?」
「いるとも。でなければ呼んでいない。」
崩壊した講堂の真ん中から声がした。
カーティス・ルメイ「合衆国海軍臨時作戦本部 臨時作戦参謀代理」は、不機嫌な顔を地面に描かれた10メートルほどの巨大な世界地図に向けながらエンライトを手招きした。
「他の方は?」
「ヴァンデンバーグ閣下はテキサス軍と協同するという名目で西海岸へ飛んでいった。ほかの海軍士官も似たり寄ったりだな。戦艦『モンタナ』艦長という名の老人を除けばもう君しか残っていない。」
昨日のうちに無理にでも逃げ出した方がよかったか、とエンライトは内心舌打ちした。
もともと生き残った海軍士官と予備役の連中を集めて作った作戦本部は、シカゴ市街戦時に大ダメージを受け、現在はサンディエゴの太平洋艦隊司令部が機能を代行しているような状態だった。
ここが今維持されているのも、アクロンの海軍航空隊基地やノーフォークの残留小艦隊、そしていくらかの航空機群を指揮するためでしかない。
だからこそ、陸軍航空隊の指揮官だったヴァンデンバーグ「大将」を本部長に据えていたのだった。
そしてエンライトは、サンディエゴからの連絡士官として飛んできたためにここに留め置かれてしまっていたのだった。
それには――
「君の妻子だが。」
ルメイが口を開いた。
「次の定期便でサンディエゴに送るように手配しておいた。」
「ありがとうございます。」
エンライトは素直に礼を言った。
この元陸軍航空隊の指揮官は、得体のしれないところがあるが、時折こうした優しさを見せることがあると彼は知っていた。
「その代わり。」
語調が強まる。
「君には、潜水艦に乗ってもらいたい。」
「はぁ?」
「ノーフォークに、『ノーチラス』が待っている。君はそれに乗り、命令書の航路を目指してもらう。突貫作業だが、改装は完了済みだ。」
「ちょ・・・ちょっと待ってください!」
「なんだ。」
「『ナーワル』級のノーチラスですか!?改装したとはいえそんな旧式艦で何を――」
「機密だ。計画はロング前大統領の頃から進んでいてな。戦局がここまで至ってしまった今となっては、これを実行するしかないのだ。」
ルメイは、暗い笑みを浮かべた。
「君の細君が乗る飛行機のガソリンだって、この計画のために用意されていたものなのだぞ。君は、従う責任と義務があることを忘れるな。」
――1943年4月6日 北米東部軍管区 ノーフォーク軍港
B−17は、そのまま引き返して行った。
鼻をつく悪臭の中、エンライトは顔をしかめた。
滑走路の傍に積み上げられていたのは、大量の瓦礫に加え、おびただしい数の死体だった。
焼却しようとしたらしく黒こげになってはいるが、燃料不足のためかハエや野犬が群がるままになっている。
周囲は見渡す限り無人である。
あの津波が持ってきたらしいヘドロや何やかやが堆積し、かわりにこの町のあらゆるものを持ち去ってしまったためだった。
機内で聞いた説明でも、ここには海軍関係者が500名ほど残っているだけだということだった。
ほかは、皆が押し流されるか寒さで凍え死ぬか、あるいはアパラチア山脈を越えたのだ。
合衆国海軍大西洋艦隊という名の存在は、もはやない。
津波の難を逃れた残存艦はすでに本土決戦準備の一環としてサンディエゴに移動しており、ここには辛うじて哨戒艇数隻と潜水艦が2隻ほどいると聞いている。
書類上は戦艦「モンタナ」が就役しているが、ドック内に巨大な砲塔を据え、半分だけ艦橋構造物が作られた戦艦として鎮座する以外は何もできない。
かつて世界第2の巨大海軍として大西洋を威圧していた合衆国海軍のなれの果ては、このざまだった。
-
視界を、土煙が横切った。
ジープだった。
燃料事情がひっ迫している東海岸らしく、車体の後部に薪を燃やす炉をつけてそこから出るガスでエンジンを動かす「ウッド・ジープ」だ。
滑走路を横切ったジープは、エンライトの横につくと止まった。
「お待ちしておりました。エンライト艦長。」
「ああ。君は?」
「『ノーチラス』副長をつとめることになっています、エリ・T・ライヒ少佐です。まぁ、艦長と同じような境遇ですな。人手が足りないので古参連中にこき使われとります。」
20代後半のライヒ青年がにかっと笑った。
「私も含め、乗組員79名はかき集められたクチです。何かよくわからないものを輸送する任務のようですが・・・」
「とりあえず、埠頭へ連れて行ってくれ。艦を見たい。」
「アイアイ・艦長!」
軍港周辺は、悲惨の一言に尽きた。
簡単に片づけられてはいたが、ドックの中では戦艦が横転し、司令部の建物もガラスが割れ、炎上した跡が生々しい。
そして、瓦礫の間には人の死体が点々と横たわっていた。
「メキシコ風邪(東部ではこう言う)にやられた連中です。それに凍死した人々も。」
ハンドルを握るライヒが言った。
「ここで1週も過ごせば、慣れてしまいますが・・・やはりいやなものですね。」
「まぁ・・・どうしようもないがな。」
エンライトはそう言うにとどめた。
かつて展開していた州軍も、今は中西部に食糧を求めて移動しており、生き残った人々はニューヨークなどの大都市に固まるか南部を目指し移動していったらしい。
どこかの軍艦のマストであったらしい旗竿に翻る星条旗の横を曲がると、埠頭に出た。
横転したり着底している艦艇の中で、2隻の船影が正常だった。
近づいてみると、少しかしいだタンカーらしき船と、大型の潜水艦だった。
哨戒艇は見当たらない。
クレーン車を使って何かを後部甲板に下ろしているところらしかった。
「おおい!艦長がお着きになられたぞ!」
ライヒが叫ぶと、手が空いている乗組員たちが整列した。
軍規は維持されているらしい。
だが、後部甲板にいる何人かの白衣の男たちは彼を一瞥しただけだった。
「艦長を任じられたエンライト大佐だ。君らと同じく、何が何やらよく分からん。」
「ここでは皆同じです。艦長。」
にかっと古参の下士官が笑った。
「水雷長のキングです。・・・ああ、キング提督とはまったく関係ありませんが。」
「とすると、あの白衣の連中が全部知っている・・・ということか?キング曹長。」
「そのようです。ですが連中、こっちを実験動物か何かだと思っているらしく一言も口をききやしません。まとめ役の陸軍士官は面白い奴ですが、教える必要はないと口止めされているらしく・・・。」
「ありがとう。では、私は命令書を見ることにしよう。早く仕事をすませてこの気の滅入る場所は後にしたいものだからな。」
「全然同意します。艦長。」
それまで聞いていたライヒも、兵たちと一緒に笑った。
なかなかいい艦のようだった。
-
「艦長、おられますか?」
「入れ。」
失礼します、と入ってきたのは、陸軍中佐の階級章をつけた南ドイツ系の男だった。
顔には多くの傷跡が走っているが、顔は愛嬌に富んでおり、その気性のよさを示していた。
「今回の計画の担当者を押しつけられてきました。リカルド・クレメント中佐です。予備役招集のクチでして・・・大学の関係で呼ばれたようです。」
「クレメント中佐。君は、『積み荷』が何か知っているのか?」
エンライトは厳しい表情でクレメントと名乗った中佐に視線を向けた。
「いえ・・・まぁ想像はつきますが。」
「というと?」
「運び込まれたのは、何個かに分けられたコンテナです。いずれも電源を本艦からとり、冷却機能を持っているらしい。そしてわたしは文化財関係の手引書を渡されました。上司いわく『合衆国再興のためにはどうしても安全な場所に置いておかねばならない』とか。」
「・・・重要な文化財・・・か。」
「独立宣言文も混じっているかもしれません。それに憲法の原文も。」
やれやれ、という表情でエンライトは艦長室の椅子に体重を預けた。
「となると、国歌にうたわれたような米英戦争時の星条旗も混じっているかもな。いや、よく津波に飲まれずに残っていたもんだ。」
「重要性は分かりますよ。艦長。でなければ北から装甲車2台に分乗して来てはいませんから。」
「命令書によると、本艦は友軍占領下のアイスランド島に寄港し補給を済ませ、英国諸島へ向かうらしい。そして指示を待てと。」
「スイスあたりで保管するんでしょうかね?」
「いや。英国だろうな。あそこはドイツに近すぎる。色々な意味で。」
まぁそうでしょうな。とクレメントは頬の傷跡をゆがませて苦笑した。
「輸送には、あの白衣の一人も立ち会うそうです。私も同乗させていただきますので勝手はさせないつもりですが・・・ご注意を。彼は気が短い。」
ははっ。とエンライトは苦笑した。
なんだ。話せば分かる男じゃないかこいつは。
「なら、相手は君に任せるよ。合衆国海軍最後の航海だ。なるべく平和裏に終わりたいものだと思うからね。」
「同感です。にしても『リバティ・ベル計画』というのも洒落た名前じゃないですか。自由の鐘ではじまった国がその名を冠した計画を最後に消滅するとは皮肉が利いている。」
くつくつとクレメントがおかしそうに笑った。
「まぁ、な。さて、クレメント中佐。君も仕事にかかってくれ。命令書の日時まで時間がない。我々は2週間で英国諸島沖に達しなければならない。出るのは早い方がいいと思う。」
-
――同日 北米大陸東岸 ニューヨーク市近郊
まるで宇宙服のように見える格好をして、男が歩いていた。
廃墟となった施設の中、周囲に同じような格好をした銃を持った護衛を従え、内藤良一は津波に荒らされたままの研究施設の廊下をゆっくり進んでいく。
「ロックフェラー研究所か・・・こうなる前に来たかったが・・・。」
「博士。急いでください。防護服の電池にも限りがあるんですから。」
「分かっている。恐らく冬の寒さで死滅しているだろうがアメリカ風邪の病原体を警戒するに如くはないからな。恐らく発生源であるここでは特に。」
「我々が出た後にモントリオールの『連山』20機がテルミット剤をたらふく積んで施設の『焼却』に来ることになっています。無線の向こうはまだかまだかとせっついていて――」
「もう少し待ってもらうように言ってくれ。」
護衛は少し苛立った様子だった。
地下施設が津波による被害を受け水没したままであることは予想通りであったし、すでにアメリカ風邪関連の資料も手に入れることができていた。
なのに彼らがここにいるのは、数日前にカリフォルニアから発せられた緊急電文が影響していた。
でなければ、カナダからわざわざ実用化されたばかりのヘリコプターで、空挺部隊が確保した平地に降り給油を繰り返しながらニューヨークまで強行軍で来てはいない。
比較的被害の少なかった最上階である3階部分から資料を金庫ごと奪い取った彼らは、内藤の命令で「何か」を見つけるまで待たされていた。
それが何かは内藤しか知らない。
所長室を物色していた内藤の手が止まる。
そして何枚かの資料を見つめていた内藤の手が震え始めた。
「恐ろしい・・・本当にやっていたのか・・・」
「内藤博士?」
「確かにあの学問はドイツだけでなくアメリカが本場だ・・・しかし、まさか、本当にこんな・・・いや南米でペスト菌を使って人体実験をしていたような国だ――ナチスに先んじてあれをやってのけていても・・・。」
「博士!」
内藤は我に返った。
「出よう。ここを焼却しておいてくれ。この所長の遺体も、書類も、欠片も残すな。これは、今この世界に存在していてはいけないものなんだ。」
「どうしたんです?何を――」
「本土の『ドリーマーズ』に最優先で緊急電を。『遺憾ながら想定通り』。・・・くそっ。半世紀以上も早くパンドラの箱を開けやがった!!」
護衛の兵士は、毒付きはじめる内藤の指令をあわてて無線機にがなり立てることしかできなかった。
-
【あとがき】――支援SSのようなネタを考えたら思った以上に長編となったので書けている分だけ中編板に投稿させていただきました。
本作はかなり黒いネタを使っていますので、その点だけをご注意くださいませ。
次回は明日以降投稿の予定であります。
-
>>968-974 の続き
――西暦1943年4月10日 大西洋上
結局、白衣の男たちは1人を除いて埠頭で「ノーチラス」を見送った。
最後まで無表情であったのが気味が悪かったが、科学者というのはそういうものだろうとエンライトは自分を納得させることにした。
「深度そのまま。間もなく第1変針点だ。周囲の警戒を怠るなよ。」
「はい艦長。」
「深さ21を維持せよ。艦長。少し休まれては?もう北米に上陸した独軍機の哨戒圏外に出るころです。」
「そうだな。そうさせてもらうよ。副長。」
「あとは私が引き継いで置きます。なに、艦長みたいな『扱いやすい』上官がいて助かります。」
「言ってくれるな。」
発令所が笑いに満ちた。
このナーワル級潜水艦2番艦「ノーチラス」は古い艦だ。
就役が1920年代中盤であり、第1次世界大戦時に戦利品となったUボートの技術を利用した機雷敷設用の「Vボート」と呼ばれる種類の大型潜水艦であるこの艦は、水上排水量2760トン、水中排水量は3900トンにも達する大型艦でもある。
発展型であるV4「アルゴノート」号が日本近海で戦没した今は、合衆国海軍が保有する最大の潜水艦となっていた。
副長であるライヒ少佐によると、対日戦争勃発に先立ちサンディエゴで改修を受けていたものの、そうこうしているうちにフィリピンやウェークが占領されてしまったうえに潜水艦の喪失が異常なレベルで続いていることから旧式艦である本艦は後方へ下げられ、ないよりマシというレベルで壊滅したノーフォーク軍港に大西洋艦隊残存艦と入れ違いに配備されたらしい。
時間だけはあったので細々と改装を受けていたところ、今回の計画に白羽の矢が立ったというわけだった。
確かに機雷敷設装置用の区画を転用し、40本にも達する大量の魚雷を搭載できるこの艦は物資輸送任務にはもってこいだ。
最大で2万カイリにも達する航続距離もまた適任といえる。
攻撃力については、外付けではあるが魚雷発射管が4本増強され6門に達しており申し分ない。
肝心の静粛性は、余った資材を手当たり次第に「徴用」し、徹底的な防音が施されていることからエンライトは非常に静かな印象を持った。
これなら、噂に聞くUボートや日本の幽霊潜水艦にも引けをとらないだろう。
「なら、そうさせてもらおうか。副長。権限を預ける(ユーハブコマンド)。」
「渡されました(アイハブコマンド、サー。キャプテン。)。飛行機の次は3日連続勤務です。お疲れでしょう。ゆっくり休んでください。」
「そんな年でもないよ。」
笑いながらエンライトは発令所を後にした。
長距離航海を念頭にしてはいるが、潜水艦であるだけあってこの艦は狭い。
前部の機雷格納庫を改装した倉庫に物資が積み込まれているため大幅に狭いわけではないが、後部魚雷発射管室を潰して設置された直径2メートルほどの円筒形のコンテナがある艦長室のあたりは、潜水艦乗りであるエンライトにも少し息苦しく感じた。
「ああ、艦長。いつもの分です。」
「ん?炊事長。これは?」
「え?三人分の食事ですが・・・艦長が命じたのでは?クレメント中佐とあのコップ女史で・・・」
「ちょ・・・ちょっと待て。「女史」と言ったか?」
「ええ。」
炊事室から出てきたティレンヌ炊事長は不思議そうにアルミ製のお盆二つを手に首を傾げた。
「マリー・コップ女史です。女性には見えないかもしれませんが、れっきとした女性で遺伝学者ですよ?なんだ、知らなかったんですか?私は以前雑誌で彼女のことを読んで――」
「炊事長。ちょっと艦長室まで来てくれ。」
エンライトは面喰うティレンヌ炊事長の太った体を艦長室に引っ張り込んだ。
「何なんです?艦長。」
「コップ女史・・・と言ったな?彼女について知っていることを話してくれないか?」
-
はぁ・・・とティレンヌ炊事長は目を白黒させながら艦長室の小さな机の向かい側に座った。
「アメリカ優生協会の研究者ですよ。遺伝学が専門で、戦前はドイツのカイザー・ウィルヘルム研究所にも招かれていたほどの天才です。大病を患った後は人前に出ませんでしたからあまり顔は知られていませんが、私の親類が・・・その、病気で、『そういうこと』に関して彼女の助けを借りたことがあったので知っているんです。
いや、あのニューヨークでよく生き残っていたものだと感心しました。」
「そのことを、誰かに言ったか?」
「いえ?こういってはなんですが――第2次大戦の勃発でナチに通謀しただのと陰口をたたかれていましたから、言わないで置きました。彼女の方も私を知っているかどうか・・・。」
エンライトは考え込んだ。
どういうことだ?
クレメント中佐はなぜ「彼」と言った?
それに、「彼女」に私を接触させないようにしようとした?
「クレメント中佐は、艦長に持っていく分の食事をいつもかわりに持っていってくれたのですが。三人で一緒に食べると言って。」
「ああ。確かに持ってきてくれた。そうか、そういうことか。なるほど、無口な人だったから分からなかったんだ。すまない。それで炊事長。」
エンライトはうそをついた。
「はい?」
「女史のことは、君の考えたとおりあまり人に知らせるものでもないだろう。これまで通り黙っておこう。中佐もあえて私に『彼』と言って気をつかっているくらいだ。」
「ああ、なるほど。そう、そうですね!」
フランス系の炊事長は何度も頷いた。
「了解しました。艦長。注意しておきますよ!」
「ああ。頼む。」
炊事長は駆け足で炊事室へ戻って行った。
エンライトは、後部のコンテナへと歩いていく。
確か、クレメント中佐は今の時間帯は散歩と称して仲のいい水雷長と話し込んでいるころだ。
ことによるとカードをしているかもしれない。
そして、それが終わると、コンテナの方へ歩いていっていた。何かを持って。
今思えば、それが炊事長に渡された食事だったのだろう。
出航以来、クレメント中佐の私室の隣にある白衣の――コップ女史の私室からは彼女がほとんど出てきたことはなかったように思う。
出てきたときは、コンテナを開けていたのだが。
おそらくそこに食事を・・・。
?
エンライトは周囲を見回した。
何か、視線を感じたような気がしたのだ。
コンテナの蓋の上部、ガラス製ののぞき穴から――
エンライトは、「立ち入り禁止」のロープを乗り越え、コンテナに近づいた。
コンコン・・・。
叩いてみる。
コンコン。
!
返事があった。
「その子に何をしている?」
カチャリ。
鈍い音が響いた。
聞きなれたけん銃の音だった。
エンライトは振り返った。
冷たい光を宿した瞳がぼさぼさのボブカットの前髪の間から覗いている。
よくよく見てみれば、女性であることは確かに見える。
マリー・コップ女史だった。
-
――同 ルイジアナ ドイツ進駐地域 某所
「ようこそ。ルメイ中将。」
「はじめまして、ですか?モレル博士。」
天幕の中では、二人の男が向かい合っていた。
ひとりは、シカゴでエンライトと話していたカーティス・ルメイ中将。
もうひとりは、ドイツ北米派遣軍衛生統括責任者という長ったらしい職についている男。
テオドール・モレル医学博士。
ロンメル将軍率いる北米派遣軍の中にあって、彼らは露骨に避けられていた。
シカゴが再び戦乱状態に突入したという報告があった直後に単身飛行機で乗り付けたルメイと、それを知っていたらしいモレルは親衛隊長官ヒムラーの特命だとしてこの天幕から人を遠ざけていた。
確かに命令書は正式な書式と紙だったし、サインも同様だった。
だが、問い合わせを禁ずという内容その他は真っ赤な偽物であるということは、ルメイとモレルしか知らない。
「カイザー・ヴィルヘルム協会の方はすでに。上の方はまだですが、優秀な者が協力者となっています。」
「その者の名は?」
モレルは、黄色い歯を出して笑った。
「フォン・フェアシュアー。オトマール・フォン・フェアシュアーです。弟子も『優秀』で、これからの研究発展に益するところ間違いないでしょう。」
「そしてあなたの復権も・・・だな?」
二人は笑いあった。
「予定通りなら、あと3日ほどでアイスランドへ。現地じたいがひっ迫しているから補給は手配できなかったが、まぁあの艦の航続距離にとっては問題ない。食糧も十分積んである。浮上したあたりで指令を変更する予定だ。」
「万事計画通り・・・。」
二人の密談は続く。
いんちき療法と断じられ北米へ左遷されたモレルと、何事かをたくらむルメイ。
その内容は歴史には記録されていない。
――同 大西洋上 USS「ノーチラス」
「この子の名は?」
「マリー・アックス。」
「『マリアの斧』?」
「なんだっていいと思うが?」
エンライトは、コンテナの『中』にいた。
一緒にいるのは、コップ女史。
コンテナの中はこじんまりとしたキャビンのようで、簡単なベッドがあった。
そんな中で無表情で「彼女」は、赤ん坊を抱いていた。
赤ん坊は、生後1年たっていないだろう。
白い髪と、赤みがかったブラウンの瞳。彼女の言葉で女児と分かる。
奇妙なことに、赤ん坊は鳴き声を上げない。
そんな赤ん坊――マリアに、コップ女史はミルクの入った哺乳瓶を与えていた。
「察するに・・・要人の子か?」
「・・・・そんなところだ。」
彼女は男口調を崩さなかった。
「1日に1度ミルクを与える。睡眠薬入りだから迷惑はかけない。」
「赤ん坊に睡眠薬か?」
暗に非難しても、返答はない。
「このことは秘密に。」
「それは了解した。協力もしよう。赤ん坊は――まぁ国の宝とも言うしな。」
無言で彼女は頷いた。
-
――西暦1943年4月8日 日本帝国 帝都東京
「間違い・・・ないのですか。」
「はい。」
そうですか・・・と、辻正信は執務室の椅子に腰を下ろした。
「我々の存在ゆえの弊害ですかね?電子顕微鏡に抗生物質。遺伝子構造概念の発表ときて、それに優生学という悪魔が加われば、このようなことが起きると。」
「あの細胞に独自に迫った手腕は驚愕に値します。
平成の我々でも研究途上の技術でしたから――あのマリー・コップ博士は、まさに天才というにふさわしいかと。」
「敵をおだてるな・・・と言いたいところだが、この場合そう言うしかないか。石井君。」
「はい。」
日本版CDC(疾病対策予防センター)を束ねる石井四郎は、極秘の報告を上げていた辻に向き直った。
「可能な限り早急に『確保』するように要請は出しておく。そうでなければ撃沈せよとも。
このタイミングで欧州にわが軍の艦隊がいるのも何かの運命なのか・・・。」
辻は、何かを言おうとして、やめた。
「歪み――か。時代の歪みと、我々という歪み、まさに人の作りだした悪夢・・・だな。」
彼は、手元の電話機から受話器を手にとると、交換手に「外務省へ」と告げた。
――西暦1943年4月10日 北海 ユトランド沖
ドイツ海軍の駆逐艦Z−12は、待機を命じられていた。
党の上からの命令だという男を乗せて。
まったく困ったものだと艦長は思い、乗り込んできた老人をにらみつけた。
カイザー・ウィルヘルム研究所の遺伝学者はどこ吹く風で灰色のユトランド沖の海面を見つめていた。
同時刻、英国 スカパフロー泊地を1隻の軽巡洋艦が出航していった。
軽巡「神通」。阿賀野型巡洋艦の後期型であり、中でも本艦は対潜能力を付与されている。
ひきつれているのは、海防艦2隻と護衛空母「福原丸」、そして駆逐艦「漣(さざなみ)」。
関係改善の意思を見せた英国を表敬訪問していた艦隊から分派されたこの小艦隊は、指揮官として五藤存知少将を戴き、本国からの特別命令を受けていた。
英国海軍はこの動きをいぶかったが、領海外まで航空機で追尾した以外の動きは見せなかった。
というよりも、北米に気を取られてそこまで手がまわらなかったのだ。
この動きを知ってか知らずか、英独停戦後再び大使を迎えていたベルリンの日本大使館と新総統官邸の間を慌ただしく人が行き来しはじめる。
同時に、国防軍総司令部にも日本大使館から駐在武官や私服ながらも目つきの鋭い男たちが出入りし始めた。
「何か」が起きていた――。
-
【あとがき】―― >>968-978 明日と言っておいたので日付が変わってから投稿いたしました。
いえ、earth閣下の第54話に歓喜しまして(汗)
-
>>968-979 の続き
――西暦1943年4月13日 北大西洋 アイスランド沖
「命令変更?このままユトランド沖へ向かい、ドイツ駆逐艦と会同、積み荷を引き渡せ!?」
「英国ではなかったのか?」
『ノーチラス』の発令所がざわめきに満たされた。
通信文を再読したエンライトは、周囲からの戸惑いの視線を受け固まっていた。
補給前に最後の命令を受け取るべく浮上した「ノーチラス」に向け、ルメイから放たれた命令は目を疑うものだった。
「なぜナチに・・・スイスへ送るつもりなのか?」
「いや、それよりも積み荷の中身だ!中身は――」
「落ち着け!」
エンライトは一喝した。
「針路変更。ユトランド沖に向け変針するぞ。ともかく行ってみなければ分からん。」
「艦長・・・。はい。了解しました!」
エンライトは、ライヒ副長に後を託すと、艦長室――いや「彼女」の部屋へ向かった。
聞かなければならないことがあった。
「ああ。艦長か。」
「ドイツ艦に、荷物を引き渡せ、そう命令が下った。」
彼女の動きが、止まった。
数分が過ぎる。
「やはり、そうか。」
女史は、何か自嘲するように笑っていた。
「教えていただきたいものですな。」
「中佐。いつから?」
エンライトは、いつのまにか扉を開け立っていた頬に傷のある中佐――クレメントに驚いた。
「最初から、というべきでしょうかな?艦長。」
「君も、言うべきことがあるという顔だな。」
「ですな。艦長。」
船室の扉を閉め、鍵をかけた(どうやら合鍵を使って開けたらしかった。いつの間に・・・)クレメントは、不躾にベッドに腰かけた。
すでに椅子にエンライトと女史が座っているためだった。
「まず、私の方から言っておきましょう。クレメントというのは私の本名ではありません。」
クレメントは苦笑した。
コップ女史が目を見開いている。
「私の名は、オットー・スコルツェニー。いちおうドイツ第3帝国親衛隊の所属ということになっています。」
エンライトは目を見開いた。
「私は、ルイジアナに進駐した北米派遣軍に先立って現地に潜入していました。そこに、命令がきたのです。まぁ、ロンメル将軍に指揮権は預けられていますが、便利屋のようなものですからね。
カーティス・ルメイ将軍の命令に従えと。命令を伝えてきたのが総統にクビにされた侍医だったのは引っ掛かりましたが、まぁ面白そうでしたので。」
「本気か?」
「本気ですとも!僕は冒険がしたいんです。今やっていることは何ですか?冒険そのものでしょう?それに、あなたは私を問答無用で殺すことはしないだろうし、この女史の話を皆に知られるのは避けたいはずだ。」
ふてぶてしくクレメント・・・いやスコルツェニーは笑ってのけた。
癪に障るが、どこか憎めない、そんな男であることは変わっておらず、なぜかエンライトは安心していた。
「実のところ、僕もあのコンテナの中身は知りません。女史。説明をお願いできますか?
先ほどの反応を見る限り、あなたはドイツへ行くと予想をしていたが、本当にそうなるとは思っていなかったようだ。」
-
「その通りだ。」
マリー・コップ女史は何か、憑き物が落ちたように、頷いた。
「・・・そうだな。ここで話しておかずにいつ話すということだろう。
神の禁忌を冒したその首謀者にして生き残りとして・・・ね。」
「コップ女史。」
エンライトはなぜか先ほどまでとは正反対の感覚を抱いた。
この人に話させてはいけない。
「いや、言わせてくれ。艦長。あなたには頼みたいことがある。
クレメント――いやスコルツェニー。君も、少し露悪趣味なところはあるが人間としては信頼できる・・・と思うから。」
女史は、自分の体を手で抱きしめ、語り始めた。
4日後――1943年4月18日 北大西洋
「磁気探知機反応あり!」
「反応照合・・・間違いない。米国のナーワル級だ!『神通』!こちらカモメ3、目標発見!4E5海域地点42で停止中!」
艦上攻撃機を改造した対潜哨戒機のコクピットで機長は叫んだ。
「了解、カモメ3号機。」
「艦隊全艦、単縦陣と為せ。本艦と『漣』『小豆(しょうど)』は先行、目標へ接近する!」
「神通」艦内の戦闘情報室(CIC)で五藤存知少将は叫んだ。
護衛空母「福原丸」と海防艦「屋代」をこの場に残し、「神通」と駆逐艦「漣」、海防艦「小豆」は反応があった海域まで10キロほどを駆けるのだ。
護衛空母から常時5機が対潜哨戒機として周囲を索敵していたが、それらは2機を残し反応海域へ集結しつつある。
空中から海中の潜水艦が発する磁気を探知、そして攻撃を行えるという日本海軍が誇る秘密兵器は太平洋で発揮された通りの性能を大西洋でも発揮。
正確に米潜水艦を補足していた。
もちろんこれは、日本本土で行われた米軍の暗号解読の成果もある。
「さて・・・うまくいくか?」
――同 USS「ノーチラス」
「艦長!日本艦隊は増速、こちらへ転舵しました!」
「なぜだ!なぜ日本海軍は――」
「やはり、本当だったか・・・。」
「艦長?」
エンライトは、副長の目を見ながら言った。
「太平洋で潜水艦の損失が相次いでいることは知っているだろう?日本海軍は何らかの特殊な・・・赤外線か磁気かは分からないが探知手段を開発したという話が出たことがあった。」
「なんて反則だ・・・。それが事実なら・・・」
「艦長!こちらに向かってくる敵艦は『アガノ』クラス軽巡1、ほかに駆逐艦2です!」
「厄介な。アガノクラスは対潜能力を持っているという情報がある。それに駆逐艦か。後方の護衛空母は対潜哨戒機も飛ばしているだろうから――」
「艦長。」
「仕方がない。――副長。全艦全速!対艦戦闘用意!」
「了解しました!」
エンライトは奥歯を噛んだ。
さて、ここが正念場だぞ。ドイツ艦の前に日本艦隊に見つかるのは想定外だったが・・・いや、むしろ都合がいいのかもしれない。
うまく艦を沈められずに、「敗北できる」だろうか?
-
――同 軽巡「阿賀野」
「『ノーチラス』増速しました!的速5ノット!」
「了解。指向性音通用意!」
「指向性音響通信用意・・・完了!文面は何にされますか?」
「そうだな。『こちらはIJN「神通」。本艦に貴艦を攻撃する意図なし。浮上されたい。』」
「は!」
――同 USS「ノーチラス」
「日本艦より音響モールスです!ええ・・・『こちらはIJN「神通」。本艦に貴艦を攻撃する意図なし。浮上されたい。』です!」
「舐めた真似を・・・」
「距離は?」
「9000メートルです!」
「よし。魚雷発射用意。1番2番装填!」
「は。1番2番装填します!」
水雷長の号令が響き、魚雷発射管に2発の53センチ魚雷が装填される。
「外扉開け。」
「外扉開きます。」
「発射しますか?」
「いや、待て。」
――同 軽巡「神通」
「『ノーチラス』発射管開きました!」
聴音が報告した。
「発射はされたか!?」
「いえ。発射管外扉の開放のみです!」
「司令!?」
「カモメ1番機に下命。『ノーチラス』近傍に爆雷を投下せよ。ただし当てるな。圧力信管は限界に設定!」
「は!」
-
――同 USS「ノーチラス」
「艦長!距離30海面に突発音!・・・爆雷です!数2!」
「どこからだ!?敵艦までの距離はまだ8000メートル以上あるんだぞ!」
「転舵20!副長。航空機だ!上にはうようよいるに違いない。」
艦が傾き、大きく傾斜する。
しかし、予想されたような水中衝撃波はこない。
「爆発・・・しない?」
やがて、はるか下の海中から衝撃波が艦を打った。
「日本艦より再びモールス!『浮上されたい。当方に危害を加える意思なし。』」
「・・・どうされますか?」
「魚雷発射だ。水雷長!ただし――」
――同 軽巡「神通」
「『ノーチラス』より魚雷発射!射線2!雷速40ノット!」
「司令!」
「待て。聴音!40ノットと言ったか!?」
「はい!」
「射方向は本艦に向かっているか?!」
「は・・・・いえ!本艦前方100を通過するコースです!」
五藤は、息を吐いた。
「なるほど。な。艦は浮上しても誇りは捨てない・・・か。」
「司令。『ノーチラス』浮上をはじめました!」
「各艦に指令。礼をもってあたれ。」
「!・・・『ノーチラス』艦内で突発音!発泡音です!」
――同 USS「ノーチラス」
「女史・・・」
「逝ってしまわれた・・・ですか。」
銃声に反射的にエンライトは動いていた。
同時に、スコルツェニーことクレメント中佐も。
駆けつけた先では・・・手にけん銃を握り締めたマリー・コップ博士が倒れていた。
壁には、血とナニカが「華」になっていた。
脈は・・・ない。
やはり、やはりこうするつもりだったのだろうか。最初から。
「艦長。無線機を貸してもらえますかな?」
何かに耐えるようにスコルツェニーが言った。
-
――同 西暦1943年4月18日 メキシコ湾
客船「ゲルマニア」の甲板で、ルメイとモレルは談笑していた。
この客船は、北米方面軍の兵站を預かる1隻で、周囲をイタリア艦とドイツ艦が護衛していた。
「あと1日で、会合海域ですか。」
「そうだな。」
ルメイは笑っていた。
長かった。
あのロング政権下で進められていた「リバティ・ベル計画」にアメリカ第一運動を通じて参加し。
そして軍での出世と崇高なる使命を自分は得た。
あの汚らわしい黄色人種を絶滅できず、このアメリカが半壊してしまったのは誤算だったが、これからは新天地で明白なる天命(マニフェスト・ディスティニー)を遂行すればいい。北米大陸に再びアメリカを興す鍵はもう間違いなく第3帝国にわたるだろう。
「あれ」を使い復活した偉大なる存在たちがカギ十字とともに北米に再臨する頃には、アジアから黄色人種は一掃され、輝かしいアーリアと白人による世界が生まれていることだろう。
手始めは、ゲーリングだ。
我々のウィルスと、戦略爆撃の融合。これをもって劣等人種を「処理」し・・・
「失礼。カーティス・ルメイ閣下はあなたでよろしいですか?」
「うん?」
1等のプロムナードで、ルメイは不機嫌な表情になって振り返った。
不躾なやつだ。
今やあのアメリカ風邪の惨禍を逃れた唯一の「優生保護計画」参加者である自分は予備捨てられていい存在でない。
神の偉大なる力を集中に――
「閣下。われらが総統からの命令です。『第3帝国に反逆者はいらぬ』と。『汚らわしい病原体をもって取り入る者を余は許さぬ』との仰せです。ああ、モレル医師。インチキ療法で総統を苦しめた挙句、こんなことを企て国家命令を偽造するなど――許しがたい暴挙ですな。」
「き・・・貴様!シュレンベルグ!総統に何を吹き込み――」
「待て。君は何か誤解してはいないか?私は――」
ルメイは、胸がやけるような感覚と同時に、自分に向けて弾丸が発射されたことを悟った。
眼帯の男、ワルター・シュレンベルグ少将は冷たい目でルメイを見ていた。
「日本大使館は全てお見通しでしたよ・・・総統は祖国に二重に恥をかかせようとした連中を許すほど甘くはありません。」
ルメイは叫ぼうとした。
違う!あの黄色人種どもの言うことを信じるな!
建国の父祖たちを再生し、総統に永遠の命を献上できる偉大な成果をもってきたのに、この仕打ちは何だ!
と。
そうか。あのジャップどもが総統をだましたのだな。
お得意の汚らしい企てで。
騙されるな!奴らこそが世界の敵だ!奴らこそこの世から抹殺すべき――
「片づけておけ。・・・まったく、日本軍とカナリス提督に、あのスコルツェ二ーの共同作業か。時代も変わったものだな。」
ルメイとモレルは、客船「ゲルマニア」からの転落死として「処理」された。
-
エピローグ
――現在 1962年4月 日比谷公園
「万能細胞・・・iPS細胞を作り出していたのにも驚いたが・・・まさかジョージ・ワシントンやベンジャミン・フランクリンら建国の父たちの遺した髪から細胞核を取り出して染色体を別の細胞に移植・・・それから万能細胞を作り、生殖細胞を作るとは、恐れ入ったな。
卵子と精子を同じ細胞から作って結果的にクローンになる胎児を作ったというわけか。」
「万能細胞自体はある酵素を3種類導入すれば自然と生まれますからね。
リセットというやつです。もともと、細胞の不死化の研究をしていた時に見つけられたらしいです。資料によれば。」
辻は、3杯目の紅茶をすすった。
「遺伝子の中に控訴を導入する際にウィルスを使う方法をとったのか、それとも酵素を直接注入したのか・・・博士が自殺した今は分かりません。」
「そしてそれが成功したのかも、か?」
「ええ。同じ遺伝子を持つ精子と卵子では、どうしても受精ができなかったそうです。受精しても母胎の中に戻したら死産ばかり。その中にあってほぼ唯一の成功例だったマリアは、女児だった。」
嶋田は寒気を感じていた。
自分たちは、抗生物質をもたらし、電子顕微鏡をもたらし、そして遺伝子の二重らせん構造の概念をこの世界に持ち込んだ。
それが、アメリカで隆盛を極めていた優生学と結びついた時、恐るべき化学反応が起こったのだった。
もともと、ナチスの人種観に賛同し、人種改良や障害者の断種をアメリカの蚊が者たちは支持していた。
実際のところ、カイザー・ウィルヘルム研究所の若き天才ヨゼフ・メンゲレのような存在とアメリカの研究者たちとの繋がりについては分かっていないことの方が多い。
が、マリー・コップ博士のような存在は数多くいたし、第2次世界大戦中にもそのやりとりが――ナチス上層部の把握していないところでさえ――進んでいたのは事実だった。
そして、アメリカでも根を張っていた白人第一主義と結びついた時・・・いや、想像するのはよそう。
あのアメリカ風邪が対日・対異人種用に用意されつつあった致死性の高い生物兵器で、遺伝的なクローンを生産する技術をもって「永遠の命」を手に入れた人々と復活した古の賢者や建国の父祖とともにアメリカという「新たなローマ」が世界を支配するなどと考えていたなんてことは――
情報部を総動員してヒトラー総統に「アメリカ風邪の病原体を手土産に亡命しようとしている病原体の製作者の一味がいる」と吹き込み、モレル医師の悪行を資料付きで提出させていなければ、カーティス・ルメイはあのメンゲレと仲良くこの技術を分け合っていたかもしれない。
資料は一部を残してエンライト艦長と潜入していたスコルツェニーに処分されてしまったが、それはそれでよかったのかもしれない。
「おしいことをした・・・と、私には思えないのですよ。ですが。」
「この技術は有益、か。確かに臓器移植を自分の細胞から作ったものでできるというのは、夢の医療だ。我々にはそれを可能にする力もある。」
嶋田は、ガーデンテラスごしにこちらに気づいた男女に会釈した。
ああ、そういえばあの青年たちはカリフォルニアに赴任する新しい大使夫妻になったのだった。
辻が養女を迎えたと聞いた時には耳を疑ったっけ。
白い髪にブラウンの瞳きれいな娘が今は美しい奥方に・・・
嶋田は思い切り目を見開いた。
辻を見る。
辻は頷いた。
「一人の人間が、何にもとらわれずに自由に生きる自由を得た。コップ女史はそれを欲したから自らとともにその計画と製法を絶ったのかもしれませんね。」
「かも、しれんな。」
嶋田はティーカップに口をつけた。
辻のことだから、打算も何もあるだろう。
あの夫妻がアメリカに行くのだって、辻の差し金かもしれない。
だが――
幼少の頃から足長おじさんとして「彼女」を支援し、ともに泣き、笑い、そして良人となりたいという人間が来た時にはとことん飲み明かし、結婚式では涙を見せた辻を、嶋田は知っていた。
「山本と一緒だが、今晩は飲みにいくか?」
嶋田は訊いた。
「ありがたい話ですが、アメリカ側と話すことがありますので。」
そうか。と嶋田は頷いた。
「親ばかだな。」
〜終〜
-
>>969-986 「リバティ・ベルが鳴る日には」
【あとがき】――というわけで「アメリカからきた幼女(乳児)」でした(爆)。
ネタですまそうと思っていたら話が長くなりすぎて・・・随分カットしましたが唐突感がある描写が多くなってしまいました。
このような妄想100%な駄文を読んでくださった皆様に感謝を申し上げます。
-
>>968-987 でした。修正しておきます。
-
>>968-988「リバティ・ベルが鳴る日には」蛇足
――1962年4月15日 大日本帝国 帝都東京
「ああ、君か。スコルツェニー。」
「どうも『艦長』。たまたま近くに寄る用事が出来ましたので寄らせていただきました。」
「相変わらず大胆不敵というか・・・公的には君の祖国とこの国は敵対未満友好未満の関係だろう?最近のエリザベス王女訪日で感情的にケリがやっとついた英国人と同レベルだったはずだ。」
「まぁ、僕も稼業を引退してから各国の連絡役をやっていますからね。同じく引退した元総統閣下の名代を仰せつかってますので気楽にやらせてもらっています。それと、ここでは僕はクレメント中佐で。」
「分かっているよ。」
ジョセフ・エンライト退役中将は笑った。
下町と呼ばれる一角に屋敷を構える彼は、パシフィック・アメリカ同盟(太平洋岸同盟)、一般的には西米と呼ばれるゆるやかな旧西海岸諸州の連合体が保有する海軍の名誉顧問的な役職を仰せつかっていた。
彼は、西海岸に脱出に成功していた妻子を呼び寄せてあの大西洋での一件以来友誼を結んだ五藤存知大将(そろそろ退役の話がでている)や辻正信というこの国のフィクサーの一人の庇護下に入っていた。
そうでないと、どこからか「リバティ・ベル計画」をかぎつけた連中に狙われるかもしれないとその頃の彼は本気で心配していたのだ。
「あの娘は・・・大きくなりましたか?」
「ああ。結婚式の時にも言っていたよなお前。」
「まぁ定型句ですよ。『ノーチラス会』にも出させていただいて、それであの娘の成長を遠くから見守ることができた。艦長たちには感謝しています。」
「『欧州一危険な男』だったか?ソ連の一件や少し前の半島危機では随分名を上げたと聞いているぞ?」
「まぁ、冒険があればそこに僕はいますからね。総統にはずいぶん好きにやらせてもらってます。」
「あのことは報告せずに?」
もちろん。と、オットー・スコルツェニーは頷いた。
彼ら二人の「娘」のような存在である辻氏の養女のことは、辻氏と彼らだけの秘密ということになっていた。
もちろん、元総統で今はドイツで悠々自適に画家生活を送っているアドルフ・ヒトラーにも秘密だった。
「今度、あのコンテナの中身の一部をニューヨークに持っていくことになっている。」
「大使に任命されたらしいですね婿殿は。」
ああ。自慢の娘婿だ。とエンライトは笑った。
「今日の『ノーチラス会』には出るか?そのために寄ってくれたのだろう?
今日はマリア夫妻の壮行会も兼ねている予定なんだが。」
ありがたいですな。とスコルツェニーはふてぶてしい表情で頷いた。
と、呼び鈴が鳴った。
二人は、はじかれたように玄関へ向かう。
ドアを開けると、エンライトの妻と、若い二人の男女がそこには立っていた。
二人とも、大使として赴任するにあたって宮中でこの国の主夫妻とお茶をしてきた帰りらしく、フォーマルな格好をしている。
「ただいま!」
白い髪の女性がはじけるような表情で言った。
「おかえり。」
「おかえり!」
二人の男は、つられて一緒に笑った。
〜完〜
-
そろそろ防衛軍がくると思うので
-
すいません。防衛軍は遅れ気味でして……。
リアルで色々と問題が多発しており、長編を書く余裕が……。
暫くはネタでご勘弁を。
-
「アステカの星」 −奇跡の谷− New Shangri-La
前に長・編スレを使用すればというご指摘と、読みにくいというお叱りを受けました。なるべくレスを多く
使わないようにと思っているうちに、つめつめの文章になってしまっていました。
今回もまだ少し空行が少ないかもしれませんが・・。長目の中編?です。
本編より少しだけ時期が前に出てしまっています。情報不案内の地域が舞台ということでご容赦ください。
earth様、「憂鬱世界」という素晴らしい舞台を用意してくださいましたこと感謝しております。
よいお年をお迎えください。
支援ssのまとめwikiに関して→支援SSその2の636は行程図の投稿に失敗しています。削除要請も十日の菊
のようですし、earth様のお手を煩わすのもと思いそのままです。もしまとめられるならその部分は削除してく
ださい。
-
「アステカの星8」 −奇跡の谷− New Shangri-La PART1 Appalachian Trail
1943年5月6日 テネシー州北東部アパラチア山脈西麓キングストン近郊
テネシー州のキングストンといえばアパラチア山脈の西山麓地域にあたり傾斜地の多い山間部である。数日前か
ら降り続いた雨がようやくあがり、例年より遅いが春の陽光でようやく成長を始めた広葉樹の若葉を照らしている。
「本当に春が遅かったけど、でもやっぱり春は来たわよ。そんなにあわてて出ていかなくてもいいのに。」ステイ
シー先生は昨夜納得した話をまた持ち出した。
「いや、一月近くもいたからな。家の補修も終わったし、当面の食べ物の備蓄も出来た。」ジョーも昨日と同じよ
うな理屈で返す。旅で離別になれたジョーは繰り返しは別れの挨拶みたいなものだと感じていた。
「カリフォルニアへ帰るの。」ステイシー先生は少し寂しげに聞いた。
「そうだな。別に好きこのんで危険な場所にいたいわけじゃないからな。出発するなら今だ。来るときより状況は
更に悪化しているだろうから、食糧を得やすい夏の時期を無駄にしたくない。」これもジョーが昨夜語ったことだ。
「当面、ここは安全そうよ。」それでもステイシー先生は粘る。
「疎開者と住民の抗争が原因で十日前にキングストンの町の半分が焼け落ちてるんですよ。東の空が赤く染まって
いたのが家の二階かでも見えたでしょう。」ロジャーは、そう反論すると家の裏手に急ぎ足でまわった。
「こんな山奥には誰もこないし。第一、道を知っていてもこの家に来るのは難しいわ。」ステイシー先生はロジャ
ーの後ろ姿に怒鳴った。
「というハシからジャズがきたぜ。」ジョーが顎で森の小径の方を示した。
森の中から馬に乗り麦わら帽子を被った四十ばかりの陽に焼けた男が現れた。ここに到着して三日目の昼にこの
男が家の回りをうろついているのに気づいた時は、家の中に籠もってやり過ごそうした。ところが、窓から男の顔
を見たステイシー先生は突然家から駈けだしてびっくりしている男に声をかけた。
男はジャズ・ボーレンといい2マイルばかり山を下ったところに彼を含めた妻子四人で住んでいる。大恐慌時に
失業して行き詰まり、自殺しようと山中を彷徨していたジャズをステイシー先生の両親が見つけて近所の廃屋を世
話して家族で住めるようにしたという。
それ以来ジャズは小さな自家用農園を耕しながら、車に田舎では珍しい加工食品や雑貨、安物の衣服を車に積
んで近所の農家相手の行商をしている。
ステイシー先生は母親が亡くなった時に数ヶ月に一回でいいから家の見回りを頼んだのを律儀に実行していたと
いう。この男の紹介と手助けのおかげでもあり納得いく相場で備蓄用の穀物、乾燥肉やステイシー先生が育てると
いう菜園用の種子などを入手できた。
-
「なあ、まだ、アスピリンが余っていたら分けてくれないか。テンシー産密造バーボン4本と交換だ。」ボーレン
はジョーの顔を見るなり挨拶に抜きで声をかけた。ジョーがテネシーに来る途中でミネアポリスで奮発して大量に
仕入れたものにアスピリンがある。かさばらず需要があるという算段は当たり、アメリカ風邪への恐れから大概の
農家は欲しがった。
「いいだろう。四十錠渡そう。でも、今日でお別れだ。」ジョーはリュックから錠剤を取り出しながら数えだした。
「そうか、ここはいいとこだぜ。でも、あんた見たいな流れ者には退屈だろうな。でもよ、今のアメリカじゃ退屈
できるって幸せだと思わないか。」ボーレンは馬を下りながらジョーに言った。
「退屈すると思い出さなくてもいいことも思い出す。」ジョーは両手をポケットに入れた。
「そうか、元気でな。肝心の乗馬の方は大丈夫かい。まあ、あの馬に乗れなかったらこの世に乗れる馬はいないがな。」
ジャズは右手を差し出した。ジョーも躊躇ってからポケットから右手を差し出して軽く握手した。
ジャズは元来、目端の利く男らしく戦争が始まったと聞くと近所の農家を回って数頭の馬を入手した。ガソリン
が統制されると考えたのだ。その数時間後には何かの災厄が東海岸を襲ったという一報が入り、一週間後には馬を売
ってくれるような手合いはいなくなった。ジャズは手持ちの馬のうち一頭の去勢馬を銀貨数十枚とトラック2台分
のトウモロコシで交換したそうだ。
ジャズが手元に残したうちの2頭をお礼にと、ステイシー先生が後生大事に持ってきた銀貨でジャズから購入して
ジョー達に贈った。ジャズは只でいいと言ったがステイシー先生に押し切られ相場からすれば格安だが対価を受け
取らされた。
「ジョー、準備できたぜ。」ロジャーが旅支度ができた二頭のクォータホース種の去勢馬を引いてきた。ジョーは
アスピリンとバーボンを交換して、ロジャーはステイシー先生に別れの挨拶をする。ジョーとロジャーはさっそう
と馬に乗った。ただ、ジョーでさえ内心はほっとしていた。ステイシー先生のきつい指導のもと昨日までに何回落
馬したことか。
「じゃあな。」ジョーがウエスタンを気取るように軽く帽子に手をやり軽い口調で言った。
「また会えるわよね。それからわたしからの餞別よ。」ステイシー先生は隠し持っていたサザンカンフォートのボ
トルをジョーに渡した。
「オレはまた会える気がする。」ジョーは軽く微笑んだ。ボーレンと並んだステイシー先生はいつまでも手を振っ
ていた。
「取りあえず何処に行く?」数日前から偵察していた山道に入ったところでロジャーが聞いた。
「まず、ここからはなるべく人に出会わないようにアパラチア山脈に沿って北を目指す。その先は様子を見ながらだ。」
結局、この日は山道に沿って10マイルばかり進む。それ以上は尻の痛みに耐えられなかったのだ。ただ、二三
日もすると次第にこつがわかったのか乗馬に慣れて人家を避けて迂回しながらも直線で15から20マイルほどは進
めるようになった。
-
保存食糧節約の為もあって、一日に一時間程度は猟をしてウサギや鳥を撃った。ステイシー先生に実家の地下室
に厳重に保管されていた彼女の父親が収集していたという小口径の猟銃と散弾銃を、無理に持たせれたことが意外に
役だった。
雨に降られて一日テントで凌ぐ日があり、長くなった日差しに苦しめられる日があり、碌な飼料をやれないので
馬に負担をかけないようにできるだけゆっくり進み、一週間目でバージニア州へと入った。
「中西部はだだっぴろい。行けども行けども地平線ばかり。ここじゃ行けども行けども山ばかりだ。神様も手抜き
せずに適当に散らばらしたらどうだい。それにしても、昨日の午後から民家一つも見ないし、道路一本も横切らな
いとはどんな僻地だよ。」日差しと人目を避けて山の中腹の狭い山道を進んでいるとロジャーは何度目かの同じよ
うな愚痴をこぼした。
「この先にも誰かいる。馬を後ろに。」ジョー自身が馬を苦労しながら来た方向へ向けながら言った。
「少し高いところに行って見よう。」ジョーは馬を下りるとちょっとした斜面を馬の手綱を引いて駆け上る。あわ
ててロジャーが続く。
二人が馬をようやく尾根の反対斜面に隠すと、下の山道をジョー達が進もうとしていた方向から谷道を数人の軍
服姿の男が走ってきて左右の斜面に分かれて木の陰に隠れた。尾根から山道までは100ヤードほどもあり木々が視
界を遮る。それでも男達は軍服は着ているが、兵士とはどことなく挙動が異なっているようだった。
暫くすると、軍服の男達がやってきた方向から、山高帽みたいな帽子を被りポンチョをまとった二人連れが荷物
を背に積んだ一頭の馬を引きながら、自分たちも背中に結構な荷物を背負ってやってきた。
男達は道ばたから飛び出すとが銃を構えて二人連れを威嚇した。二人は馬をかばうように馬の左右にたった。何
か言い合っているが声は聞こえない。軍服の男の一人が背の高い方のポンチョ姿の人物に突然発砲した。女の悲鳴
が聞こえてくる。
「追いはぎか?」ロジャーが尋ねる。
「ちょっと様子がちがうな。」ジョーが暫くして答えた。倒れたポンチョ姿に、多分女らしいポンチョ姿の人物が
すがりついている。その女に男たちが何事か詰問しているらしい。ジョーは馬から銃を持ってくると、自分は猟銃
を持ち、ロジャーにには散弾銃を渡した。
「どうするんだ。助けてやるのか。しかし、こんな銃で立ち向かえるのか。」鳥打ち用の小口径散弾銃を持たされた
ロジャーがあきれたように聞く。
「助ける気がなくても巻き込まれてしまえば、降りかかる火の粉は払いのける必要があるさ。それに、もっとこま
しな銃が手に入るしな。」
「おいおい近所に銃砲店でもあるっていうのか。それに降りかかる火の粉ってなんのことだい。」
「ここで何してる。」突然、M1903小銃を持った二人の男が木の陰から出てきた。片方の男の上着は陸軍兵士の軍
服だがズボンは作業着のうえに、二人とも中年で正式の兵士ではないようだ。
-
「猟です。」ジョーは猟銃の銃身を右手で持ったまま手をあげた。
「銃をこちらに投げろ。」ズボンが作業着の男が銃をジョーに銃で狙いをつけて言った。
ジョーはロジャーの持っていた散弾銃の銃床を左手で掴んだ。そして、左右の手に持った銃を電光石火の早業で二
人の男に投げつけた。猟銃は銃床で作業着ズボンの男の額を割り、そのまま男は上向きになって昏倒した。散弾銃
の銃床は、もう一人の男のみぞおちにめり込んで男はうずくまるように前に倒れた。
「ちゃんと投げたぜ。」ジョーはつまらなそうに言った。
「どうするこいつら。」倒れた男達の方へ駆け寄りながらロジャーが興奮気味に言う。
「縛っとけ。」ジョーは下の山道の様子を見ながら返事した。
「それでいいのかい?」意外そうにロジャーが言う。
「殺したいのか。」ジョーの言葉にロジャーは大きく頭を左右に振った。
ロジャーは素早く馬に積んでいたロープで男達を縛り上げて、ナイフで短く切ったロープで猿ぐつわをかませた。
「こいつトンだ色男だぜ。でっかい手鏡持ってら。」男を縛りながらロジャーが言う。
「そこのピークの上で見張ってて、下の山道に誰かがきたら、鏡で物騒なお仲間に合図してたんだよ。」
「こらからどうするんだ。」ロジャーが男の持っていたM1903を点検しながら言った。
「そうだな。運試しだな。俺たちと、あの女の。」ジョーは落ちていた散弾銃を拾うとゆっくり狙いをつけた。
「女がこちらの方へ逃げてきたら、判断力があるってことさ。」ジョーは散弾銃を撃った。
下の山道にいる男達の真ん中に鳥が落ちてきた。男達の注意が鳥に集中した。女は脱兎のごとく斜面をジョーた
ちの方に向かって登りだした。
「ダスティン、女がそっちへ逃げた捕まえろ。抵抗したら撃て。ただし殺すな。」リーダー格らしい男が怒鳴る。
兵士達は女を追いかけてばらばらに斜面を駆け上がってくる。
女が尾根にたどり着く。
「暫く隠れていろ。やばそうだったら逃げろ。」ジョーは女に素早く言う。
最初の男が尾根に到着した。伏せていたジョーはM1903の銃床で男の腹を抉った。二人目の男もそうやって始末
すると、ジョーはM1903をつづけさまに三発発砲した。三人の兵士が肩や腕を打ち抜かれてうずくまる。
「逃げろ。」ロジャーが叫ぶ。男達は一斉に斜面を駆け下りる。撃たれた男達もよろめきながら逃げていく。やが
て、男隊は山道をもときた方向へ走り去った。
「出てこいよ。」ジョーが声をかけた。
小柄な女が茂みから現れた。黒髪、黒い瞳、顔立ちは一見アングロサクソン系だが、小さな鼻や頬の様子からイン
ディアンの血が混じっているようだった。まだ、二十歳そこそこだろう。
-
「早く逃げないと、あいつら仲間を呼んでくるわ。いっしょに来て。」女はロジャーの乗っていた馬の手綱を引き
ながら斜面を下っていった。
「おい、オレの馬をどするんだ。話ぐらい聞かせろ。」ロジャーはM1903を持ってあわてて追いかける。
「話は安全な場所に行ってからよ。」女は振り向かずに大声で言った。
馬を連れたジョーが山道にもどると。ロジャーは女の指示で女と撃たれた同行者を荷物を馬の背に載せていた。
「あんたの馬には仲間を乗せて。」撃たれた同行者は、銀髪で日に焼けた精悍な感じのする五十歳前後の男だった。
女は男の腹に着ていたポンチョを押し当てて男を立たせた。ロジャーが手助けして男を馬に乗せる。
「さあ、行くわよ。」
「どこへ。」
女はロジャーの質問に答えず男を乗せた馬の手綱を慣れた手つきで引いて、山道から更に谷底の方へ馬を引いて下
りだした。
その後をジョーとロジャーが必死で追いかける。谷底にくると上流に向かって女は小走りで進む。三十分くらい
走ると、木が覆い被さりちょっと見逃すような谷に流れ込む小さな沢に入った。十分ほど走るとまたより小さな沢
に入る。
「ここどこなんだよ。」ロジャーが情けなさそうに呟く。
「ちょっと休みましょう。」女はようやく立ち止まった。
「何処へ行く。」ジョーが低い声で聞いた。
「助けてくれたから私の村に案内する。」女は軽い口調で言った。
「オレにはていのいい護衛のような気がするがな。しかし、早くしないと連れがやばいぜ。」ロジャーがへたばっ
たような口調で言った。
「そうかもね。あの連中は命なんてなんとも思ってなしね。その連中を怒らせるなんてバカよ。」女は年に似合わ
ずさめた口調である。
「口の利き方が大事だな。」ロジャーも追い打ちをかけるように言う。
「あなたバカよ。なんで相手を侮辱するようなこと言うのよ。」女は撃たれて男に傷を確かめながら言った。
「あの連中とやらは山賊かい。」ジョーが馬からM1903を取り出しながら言った。
「そんなものよ。自分達じゃ、民兵とか言ってるけどね。適当な道路で検問所をつくって通行料を取ったり、勝手
に警備料だといって、集落から物資を徴発してるわ。よそ者や難民が通ろうものなら因縁をつけて物を巻き上げる。
スパイだと決めつけて処刑するって連中よ。脱走兵や、この当たりの食い詰め者が徒党を組んでるの。」女ははっ
きりした口調で説明する。
ジョーがM1903を構えた。女は立ち上がって沢の上流を二三分じっと眺めていた。
「大丈夫、仲間よ。でも、よくわかったわね。」女は感心したように言う。
木々が覆い被さり薄暗くなった小さな沢の奥から銃を持って三人の男が現れた。最後尾の男はロバを連れている。
-
「クローイ、この連中は?」オーバーオールを着込んだ三十前後の農夫のような男が怪訝そうに聞いた。
「エイプリル峠を越えたところで民兵の一隊に見つかって襲撃されたの。まさかあんな山奥まで出張ってるとは思
いもしなかったのがいけなかったのね。ちょうど居合わせたこの人たちが助けてくれたの。」クローイと呼ばれた
女は相手を動揺させないためか事務的に言った。
「民兵の一隊ってどのくらいいたんだ。」それでもオーバーオールの男は心配気に聞いた。
「三十人くらいかな。」クローイと呼ばれた女が答えた。
「それを二人でか?」後ろの方にいた、まだ二十歳くらいの男が眉唾そうに言った。
「そんなに居なかったぜ。せいぜい二十人だ。」ジョーが返答する。
「バート、ともかく詳しい話は後よ。お客さんが怪我してるから早く運んで。」クローイという女は指示をする。
男達はあたりの木を山刀で切り出すと、女のポンチョと組み合わせて即席の担架を作って、苦しそうに腹を押さえ
ている男を寝かせた。
「あなた達は自分の馬に乗って。でも、悪いけどこれもしてね。」クローイはジョーとロジャーに目隠しをすると
二人を馬に乗せた。
「レックスもグズグズしないで荷物をロバに乗せて。」クローイは命令口調で言った。
三時間ばかり登ったり降りたりを繰り返して馬は進む。時々、小枝が顔に当たるが避けようがない。途中から小
雨が降ってきて、鳥の声も絶えてしまった。
「今年は雨が多いわね。」ずっと黙っていたクローイが馬の手綱を引きながら初めてしゃべった。
「クローイさん、あんた連れの男が撃たれた時に悲鳴を上げたがあれはわざとだろう。」ジョーが尋ねた。
「何故、そう思うの。」
「連れが撃たれて冷静に見てる女なら、相手は警戒、いや不気味に思って目を離さないだろうからな。」
「いったいどこに行くんだい。目隠しを取ったら地獄の七層目ってことはないよな。」ロジャーが情けない声で言う。
「いいわよ、馬を下りて。目隠しを取って上げる。」馬がようやく歩みを止めるとクローイが言った。
「ヒューーーー、たまげたぜ。」幻想的な風景にロジャーは感嘆した。
四方を深い山に囲まれて森に覆われたこぢんまりとした盆地。先ほどの雨が上がり、夕日が見事な虹をその上にか
けている。
深い森の所々に小さな家々が見える。これらの家は四方の山から見れば森に隠されて見えないだろう。
森の隙間の少しばかりの空き地は耕作地として利用されているようだ。お伽の国のような光景である。
「ようこそテラビシアへ」クローイは微笑んで言った。
ロジャーは森の風景をバックにしたクローイの黒髪と白い肌、赤い唇を見て「白雪姫」みたいだなと思った。
-
「アステカの星9」 −奇跡の谷− New Shangri-La PART2 Terabithia
1943年5月14日 ヴァージニア・ウエストヴァージニア州境付近アパラチア山脈中のどこか。
「ロジャー、朝飯だ。」ジョーがお盆にクルミとレーズンの渦巻きパンとミルク、エンドウ豆のベーコン添えとい
った料理二人分がのっているテーブルで食事をしている。
「ここは?あ、そうか。嫌な夢を見た。」ロジャーは壁際に置かれた二段ベットの上段からジョーに言った。
「さっき、昨日の男が食事を持ってきた。すぐここの長老が来るそうだから早いとこ食べてしましな。」
昨夜から、あてがわれている部屋というか、監禁されている部屋は、窓に鉄格子が入っていることと、ここがア
パラチアの山奥ということを差し引けば素晴らしい部屋である。清潔な綿入り枕とシーツのベット、白い壁紙、水
色のカーテン、ちょっと裕福な学生寮の部屋並と言っていいだろう。
昨夜は食堂のような場所に連れていかれて、ハムエッグや茹ポテトといった食事を振る舞われた後で、二時間ほ
ど別々の部屋で身分素性を尋ねられた。ジョーは聞かれた事には正直に答えた。隠す必要のない時には正直に言っ
ておくことが身のためであると、放浪者の先輩であるロジャーが言っていたからである。尋問が終わると食堂の二階
にある部屋に監禁された。
ロジャーが部屋に入ってきたのはそれからまた1時間あとだった。ロジャーを尋問したのは昼間、会ったレックス
という男だったが、警察顔負けの尋問だったですっかりくたびれ果てていた。
ロジャーの食事が済むか済まないうちに長老が部屋に入ってきた。
レックスが怖い顔をして拳銃を腰に下げて続いて入ってくる。その後に一見してインディアン系とわかる初老の男、
最後がクローイだった。
「私はここの責任者をしているゴドフリー・ドナファーというジジイだ。みんなは長老と呼んでいるがな。ジョー
にロジャー。そう呼んでかまわんかな。」七十の坂に達そうかという大柄な男が尊大に言う。
「いいぜ。」ジョーは軽く流した。
「それでは、ジョー、ロジャー。孫娘のクローイの危難を救ってくれたことに感謝する。」ドナファーの言い方は
尊大でも真の感謝が感じ取られた。
「なあ、昨夜は色々と聞かれたから少しこっちから聞いてもかまないか。」ジョーがつけ込むように言った。
「どうぞ。」今度はドナファーが軽く受け流す。
「ここは地図にのっているような村じゃないな。」ジョーの質問はいつも簡潔だ。
「そう、のっておらん。我々がテラビシアと呼んでおる人の知らない村だ。」ドナファーは自慢げである。
「ここはアメリカかい?」ロジャーが横から割り込んできた。
「アメリカ合衆国、今もあるとすればだが。その一部には違いない。ここは大不況の時代に行く当てのなくなった
失業者が集まってできた村だ。ここにいるチェロキー族のタヒクパス氏の好意で彼らの聖地の一部に住まわせても
らっておる。タヒクパス氏は本物の長老じゃぞ。」そう言うドナファーの表情は上々である。
-
「タヒクパスさん、見返りはなんだい。」ジョーの問にドナファーとタヒクパスが顔を見合わせた。
「いきなりかね。地代を貰っている。ドナファー氏らの援助でアメリカ風の家も建ててもらった。」ドナファーの
顔色を察したタヒクパスは笑顔で言った。
「地代と言っても州政府に納める税金の何分の一だがね。」ドナファーが間髪を入れずに言う。
「去年からは食糧の一部渡しにして貰った。」タヒクパスがドナファーの横顔を見ながら言った。
「税金天国みたいなとこか。しかし、税金を払わないとその恩恵もない。」ジョーはたたみかけるように言う。
「政府に納める税金で何の恩恵があった。」昨日、沢で会いジョー達を尋問した男が吐き捨てるように言った。
「まあ、そういう社会もあるがね。ここは元警官や元消防士、元教師もいれば、元大工だの各種の元職人も、それ
から元コックもいる。それぞれが自分の職業を生かして生活している。それらの技能は全てみんなのために無料で
奉仕するのがここの税金だよ。その対価は村で生産した食糧、衣料だ。ただ、人数がたりないものは・・。例えば
家の棟上げとか、自衛団は義務として共同でしておる。それがここの税金だ。」ドナファーが丁寧に微笑を浮かべ
ながら言った。
「アーミッシュ(プロテスタント系キリスト教徒の一派、機械文明を拒否して移民当時の生活を行う)みたいなも
のか。」ロジャーが少し考えて聞いた。
「いいや、我々の宗教は個人的に自由だ。主義主張でここの暮らしを選択したわけではない。電気も使うさ。ただ
いくつかの発電機が故障で今は公共の建物だけ電気を通しているがね。」
「ランプも嫌いじゃないぜ。」ジョーは壁際のランプを見上げながら言った。
「じゃ、共産主義だ。」すっかり自分の世界に入ってしまったロジャーが唐突に言った。
「それも違うな。我々は私有財産についての制限などしていない。土地も公有ではない。地代を払っているといっ
ただろう。その額に応じて土地の使用面積を決めておる。」ドナファーは心外とばかりに興奮気味に言う。
「この山奥での生活に必要な技能労働をそれぞれが相応の対価で提供しあう村かい。ただ、存在が知られれば税務
署が飛んでくるから絶対秘密の村だ。」ジョーが助け船を出した。
「そうだ。それが的確な答えだ。」ドナファーは落ち着いて答えた。
「ここはアメリカのいかなる公権力が及ばない場所だと理解でいいんだな。」ジョーは念を押すように言う。
「そうだ、テラビシア独自の法に従ってもらう。それができない。あるいは嫌なら君らにはそれ相応の対応を取ら
ねばならない。そんな、ことになればクローイが悲しむだろから是非避けて欲しい。」ドナファーは手を組んで言
った。
「ずばり聞くぜ。ここから出られのか。」ジョーはドナファーの機嫌を見て聞いた。
「暫くここにいてもらう。信用できる人間かどうか判断できるまでは出て行ってもらては困る。」ドナファーの言
葉には刺があった。殺してでも出て行くことは阻止するいうことらしいとジョーは理解した。
-
「大丈夫だぜ。俺たちはここが何処にあるか知らない。」ロジャーが脳天気に言う。
「どこの近くかはわかっているだろう。」今まで黙っていたレックスが大きな声で言う。
「ずっとこの部屋に閉じ込めておくのか。」ジョーがドナファーに向かって聞いた。
「いいや、昼は自由に出歩いてくれ。日が暮れたらここに戻ってくること。夜の間は鍵をかけさせてもらう。それ
に自分の食費は稼いで貰わんとな。」ドナファーの言葉には殺気がなくなっていた。
「おいおい、ここに拘留するのにテメエで食い扶持を稼げかよ。」ロジャーが抗議する。
「畑仕事の手伝いや家の修理なんでもしてくれ。君たちは馬を持っているから仕事はすぐ見つかるだろう。ただ、
孫娘の件があるからここの部屋代はわたしのおごりだ。ついでに一週間分の食事もおごる。」ドナファーは最初の
尊大さを取り戻してきっぱり言った。
この後、しばらく雑談をしてドナファー以下の一行はクローイとレックスを残して引き上げた。
「テラビシアを案内するわ。」クローイは微笑んで言った。
「そうしてくれると助かる。仕事をしろといっても右も左もわからないからな。」ロジャーがジョーとクローイの
間に割り込んできて言った。
「テラビシアって妙な名前だな。インディアンの言葉か。」ジョーが聞いた。
「いいえ、もとはこの当たり一帯はインバって呼ばれる地域だったから、インバ村って名前だったの。でも、わた
しが気まぐれにテラビシアって呼んでたらお祖父さんも気に入って。」クローイが恥ずかしそうに言う。
クローイはさして広くはないが、見通しの悪い村の主要部を二時間ほどかけて案内してくれた。行く先々では、二
人を村人に紹介し、二人にはその村人がしている仕事を説明した。
「さあ、共同食堂に帰ってきたわ。村の人は全員ここで食事を摂るるか、料理を持って帰るのよ。」クローイは最
後にジョー達が押し込められた大きな建物の一階にある食堂の説明をした。昼にはまだ少し早い時間だったが、食
堂の席はすでに四半分ほどは埋まっていた。
「自分の家じゃ、料理を作らないのか?」ロジャーがクローイに聞いた。
「食材を各家に分割して渡すより、まとめて調理した方が無駄が少ないだろう。ここでの生活は、無駄は出来ない
んだよ。」おもしろくないといった顔で、一行の後を歩いていたレックスが言う。
「それじゃ、仕事の希望が決まったら教えてね。」クローイはジョー達二人に手を振った。
「どこに行けば会えるんだい。」ロジャーが名残惜しそうに聞いた。
「何言っての。村を案内したときに、ここがお祖父さんの家って言ったでしょう。そこに住んでいるのに決まって
るでしょう。」クローイーはクスリと笑った。
つづきは「中・長編SS投稿スレ その3」へ
|
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板