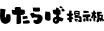レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
おしゃべりルーム
-
ミイラと狂乱の場
なんかすごいタイトルですが、昨日上野の文化会館にベルガモ・ドニゼッティ劇場のオペラ『ルチア』を観るついでに、同じ上野の科学博物館でエジプトのミイラ展を観たので、その二つについて。感想を聞かせてほしいという友人がいるので、ここに書きます。
ミイラ展は、3Dシアターの映像がすばらしいというので期待して行きました。まず入れ替え制のシアターを経てから展示場にいけるという作りで、3Dメガネをもらってわくわく、アトラクション・パークの人気シミュレーションを待ってる感じです。保存状態のいいミイラの包帯をとらず、CTスキャンに入れるという画期的な話で、その体の中に3D映像で入っていくというのですが、結果的に、あまり感動しませんでした。昔初めて大英博物館に行ったとき、パリのルーブルよりもミイラの展示が多く、その即物的な敬虔さのなさ、に感じ入りました。ヨーロッパでエジプトコレクションを見るたび、帝国主義とか盗掘とか、無邪気なモラルのなさに見てる方まで後ろめたくなります。
日本では昔ツタンカーメンの黄金の棺の展示を見ました。ミイラの干からびたイメージとは無縁の輝きで、罪悪感はなかったです。3Dで、ミイラの体の中に侵入していく感じもあるんですが、普通の特撮映画みたいで、『ミクロの決死圏』(古い!)の感じです。
ツタンカーメンという名が、すばらしい響きを持ってたのに対して、このミイラさんの名は、「ネスペルエンネブウ」といって、コピーライターが提出したとしたらすぐ却下されそうな名です。コピーとしていいのは、展覧会の副題の「ザ・インサイド・ストーリー」ですね。
実際の棺の外側は、色鮮やかですばらしく、しかしさっき親しく中身に侵入した記憶に比べるとフラストレーションが起こります。展示品では、両側がハヤブサの頭と人間の手である細長い香炉が気に入りました。後、ミイラは内臓はいったん取り出されて塩を振りかけられて乾燥させられ、また布にくるまれて体に戻されるんですが、心臓だけはそのまま体内に残したままなんですね。脳はほとんどゴミみたいに鼻から掻き出されて捨てられます。脳と心臓の運命の違いはおおきい。しかも、死後の世界の生前の善悪審判で、心臓が、生前の悪行を暴いて不利な証言をしないように、スカラベ型の護符をおいておきます。心臓に裏切られるかもしれないとは! でも心臓を残さないといけないというのは、心臓は元々お目付け役で、体の中で、来世と結びついているスパイみたいな特殊器官なのでしょうか。悪いことをするとき、心臓がドキドキするのは、警告か、記録してるからなのだと思っていたのでしょうか。第一、生前悪いことをしても、死後、心臓に護符を置いて口を封じさえすればOKというご都合主義も可笑しいです。生きてるうちに罪障消滅のシステムがなかったんですね。カトリックなら、告解して赦してもらうとか、免罪符をもらうとか、死んだ後、残った人に煉獄から出してもらえるよう祈ってもらうとか、何らかの「罪のあがない」の仕組みがあります。そして、死後の善悪の審判というのは、まさにエジプトのような地中海文明の影響で、ヨーロッパ固有ではないのですが、本家のエジプトでは、罪をあがなわなくても、口をぬぐって隠していればOKだったなんて。
第2会場の、CTスキャンからミイラの健康状態の診断をしてるのはおもしろいでした。日本人の骨とかを展示して比較しながら、大英博物館と別の所見をしてるのが愉快です。たとえば、大英博物館が歯の磨耗と言ってるのを虫歯と診断したり。
そんなわけで、ミイラ展は期待はずれだったのですが、常設展を見て、牛の胃腸とライオンの胃腸の比較とか見て楽しめました。最近パリの自然史博物館のドラゴン展など何度か行ってるので、目新しいものは発見できませんでしたが、干支シリーズ2007があって、触れるイノシシの剥製があり毛の感触を確かめたり、ウリ坊も見たり、賢そうなハチ公の剥製を見たことが、日本的です。外には、30メーターの実物大シロナガスジクジラのジャンピングのオブジェがあり、それが一番感動的でした。
それから文化会館のオペラです。「ランメルモールのルチア」という言葉を聴いただけで、どきどきします。観るのは初めて、マリア・カラスの全曲のLPを持ってましたが、CDは持ってないので、もう長いこと聴いてません。そのカラスが死んだ頃に生まれたデジレ・カントーレ(パレルモ出身ですが、デジレはフランス語名ですからフランス人の血を引いてるかも)が29歳で絶頂期にあり、この種のプリマドンナ・オペラを聴くには最高という贅沢です。30年以上前、日本でカラスのコンサートに行きました。最後、舞台に近づいて握手してもらったら、汗と香水の臭いが強烈だったことを覚えています。でもすでに晩年で、ヴィルチュオジテを楽しめるというより、オーラを拝みに行った感じです。
狂乱の場はLPで何度も聴いたのでそらで覚えてますが、ルチアが死んだ後の最後の場は全然記憶になく、今回エドガルドのアリアに感心しました。スペイン人テノールのアントニア・ガンディアです。デジレ・カントーレは最初からすばらしく、狂乱の場の期待がますます膨らみます。コロラトウーラ・ソプラノですが、全ての音域が豊かでたっぷりしていて、テクニック的には私には難しいところがない、表現だけが問題とインタヴューに答えているように、安心して堪能できます。
幕間にグラスハーモニカのおじさんが注入器で32のグラスの水量をチューナーを使って調節してるのを見物しました。グラスの縁を触っただけで音がでるような手と指が洗い上げて真っ白なのが印象的です。
それで、いよいよ狂乱の場です。会場が興奮していくのが分かります。これって、要するに、スポーツ観戦なんですね。トリプルアクセルの成功が約束されてるフィギュアスケートを見るみたいです。すばらしい着地技を約束されてる鉄棒演技とか。超絶技巧を商品にして成り立ってる世界です。イタリアオペラのスターシステムの典型例です。フランスのバロックオペラやイタリアの前期バロックオペラはテーマパークの楽しみで、充実したコーラスとか、祝祭性とか、ふんだんに踊りがあって、イメージとしてはこちらも祭りに参加している気になります。でもプリマドンナオペラって、一人のヒロインと、彼女の鑑賞者=消費者たちという構図です。その意味では、一人の男役トップのために全視線が集められる宝塚とちょっと似てますが、宝塚は別に超絶技巧を求められているわけじゃなくファンの熱気が一緒になって作るスターの存在そのもののオーラなので、見所が集中しているわけではありません。
バロックオペラから、バレーが独立して、バレーの方も超絶技巧のスターシステムになっていきました。たとえば白鳥の湖で黒鳥の32回転ピルエットがいかに安定していて美しいかというのが求められたり、アラベスクで両脚が180度以上開いたり・・
そして、バレーを失ったオペラのほうも、テクニックのためのテクニックへ進化していくのですね。声が楽器と共に高性能を競っていきます。
そういうプリマドンナオペラとしてのルチアですが、デジレ・カントーレはすばらしいでした。はじめは、なんだか表情がヒラリー・クリントンみたいで、悲劇のヒロインっぽく見えなかったのですが、さすがに狂乱の場にくると、もう彼女のこれしかないというくらい、圧倒的な存在感でした。実際に見たことはないけれど、狂乱の場はマリア・カラスのドラマチックでパセティックな顔と結びついていて、寝衣を血に染めて短剣を手に持って現れるイメージだったのですが、緋色の布を白い階段に広げ引きずりながら降りてくるカントーレは痛々しくて、その劇的表現は説得力がありました。しかし、会場の全聴衆が固唾を呑んで待っているのは、人間技と思えない高音域のヴィルチュオジテの部分であり、芸術とスポーツが遊離してる、不思議な感覚です。カントーレは、その人が出てきてそこにいるだけでいいという、確立したスターではありません。見せ所のトリプルアクセルで転倒したら、彼女にもオペラ全部にも意味がなくなる、そんな危うさ、がちょっと倒錯的です。バロックオペラとあまりにも違う方向に進化してきたなあとあらためて感慨深いでした。
これからカントーレのプリマドンナ・オペラをちょくちょく観にいこうと、楽しみです。同時に、こういうオペラのイメージでラモーのバロックオペラを観る人がいるかもしれないと思うとあせります。ラモーのオペラは音楽的にはもっと難しいのですが、概してフランスオペラは、スターという「人につく」んじゃなくてバレー団やコーラスやからくりをかかえたオペラ座という「場所につく」形で発展してきたんですね。スポーツとしても、わいわい型のサーカス風かしら。ルチア頭より歌舞伎頭で観てほしいです。
|
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板