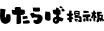レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
おしゃべりルーム
-
利他について
1月9日付けの記事を読んで、中島岳志が若い頃にインドで体験した話を思い出しました。それは、やはり手助けの場面なのですが、竹下さんの場合とは立場が逆で、しかも当事者どうしが違和感を抱いた特異な体験談でした。
中島岳志をご存じでしょうか。私は、『ヒンドゥー・ナショナリズム』(2002)を読んで以来、当人の著作を追いつづけています。(ちなみに、竹下さんの愛読者になったのは、遅ればせながら、『無神論』(2010)に出会ってからでした。)
中島は、大学院時代にヒンドゥー・ナショナリズムのフィールドワークのためにインドに長期滞在していました。体験談というのは、彼が大量の調査資料を詰め込んだトランクを手にして、鉄道駅のやや長めの階段を登ろうとしていたときのことです。重さに苦労しながら登っていると、通りかかった現地の人が無言で手を貸してくれたそうです。登り切って、助かったおもいを感謝の言葉にして伝えると、その人は表情を曇らせ憮然として足早にその場を立ち去ってしまったという話。中島本人は、しばらくはそうなった事情をうまく理解できずにいたようです。
やがて中島が納得したのは、熱心なヒンドゥー教徒は、日常生活の中で「ダルマ:宇宙全体の法則であり、そのなかで人が果たすべき役割」を体得し自然に実践できるように暮らしているということでした。そういう人は、たまたま出会った人間でも隣人と受けとめ、苦労や不自由に気づけば、思わず自動的に体が動くようになっている。中島が出会った人物も、当然の役割を自然に果たしただけで、返礼を求めての手助けではなかった。それは特別なおもいやものをやりとりする交換関係とは無縁な、ありふれた相互扶助の関係だったのだ。そういう人間関係を大切にしている共同社会があるのだ、と中島岳志は理解しているようです。
竹下さんは、「彼らは私にメルシ―とさえ言わなかったのに、私はまったくお礼の言葉を期待していなかった」「少し困っていた彼らのそばに居合わせた偶然が、まるでプレゼントのように感じられた」と書いていました。相手はヒンドゥー教徒ではなくムスリムだったようですが、竹下さんがためらいもなく、自然にさりげない対応ができる姿勢を身につけていたため、相手もその場ではあたりまえのことをしてもらえたのだという受けとめ方になっていたのかもしれません。その場のやりとりを振り返って「プレゼント」のように感じられたのは、意図したわけでもないのに自然に相互扶助の関係にめぐまれたということだったのかもしれません。
中島岳志は、一昨年あたりから「利他」を捉え直す本をたてつづけに世に出しています。そのテーマを所属の東京工業大学で共同研究に取り上げていて、とりあえずの成果の妥当性を確認する意図があるようです。
中島たちの考える利他は、同情や共感とは異なったところに動機があるようです。同情や共感が動機となる利他には、大なり小なり利己的なはたらきがあると考えられています。同情や共感を寄せられる側にも、同情や共感を抱かれるありかたでないと助けてもらえないというプレッシャーが生ずる場合がある。環境対策を掲げる企業、途上国の開発援助、慈善事業を支援する企業や個人、世の中や他人のためになる仕事に励むという意志、思いやりのある人になろうとか好かれる人になろういう要請、などはどこかに自分(たち)のためという動機を潜ませている。けれども、人間が抑圧のない共同性を失わないでいるためには相互依存や相互扶助の関係が欠かせない。というわけで、利己的に傾かない利他のありかたを、文学、宗教、落語、料理、商業、社会内外の交換関係の中に見いだそうとしているようです。今のところ中島岳志が考えている利他は、偶然に立ち会った場面で、思いがけずとっさに行ってしまうことが、結果的に相手の利益になること、とみなされています。そのような思いを込めて、『思いがけず利他』という本が昨年刊行されました。
東京工業大学に「未来の人間研究センター」という研究機関があって、伊藤亜紗という、東大で生物学から文転しヴァレリーを研究した若手の美学者が代表を務めています。仏教徒を公言している中島岳志、カトリック教徒の若松英輔、小説家の磯崎憲一?、スピノザ学者の國分功一郎(東大に転出)が中心メンバーです。それぞれに成熟期を迎えている面々であるだけに、私なりには、しばらく彼らの活動と発言に注目してみようとおもっています。昨年は、最初の成果を『「利他」とは何か』(集英社新書)として出版し、一定の評価を受けています。
長くなってしまい、申し訳ありません。
|
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板