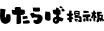レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
尚六SS「永遠の行方」
-
シリアス尚六ものです。オムニバス形式。
-
夏の間、書き逃げスレでいろいろ投下させていただいた尚六ものは、
3Pのエロネタ以外、すべて同じ設定を背景に持つ話です。
最初は何作もこちらに上げるつもりはなかったのと (せいぜい三作くらいのつもりだった)、
My設定の説明をされてもうざいだけだろうと思って、これまで言及しませんでした。
何かとワケワカメで申し訳ない。
でもこのままではさすがに中途半端ですし、他にもエピソードはあるため、
この際なので書き逃げスレの邪魔にならないよう専用にスレを立てて、
片隅でひっそりやらせていただくことにしました。
もっとも最後まで書ききれるかどうかわかりませんし、
各話で主人公が一定していない上に時間軸も過去と未来を行ったりしますが、
それぞれの話でいちおうのオチはついているのでご容赦ください。
イメージとしては雁主従の想いが通じ合う「永遠の行方」という話を基軸に、
その前後を含めて描くという感じです。
「永遠の行方」本編を書き上げていないため、まだ「前後」のほうしかありませんが。
参考までに、今まで書き逃げスレに上げていた話は、
時系列順だと以下の通りになります。
・後朝
・続・後朝
・腐的酒場
・腐的酒場2
・体の相性
もしかしたらたまにコメディ的なものもあるかもしれませんが、基本は超シリアス。
投下ペースはかなりゆっくりめのつもりですが、年内にかぎり月一本は投下します。
-
路寝にある広大な園林のはずれ。雲海を臨むわびしい岸辺で数日ぶりに主の
姿を見かけた六太は、いったんはそのまま見なかったふりを決め込もうとした
ものの、立ち止まってもう一度主の遠い後ろ姿に目をやった。
あんなふうに王宮で物思いにふける尚隆は珍しい。そんなときは大抵、市井
に降りて、名もない大勢の民に紛れることが常だと今の六太は知っている。
ひとりになりたいのだ。しかし誰かにそばにいてもらいたいのだ。
そんなことまで何となく感じ取れるようになってしまったのは肉体関係がで
きたからだろうか。わからない。これまで知らなかった彼のいろいろな顔を見
るようになったのは確かだけれど。
しばらく雲海を眺めていた尚隆は、やがてその場に腰をおろすと、ついでご
ろりと仰向けに寝転がった。
潮の香り、寄せては返す波の音。目を閉じれば、今でも遠い記憶がおぼろに
蘇ってくる。遮るものもなく降りそそぐ太陽の光を忌むかのように、閉じた目
の上に腕を置く。
どのくらいそうしていただろう。草を踏み分けて近づく足音に気づいたが、
身じろぎもしなかった。
ゆっくりとした足音は尚隆の頭のあたりで止まり、そのまま座りこむ気配が
した。腕をずらしてちらりと見やると、視界の端で金色の光が揺れた。別に尚
隆を見てはいない。両膝をかかえて静かに雲海を眺めている。
尚隆はそのまま腕を投げだし、ふたたび目を閉じて潮騒の中に身をゆだねた。
静かな時間が、ただ過ぎていく。
ふと相手の気配が動いて、尚隆の閉じた目を温かな掌が優しく覆った。
「尚隆。悲しいときは泣いていいんだ。人は悲しいときに泣くことで慰められ
る」
静かな言葉。見かけは年端もいかぬ少年のくせに、こいつはときどき誰より
も包容力があるところを見せる、と少しおかしく思う。
「王は人ではなかろう」
「人だとも。笑いも怒りもする、飲食できなければ飢えもする。王も人だ。た
だちょっと丈夫で長生きするだけで、心のありようは只人と何も変わらない」
淡々と綴られる言葉は、不思議と心に染みいっていく。岸辺に寄せる波のよ
うに。
それとも目を閉じているせいだろうか。闇は人を素直にする。互いの顔が見
えないときのほうが、思いを言葉に乗せやすく、受け入れやすいのは確かだ。
暗い閨での睦言のように。
-
「泣けぬのだ。俺は」
つぶやくように答えた声が、思いがけずかすれた。
そうだ、俺は蓬莱にいた頃から、長らく泣いた記憶はない。こちらの世界に
来てからも五百年以上経つというのに、泣いたのはただ一度。
俺の身代わりになって謀反人の呪を受け、永遠に意識を封じられたままで終
わると思われた六太が、長い眠りのあとで思いがけず目覚めた――それを目の
当たりにしたときだけ。
お笑いぐさなことにあの事件が起きるまで俺は、自分が六太から離れること
はあっても、その逆の可能性を考えたことは一度もなかったのだ。こいつが殺
されるのでも幽閉されるのでもなく、肉体は側にありながら、心が永劫の彼方
に行ってしまうなどとは。
この世界に来てからあれほど孤独を感じた時間はなかった。なのに自分は誰
の支えもなくひとりで立っているつもりだったのだ。
六太こそは、遠い蓬莱での自分を知る唯一の存在だった。俺の根を知ってい
る唯一の。ひとりで蓬莱の亡き民を懐かしむよりも、ほんの一部とはいえ思い
出を共有する者がいると無意識に考えられることが、何よりの慰めだったこと
にやっと気づいた……。
そんな彼の物思いをよそに、何を考えているのかしばらく沈黙していた六太
は、やがて言葉をつなげた。
「尚隆。人と人は支え合うことができる。助け合うことができる。ただしお互
いの距離は手を伸ばさなければ届かない程度には離れている。片方だけではだ
めなんだ。双方が手を伸ばさないと届かない。しかし手を伸ばしさえすれば何
かが触れる」
「……」
「后妃を娶ってもいいんだぞ」
「莫迦を言うな」
尚隆は即座に言い返した。――こいつは包容力があるどころか、時折とんで
もないことを言い出すから困る。
「好いた女はいないのか? 偽名ではなく真の名前で呼ばれたいと思う女は?」
「後宮に女人を入れたらどうすると言ったら泣いたおまえがそれを言うか」
沈黙がおりた。やりこめたと思った尚隆がほくそ笑む。しかしすぐに、絶句
したのではなく、溜息をついていたのだと悟る。まさか俺がこいつに憐れまれ
るとはな……。
「六太としての俺の気持ちは、麒麟としての俺が抑える。おまえが俺を気にす
る必要はない」
-
六太は静かに答えた。淡々と、それでいて優しく。
「俺はおまえが大事だ。麒麟として王が大事、六太として尚隆が大事。その前
には俺のことなどどうでもいい。俺ではおまえの悩みの役に立てないなら、役
に立てる人間をいくらでも側に置いていい」
「……」
「俺は想いを遂げた。僥倖みたいなもんだと思っている。おまえとこうなると
きが来るなんて思わなかった。これ以上は望めない」
「おまえは何も言わなかったな……。長い間、何も気取らせなかった」
くすりと笑う気配がした。
「宴席で話の種にでもされたらたまらないと思ったからな」
「そこまで主を信用しないか」
「あいにく誰かさんは日頃の行ないが悪いから」
おどけた調子が声音に混じる。こればかりは分が悪いので、尚隆は黙ってい
る。六太の反応がおもしろくてからかったことが多いのは事実だったから。
「なあ、尚隆。麒麟は王のもので、俺は尚隆のものだ。でも王は麒麟のものじ
ゃない。尚隆も俺のものじゃない。おまえは俺から自由でいていいんだ」
ある意味では、恋人と距離を置け、と言ったも同然の残酷な言葉。淡々と告
げる六太は慈悲深いようでいて冷たい。冷たいようでいて優しい。
なぜなら彼は知っているのだ、良きにつけ悪しきにつけ、人というものが変
わることを。変わるなと枷をつけて相手を縛るのではなく、変わってもいいの
だと許す。そうして自分は変わらずにそばにいると無言で慰める。そんな彼を
見る相手がどれほど切なくなるか知らぬげに。
尚隆が沈黙していると六太も、もはや何も言わなかった。永遠に続く潮騒に
包まれて、時間だけがゆっくりと過ぎていく。
やがてうとうとし始めた尚隆の耳に、六太の声がひそやかに届いた。
「少し眠れ。眠って夢の中だけでも泣いて人に還るといい」
尚隆の意識の中で、夢幻と現実の境目がにじんでいく。沈みゆく意識の中で
彼は、六太の掌がそっと離れるのを感じた。足音だけを残して、気配が遠ざか
る。
まったく主を見捨てて行くとは薄情なやつだ……。
完全に眠りに落ちる前の一瞬でぼやく。そうして苦さと切なさがないまぜに
なった思いをいだいたまま、二度とくだらぬことを言い出さぬよう今夜は仕置
きをしなければな、と意地悪に考えた。
-
「体の相性」の少し前の話になります。
書き逃げスレ300-303の「王后」はこの話から派生した没ネタでした。
「後朝」あたりの六太と同一人物には見えませんが、
あの話の前後は一時的にかなり情緒不安定になっていましたので。
またあれからけっこう時間が経っているため、初々しさも失せています。
最初のイメージでは六太が尚隆を膝枕してあげていたのですが、
そんな甘々はさすがにあんまりだろうということで変更しました。
とはいえ、いつかどこかで膝枕もしてあげていると素で思っています。
-
雁主従の想いが通じあったあとの「後朝」などのラブラブ話より数年ほど前の話です。
表面上の主役は鳴賢で、主題は彼のノーマルな失恋を慰める六太の図ですが、
副題は、長いこと片思いをしている六太の心中です。オリキャラあり (名前だけですが)。
-----
「まー、なんだな、女なんて星の数ほどいるさぁ。それに俺たちゃ、卒業して
高級官吏になりゃあ、色街でもモテモテだぞぉ」
「そーそー。そんなあばずれ、縁が切れて正解だぜぇ」
「どうせ最初から間男とよろしくやっていたに違いないって」
深更の大学寮。すっかりできあがって、それでもいちおう慰めてくれていた
つもりなのだろう、失恋した鳴賢に何かとからんでいた悪友たちは、楽俊と六
太に引っ張られて千鳥足でそれぞれの房間に引き上げていった。
そんなあばずれ。
最初から間男とよろしく。
幼なじみの娘の地味でおとなしい面影がよぎり、わずかに心が痛んだが、鳴
賢はそんな思い出を振り払うように頭を振った。誰もいなくなって静かになっ
た自分の房間で、ささやかな酒肴を載せていた懐紙や酒杯が散乱しているのを
片づける。さんざん飲んだはずなのに、まったく酔った気がしなかった。
ふと扉が開く音がしたので振り返ると、そこに六太が立っていた。さっきま
で彼が使っていたものだろう酒杯を差し出し、「水だ。飲めよ」と言った。鳴
賢は「ああ……」と頷いて受け取り、書卓の椅子に腰をおろすと酒でひりつい
た喉を潤した。
「楽俊も自分の房間に戻ったぜ」
「ああ」
六太はさっさと奥の臥牀に座りこんだ。組んだ足の一方の膝に頬杖をついて
鳴賢を眺める。悪友たちに劣らず、この少年も相当飲んでいたはずだが、酔っ
ているようにはまったく見えなかった。
子供と言っても差し支えない年頃なのに、座りこんでいるその仕草自体が妙
に大人びているのを、鳴賢はあらためて不思議に思った。よほど家庭が荒れて
いて、すれてしまったのか――いや、六太からそんな無秩序でささくれ立った
気配を感じたことは一度もない。口は悪いし、この少年は一見、ただの悪ガキ
のように思える。しかし普段はふざけているようでも実際には真面目な気質だ
し、意外にも繊細で気配り上手でもあった。
-
「あんまり気にすんなよな」
「え?」
「玉麗のことをあばずれだとか何だとか――あいつらはそれでおまえを慰めて
いるつもりだったんだよ。気にするな」
鳴賢は絶句した。自分でさんざん玉麗を悪く言ったくせに、いざ悪友たちに
彼女を罵られてみれば不快だったことを悟られているとは思わなかったからだ。
動揺を隠すために、既に水を飲みほして空になっていた杯に誤魔化すように再
び口をつけ、そして言った。
「別に、つきあっていたわけじゃないんだ。単に幼なじみだったってだけで何
か約束をしていたわけでもないし、それが休暇でたまたま帰省したら結婚して
他の里に移っていて、それをあいつらが勝手に誤解して――」
言い訳が勝手に口をついて出る。実際、それは本当のことだった。鳴賢は玉
麗と何の約束もしていなかった。内心でずっと、彼女が自分の卒業を待ってい
ると思っていたとか、向こうの態度の端々からもそれを感じ取れたとか、里で
の周囲もそういう目でふたりを見ていたというのは、鳴賢が知らないうちに玉
麗が他の里に移って結婚してしまった今となっては無意味だ。
もっとも酔いに任せたとはいえ、さっきの飲み会でさんざん、彼女とは目と
目で通じ合う仲だったというようなことを言ってしまっていたので、相手が六
太でなくても誤魔化しにしか聞こえなかったろう。
だんだん支離滅裂になっていく鳴賢の言い訳が、やがて尻すぼみになってお
さまったところへ、一言も口を挟まずに黙って聞いていた六太が言った。
「年末年始ってのは農閑期でもあるから帰省者も多いはずだけど、その娘は親
元に帰ってこなかったのか。普通、年始の祭りって親戚が集まるから賑やかだ
ろ」
「さあな。亭主のほうの親元にでも行ったんじゃないか」
鳴賢は投げやりな態度で首をすくめた。六太は「そっか」とつぶやいて目を
伏せた。
「鳴賢は去年は帰省しなかったわけだから、それじゃあ今年はきっと帰ってく
るとわかるよなあ。とてもじゃないが顔を合わせられねえか」
その言葉に、鳴賢は胸をえぐられたような気がした。実際、故意に避けられ
たと思っていたからだ。六太は目を伏せたまま淡々と続けた。
-
「好きな相手を諦めて結婚してさ、でもその相手に会っちまったら、自分が惨
めだもんな……」
「そんなことあるもんか……」鳴賢は顔を背けた。「単に比べただけだろ。比
べて、将来性のあるほうを取っただけだ。俺は卒業も危ういし」
脳裏に浮かんだ娘のはかなげな顔に、そんな計算高さはまったく似合わなか
ったが、鳴賢は吐き捨てるように言ってのけた。六太は目を上げて静かに彼を
見た。無言のままの様子に、何だか鳴賢は自分が責められているような気分に
なった。
「そりゃ、手紙も書かなかったけど。毎年帰省して会っていたわけでもないけ
ど。でもこっちは允許を取るのに忙しいし、大学に入ったからには卒業しない
と意味ないだろ」
「手紙、一度も書かなかったのか?」
鳴賢は言葉に詰まった。
「その、つい面倒で――さ。どうせ帰省すれば会うし。でも会っても別に変わ
りはないようだったし」
「恨み言も何も言われなかったのか」
鳴賢はうろたえて目を泳がせた。手紙のことにしろ、痛いところを突かれて
しまったからだ。
「最初の二年くらいは遠回しに言われたかな……。でも、何て言うか、そうい
うのうるさく感じてさ、適当に受け流して……。大学に入ったばかりの頃は関
弓での生活が楽しかったし。そしたらいつのまにか何も言われなくなってさ。
そうなるとそっちのほうが面倒がなくて」書卓に肘をついて、片手で目を覆う。
「―― 自業自得、か……」
六太は黙っていたが、やがてつぶやくように言った。
「その子、鳴賢のことがとっても好きだったんだろうな」
「……」
「でも人の心なんて弱いもんだ。鳴賢のことが好きで好きで。鳴賢に会えない
のが寂しくて。それで耐えられなくなっちゃったのかな」
「……」
「それとも自分よりもっとふさわしい女性がいるって思ったのかな。首尾良く
卒業して官吏になったら、鳴賢は高級官吏だ。最低でも下士にはなれて仙籍に
載る。年も取らなくなるし、普通の民にとっては雲の上の存在になってしまう」
-
鳴賢は考え込んだ。はたしてそうだろうか。いや、玉麗はおとなしくて控え
めだが、芯の強い娘だった。自分が高級官吏になったからといって、それだけ
で尻込みするとも思えない。そもそも大学に入った以上、卒業して官吏を目指
すのは当たり前のことだ。単に身を引くなら自分が大学に入ったときにそうし
ただろう。
「幼なじみだったんだ。官吏になろうがなるまいが関係ない」
「それでも、さ。鳴賢が長いこと苦労しながら頑張っているってことは知って
いたわけだ。便りもない、帰省もしない。自分は寂しいけれど、そんなふうに
思うのは鳴賢のためにならないんじゃないだろうか、むしろこのままでいては
いけないんじゃないだろうかって――考えたことがあったのかもな、と思って。
ま、勝手な想像だけど」
「……」
「好きだから……寂しさに耐えられなくて。でも相手には幸せになってほしく
て、だからこそわがままをぶつけられなくて。そして他の男を選んで結婚して、
鳴賢に会わせる顔がなくて。悩んだのかな。鳴賢のことが好きだから。でもそ
のままじゃ鳴賢にも亭主になった人に申し訳がないから。だから故郷を去って
踏ん切りをつけようとしたのかな」
鳴賢は黙り込んだ。あばずれだの何だのという悪友たちの罵りに比べれば、
はるかに玉麗に似つかわしい想像ではあったが、それが事実かどうかは別の問
題だ。それでも長年彼女を放っておいたという自覚はある鳴賢に、六太の言葉
はちくちくとした痛みをもたらした。
「まあ――何も約束してなかったしな……。別につきあってたわけでもないし」
「それでも八年待ったわけだろ」
「八年か。長いよなぁ……。さすがに卒業も危ういし、見捨てられても仕方が
ないよな……」
「正直に言ってりゃ良かったかもな。允許を取るのに苦労して、先行きどうな
るかわからない。手紙を書く暇もない。でもとにかく死にものぐるいでやって
いるから待っててくれって」
「そんなこと言えるか」
鳴賢は力なく笑った。こんなことを言われたら普段なら腹が立ったに違いな
いが、今はその気力もなかった。むろん相手が年端もいかない子供にすぎない
せいもあったろう。ここで怒っては年長者の立場がない。
-
「自尊心が許さなかった?」
あっさりと尋ねた六太に、鳴賢は溜息をついた。いくら六太がませていると
はいえ、たった十三歳の少年に男の矜持を説いても無駄だろう。
「おまえにはまだわからないだろうが、男にはいろいろあるんだ。そう簡単に
弱音を吐くわけにはいかない」
「好きあった娘にも言えないのか?」
「だからこそ、だ。通りすがりの見知らぬ人間になら何でも言えるかもしれな
いけどな。知り合いだからこそ言えないってことがあるんだ」
六太はまた目を伏せた。こういう仕草が妙に大人びている少年だった。
「そうだな。そうして人はすれ違っていくんだ……。身近にいても気持ちを通
じ合えるとは限らない。離れていればなおさらかもな」
そのつぶやきの切々とした響きに、鳴賢は妙に胸を突かれて相手を見つめた。
ほのかな初恋くらいは経験しているかもしれないとしても、色恋沙汰と形容で
きるほどの経験は積んでいない年頃だろうに、なぜだかひどく心に迫るものが
あった。
「おまえ……。恋したことあるのか?」
「あるよ」
「ふーん……。いつ?」
「今」
「へえ?」鳴賢は途端に興味をそそられた。このこまっしゃくれた子供にも、
そんな相手がいたのだ。「どんな娘だ?」
「言えない」
「俺にばかり喋らせておいてそれはないだろ。内緒にしといてやるから教えろ
よ。何なら助言してやる。少なくともおまえよりは経験があるはずだからな」
からかったつもりだったが、六太の目は穏やかで、それでいてひどく真摯だ
った。
「悪いけど言えない」さざ波ひとつない水面を思わせる静かな声。「これはお
まえだけじゃない、誰にも言えないことだし、実際、誰にも言ったことはない
から。そもそも片思いだし」
「餓鬼が、もったいぶりやがって」
「そのとおり。大の大人がこんないたいけな子供をいじめるものじゃない」
六太がやっといつものようににやりと笑ったので、なぜか鳴賢はほっとした。
-
「どこがいたいけだ。言っとくが、おまえは子供じゃないぞ」
「今さっき、俺を餓鬼だって言ったくせに」
「ああ、餓鬼だ。餓鬼のふりをしている、こまっしゃくれた餓鬼だ」椅子の上
で、六太のほうに身を乗り出す。「なあ、片思いって言ったよな。もしかして
相手の娘に言ってもいないのか? 言ってみれば案外、向こうもおまえに気が
あるかもしれないぞ?」
「それはありえない」
「へえ? 言い切ったな。もしかしてあれか? 同じ年頃ってわけじゃなく、
近所の姉さんとかか? まさか人妻ってことはないよな? おまえくらいの年
だと、年上の綺麗な女性に妙に惹かれることはあるが……」
「言わない」
「頑固だな」
「俺が死ぬ直前なら、教えてやってもいい」
不意にほほえんで答えた六太があまりにもはかなく、そして遠く見えたので、
告げられた言葉の重さと併せて鳴賢はぎょっとなった。
「もしそのときおまえが生きていたら教えてやるよ。それで我慢しろ」
まるで日々、生死を見つめているかのような物言いだった。からかわれてい
るわけではないのは明らかだったので、鳴賢は動揺した。まさか余命いくばく
もないというわけでもあるまいに。
「おまえ……。そのう、何か悪い病気にかかっているってわけじゃないよな」
「ああ。ぴんぴんしてる。普通に考えれば長生きするだろうな。実際にはどう
だか知らないけど」
「ふうん……」
鳴賢は何とか相づちを打ったが、相手の突き放したような言い方に妙に心が
騒いだ。思春期にはやたらと自分の死について考える時期もあるが、六太の年
頃はまだちょっと早い。それとも以前、身内に不幸でもあったのだろうか。
「そのう――ずっと相手を思い続ける自信があるってことか。まあ、餓鬼の頃
は、そのときの自分の気持ちが一生続くような錯覚をするもんだからな……」
「うん、だからそう思ってろよ」
六太は諦めたような優しい微笑を浮かべて鳴賢を見た。まるで聞き分けのな
い幼子に対し、あなたにはまだわからないことなのよ、と母親がほほえんでい
るような、やわらかい表情と声音だった。
-
はるか年上の相手に対するとは思えない言いように、鳴賢は「おまえさあ」
と呆れ顔で言いかけた。しかしすぐに「いや、いい」と手を振って口をつぐん
だ。確かに相手は自分の半分以下の年齢だったが、今までそんな年齢差を考え
ずに対等に話していたことに気づいたからだ。それを言えば楽俊の房間で出会
った当初はともかく、もはや日頃から特に年齢差を意識せずに話すようになっ
てしまっていたから、今さらとも言える。
そもそも六太は子供らしくないのだ。いや、故意に子供っぽく振る舞うとき
もあるが、何しろ語彙と言い知識と言い、大学の悪友たち顔負けなので、普段
は年齢などまったく意識しないで話せてしまう。場合によっては六太のほうが
ずっと年上であるかのような錯覚を起こすくらいだ。そういえば外見に似合わ
ず、この少年は非常に達筆でもあった……。
六太は淡々として続けた。
「おまえを信頼して言った。だからこのことは誰にも漏らすなよ。楽俊にもだ」
「このことって……。おまえに好きな娘がいるってことか? たったそれだけ
の話なのに?」
「それだけのことでも、今まで誰にも言ったことはないんだ」
「へえ……。そりゃ、六太の頼みなら言わないけど」
「ああ。何があっても、誰にも言わないでくれ。たとえ相手が天帝でも」
「天帝か。大きく出たな。もし言ったらどうする?」
「どうもしない。俺が壊れるだけだ」
「壊れるって……」あっさりと答えた六太に、鳴賢は言葉を失った。
「まあ、そうなっても気にするな。そのときはそのときだ。別に鳴賢を恨んだ
りはしない」
「おまえ……」鳴賢の背筋がぞくりとなった。穏やかな声音とは裏腹に、六太
の恐いほど真剣な心持ちが伝わったからだ。子供の戯れ言と笑い飛ばすには、
あまりにも重たい手触りだった。「言わない」必死に声を押しだす。「絶対に、
誰にも言わない」
「うん。ありがとな」
六太はほのかに笑った。まるですべてを諦めているかのような……。焦った
鳴賢は必死に考えを巡らせた。
-
表沙汰になれば相手に迷惑がかかるというたぐいの話ではなかったため、人
妻やはるかに年上の女性といった、倫理的に問題のある相手に恋しているので
はないだろうか、と考える。もしかしたらこのませた子供は、妓女にでも想い
を寄せているのかもしれない。それなら相手は六太のような子供など歯牙にも
かけないだろうし、知られて恥ずかしい思いをするのは六太のほうだけだ。
ただ、そこまで真剣な想いをいだいている六太の心情を汲み、せめてその恋
が良い思い出になればいいと鳴賢は願った。もっと成長して相応の相手に出会
ったとき、新しい恋が古い傷を癒すはずだから。六太はまだ幼いから、ある意
味で一途なだけだろう。
――そう、いずれ恋は終わるのだ。そして自分の恋も終わったのだ。
「つまんない話をした。そろそろ帰る。まあ、元気出せよな」六太はそう言っ
て立ち上がると、通りすがりざまに、座っている鳴賢の肩を軽くぽんぽんと叩
いた。「玉麗はおまえが幸せになることを望んでいたんだろうから」
言葉もなく見送る鳴賢を残して、六太は房間から出ていった。楽俊のところ
に戻るのだろう。
今度こそ誰もいなくなった房間で、やがて鳴賢は「手紙くらい、一度でも書
いてやれば良かったな……」とつぶやいた。相手をつなぎとめるためではなく。
結果は同じだったかもしれないが、少なくともいくらかは寂しさを紛らわせて
やれたかもしれないから。
自分が本当に玉麗を想っていたかといえば、そうではなかったかもしれない、
と今にして思う。黙って結婚した話を伝え聞いたときは衝撃を受けたが、大学
にいて彼女が気になるというほどではなかったし、允許の問題を除けば、大学
生活を謳歌していたと言っていい。少なくとも賑やかな関弓での生活は楽しか
った。おそらく玉麗ほどには寂しくなかったのは確かだ。
――そう。きっと自分はそこまで彼女を想ってはいなかったのだ。
もしかして黙って結婚したことで、妙な罪悪感を抱いているということはな
いだろうか。それで自分に会うことになるのが後ろめたく、新年だというのに
親元にも帰ってこられなかったということは。
そうかもしれない。そうでないかもしれない。もはや鳴賢にそれを知る手だ
てはない。でももしそうだとしたら、もういいんだ、と言ってやりたいと彼は
初めて思った。
玉麗はきっと、自分の幸せを願ってくれただろう。昔からそういう娘だった。
控えめで優しくて、常に他人を気遣っていて。
だから今度は自分が願おう。どうか幸せになってくれ、と。
-
「後朝」と「続・後朝」の間の尚隆の様子です。
-----
重要な書類のすべてに目を通して差し戻すべきは差し戻すと、認可を下すぶ
んの書類に署名をし、玉璽を押印する。決裁できる書類は既に幾度も官の吟味
を経て練り込まれ、あるいはいったん差し戻されてのち内容をあらためて奏上
されたものばかりだから、ここまでくればほとんど流れ作業となり造作もない。
おまけにしばらく王宮を抜け出すこともなかったとあって書類もたまっておら
ず、尚隆は午後の早いうちに面倒な作業から解放された。
冢宰の白沢が、決裁済みの書類を所轄の官府に渡すべく指示を与える。その
様子を眺めながら尚隆はふと、今朝、腕の中の六太が、目覚めるなりおびえた
表情を見せたことを思い出していた。まるで――そう、まるで夢が覚めるのを
恐れるような。あるいは今にも尚隆が「実は冗談だった。からかってすまなか
ったな」とでも言い出すとでも思っているかのような。
昨夜、想いを告げたときに見せた妙な恐慌と言い、五百年も連れ添ったとい
うのに、あそこまで動揺している六太を見るのは初めてだった。幼い外見に似
合わず、普段はふてぶてしいほど落ち着いている彼が、今朝はまともに尚隆を
見ようとしない。それどころか近づこうともしない。無理に顔を上げさせよう
とすれば、耳まで赤くして金色のまつげにふちどられた目を伏せる。
むろん恥ずかしがっているのだろうが、その暁色の瞳に時折よぎるおびえの
表情を思い出すたび、尚隆は妙に切ない気分になるのだった。それほど不安な
のか、と。
だいたい六太はいつも何かと考えすぎるのだ。それにもはや彼らは愛人同士。
好きなら好きで相手に甘えればいいし、人目を気にする必要もない。何と言っ
ても五百年の長きに渡って大国雁を支えた王と麒麟ではないか。それだけの確
固たる実績を築いた彼らに、国政を疎かにしないかぎり禁忌のあろうはずはな
い。
-
先ほど人払いしたときに六太に仕掛けた戯れを思いだした尚隆は、書卓に頬
杖をついて窓の外を眺めた。さすがの六太も理性が飛んでしまえば快楽に身を
委ねるということか。今夜はどんなふうに抱いてやろうかと考え、自然と好色
な笑みが口元に浮かぶ。むろんまだ無理をさせるわけにはいかないだろうが、
それでも……。
「主上?」
白沢の怪訝そうな声が耳に届いたが、尚隆は頬杖をついたまま目も向けなか
った。透明な玻璃を通して窓の外を眺めていた彼は、やがて「宰輔の御座所を、
仁重殿から正式に正寝に移す」言った。白沢は一瞬だけ黙り込んだものの、す
ぐに何ら動揺の窺えない声でおっとりと尋ねた。
「正寝とおっしゃいますと……。もし長楽殿の近くということでございますれ
ば、太和殿か玉華殿となりますが。台輔のご身分ですと、規模を考えれば他の
建物というわけにはまいりませんでしょう」
「そうだな、玉華殿でいいだろう。どうせ普段は今のまま長楽殿で寝起きする
のだ。しかし万が一、俺が怪我でもすれば、血の穢れの苦手な六太は近づけん
わけだからな。御座所としては、形式だけでも長楽殿とは異なる建物を用意す
る必要がある」
「仁重殿はどうなさいますか?」
「広徳殿と同じく、靖州府の一部として扱えばよかろう。その辺は任せる」
「すぐに検討を始めますが、そうなりますと侍官や女官の異動も正式に必要と
なりますな。書類の準備に、二、三日、お時間をいただいてもよろしゅうござ
いますか」
「ああ、別にかまわん。どうせ俺と六太の生活は変わらんからな」
「ではすぐさま太宰に諮って詳細を煮詰めることにいたします。警護の問題も
ありますから、とりあえず大司馬には今日のうちに簡単な話を通しておきまし
ょう」
|
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板