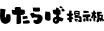レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
うにゅほとの生活4
-
うにゅほと過ごす毎日を日記形式で綴っていきます
-
2023年12月31日(日)
寿司をたらふく食べ、自室に戻る。
「はー、食った食った……」
「くったー」
「2023年も、残り五時間か」
「なにする?」
「ガキ使やらなくなってから、大晦日って感じあんましないよな」
「わかる」
「YouTubeでもいいけど、あまりに普段通りだし……」
「たしかに……」
「なんか、ゲームやるか。ウィンターセールでそこそこ買い込んだし」
「すちーむ?」
「そう」
「いいね!」
乗り気だ。
俺がパソコンチェアに腰掛けると、部屋の隅からうにゅほが丸椅子を出してきた。
「あれ、膝座らないの?」
「げーむしだい」
「ゲーム次第……」
「あくしょんとかだと、わたし、じゃまかなって」
「……あー」
俺はゲーム中にそこそこ体が動いてしまう性質なので、申し訳ないが邪魔なときもある。
「買ったの、だいたいロックマンとかなんだよな」
「うん。だったきーして」
気の利く子だ。
その気遣いに甘えよう。
「じゃあ、ロックマンXやってみようかな」
「わたし、みてるね」
「ああ」
ロックマンX アニバーサリーコレクションを起動し、ロックマンXを開始する。
「実は、これ初めてやるんだよな」
「そなんだ。こどものとき、やってたのかとおもった」
「家にX2だけ何故かあってさ。そっちはクリアしてたんだけど」
「へえー」
オープニングステージをクリアしたあと、適当にペンギンぽい敵のステージを選択し、進めていく。
「むっず!」
「え、そんなに?」
「操作に慣れてないのもあるけど、これ難しいぞ……」
そうは言いつつも、なんとか一機も落とさずにボスへと辿り着く。
だが、
「えっ」
ほんの二、三発で、HP満タンのエックスが落ちた。
「ちょ、無理無理無理!」
ライフアップをひとつも取得していないとは言え、これはない。
「これ、小学生クリアできんのか……?」
「わたしはむり……」
「最初にペンギンは無理だな。ライフアップかパーツ入手して、弱点武器を取ってこないと」
そんなこんなで攻略なしで進めていくと、一時間半ほどで八体のボスすべてを撃破することができた。
「ふー……」
「すごい、かてたね!」
「休憩、休憩。今日はここまででいいや」
「おつかれさま」
「ほら、膝来ていいぞ」
「はーい」
うにゅほが俺の膝に腰掛ける。
「なんだかんだで、結局はYouTube見ながら年越しか」
「それもまたよし」
「かもな」
やがて、時計がてっぺんを迎え、軽く年越しの挨拶を済ませる。
「あけまして、おめでとうございます」
「ことしもよろしくです」
「ああ、よろしくな」
「うん」
2024年はどんな年になるだろう。
なるべく健康に生きて行きたいものだが。
-
以上、十二年一ヶ月め 後半でした
引き続き、うにゅほとの生活をお楽しみください
-
2024年1月1日(月)
「……地震?」
「?」
座椅子でくつろいでいたうにゅほが、俺の言葉に周囲を見渡す。
「ゆれてる……?」
「こっちは揺れてない。本州で大きな地震があったんだって」
「そなんだ」
「元日早々、大変だよなあ」
「ほんとだね。だいじょぶかな……」
などと、のんきな会話を交わす。
この地震──令和6年能登半島地震が生半可な規模でないことを理解したのは、続報が次々入ってきてからだった。
最大震度7。
ビルが倒壊。
大津波警報発令。
市街地で大火災が発生。
「──…………」
「──……」
東日本大震災が発生したときのことを思い出して、血の気が引いた。
これは、よくあるただの大きな地震ではない。
震災だ。
「◯◯……」
うにゅほが、不安げに俺の腕を抱く。
俺は、うにゅほの髪を優しく手櫛で梳いた。
「大丈夫。みんな、東日本大震災のことを覚えてる。津波が来る前に避難するはずだよ」
「……うん」
「なんか、五年くらい前の地震を思い出すな」
2018年の北海道胆振東部地震だ。
丸一日停電したことを、今でもよく覚えている。
「ほし、みたね。きれいだった」
「あのときは、北海道全域が停電してたからな。天の川も、北斗七星も、よく見えたっけ」
「なつかしいな」
すこしだけ微笑んだあと、うにゅほが目を伏せた。
「あのじしんより、おおきいんだよね……」
「たぶん。それに冬だしな。みんな寒いと思う」
「うん……」
ここから何ができるわけでもない。
寄付だって始まってすらいない。
できるとすれば、こうして祈ることくらいだ。
これ以上、大きな被害が出ませんように。
心の底からそう願うのだった。
-
2024年1月2日(火)
「なんか、あんまり正月気分って感じでもないな……」
「うん……」
どうしても地震のことが脳裏をよぎる。
のほほんと過ごすことに、ほのかな罪悪感があった。
俺たちには何もできない。
だが、できないなりに取るべき態度があるのではないか。
そんなくだらないことを考えてしまう。
だから、思った。
「……寝るかー」
ひと眠りして気分をリセットするのも悪くはないだろう。
「ねるの?」
「なんか眠いし。××は?」
「ねようかな。ひるねのじかんだし……」
「ああ、たしかに」
うにゅほは、遅く寝て早く起きている。
不足したぶんの睡眠時間は昼寝で補っているのだ。
「ね、いっしょにねよ」
「いいけど」
同衾に躊躇があったのは既に過去のことだ。
アイマスクを装着し、ベッドに入る。
「うへー……」
うにゅほが潜り込んできて、俺の胸元に抱き着いた。
「そこ息できる?」
「がんばる」
頑張らせるのも悪いので、うにゅほの口元まで布団を下げる。
「かた、さむくない?」
「大丈夫だろ」
「そか」
アイマスクを下ろし、目を閉じる。
胸元にぬくもりがある。
もぞ、と身じろぎをする矮躯が、どうにも愛しい。
同衾に躊躇こそないが、抱き締められるといまだにどきどきするし、よく眠れないのは以前から変わらないままだ。
「──…………」
「……すー」
いつも、うにゅほだけがあっさり安眠してしまう。
なんだかずるい気もする。
結局、三時間ほど布団に入り、ちゃんと眠れたのは一時間程度だった。
とは言え、起きていた二時間は幸せタイムなので、特に文句もないのだった。
-
2024年1月3日(水)
親戚が子供を連れてきて、お年玉をむしり取られた。
「あー、お金ないのに……」
「とられちゃったね」
中学生がひとり。
小学生がふたり。
合計で四千円も搾られたにも関わらず、うにゅほはなんだか嬉しそうだ。
「久し振りに子供と遊べて嬉しかった?」
「うん」
「お姉ちゃん、お姉ちゃんって、すごい人気だったな」
「うへー……」
うにゅほがてれりと笑う。
「いちばん上の男の子が、今は中学二年生か」
「あのこね」
「うん?」
「すーごい、へんなかおしてた。おとしだまあげるとき」
「あー……」
だろうな。
「あーって、なに?」
「いや」
「?」
うにゅほが小首をかしげる。
これ、言っていいのかな。
いいか。
「あの子、たぶん、××のこと大人だって気付いてなかったと思う……」
「え」
「××ってさ。俺と出会ったときから、見た目変わってないからさ」
「──…………」
「同い年か、下手すると年下の子からお年玉もらった気分だったんじゃないかな……」
うにゅほが、遠い目をしながら天井を見上げる。
「きづいてはね、いたんだよ」
「ああ」
「わたし、どうがんだって……」
「うん」
「……でも、そこまで?」
「そこまで」
「そこまでかー……」
フォローを入れておこう。
「いいじゃん、可愛いし」
「……かわいい?」
「可愛い。最高。大好き」
「ふへ」
ちょろい。
だが、そのちょろさもまた魅力なのだった。
あの子、また来年来たときに、うにゅほを見て何を思うんだろうな。
-
2024年1月4日(木)
「──…………」
「──……」
うにゅほを膝に乗せたまま、ぼけーっとYouTubeを眺めていた。
年明けからいろいろあったが、ようやく正月気分が戻ってきたように感じる。
被災した方々には申し訳ないけれど、自粛自粛では心が疲れ切ってしまうのだ。
「あ」
「?」
うにゅほがこちらを振り返る。
「いや、なんでもない」
「なにー?」
「大したことじゃなくて……」
「なになに」
「気にしないで」
「きになる」
「──…………」
仕方がない。
「ディスプレイの右下に、曜日が書いてあるだろ」
「うん」
「今日は木曜日だ」
「うん」
「一瞬、ジャンプ買い忘れたかと思ったんだよ……」
「がっぺいごう」
「わかってます。すぐ思い出したから、なんでもないって言ったの」
「なるほど……」
「大したことじゃなかったろ」
「でも、わかる」
「ならいいけど……」
そもそも、ジャンプをKindleで購入することにしたため、買い逃しても数週間程度なら遡ることができる。
何重にも気にする必要がない。
「きんどる、べんりだねえ」
「Kindleと言うか、電子書籍全般だけどな」
「かみのほんもすきだけど……」
「俺は最近、紙の本読むのが面倒になってきた」
「そなの?」
「ディスプレイで読むのが手軽過ぎて……」
「あー」
「画面もでかいし」
「ちょっとわかる」
「自分がだんだんものぐさになってきているのを感じる」
「……うん、それは」
「だよな……」
どこかで切り替えなければならない。
体調がよくなったら、もっと外出するようにしよう。
-
2024年1月5日(金)
「今日の最高気温、マイナス一度だってさ」
「えっ」
俺の膝の上で、うにゅほが身を強張らせる。
「なんか、すこしだけまえにもどったきがするんだけど……」
「気温はな。でも、雪の降らない日はこんなもんだぞ」
「そかー……」
外は確かに寒いのだが、エアコンをつけているため部屋の中はそうでもない。
以前うにゅほが風邪を引いた際もそうだったのだが、案外エアコンを使うと暖まりすぎて、寒く感じてしまうのかもしれない。
「××って体温低いし、免疫力もなさそうで心配だよな」
「そかな?」
うにゅほが自分の頬に手のひらを当てる。
「ほら、ぜんぜんちがう」
「いや……俺のほうが冷たいんじゃないか……?」
自分の頬を触ると、俺よりひんやりしているように感じた。
「うん?」
これは本格的に体調管理に気を付けたほうがいいかもしれない。
マスクを買い足そう。
「──××、これ読んでこれ」
「?」
俺の膝に腰掛けてiPadをいじっていたうにゅほが、そっと顔を上げる。
ディスプレイにはWordが表示されていた。
「にっき?」
「まあ、読んでみ」
「うん」
しばしして、
「……あれ?」
うにゅほが小首をかしげた。
「エアコンのしつがいき、カバーかけてるからつかえない……」
「ああ」
「こんなはなしした……?」
「してない」
「……?」
「これ、AIのべりすとに過去一週間分の日記を読み込ませて出力した架空の日記」
「あ、まえやったやつ!」※1
「たまに"AIでも書けそう"って言われるから試してみた」
「そんなこといわれてるの……」
「実際、それっぽいの書けちゃってるのが面白いよな」
「でも、これ、なかったことだよ?」
「そうだな。日記の意味がない」
「だよね……」
「まあ、そこはそれ。適当に読み飛ばしてくれ」
「うん……?」
うにゅほが再度小首をかしげながら、iPadの画面に視線を落とす。
そして数分後、
「……これおもしろいね」
「お?」
どうやら気に入ったらしい。
「いろんなことおぼえてるね。わたしよりたくさん」
「まあ、俺の生活史だからな」
「べんきょうになりそう……」
どうやら、興味を引くことに成功したようだ。
とは言え、架空の日記とは言えAIに仕事を奪われるのはなんだか悔しいので、これ以上の精度向上は控えることにしようと思うのだった。
「××、××。読んで」
「また?」
うにゅほが顔を上げ、ディスプレイへと視線を向ける。
「日記の途中から、またAIのべりすとに生成してもらいました。どこからかわかる?」
「え、わかんない……」
「わからんか」
「ほんとにえーあい?」
「本当にAI」
「ふうん……」
膝の上で軽く居住まいを正し、うにゅほが言った。
「よんでるひと、こんらんするから、やめたほういいとおもう」
「……それは、まあ。うん」
おっしゃる通りである。
さて、読者諸兄はどこからどこまでAI製かわかるだろうか。
AIの進歩は凄まじいものだと、改めて感じるのだった。
※1 2021年11月11日(木)参照
-
2024年1月6日(土)
「なんか、あれだね」
「どれだね」
「おしょうがつ、おわったかんじ」
「あー」
正月三が日を過ぎ、さらに三日が経つ。
仕事始めで忙しない日々を送っている方々も多いことだろう。
「ぜんぜん関係ない話していい?」
「いいよー」
「paypayを導入しようかと思って」
「ぺいぺいって、ぺいぺい!ってやつ?」
うにゅほが決済音の真似をする。
似てない。
でも可愛い。
「そう、それ」
うにゅほが小首をかしげる。
「なんで?」
「ほら、俺たちってアップルウォッチ着けてるだろ」
「うん」
「paypayって、これで支払えるんだよ」
「これで……?」
「楽だろ?」
「らく」
「いちいち財布を開く必要もないし、なんならスマホすら出さなくていい。アップルウォッチを操作して、バーコードを読み込んでもらうだけ」
「はー……」
うにゅほが、うんうんと頷いた。
「べんりだねえ」
「そうなんだよ」
「わたしもできる?」
「できるできる」
「して!」
「はいはい」
paypayの導入は、思ったほど面倒ではなかった。
しばしして、うにゅほが自分のアップルウォッチに支払い用のバーコードを表示させる。
「これでいいの?」
「ああ、それでいいはず」
「かいものしたい!」
「あー……」
壁掛け時計で時刻を確認する。
「明日かな。今からだとコンビニくらいしか開いてない」
「かうものあった?」
「明日、飲み物の買い出しするからさ。××にはそのときに支払い頼むよ」
「はーい」
うにゅほは、しっかりとpaypayで支払いできるだろうか。
乞うご期待である。
-
2024年1月7日(日)
「ゆーき、ゆーき、ふーれ、ふーれ、かーあさーんがー」
童謡の替え歌を適当に歌いながら、うにゅほが窓に貼り付いている。
「ふーふふーふ、ふーふふーふ、うーれしーくなーい」
「吹雪、すごいな」
「うん……」
paypayのテストがてらに外出しようと思っていたのだが、この吹雪ではよしたほうがいいだろう。
「おとうさん、ゆきかき、さんかいやったって」
「三回も」
「でも、てつだわせてくれないんだよ……」
「除雪機使うからなあ」
除雪機を導入してから、雪かきは父親が一手に引き受けるようになった。
個人的には楽でいいのだが、うにゅほは雪かき好きだからな。
「ぶー」
「豚?」
「ぶたじゃないよ」
うにゅほが、当然のように俺の膝に腰掛ける。
すっかり定位置になってしまった。
「おもしろいはなしして」
「ええ……」
えらい無茶振りが来た。
すこし機嫌が悪いらしい。
「じゃあ、今朝の夢の話でいい?」
「いいよ」
「××と俺で、婆ちゃんの買い物を手伝ってたんだよ」
「あ、なつかしい……」
「あったよな。近所のスーパーで、××がよくマカダミアナッツ買ってもらってた」
「うん、うん」
「まあ、その婆ちゃんは、夢が進むごとに小さくなっていって、最終的には胎児サイズになって死ぬんだけど……」
「うー……、ん」
うにゅほが、渋い顔で大きく首をかしげる。
「……おもしろい、はなし?」
「いきなり言われても、パッとは思いつかないって」
「そだけど」
「じゃあ、××が面白い話をしてみてくれよ」
「え!」
「人に言うくらいだから、自分でもできるはず」
「──…………」
「──……」
「うへー」
「笑って誤魔化すか」
「だめ?」
「可愛いからよし」
「やた」
うにゅほには、とことん甘い俺である。
-
2024年1月8日(月)
「うー……、ん」
雪が、まあまあ降っている。
当然ながら、しようと思えば外出はできる。
だが、悪天候の日に無理を押して出掛けるほど、強い理由があるわけでもない。
paypayのお試しなんて、ついででいいし。
「××、どうする?」
「のみもの、まだあるし、あしたでいいかなあ……」
「そうだな」
悪天候の雪道で事故でも起こしては事である。
賢明な判断だろう。
「でも、あれだな。ジャンプ買いにコンビニ行く必要なくなったから、楽だよな」
「ジャンプ、あいぱっどにあたらしいのはいってた」
「買いました」
「はやい……」
「コンビニ行くと、ついでに甘いもの買っちゃうからさ。誘惑がないのはありがたいよ」
「いいことづくめだ」
「その代わり、ますます引きこもりに拍車が掛かったけどな……」
「きにしない」
用事がなければ家から出ない。
用事があれば普通に出るので、問題ないと言えば問題ないけれど。
「あ、そだ」
「うん?」
「そろそろ、◯◯のたんじょうびだね」
「あー」
そうだった。
「ほしいの、ある?」
「欲しいものか……」
正直言って、特にない。
欲求に忠実な性格なもので、欲しいものがあれば即座にサッと買ってしまうからだ。
「特に──」
「ない?」
「ない……」
「そかー……」
「悪いな。パッと思いつかなくて」
「きにしないで。わたしもかんがえてみる」
「そっか」
「でも、おもいついたらいってね。なんでもいいよ」
「わかった」
誕生日プレゼント、か。
欲しいもの、しっかり考えてみようかな。
-
2024年1月9日(火)
「××、そろそろ行くぞー」
「はーい!」
身支度を整えたうにゅほが階段を駆け下りてくる。
「ぺいぺい、つかえるかな」
「使えないってこたないから、大丈夫だよ」
「そか!」
雪がようやく降り止んだので、久方ぶりの外出だ。
愛車に乗り込み、まずはコンビニへと立ち寄る。
「豆乳と、何にする?」
「うーと、シュークリーム……」
「俺は白いたい焼きにしよう」
「あ、それもいい」
「半分こかな」
「はんぶんこ」
レジに赴き、店員にpaypay払いであることを伝える。
そして、アップルウォッチにバーコードを表示させ、それをリーダーで読み取ってもらった。
「……はらえた?」
「払えた払えた」
「すごい」
「たしかに便利だわ……」
クレジットカードでの支払いでも随分楽だと思っていたのに、それ以上があるとは思わなかった。
「よし、次はホームセンターだな。××が支払ってみてくれ」
「うん!」
近所のホームセンターへと車を走らせ、ペプシゼロと麦茶のダンボール箱をカートに積み込み、レジへと向かう。
ぽん。
うにゅほの背中を、そっと叩く。
「ぺ、ぺいぺいで……」
そう言って、うにゅほが店員にアップルウォッチを見せた。
画面には既にバーコードを表示させている。
完璧なムーブであるように思われたが、店員がすこし困った表情を浮かべた。
「ええと、QRコードは出せませんか?」
「え」
「……××、タップしたらQRコードになるから」
「あ、はい!」
バーコードがQRコードに切り替わる。
「そうしたら、そこのリーダーでお願いします」
店員が右手で示したのは、個人的に馴染み深いクレジットカードリーダーだった。
左上にカメラレンズがあり、そこでQRコードを読み取らせることができるらしい。
「──…………」
想定外の事態が続き、うにゅほがフリーズしている。
「……××、そこのレンズにQRコード!」
「!」
うにゅほが手の甲を下に向け、不器用にQRコードの読み取りを行う。
非常にやりにくそうだ。
これ、スマホで支払うことしか想定してないんだろうな。
三十秒ほどたっぷり格闘して、なんとか決済が完了する。
「ご利用、ありがとうございましたー」
微笑ましげな店員に見送られ、レジを離れる。
「……××、どうだった?」
失敗した。
コンビニでの支払いのほうを頼めばよかった。
あっち、マジで楽だったし。
少々心配していたのだが、
「──ちゃんとはらえた! すごいねえ、すごいねえ」
うにゅほが目を輝かせ、自らの体験を感動と共に口にする。
杞憂だったようだ。
特にお金をもらっているわけでもないが、paypay便利です。
しばらく使わせてもらおう。
-
2024年1月10日(水)
「──…………」
目を覚まし、のそりと身を起こす。
アイマスクを外し、自室の書斎側へ顔を出すと、うにゅほが俺のPCでYouTubeを見ていた。
「あ、おはよ」
「おふぁよ……」
挨拶の途中であくびが出た。
「はい」
うにゅほがチェアから立ち上がり、俺に着席を勧める。
素直に座ると、その膝の上にうにゅほが腰掛けた。
「なに見てたんだ?」
「うーと、しゃべるしばいぬのどうが」
「あー」
「みる?」
「見る見る」
うにゅほと共に、おやつを前にして犬語を喋りまくる柴犬の動画を見始める。
「このいぬ、コロににてるね」
「柴犬はたいてい似てるけどな」
「そかな」
「そうだよ」
「でも、コロ、しばいぬじゃなかったよ?」
「柴系の雑種だよな。マズルが長くてさ」
「まずる?」
「ほら、犬って口が前に張り出してるだろ。あれがマズル」
「◯◯、よくにぎってたとこ」
「握ってたな……」
長く握っていると嫌がるから、ちょいちょいとだけれど。
「なつかしいね……」
「そうだな」
もう、あまり覚えてはいないけど。
「十年以上前か」
「コロしんだの?」
「そう」
「そだねえ……」
「あのときは、あんなに悲しかったのにな」
「……うん」
「でも、ずっと悲しんでは生きられないから、人は死を忘れるようにできてるんだろうな」
「わすれるのも、かなしいな」
「そうだな……」
なんだか、しんみりしてしまった。
「別の動画見ようか」
「うん」
次は、笑えるチャンネルにした。
気が紛れた。
-
2024年1月11日(木)
「欲しいもの、欲しいもの……」
誕生日が明日に迫っていた。
「ふだんのせいかつで、こまることとか」
「──…………」
思案する。
「特に……」
「うーと、ぱそこんかんけいは?」
デスク周辺を見渡す。
「ディスプレイに不満はなし」
「うん」
「液タブも普通に使えてるし」
「うん」
「オーディオ環境も、これ以上はちょっと考えられないし……」
「うん……」
「キーボードは、一昨年に××がくれたREALFORCE R3をずっと愛用してる」
「ぱそこんほんたいは?」
「去年買い替えたばっかだろ」
「そだね……」
そもそも、いくら誕生日とは言え、数十万もする品物をうにゅほにねだれるものか。
「じゃあ、すまほかんけい」
「まず、iPhone本体はまだ一年少々だろ。Bluetoothイヤホンも買ったばかりだし、アップルウォッチも調子いいし」
「ほ、ほん!」
「あー、漫画をシリーズまるごととか?」
「そう、それ」
「それはアリだな」
「なにがいい? なにほしい?」
「ちょっと待って……」
取っ掛かりを見つけたからか、圧が強い。
数分間ほど考え込み、
「──ぼざろ、とか」
「ぼっちちゃん?」
「ああ」
ぼっち・ざ・ろっく!
俺のバイブルである。
「でも、もってる……」
「Kindleでな。アニメ見終わって続き読みたさにすぐさま電子書籍で買っちゃったけど、ずっと後悔してたんだよ。紙で欲しかったなって」
「じゃあ、そうする?」
「××が納得行くなら……」
既に電子書籍で持っている漫画をもう一度買うのだ。
抵抗があるかもしれない。
「いいよ!」
なかった。
「じゃあ、おかねあげるね」
「ありがとうな」
うにゅほからのプレゼントだ。
届いたら、くたくたになるまで読み込もう。
-
2024年1月12日(金)
家族の誰かの誕生日には、みんなでステーキを食べに行く。
それが我が家の慣習だ。
近場のステーキハウスが潰れてしまったので、すこし遠めの系列店へと赴いた。
地吹雪吹き荒れる豪雪の中を父親の運転で往復し、満足この上ない腹を撫でてベッドへと倒れ込む。
「やっぱ、誕生日はステーキだよなあ……」
ぼす。
コートも脱がぬまま、うにゅほも自分のベッドに倒れ込んだ。
「にく、たまにはたべたいもんね」
「タンパク質の暴力……」
「おいしかったー」
「普段も、もっと肉料理出してくれていいんだぞ」
「たまにだから、おいしい」
「それもわかるけど……」
「にく、ちゃんといれてるよ?」
「それはそうなんだけど」
「?」
うにゅほが小首をかしげる。
「贅沢言って申し訳ないけど、肉入ってる料理と肉料理は違うと思うんだよ」
「ふんふん」
「カレーは肉料理だと思う?」
「ち、がう……?」
「そう、違う。何故なら、カレーは肉を抜いてもカレーだから」
「あ」
「ステーキは、肉を抜いたら?」
「つけあわせ……」
思わぬ五七五が生まれてしまった。
「にくぬいたら、そのりょうりじゃなくなるのが、にくりょうり」
「そういうこと」
「たしかに、にくりょうり、あんましつくってないかも……」
「しょうが焼きは多いよな」
「かんたん」
「簡単なんだ」
「うん」
「ザンギとかトンカツとかの揚げ物は少なめかな」
「あげもの、あとかたづけが……」
「……あー」
後片付けのことは考えてなかった。
「でも、おかあさんとそうだんして、にくりょうりふやすね」
「いいのか?」
「しょくひ、いうほどかわんないし……」
「そうしてくれるなら嬉しいけど」
「うん、わかった」
俺は、肉が好きだ。
日々の食事に肉が増えるのは素直に嬉しい。
なんとなくメンタルに良い気もする。
最近また調子が悪いので、肉を食べて元気になりたい。
-
2024年1月13日(土)
今日の夕飯はピーマンの肉詰めだった。
リクエスト通りの肉料理だ。
夕食後に自室でくつろいでいると、膝の上のうにゅほが振り向いた。
「がっかりした?」
「何が?」
「ピーマンのにくづめ……」
「あー」
以前、ピーマンの肉詰めはハンバーグの下位互換だという持論を展開したことがあった。※1
そのときの会話を覚えていたのだろう。
「べつに、がっかりはしてないよ。美味しかったし」
「おかあさんがね、やさいもって」
「だろうなあ」
「ハンバーグにしたかったな……」
「まあ、ほら。ステーキ食べた翌日だからって配慮じゃないか」
「わかるけど」
うにゅほは俺至上主義である。
故に、俺が下位互換と称したピーマンの肉詰めを、内心忸怩たる思いで作っていたのだろう。
「でも、美味しかったよ。ほんと」
「そう?」
「ああ。手間掛けて作った甲斐はあるんじゃないかな」
「ハンバーグと、どっち好き?」
「……ハンバーグ」
嘘はつけなかった。
「やっぱし……」
「ごめん、そうなっちゃう」
「ハンバーグ、おいしいもんね」
「美味しいです……」
ピーマンの肉詰めも決して嫌いではない。
ただ、ハンバーグが好きなだけなのだ。
「……近所にハンバーグのお店できたし、今度行ってみないか?」
「あ、きになってた」
「んじゃ、今度な」
「うん」
肉を食おう。
肉を食うのだ。
※1 2018年8月31日(金)参照
-
2024年1月14日(日)
「……かきって、あんましおいしくないね」
「あー」
昼食時、父親が食べていた牡蠣弁当の牡蠣をひとつもらっていたっけ。
神妙な顔をしていると思っていたが、不味かったんだな。
「俺も、あんな感じの牡蠣は好きじゃないな」
「あんなかんじ?」
「弁当に入ってるやつ」
「おべんとうにはいってないのは、すきなの?」
「場合による……」
「ばあいに」
「生牡蠣と牡蠣フライは好きだよ」
「わたし、たべたことないかも」
「たしかに」
我が家は母親が牡蠣嫌いなので、まず食卓に並ぶことがない。
俺も、十年単位で食べていない気がする。
「なまがき、おいしいの?」
「美味しい。俺は美味しいと思う」
「ほー」
「ただ、磯臭さが苦手だときついかな」
「そうぞうつかないかも」
「あと、生牡蠣はあたるとでかいらしい」
うにゅほが小首をかしげる。
「あたる?」
「食あたりの、あたる」
「あー……」
「俺はあたったことないけど、あたりやすいらしくてさ。美味いけど無理して食うほどのもんでもないとも思う」
「そなんだ」
「だから、食べるとしたら牡蠣フライにしよう」
「あじちがうかな」
「牡蠣って、新鮮な牡蠣とそうでないのとで味がめちゃくちゃ変わる気がするんだよ。だから、新鮮な牡蠣をフライにしたら美味しいはず」
「ふうん……」
うにゅほが、うんうんと頷く。
「いつか、たべてみたい」
「今度小樽行ったときにでも探してみるか?」
「うん!」
そのうち、うにゅほと一緒に牡蠣フライを食べる。
どこかにメモしておこう。
-
2024年1月15日(月)
睡眠時無呼吸症候群の精密検査を行うため、猛吹雪のなか病院へ向かった。
脳波や呼吸、その他もろもろを測定するための装置を取り付けられ、帰途につく。
明日起きるまで外せないらしい。
「……俺、すごい状態じゃない?」
「うん、すーごい。びょういんからにげたみたい……」
頭部にヘッドギア、顔面に電極、鼻の穴にはカニューレを挿入し、その状態で車を運転しているのだ。
対向車の運転手は何を思っているだろう。
「なんかさ」
「?」
「このままコンビニ行きたくない?」
「え!」
「店員とかお客さんがどんな顔するか気になる」
「きになったらだめだよ……」
「大丈夫、行かない行かない。冗談さ」
「そか……」
うにゅほが、ほっと胸を撫で下ろす。
まあ、そうだよな。
もしノリノリだったら次のセブンイレブンに入ろうかと思っていたけれど。
帰宅し、夕食を取る。
あごの電極のおかげで口が大きく開けられず、あまり食べることができなかった。
ダイエットには良いかもしれない。
そして、こうして日記を書いているのだが、
「……すげー打ちにくい」
「だよね……」
中指の先に着けたパルスオキシメーターのおかげで、左手が満足に使えないのだ。
普段の中指の役割を薬指に当ててタイピングするのだが、だんだん攣りそうになってくる。
「はずせないの?」
「外したらピーピーうるさいらしい」
「そなんだ……」
「さっさと寝て起きて外すのがいちばんなんだろうな」
「でも、◯◯ねれない」
「そこが問題だ」
早めに寝なければならないが、早めに床に就くと眠れない。
諸行無常である。
日記投稿したらさっさと寝よう、うん。
-
以上、十二年二ヶ月め 前半でした
引き続き、後半をお楽しみください
-
2024年1月16日(火)
「──…………」
睡眠時無呼吸症候群の測定装置を取り付けたまま、のそりと起き上がる。
「あ、おきた」
「起きた」
「ねれた?」
「寝れない……」
うにゅほが苦笑する。
「だよね……」
簡易検査のときより機材が多い。
当然だが、さらに眠りにくかった。
「そくてい、できてるかなあ」
「さあー……」
「しーぱっぷ、かりれるかなあ」
「わからん」
「わからないだらけだね」
「人生、それはわからん。ただ働かなくてはいけないのだ」
「めいげん?」
「好きな漫画の台詞」
「へえー」
測定装置をひとつずつ外していく。
パルスオキシメーターを外すと、中指の先の皮膚がふにゃふにゃになっていた。
「××、ほらこれ」
「わ」
「長く絆創膏貼ってたりしたら、たまにこうなるよな」
「なる」
うにゅほが、つんつんと中指の先をつつく。
「これさ」
「?」
「そこらの壁でガ──ッ!て擦ったら、皮膚剥がれるのかな」
「やめて!」
「しないけど」
「こわいこわいこわい」
「ごめんって」
うにゅほを怯えさせてしまった。
気を付けよう。
「じゃあ、これ返しに行くか……」
窓の外を見る。
雪はやんでいるが、昨晩は豪雪だった。
「××、どうする? たぶん、死ぬほど道混んでると思うけど」
「?」
うにゅほが小首をかしげる。
「わたしいなかったら、◯◯、ひま……」
「それは、うん」
「いかないと」
相変わらずの俺至上主義である。
結局、夏場であれば往復三十分で済む道を、一時間半かけて踏破した。
冬は一生引きこもっていたい。
-
2024年1月17日(水)
「──……ふあ、ふー……」
うにゅほが大きくあくびをする。
「お昼寝?」
「うん、おひるねする……」
遅寝早起きのうにゅほは、昼間に一度仮眠を取る。
「◯◯、ねない?」
「今日はいいかな。することあるし」
「そか」
うにゅほが膝から下り、のそのそと自分のベッドへ向かう。
「おやすみいー……」
「ああ、おやすみ」
しばらくして、トイレに立ったついでにうにゅほの様子を覗いてみた。
「…………すー……」
胎児のように丸まりながら、側臥と伏臥の中間のような寝相をしている。
ヤムチャが無茶をした際のポーズにも見えるが、布団の下まではさすがに確認できなかった。
「──…………」
うーん、いたずらしたい。
よく眠っているうにゅほを見ると、決まっていたずらしたくなるんだよな。
とは言え、うにゅほは睡眠時間を確保している最中だ。
起こすわけには行かないし、睡眠の質を低下させてもいけない。
しばし悩んだあと、何もせずにその場を立ち去ることにした。
良いアイディアが思いつかなかったとも言う。
PCに向かって作業を進めていると、うにゅほが二時間の午睡から目を覚ました。
「おはよー……」
「おはよう」
「◯◯、さっき、わたしのよこたってた……?」
「えっ」
起きていたのか。
「たってた?」
「まあ、うん。××の寝顔見ようかと思って」
「やっぱし……」
「起きてたんだ」
「はんぶん」
いたずらしなくてよかった。
「じゃあ、ゆび、おでこにたてて、なんかいった?」
「……は?」
「いってないか……」
「してないし、言ってない。たぶん夢だ、それ」
「そんなきーした」
あのとき、うにゅほは、夢と現の狭間にいたんだな。
そう考えると、なんだかすこし面白かった。
-
2024年1月18日(木)
睡眠時無呼吸症候群の精密検査の結果、CPAPを保険適用でレンタルすることができるようになった。
「ほんとよかったよ。な、××」
「──…………」
助手席で、うにゅほが真っ青な顔をしている。
「ほら、よかったじゃん。こうして借りられたんだから問題ないって」
「う、ん……」
理由はわかっていた。
医師によるCPAPの説明に、以下の内容があった。
一時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数が二十回以上の人間は、CPAPによる治療を行わなければ、十年後の生存率が60%程度まで落ち込むと言うのだ。
睡眠時無呼吸症候群は、思った以上に重篤な病気なのである。
つまり俺は、十年後に三分の一の確率で銃弾が発射されるロシアンルーレットに、ギリギリで不参加を表明したことになる。
「……大丈夫か?」
「うん、よかった。よかった……」
ようやく緊張から解き放たれたのか、うにゅほはすこし涙目だった。
「ちゃんと毎日使うから。××と一緒に長生きするよ」
「ほんと、してね。ぜったいしてね。しなないでね」
「死にたくはないなあ……」
成さねばならないことが、たくさんあるから。
帰宅し、さっそくCPAPを枕元に設置する。
マスクを装着し、送気用のホースを接続すると、いよいよもって末期患者になった気分だった。
「……ねれる?」
「慣れるしかないよなあ……」
「ねてみる?」
「試しに、ちょっとだけ」
CPAPとは、空気を鼻孔に押し込んで無理矢理呼吸をさせる装置である。
慣れるまで快眠とは行かないだろう。
「はい、あいますく」
「ありがとう」
アイマスクを装着しようとして、すぐに気付く。
マスクのせいで入らない。
「……このアイマスク、気に入ってたんだけどな」
「しかたないよ……」
「××、使う?」
「つかう!」
うにゅほがアイマスクを受け取り、うへーと微笑んだ。
明るさを我慢して目を閉じる。
だが、一時間経っても深い眠りに就くことはできなかった。
前途多難だ。
ひとまず、CPAPのマスクがあっても着けられるアイマスクを探すことから始めよう。
-
2024年1月19日(金)
寝苦しさすら覚えながら目を覚ました。
「──…………」
CPAP用のマスクを外し、のそりとベッドから下りる。
何が変わっただろう。
「あ、おきた?」
気配に気が付いたのか、自室の書斎側からうにゅほが顔を覗かせる。
「おはよう」
「おはよ。どうだった?」
「……寝にくかった。それはもう、とにかく」
「そんなきーは、した」
うにゅほは、CPAPを装着しながら眠る俺の姿を見ているのだ。
さぞ物々しいことだろう。
「ねれなかった……?」
「眠れた、とは思う。劇的に変わった感じはしないけど、いつもより目は冴えてるかな」
「おー」
「CPAP自体に慣れれば、もっと眠りも深くなるのかも」
「なるといいね……」
「だな」
俺は、重度の睡眠時無呼吸症候群ではない。
中等症だ。
それゆえ、目に見えるような大きな効果が表れていないのかもしれない。
すこしだけがっかりして、日常に没頭していく。
それに気が付いたのは夕刻のことだった。
iPhoneの睡眠管理アプリを何気なく開くと、驚くべき情報が記録されていた。
「……××、これ見て」
「?」
膝の上のうにゅほにiPhoneの画面を見せる。
「今日の睡眠は、8時間50分。めっちゃ寝た」
「すーごいねてる……」
「でも、そこじゃないんだ。睡眠の評価のとこ」
「うーと」
8時間50分中、良質な睡眠が8時間9分。
深い睡眠が、5時間27分。
「え!」
「睡眠、めちゃくちゃ改善されてる……」
「しーぱっぷのおかげ?」
「だろうな」
「すご……」
寝にくい、眠れない、とすら思っていたのに、これなのだ。
CPAPとは、思っていたより遥かに凄まじい医療機器なのかもしれない。
ちゃんと毎日着けて寝よう。
-
2024年1月20日(土)
所用で外出し、コンビニへと立ち寄った。
paypay支払い用のバーコードを表示させ、アップルウォッチの画面を店員に見せる。
だが、
「……あれ?」
店員が困っている。
バーコードをなかなか読み込んでくれないのだ。
「?」
うにゅほと顔を見合わせる。
paypay、ファミリーマートでも使えるはずだよな。
仕方がないのでクレジットカードで支払い、事なきを得た。
車内に戻り、うにゅほに豆乳とミルクレープを渡す。
「なんで読めなかったんだろ……」
「なんでだろ」
「調べてみるか」
iPhoneを取り出し、アップルウォッチでバーコードが読み取れなかった理由を検索する。
「──画面が暗い、店員の読み取り方が悪い、そもそも小さくてスキャンしにくい」
「はい、◯◯。あーん」
「あー」
ミルクレープをひとくちもらい、思案する。
「画面の明るさ調節すると、ただでさえ充電の持ちが悪いのに、さらにひどくなりそうだなあ……」
「どうしよっか……」
「──…………」
「あーん」
「あー」
ミルクレープが口の中に入ってくる。
甘くて美味しい。
「……iPhoneでバーコード出すのが、なんだかんだ確実なのかなあ」
「そうかも……」
アップルウォッチで支払うときも、結局のところ操作は必要なのだ。
iPhoneを取り出し、アプリを開き、バーコードを読み取ってもらう。
手間はさして変わらない。
そして、財布からクレジットカードを出すより手軽であることは間違いない。
「──うん。今後、paypayでの支払いはiPhoneですることにしよう」
「いぎなし」
「アップルウォッチを活用したかっただけだしな……」
「そだね。あーん」
「あー」
うにゅほのミルクレープ、三分の二くらい食べてしまった。
くれすぎである。
-
2024年1月21日(日)
「──◯◯、なんかきたー」
「おー」
うにゅほから小さなダンボール箱を受け取り、開封する。
出てきたのは円筒形の容器だった。
うにゅほが小首をかしげる。
「なに?」
「開ければわかるよ」
ポン、という小気味良い音と共に、中身が現れる。
「あ、わかった。あいますくだ!」
「正解」
「うへー」
愛用していたアイマスクが、CPAPの利用開始と共に装着できなくなってしまった。
そこで探し当てたのが、nodpodという特殊なタイプのアイマスクである。
「……あれ?」
nodpodにぺたぺた触れていたうにゅほが、不思議そうな声を上げる。
「まじっくてーぷ、ないよ」
「それ、軽く巻くだけのアイマスクなんだよ。すこし重いだろ?」
「おもい」
「だからずれない」
「おー……」
「つまり、CPAPのマスクを着けてても使えるわけだ」
「ね、つかってみて」
「わかった」
使用感を試すため、CPAP用のマスクと共に装着する。
CPAPが自動的に起動し、鼻孔に空気が送られると共に、目の前が真っ暗になる。
遮光はバッチリだ。
そのとき、うにゅほがぽつりと言った。
「しんでるみたい……」
「生きぼへっ」
鼻に空気が流し込まれていると、上手く喋れない。
両方のマスクを外し、うにゅほを軽く睨む。
「生きるためにしてるんですけど」
「ごめん、じょうだん」
「いいけどさあ」
うにゅほも、こんな冗談言うんだな。
「あいますく、みつかってよかったね」
「高かったけどな……」
「おいくら?」
「五千五百円」
「たか!」
アイマスクとしてはかなり高価だが、他に選択肢がないのだから仕方ない。
擦り切れるまで使ってやろう。
-
2024年1月22日(月)
「××」
「?」
膝の上のうにゅほが振り返る。
「すっげーどうでもいいこと思い出しちゃった……」
「きになる」
「聞きたい?」
「ききたい」
「俺が子供のころ、購読してた雑誌があったんだよ」
「ジャンプ?」
「ジャンプも買ってたけど、いわゆる学年誌。小学一年生とか、小学五年生とか、今はないのかもしれないけど」
「そんなのあったんだ」
「そこで、具体的に誰か忘れたけど、オリンピックで銀メダルを取ったスポーツ選手を題材にしたコラムが連載されてたんだ」
「ふんふん」
「そのスポーツ選手を銀メダルマンってことにして、面白おかしくスポーツを推奨する──みたいな感じの」
「あー、ありそう」
「実際あったからな」
「それでそれで?」
「たぶん、そのコラムの最終回かな。銀メダルマンが進化したんだ」
「しんか」
「どんな進化をしたと思う?」
「うと、きんメダルマン……?」
「正解」
「え、いいの?」
「俺も××と同じ感想を抱いたと思う。だって、金メダル取ってないじゃん」
「うん……」
「銀メダル取った人を銀メダルマンにするのはいいと思うけど、金メダルマンにするのは本人にも失礼じゃない?」
「そうおもう」
「そこ、すげー引っ掛かってたのをなんとなく思い出した」
「わたしもひっかかるきーする……」
「だよなあ」
「まえむきにかんがえれば、つぎがんばってねってかんじかもだけど」
「そういう捉え方もあるか」
「でも、やっぱし、へんはへん」
「だよなあ」
そのコラムについて検索してみるものの、情報の一片も出てくることはなかった。
この記憶、事実なのかな。
-
2024年1月23日(火)
午睡から目覚めたうにゅほが、開口一番こう言った。
「へんなゆめみたー……」
「ほう」
俺も、うにゅほも、変な夢は大好物だ。
つげ義春を愛読しているほどである。
「どんな夢だった?」
「うーとね」
寝起きの頭を大きく傾けながら、うにゅほが続ける。
「ところさん」
「所さん」
「ところさんの、ほうもつこがあって……」
「所さんの宝物庫?」
「うん」
「……なにそれ」
「ところさんの、いさんが、たくさんはいってる……」
「生きてるのは知ってるよな」
「うん」
まあ、夢だからな。
「わたしと、◯◯と、(弟)で、ところさんのほうもつこにはいって、たからをみるの」
「どんなのあった?」
「ライターとか……」
「ライター」
「あと、くつとか、テーブルとか、ベルトとか」
「ハードオフ……?」
「あ、ハードオフ。そんなかんじ!」
「わかる」
舞台は明らかにハードオフなのに、夢の中のうにゅほは所さんの宝物庫だと思い込んでいたのだろう。
夢によくある齟齬だ。
「いろいろみてまわってね」
「うん」
「テニスコートあったから、(弟)とテニスした」
「……俺は?」
「わかんない。いなくなってたかも」
「──…………」
「ごめん……」
「いや、夢だもんな。あるある」
ちょっと切ないけど。
「それでね、おきた」
「どっちが勝った?」
「わかんない。わたし、テニスのルールしらないし……」
「俺も知らない」
「ねー」
「ちょっと面白い夢だな。日記に書こ」
「え、かくの?」
「許可が出たら」
「うーん、いいよ」
「よし!」
と言うわけで、書いた。
世の漫画描きたちは、もっと夢を漫画にすべきだと思う。
ここに読者がふたりいるぞ。
-
2024年1月24日(水)
「──あ、灯油切れた」
断末魔の電子音を響かせたファンヒーターへと視線を向ける。
「わたし、いれてくるね」
うにゅほが俺の膝から下り、ファンヒーターの灯油タンクを取り出す。
「俺が行くよ」
「いいの。◯◯、ぐあいわるいんだから」
「……悪いな」
「わるくないよ」
そう微笑み、うにゅほが階下へ消えていく。
弱い自分が情けない。
だが、うにゅほの心遣いが嬉しくもある。
複雑な心持ちだった。
「──うーしょ、と」
小型のファンヒーターに換えたため、灯油タンクは以前ほど大きくはない。
うにゅほの細腕でも十分に運べる程度の重さだ。
がしょん。
うにゅほが、灯油タンクをファンヒーターにセットする。
「ふー」
「お疲れさん」
「ただいまー」
灯油がファンヒーターに流れ込むのを待ち、運転ボタンを押す。
しばらくすれば、また火が灯るだろう。
「ほら、××」
ぽんぽん。
膝を叩いてみせると、うにゅほが我が物顔で腰掛けた。
「てー、くさくなっちゃった」
「あれ? ××、灯油の臭い好きじゃなかったっけ」
「すきなのは、◯◯のてーについたにおい」
「自分のは?」
「あんまし……」
「どれどれ」
うにゅほの手を取り、鼻先に近付ける。
灯油の臭いに混じり、なんだろう、快い芳香を感じる。
すんすんすんすん。
「かがないでー……」
「あ、ごめん」
以前から思っていた。
灯油のついた俺の手はただ臭いだけなのに、何故うにゅほはこんなに嗅ぎたがるのだろうと。
その答えが、なんとなくわかった気がした。
「……もっかい嗅いでいい?」
「うー」
「ダメ?」
「……いいよ?」
すんすんすんすん。
「わあ」
なんかハマりそうかも。
-
2024年1月25日(木)
「いいちこ」
「?」
「いいちこ」
「いいちこ……?」
「なんか、お酒」
「おさけ、のみたいの?」
「べつに……」
「……?」
「なんか、響き可愛くない? いいちこ」
「かわいいかも」
「だから」
「◯◯、つかれてる?」
「疲れてる……」
「あー」
得心が行ったように、うにゅほがうんうんと頷く。
「ねる?」
「眠くはー、ない」
「やすむ?」
「休んでるようなもんだし……」
「じゃあ、まっさーじがんだ」
「お」
うにゅほが膝から下り、マッサージガンを手にする。
「おきゃくさん、どここってますか?」
「肩かな。肩をお願いします」
「へいらっしゃい!」
粋でいなせな返答と共に、うにゅほがマッサージガンの先端を俺の肩へと押し当てる。
ぶいいいいいー……。
「こってるねえ!」
「マッサージガン越しでわかるの?」
「わかんないけど、ぜったいこってるし」
さすがである。
しばし肩の凝りをほぐしにほぐしたあと、ベッドへ移動する。
「腰もお願いします」
「はーい」
最近あまり使っていなかったマッサージガンだが、使えばやはり気持ちがいい。
凝りは万病の元なのかもしれない。
「はい、おしまい」
「ありがとうな」
「うへー」
「今度は、××もほぐしてあげよう」
「おねがいします」
ふたりいると、届きにくい位置の凝りもほぐせるからありがたい。
すこしだけ身も心も楽になったのだった。
-
2024年1月26日(金)
「うあー……」
だるい。
いやに体が重かった。
「だいじょぶ……?」
「あかん」
「あかんかー……」
運動したいのだが、それどころではない。
「わたしにできること、ある?」
「……あー」
正直に言えば、ない。
ないが、その気持ちが何より嬉しいし、一言で切り捨てたくはなかった。
「ある」
「わたし、なんでもするよ」
「……なんでも?」
「なんでも」
ほう。
「お手」
「はい」
座椅子から腰を上げたうにゅほが、差し出した手に自分の手を乗せる。
「おかわり」
「はい」
「伏せ」
「はい」
「ちんちん」
「ない」
「……まあ、うん」
そういう意味ではないのだが。
「立って」
「はい」
「回って」
「はい」
「ぐるぐるぐるぐる」
「ぐるぐるー……」
「止まって」
「はい」
すこしだけ、うにゅほがふらつく。
「甘いもの食べたい」
「あまいもの……」
軽く思案し、うにゅほが答える。
「いま、なにもないかも」
「ないか……」
「かってくる?」
「いや、そこまでは」
「なら、つくる?」
「作る?」
「ほっとけーきみっくすで、どーなつとか」
「──…………」
急激に腹が減った気がした。
「食べる」
「わかった。つくってくるね」
「ありがとな」
「うん」
いい子だな、うにゅほ。
俺にはもったいないくらいだ。
うにゅほの自家製ドーナツは、なんだか懐かしい味がした。
-
2024年1月27日(土)
ボカコレ投稿用の楽曲の動画を作り始めている。
「──◯◯、◯◯」
「んー?」
手を止め、うにゅほを見上げる。
「きゅうけい、しよ」
うにゅほの手には、豆乳のパックが二本あった。
「あ、ちょっと待って」
「だめ」
「……駄目?」
「よじかんくらい、ずーっとやってるから、だめ」
「はい……」
マウスを握り締めていた手を止め、豆乳を受け取る。
肩が、ずん、と重かった。
ひとたび集中すると止めどころがわからない性格だから、無理矢理休憩させてもらってよかったのかもしれない。
「すーごいがんばってるね」
「まあな。ボカコレは外せないし……」
「いつ?」
「あと一ヶ月弱、かな」
「そか」
パックにストローを刺し、豆乳を吸う。
「……美味い」
「おいしいね」
「××、昔は豆乳嫌いだったのにな」
うにゅほが口を尖らせる。
「◯◯、すぐそれいう」
「ごめんごめん」
擦りすぎてるな、このネタ。
「あ、そだ。きょうね、ハンバーグだよ」
「ハンバーグ!」
ピーマンの肉詰めの上位互換だ。
「いいね、やっぱ肉だよ肉。肉を食らわねば」
「たくさんたべてね」
「ああ。ありがとうな、××」
「うへー……」
壁掛け時計へと視線を送る。
午後五時半。
我が家では夕食は午後六時だから、もうすぐだ。
「あとは焼くだけ?」
「うん。タネ、もうせいけいしたから」
「そっかそっか」
「いちばんおおきいの、◯◯のにするね」
「お願いします」
久し振りに食べたハンバーグは、肉汁も多くたいへん美味だった。
毎日でもいいな、これ。
-
2024年1月28日(日)
「──でーきた!」
「!」
座椅子でうとうとしていたうにゅほが、ぱちくりと目をしばたたかせる。
「あ、ごめん」
寝ているとは思わなかった。
「どうが、できたの?」
「できた」
「おー……」
うんうんと頷き、うにゅほが言う。
「みして!」
「もちろん」
うにゅほを膝に抱き、ヘッドホンを着けてやる。
「じゃあ、再生するぞ」
「うん」
メディアプレイヤーの再生ボタンを押すと、完成したばかりの動画が始まった。
「──…………」
「──……」
うにゅほが動画に見入っている。
まじまじと見られると緊張するものだ。
四分半が経過し、うにゅほがヘッドホンを外す。
「すごかった……」
「よし!」
反応は上々だ。
「しゃしん、なんまいつかったの?」
「フリー素材サイトから、ざっと四百枚ほど」
「よんひゃくまい!」
ぱくたそさん、いつもお世話になっております。
「これは、じかんかかるねえ……」
「まあな……」
今日も、朝から夕方までPCに張り付きっぱなしだった。
「じーも、◯◯?」
「そうだよ」
「はつねミクは?」
「画像生成AIに出力してもらったのを、俺が描き直した」
「すごいねえ……」
「頑張りました」
「◯◯、くらいうたすきだね」
「自分を切り売りして歌詞を書くと、どうしても暗くなっちゃうんだよ……」
「そか……」
「嫌い?」
「こんかいのはね、すき」
「よかった」
前曲は「あんましすきじゃない」と遠慮がちに言われてしまっていたのだ。
わりとショックだったが、全肯定botをされるより遥かにいい。
「伸びたらいいなあ……」
「ねー」
クオリティに自信はあるが、運の要素も大きい。
だが、しつこく投稿を繰り返していれば、いずれはどうにでもなるだろう。
そこは楽観的なのだった。
-
2024年1月29日(月)
冷蔵庫で冷やしていたペプシゼロを飲みきってしまったため、ダンボール箱から新しいペットボトルを取り出した。
その場で開封し、ひとくち飲もうとして、
ぷし。
──ぶしゃあああああッ!
「うおわッ!」
「わあ!」
ペットボトルの口から茶色の泡と液体が噴水のように溢れ出した。
いま思えば即座に蓋を閉めればいいのだが、それは後知恵というものだ。
数秒戸惑っているうちに逆噴射は終わり、周囲にはペプシゼロの池が出来上がっていた。
「──…………」
「──……」
「ごめん、後片付け手伝って」
「わたしこそ、ごめんなさい……」
「うん?」
「さっきね、たおしちゃった」
「あー……」
そうだよな。
原因がなければ結果はないのだから。
「大丈夫大丈夫。作務衣紺色だし、本とか機械類にはかかってないし」
「うん……」
落ち込んでしまった。
「ほら、ひとまず片付けよう?」
「……うん、わかった」
洗面台の下の引き出しから雑巾を二枚取り出し、飛び散ったペプシゼロを拭き取っていく。
「これ、ノンシュガーでよかったな。普通のペプシだったら、あちこちべったべただ」
「ふこうちゅうの、さいわい?」
「そうそう」
黄色い雑巾を茶色く変色させて、拭き掃除は終わりを告げた。
「ふう」
「おわったー!」
「お疲れさん」
「◯◯も、おつかれさま」
「お互い、気を付けないとな……」
「うん。たおしたら、いわないとだった」
「俺も言うよ。今回、開けたのが俺だったからよかったけど、××が明るい色の服着てるときだったら惨劇なんてもんじゃない」
「クリーニングだね……」
作務衣ばかり着ている俺とは異なり、うにゅほは作務衣以外もちゃんと着る。
だが、おしゃれが仇となる場合もあるのだ。
すっかり炭酸が抜けてしまったペプシゼロをひとくちあおる。
やはり、すこしだけ物足りなかった。
-
2024年1月30日(火)
あまりに体が重いので、追加の薬をもらうために病院へと向かった。
「……この、毎度一時間は絶対待たされるの、どうにかならないかな」
「よやく、できないの?」
「予約制じゃないんだよ」
「できたらいいのに……」
「まあ、いいよ。予約できても結局は一時間待たされると思うし」
「はいしゃさんも、まつよね」
「待つ。特に、席に通されてから待つ」
「なんでだろ……」
「単純に、患者が多すぎるんじゃないか?」
「あー」
「まあ、我慢するしかないか……」
「うん……」
診察を終え、薬局で薬を受け取り、車に戻る。
「コンビニ寄る?」
「あ、わたしはらう!」
「paypay使いたいだけだろ」
「うへー」
「ま、たまには奢ってもらおうかな」
「いいよー」
俺は、豆乳とおにぎり、シュークリームを。
うにゅほは、豆乳とレタスハムサンドイッチを。
まとめてレジへと持って行き、うにゅほがiPhoneを取り出す。
「ぺ、ぺいぺいで……」
「はい」
車内で五回ほど練習した通り、うにゅほがiPhoneにバーコードを表示させる。
店員がリーダーでバーコードを読み取ると、「ペイペイ♪」という支払い音が小さく鳴った。
「ふー……」
「買えたな」
「かえた!」
「奢ってくれてありがとうございます」
「いえいえ」
商品を受け取り、愛車に乗り込む。
「サンドイッチ、かたほうあげるね」
「じゃあ、おにぎりとシュークリーム半分やるよ」
「ありがと!」
昼食にはいささか少ないが、ダイエット中にはちょうどいい。
体が動くようになれば、運動もできるんだけどなあ。
-
2024年1月31日(水)
「──…………」
肉が食いたかった。
「××、肉食いたくない?」
「くいたい」
「ハンバーグ食べに行く?」
「いく!」
「よし」
近所にハンバーグレストランが開業したのは、いつのことだったろう。
まだ一年と経っていないことは間違いないのだが。
身支度を整え、愛車に乗り込む。
「肉食うと、多少気分が上がるんだよな。こないだハンバーグ食べたときもそうだったけど」
「にくばっかはだめ。やさいもたべる」
「はい」
「でも、きょうはにく」
「よっしゃー」
ハンバーグレストランは程近い。
雪道でも、車であれば五分とかからないほどだ。
入店し、席につく。
四人席で隣に座るのは、もうあるあるだった。
「ハンバーグ、ザンギ、メンチカツ。いろいろある」
「ハンバーグかなあ」
「ハンバーグ食いに来たんだしな」
「うん」
「でも、チーズは乗せようかな」
「いいね」
「あと、サイドでザンギとメンチカツ注文できるっぽい」
「いいね!」
チーズバーグ定食をふたりぶんと、サイドメニューのザンギとメンチカツをタブレットから注文し、待つ。
「──…………」
「──……」
待つ。
「──…………」
「──……」
待つ。
「……かかるなあ」
「そだねえ」
実際には無言ではなく雑談を交わし続けてはいるが、待ったのは確かだった。
やがて注文の品が届くと、俺の胃がギュウと悲鳴を上げた。
「……いただきます!」
「いただきます」
箸で切ったハンバーグを口へ運ぶ。
美味い。
普通に美味い。
ザンギは巨大で、メンチカツもサクサク。
味は文句なしだった。
支払いを済ませ、車に戻る。
「肉食ったー!」
「くったね!」
「夕飯無理!」
「わたしも、はいらないかも……」
遅い昼食に重いものを選ぶと、こうなる。
「でも、いい店だな。今度家族で来ようか」
「うん、またこよう」
こうして、大満足で自宅へ帰るのだった。
まあ、深夜に空腹を抱えながら日記を書くことになるのだが、それは我慢しよう。うん。
-
以上、十二年二ヶ月め 後半でした
引き続き、うにゅほとの生活をお楽しみください
-
2024年2月1日(木)
「──……んー……」
自室の寝室側で、吐息混じりの声が聞こえた。
しばしして、髪がぐしゃぐしゃのうにゅほが起き出してくる。
「おはろー……」
「おはよう」
「ずっと、おきてたの?」
「起きてたの」
うにゅほがディスプレイを覗き見る。
「ちゃっと、じーてぃーぴーだ」
「GPTな」
「じーてぃーぴー」
「GPT」
「それ」
諦めた。
「小説のアイディア思いついたから、ChatGPTとブレストしてたんだよ」
「ぶれすと」
「ブレインストーミング」
「みんぐ」
「××、頭働いてないだろ」
「はたらいてない……」
寝起きだものな。
「ともあれ、小説のネタ出しみたいなことをしてたわけ」
「がんばってるねえ……」
よしよしと、うにゅほが俺の頭を撫でる。
「れも、ねたほういいよ」
「六時か……」
「うん」
「……切りのいいとこまでやっていい?」
「きりのいいとこ?」
「今、起承転結の転までプロットが立ったとこだったんだよ。このまま結まで行ってしまいたい」
「おわったら、ねる?」
「寝る。さすがに眠くなってきたし」
「なら、いいよ」
「ありがとう」
改めてディスプレイに向かったところで、パソコンチェアが回転した。
「うしょ」
うにゅほが膝に腰掛ける。
「どんなことはなしてたの?」
「気になるのか」
「きになる」
「じゃあ、ログ読む?」
「みして」
「はいはい」
ブレインストーミングのログを、うにゅほと共に読み返していく。
「……どうだ?」
「おもしろい、かも」
「完成したら最初に読んでくれるか」
「よむ」
果たして、いつ完成することやら。
まずは手をつけるところからだな。
-
2024年2月2日(金)
「ね、◯◯」
「んー?」
膝の上でくつろぐうにゅほの絹糸のような髪を、手櫛で梳く。
「はりーぽったーって、しってる?」
「そら知ってるよ」
「みたことある?」
「映画はないな。原作の一巻は読んだはずだけど、ぜんぜん覚えてない。記憶ゼロ」
「そなんだ……」
「興味あるのか?」
「ないけど」
「ないんかい」
「でも、じょうしきなのかなって」
「あー……」
手を止める。
「知ってて当然、みたいな雰囲気あるよな」
「ある」
「常識扱いされてるって言うか……」
「◯◯、どのくらいおぼえてる?」
「そうだなあ」
つるりとあごを撫で、思案する。
「なんか、こう、ハリーのところに魔法学校への招待状?みたいのが届くんだよ」
「うん」
「ハリーは、伝説の魔法使いの息子で、額に雷の形の傷があった気がする」
「あ、それしってるかも」
「それで、魔法学校へ行くためには、なんかスゲー半端な数字のホームから電車に乗らないと行けなくて」
「なんの、なんぶんのいち、みたいなやつ」
「そうそう。それで、魔法学校には四つの寮があるんだ」
「ぐりふぃんどーる」
「スリザリン」
「あとわかんない」
「ハッフルパフ、とー……」
「あとひとつ」
「──そうだ、レイブンクロー」
「すごい、ぜんぶでた!」
「それで、なんか友達とかできて、授業でクィディッチっていう空飛ぶホウキを使ったスポーツをするんだよ」
「へえー」
「おしまい」
「しってるの、ぜんぶ?」
「全部。あとハーマイオニーとロンしか覚えてない」
「◯◯、すーごいしってた」
「いや、断片的過ぎるだろ……」
何も知らないのと大差ない。
「それで、なんでいきなり。ハリーポッター見たいのか?」
「ゆーちゅーぶで、はりーぽったーのこすぷれしてたのみたから」
「あー……」
なるほど。
ハリーポッター、見れば面白いんだろうな。
そんなことを言いながら一生見ない気がするのだった。
-
2024年2月3日(土)
「せつぶん!」
「あー」
カレンダーへと視線を送る。
2月3日だった。
節分だ。
「えほうまき、かってあるよ」
「おー」
「でも、えほうまききられてるから、むごんでたべるのできないの……」
「普通に食べたほうが美味しいし、いいじゃん」
「そだけど」
「豆まきは?」
「まめまきはね、しないって」
「そっか」
うにゅほが、俺の顔を覗き込む。
「てんしょんひくい」
「節分って、そうテンション上がるイベントでもないから……」
「そかな」
「××、昔から節分好きだったもんな」
「すき」
「クリスマスより?」
「より、ではない」
「バレンタインデーより?」
「ではない……」
「じゃあ、冬至」
「とうじより、すき」
「冬至、かぼちゃ食う以外にすることないしな……」
「うん」
「ハロウィンは?」
「はろうぃんより、すき」
「うち、特になんもしないしな……」
「うん」
「豆まきもしない、恵方巻きも丸かぶりしないとなれば、ちょっと寂しいか」
「うん、さみしいの」
「……いちおう、恵方だけでも向いてみる?」
「みよう」
今年の恵方は東北東だ。
一年に一度しか使わないアップルウォッチのコンパス機能で、東北東を向く。
「こっち。本棚のほうだ」
「おー」
うにゅほの横に並び、本棚を見る。
「──…………」
「──……」
「読む漫画選ぶときと変わらないな」
「うん……」
いまいち盛り上がらない節分だった。
-
2024年2月4日(日)
近所にお弁当の無人販売所がある。
特にお弁当が欲しいわけでもないのだが、ふと駐車場に車を停めてみた。
「?」
うにゅほが、不思議そうな顔でこちらを見る。
「どんな感じか気にならない?」
「きになる」
「じゃあ、見てみよう」
「うん!」
無人販売所の中は、思いのほかしっかりとしたつくりだった。
棚にはお弁当が幾つも並び、冷凍庫にはハンバーグのタネや冷凍餃子などが詰め込まれている。
「おー……」
「こんな感じなんだな」
「アイスうってる」
「アイスは買ってくか」
「うん」
物珍しさに周囲を観察するが、そもそも広くはない。
五分もいれば、すぐ飽きる。
「ミルクとチョコ、どっちいい?」
「ミルク」
「わたしも」
ふたりぶんのアイスを手に取り、セルフレジへ向かう。
「あ、わたしやりたい」
「奢ってくれるのか……」
「いいよ」
スーパーのセルフレジで、やり方は既に履修済みだ。
さして迷うこともなく、うにゅほが支払いを済ませていく。
「!」
レシートを手にしたうにゅほが、どや顔でこちらを見上げる。
「えらいえらい」
髪を手櫛で梳いてやると、嬉しそうに微笑んだ。
「かえってアイスたべよ」
「だな」
無人販売所を出て愛車に乗り込み、自宅へ向かう。
「無人だからって商品盗みまくるアホがいるってニュースで見たっけな」
「カメラあるのにねえ」
「犯罪機会論ってやつかな」
「?」
「この世界では犯罪が起こる。犯罪を起こすやつがいる。これはもう、どうしようもないことだろ」
「うん……」
「原因を潰すことができないから、犯罪を起こす機会を減らす。それが犯罪機会論の考え方だ」
「むじんだと、だめなの?」
「実際には監視カメラがあるのだとしても、監視員にジロジロ見られながらよりは盗みやすそうじゃないか?」
「たしかに……」
「無人販売所って業態自体が、犯罪を助長してるのかもな」
「べんりなのにねえ」
残念ながら、世の中とはそういうものである。
-
2024年2月5日(月)
膝の上でくつろいでいたうにゅほが、ふとこちらを振り返った。
「さいきん、ぐあいどう?」
「具合か……」
就寝時にCPAPを装着するようになって、既に二週間が経過している。
何かが劇的に変わったわけではない。
だが、睡眠の質は確実に良くなっているとアップルウォッチが教えてくれた。
それでも体が重いからと、薬を増やしたのが一週間前のことだ。
増薬の効果は一、二週間で出るそうだから、そろそろ効果が見え始めてもいい頃だった。
「……まあ、気分は悪くないかな。うん」
「おおー」
「体は変わらず重いけど、なんだかやる気は出てきてる気がする」
「どうが、つくったもんね」
「ChatGPTと小説のネタも話し合ったぞ」
「よくなってる?」
「かも」
「かも!」
うにゅほが、自分のことのように喜ぶ。
俺のことを俺以上に心配してくれる子だから、症状の改善を伝えられたのは嬉しい。
「うんどう、できる?」
「そうだな。この調子なら、そう遠くなく」
「むりしないでね」
「そうするよ。無理してもいいことなんてないって、よッくわかったからな……」
無理はできる。
だが、それをずっとは続けられない。
仮に続けられたとしても、心か体のどこかが負債を押しつけられる。
負債は不発弾となり、いつか爆発するのを待つことになる。
結果を焦ることなく、長期的な視野で生活すること。
それが長生きのコツなのかもしれなかった。
「まず、すとれっちからはじめようね」
「そうだな。まずは、風呂上がりにストレッチをする習慣をつけよう」
「だいじ」
こんな前向きなことすら考えられない数ヶ月だった。
春も近い。
このまま改善に向かえばいいのだが。
-
2024年2月6日(火)
「なんか、気分いいなあ……」
「ほんと?」
「薬が効いたかな。調子いいかも」
「おー!」
うにゅほが嬉しげに微笑む。
「よかったー」
「風呂はまだだけど、ストレッチでもするか」
「しよ。やるきあるときに」
「ああ」
チェアから腰を上げ、腕を回す。
背中がパキリと音を立てた。
凝り固まった筋肉をほぐしていくと、如何に体を動かしていなかったかがすぐわかる。
「××さ」
「?」
「俺、昔は体柔らかかったって言ったら信じる?」
「しんじるよ」
「股広げて座って、その状態で床に胸がついたんだぞ」
「やわい!」
「××、できる?」
「わかんない。まえはできたきーするけど……」
うにゅほが足を広げて座り、前屈していく。
「んにー……!」
だが、つかない。
十分過ぎるほど柔らかいのだが、頬を床に触れさせるのが限界だった。
「だめだー」
「ダメか」
「むかしの◯◯、すごいね!」
「昔を褒められてもな……」
「いまもすごいよ」
「何が?」
「なんか」
「なんか」
適当に褒められた。
「からだ、うごかせたね」
「最低限だけどな」
「さいていげんができるようになったから、すごい」
「……そうだな」
そう思うべきだろう。
前向きに、前向きに。
雪が解けるころには、うにゅほと散歩のひとつもしたいところだ。
-
2024年2月7日(水)
「××」
「はい」
「エアロバイクを漕ごうと思う」
「!」
うにゅほが目をまるくする。
「うんどう、できるの?」
「今ならできる気がする……」
「がんばって!」
俺の膝から降り、うにゅほが隣の丸椅子に腰掛けた。
俺のデスクの下には小型のエアロバイクが仕込んであり、その気になればいつでも漕ぐことができる。
その気にすらなれなかったのがこの数ヶ月ということだ。
ペダルを漕ぎ始めて数分で、血流がよくなってくるのがわかった。
「さんじゅっぷん、いけそう?」
「行ける行ける。始めてしまえば行けるわ」
「おおー!」
「ほら、一緒に動画見よう。三十分の動画を一本見れば、それでノルマはおしまいだ」
「うん!」
三十分が経過し、そっとペダルを止める。
「フー……」
「おつかれさま」
「ありがとう」
「がんばった!」
「ああ、頑張った。健康に一歩近付いたな」
「いちじかんくらい、じゅみょうのびたかも……」
「馬鹿にならないなあ」
「つみかさねだね」
「××も漕ぐか?」
「うん、こぐ」
席を交換し、うにゅほがペダルを漕ぎ始める。
「わ、わ、うしろいく!」
漕げば漕ぐほどパソコンチェアが後方へずれていく。
「ああ。これ、コツがあるんだよ」
「こつ?」
「ペダルに足乗せて」
「うん」
うにゅほがペダルに爪先を掛ける。
「ここで、──こう!」
「わ」
パソコンチェアのキャスターを、ほんの5度ほど回転させた。
「こうすると、エアロバイクとキャスターが垂直になるだろ。後ろに動きにくくなる」
「へえー」
「こっちのエアロバイク漕ぐのって、実は初めて?」
「はじめてー、だとおもう。おへやサイクリングのとき、もいっこのこいでたし……」
「お部屋サイクリングもまたやりたいな」
「◯◯、げんきになったらね」
「ああ」
健康になりたい。
健康になりたいのだった。
-
2024年2月8日(木)
昼食後、食器を洗っているときに気が付いたことがあった。
愛用の塗り箸の、うさぎが描かれたプラスチック製のプレートが欠け、木地が覗いてしまっていたのだ。
「あー……」
「?」
隣で食器を拭いていたうにゅほが、俺の手元を覗き込む。
「あ!」
「割れちゃった」
「どうしよう……」
「割れた部分、どっかに落ちてないかな。あれば接着剤で直せるんだけど」
「さがしてみる!」
うにゅほと共に、食卓の周辺を探る。
十分ほど調べてみたが、プレートの欠片が見つかることはなかった。
「◯◯のはし……」
「まあ、十年近く使ってるしな。そろそろ買い替えようか」
「──…………」
うにゅほが目を伏せる。
これは、夫婦箸だ。
俺とうにゅほのお揃いの箸だ。
思い出がたくさん詰まっている。
だが、だからこそだ。
「××」
「──…………」
「この箸は、捨てないよ。仕舞っておこう」
「……すてない?」
「ああ。大切なものだからな」
「ん」
「だからさ。もっと壊れる前に、引退させてあげよう?」
「いんたい……」
「このまま使い続けたら、きっと折れてしまう。折れた箸は、見るたびちょっと悲しくなるだろ」
「うん……」
「だから、引退。××の宝物入れに仕舞って、新しい夫婦箸に頑張ってもらおう」
「……うん、そだね。いんたいだ」
「随分長く使ったもんなあ……」
感慨深い。
「あとで、ネットで探そうか。名前入りとかもできるかもだぞ」
「おおー」
うにゅほも、なんとか切り替えられたようだ。
今度はどんな夫婦箸にしようかな。
-
2024年2月9日(金)
「××、これこれ」
「?」
うにゅほを手招きし、膝に乗せる。
「はし?」
「そう。夫婦箸、楽天で探そうと思って」
「おー……」
「××はどんなのがいい?」
「……うさぎ?」
「それは前のだろ」
「そだけど」
「いろいろ見てこう。気に入るのがあるかも」
「うん」
夫婦箸の検索結果を上から順に見ていく。
「ほら、この桜のとか」
「あ、かわいいね」
「悪くないよな」
「これにする?」
「早い早い。もうすこし吟味しようぜ」
「そだね」
案外、決断力のある子だ。
夫婦箸と一口に言っても、いろいろある。
手彫りの箸に漆箸、八角箸と、種々様々な箸に目移りしてしまう。
「たくさんあるねえ……」
「そうだな……」
「◯◯、どんなはしがいい?」
「……こだわりはないけど、大切にし甲斐のある箸がいいかな」
「たいせつにしがい」
「ほら、綺麗だったり」
「きれい……」
うにゅほがマウスを手に取り、ホイールを回す。
「これとか?」
うにゅほが開いたのは若狭塗の箸のページだった。
螺鈿という技法で貝の輝きを留めた、ディスプレイ越しにも美しい夫婦箸だ。
「ああ、いいなこれ。最初の桜のと迷うくらい」
「ね、いいよね」
「高いけどな……」
なにせ、二膳で五千円だ。
良い品物なのはわかるが、高いは高い。
「これにしよ。わたしだすよ」
「半々でよくないか?」
「わたしだす。◯◯はおかねためて」
「……わかった」
最近、お金出したがるなあ。
注文を済ませ、あとは届くのを待つばかりだ。
うさぎの夫婦箸には、余生をうにゅ箱の中で過ごしてもらうとしよう。
-
2024年2月10日(土)
「たとえば」
「?」
「君がいるだけで」
「……?」
「心が強くなれること」
「なんか、うた?」
「そうそう」
「なんのうた?」
「……わからん」
「わからんの」
「サビだけ歌える。古い歌だってことはわかる。でも、それ以外の記憶がほとんどない」
「しらべてみる?」
「だな」
歌詞で検索すると、すぐに答えに辿り着いた。
「あー、米米CLUBかあ」
「しらない……」
「××は知らないだろうな。産まれてないよ」
「うん」
「でも、聞いたことない?」
「ききおぼえー……、は、ある、かも」
「そのくらいか」
「そのくらい」
ふと、疑問が降って湧いた。
「××って、懐メロどのくらい知ってるんだろ」
「なつめろ」
「むかーしの、曲」
「◯◯のいきたじだいのきょく?」
「俺、今も生きてるからな」
「うん」
「じゃあ──」
"懐メロ"というワードで検索し、適当にタイトルをつまむ。
「ZARDの負けないで」
「……?」
「愛しさと、切なさと、心強さと」
「──…………」
「ズルい女……」
「わかんない」
「……そうか」
そうだよな。
俺とうにゅほって、干支のひと回り以上余裕で違うもんな。
「じゃあ、島唄」
「しってる!」
「知ってるのか」
「◯◯、カラオケでたまにうたう」
「あー……」
俺発信だった。
そら知ってるわな。
なんだか遠い目をしてしまうのだった。
-
2024年2月11日(日)
夫婦箸が届いた。
「とどくの、はやいね!」
「マジでな」
もう二、三日は余裕でかかると思っていた。
だが、早いに越したことはない。
さっそくダンボールを剥がしていくと、桐箱が出てきた。
「二膳で五千円ともなると、箱まで豪華だな……」
「ね、あけていい?」
「いいぞ」
わくわくと興奮を隠さず、うにゅほが桐箱を開けていく。
「わあー……!」
青と赤。
螺鈿細工の美しい二膳の箸が、並べて飾られていた。
「きれい」
「写真より綺麗だなあ」
「うん、きれい……」
螺鈿とは、貝の裏側の真珠色に光る部分を加工し装飾する工芸技法だ。
オパールにも似た独特の輝きが、きらきらと光を跳ね返している。
「今日から十年、これで食事をするんだな」
「うへー……」
「この箸、選んでよかった?」
「うん、よかった」
「じゃあ、前の箸持っておいで。仕舞おう」
「うん!」
うにゅほが一階へと駆け下り、今朝まで使っていた二膳の夫婦箸を手に戻ってくる。
「わたしのたからものいれ、しまうね」
「ああ」
「◯◯のはしも、いっしょでいい?」
「夫婦箸だからな。引退後も一緒のほうが幸せだろ」
「そだね」
「俺たちみたいにな」
「ふへ」
うにゅほが、ほにゃりと笑う。
夫婦箸をうにゅ箱にそっと入れ、蓋を閉めた。
「おつかれさま」
その言葉は、きっと、箸にも届いただろう。
「──よし、なんか食べるか!」
「おひる、まだだよ」
「なんかない?」
「かきのたね、あったきーする……」
「じゃ、柿の種を箸で食べよう」
「おー」
新しい箸で食べた柿の種は、なんだか上品な味がした。
普段は一気に食べるからだな、うん。
-
2024年2月12日(月)
「……あー」
ディスプレイを見つめながら、ゆっくりと頷く。
「?」
座椅子に背中で座りながらiPadをいじっていたうにゅほが、不思議そうに顔を上げた。
「どしたの?」
「日記あるじゃん」
「うん」
「今日で4444回目みたい」
「え、すご」
「すごいよな」
「よんせん、よんひゃく、よんじゅう、よんかいって、なんかい?」
「……4444回だよ」
天然なのか、ボケなのか。
「あ、ちがう。どのくらい?」
「どのくらいって言われてもな……」
「なんねん?」
「十二年ちょいだな」
「あ、それはしってる……」
「××、さっきまで寝てた?」
「ねてない……」
「知ってる」
「もー」
あまりの数字に動揺したということにしておこう。
「十年前の今日、何してたっけな」
日記を十年ぶん遡っていると、うにゅほが俺の膝に腰掛けた。
「なにしてた?」
「ちょっといいワイン買って飲んでた」
「あー! ◯◯、ワインのんでたときあった!」
「なんかハマってたんだよな……」
「もうのまないの?」
「結局、安いワインにコーラ混ぜて飲むのがいちばん美味いことに気付いたから」
「……いいの?」
「自分の金で買ったもの、どんな飲み方してもいいだろ」
「そだけど」
「せっかくだし、ふたりで晩酌しようか」
「ワインないよ?」
「チューハイあったろ」
「わたし、はんぶんでいいよ」
「なら、俺も半分でいいや」
「わけっこしよ」
「ああ」
「とってくるね!」
うにゅほが膝から降り、階下へと駆けていく。
十年前は、ふたりで酒を酌み交わすこともできなかったっけ。
うにゅほはお酒に弱いから、今も大してしないけれど。
否が応にも時は経つ。
十年後には、どんなふたりになっているのかな。
-
2024年2月13日(火)
バレンタインデーが近い。
と言うか、明日だ。
毎年この時期になると、なんだかそわそわしてしまう。
「──…………」
「──……」
ベッドで腹這いになりながら、うにゅほが漫画を読んでいる。
チョコを作った様子はない。
だが、俺が寝ているあいだに事を済ませた可能性は否めない。
「……××さん?」
「?」
うにゅほが上半身をもたげ、こちらに視線を向けた。
「明日、何の日かわかる?」
「バレンタイン?」
「そう!」
「チョコ、つくってあるよ」
「よーしよしよし」
「あげないわけ、ないのに……」
「なんかな」
学生時代モテなかった反動かもしれない。
「あ、そうだ。さっき買ったグミ食ってみないか?」
「ぺたぐー?」
「そうそう。ハードグミってどんなんだべって買ってみたやつ」
「きになるもんね」
「固いっつっても限度はあると思うけど……」
デスクの上に放置していたレジ袋に手を突っ込み、ペタグーグミのグレープ味を開封する。
「ほい」
「はい」
うにゅほに一枚手渡し、適当に口に放り込んだ。
ごりごり。
固い。
噛み切れない。
なんだこれ、食べものか?
「かた!」
「固いな……」
「おもったかたさとちがう……」
「それもわかる」
噛み続けて、ようやく理解する。
グミが徐々に口内から消えていくのだ。
ハードグミとはガムの代替品であり、吐き出す必要がないぶん優れているのかもしれない。
とは言え、
「……慣れないなあ」
「ね……」
買ったぶんは全部食べるけど、リピートはしないかも。
そんな感じの商品だった。
-
2024年2月14日(水)
起床し、顔を洗い、朝一番にうにゅほに詰め寄る。
「××、チョコ!」
「ふふ」
微笑ましげにくすりと笑い、うにゅほが立ち上がった。
「まっててね」
「はい」
自室を後にするうにゅほを見送り、しばし待つ。
「はい。バレンタイン、おめでと」
手渡されたのは、猫のイラストが描かれたシックな角缶だった。
ただし、思いのほか小さめである。
「ありがとう。開けていい?」
「いいよ」
逸る気持ちを抑えながら、ゆっくりと蓋を開く。
そこにあったのは、まるで売り物のようなクオリティのトリュフチョコの列だった。
「おお……」
「ことしはね、すたんだーどに」
「××、腕上がり過ぎだろ。詰め方まで凝ってたら手作りだって気付かないぞ」
「がんばった!」
「ああ、頑張った。食べてみていい?」
「たべてたべて」
トリュフチョコをひとつ取り、前歯で半分に噛み割る。
すると、中には大粒のマカダミアナッツが入っていた。
「お!」
「なんだった?」
「マカダミアナッツ。他にもあるの?」
「アーモンドと、カシューナッツと、くだいだピーナッツもあるよ」
「豪華……」
「◯◯、ナッツすきだから」
「好きです」
「わたしのことは?」
「好きです」
「うへー」
「言わせんな恥ずかしい」
バカップルである。
「大事に大事に、ゆっくり食べよう……」
「あ、だいじょぶだよ」
「うん?」
「あとふたかんあるから」
「量まで」
たしかに、例年に比べて少なめだとは思ったんだよな。
あればあるだけ食べてしまう俺が一気に食べきらないように、うにゅほが調節してくれるらしい。
ありがたさと情けなさが同時に来るが、今日くらいは喜び一辺倒にしておこう。
バレンタインデーだしね。
-
2024年2月15日(木)
睡眠時無呼吸症候群との診断を受けた病院へ、CPAPの使用感を報告するために向かった。
愛車に乗り込み、アクセルを踏む。
ガリ、ガリガリガリ。
半端に上がった気温のため雪の解けかけた中道が行く手を阻む。
「うーわ、道すごいな……」
「がりがりしてる……」
「これ、車体の裏側削れてるぞ。絶対」
「くるま、こわれない?」
「この程度なら大丈夫だとは思うけど……」
自信はない。
幹線道路まで出れば、そこは天国みたいな道路環境だった。
積雪のために道幅こそ狭いが、道路は完全に乾いている。
「××、テキトーに曲流して。なんか歌おう」
「いいねー」
うにゅほが、自分のiPhoneからサカナクションを再生し始めた。
新宝島から始まって、車内でふたり熱唱する。
わりとやるのだが、これが楽しい。
往路の三十分を八割ほど踏破したときのことだった。
「……?」
歌っていると、なんだか舌の奥が痛い。
痛みに鈍感な俺が"痛い"と感じるのだから、相当だ。
舌の奥を気にしながら歌っていることに気付いたのか、うにゅほが俺の顔を覗き込む。
「◯◯?」
「なんか、舌が痛い……」
「した」
「悪い、着いたら見てくれる?」
「いいけど……」
熱唱をやめ、運転に集中する。
数分で病院へと辿り着き、駐車場に車を停めた。
「した、べーして」
「べー……」
思いきり舌を出し、痛む箇所を指差す。
「あ」
「ろうらっら?」
「でっかいこうないえん!」
「まりで」
「これいたいよ……」
「帰ったら、チョコラBBでも飲むか」
「うん……」
病院では、特筆すべきことは何もなかった。
帰宅してから洗面台で口内炎を確認したが、初めて見るくらい大きかった。
こりゃ痛い。
噛んだ記憶もないんだけどなあ。
|
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板