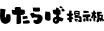レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
あの作品のキャラがルイズに召喚されましたin避難所 2スレ目
-
もしもゼロの使い魔のルイズが召喚したのがサイトではなかったら?そんなifを語るスレ。
(前スレ)
あの作品のキャラがルイズに召喚されました Part233(実質234)
ttp://changi.2ch.net/test/read.cgi/anichara/1244070866/
まとめwiki
ttp://www35.atwiki.jp/anozero/
避難所
ttp://jbbs.livedoor.jp/otaku/9616/
_ ■ 注意事項よ! ちゃんと聞きなさいよね! ■
〃 ` ヽ . ・ここはあの作品の人物がゼロ魔の世界にやってくるifを語るスレッドよ!
l lf小从} l / ・雑談、SS、共に書き込む前のリロードは忘れないでよ!ただでさえ勢いが速いんだから!
ノハ{*゚ヮ゚ノハ/,. ・投下をする前には、必ず投下予告をしなさいよ!投下終了の宣言も忘れちゃだめなんだからね!
((/} )犬({つ' ちゃんと空気を読まないと、ひどいんだからね!
/ '"/_jl〉` j, ・ 投下してるの? し、支援してあげてもいいんだからね!
ヽ_/ィヘ_)〜′ ・興味のないSS? そんなもの、「スルー」の魔法を使えばいいじゃない!
・まとめの更新は気づいた人がやらなきゃダメなんだからね!
_
〃 ^ヽ ・議論や、荒らしへの反応は、避難所でやるの。約束よ?
J{ ハ从{_, ・クロス元が18禁作品でも、SSの内容が非18禁なら本スレでいいわよ、でも
ノルノー゚ノjし 内容が18禁ならエロパロ板ゼロ魔スレで投下してね?
/く{ {丈} }つ ・クロス元がTYPE-MOON作品のSSは、本スレでも避難所でもルイズの『錬金』のように危険よ。やめておいてね。
l く/_jlム! | ・作品を初投下する時は元ネタの記載も忘れずにね。wikiに登録されづらいわ。
レ-ヘじフ〜l ・作者も読者も閲覧には専用ブラウザの使用を推奨するわ。負荷軽減に協力してね。
. ,ィ =个=、 ・お互いを尊重して下さいね。クロスで一方的なのはダメです。
〈_/´ ̄ `ヽ ・1レスの限界最大文字数は、全角文字なら2048文字分(4096Bytes)。これ以上は投下出来ません。
{ {_jイ」/j」j〉 ・行数は最大60行で、一行につき全角で128文字までですって。
ヽl| ゚ヮ゚ノj| ・不要な荒れを防ぐために、sage進行でお願いしますね。
⊂j{不}lつ ・次スレは>>950か480KBからお願いします。テンプレはwikiの左メニューを参照して下さい。
く7 {_}ハ> ・重複防止のため、次スレを立てる時は現行スレにその旨を宣言して下さいね。
‘ーrtァー’ ・クロス先に姉妹スレがある作品については、そちらへ投下して盛り上げてあげると喜ばれますよ。
姉妹スレについては、まとめwikiのリンクを見て下さいね。
・一行目改行、且つ22行以上の長文は、エラー表示無しで異次元に消えます。
SS文面の区切りが良いからと、最初に改行いれるとマズイです。
レイアウト上一行目に改行入れる時はスペースを入れて改行しましょう。
-
*本スレから避難所に投下先移転に伴い、暫定の投下スレとして再利用。
ちなみにこのスレのテンプレートは本スレの写しですが、
この避難所での実際の仕様は最大文字数が倍の4096文字。
行数は最大100行、スレ容量に至っては無制限だったりします。
意外と余裕があるので気兼ねなくどうぞ。
-
こんばんは、焼き鮭です。こちらでの最初の投下をさせていただきます。
開始は23:08から。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第七十五話「怪談・ミノタウロス」
オイル超獣オイルドリンカー 登場
それは、ゼロが命の光を引き替えにゼロキラーザウルスを消滅させてから、才人が発見されるまでの
間の出来事だった。
「キャアアアァァァ!」
『うっらぁぁぁッ!』
夜の帝政ゲルマニアの、地球で言うところの工業地帯が設けられた湾岸。今この地でグレンファイヤーは、
立ち並ぶ工場を襲おうとした怪獣……いや、超獣と戦いを繰り広げていた。
超獣の名はオイルドリンカー。アルビオンの死闘での超獣軍団の中にはいなかった超獣だ。
「キャアアアァァァ!」
オイルドリンカーは口から高熱火炎を吐く。そして場所はあちこちに火石や油など可燃物が
充満している工業地。かわしてしまったら非常に危険だ!
『ふんッ! こんなもんかよッ!』
だがグレンファイヤーはかわそうなどと微塵も考えず、火炎を真正面から受け切った。
そして炎の戦士の彼にダメージを与えられる威力はなかったようだ。
『ヤプールのみじめったらしい置き土産が! とっととケリつけてやるぜぇッ!』
グレンファイヤーは火炎を受け止めながら前進。オイルドリンカーに肉薄して強烈な炎の
アッパーを食らわせた!
「キャアアアァァァ!!」
巨体が軽々と空へ吹き飛んだオイルドリンカーは、炎の拳が体内の可燃物に引火、大爆発を起こした。
しかしはるか上空まで飛ばされていたので、工業地に被害はなかった。
『よっとぉッ!』
オイルドリンカーを一蹴したグレンファイヤーは空を飛んで工業地を離れていき、適当な人のいない
場所でグレンウェールズの姿に戻った。
「ふぅ……あいつを見逃してたらハルケギニアにでけぇ被害が出てたとこだった。ったく、ヤプールめ、
消滅したってのにまだこっちを苦しめようとしやがるとは。ほんとに始末が悪い奴だぜ……」
悪態を吐くグレン。先ほどのオイルドリンカーは、ゼロキラーザウルス=巨大ヤプールが
消滅間際に密かに飛ばしていた自身のマイナスエネルギーの結晶が成長して誕生したもの
なのであった。しかも地球では名の通りオイルを食らう超獣だったのが、ハルケギニアの
主要エネルギーである火石や風石などを食らう性質に変わっていた。ミラーナイトが、
結晶が浮遊大陸から地上の大陸へと放たれるのに気づいていなかったら、オイルドリンカーが
ハルケギニアのエネルギーを奪い尽くしてしまっていたところだった。被害が出る前に
発見できて、本当によかった。
そして勝利したというのに不機嫌そうなグレンである。この時点ではゼロと才人の行方が不明で、
彼らを心配するあまり気が気でない状態が続いていたのだった。オイルドリンカーをいつにもまして
荒々しいやり方で倒したのも、そこが影響していた。
「ミラーナイトの話じゃ、放たれた結晶は二つってことだったな。一つは今のでぶっ飛ばして、残り一つは……」
ミラーナイトはヤプールの結晶の行方もちゃんと確認してくれていた。一つはここゲルマニア、
そしてもう一つは……。
「ガリア王国だったな」
そういうことでグレンがガリア王国に移り、結晶の落下地点と思しきある一地方で調査を
行っていたところ、身長がデコボコの二人娘に出会った。
「あッ、あなたは!」
「おぉー、お前たち。久々じゃねぇか。魔法学院での戦い以来だな」
それはタバサとシルフィード。学院がメンヌヴィルと、超獣軍団の襲撃を受けてからずっと
顔を見ていなかった。何故かコルベールの遺体を実家に持ち帰ったキュルケについていった
ということだけは聞いていたが。
-
今のシルフィードは人間の姿に化けている。そしてシルフィードの正体が風韻竜イルククゥと
いうことは秘密のはず。なのだが……。
「タバサも、シルフィードも元気そうじゃねぇか。よかったぜ」
グレンはひと目で、タバサのお付きがシルフィードだと見抜いた。これにより、タバサは
シルフィードにきつい視線を向けた。
その視線には、何故彼がそのことを知っているのか、という疑問が非難とともに乗せられていた。
「お、お姉さま! これは、その、違うのね! シルフィからバラした訳じゃないのね!
何て言うか、その……!」
非難の視線から逃れようとするかのように、必死に弁明するシルフィード。その額は冷や汗
だらだらだった。
シルフィードを擁護するように、グレンはカラカラ笑った。
「だーいじょうぶだぜ、タバサ。シルフィードのことは誰にも話したりしてねぇからよ。
こいつと男の約束をしたからな!」
「だから、シルフィは女の子なのね……」
果たしてグレンはいつ、どのようにシルフィードの秘密を知ったのか? それはまたの機会に
語るとしよう。今回の話は、それが主題ではないのだ。
タバサたちと遭遇したグレンは、ともに場末の酒場に入って、食事を取りながら会話することにした。
と言っても、タバサは無口なのでグレンとシルフィードばかり話しているが。
「ふーん。お前たちは今、キュルケんとこに身を寄せてんのか」
「そうなのね。でも戦争が終わったから、もうしばらくして落ち着いたら学院に戻るつもりなのね。
今はお姉さまのお仕事でこっちに来てて、終わったからあの赤毛のお屋敷に戻るとこだったのね」
タバサは例の如く、イザベラから言い渡された任務をこなしたのであった。だが厄介になっている
ツェルプストーの屋敷に帰る道中でシルフィードが、お腹すいた、街でご飯食べたいと駄々をこねたので、
仕方なく街にやってきたという経緯であった。
「なるほどねぇ。……しかし、お前たちといると思い出すな、あの時のこと……」
グレンは沈んだ表情を見せた。超獣軍団との戦いで死なせてしまったコルベールのことを思い返したのだ。
「くそッ、悔やんでも悔やみ切れねぇぜ。俺がもっとちゃんとしてりゃあ……」
「あッ、そのことなんだけど……」
シルフィードが何かを言いかけたが、その瞬間タバサが素早くシルフィードの脇腹を小突いた。
「ん? 今何か言ったか?」
「あっ! な、何でもないのね!」
慌ててごまかしたシルフィードは、話題をすり替える。
「そ、それより、グレンはこんなところで何してるの?」
「ああ、実はな……」
グレンがヤプールの結晶の調査の件を話そうとしたその時、店の片隅にいた痩せこけた老婆が
タバサの元にすがりつくようにすり寄ってきた。
「ん? どうしたのね?」
シルフィードがそちらに気づくと、老婆はタバサに涙声で訴えた。
「騎士さま! 騎士さまをこれと見込んで、お頼みしたいことがありますのじゃ!」
奥から店主が出てきて、老婆の肩を掴んだ。
「おいばあさん! そういうことは他所でやってくんな! 商売の邪魔だ! 失礼しました騎士さま。
このばあさん、頭が少しアレなんで」
「お前に話しているわけじゃないよ! 黙ってておくれ! ごほ! ごほごほ!」
クソババア……、と、咳き込む老婆に店主が腕を振り上げたのを、グレンが腕を掴んで遮った。
「やめな。お年寄りには優しくするもんだぜ。ほらばあさん、これ飲んで一旦落ち着きな」
グレンが差し出したワインの杯を、老婆はすするように飲んだ。ゆっくりとその呼吸がおさまっていく。
-
「おお、この婆の頼みを聞いてくれますか……」
「ほっときなせえ! このばあさん、昨日ふらりとやってきたと思ったら、来る客来る客に
同じことを話すんでさ! まったく薄気味悪いったらありゃしねえ!」
店主の言葉をタバサが無視して、老婆を促した。
「話して。なにがあったの」
タバサたちのテーブルで、ドミニクと名乗った老婆はとつとつと自分たちの村、エズレ村に
起こった悲劇を語った。
「ミノタウロス?」
最近、村の近くの洞窟に、ミノタウロスと呼ばれる牛頭の怪物が住み着いた。ミノタウロスは毎月一人、
若い娘を要求しているのだという。要求に応じなければ、村人を皆殺しにすると脅しているとのことで、
老婆はタバサにミノタウロス退治をお願いしたいのであった。
「十年ほど前にも、一度ミノタウロスは住み着いたのです。そのときも、こうして行きずりの
騎士さまにお退治願ったんでございます」
「領主様に訴えな! それが筋ってもんだ!」
「エメルダ様にはもう訴えただよ! だが、多忙を理由に断られちまっただよ! まったく絞るだけ
年貢を絞るくせに、いざとなるとナシのつぶてだわさ! こんなちっぽけな村一つ、どうなっても
いいってことだわさ!」
すると店主は、困ったように言葉を返した。
「なんだね、まぁ、気の毒だが……、それがお上ってもんだ。というかなぁ、知ってるだろ?
この辺りじゃ最近、質の悪い牛泥棒が流行ってて、酪業に無視できねえ被害が出てんだ。
ミノタウロス退治どころじゃねえんだよ」
「なんだい、わたしらみたいな貧乏人は、黙って娘がとられるのを我慢しろっていうのかえ?」
「いや、そうは言ってねえが……、物事には順番ってものがあるだろうよ」
老婆はそれ以上、店主の言葉に耳を貸さずに、タバサに向き直った。
「重ねてお願い申し上げます。なにとぞ、あの化け物を退治してくだされ。最初に生贄に選ばれたのは、
わたしの孫娘なのでございます……。可愛い可愛い娘なんです。まだ嫁入り前だってのに、この世の
幸せをなに一つ知らんで死ぬなんて、ほんとに可哀想な話じゃありませんかえ」
それを傍から聞いていたグレンが膝を叩いた。
「全くその通りだッ! 安心しな婆さん。ミノタウロス退治は俺がやってやるよ!」
「へ?」
タバサに頼んでいたのにグレンが返事したので、老婆はきょとんとしてしまった。
「なぁーに、自分で言うのも何だが、俺はメイジじゃねぇが百戦錬磨の傭兵よ。怪物牛なんかにゃあ
負けはしねぇぜ!」
「グレン、ミノタウロスはまずいのね。ただの怪物じゃないのよ」
シルフィードが忠告した。ミノタウロスは首をはねてもしばらくは動くことのできる生命力を持ち、
巨大ゴーレム並みの怪力を誇る、恐ろしい怪物だ。おまけにその皮膚は刃や矢弾など受け付けないぐらいに
硬いのである。小型の怪獣と呼んでも差し支えないだろう。
だがそれで怖気づくグレンではない。
「なぁに、素手じゃ敵わんごついやでかいかもしれねぇが、こちとら人間様だい! 知恵比べで
参らせてやるぜ!」
知恵比べからは最も縁遠そうな男がそう言った。
「ミノタウロスは悪知恵も働くのね……」
シルフィードは呆れてため息を吐いた。しかし、グレンが真の力を解放すればミノタウロスなんかに
絶対負けはしないだろう。もっと大きくて力が強い敵と戦う日々なのだから。そのため、そこはあまり
心配していない。
一番心配しているのは……タバサがどう返事するかだ。その肝心のタバサは、老婆にこう
尋ねたのであった。
「どこ?」
ということで、タバサたち三人はミノタウロス退治のためにエズレ村に赴いた。エズレ村は、
なるほど領主が見捨てたのも頷けるような、わずかな畑が広がるばかりの寒村であった。
-
ミノタウロスは獣の毛皮に血文字で、『次に月が重なる晩、森の洞窟前にジジなる娘を用意するべし』
と要求したという。だがタバサはここで疑問を抱いた。食べるために娘を要求するミノタウロスは、
普通名指しなどしないはずである。実際、十年前の事件の時はただ“若い娘”とだけ書いてあったという。
これは一体?
それはともかく、タバサはミノタウロス退治のための作戦を講じた。まずは、相手を見極める
必要がある。そのための策とは……。
「こんなことだと思ったのね」
指定の晩に、洞窟の前にジジと同じ服を着て、同じ色に髪を染められたシルフィードが縛られて
転がされた。彼女を囮にして、ミノタウロスを観察するという算段であった。タバサやグレンでは
体格が違いすぎるので無理だったので、シルフィードにやらせた。
そうして現れたミノタウロスは……かなり奇妙だった。洞窟に住み着いているはずなのに
茂みから現れ、シルフィードをすぐに食らおうとせずに抱え上げてどこかへと連れ去り始めたのだ。
しかも、シルフィードはそのミノタウロスから獣の臭いがせず、代わりに汗の臭いを嗅ぎつけた。
決定的だったのは、首の皮が胴体とつながっておらず、腕に生えた毛が完全に人間のものだったことだ。
ここまで説明すればお分かりだろう。このミノタウロスは本物ではない。大男が、牛の首の
被り物を被っただけのものであった。
にせミノタウロスが向かった先には、五人のならず者がいた。そういうことだったのだ。
ならず者の集団が、エズレ村の過去の事件を利用して人さらいをしようとしていたというのが
真相だったのだ。
「剣を持った人が二人に、銃が二人。槍まで持っちゃってからに……。ミノタウロスの人は
大きな斧なのね。ああ、怖いのね。あう、恐ろしいのね」
シルフィードはさりげなく、いや、わざとらしく、尾行してきているだろうタバサとグレンに
ならず者たちの得物を教えた。が……。
「お前……、よく見りゃ、ジジじゃねえな?」
カンテラの明かりで観察されて、シルフィードの変装がばれてしまった。
「こいつなんだか怪しいぜ。おいお前、何者だ? ……領主の手の者じゃねえのか?」
「違うのね」
シルフィードはとぼけたが、ミノタウロス役だったならず者は追及する。
「おい、エズレ村の村長の名前を言ってみろ。お前があの村の者なら、言えるはずだな」
そんなの知らない。シルフィードが窮した、その時!
「うらあああぁぁぁぁぁぁぁぁぁッ!」
「な、何だ!?」
グレンが一気呵成に飛び出してきた! ならず者たちが動揺している隙に、まずは一番危険な
銃持ちの二人に当て身を食らわせて昏倒させる。
「ち、ちくしょう! やっぱ領主の差し金だったんだな!?」
残る三人が武器を構え直したが、その手にタバサの氷の矢が正確に突き刺さり、武器を
落としてしまった。その武器も全てグレンが素早く投げ捨てて、ならず者の手の届かない
ところへやった。
「動かないで。次は心臓を狙う」
あっさりと決着はついた。ならず者たちは降参して手を上げる。
「縛り上げて」
「はいなのね!」
シルフィードに巻きつけていたロープで、三人を一まとめに縛り上げた。これで完全に無力化だ。
シルフィードが男たちを問い詰める。
「誰がリーダーか言うのね!」
「私だ」
振り返ると、捕まえたならず者たちとは別の男がこちらに杖を向けていた。メイジの盗賊だ!
しかし一流の戦士であるグレンは、その攻撃の気配に既に気づいていた。
「危ねぇッ!」
彼はタバサとシルフィードの手を引き、男の放ったウィンディ・アイシクルから逃れさせた。
-
「何!? 小癪なッ!」
男は新たに呪文を紡ごうとしたが、その瞬間にグレンは踏み出していた。電光石火の踏み込みで
男との距離を縮める。
「はッ!?」
「おせぇッ!」
グレンは男の反応を許さずに杖を奪い取り、ベキリと力ずくでへし折った。それにより
男は一気に青ざめる。杖を失っては、痩せ気味の彼では屈強な肉体のグレンに敵う訳がない。
グレンは拳をポキポキ鳴らした。
「女相手に後ろから襲いかかろうなんざ、ふてぇ野郎だ。性根叩き直してやるぜ」
「……」
メイジの男はダラダラ脂汗を垂らすと……背中を向けて一目散に暗闇の中へと逃走し出す。
「待てこらぁッ! 逃がすかよ!」
当然すぐに追いかけるグレン。足でも彼に敵うはずがない。すぐにとっ捕まえて、それでこの
にせミノタウロス事件はおしまい……。
そう思われたが、事態は意外な方向に進んだ。
「ぎぃやああああああああああああああああ!」
男が暗闇に飛び込んですぐに、男の声が轟いた。悲鳴として。
「ああ!? な、何が起きた?」
さすがに動じるグレン。男に追いつくと、何とメイジの右腕が肩からなくなっていた!
メイジの男は激痛と失血で、瞬く間に気絶して倒れ込んだ。その傍らに立っているのは……。
「なッ……!? こいつは……!」
高さは二・五メイルはあるだろうか。丸いボールを繋ぎ合わせたかのような筋肉が身体中に
盛り上がり、見る者を圧倒する。その右手には、子供の大きさほどもある大斧を握り締めていた。
今まさに、メイジの右腕を切り落とした大斧であった。
そして、異様なのはその頭である。
太い角が巻貝のようにねじれながら生えていた。
突き出た口からは涎が垂れ下がる。
鼻と口から吐き出された息が夜風に当たり、白くにごる。
首の上に存在するのは、紛れもなく雄牛のそれであった。
「ミノタウロス! しかも本物だ!」
エズレ村を脅すミノタウロスはならず者の変装だったはずなのに……グレンの目の前に現れたのは、
確かに本物のミノタウロス! さすがに度肝を抜かれたグレンだが、即座に警戒して格闘の構えを取る。
ならず者を全員眠らせてから彼の後に続いてやってきたタバサとシルフィードも絶句した。
タバサは咄嗟に杖を構えて臨戦態勢に入り、シルフィードは震えて立ち尽くした。
突っ立っていたミノタウロスはやおら動きを見せる。グレンとタバサはより緊張で強張ったが……
ミノタウロスは彼らに襲いかかったりせず、何故かメイジの男の腕を拾い上げ、元の肩に押し当てた。
「?」
その行為に呆気にとられるタバサ。ミノタウロスは獰猛な食人の亜人。人間は食い物としか
見ておらず、その行動に一切の慈悲はない。それなのに、このミノタウロスは何をやっているのか?
ミノタウロスは腕を肩の切り口に押しつけたまま、喉から野太い声を発した。獣の咆哮ではなく、
れっきとした人の声。だが、どことなくぎこちなかった。ミノタウロスの喉を使って、無理やり
声を絞り出している、そんな感じだった。
「イル・ウォータル……」
しかも出てきた言葉は、確かに人間の使う魔法の呪文だった。
「じゅ、じゅ、呪文?」
面食らうシルフィード。呪文を使うミノタウロスなど、聞いたこともない。
メイジの腕が、みるみるうちに繋がっていく。なんとも見事なヒーリング。ミノタウロスの、
人間の真似事という訳でもなさそうだ。
「こいつをロープで縛りなさい」
ミノタウロスが丁寧な口調で言った。グレンがその通りにすると、タバサがミノタウロスへ尋ねる。
「……あなたは?」
「そうだな。この姿では、わたしが何者なのか気になるだろうな。まあいい、説明しよう。
こっちに来たまえ」
ミノタウロスに促されて、タバサたちは前にシルフィードを寝かせていた洞窟まで戻ってきた。
果たしてこの奇妙なミノタウロスは何者なのだろうか?
よく見たら、ミノタウロスの右腕には何故か鼻ぐりが嵌められていた。
-
以上です。
怪獣の出番がめっちゃ少ない……。
-
乙ですー
-
皆様、こんばんは。
今後はこちらの方で投下させていただくことになりました、またよろしくお願いいたします。
それでは、他に予約の方が無ければ、19:55頃から続きを投下させてください。
-
「ひぃぃ! ばっ、化け物!」
「きゃああぁぁぁ!?」
突如現れた身の丈2メイル半はあろうかという異形の魔物を見て、一斉に悲鳴を上げて逃げ惑う一般客たち。
ヴロックのヘルマスはそんな連中を塵を見るような目で見下ろしながらも、やや怪訝そうに首を傾げた。
(はて……、ワシを呼び出したあの小娘は、どこにいる?)
彼がサキュバスのリスディスの召喚に応じるのは、これが初めてではない。
物質界の脆弱な者どもを殺戮する機会を待ちわびる彼にとって、彼女は“お得意様”の一人なのだ。
しかし今回は、いつもならばすぐにあるはずの、彼女からのテレパシーでの指示がない。
それに、こんな人込みの中にいきなり召喚するのも、これまでの彼女の流儀からは外れているように思えた。
あの美しい毒蛇は、もっと巧妙で陰湿な、ヘルマスの嗜好から言えばいささかじれったくて回りくどいやり方を好んでいたはずだ。
(面倒なことを抜きにして今すぐ皆殺しにさせてくれるというのならば、有り難いことなのだがな)
ヘルマスはひとまずその大きな翼を窮屈そうに広げて飛び立つと、客たちが逃げ出そうとしている扉の前に降り立った。
そうして獲物どもの退路を塞いでから、ゆっくりと首を巡らせて、召喚者の姿を探し始める。
ついでに人間どもへの挨拶代わりに、体を震わせて体表から胞子を噴出させてやった。
やっと扉に辿り着いたと思った瞬間、突如目の前に降り立った怪物から逃げ出すのが遅れた2人の客が、その胞子の雲に包まれる。
「……ひっ、ひぃぃいい! な、なんだこいつはぁぁ!?」
「いやあぁあ! 助けて、誰か助けてぇぇ!!」
胞子はたちまち彼らの体の奥へ食い込み、根付いて、芽を吹き始めた。
皮膚を食い破ってあちこちから醜い緑色の蔦が生え出し、彼らの体を覆っていく。
その光景に対する恐怖と激痛とで2人の客は半狂乱になり、血まみれになりながら床をのたうち回った。
その悲痛な絶叫も、奈落の魔族にとっては耳に心地の良い音楽のようなものだ。
気分よく召喚者の姿を探していたヘルマスは、血に塗れた短剣を携えたまま、呆然とこちらを見ている若い人間の足元で目を留めた。
(……ヌッ?)
そこには、急速に腐敗して融けてゆく、異形の躯が転がっていた。
何があったのか、酷く歪んで獣じみた様相を呈している上に氷柱が体を貫き、刃物で無残に切り裂かれている。
それでも、かろうじてサキュバスの屍だとわかった。
(あの小娘めが、やられたというのか?)
そう察したヘルマスの胸中で、急に怒りが湧き上がり、膨れ上がっていった。
もちろん、殺されたサキュバスに対する仲間意識などからではない。
人間ごときに後れを取った負け犬なぞ、ヘルマスの知ったことではなかった。
しかし、彼女が殺されて奈落へと送り返されたことで、自分が脆弱な物質界の住人を虐殺する機会がひとつ失われたことになる。
そうして腸を煮えくり返らせていたところへ、追い打ちをかけるように、肌に何か不快な衝撃を受けた。
痛みはなかったが、どうやら何か攻撃をされたらしい。
ヘルマスは真っ赤に燃えた目で、じろりとそちらのほうを睨んだ。
「……ひっ!」
睨まれた男は、発砲したばかりの拳銃を握ったままがたがたと震え出した。
護身用に隠し持っていたゲルマニア製の新型銃を取り出して怪物の脇腹に打ち込んだのだが、かすり傷ひとつついていない。
慌てて踵を返して逃げ出そうとしたところで、その小太りの体がふわりと宙に浮いた。
「な……、なんだぁ!?」
じたばたともがくが、足が床に届かないのでどうにもならない。
ヴロックの使った《念動力(テレキネシス)》の魔力が、男を捕えたのだ。
ヘルマスがごみを投げ捨てるかのようにぶんと腕を振ると、男は勢いよく投げ飛ばされた。
そのままバーのカウンターを越えて戸棚に叩き付けられ、食器の破片や刃物が降り注いで、全身にひどい傷を負う。
「うぎゃあぁぁ! 痛い、痛いぃぃ!!」
血だらけになって悲鳴を上げながらのたうち回る男の姿を見ているうちに、ヘルマスの気分はあっさりと晴れていった。
まあ、先のことは先のことだ。
それよりも今ならば、小賢しい召喚者によって制限されることもなく、存分に殺戮を愉しめるではないか。
今見えている範囲だけでも数十人はかたい、陶酔するまで血の美酒を啜ることができるだろう。
だが、すぐに皆殺しにしてもつまらない。
その気になれば1〜2秒に1人のペースででもやれるのだし、時間はまだまだ、たっぷりとあるのだから。
まずはこやつらを存分に嬲り、悲鳴と命乞いの大合唱を奏でさせてからだ。
-
「みんな、そいつに手を出さないで! 早く離れて!」
ディーキンはそう周囲の客に呼びかけながら、慌てて先ほど胞子にやられた犠牲者の元へ駆け寄ろうとした。
戸棚に叩き付けられた男はかなりの怪我を負ったようだが、早急に救わなくてはならないのはむしろ胞子を受けた2人の方だ。
ヴロックの胞子は、取り除かなければじわじわと成長してダメージを与え続けるのだ。
今はまだ大丈夫でも、放っておいたら致命傷になる。
内心では、招来の機会を与えずに先ほどのサキュバスを仕留めることができなかったことを悔やんでいた。
予定では、透明化して斬り殺せる間合いまで近づき、問答無用で一気に仕留めようと考えていたのである。
ディーキンの近接戦闘能力なら、サキュバスなどものの数秒で、ほぼ確実に屠れる。
そうしていれば、《次元界移動拘束(ディメンジョナル・アンカー)》のスクロールを消費する必要もなかっただろう。
しかし、タバサとサキュバスの周囲には予想以上に多くの観客がいて、密かに接近するのは難しかった。
おまけにタバサが辱めを受けているのを見て逆上したトマが、先走って攻撃してしまったのである。
そうなった以上、こちらが悪役に仕立てられたりサキュバスが逃走したりする前に、なんとか事態を収拾する必要があった。
そこで敵の逃走手段を封じ、本性を暴いてこちらの正当性を証立てた上で仕留めるという方針に急遽切り替えたのだが……。
結果的にはそれが敵に招来の猶予を与えることになり、無関係の客たちまで危険に晒すことになってしまったのである。
だからといって、トマを責めることはできない。
タバサと彼とは昔馴染みで、主従の間柄でもあったと先ほど既に聞いている。
男として女性が、それも親しい女性が下劣な怪物から辱めを受けているのを見れば、義憤に駆られるのは当然であろう。
多くの人間の文化圏では、特に女性にとっては、公の場で肌を晒すことが非常に屈辱的なことだというのはディーキンも知っていた。
むしろ自分のほうにこそ否がある、とディーキンは思っていた。
ディーキンはサキュバスの正体を見抜いた時、すぐに倒すのではなく、他にもデーモンがいないかなどのより詳細な情報の把握を優先した。
そうでなければ、思わぬ落とし穴に嵌ることにもなりかねないと考えたからだ。
だからタバサがサキュバスが相手をしてくれている間にトマの術を解き、事情を聴きだした上で、奥の部屋を調べていたのだ。
敵の正体を伝えなかったのは、もちろんサキュバスに読心の能力があることを知っていたからである。
だが、まさか彼女が奥の間へ連れ込まれる前に、衆人環視の中でこのような辱めを受けるなどとは考えてもみなかった。
結果として彼女に屈辱的な思いをさせてしまった上に、このように危険な事態を招くことになったのだ。
これは明らかに、自分の責任である。
不幸中の幸いというべきか、あのヴロックはどうやら客たちを逃がさないために当面は扉の前に居座り続けるつもりらしい。
だがもし気が変わって、客たちの真っただ中に飛び込んで鉤爪や嘴を使い始めたら、十数秒のうちに死体の山が積み上がることだろう。
なんとしてでも、これ以上の惨事は防がなくては……。
「ギキィィィ……、」
ヘルマスは、自分の足元でのたうつ2人を救おうと駆け寄ってくるディーキンを嘲笑った。
嘴を醜くゆがめて、金属が擦れ合うような不快な鳴き声を漏らす。
(なんとバカな小僧だ、気でも違ったか。それとも、目が見えぬとでもいうのか?
餓鬼の分際で、このワシからこ奴らを救えるつもりか?)
ディーキンが既にぐったりしている女性の元に手を伸ばそうとした瞬間、ヘルマスは無造作に、右足で彼を蹴りつけた。
鋼板をも引き裂ける鋭い鉤爪が、ディーキンの喉笛に迫る。
だが、ディーキンはそれを自分の手で押さえるようにして難なく掻い潜ると、女性をさっと抱き抱えた。
そのままもう一人の男性の方に、跳ぶようにして移動する。
(……何ぃ!?)
ヘルマスは、ただの無謀な子どもと思っていたディーキンの予想外の動きに驚いた。
だが、次の瞬間には自分めがけて2本の短剣が飛んできたために、注意がそちらに逸れた。
煩げに腕を一振りしてまとめて叩き落とすと、攻撃者の方を睨む。
-
「くっ……!」
目を向けられたトマは、それに臆することなく真っ向から睨み返しながらも、悔しげに顔をゆがめた。
足元に駆け寄るディーキンに魔物の注意が逸れたと思った瞬間を狙って、2本の短剣を投げつけたのだが……。
魔物は予想以上に素早く反応して、簡単にそれを叩き落してしまったのだ。
恩人であるディーキンの無事にはほっとしたが、これでもう、自分には手持ちの武器がない。
もっとも、どのみち彼の攻撃では、当たったところでろくな効果は望めなかっただろう。
単なるナイフや拳銃程度の武器では、その分厚い外皮とダメージ減少能力の前にはほとんど歯が立たないのである。
事前に対サキュバス用にとディーキンが渡していた“冷たい鉄”製の短剣も、ヴロック相手にはとりたてて有効な武器ではないのだ。
(たかが血の詰まった肉袋の分際で、うっとおしい奴ばらが……)
ヘルマスは苛立たしげにトマの方を見やる。
次いで足元にもちらりと目をやって、どうしたものかと考えた。
本当ならば今すぐに飛んで行ってあの男を八つ裂きにし、腸を食いちぎって殺してやりたいところだが……。
しかし今、この扉の前から離れて、せっかくの獲物どもを逃がすリスクを負うのは面白くない。
小賢しい真似をしてくれた報いを存分に味わわせてやりたいところだが、まあ他にも獲物はいくらもいるのだし、こだわることもあるまい。
足元の小僧と残り2人は、後回しでもよかろう。
あの餓鬼はどうやら、見た目とは少々違う相手のようだが……。
どうせいくら頑張ったところで、自分の胞子が既に体内を食い荒らし初めている以上は、あの連中は助からぬ。
必死に救おうと手当をしてもどうにもならぬという無力感を存分に味わわせてから、じっくりと嬲り殺しにしてやるのも一興だ。
そう結論したヘルマスは、先程の客に対してしたのと同様に、トマに対しても《念動力》で攻撃をかけることにした。
(ちと味気ないが、貴様はこれでも食らっておけ!)
精神を集中させ、内なる“力”を呼び起こす。
ただそれだけで、トマ自身が先程サキュバスに対して投げたナイフや、散乱した瓶やフォークなどが、ふわりと浮かび上がる。
気分的に声を出したり腕を振るったりすることはあるが、本来疑似呪文能力にはなんの詠唱も動作も必要ないのだ。
それらの即席の矢弾は、次の瞬間、ヘルマスの意志に従って四方八方からトマに襲い掛かった。
トマは寸前で気が付いて慌てて身をかわそうとするが、周囲全方向からの攻撃は避けきれるものではない。
それらの矢弾が彼を襲おうとした、まさにその瞬間。
突然屋内には似つかわしくない突風が吹きつけ、攻撃の軌道を逸らせて、彼の身を守った。
「ぐ……っ!」
だが、屋内ゆえに『風』の魔法が十全な威力を発揮しきれなかったのか。
一陣の突風が過ぎ去った後、逸らし損ねた一本のナイフがトマの左腕に浅く突き刺さっていた。
先程のサキュバスとの戦いでも肩に傷を受けていた彼は、苦痛に呻いてその場に膝を落とす。
「トーマス!」
先程の突風を吹かせたタバサが、トマの本当の名を呼んで彼の下に駆け寄った。
彼女は既に、その給仕が子どもの頃に自分とよく遊んでくれていた、兄のようだった年上の使用人であることに気が付いていた。
懐かしい思い出が胸をよぎったが、今は昔話に興じていられるような状況ではない。
「すぐに手当てを」
傍に駆けつけると、怪物の視界に入らないように彼を机の陰に引き寄せて、『水』の治癒魔法をかけようとする。
しかし、トーマスは無理に笑顔を浮かべると、それを手で制した。
「私のような者のことを覚えていてくださって光栄です、シャルロットお嬢様。ですが、私は大丈夫です。
それよりもディーキンス様を。あの化物を相手に、お一人では……」
タバサはそう言われて、はっとした。
そうだ、彼を手伝わなくては。
他の客たちを助けようとして、今も頑張っているはずだ。
相手が何者であれ、あの人だけに危険な仕事をさせておくことはできない。
トーマスの方は、もう大丈夫だ。命に関わるほどの怪我ではない。
-
「わかった、あなたはここで待っていて」
「そうなのね、お姉さま。
早くこれを着て、お兄さまのお手伝いをするのね!」
そういって先程脱いだシャツやマントを運んできてくれたシルフィードに対して、タバサは首を横に振った。
「そんな暇はない」
確かに今のシュミーズ姿のままでいることは恥ずかしいが、物事には優先順位というものがある。
彼女の気遣いは嬉しいが、トーマスを助けるためならまだしも、着替えなどをするために行動を遅らせるわけにはいかない。
結局、あの女の正体……自分にはいまだによく分かっていないが、何かの怪物……を暴いて、実質的に片を付けてくれたのはあの人だった。
トーマスがこうして自分の元に来てくれたのも、きっと彼のお陰なのに違いない。
本来ならば、これは自分の任務だというのに、だ。
(また、あの人に大きな借りができた……)
だからこそ、このまま彼の世話になりっぱなしでいたくない。
なんとかして、彼の力になりたい。
本来ならば自分の力など、必要ないのだとしても……。
タバサはそんな決意を胸に、ぐっと杖を握り直して立ち上がった。
一方、何らかの邪魔が入ったためにトーマスを仕留め損ねたヘルマスは、苛立たしげに舌打ちをした。
だが、さらに追撃をかけようかと思った、その時。
自分が目を逸らしていた隙に、足元でディーキンが妙な動きをしていたのに気がついた。
いつのまにか荷物を探って取り出したらしい小瓶の中の液体を、ぐったりした女性の全身にふりかけていたのだ。
彼女の全身に絡みついた醜い蔦は、その液体に塗れるや否や、急速に枯れて崩れ去っていった。
(こやつ……!)
まさか、聖別された水によって自分の胞子を取り払えるということを知っていたとは。
一時的に助け出されるくらいどうでもよいといえばよいのだが、だからといってこのままみすみす取り逃がすのは面白くない。
ヘルマスはディーキンが助け出したばかりの女性と、もう一人の男とに止めを刺すべく、両足の鉤爪で2人を踏み躙ってやろうと考えた。
しかし、彼がまさに2人の胸を押し潰そうとして足を持ち上げた、その瞬間。
「《ソード・オヴ・カフレイ》!」
ディーキンは彼らの手をしっかりと握って、すばやく《次元扉(ディメンジョン・ドア)》の呪文を完成させた。
「……タバサ、ディーキンはすぐに戻るから!
だからちょっとの間だけ、こいつの相手をお願いするよ!」
最後にディーキンがそう言った、その直後に3人の姿は空間に開いた扉の奥に飲み込まれて、その場から消え去った。
ディーキンとしては、本当は逃げ出したりせずに、この場で直ちにヴロックを片付けたかった。
しかし、その間にヴロックが倒れている2人の方を目標にする可能性も高く、危険が大きい。まずは、無関係の客の命を救うのが最優先だ。
ゆえに、一刻を争う状態の女性の方を聖水で治療した後、2人を連れて一旦退くことを決断したのである。
場所を変えて残る男性の方からも胞子を取り払い、彼らに最低限の治療を施して、命の危険が無くなり次第すぐに戻って来るつもりだった。
ディーキンはこの事態の責任が自分にあるとは思っていても、だから自分一人で戦うべきだ、などとは決して考えない。
そんな独り善がりな責任の取り方をしようとすれば、往々にして余計に事態を悪化させ、かえって仲間に迷惑を掛けることになる。
もちろん、タバサらに負担をかけることに対して、心苦しい思いはある。
だが、互いに支え合うのが仲間だ。自分は自分の責任を果たし、その間、他の仕事については仲間を信頼する。それが冒険者というものだ。
-
ヘルマスは、驚きと困惑とで3人がいた辺りをまじまじと見つめながら、しばし物思いに耽っていた。
(あの小僧……)
ワシの能力の性質を知っておる上に、《次元扉》の呪文まで扱えるほどの術者であったのか。
さてはあ奴も、リスディスめを仕留めたらしい先ほどの男の仲間か?
確かに先程の男だけでは、あの小娘を屠るにはいささか力不足のように思えたが……。
そう考えていた時、ふと妙な気配を感じた。
(ぬ?)
怪訝に思って顔を上げると、長い杖を持った、小柄な薄着の少女の姿が目に入る。
その少女は、次の瞬間杖の先に絡み付かせた槍のような氷柱を、こちらに向かって放ってきた。
ヘルマスは咄嗟に体を捻って、その攻撃を間一髪で避ける。
氷柱は背後の扉に命中して、その表面を大きくへこませた。
(小癪な……!)
今の攻撃が何かは分からなかったが、おそらくは秘術呪文の使い手か。
さては先程、ナイフ使いの男を仕留めようとした時に邪魔を入れたのも、この小娘だったのか。
ならば、どこへ消えたのかわからぬ小僧は後回しだ。
(貴様から先に、八つ裂きにしてくれるわ!)
ヘルマスは嘴の端を歪めて、タバサの方へ向き直った。
攻撃を避けられたにもかかわらず、タバサの気分はむしろ高揚していた。
(あの人は、私に“お願いする”と言ってくれた)
別に、勇気を鼓舞する詩を歌われたわけではない。励まされたのですらない。
ただ一言、そういわれただけなのだが。
正直なところ、彼は自分の力など、必要としていないのではないかと思っていたのだ。
だが、彼は私にこの場を頼むと言ってくれた。
彼は私を信頼してくれていたのだ。気持ちの面だけではなく、力の面でも。
ならば、私はそれに答えるまでだ。
敵は謎めいた術を使う、正体不明の魔物だ。果たして自分が勝てる相手かどうかも分からない。
そんな状況であるにもかかわらず、タバサはかすかな笑みを浮かべてさえいた。
恐怖はない。かといって、これまでそうしてきたように、心を雪風で凍てつかせているわけでもない。
ただ、不思議と高揚しているのだ。状況を考えれば、不謹慎なほどに。
タバサが任務の時にそんな気分になったことは、これまで一度もなかった……。
-
テレキネシス
Telekinesis /念動力
系統:変成術; 5レベル呪文
構成要素:音声、動作
距離:長距離(400フィート+1術者レベル毎に40フィート)
持続時間:精神集中の限り(最大で術者レベル毎に1ラウンドまで)、または瞬間
術者は精神集中することで、物体やクリーチャーを動かすことができる。
選択したバージョンによって、術者は穏やかで持続的な力を及ぼすことも、一瞬荒々しく押す力を1回だけ及ぼすこともできる。
持続的な力は、術者レベル毎に25ポンド、最大で375ポンドまでの物体を、1ラウンドあたり20フィートまでの速度で動かすことができる。
クリーチャーは自分の所持している物体に対する効果を、意志セーヴに成功することや呪文抵抗で無効化できる。
このバージョンは術者レベル毎に1ラウンドまで持続するが、術者が精神集中を解けば切れてしまう。
対象の物体を片手で扱っているかのようにレバーやロープを引っ張ったり、鍵を回したり、物体を回転させたりすることもできる。
ただし結び目をほどくなどの細かい作業をする場合には、【知力】判定が必要となる。
また、敵に対して持続的な力を使うことで、突き飛ばし、武器落とし、組みつき(押さえ込みを含む)、足払いを試みることもできる。
術者は一度に呪文のすべての力を使って、術者レベル毎に1つ、最大で15個までのクリーチャーや物体を目標に対して投げることもできる。
術者は術者レベル毎に25ポンド(最大で15レベル時の375ポンド)までの合計重量を投げつけることができる。
目標に与えられるダメージは、どんな形状や密度の物体を投げるかによって変わってくる。
アイテムを目標に命中させるためには、術者は攻撃ロールに成功しなければならない。
呪文の重量制限内ならばクリーチャーを投げつけることもできるが、クリーチャーは意志セーヴに成功すれば効果を無効化できる。
要するに、ス○ーウォーズのジェダイやシスが使うフォースのような真似ができる呪文だと思えばよいだろう。
-----------------------------------------------------------
今回は以上になります。
また、できるだけ早く続きを書いていきますので、次の機会にもどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、失礼します……(御辞儀)
-
おつです
>ス○ーウォーズのジェダイやシスが使うフォースのような真似
サイオニック勢「ガタッ」
-
皆様、お久し振りです。
よろしければ、また21:00頃から続きを投下させてくださいませ。
-
招来されたヴロックとタバサとが、雑然としたカジノ場の中で、若干の距離を置いて対峙した。
最初に放った氷の槍を避けられたタバサは、すぐさま次の呪文の詠唱にかかろうとする。
今度は、比較的詠唱が短くて済み、かつほとんど不可視で回避の困難な空気の鎚、『エア・ハンマー』を放つつもりだった。
それで魔物の体勢を崩させて、更なる追撃に繋げようというのだ。
だが、タバサが連続で攻撃をかけるよりも、ヴロックが内なる“力”を呼び起こす方が早かった。
奈落の魔物が内在する魔力を高め、解き放つと同時に、その姿が何重にもぶれる。
僅か一瞬のうちに、ヴロックはその数を7体にも増やしていた。
「……!!」
それを見たタバサは、驚愕に目を見開いた。
離れた場所に身を潜めていたメイジの一人もまた、その光景を見て、悲鳴のような声を上げる。
「へっ、遍在!? ……し、しかも、6体も同時に!」
『ユビキタス(遍在)』の呪文は、『風』系統のスクウェア・スペルだ。
ひとつひとつが意思と力とを持つ、自身の分身体を作り出す。
その強力さゆえに、風のメイジが己の系統こそ最強であると主張する際にしばしば引き合いに出す、奥義とも呼ぶべき呪文である。
だが、強力であるぶん負担も大きく、長時間・長距離の維持や、多数の同時使用は難度も消耗も飛躍的に増す。
通常はごく近距離で一度に1〜2体、余程腕の立つ術者が数ヵ月かけて蓄えた精神力を放出しても、せいぜい4〜5体が関の山だ。
それを、こともあろうに、一度に7体とは……。
自分たちの扱う系統魔法を遥かに超えた所業を見て、メイジが悲鳴を上げるのも無理からぬことだといえよう。
悪名高いエルフでさえ、果たしてそれほどの真似ができるものかどうか。
(気圧されては、駄目)
相手の強さがどうであろうと、自分は戦うしかないのだ。
心を乱したままでは、それこそ勝てない。
タバサは内心の動揺を努めて押さえると、完成した『エア・ハンマー』をその中の一体に向けて放った。
「ラナ・デル・ウィンデ」
杖から放たれた不可視の空気の鎚は、狙い違わず目標を捕える。
だが、その途端にエア・ハンマーに打たれた魔物の姿は、ふっと掻き消えてしまった。
どうやら本体ではなかったらしい。
「「「「「「キシシシシ……、シャアアァァ!!」」」」」」
残る6体の魔物たちは一斉に身を震わせ、タバサに向けて嘲笑うような鳴き声を上げる。
しかし、優秀な風のメイジとしての鋭い知覚力と観察力とを備えたタバサは、それを見て妙なことに気が付いた。
(動きが、まったく同じ……?)
遍在は、それぞれが個別の意志を持ち、独立して動ける分身体のはずだ。
しかるに6体の魔物はすべてがまったく同一の動きをしており、声までもがまったく同じように重なっていた。
それに注意深く風の動きを探ってみると、巨体の魔物が6体も近くに寄り集まっているにしては、空気の動きの乱れが妙に少ない。
エア・ハンマーを受けただけであっけなく消滅してしまったのも、妙だ。
たしかに遍在も、概ね風によって構成されているために、見た目よりも実体は希薄である。
ある意味では風船のようなもので、本体に比べればかなり脆い。
だが、それにしても、殺傷力のほとんどないエア・ハンマーを一回受けただけで消え去ってしまうほどに脆くはないはず。
(あの分身は、遍在とは性質がまるで違うということ?)
そんな疑念を抱いていたところに、ヴロックからの反撃が飛んできた。
《念動力(テレキネシス)》の能力によって、カジノ内の食器や酒瓶、テーブルなどが、四方八方からタバサ目がけて襲いかかる。
「デル・ハガラース」
タバサは襲い来る攻撃に備えて素早く『ライトネス(軽量)』の呪文を唱え、身を軽くした。
そうして縦横無尽に動き回って攻撃を回避し、避けきれないものはさっと物陰へ滑り込んで、遮蔽物を盾にしてかわしていく。
ある時はまるでバネ仕掛けの人形のように跳ね、ある時は綿埃のようにふわりふわりと舞う。
それでも避けきれないと見れば素早く杖を振り、突風で攻撃の軌道を逸らせる。
体術と魔法との、見事な組み合わせであった。
-
そうして避けながらも、タバサはヴロックの作った分身の性質を、冷静に分析していく。
(攻撃の数は、増えていない)
先ほどトーマスに仕掛けた攻撃と、飛来してくる物の数はほとんど変わらなかった。
6体も存在しているのだから、もしも遍在と同様にそれぞれが攻撃を仕掛けられるのなら、到底かわしきれない数になっているはずだ。
と、いうことは……。
あれらの分身体は、風の動きを乱すこともないほどに非常に希薄で脆く、攻撃もできないということだろうか?
もしもそうであるのならば、そこまで恐れることはないだろう。
とはいっても、敵の本体がどれかを見極められないために、攻撃を無駄打ちさせられてしまうのは厄介だ。
風の動きだけを頼りにしてタバサに分かるのは、ある程度離れている敵の大まかな位置程度である。
ごく近くに寄り集まっている6体の魔物のうち一体どれが本物なのかを、戦いながら正確に断定する、などということはできないのだ。
であるならば、まとめて始末すればよいのだが……。
しかし、複数の攻撃を同時に放つタイプの呪文は総じて比較的高レベルであり、相応に長めの詠唱時間を必要とする。
敵の攻撃を回避するためにも呪文を必要としている現状では、そのための余裕がない。
そうなると、一体一体始末していくしかないことになるが……。
果たして敵の分身体をすべて始末するまで、自分は持ちこたえられるのだろうか。
一度でもまともに攻撃を喰らってしまったら、それまでだ。
体力と体格に劣る自分では、些細なミスでも容易に致命傷を受けてしまう。
自分の置かれている状況が依然としてかなり不利であることに、タバサは内心焦りを覚えていた。
ただディーキンが戻ってくるまで持ちこたえればいい、それが自分の役目だ、という考えは彼女の頭にはなかった。
一人で戦うことに慣れているゆえに失念しているのか、あるいは彼に頼らず自分で何とかしてみせたいという、無意識の対抗心からか……。
タバサは剥き出しの左脚をナイフに掠められながらも、反撃に氷の矢を一本飛ばして、またひとつ分身体を消した。
一方でヴロックのヘルマスも、内心苛立ちを募らせつつあった。
(小娘が……!)
あの小娘は、小癪にもこちらの《念動力》による再三の攻撃を凌いでいる。
しかも、《鏡像(ミラー・イメージ)》の守りも何体か消された。
まったくもって、腹立たしい限りだった。
この扉を封鎖することなどもう止めて、すぐにでも飛びかかっていって引き裂いてやろうかという誘惑にかられる。
実際のところ、ヴロックは何度でも、それも何らの消耗もなく、《念動力》や《鏡像》の疑似呪文能力を使うことができる。
だから、一方的に体力や精神力を消耗しているタバサのほうが明らかに不利な立場であり、状況は別段悪くはない。
焦らずにこのまま持久戦に持ち込んでも、じきにタバサが疲れ切ってミスを犯し、打ち倒されるだろう。
しかし、殺害欲を満たしたくてうずうずしている今のヘルマスにとっては、たかが数十秒であれ、おあずけを食らうのは我慢ならなかった。
この場を離れずに、さっさとあの餓鬼を片付ける方法はないものか。
そう思案を巡らせるヘルマスは、ふと、タバサの持っている杖に着目した。
あの小娘は、自分の知らぬ奇妙な呪文を使うようだが……。
見たところではどうもあの杖が、焦点具として必須なのではないか。
少なくとも、これまで呪文を使う際には、常にあれを振るっていた。
《念動力》で物を投げつけても呪文で対応されてしまい、なかなか直撃させられないが、その呪文が使えなければ……?
(試してみる価値はあろうて)
ヘルマスはにやりと嘴の端をゆがめると、次の《念動力》の狙いを決めた。
「……!?」
タバサは、突然自分の携える杖に、もぎ取るように横へ引っ張る力がかかったことに意表を突かれた。
相手の動向には常に注意を払っていたし、死角から急に物品が飛んで来ないかを警戒して、空気の流れの変化にも気を配っていた。
また、先ほど銃を発砲した客がされたように、自分自身の体を持ち上げてどこかに叩きつけられそうになったらどうするかも想定していた。
だが、迂闊にも杖の方を狙われる可能性は、考えから抜け落ちていたのである。
-
もっとも、考えていたところでどうにもならなかったかもしれない。
物品を飛ばしてこられたなら、避けるなり風で軌道をそらすなりして対処ができる。
自分の体をどこかに叩きつけられそうになっても、『念力』で止めるなり風のクッションを作るなりで対応はできるだろう。
しかし、呪文を使うために必要な肝心の杖そのものをもぎ取られそうになったら、どうすることもできない。
風の防御は不可視の力を遮る役には立たないし、念力で対抗しようにも、それに必要な杖自体を引っ張られていては難しい。
せいぜい意思力で呪文の効果をはねのけるか、自分の頼りない腕力で抵抗するくらいしかないだろう。
系統魔法の『念力』でも同じような事ができなくはないのだが……、射程距離や精度、即効性等の関係で、あまり実戦的ではないのだ。
(杖を取られたら、終わり……!)
杖が無ければ自分に勝ち目はない。父様の形見でもあるこの大切な杖を、あんな化物に奪われてなるものか。
タバサは自分にそう言い聞かせて必死に精神を集中し、杖を握る手に一層力を込めて、呪文の効果を振り払おうとした。
時間にすれば僅か一秒にも満たぬ攻防だったが、タバサにはひどく長く感じられた。
やがて、杖に絡み付いた不可視の力は急にほどけて離れていった。
どうやら耐え抜くことができたらしい。
タバサはほっとして息をつく暇もなく、直ちに反撃のための呪文を紡ぎ始めた。
今ならば、飛来物を逸らしたり身を軽くして攻撃を避けたりするための、防御用の呪文を紡ぐ必要はない。
絶好の攻撃の機会が訪れたのだ、逃すわけにはいかない。
「ラグーズ・ウォータル・イス・イーサ・ウィンデ……!」
呪文の完成と共に多数の氷の矢が四方八方に散らばり、5体の魔物めがけて周囲から殺到する。
タバサお得意の、『ウィンディ・アイシクル』だった。
「「「「「……グオォオォォッ!?」」」」」
突然の反撃に、ヴロックは怒りと驚きとが入り混じったような唸り声を上げた。
無数の氷の矢が、僅かな間、水蒸気の煙幕を作り出す。
それが晴れた後には……。
元通り一体だけになった魔物が、目に怒りを湛えて佇んでいた。
《鏡像》の疑似呪文能力によって作り出された幻影の分身体は、今の攻撃によってすべて破壊されたのである。
「……」
しかし、それを見てもタバサの表情にはさしたる快哉の色もない。
確かに分身体を取り除くことには成功したものの、一緒に攻撃に巻き込まれた本体はまったくの無傷だったからだ。
気を緩めることなく、ぐっと杖を構え直す。
タバサはそうして相手の動向に注意を払いながらも、頭の中では次の手を検討していた。
どうやらあの魔物の外皮は、予想以上に頑強なようだ。
一本一本の矢の威力が低いウィンディ・アイシクルでは、急所にでも当てない限り効果は期待できないだろう。
しかし、急所を正確に狙うとなると遠距離からでは厳しいが、あの魔物はどうみても接近戦を仕掛けるには危険そうだ。
(次は、『ライトニング・クラウド』? それとも、『ジャベリン』?)
それらの呪文はウィンディ・アイシクルとは違って単発だが、急所を狙わずとも高い威力がある。
普段の自分は手数で押すことが多いが、現状では一撃の威力が重要だ。
分身体をすべて消滅させた今ならば、狙いをつける上での問題はないだろうが……。
問題は、はたしてあの魔物が今一度長い詠唱の機会を与えてくれるかということだ。
(糞餓鬼めが、ワシにどこまで楯突くか……!!)
ヘルマスは、胸中に怒りを煮え滾らせていた。
目の前の小娘は、生意気にも自分の術に抵抗してみせた上に、反撃まで浴びせてきたのだ。
たとえ害はなかったにせよ、許しがたい態度だった。
もう、我慢がならぬ。他の連中のことなど後回しだ。
今すぐあの小娘の腸を引き裂いて喰らい、その血で羽根を洗ってくれよう。
たかが人間の分際で、偉大なる魔族である自分に対して分を弁えぬ反抗をしたことを、奈落に堕ちてから後悔するがよい。
『ワシはお前を殺すぞ、小娘!
殺して、その柔らかい腸を喰らい尽くしてくれる!』
-
ヘルマスはその恐ろしい宣言を、タバサの心の中に直接送り込んだ。
殺す前に、彼女をより怯えさせようとしてのことだった。
ヴロックには、サキュバスとは違い、どんな言語でも話すことができるような能力はない。
だがテレパシーの能力によって、何らかの言語を有するいかなるクリーチャーとでも、意志の疎通を図ることができるのだ。
タバサは突然自分の中に響いた不快な金切り声に、一瞬たじろぐ。
しかし、いつまでもそれについて考え込んでいるような余裕はなかった。
その次の瞬間には、翼を広げたヘルマスが自分の方に向かって猛然と突っ込んできたからだ。
とっさに杖を振るい、『エア・ハンマー』を叩きつけて魔物を迎撃しようとする。
だが、それは誤った選択だった。
風の鎚は魔物の体表に触れるや否や、何の衝撃も与えずに形を失って流れ去ってしまったのである。
「!?」
タバサはヴロックの持つ、生来の呪文抵抗力を克服するのに失敗したのだ。
しかし彼女は、目の前の魔物がそんな能力を持つことなど知らない。
そのため、風の鎚をかわすでもなく、受けて堪えるでもなく、まったく何の影響も受けずに突進してくるヴロックに驚愕した。
咄嗟に飛び退いて爪をかわそうとするが、『ライトネス』の呪文無しでは素早い一撃を避けきれない。
剣呑な鉤爪によって、腹部を掠められた。
魔物の宣言通りに腸を引き出されるまではいかなかったが、シュミーズが裂けて血が噴き出す。
「っ……!」
タバサは片腕で腹を押さえ、痛みに顔をしかめながらも、必死に杖を構えた。
どうにかして、体勢を立て直さなくては。
だが、眼前に迫ったこの恐るべき魔物から、今更逃れられるだろうか。
ヴロックの背後では、状況を見守っていた客たちが早速扉へ殺到して、逃げ出そうとしている。
タバサとしては、別に彼らを不人情だ不道徳だと責めようとは思わなかった。
居てくれたところで役に立つとも思わないし、むしろさっさと逃げてくれた方が守る負担が掛からないのでありがたい。
タバサは、このような窮地にあってさえも、他人を頼みにしてはいないのだった。
『終わりだ、小娘!
お前の魂なぞ、永遠に奈落で苦しむがいいわ!』
勝ち誇ったような言葉をタバサに送りながら、ヘルマスは両腕を広げて彼女に躍り掛かろうとする。
その四肢すべての鉤爪と嘴とによる多重攻撃にかかれば、タバサのか細い体など、ものの数秒で完全に引き裂かれてしまうだろう。
だが、そうはならなかった。
突然横合いから皮袋のようなものが飛来し、ヘルマスの頭部に命中して弾ける。
真っ赤な液体が流れ出して、彼の目に鼻に降りかかった。
「ギィッ!?」
完全な目潰しにはならなかったものの、視覚と嗅覚とに唐突にノイズが混じり、不快な痛みが走る。
ヘルマスは呻き、手で顔を擦って液体を落としながら、皮袋の飛んできた方を睨んだ。
そこには、シルフィードに肩を支えられながら立つ、トーマスの姿があった。
「怪物め、お嬢様に手はかけさせん……!」
「そうなのね、お姉さまから離れるのね!」
タバサは、ヴロックの注意が一瞬自分から逸れた、その好機を的確にとらえた。
今のうちに逃げる? いや、それでは事態は何も変わらない。
反撃をして、この怪物を倒さなくては。
(ありがとう、トーマス、シルフィード……)
自分に思いがけない救いの手を差し伸べてくれた2人に、心の中で感謝しながら。
タバサは、速やかに身を捻って呪文を唱えた。
-
「ラグーズ・ウォータル・イス・イーサ・ウィンデ」
唱えた呪文は、先程と同じ『ウィンディ・アイシクル』だった。
だが、今度は空気中の水蒸気を凝固させるのではない。
呪文が完成すると同時に、ヘルマスの顔にこびり付いた手品用の血糊の水分が瞬時に氷結して、複数の氷の矢に姿を変えた。
何本もの真っ赤な矢が至近距離から魔物の顔に襲い掛かり、目や鼻孔の周囲をずたずたに裂いていく。
「ギャアァアァァ!?」
奈落の強大な魔物は、紛れもない苦痛の叫びを上げた。
怪物自身のおぞましいほどにどす黒い血液が噴き出して、その顔を再び濡らしていく。
魔物は悶えながらも、盲滅法に腕を振り回した。
タバサは魔物から飛び退いて、距離を取るようにしながらその腕を掻い潜る。
だが、鋭い鉤爪が一度、右肩を掠めた。
シュミーズの肩紐が切れ、激痛が走って血が溢れ出す。
タバサはそれを庇う様子も見せなかった。
自分のことに構っていては、反撃の好機を逃してしまうことになる。
タバサは気力を振り絞ってもう一度杖を振り、更なる追撃をかけた。
絶叫する怪物の嘴の奥にある、汚らしい唾液らしき液体を鋭い氷の矢に変えて、喉の奥へと飛び込ませる。
氷の矢が喉を貫くか、内臓をずたずたに切り裂くかすれば、いかな怪物とて生きてはいられまい。
ヴロックは痙攣するように身を震わせ、その嘴の奥からどす黒い血がごぼごぼと溢れだしてきた。
(勝った……)
タバサはそう確信すると、ようやく張り詰めていた気を緩め、床にへたり込んだ。
同時に、それまでは戦いの高揚で半ば麻痺していた痛覚が悲鳴を上げ始めて、一瞬気が遠くなりかける。
魔法の助けを借りたとはいえ激しく動き回った肉体的な疲労、そして精神的な消耗。
脚、肩、そして腹に受けた傷も決して浅いものではなく、無残に裂けた薄手の衣服に血が滲んでいた。
しかし、直後にそんな彼女の目を一瞬で覚まさせる凄まじい怒号が、心の中に響き渡った。
『ヴオォォオオオオオォオオオ!!!!!』
それはヴロックからのテレパシーだったが、もはや声ですらない。
タバサでさえ思わず身を竦ませ、全身の血が凍りつくような思いを味わう、純然たる怒りと憎悪の雄叫びだった。
「そ、んな……」
一旦安堵して気を緩めてしまったタバサは、即座に反撃の気力を奮い起こすことができなかった。
彼女らしからぬ呆然とした呟きを漏らして、目の前の魔物を見上げる。
ヴロックの目は半ば潰れかかり、怒りに歪んだ顔はあちこちずたずたに裂けて、どす黒い血がこびりついている。
砕けた氷の矢の破片を吐き捨てる嘴は憎々しげに歪み、その奥からはごぼごぼと黒い血を溢れさせている。
だが、それほど傷つきながらも、巨体に漲る生命力は依然として衰えた様子もなく、煮え滾る怒りに身を震わせていた。
オーク鬼やミノタウロスのような、彼女の常識の範囲内にある頑強な生物であれば、先程の攻撃で仕留められていただろう。
だが、異界の生物の超常的なまでの生命力とダメージ減少能力との前には、今一歩及ばなかったのだ。
ヘルマスは怒りに身を震わせながら、タバサの方にじりじりと歩み寄っていく。
八つ裂きにしても飽き足らぬ小娘だったが、その涼しげな顔に初めて浮かんだ明らかな恐怖の感情を味わうのは心地よかった。
それが幾許かは受けた苦痛を和らげてくれたが、こいつが自分に対して犯した、万死に値する罪の償いにはならない。
こいつは嬲り苛み、喉が潰れるまで命乞いの悲鳴を上げさせてから叩き殺してやろうと既に決めている。
それからゆっくりと柔らかい肉と腸を喰らい、血を飲んでこの傷の痛みを癒すのだ。
そんなおぞましくも甘美な計画を思い描いてタバサににじり寄るヘルマスの前に、突然邪魔者が飛び込んできた。
タバサよりもずっと小柄な人間の少年のようで、一見ひどく頼りなく見えるそれは、もちろんディーキンだった。
《次元扉(ディメンジョン・ドア)》の呪文を使って帰還すると、即座に駆け出して、ヴロックとタバサの間に割って入ったのだ。
「遅くなってごめんなの、タバサ。みんな。
……やいこら、あんたの相手は今からディーキンがするの!」
「ふうむ、異界の来訪者ですか。なかなか斬り裂き甲斐がありそうな相手で。
しっかりと握って振り回してくださいよ、コボルド君」
ディーキンが携えたエンセリック(今は長剣の姿をしている)が、暢気そうにそんな注文をつけた。
《清浄なる鞘(セイクリッド・スキャバード)》による祝福の効果で、今は漆黒の刀身から仄かに清浄な白い輝きを放っている。
-
(先程の小僧か……、どいつもこいつも、愚か者どもが!)
貴様らはただ我ら魔族に弄ばれ、殺されるだけが運命の家畜でしかないというのに。
それが身の程も弁えず、偉大なる自分の邪魔立てをするから、なおさら苦しんで死んでゆくことになるのだ。
ヘルマスは激情にまかせて、邪魔者に踊り掛かった。
ディーキンもまた両手でエンセリックを構え、ヴロックに飛び掛かるようにして迎え撃つ。
そうして両者が交錯する瞬間、ヘルマスは初めて、間近でディーキンの目を見た。
(……!?)
それまでは何も知らぬ、無邪気で無力な小僧としか見えなかった少年の目。
その瞳の中に燃える怒りの光。魔族のそれとはまったく違う、他人のために燃え上がった炎の輝き。
それが、まるで自分への確実な破滅の宣告であるかのように思われた。
ヘルマスの中に沸き上がっていた憎悪と怒りが、瞬時に凍りつくような恐怖と困惑にとって代わる。
(馬鹿な……!)
千数百年もの間奈落の闇に潜み、脆弱な種族の血肉を存分に喰らってきた、このヘルマスが。
こんな幾十年も生きておらぬような、物質界の下等な種族の、ちっぽけな餓鬼から。
まるで死王魔族(バロール)や赤死鬼王(モリデウス)に対峙した時の如き、威圧感を感じるなどとは……。
「ディーキン……」
杖にすがりつくようにしてどうにか立ち上がろうとしていたタバサは、彼の姿を認めるとか細い声を漏らした。
胸中では、安堵と不安の入り混じったような、複雑な思いが渦巻いていた。
彼の強さは理解しているが、はたしてあの常軌を逸した魔物と戦って、無事でいられるのだろうか。
(あの人を、手伝わなくては)
そう思って杖を構え直すタバサは、その時ディーキンと魔物とがお互いに飛び掛かり合い、交錯したのを見た。
ほぼ同時に繰り出された魔物の両脚の鉤爪を掻い潜り、右脚を蹴るようにして懐へ飛び込む。
その勢いのまま胸板に剣を深く埋め、そこに振るわれた両腕の鉤爪を剣を軸に回転するようにして避ける。
そうして虚しく交差した腕を、胸板から引き抜いた剣を目にもとまらぬ速さで振るって叩き斬った。
最後の反撃として繰り出された嘴も足で蹴り上げて軌道を逸らし、逆にその小さな口を大きく開いて、剥き出しになった喉笛に食らいつく。
タバサにかろうじて追えたのは魔物とディーキンの身のこなしだけで、素早く振るわれた剣閃は見切れなかった。
呆然と見守る彼女の目の前で、両腕を失った魔物はひゅうひゅうと喉を鳴らし、嘴からごぼりと血を溢れさせて、仰向けに倒れる。
自分に起きた運命が信じられないと、その驚愕にゆがんだ顔が物語っていた。
ヴロックの屍はそのまま、霞のように薄れて消えていった。
物質界へ送り込まれた活動体がすべての生命力を失ったことで、招来の効力が切れたのである。
奈落にあるヘルマスの本体は何の害も受けてはいないが、少なくとも敗北感や恐怖を味わわせることはできたであろう。
「なんだ、もう終わりですか。思ったより斬り応えのない輩でした」
そう言ってぼやくエンセリックを鞘に納めると、ディーキンはタバサに向かって頭を下げる。
それから、すぐに残る負傷者の手当てに向かっていった。
「……すごい……」
タバサはぽつりと呟いて、そんなディーキンの姿をただじっと見つめていた。
自分が、自分たちがあれだけ手こずった怪物を、彼はただの数秒で仕留めてしまったのだ。
少し前までの自分なら、劣等感や悔しさで心をかき乱されていただろう。
今でも、そんな気持ちがまるで無いわけではない。
それでも、タバサがディーキンを見る目は、この短期間の間に随分と変わっていた。
まるで、彼自身が語る、物語の中の英雄のように。
あの『イーヴァルディの勇者』のように。
彼はあの恐ろしい魔物をこともなげに倒して、自分を助けてくれたのだった。
-
ミラー・イメージ
Mirror Image /鏡像
系統:幻術(虚像); 2レベル呪文
構成要素:音声、動作
距離:自身(本文参照)
持続時間:術者レベル毎に1分
術者は自分そっくりの虚像を、自分の周囲5フィート以内に1d4+術者レベル3レベル毎に1体(ただし最大で8体まで)作り出す。
虚像は術者の行動をそっくりに真似、術者と同じ音を出すので、視聴覚によっては本物と虚像とを識別することはできない。
術者は虚像と混ざり合ったり、互いに通り抜け合ったりすることで、いずれが本物かを一旦見破った敵をも再び混乱させることができる。
虚像はそれをターゲットとした攻撃が命中すれば消滅するが、範囲攻撃に巻き込まれても消滅しない。
ブレス・ウェポン
Bless Weapon /武器祝福
系統:変成術; 1レベル呪文
構成要素:音声、動作
距離:接触
持続時間:術者レベル毎に1分
この呪文は1つの武器を、悪の存在に対して正確無比な一撃を与えられるようにする。
悪の属性を持つクリーチャーに対して使用する際、対象の武器は善の属性を持つ魔法の武器であるものとして扱われる。
また、この武器による悪の属性を持つ敵に対するクリティカル・ヒット・ロールはすべて自動的に成功する。
ただし、クリティカルに関する他の魔法的な能力を既に持っている武器に対しては、この最後の効果は適用されない。
この呪文は、パラディンにしか使うことができない。
ディーキンが所持している《清浄なる鞘》は、収めた武器に合言葉でこの呪文の効果を与える鞘である。
鞘には武器を清潔かつ鋭利に保つ効果もあり、剣でも斧でも、双頭武器でも、どんな武器にでも合うようにその形を変えられる。
値段は4400gp(金貨4400枚)で、マジックアイテムとしては高価な部類ではない。
ヴロック(凶鳥魔族):
サキュバスと同様、奈落界アビスに棲まうデーモンの一種族で、副種別としてはタナーリに属する。
鉤爪の生えた逞しい四肢と羽毛に覆われた大きな翼、ハゲタカの頭を持ち、身の丈は8フィートもあって、鳥人めいた姿をしている。
並みの人間以上に知的ではあるが凶暴で戦闘好きであり、より強力なデーモンに衛兵や戦場における飛行強襲兵として仕えることが多い。
その体は善の属性を持つ武器によってでなければ容易に傷つかず、呪文抵抗力によって弱い呪文を水のように弾く。
加えてサキュバスと同様の耐性やテレパシーの能力も持っている(これらは一部の例外を除いてすべてのタナーリに共通した特徴である)。
数種類の有用な疑似呪文能力を持ち、おぞましい胞子をまきちらして周囲の者を殺害し、聞く者を朦朧化させる絶叫を上げる。
しかし、最も恐るべきは翼や瞬間移動を用いたその機動力と、強靱な五体から繰り出される近接攻撃であろう。
また、3体以上で手をつないで3ラウンドの間特殊な踊りを行うと、周囲30フィートを薙ぎ払う強烈な衝撃波を発生させることができる。
危機的な状況に際しては、アビスから同族や下位のデーモンの招来を試みることもできるが、成功率はあまり高くはない。
なお、招来された存在は自身の招来能力を使ったり、瞬間移動をしたりすることはできない。
彼らはデーモン全体としては中の下程度の強さだが、およそ尋常な人間の太刀打ちできる相手ではない。
平凡な傭兵などでは、数十人でまとめてかかっても返り討ちにされるのが関の山である。
ヴロックは、サモン・モンスターⅧの呪文で招来することができる。
-
今回は以上になります。
それでは、またできるだけ早く続きを書いていきますので、次の機会にもどうかよろしくお願いいたします。
失礼しました……(御辞儀)
-
おつです。
死王魔族はサルバトーレのダークエルフで見た覚えがあるけど
赤死鬼王って何に出た奴ですか?
-
>>659
あー、それはですね……
実はその漢字の名称は私の勝手な創作です
ヴロックのもですけど
サキュバスやバロールだけ漢字名があって、モリデウスやヴロックにはカタカナだけというのも見栄えが悪いかな、と思ったもので
-
了解ですー
回答ありがとうございました
-
おつです
-
乙です
-
こんにちは、暗の使い魔です。
よろしければ22時30分頃から投下させてください。
-
狭く長い階段が、延々と上に続く。建物の隙間を縫うように築かれたそれを、複数の足音が駆け上がった。
僅かな月明かりに照らされながら、その六人、官兵衛一行は息を弾ませて、真っ直ぐに桟橋を目指していた。
先頭をワルドが駆ける。後をルイズ、タバサ、キュルケ、ギーシュと続き、最後尾には官兵衛が居た。
官兵衛は鉄球の鈍さもあるが、近接戦闘を得意とするために殿をつとめた。
後方に注意を傾ける官兵衛。風の流れで、周囲の動きを察知するワルドとタバサ。
気の休まらない行軍が続いた。
そして駆けること十数分、遥か上方に階段の切れ目が見えてきた。
もうすぐか、と官兵衛が息を切らして、そのさらに上を見上げた、その時だった。
「なっ!なんだコイツは……!」
彼は息を呑んだ。
そこにあったのは、月明かりに照らされた巨大な影。百メイルをゆうに超え、天まで届かんとする大樹であった。
四方八方に枝が伸び、空を掴まんとしている。そして良く見ると、その枝には果実のように、無数の帆船がぶら下がっていた。
官兵衛は思った。
「(これが『桟橋』か、驚いたな……)」
なるほど、船は船でも天駆ける船。そして発着場は高く聳える巨木ユグドラシル。
山を登らねば辿り着けないわけだ、と納得した。
長い階段を登り終え巨木が近づく。黒く影をつくる幹、その根元に僅かな明かりが灯ってるのが見えた。
どうやらあそこが入り口らしい。
一同は、周囲を見渡しながら、素早く巨木の中へ駆けて行った。
中に入ると、そこは吹き抜けの広大なホールになっていた。
見上げれば天井は見えず闇が広がる。
大樹の幹をくりぬいて作られたその空間に、再び驚く官兵衛。
「こっちだ」
不意に、ワルドが方向を指し示す。そこには、木で出来た階段があった。
隣の壁には、鉄の板に文字が書かれたものが貼られており、船の行き先を示しているらしかった。
見上げると、階段は遥か上の枝にまで続いてる。
ギシギシとしなる階段を、登り始める一同。官兵衛は、鉄球の重みで階段が崩れやしないか、と不安に思いながら後に続いた。
官兵衛達は、ただひたすら上へと上り続けた。
暗の使い魔 第十八話 『ユグドラシルの攻防』
上り始めて約十分。まだ船は見えず、下を見れば黒一色の世界があった。
周囲にはくもの巣のように、桟橋への階段が張り巡らされている。
しかし、メイジでもないかぎり、落ちたら一巻の終わりだ。
「ハァ……」
「どうしたね?」
目前を走るギーシュが、官兵衛のため息に振り返った。
「いやなに。こういう場所じゃあ、小生が落っこちるのが容易に想像できてな」
官兵衛の言葉に、ギーシュが笑った。
「なんだい?君は高いところが苦手なのかい?」
「違うわ。小生のツキを象徴してるようで嫌なんだよ」
官兵衛が吐き捨てるように言った。なるほど、下に広がる闇は奈落を思わせ、地獄まで続くように錯覚させられる。
官兵衛の不運を考えると、彼は真っ先に引きずり込まれそうである。
そう思うと、彼は不安に駆られずにはいられなかったのだ。
それを聞いてギーシュが言う。
「まあ安心したまえよ。一見頼りないが、意外と頑丈なんだぜ?この階段」
ギーシュがニヤニヤ笑いながら、激しく足踏みした。
「おいおいよせ!」
官兵衛が上ずった声で止める。それを見て、ギーシュはますます笑みを浮かべた。
「やっぱり怖いんじゃないかね!大丈夫だとも!ゴーレムでも現れない限り壊れは――」
その時だった。先を走るタバサが別の気配を察知したのは。
「来る」
「え?」
タバサが短く呟く。ギーシュが慌てて振り向いた。
その瞬間、どおん!と桟橋の階段全体に激震が走った。
「う、うわああああっ!?」
木の階段が、激しく軋んで揺れ動く。油断していたギーシュが、慌てて柵につかまった。
突然の出来事に動揺しながら、一向は衝撃の原因を探した。目前の階段、数十メイル先を見やる。
するとそこに白黒の甲冑の男が、薙刀を携えて佇んでいた。
闇に溶け込むようにたたずむ男は、薙刀をリズミカルに振るいながら、こちらに対峙している。
「新手か」
ワルドが敵を見て呟いた。
「平民の傭兵かしら?メイジ相手にたった一人なんて……」
ルイズが警戒しながら言う。しかしタバサが、即座にその言葉を否定した。
「一人じゃない、三人」
「え?」
タバサの言葉に、ルイズが辺りを見回す。官兵衛が後ろを振り返った。
するとそこには、いつの間に現れたか、同じ甲冑に薙刀を構えた傭兵が。
「挟み撃ち!?こんな場所で!」
ギーシュが叫んだ。
-
だが問題はそこではない。敵の残り一人の居場所だった。
官兵衛が、鋭くその気配を察知し、叫んだ。
「ルイズ、タバサ!上だ!」
官兵衛が言うと同時に、タバサとワルドが動いた。タバサは自分のいた場所から一歩背後に飛ぶ。
ワルドはルイズを抱えた。その瞬間、二人が居た場所に白刃の一撃が降ってきた。
轟音とともに階段が揺れ、埃が舞い上がった。そのあまりの出来事に、ギーシュが悲鳴をあげた。
恐るべき力で、刃が階段を割る。
メキメキと音が鳴り、階段に激しいヒビ割れが走った。
「いけない!」
キュルケが叫んだ。
各々が即座に詠唱を完成させ、フライで飛び上がる。ワルドはルイズを抱えたままで飛び、官兵衛は即座にその場で跳躍した。
すると、数十メイルに渡って伸びていた足場が、音を立てて崩落した。奈落に吸い込まれるように、階段が落ちていく。
ギーシュは宙に浮かびながら、青ざめた表情でそれを見ていた。官兵衛が壁にしがみ付き、手近な階段に飛び乗る。
キュルケとタバサは、一番近い数メイル下の階段に着地した。
そしてワルドが、上方に張り巡らされた別の階段に移るのを見て、ギーシュもそれに従おうと浮遊した。
その時、キュルケが叫んだ。
「ギーシュ!危ない!」
「へ?」
キュルケの言葉にギーシュが側方を振り向き、そして目を見開く。
なんと彼の目前に、薙刀を構えた男が迫っていた。
「なっ!?う、うわああああああっ!!」
驚愕し、声をあらんばかりに張り上げる。
ギーシュが居る位置は、崩落した階段の中腹。つまり空中だ。
階段が崩れた今、足場は無いはずなのにそこに敵がいる。
そしてその敵は今にも、その手にした得物でギーシュを叩き斬ろうとしていたのだ。
慌てて薔薇の造花を振り、回避を試みる。しかし、敵が一瞬早かった。
キュルケやタバサが呪文を詠唱するが間に合わない。
風を切り、数サント鼻先に刃が迫った。
「まずは一人」
まるで手作業を確認するかのように、淡々と男が呟いた。
斬られる――ギーシュが思ったその時、鈍い衝撃音が、その場に響き渡った。
「斬られっ!………へ?」
なんと目前の男が、黒い塊を胴体に受け、彼方へと吹き飛んだのだ。
甲冑の傭兵が、遥か下の闇に消えていく。
鎖つきの鉄球が敵をなぎ払うのを見て、ギーシュはそれの飛んできた方向を見やった。
「き、君!」
ギーシュが叫ぶ。
そこには、やや高い足場から鉄球を振るう官兵衛の姿があった。
「た、助かった」とギーシュは安堵した。しかしキュルケらの声で現実に引き戻される。
「ギーシュ!はやくこっちに」
見ると、数メイル下方に張られた階段で、キュルケとタバサが背中を合わせて周囲を警戒していた。
素早く二人のもとに降り立つギーシュ。彼はそんな二人に向かって言った。
「君達、こんな所にいないで、早く上に!桟橋に行かないと!」
しかし、その言葉をタバサが遮った。
「駄目」
「どうしてだね!?」
ギーシュが尋ねる。タバサに代わり、キュルケが答えた。
「狙い撃ちにされるわ」
キュルケの言葉に、えっ?と疑問符を浮かべるギーシュ。珍しく真剣な表情で、キュルケが続けた。
「わからない?あの妙な格好の傭兵達、闇の中からこっちを狙ってるわ。
フライで上に行こうとすればたちまち飛び掛ってくる」
「なんだって?」
ギーシュはそれを聞いて言った。
「冗談はやめたまえ!メイジじゃあるまいし、魔法無しでぼくらに飛びつこうだなんて――」
そのとき、ギーシュの言葉を遮るように、下方に無限に広がった闇の中から、影が飛び出てきた。
「なっ!」
ギーシュは驚愕に目を見開いた。
その影は、桟橋中に張り巡らされた階段を、ムササビのように渡りながら、こちらに向かってきたのだ。
階段同士の距離は数メイルから数十メイル。にもかかわらずそれを、脚の跳躍だけで飛び越える。
そして影は、彼らから三十メイル程離れた場所でバネのように身を屈めると、弾丸のような速度で一直線にこちらに飛んできた。
キュルケが即座に炎を放ち迎撃する。灯りに照らされ、ドクロの様な惚面が闇に浮かび上がった。
炎の塊と薙刀が交差する。
しかし炎は刀で受ける事は適わず、そのまま男の身体を包み込んだ。灼熱に身を焼かれ、下へと落ちていく男。
その姿は、再び闇の中へ掻き消えていった。
一連の攻防を見ていたギーシュは、震える声で言った。
「今のは、一体!?と、ととと飛んできた!魔法も無しに!」
「だから言ったでしょう?」
キュルケが油断なく杖を構えながら言う。
-
先程ギーシュに襲い掛かった傭兵も、このようにして空中の彼に迫ったのだ。
「フライで飛んでる隙に、あんなのに飛びかかられちゃたまったもんじゃないわ。だからうかつに上に行けない訳」
メイジは通常、フライを唱えてる最中の魔法の詠唱が難しい。飛んでる最中に狙い撃ちされれば、非常に分が悪いのだ。
敵の新たな攻め手を三人が警戒している時、上のほうから声がした。
「無事か!お前さん達!」
官兵衛の声だった。それを聞き、三人が顔を見合わせる。
キュルケが、三人とも無事である事を伝えると、官兵衛もこちらは皆無事である事を伝えてきた。
「こっちに来れるか!?」
「ちょっと取り込んでて無理ね!しつこくアプローチしてくる方々のせいよ!」
キュルケが軽口を叩きながら言う。そして、上で待ちあぐねている官兵衛らに伝えた。
「ダーリン!ルイズ!悪いけど私達、ここでお別れよ!」
「ちょっと、どういうことよキュルケ!」
ルイズの鈴のような声色が、ホール内にこだまして良く響いた。
「この面倒な方々は、ここで私達が食い止めるわ!その間に桟橋に向かって!」
キュルケが続ける。
「私達はあなた達が何しにアルビオンに行くか知らないし、これでいいのよ!
あ、言っておくけど残るのはダーリンの為よ!貴方の為じゃないからね!」
キュルケの勇ましげな言葉に、ルイズは唇を噛んだ。
キュルケは家同士の因縁もあり、普段喧嘩してばっかりで、お世辞にも仲が良いとは言えない。
タバサだって、普段無口で殆ど話した事は無い。ギーシュなんてキザで女の子に目が無い見栄っ張りだ。
それでも、これまで学院の日々を共に過ごしてきた仲間である。
任務の為とはいえ、こんな危険な場所に皆を残して行くなんて、とルイズは思った。
「ルイズ、ここは彼らに任せて先に行こう」
そんな彼女の心情を察してか、隣でワルドが囁いた。
肩にやさしい手の感触がかかる。
ルイズは意を決すると、下で奮戦しているキュルケらに対して言った。
「かならず追いつきなさいよ!あんたみたいなのでも、何かあったら後味悪いんだから!」
ルイズの言葉に、キュルケはフッと笑った。
「おい金髪の!行き先は昨日話したよな!迷子になるなよ!」
次に官兵衛が、ギーシュに向けて言い放つ。
ギーシュがわかったと返事をすると、官兵衛達は一目散に上を目指し始めた。
「どうするんだね?」
ギーシュが二人に問う。
「決まってるじゃない。無粋な御仁にはお帰り願うわ」
キュルケが杖に火を灯しながら、笑みを浮かべた。
「まずはこの暗闇ね。こんな場所でさっきみたいに飛び掛ってきたら困るから……」
そういうと、キュルケは杖を振るった。杖先に灯った炎が打ち上げられ、辺りを真昼のように照らす。
「姿を現していただくわ」
階下の階段に、薙刀を携えた二人の傭兵が見えた。
突然照らされたため動揺しているのか、下からこちらの様子を窺う二人。
とその時、タバサが不意に視線を持ち上げ詠唱を開始した。彼女の周りに、無数の氷の刃が形成されていく。
膨れ上がった魔力に乗り、氷の刃がある方向へ吸い込まれるように飛んだ。
そこには、階段を伝い上へと向かおうとする一人の影があった。手には薙刀ではなく太刀を手にしている。
先程頭上から奇襲し、階段を崩落させた男だ。
男は向かってくる氷刃に気づくと、一直線に太刀を振るった。
ぶおんっ!
と剣筋が風を呼び、無数の氷の矢を逸らす。
先頭の氷矢がクルクルと回り、あらぬ方向へと弾け飛んだ。
しかし、防いだ氷の矢はブラフ。後ろに隠れるように放たれた氷の矢が男をとらえ、正確に鎧の隙間を貫いた。
「ぬ……っ!」
太刀の男がうめく。
装甲の間から血を噴出しながら、彼はぐらりと体勢を崩した。
タバサの研ぎ澄まされた技量を窺わせる、実に緻密な攻撃であった。
「やった!」
ギーシュが声をあげる。強力なトライアングルスペルは喰らったら致命傷である。ひとまずこれで一人が片付いた。
彼はそう思った、しかし。
「……まだ」
タバサが感情なく呟く。
「なんだって?」
ギーシュは首を傾げた。
ある程度の手傷は負わせたはずである。常人が動ける負傷ではない筈だ、しかし。
「……」
-
負傷した影が、ゆっくりとこちらを向いた。チャキリと刀を反す音が鳴る。
そしてその刹那、男は跳躍すると瞬時に、タバサたちが陣取る足場に降り立った。
彼女らの目前、数十メイルの場所に、男の姿が灯りによって鮮明に映し出された。
両者の間に緊張が走る。
「あら、ようやくご対面ね」
キュルケが、これまで散々姿を見せなかった男を、小ばかにしたように言った。
しかし、そんな言葉を気にした風もなく、甲冑の男はゆっくりと佇んでいた。
タバサはそんな男を注意深く観察する。
見ると鎧兜の隙間から、黒髪の長髪が伸びている。手にした太刀は三日月のように光を反射し、中々の業物を思わせた。
そして負傷の具合を探る。先程の魔法の矢は致命傷には程遠く、わずかに甲冑を血で染めただけのようだ。
さらには魔法をその身に受けても怯まない、強靭な精神力。
どうやらこの男が、この三人のリーダー格であるようだった。
「中々やるな、予定が狂う」
歳若い男の声が、惚面の奥から発せられた。
「お生憎様、あなた方のご予定にお付き合いするほど暇ではございませんの」
キュルケが杖を突きつけて言い放つ。しかし、それを意に介した様子も無く、男は口を開く。
「だが、これまでだ」
すると、階下から猛烈な勢いで飛び上がる影が一つ。下で様子を見ていた二人の薙刀の男の一人だ。
そしてもう一人、階段を素早く駆け上がってくる男。
二人は、男の言葉に呼応するように背後に降り立った。
「命を請え」
背後の一人が、呟きながら得物を鳴らす。
「泣き喚け」
もう一人も同じように喋りだす。
三者は、長髪の男を先頭に並ぶ。そして舞うように身を翻し、横一列に並んだ。
「「「我らは死神、三好三人衆。主の命により、お前達を闇に葬らん」」」
一定の調子で奏でられる鍔鳴り音が、不気味に響き渡った。
「ミヨシ三人衆……」
キュルケ達に緊張が走る。バラバラだった男たちが揃い、目の前に現れたのだ。
普通のメイジなら、たかが平民の傭兵ごとき束になってもメイジの前には適わない、と思うだろう。
しかしこの三人が醸し出す雰囲気は、平民のそれとは比べ物にならない危険を感じさせた。
加えてメイジ殺しを遥かに上回る、人間離れした身体能力を見せ付けてくる三者。
彼女たちは、各々杖を構えた。
「タバサ、作戦は?」
「各個撃破」
「そ、それだけかね?」
タバサのあまりに簡潔な一言に、ギーシュはよろめいた。しかし、気を取り直すと杖を振るった。
二つの花びらが散り、ワルキューレを形成する。
手には柄の長い戦斧を携えた戦乙女が、凛々しく立ち上がった。
ギーシュは高らかに言い放つ。
「無礼な賊共!先程は遅れを取ったが……この青銅の戦乙女、ワルキューレが揃ったからには、好きにはさせないぞ!」
勇ましく口上を述べる。しかしポーズを決めようとして、階段に片足を乗せるも、その足は震えていた。
ギーシュの斜め後ろで、キュルケがため息をつく。
三好三人衆は、淡々と言葉を発した。
「人形遊びか」
「児戯だな」
「手早く終わらせよう」
それを見て、三人衆は跳躍した。
「一体何のマネだねあれは?」
それは、実に不可解な行動であった。三人衆は、長髪の男を頂上に肩車をして見せた。
縦に連なる三者は、少しも乱れず、見事な感覚で肩に足をのせ直立する。
「なんだね?まるで平民がやるような大道芸だ」
ギーシュは首を傾げた。三人衆は、手にした得物を縦に連なるように合わせる。
そしてその穂先と柄尻をカシリと繋げて見せた。
するとどうであろう。
二本の薙刀と、一本の太刀が合わさり、9メイルにも及ぶ一本の大薙刀が出来上がったではないか。
連なった三者に大薙刀。それが堂々と屹立する。
そんな一連の動作を気にも留めず、ギーシュはワルキューレに突撃を命じた。
「合体してみせたつもりかい?よくわからないが、いけっワルキューレ!あの三人を突き崩せ!」
突撃するワルキューレを見て、男達の目が殺気に満ちた。
いけない!――キュルケは叫んだ。
-
「危ない!下がってギーシュ!」
彼女が叫ぶと同時に、それは起きた。
「「「ゆくぞ」」」
三つの声が重なり響く。
肩車をした三人衆がその場で、車輪のごとく旋回した。
周囲の空気がゆっくり、しかし徐々に速くかき回される。
ぎゃるぎゃるぎゃる!と、刃と地面が擦れる。
乱雑な摩擦音が響き、煙が舞い起こった。
ワルキューレの目前で完成した『それ』。それは、長さ9メイルに及ぶ、白刃のかまいたちであった。
輝く刃が風車のごとく旋回し、迫りそして――。
ずぎんっ!ずぎぎぎぎん!
ミキサーのように目前の全てを切り刻んだ。
壁も、足場も、ゴーレムも、そしてゴーレムを操る者自身も。
「え?」
粉微塵になった青銅の塊を蹴散らして、呆気に取られたギーシュに刃が襲い掛かる。
タバサが咄嗟に、威力を抑えたエア・ハンマーをギーシュに向けて放った。
「うわあっ!」
間一髪、ギーシュは横殴りに風を受け、階段から空中へと投げ出される。
そして吹き飛ぶギーシュの横スレスレを、刃となった三人衆が通り過ぎた。
タバサとキュルケも階段から空中へ身を投げ出して、それを回避する。
その時だった。三好三人衆が即座に合体を解除し、空中に身を躍らせた三人に狙いを定めたのは。
「しまったわ」
キュルケは舌打ちした。あの三人の狙いは自分達を空中へおびき出すことだったのだ。
空中で呪文を使えない自分達を、狙い撃つ為に。
それを証明するかのように、三人衆の一人が跳んだ。狙いは、僅かな精神力で宙を舞う彼、ギーシュだった。
「くっ!」
「弱者より消え行くのが戦の常。悪く思うな」
淡々と語る三好。このまま援護しようにも、空中では思うように魔法が撃てない。キュルケは歯噛みした。
男の刃が、静かに吸い込まれるように、ギーシュを貫いた。
「うわあああああっ!!」
ギーシュの叫び声が、ホールに響き渡った。その時だった。
「何?」
ギーシュに一撃を加えた男は、目を疑った。己の武器を持った腕に、巨大な氷の槍が突き刺さっていたのだから。
「これ、は?」
どくり、と血が滴り落ちる。氷の槍がずぶりと、肉を抉った。その感覚に、負傷した腕が武器から離れた。
そして男は、背後に冷気を感じて振り返った。そこには。
「ッ!?」
風に唸る杖の先端が、目前に広がっていた。
ドゴン!と鈍い音がして兜がひしゃげる。
兜の隙間から血を噴出しながら、その男は意識を手放した。
意識がなくなる直前、鮮やかな青色の髪が視界の端に映った。
長髪の男は、その瞬間を逃さず目撃していた。
三好の三男があの金髪の貴族を貫こうと、飛び迫った瞬間。
視界の遥か上から、人の脚ほどある氷の槍が降り注いだのを。
それが三男の腕を貫き、攻撃の狙いを逸らせたのを。
そして、ツバメのごとき速度で降下した青髪の少女が、勢いのまま杖を頭部に叩き込み、弟を葬り去ったのを。
隣に控えた次男はあまりの速さに、何が起こったのかすらわからず、ただ闇の底に落ちていく三男を見つめていた。
長髪の男――三好の長男は、落ちていった三男を見た後、宙に浮かぶキュルケらに目をやった。
「潰えたか?」
「わからぬ」
キュルケらを見つめながら、次男は長男に語りかける。三男は頭を砕かれ落下していったが、死んだかは分からない。
分かるのは、この場でこちらが一人が欠けた。そんな状況だった。
キュルケが足場に降り立ち、二人の男に対峙する。そしてゆっくりと力強く、呪文を唱え始めた。
階下では、ギーシュを抱えたタバサが彼の傷を見ている。
「あらあら?少々おいたが過ぎるんじゃあありませんこと?」
キュルケが冷ややかな笑みを浮かべながら、三好の二人を見据えた。
-
しかし彼女は笑ってはいるが、内心は溶岩のような怒りが支配していた。
自分のクラスメイトに傷を負わせた傭兵風情、このゲルマニアの炎で骨の髄まで焼き尽くしてやる。
そんな感情が渦巻いていた。
そんな彼女の怒りを察してか、次男が武器を構えたまま後退する。
すると、キュルケの杖先から炎が伸び、三好の背後に炎の壁を作った。
「どこへ行かれるのかしら?このわたくし主演の歌劇はこれからでしてよ?」
キュルケの底冷えするような笑みが、次男に恐怖の感情を芽生えさせた。
「おのれ……!」
次男が奥歯を噛み締めながら、キュルケに踊りかかった。
頭上から一直線に薙刀を振るう。
かなりの大振りだが、しかしその速さは達人のそれに近い。
初撃で仕留めるべく、渾身の力が籠められた一撃だった。
その華奢な杖ごと頭を裂いて葬ってやる。そう次男は思った、しかし。
がしん!とその一撃はあっけなく受け止められた。キュルケは涼しい顔で、横にした杖で薙刀を受け止め、次男を見据えた。
「何だと……!?」
「あらあら?か弱い女一人手篭めに出来ませんの?随分と期待はずれな御仁ね」
この女のどこにこんな力が。次男はそう思いながら歯噛みした。
キュルケが男の薙刀を弾き返し、その無防備な身体を炎であぶる。
即座に熱せられた鎧が次男の全身を焼いた。
「ぐおおおおっ……!」
あまりの熱にその場に倒れ伏す次男。そして歩み寄る足音に見上げれば、そこには赤毛を逆立たせたメイジの女が見下ろす。
その目に、目前の獲物を品定めする獣のそれを感じ取り、次男は声を上げた。
「ひっ!」
キュルケの杖先に再び炎が宿る。小さな火種は徐々に膨張し、直径一メイルはあろう大きさにまで膨れ上がった。
次男は恐怖に震え、とうとう命乞いを始めた。
「ヒッ!命は、命だけはっ!」
「あら、死神と名乗っておいていまさら命乞い?
オホホホ、どこの生まれか存じませんけど、随分とつまらない冗談を口になさるのね?ミヨシ?」
「ち、違う!俺はミヨシなんとかとは関係ない!そいつに、そこの黒髪に雇われただけだ!」
離れた場所の黒髪の甲冑を指差しながら、男は喚いた。
「俺はただのハルケギニアの人間だ!メイジ殺しなんて呼ばれちゃあいたが、ニホンの人間なんかじゃない!」
「ニホン?」
その言葉に、キュルケの眉が釣りあがった。ニホン、間違いでなければ官兵衛のやってきた国の名だ。
そこの人間ではない、とはどういう事だろう?
「何をおっしゃってるのかさっぱりだわ?そのニホンがどうかしたのかしら?」
それに対して、男は震えながら喋り続けた。
「知らねえのか?バカみたいに強いやつだよ!
俺みたいなメイジ殺しなんか、いやメイジなんか及びもつかねえ程な!俺みたいな裏の人間ならよく知ってる!」
まくしたてる男に、キュルケはさらに質問した。
「へぇ、そう。その人間が他にも居るって訳ね?」
「そうさ!そこの黒髪や、噂じゃあ今アルビオンで内戦中の――」
その時、ドス!と鈍く貫く音が聞こえた。ぶしゅう、と液体が噴出した音が響く。
ごぽごぽっ、と男の口から赤黒い液が漏れた。
男は続きを話すことが出来なかった。その喉から生えた刀の切っ先が、男のそれ以上の生存を許さなかったから。
キュルケの目の前で、鮮血を撒き散らしながら男は事切れた。ビクンビクンと痙攣した死体が、血の海を泳いだ。
その死体を冷ややかに見つめながら、男を殺した張本人、三好の長男はこう呟いた。
「我らは死を恐れない、我らは過去を忘れた、そう誓約した筈だ。それを忘れるとは……」
呟きながら、長男はもう興味なさげに、死体を蹴り飛ばす。
「メイジ殺しなど当てにはならぬ……」
ずるり、と血の跡を残し、次男だったモノは冥底を思わせる奈落へと落ちていった。
キュルケは、息を吸うように人を殺してみせた目の前の男の様に、ごくりと唾を呑んだ。
ゆらり、と長男がこちらに向き直る。白い仮面の奥の瞳が、じっとキュルケを見た。
一切の感情を宿さない、淀んだ瞳だった。たった今人を殺したにも関わらず、まるで意に介した様子も無い。
男が、キュルケを見て呟く。
「お前は我らを怖れるか……?」
淡々と、感情を込めずに口ずさむ。
「我らはお前を怖れない……」
まるで歌うように。
「怖れるとすればただ一つ……いや、言うまい」
言い終わるや否や、三好は刀を振りかぶった。
-
その荒れ狂う振り下ろしを、キュルケは即座に杖で受け止める。がしん!と鈍い音が鳴った。しかし。
「こいつ……!」
速く、重い一撃。先程の次男とは比べ物にならなかった。
キュルケは一筋の汗を浮かべ、渾身の力を込めて刀を弾き返す。
そのまま即座に距離をとり、ファイヤーボールを唱える。
燃え盛る一メイルもの炎が、長男を飲み込んだ。焼けるなんてものじゃない、炭になる程の火力だ。
そのまま燃え尽きなさい、とキュルケはそう思った。
それ程までに、目の前の男は得体が知れなかった。このまま終わってくれと、願うほどに。
上半身を炎に包まれた長男はしばらく微動だにしなかった。
しかしその次の瞬間、長男は太刀を無造作に振るった。
疾風が巻き起こり、上体を包んでいたキュルケの炎をかき消した。
「ッ!?」
キュルケが驚愕に目を見開く中、三好の長男は埃を払うように、残った火の粉をよけた。
彼女の奥歯が噛み締められる。ならばさらに強力な炎の二乗、フレイムボールで。
彼女がそう思って杖を振るった、その時だった。
三好の太刀が唸り、地面を捲り上げるように太刀が振り上げられた。
ミシミシと階段が軋んだかと思いきや、その一撃はなんと、地面を巻き上げながら進む衝撃波へと変貌。
キュルケに襲い掛かった。
「(速い!フライを――ッ!?)」
恐るべき速度で地面を這う一撃。彼女は咄嗟に杖を振るった、しかし。
「(痛――ッ!?)」
なんと巻き上がった木屑が一瞬速く、彼女の杖持つ腕を裂いていた。三好が太刀を振り上げる際、同時にこちらに飛ばしたのだろうか。
痛みで詠唱が中断される。そして。
「あうっ!」
彼女は不意をつかれ、押し寄せる衝撃波に吹き飛ばされてしまった。
数メイル程高く宙を舞い、地面に激突するキュルケ。
「ぐうっ!ん……!」
階段に身を打ち付け、思わずうめき声を上げる。
三好がそれを見て、刀を翻しながら一歩一歩と近づいてきた。
まずい、殺られる。
急いで身を起こそうとしたが、打ち所が悪かったか呼吸が出来ない。
「うっ……!」
「これ以上足掻くな。そのまま潰えるがいい」
「だっ……れがっ!」
息を切らしながら、よろりと立ち上がる。
「まさか、これで……勝った、おつもりっ、かしら?」
その手に固く杖を握り締め、キュルケは誠意一杯の抵抗を見せる。
三好は淡々と呟いた。
「終わりだ」
甲冑が軋み、男が駆け出す。振りかぶられた太刀が光を反射し、迫った。
脇腹に鋭い痛みが走る、がその痛みをごまかしながら、キュルケは身構えた。
その時であった。
ヒュンヒュヒュヒュと、自分の背後から、冷たい空気とともに無数の風切り音が聞こえた。
ハッとしてそちらを見やる。
そこに立つ小さな人影を見て、キュルケは安堵した。
「タバサ……」
タバサが、キュルケを庇うように三好と対峙していた。
-
無数のウィンディ・アイシクルを刀で捌きながら、三好は一歩、二歩と後退する。
十数メイルの距離を開けて対峙する両者。
タバサは無表情だが、見るものには分かる威圧の光を目に宿し、三好を見据えた。
そのまま、時間にして数分が経過する。
と、突如三好が空を見上げ、呟いた。
「頃合か……」
その言葉に、キュルケらも空を見上げる。するとそこには帆を広げて風を受け、アルビオンへ飛び立つ船が浮かんでいた。
速度を上げ、雲の彼方に小さく消える帆船。どうやらルイズ達は、無事出航したらしい。
標的を逃してしまった事を確認すると、三好は対峙するタバサとキュルケを見据え、静かに呟いた。
「やはり、中々やる。あの男が警戒するだけはあったな」
未だ自分に杖を向けるタバサを尻目に、三好は階段の縁に立つと、その深い闇の底へ身を躍らせた。
そして静かに、底へ底へと降下していった。
脅威が過ぎ去ったのを見て、タバサは静かに杖を下ろした。
「あいででででっ!痛い!痛いじゃないか!もう少し優しくだねっ!」
「あんた、男なんだから少しは我慢なさいな。全く!」
キュルケは呆れながら、目の前の出来事を見やっていた。
ギーシュは今タバサの手によって、負傷した傷の応急的な処置をほどこされていた。
見るとギーシュの肩には、薙刀で切りつけられた裂傷があった。
骨には達しておらず、パックリと切り裂かれたその傷からは血が滲んでいたが、軽症だった。
あの時タバサがジャベリンを放ち、攻撃を逸らしてくれていなかったら。彼はもっと重傷を負っていたに違いない。
「はあ全く、死ぬかと思ったよ……」
「なあにが死ぬかと、よ。こんなかすり傷程度であんな大声上げて。情けないわねぇ」
「だって考えても見たまえ!あんなおっそろしい連中に、精神力ギリギリで追い詰められて!殺されそうになって!
叫ばないほうがおかしいじゃないか!」
ギーシュはキュルケの言葉に、ひたすら異を唱え続けた。
タバサがギーシュの手当てを終える。
二人のやり取りを聞いて、タバサは役目は終わったとばかりに本を読み始めた。
そんな彼女を見て、キュルケが言う。
「それにしてもタバサ、ナイスだったわよ!ギーシュのときも私のときも。」
タバサは気にしないで、といった視線をキュルケに送った。ギーシュも続ける。
「いや!本当にあの時は助かったね!しかし、君はあの状況でどうやって魔法を?」
あの状況とは、ギーシュが空中で狙われたときの事だ。
フライで浮いていたにも関わらず、どうやって魔法を唱えたのかという事だろう。
あの時タバサは、フライで上へ上へと飛んだのだ。
そして程よい高さに来たところでフライを解除、ギーシュに向かって急降下した。
降下しながら恐るべきスピードで詠唱を終えたタバサは、ギーシュに殺到する刺客に向けてジャベリンを放った。
つまり彼女は、落下の時間を利用して魔法を唱えたのだ。
そしてあとは、そのままの勢いで敵を殴打して倒す。
それがあの攻防の一連の流れだった。
タバサの咄嗟の判断力が、ギーシュを救ったのだった。
そんなキュルケの解説を聞いて、ギーシュは空いた口が塞がらないでいた。
「全く、感心してないで少しは自分を恥じたら?貴方、守られてばっかりじゃない」
キュルケが指を立てて言う。そう言われたギーシュは一瞬、表情をこわばらせた。
軽く唇を噛み締め、うつむく。
「ちょっとギーシュ?」
キュルケが返事が返ってこないのをいぶかしんで呼びかける。
しかしギーシュは、すぐに薔薇を振りかざすと、口調を強くして言った。
「わかってるとも!今回は遅れを取ったが次こそは!グラモンの名に懸けて獅子奮迅の活躍を……って、いだだだだっ!」
大げさなポーズをとろうとして傷が痛んだのか、ギーシュはその場でうずくまった。
彼のキザったらしい仕草。それにいつものキレが無い事を、二人はうすうす感じていた。
キュルケとタバサはそんなギーシュを一先ず置いて、空を見上げた。
出航したアルビオンへの連絡船は影も形も無い。
追いかけるのは骨が折れそうね、と思うキュルケとタバサ。
その時、三人は桟橋の外から聞こえてくる羽音に気付いた。
-
幹の穴から外を見る。するとそこに、重なった月を背に、大きな翼を持った風竜が現れた。
タバサの使い魔シルフィードだった。口に何かをくわえているようだが、暗がりで良く見えない。
ともかく三人はホッと息をつく。そしてキュルケは声を大きくして言った。
「さあダーリン達を追うわよ!なんの任務か知れないけれど、置いてけぼりなんて冗談じゃないわ」
彼女の勇ましい言葉に、二人も頷く。三人は幹の外へ出るべく、階段を駆け上がった。
「(それにしても……あの男といい、テンカイといい。ニホンから来た連中。一体なんなのかしら?)」
キュルケは密かに考えを巡らせる。
殺された男が直前に言っていた言葉。内戦中のアルビオンに行けば、官兵衛と同じ日本の人間に会うのだろうか?
そしてその時はまた、戦いになるのだろうか?
「(このままいいようにされてたまるもんですか)」
未だ鋭い痛みを発する脇腹を、密かに庇いながら、キュルケはシルフィードに跨るのだった。
今回は以上になります。
こちらだと快適に投稿できて良いですね。
次回までにまた一ヶ月ほど間が空くと思いますが、よろしくおねがいします。
それでは。
-
乙ですー
-
こんばんは、焼き鮭です。今回の投下をさせてもらいます。
開始は23:50からで。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第七十六話「黒い牛の呪い」
牛神超獣カウラ 登場
ヤプールが消滅間際に放った怨念の欠片の最後の一つを探すグレンは、タバサとシルフィードと遭遇。
そこに老婆が助けを求めてきた。曰く、彼女の孫娘が怪物ミノタウロスの生贄に指名されてしまったという。
一行はミノタウロス退治に向かったが、その正体はミノタウロスの振りをした人さらいたちであった。
そんな悪事を見逃すグレンたちではない。人さらいたちをやっつけるが、そこに現れたのは何と本物の
ミノタウロス! 本物もいたのだ! しかもそのミノタウロスは流暢に口を利き、魔法まで使う。
明らかに普通ではない。果たしてその正体は何なのだろうか?
グレン、タバサ、シルフィードは不思議なミノタウロスに案内され、彼がねぐらにしているという
鍾乳洞の内部へ通された。
鍾乳洞の奥部は、実験室のようになっていた。ミノタウロスのサイズに合わせているのか
かなり大きい机、椅子、かまどといった家具に、ガラス壜、秘薬が摘められた袋、マンドラゴラが
栽培されている苗床まであった。
その実験室に似つかわしくないものが片隅にあった。牛の頭蓋骨や骨の山積み。その一部だけ
塚のようで、シルフィードは若干不気味に感じた。
ミノタウロスはこう名乗った。
「わたしはラルカスという。元は……、いや、今もだが、貴族だ」
ラルカス……、その名前にタバサは聞き覚えがあった。村で聞いた名前だ。
「十年前に、ミノタウロスを倒してのけたという」
「ああそうだ。そのわたしが、どうしてこんな格好をしているのか、気になるだろうな」
ラルカスは十年前の出来事と、そこから現在に至るまでを説明した。衝撃的な内容であった。
かつてラルカスは村人たちに頼まれ、ミノタウロス退治を行ったが、洞窟に火を放って
蒸し殺そうとしてもなかなか死なないミノタウロスの強靭な生命力に感嘆し、同時に目をつけた。
実はラルカスの元の肉体は、不治の病に侵されていた。そして生き延びるために、ある決断に
至ったのだ。自らの脳を、殺したミノタウロスの肉体に移植したのだ。
「驚いたかね?」
タバサたちは頷いた。
「まあ、それも無理はなかろう。しかしな、この身体はすばらしいぞ。いいかね、魔力は脳に由来する。
呪文を使うにはまったく問題がないどころか、この身体を得てからは精神力も強くなった。体力、
生命力だけでなく、魔法もさらに強力となったのだ。それからわたしはずっと、ここで研究に打ち込んでいる」
「寂しくないのね?」
「もともと独り身だ。洞窟も、城も大して変わらぬ」
話していたラルカスは突然、う、と呻いて頭を押さえた。
「どうしたのね?」
「さわるな!」
近づこうとしたシルフィードに怒鳴ったラルカスは、かまどの側にある布を被せた何かに
手を伸ばし、布を取り払った。
下から出てきたのは、生肉のブロックの山だ。シルフィードはミノタウロスの主食が人間ということを
思い出して思わず顔が引きつったが、グレンが囁きかける。
「落ち着きな。ありゃただの牛肉さ」
ラルカスは牛肉のブロックの一つを鷲掴みすると、思い切り被りついた。貴族の品格や作法など
ひとかけらもない、獣じみた振る舞いであった。
牛肉を食らうと、ラルカスは口をぬぐって改めて言葉を発する。
「失礼。見苦しいところを見せた」
「ラルカスさんとやら……あんたもしかして、ミノタウロスの本能に影響されてるんじゃねぇのか?」
グレンが問うた。ラルカスは変に否定せずに首肯した。
-
「実は、そうなのだ……。この身体の唯一の欠点が、そこだ。脳が肉体に影響されて精神力が
強まったように、脳が人間のものとなっても、ミノタウロスの人肉を食らいたいという欲求が
消えずに残ってしまってるのだ……。それを慰めるために、こうして定期的に肉に食らいついてるのだ。
生肉を食するなど貴族のすることではないので本当は嫌だが、本能に飲まれて獣に落ちるよりはましだ」
「……それで、十年もごまかせるものなの?」
今度はタバサが疑問をぶつけた。ミノタウロスが食べるのは、あくまで人間。牛でいいのなら、
全てのミノタウロスがそうしているだろう。牛の方がはるかに肉付きがいいのだから。一時的には
良くても、十年も本能を騙せるものとは少し考えにくい。
その点について、ラルカスは語る。
「如何にも、ただ別の生物の肉を食するだけでは、この忌々しい本能は抑え切れなかった。
豚や熊なども試したが、欲求は日に日に強まっていくばかり。いつか本当に人間に手を出して
しまうのではないかと、一時は夜も寝つけなかった。しかしあることを境に、状況は一変した」
言いながら、自らの右腕に嵌めた鼻ぐりを撫でる。
「ある日のこと、畜産が盛んな地方にある、牛の霊を祀る鼻ぐりの塚の側を通り掛かった際、
ふとした思いつきから鼻ぐりを一つ失敬して、こうして自身に嵌めた。ミノタウロスは牛の
怪物なのだから、鼻ぐりをすれば飼い牛のように大人しくなるのではないか……と。何とも
滑稽な思いつきだったが、わたしはそんな滑稽さにすがりつくほど心をすり減らしていた。
そして意外にもそれが正解だったのだ。鼻ぐりをつけてからは、牛肉でのみ食人の欲求を
抑えられるようになったのだ。以来、わたしは一度も人を襲うことなく今日までやっていけている。
きっと、鼻ぐりに宿った牛の霊が助けてくれてるのだろうな」
だから鼻ぐりを嵌めているのか。そういえば、最初に立ち寄った酒場の店主が、質の悪い
牛泥棒がどうこうと言っていた。
「牛泥棒の正体はあなただったのね。泥棒だって、貴族のすることじゃないはずなのね」
シルフィードが突っ込むと、ラルカスは申し訳なさそうに頭をかいた。
「そこは重々承知してるが、何分この顔では人里で買い物する訳にはいかない。金も稼げん。
悪いとは思ってるが、こうする他にないのだ」
確かに、人が誘拐されて食われるよりかは牛泥棒の方がましかもしれないが……。どうも釈然としない。
それからもう一つ、グレンが指摘した。
「ところで、何で鼻ぐりを腕に嵌めてんだよ。鼻ぐりなんだから、鼻につけた方が効果あるんじゃねぇのか?」
するとラルカスは気分を害したように鼻を鳴らした。それが牛の突進の合図のようだったので、
シルフィードは思わず怯えた。
「わたしはこんな見た目になっても貴族だ。鼻にものをつけるような真似は、貴族の矜持が許さん。
それでは丸きり牛ではないか。わたしは人間だ!」
「……」
グレンは困ったように腕を組んだ。……怪物の肉体を奪って、独りきりで閉じこもって生活し、
牛泥棒にまで身をやつしながら、貴族であることに固執するのか。虚しくならないのだろうか?
だがそこを指摘して、怒りを買ってもまずい。もしここで暴れられでもしたら、タバサたちが危ない。
「わたしの話はこのくらいでいいだろう。あの人売りどもを連れて村に帰れ」
ラルカスはそれ以上話を続けなかった。去り際にタバサたちに、わたしとここのことは
誰にも言うな、と釘をさした。
村へ帰ると、タバサたちは村人たちの歓声で迎え入れられた。捕獲した人さらいたちは
村人に散々罵られ、翌日に役人に引き渡すこととなった。
そして翌朝に村の者たちが人さらいを街に連れていき、タバサたちも同行するはずだったのだが……
昨晩から妙にふさぎ込んでいたグレンが、こんなことをつぶやいた。
「……ヤプールの結晶は、ちょうどこの辺りに落っこちたはずだ。あれはマイナスエネルギーに
引きつけられるはず……。死んだ霊の放つ強力なものには特に……」
そうして村を出発する直前に、村人たちから踵を返した。
-
「ちょっと用事を思い出した。引き渡しはあんたたちだけでやってくれ!」
言い残してずんずんと昨日の森へ向かっていく。彼の様子を気にかけたタバサとシルフィードも
後を追いかけていく。
グレンの向かう先は、ラルカスの住む洞窟だ。
その少し前、ラルカスは洞窟の中で一人、頭を抱えて苦しんでいた。
「ぐッ……はぁはぁ……一体どうしたというんだ。ここ最近、変に頭痛が激しい……。こんなに
ひどいのは初めてだ……」
ラルカスは頭痛を抑えようと、いつもやっているように牛肉へ手を伸ばした。しかし口に
運ぶ寸前になって、顔を大きく歪める。
「うッ! 嫌な臭いだ……!」
肉を投げ捨て、洞窟を出ると森の木の一本に目をつける。熱に浮かされるように、木に茂る
葉っぱにむしゃぶりつくと、恍惚の笑みを浮かべた。
「美味い!」
だがすぐに我に返り、慌てて口に含んだ葉っぱを吐き捨てた。
「馬鹿な……! 葉が美味いなんて、そんな訳があるか! これではミノタウロスどころか……
ただの牛ではないか!!」
激しく動揺するラルカスは右腕の鼻ぐりをなでるが……その時に気がついた。
「なッ……!? 鼻ぐりが締めついて、外れなくなってる……!?」
昨日までは確かに着脱可能だったのに、今は腕にきつく締まっていて取れなくなっていた。
何もしていないのに、こんなことになるはずがない。
「ま、まさか……鼻ぐりに込められた牛の霊が、怨念となってわたしを呪ってるのか……!?
勝手に鼻ぐりを持っていき、牛の肉に食らいつくわたしを、牛にしようと……。そんな……
そんな馬鹿なぁ!」
愕然と立ち尽くすラルカスだが、彼の信じたくない気持ちとは裏腹に、実際に身体が牛の方に
傾きつつあった。
「う……ん……ンモォ―――――! こ、言葉まで牛に……!?」
自分の口から、牛の鳴き声そのものが発せられたことに、ラルカスはいよいよ恐慌し出した。
「や、やめてくれ……! 誰か助けてくれぇぇぇッ!」
狂ったように喚きながら、どこかへと向けて駆け出していく。
初めは二足歩行だったが……徐々に前傾姿勢になっていき、遂には四足で走っていた。
グレンたちが洞窟に到着した時には、ラルカスは既にいなくなっていた。彼らは洞窟の前に、
大きなミノタウロスのものの足跡が連なっていることに気づいた。
「この足跡、新しい……」
「追いかけるぜ! 嫌な予感がする!」
足跡をたどって走っていく一行。その足跡が、途中から蹄に変わったことにタバサと
シルフィードは息を呑んだ。
「ひゃああああああああああッ!?」
そして前方から、人の悲鳴が聞こえた。急いでそちらへ向かうと、近くの住民と思しき
男性が腰を抜かしていた。
「そこのあんた! 一体どうした!?」
「み、ミノタウロス……いや、牛の化け物が走ってった……!」
ミノタウロス、ではなく牛の化け物、と呼んだことにグレンは青ざめていった。自分の懸念は、
的中していたのか。
三人はそれから脇目もふらず、蹄の痕跡を追うのを再開した。
その頃ラルカスは、かつて鼻ぐりを取っていった塚の前へとたどり着いていた。その時には、
彼の姿はもうミノタウロスと呼べるものでもなくなっていた。胴体だけが辛うじて人間の、人間牛だ。
「はぁ……はぁ……」
屠殺された牛たちの鼻ぐりを山にした鼻ぐり塚にすがりつき、ラルカスは叫ぶ。
「許してくれぇッ! 頼む! 牛にしないでくれぇぇッ!!」
-
だが懇願も虚しく、ラルカスの身体はめきめきと膨れ上がり、けばけばしく変色していく……!
「ブモォ――――――――!」
森の中を走るグレンたちの視界に、景色に突然立ち上がった牛のような超獣の姿が飛び込んだ。
その超獣の右腕には、鼻ぐりが嵌まっていた。
「あれは!? くそッ、やっぱりこうなっちまったか……!」
「あれってまさか、ラルカスさんなのね!?」
驚愕するシルフィード。彼女の言う通り、ラルカスはヤプールの結晶の影響によって噴出した
鼻ぐりに込められた牛たちの怨念を一身に受けたことで、恐ろしい超獣カウラになってしまったのだった!
「ブモォ――――――――!」
カウラは人の住んでいる村の方へ向かおうとしている。人間たちに殺され食べられていった
牛の呪いの化身であるカウラは、その復讐として人間を食らい尽くそうとしているのだ!
「やべぇ! 止めなくちゃなんねぇぜ!」
「頑張ってなのね、グレン!」
グレンはカウラに狙われる人々を救うため、シルフィードの応援を受けながら変身!
グレンファイヤーが飛び出していき、カウラの面前まで先回りした。
『止まれ! ここから先には行かせねぇぜ!』
「ブモォ――――――――!」
カウラは立ちはだかったグレンファイヤーに、遠慮なく突進! 鋭い角がグレンファイヤーに襲いかかる!
『ぐッ! 聞く耳持たねぇってか!』
咄嗟に受け止めたグレンファイヤーは、上腕筋を盛り上がらせて剛力を発動。カウラの突進を
押し返す。パワーファイターであるグレンファイヤーの力は、牛そのものの力が宿ったカウラにも
引けを取らない。
「ブモォ――――――――!」
しかしその時、カウラの姿が大きくぶれ、分身したように見えた! 牛たちの怨念の迫力が成せる業か!
『んッ!? 何だこりゃ、幻覚か!?』
突然の幻惑攻撃に、さしものグレンファイヤーも戸惑った。どれが本物のカウラなのか?
見抜く前に、カウラの頭頂部の中央に生えた角から紫色の光線が発射された!
『ぐわぁッ!』
光線の直撃をもらったグレンファイヤーは大きくひるむ。その隙を突いて、カウラが肉薄して
腕の先の蹄で殴り掛かってくる!
「ブモォ――――――――!」
『うおぉぉッ! くぅッ……!』
蹄の振り下ろしは最早鈍器の叩きつけだ。殴打の強烈な衝撃にグレンファイヤーも追い詰められるが、
『怨念なんかにゃ、二度と負けてたまるかぁッ! もう誰の命も、奪わせやしねぇぜッ!』
叩きのめされながら、グレンファイヤーの戦意は強く燃え上がった。その理由は、怨念の前に
大事な仲間が消え去ってしまったから。もうあんな悲劇は起こさないと、彼は誓ったのだ。その想いが、
熱い炎を作り出す! ファイヤーコアが点灯した!
『うおおおぉぉぉぉぉ――――――――――! ファイヤァァァァァァァァ――――――――――――ッ!!』
「ブモォ――――――――!!」
盛り返したグレンファイヤーの炎の拳が、逆にカウラを追い詰め始めた! 凄まじい気迫の
拳打は怨念の力を押し返し、カウラに物理的以上のダメージを与える。
戦況は一気に逆転。カウラはグロッキー状態になり、もうひと押しすれば完全に倒せる状態まで行った。
が、しかし、ここに来てグレンファイヤーはとどめを躊躇う。その理由は次の通りだ。
『このまま倒すのは簡単だ。けど、こいつはラルカスが変身したもの。やっつけちまっていいのか……!?』
-
ラルカスは、ミノタウロスの身体になり果てながらも、あくまで人間。カウラを倒すということは、
彼を見殺しにすることになる。そんなことをしていいのか。だが、カウラに宿った怨念をどうやって
晴らせばいいものか……。
手をこまねいていると、グレンファイヤーに応援がやってきた。ミラーナイトであった!
『グレン、事情は伺いました。超獣を元に戻すのは任せて下さい』
『ミラーナイト! 分かった、頼んだぜ!』
体力を戻したカウラは、新たに現れたミラーナイトへと突進を仕掛けていく。だがミラーナイトは
よけようとも逃げようともせず、視線をカウラのある一点に集中していた。
その一点とは、腕の鼻ぐり! 牛の怨念の中心がそれであると、ミラーナイトは見抜いたのだ!
『はぁぁぁッ!』
そして流れるような蹴り上げを見舞った! タイミングは見事ばっちり。つま先が鼻ぐりに命中し、
鼻ぐりは腕から外れ吹っ飛ぶ!
怨念の中心が離れたことで、カウラは一気に力を失った。
『いやぁッ! とぉあッ!』
ミラーナイトはそのままジャンプして鼻ぐりをキャッチ。そして降下しながら、それをカウラの
鼻に目にも留まらぬ速さで嵌め込んだ!
「ブモォ――――――――……」
その途端に、カウラは先ほどまで猛っていたのが嘘のように大人しくなった。鼻ぐりが本来の
位置に嵌まったことで、牛の怨念は慰められて落ち着いたのだ。
『さぁ、仕上げです。ヤプールの結晶にとどめを!』
『よっしゃあッ!』
最後はグレンファイヤーが決める。カウラの巨体を高々と持ち上げると、地面へ向けて勢いよく投げた!
その衝撃により、ヤプールの結晶は粉々に砕け散って消滅した。それにより牛の怨念も霧散していき、
カウラは元のラルカスの状態に戻った。
ヤプールの悪あがきの超獣を無事に退治したことにより、ミラーナイトは帰還していった。
グレンファイヤーも人間の姿に戻り、タバサたちの元まで駆け寄る。タバサとシルフィードは
仰向けに倒れているラルカスの側にいた。
「おーい! お前らー!」
「あッ、グレン! お見事だったのねー!」
シルフィードは戻ってきたグレンに向けて歓声を上げた。これで事件は解決……。
が、その時にラルカスが勢いよく起き上がり、タバサに飛びついた!
「えッ!? お姉さま!」
ラルカスの目は鈍く、赤く光っており、粘性の高い涎が垂れている口から言葉が漏れ出た。
「ぐぅお……わ、わたしはき、貴族……ウマソウ……人間……オマエ、ウマソウ……タベル……!」
明らかに様子がおかしい。言動がミノタウロスそのものになってきている!
「そんな……ここまで来て、ラルカスさんはミノタウロスになっちゃったのね!?」
シルフィードは“変化”を解いてタバサを助け出そうと身を乗り出した。が、それをグレンにさえぎられた。
「待て」
「どうして止めるのね!? 早くしないとお姉さまが……」
「タバサの目を見ろ」
タバサはこの状況で取り乱さず、じっとラルカスを、冷たい、蒼い瞳で見据えていた。
それに気づき、シルフィードもゴクリと息を呑みながらも見守ることにする。
「ウマソウ。ダカラオレ、オマエヲタベル……」
葛藤を見せていたラルカスだが、とうとうミノタウロスの本能の方が勝ったのか、捕らえた
タバサに対してかぶりつくように大口を開けた。
その瞬間にタバサは呪文を唱えた。
「ラグーズ・ウォータル・イス・イーサ・ウィンデ」
一瞬で、ラルカスの口腔内の涎が氷結して、“矢”へと変化した。何十本もの氷の矢は喉から
食道を通って体内に飛び込み、内臓をズタズタに引き裂いた。
ごぽっ、とラルカスが血液を吐き出し、タバサを放して横に倒れた。
-
その目から、赤い、獣の光が消えていく。ついで、ラルカスの血まみれの口が開いた。
「……これでよかったのだ。藁にもすがって、牛肉にかぶりついてごまかしても、本当のところは
自分の精神が徐々にミノタウロスに近づいていっているのは自覚していた。日に日に“わたし”で
いられる時間は減っていった。いずれ近い内に、本当に人間に襲いかかっていただろう。死のうとも
考えたが……わたしには己の命を絶つ勇気がなかった。それに比べて、少女よ、君は見事だ。
わたしはかつて火を放って洞窟内のミノタウロスを窒息させて殺したのだが……、スマートな
やり方とはいえぬな。お前のように、硬い皮膚を避けて内臓を狙うことなど思いもつかなかった」
タバサがひと言告げる。
「たまたま気づいた」
ラルカスは唇のはしをわずかに持ち上げた。笑顔を浮かべているのだった。
「礼を言うぞ。気に病むことはない。わたしは本当は、とっくに死んでいたのだ。逃げ続けていた
死がとうとうやってきただけのこと……。少女よ、最後にお前の名を教えてはくれんか」
タバサはわずかに目をつむったあと……、己の本名を告げた。
「シャルロット」
「よい名だ」
「ありがとう」
小さく、タバサは頷いた。
「ああ……、自分が自分でなくなるというのはイヤなものだな。実にイヤなものだ」
ラルカスは先ほどより大きな血の塊を、ごぽ、と吐き出した。それが合図でもあるかのように、
ラルカスの小刻みな痙攣が止まる。
ゆっくりと、徐々に、ラルカスの目から光が失われていった。
ラルカスの遺体はグレンたちによって火葬された。死を避け続けた挙句に牛の怨霊になりかけたが、
最期は人として死ぬことが出来たのは幸せだったのかもしれない。
「ラルカスさん……、自分が自分でなくなるのがイヤだって言ってたけど……、そのとおりなのね。きゅい」
シルフィードのひと言にグレンが頷く。
「そうだな。人は、どんなに辛いものでも、自分の運命にゃきちんと向き合わなくちゃいけねぇんだ。
逃げたら、きっと何かがおかしくなっちまうんだろうな」
グレンの言葉を、タバサは無言で聞いていた。
ラルカスに対して黙祷を捧げたグレンは、タバサとシルフィードに向き直る。
「……これで事件は解決だ。俺はまた旅に戻る。捜さなくちゃなんねぇ奴もいるしな……。
お前らはキュルケんとこに帰るのか?」
「うん」
「もう寄り道はしない」
タバサの言葉に、グレンはゆっくりと頷いた。
「分かった。またどこかで巡り合う時があったら……お互い力に合わせようぜ」
グレンとタバサは静かに約束を交わすと、互いの道へと分かれていった。それからグレンがつぶやく。
「ゼロ、サイト……もしお前らの運命が最悪のものでも、俺はそれにちゃんと向き合う。
向き合わなくちゃなんねぇ……。けど、そうと決まるまでは、俺は諦めないからな。
運命に立ち向かうのが、人間のすべきことなんだ!」
グレンの願いが無事に叶っているということを彼が知るのは、もう少し先のことであった。
-
以上です。
牛肉食いてぇ。
-
皆さんこんばんわ。またお待たせしてしまって大変申し訳ありませんでした、ウルトラ5番目の使い魔33話投下準備できましたので始めます。
-
第33話
暗殺指令 賞金首はあのコッパゲ!?
海凄人 パラダイ星人 登場!
今、世界が危機にさらされていることは、すでに万人の知る普遍的な常識となりつつある。
始祖ブリミルによってハルケギニアの基礎が築かれてから六千年の間、この世界はエルフとの抗争を別にすれば内側での小規模な争いだけで平穏を保ってきた。
しかし、時代は急激にかつ逆流のしようのない強さで動く。ヤプールの襲来をきっかけにして、銀河の辺境の惑星でしかなかったこの星の存在が、次元を超えた宇宙にさえ知れ渡ってしまったのだ。
貪欲な侵略者たちが、地球と同じ美しさを持ちながらも文明レベルではるかに劣るハルケギニアに目をつけないはずはない。数々の凶悪星人が現れては猛威を振るい、人々はその絶大な力に危機感を募らせてきた。
そう、ただでさえハルケギニアの多くの人々は、東にはエルフ、内には山賊やオークという避けがたい恐怖との並住を強いられているというのに、そこにさらなる重みが付加されるとあってはたまったものではなかった。
人間は生きている限り、恐怖からは逃れられない。その恐怖を和らげるためにハルケギニアの人々が頼るものこそ、始祖ブリミルの残した教えであるブリミル教であり、人々はその教えにすがり、日々を懸命に生き延びようとしている。
では、そのすがりつくべき人々の心の支えこそが、人々に対して悪意を抱いていたらどうだろう? 天上に仰ぐ白い羽を持った天子の衣の下に、黒くとがった尻尾が隠されていたらどうだろう?
ハルケギニアに脅威が迫っている。それは事実としても、人々の知る脅威は今や、虚と実のふたつに分かれようとしていた。
『空が闇に閉ざされてしまったのはエルフの仕業である! 彼らは聖地を奪い、聖地の力を利用して人間を滅ぼそうとしているのだ。今こそブリミル教徒たちは団結し、エルフを打ち倒すべし!』
天使が光臨したあの日から、このスローガンが放たれておよそ一月。聖戦を呼びかける声はハルケギニアの津々浦々に響き渡り、怒涛を生むカウントダウンに入っているように思えた。すでにガリアでは無能王転じて英雄王ジョゼフの下で全面参加が公表されて、ほかの国々でも協議が続いているが、教皇の大命に対しては抗いがたく時間の問題と思われている。
そして、その中心こそがロマリア。いまや、全世界の注目の中心ともいえるブリミル教の総本山にして、救世主ヴィットーリオ教皇聖下のおわす場所。現在では都中が熱狂に包まれ、各国から集まってきた義勇兵がロマリア軍の門戸を叩き、街中に溢れていた浮浪者たちまでもが武器をとってエルフ打つべしと気勢をあげている。
しかし、このロマリアこそが世界を闇に包み込み、破滅へと導こうとしている中心であることに人々は気づいていない。
「どうやら、あなたの可愛い吸血鬼は失敗した様子ですね」
「申し訳ありません。彼女自身はなかなかよく働いてくれたのですが、まさか新たなウルトラマンがやってくるとは。僕の想定が甘かったようです」
-
大聖堂の奥の間で、ヴィットーリオが神妙な面持ちをしているジュリオに対して言うと、ジュリオは頭を垂れて謝罪した。
彼らはすでに、先日サビエラ村で起きた戦いの詳細を掴んでいた。吸血魔獣キュラノスと化したエルザの力があれば、万一にも連中を逃すことはないと確信していたが、キュラノスは駆けつけてきたウルトラマンコスモスに敗北し、連中は全員無事で、虚無の担い手であるティファニアの奪取にも失敗した。ジュリオの目論見は完全に外れたのだった。
しかしヴィットーリオはジュリオを責めるわけでもなく穏やかに対応し、微笑んでさえ見せた。
「あなたのせいではありませんよ。そのような事態まで想定して行動できるのは、それこそ神くらいしかいないでしょう。それで、そのエルザという吸血鬼はその後どうしました?」
「怪獣化して自爆しましたが、もし爆発の直前に怪獣体を捨てて吸血鬼の姿に戻っていたら生存の可能性はありました。しかし、その後サビエラ村の周辺を調査させましたが、彼女の死体も発見できませんでした。恐らくは、本当に自爆して果てたのだと思われます」
「そうですか、この汚れきった世界を浄化するための同志として期待していたのですが残念ですね。しかし次なるウルトラマンの登場とは、どこの世界でも現れて我らの邪魔ばかりしてくる。計画を少々修正する必要がありそうですね」
ヴィットーリオは沈痛な面持ちで考え込んだ。彼らにとって、現状は有利であってもいつまた何かのきっかけでひっくりかえらないとも限らない。想定外の要素が出てきた今、可能な限り周到で用心深くあって損はない。
そう、すべては愚かな人間たちによって荒らされゆく一方であるこの星を救い、そしてこの星で蓄えた力を持って、かつて救済に失敗した別次元のあの星へと再び行くためにある。長い年月をかけて用意してきたこの計画に失敗は許されないのだ。
恐らくは、今後ロマリアをどう動かしていくのかを思案しているヴィットーリオに、ジュリオは確認するように問いかけた。
「ですが、虚無の担い手を含む一行がトリステインにたどり着くにはまだ少々の時間があります。さらなる追っ手をかけてもよろしいでしょうか?」
「いえ、それには及びません。私はあわよくば、あなたの僕に追い詰められることでティファニア嬢が新たな虚無に覚醒することを期待していましたが、生命の危機に瀕しても彼女に新たな虚無は目覚めませんでした。ここで無理に我々の手に入れても持て余すだけでしょう。強引にさらうのは最後の手段で十分です」
「わかりました。では、もうひとつのほうの工作もそろそろ始まりますが、そちらも変更なさいますか?」
ジュリオが話題を変えると、ヴィットーリオはふむと考えてから答えた。
「あの船、オストラント号への刺客のことですね。私の記憶が確かならば、ガリアのシェフィールド殿から推薦された、暗部を請け負う騎士さまたちだとか。そちらはそのまま進めてよろしいでしょう。我らにとって益にならぬとわかりきっている方々には、早々に消えてもらって間違いはありません」
「同感ですね。あの船のクルーはこの世界のレベルを大きく超えた科学技術を手に入れて、異世界に対する概念も覚えてしまっています。捨て置いて、妙なことを触れ回られては危険でしょう。人間を相手にするのには、やはりその道の人間が一番です。暗殺という手段は、この世界の権力者にとって常套手段ですから」
「同族で血で血を洗う争いを何千年も続ける。人間とはなんと愚かで醜い生き物なのでしょう。しかし彼らも、自分たちの技術が世界の救済に役立つとなれば本望でしょうね。事が終わった暁には、彼らのために祈るとしましょうか、人間の歴史を終わらせるために活躍した人間の英雄に対してね」
ヴィットーリオはジュリオと意見が一致すると、暗い笑いを浮かべた。人間をハルケギニアから消し去るために人間が活躍する、なんと滑稽なことではないか。暗殺者がどこの誰かは知らないが、仕事を終えて大金を手にした彼は、遠からずその功績を誇らしげに吹聴することができるだろう。ただしその相手は酒場の店主に対してではなく、一銭もいらずに聞いてくれる地獄の悪鬼たちに対してであるが。
-
人間とは、本当になんと愚かなのであろうか。しかし滅びる前に、もう少しくらいはいい夢を見させてあげようと、ヴィットーリオはそれでこの話を打ち切って公務に戻った。表向きの教皇としての仕事も多岐に渡り、ジョゼフのように大臣たちに任せて遊んでいるわけにはいかないのである。
ふたりがこの話題に費やした時間はざっと五分ばかり。ジュリオも報告を終えると、またなんらかの暗躍をするために立ち去っていった。
しかし彼らは決して軽く考えていたわけではない。このハルケギニアにおける暗殺の歴史は古く、長い。政争においては、ひとつしかない権力の座をめぐっての奪い合いなどは日常茶飯事であり、その手段の正当性などには関わらず、勝者、つまり生き残った者がすべてである。そのため、血を分けた肉親たちでさえ当たり前のように相手の首を狙い、歴史の影で暗殺者たちは常に牙を磨き続けてきた。
それはこのロマリアも例外ではなく、教義に反する者は異端者としてあらゆる方法で排除してきた。神の祝福を受けた聖なる都でありながら、ロマリアの歴史の血なまぐささは貴族たちに勝るとも劣らない。それをヴィットーリオは知り尽くしているために、並みの人間が暗殺という手段から逃れることがいかに困難かを熟知しており、まして刺客はあのジョゼフの配下として暗躍してきた北花壇騎士団の人間だという。狙われた人間が生きていられる可能性ははなはだ低いと考えても当然のことである。
果たして、ジュリオが放った暗殺者とは何者なのであろうか?
人間の運命は、本人と大勢の人間の意志と行動が複雑に絡み合ってできている。が、人は己の預かり知らぬところで自分に関わることが起きていても、それを感知することはできない。
だからこそ、人生は一寸先は闇であり、人は未来を恐れる。だが、先行きの保障された人生になんの喜びがあるだろうか? そこが矛盾であり、矛盾を内包しているからこそ、人はその歪みの中から善悪美醜様々なものを作り出してきた。それを、ロマリアは今、ひとつの方向へと強制的に動かそうとしている。
人間という不完全なものを排除した世界。それは神の領域である”完璧なる世界”であり、アダムとイブが去った後のエデンの園とでも言えばよいか。
しかし、知恵の木の実を食べたのは人間だけではない。この宇宙には無数の生命ある星が存在し、そこにはさらに無数の知恵ある生命が息づいている。そしてそれらの星の中には、元は楽園のような星であったのに、知的生命体の文明の暴走で滅んでしまったものも数多い。
はたして知恵とは、生命自身を滅ぼす毒なのだろうか? だがなぜ完璧で美しいはずの自然から、絶えずに知恵ある生命が生み出され続けるのであろうか? それは恐らく、滅亡のリスクを背負ってでも得なければならないものがあることを、生命は進化の過程で理解しているからなのだろう。
もし、アダムとイブが知恵の実を食べなければ、人は永遠に楽園にいられた。しかし、もしも楽園になんらかの拍子に一匹の悪鬼でも忍び込んだら、知恵なき人間ではなにもできずに餌食にされ、楽園も奪われていた。しかし、楽園から追われた人間たちの子孫は知恵を使って、悪鬼の襲撃や過酷な自然の試練を乗り越えてきた。
そう、知恵とは力であり自立の象徴なのだ。知恵があるからこそ、人間は楽園とは程遠い外界で繁栄を手に出来た。
しかし、人の繁栄を快く思わない者もいる。この場合に例えるならば、そう、神だ。神は完璧なる世界を愛し、己の定めた禁忌を破った人間を追放した。神話の世界であれば神は絶対善であるからそれでよいが、今この現実の世界において神を僭称する者たちの善はいったい誰が保障するのだろうか? 本物の神であれば恐れる必要などない。だが、偽者は自分たちを守る嘘のヴェールが破られるのを恐れる。そして嘘をあばくものこそが、人の知恵だ。
-
その知恵を持つ者がトリステインにいる。既存の常識に囚われず、ハルケギニアの基準を大きく超える天才が。
物語はここで、今回の舞台となるべき場所へと転換する。
トリステイン王国の誇る巨湖、ラグドリアン。この湖からつながる大河を下ったところに、巨大な造船所を持つ工場街がある。そう、東方号の母港である。
かつてこの町でユニタング、バキシムが暴れた傷跡は、まだ郊外の破壊された倉庫街に生々しい。しかし、街そのものは現在なお活気を呈して、明日のトリステイン軍の主力艦を作るために動いていた。
溶鉱炉に炎と風を送るためのふいごの音が鳴り、巨大な鉄板を裁断するゲルマニア製の金属裁断機が轟音をあげて動く。たとえ空が闇に閉ざされたとしても、彼らは仕事を常と変わらずに進めている。決して無神経やあきらめというわけではなく、彼らは自分の仕事がトリステインにとってどれだけ重要な仕事なのかを自覚しているからだ。
「滑車回せーっ! ノタノタするなーっ! 怠けようなんて奴は、三度のパンとワインを与えてくれる女王陛下に申し訳ないと思え!」
威勢のいい掛け声が響き、工作機械が歯車の音をけたたましく鳴らして動き続ける。それを扱う人間にも、疲れの色はあっても不安はない。
自分のやるべきことを心得ている人間は少しのことでは動じない。世の中に異変が起きたなら、それに対処するべき役割の人間は別にちゃんといる。なら、自分たちはうろたえずに日々の仕事をこなせばいいと考える。ガリアでリュティスの人々がこの世の終わりだとパニックに陥っていたのとは対照的だが、それは国のトップであるジョゼフとアンリエッタへの信頼度の差がそのまま表れたものと言える。
そして、この街で今現在もっとも目立つものと言えば、もちろん帰還してきた東方号である。桟橋に係留してあるとはいえ、ハルケギニアのいかなる船はおろか建造物より巨大な鋼鉄の巨艦の威容は、それを見るすべての人に畏怖の念を抱かせずにはいられない。
東方号は今、以前の旅のなかばでメルバに襲われて負った損傷をほとんど癒して、再度の出撃がいつあってもいいように備えていた。
しかし、意外なことに東方号の親とも呼べるコルベールの姿は現在東方号にはなかった。コルベールがいたのは、東方号のつながれている桟橋からやや下ったところにある桟橋で、そこにある船に足を運んでいたのだ。
「いやあ、何度見てもすごい構造だ。こんな緻密な作りをした船はこれまでに見たこともない。まったく、サイトくんの故郷のものはどれもこれも興味深いなあ」
子供のようにはしゃいだ声でコルベールは、その船をいろんな角度から見たり、手で触ったりしていた。しかし、そんなコルベールを見て呆れたようにつぶやく少女の声があった。
「ミスタ・コルベール、好きなのはよろしいけど、よくもまあ毎日毎日おんなじことを繰り返して飽きないものですわね」
「ん? おお、これはミス・クルデンホルフ殿、いらしていたんですか。言っていただければ、研究資料を持ってこちらからお尋ねいたしましたのに」
「あなたのお話は始まれば終わらないではありませんの。このあいだだって、研究会で説明が長すぎてエーコたちが伸びてしまったのをもうお忘れかしら?」
どうしようもないな、というふうなあきらめを含んだ声が、金髪をツインテールにした小柄な少女の口からコルベールに向けられた。
-
ミス・クルデンホルフと呼ばれた彼女の名前はベアトリス。東方号のオーナーである大貴族クルデンホルフ家の一人娘であり、現在はコルベールの後ろ盾をしてくれている。
そう、あの東方号建造をめぐる戦いにおいて、大きな役割を果たしたあのベアトリスだ。彼女は今年度のトリステイン魔法学院入学を控えていたが、学院の長期休校が決まったことで、今でもこの街で東方号の面倒をコルベールと見ていたのだ。が、最近はコルベールの技術者バカぶりにやや振り回されぎみで、今日も東方号の工事の進捗状況を確認しに来たのだけれども東方号には不在だと聞いて、またか、といった感覚で仕方なくここまで足を運んで来ていたのだった。
「ほんとに、未来のクルデンホルフ大公国女王を引きずりまわすとは、いい度胸をしているわ。人の趣味にどうこう言うつもりはありませんけど、東方号のほうをおろそかにしてはいないでしょうね?」
「いやあ申し訳ないが、それはもちろん。修復率は九割以上で、普通に航行するぶんにはなんら問題はありません。ですが私としては、この際に東方号を強化改造したいと考えておりまして」
「そのために、この船を参考にしているとは何度も聞きましたわ。けど、実際この奇妙な船はいったいなんですの? あなたの報告書は専門用語が多すぎてわたしにはさっぱりよ」
ベアトリスはそう言って、自分の目の前にある奇妙な鉄の船を見渡した。
その船は、全長にして約百二十メイル強、東方号と比べれば小さいけれども、ハルケギニアの基準に照らしたらかなりの大型船だ。しかし、船体の形はハルケギニアのいかなる船とも似ておらず、全体が鉄でできた円筒形をしており、船上の構造物ものっぺりとしていて窓のひとつもなく、これがハルケギニアで作られたものではないことは明白であった。だが、船体上に大和型にもあるのと同じ二十五mm三連装機銃と、小型の単装砲があるおかげで軍艦だったということはわかる。
おわかりだろう、コルベールの熱意の対象となり、ベアトリスの困惑の対象となっているこの船は地球から来たものである。それは今から一月ほど前に、今でも続いているラグドリアン湖に沈んだバラックシップの残骸の調査の中で、これまで調査の手が及んでいなかった内部から発見されたものだった。
しかし、発見当初はこの船はほとんど原型を保っていたにも関わらずに研究者たちから無視された。形の奇妙さから敬遠されたというのもあるが、バラックシップを構成していた沈没船には多数の戦艦や空母が含まれていたために、申し訳程度に小さな大砲が載せられているだけのこの船に関心を払う者はいなかったのだ。
ところが、そこは好奇心の塊のようなコルベールである。ほうほうの体で帰還してきた東方号の修理に追われるさなかでも、わずかな時間のあいだに視察したラグドリアン湖の調査現場で、この船の特異性に気づいてすぐさま復元と回航を要請した。そして港まで運ばれたこの船を、時間を割いて独自に調べていくうちに驚くべきことを突き止めたのである。
「ミス・クルデンホルフ、この船は信じられないことに、水の中に潜るために作られた船なのです。この船体の内側に水を溜め込むタンクがあり、そこに水を飲み込むと沈んで、吐き出すと浮き上がる仕組みになっているのです。これはなんとも大変な発明ですぞ!」
「水に潜る船……? なるほど、どこを見渡しても窓のひとつもないのはそのせいなのね。けどミスタ・コルベール、水に潜る仕組みがわかったから今はどうだって言いますの? まさか東方号を水に沈めるなんて言いませんわよね?」
「はは、いやあ手厳しい。さすがにそこまでする余裕はありませんよ。ですが、この船は水に潜るために頑強な船殻をしていますので、参考にする部分は多々あります。東方号は船そのものは強靭無比ですけれども、損傷を受けるたびに人員には被害が出ています。私としては、戦いで傷つくものが出るのは仕方ないにしても、それを可能な限りに少なくする努力を怠りたくはないのです」
熱意に始まって、最後は優しさを含んだ穏やかな声色で言葉を結んだコルベールに、ベアトリスは改めて奇異の視線を向けた。ハルケギニアが広しといえどもコルベールのような男はめったにいない。単なる学者バカ、技術者バカというだけならば探せばすぐ見つかるが、ここまで人命を最優先に置いた考え方をする者はコルベールくらいだろう。
-
だが、それを悪いとは思わない。
「ミスタ・コルベールは、戦って勝つことには固執していられないようですね。そんな気持ちで兵器を作る人を、わたしはミスタ以外に知りません」
「ほめられたと思っておきましょう。これは私の持論なのですが、なにも奪われないだけの力があれば、戦いとは無理に勝つ必要はないのですよ。戦争に勝っても、大切なものを無くしてしまっては意味がない。人は、誰かから奪う喜びはすぐに冷めてしまいますが、誰かから奪われた悲しみはずっと残るものなのです」
「奪われる悲しみ、ですか……ですが、ミスタもロマリアからの発表をお聞きになられたでしょう。ロマリアへと向かった、ミス・ヴァリエールをはじめとした先輩方は……それに、聖戦が」
ベアトリスにも、先日ロマリアから発せられたとてつもない凶報は届いていた。しかしコルベールは落ち着いた様子で、力強い言葉でベアトリスに言った。
「なあに、私の教え子たちはそんなやわではありませんよ。どんなことがあろうと、必ず帰ってきます。私はそのときのために、あらゆる準備をしておくだけです。それに、聖戦なんてバカな真似に女王陛下が同意なさるはずはありません。聖戦などと銘打っても、奪い取るために攻め入る戦いなど、皆に不幸を撒き散らすだけなのですから」
「聖戦について、クルデンホルフは王政府の意向に従うむねを示しているわ。けど、もし聖戦が発動したらクルデンホルフの領地もきっと荒れていくでしょうね……ミスタの言うこと、わたしにも今ならわかる気がします。わたしも以前、他人から大切なものを奪おうとする過ちを犯して、それから大切なものを奪われる悲しみを知りましたから」
ベアトリスは少し遠くを見るような眼差しをして、さして遠くない思い出にわずかに心を浸らせた。
彼女はわずか一年前、なにも知らない高慢で残酷なお嬢様だったが、今は態度に高慢さはあっても冷酷さは影を潜め、若さと幼さの中に落ち着きが生まれつつある。そのおかげで現在ベアトリスのことを、知らなくて恐れる者はいても知っていて恐れる者はいない。それは彼女も、ほかの多くの人間たちと同じように、成長するうえで大切なものを経験してきたからだ。すなわち失敗と、そして苦難を。
コルベールはそんなベアトリスを、技術者の視線から一転して親愛の情を含んだ目で見つめて言った。
「ミス・クルデンホルフとは付き合いを始めてからざっと半年になりますが、大人になられましたな。少し前のあなたとはまるで別人のようですよ」
「んっ! し、仕事をサボってたのをごまかそうとしたってそうはいかないわよ。わたしはクルデンホルフ大公国の後継者にして、現在のあなたの上司なの! あなたごとき下級貴族に値踏みされるほど落ちぶれてはいないわ」
まるで子供が頭をなでられるようにして褒められたので、ベアトリスは照れくささをごまかすように虚勢をはってみせた。しかし、前よりは大人になったとはいえ、本物の大人にはまだまだ通じず、コルベールはにこやかに笑い返した。
「いえいえ、ミス・クルデンホルフもいずれ魔法学院に入学すれば私の教え子になるのです。教師が生徒を観察して評価するのはしごく当然のことです。早く学院が再開して、あなたの……というよりあなた方の入学がとても楽しみです。今日は、いつものご友人のお三方はいらっしゃらないのですか?」
「ああ、エーコたちなら今日は休暇を出してるわ。たぶん、姉妹の皆さんと会ってるんでしょう。今は、あの子たちの姉さんたちもこの街でそれぞれ働いてるから……」
ベアトリスは、あっさりと威圧を受け流されたことに屈辱感を覚えながらも、今むきになってもコルベールにはかなわないと思い直して我慢して答えた。
今、ベアトリスのまわりにはエーコ、ビーコ、シーコの取り巻き三人組の姿はない。言ったとおり、この日は休暇をもらって出かけていた。以前のユニタングの事件で救われた彼女たちの七人の姉たちも、今ではベアトリスに職を斡旋してもらって、それぞれの得意分野で仕事についている。
-
が、そのことをコルベールに話したベアトリスだったが、実は今ひとつ心配事があった。そのことが表情に出てしまったのであろう、コルベールが気遣うように問いかけてきた。
「なにか、気にかかっていることがおありですかな?」
「むっ、なんでもないわ。わたしの問題くらい、わたしで処理するんだから」
「と、いうことは問題がおありなんですな?」
しまった……と、ベアトリスは思ったがもう遅い。『よければ相談に乗りますよ』と言ってくるようなコルベールの視線がなんともうらめしい。ついでにきらりと光っている頭頂部が腹が立つ。
しかし、実のところ自分ひとりでは持て余している問題だったので、ため息をつくとベアトリスはコルベールに悩みを告白した。
「実は、エーコたちが最近わたしに隠れて特訓をしてるようなのよ」
「特訓、ですか?」
「そう、たまに抜け出してね。あの子たちが話してるのを偶然聞いたんだけど、「姫殿下のお役に立てるように、わたしたちももっと頑張りましょう!」とか言って」
「いいことではないですか、主君のために、いや友情のために努力をしようとしているのは美しいもの。それがどうして問題なのです?」
コルベールは首を傾げた。水精霊騎士隊だって日々訓練しているのだから、彼女たちが自己を鍛えても、喜びはしても頭を抱えるようなものではないはずだ。
だが、ベアトリスは周りを見渡して、自分たち以外に誰もいないことを確認した上で、コルベールの耳元に口を寄せてひそひそとささやいた。
「普通に鍛錬するんだったらうれしいわよ。でもね……」
「うわあ、それはまたなんとも……」
話を聞かされたコルベールも、すぐには返すべき言葉が見当たらずに、頬の筋肉が奇妙な形に歪むのをこらえることができなかった。
とはいえ、当事者であるベアトリスのほうが当然ながら深刻だ。小柄な体から倦怠感を漂わせ、愚痴をこぼすように言う。
「せっかくやる気を出してくれてるのに、うかつにやめろとも言えないし、かといってこのままほって置いたら取り返しのつかないことになりそうだし、どうすればいいのか」
「ミス・クルデンホルフなら、彼女たちにふさわしい教官をつけてあげることができるのではないですか?」
「あの子たちはあれでも誇り高いのよ。どこの誰とも知れない人間に教えを乞おうとはしないでしょうし、わたしが手を回したと知ればなおのことむきになるでしょう。まったく、誰に似たんだか」
主君が臣下に与える影響を完全に度外視してベアトリスはため息をついた。こういう意味ではベアトリスも大物の素質が備わっていると言えるのかもしれない、自分が良識と常識の友人だと信じきっているのだ。
残念ながら、コルベールにはベアトリスに対する有益な助言はできそうもなかった。むしろこの問題には、ギーシュや才人など、この場にいない悪童たちのほうが適任であったろうが、前者はまだ数百リーグのかなた、後者は数百万光年よりも遠くにいた。
-
「忠誠心が厚いというのも難しいですな。ですが、彼女たちの忠誠心が後のミス・クルデンホルフにとってかけがえのない財産となるでしょう。どうか、短気を起こさないように」
「わかっているわよ。あの子たちは、わたしの墓の隣に墓を建てるまで仕えてもらうつもりなんだから。ところで、話が逸れたけど、東方号の修復は九割完了したと言ったわね。つまり、残りの一割は改造に費やすということでしょ? 具体的なプランを、両日中に出してもらいましょうか」
「ええ、腹案はすでにまとめてあります。難しいですが、この船をモデルにすれば不可能ではないはずです。あなたをあっと驚かせてみせますよ」
不敵に笑ったコルベールに、ベアトリスも釣られるようにして笑いを浮かべた。
「たいした自信ね。ミスタ・コルベール、あなたはわたしに敬語を使いことすれ、下級貴族らしくへりくだることもなく、予算を求めて世辞を使うこともしない。でも、そうされるのがなぜか気持ちいいと思ってるわたしがいる。期待してるわよ」
「力を尽くしましょう。この船は、水に潜る複雑な仕組みを持ちながら、さらに『ひこうき』を中に格納する機能まで持っています。これを応用した設備を東方号に取り付ければ、サイトくんが帰ってきたときにきっと喜んでくれる。実を言うと、もっと強烈な案もあるのですが、それはさすがに次にまわしたいと思います」
「へえ、おもしろいじゃない。ミスタ・コルベール、この船があなたにとっての宝船だというなら、銀貨の一枚も残さないくらい宝を抜き取りなさい。わたしは欲深い人は好きよ」
「宝船ですか、わたしにとっては異世界からやってくるものすべてが始祖からの素晴らしい贈り物に思えます。人は知恵を育て続けることで、空の果てへも、海の底へでも行くことができる。この船は私にそう教えてくれているような気がするのです」
コルベールはそうつぶやき、自分たちが立っている異世界の船の艦橋を見上げた。
そこには、鉄色の船体に白い塗料を使い、日本語で『イ-403』と書かれていた。
潜水艦伊号403、それがこの船の本来の名前である。旧日本海軍の潜水艦伊号400型の三番艦で、全長百二十二メートル、基準排水量三千五百三十トン。第二次大戦当時、世界最大の潜水艦で、さらに水上攻撃機晴嵐を三機搭載する能力を有することから潜水空母とも呼ばれる。大和やゼロ戦と同じく、日本海軍が誇る一大決戦兵器である。コルベールはこの巨大潜水艦を参考にして、東方号を来るべき戦いに耐えられるような強化改造を施そうと考えていたのだ。
しかしコルベールはまだ知らない。その程度の改造では足りないくらいに大きな力を必要とする事態が、すぐそこにまでやってきていることに。
東方号が新たな旅立ちの時を必要とされる日は近い。そのときに、東方号が必要な力を発揮できなかったとしたら、それはそのまま世界の滅亡に繋がってしまうかもしれない。果たして、コルベールに腹案はあるのだろうか。
そしてベアトリスも、エーコたちのひそかな企みが、自分の将来を大きく揺るがす決断に繋がってくるとは、このとき夢にも思ってはいなかった。
潜水艦、伊号403はなにも語らずにじっとその巨体を浮かべ続けている。それを浮かべるラグドリアンの水はきれいだが、その水底の奥には数多くの謎を孕み、人間たちに試練を与えるのを楽しんでいるかのようにたゆとっていた。
だが、明日のささやかな期待すらも奪おうと、闇の中からロマリアの放った刺客が迫りつつある。
コルベールとベアトリスが伊403潜で語り合っているのと時を同じくして、この街を一望できる丘の上で、一組の若い男女が物珍しそうに街を見下ろしていた。
-
「やれやれ、やっと着いたかい。割のいい仕事だから張り切ってみたけど、ガリアからロマリアに出向いて、さらにこんな僻地までやってきたらさすがにうんざりするなあ」
「まあ、ドゥドゥー兄さまったら、仕事が始まる前はいつもぼやいているくせに。今回はダミアン兄さまもジャック兄さまも抜きなんだから、しっかりしてよね」
「わかってる、わかってるよジャネット。お前と仕事をするといつも小言ばかりだ」
ドゥドゥーと呼ばれた少年は、肩をすくめて答えて見せた。年の頃は才人たちとほぼ同じで、華美とは言わないが貴族らしい優雅な服をまとっている。いわゆるキツネ目の持ち主で、表情を読みづらい顔立ちをしているが、とりあえず美少年と呼んでいい。
もう一人のジャネットと呼ばれた少女は彼の妹らしく、兄のとぼけた態度に呆れた様子を見せているが、彼女も十分に怪しい風体をしていた。彼女自身は紫色の髪をした美少女であるのだが、白いフリルのついた黒いドレスを着ていて、フードから顔だけを覗かせている衣装はかなり目立つ。よほど自分に自信がなければできないことだ。
ふたりはその後、他愛も無いことを二言三言話し合っていたが、やがてジャネットが思い出したようにドゥドゥーに言った。
「ところでお兄さま? 今回の仕事の資料、ちゃんと覚えていますよね」
「もちろんさ。えーっと、ジョン、いやジークだっけか? ジ……えーっと……その、なんとかいうやつを始末すればいいんだろ?」
途中でドゥドゥーはもう思い出すのをあきらめて、開き直ったように答えた。が、それでジャネットの白い目が消えるわけはない。
「まあ、ドゥドゥーお兄さまったらやっぱり忘れてたのね。そんなことだろうと思って、念のためにわたしの資料を残しておいて正解だったわ。これを見て、ちゃんと覚えてから焼き捨ててちょうだい」
わざとらしい態度でジャネットが紙片を手渡すと、ドゥドゥーは気まずそうに受け取った。
「できた妹を持つと兄は幸せだね。ありがたすぎて涙が出てくるよ……ああなるほど、思い出した。思い出したよ! あまりにもさえない人相画だからうっかり忘れていた」
「まったく、しっかりしてほしいわね。この仕事には、後金二十万エキューの報酬がかかっているのよ。ほんとにわかってるのかしら」
「そう言うけどね、ぼくにだって好みってものはあるさ。なにが悲しくてこんな弱そうな男を始末するために苦労しなきゃいけないんだか。ジャネットはいいよね、そっちのターゲットは君好みの可愛い女の子なんだろ? 不公平だよなあ」
ドゥドゥーがうんざりした様子で言うと、ジャネットは待ってましたとばかりに顔を輝かせた。
「これも日ごろのおこないの差というものよ。楽しみね、金持ちのお嬢様って気が強いのが多いから、可愛がりがいがあるんだもの」
「また、心を操って”人形”を作る気かい? ぼくが言えたもんじゃないけど、仕事に差し支えがないようにね」
眉をひそめて妹に苦言するドゥドゥー。けれどもジャネットは意にも介さずに笑いながら言う。
「あら? わたしはドゥドゥー兄さまと違ってわきまえるところはちゃんとわきまえているから心配なく。すべてはダミアン兄さまの夢の実現が第一、そのためにはうんとお金が必要。でしょ?」
「ほんとお前はぼくに当て付けるね。まあいいさ、この仕事でいただける額があればダミアン兄さんたちもぼくを見直すだろう。さっさと済ませに行こうか」
そうして、ドゥドゥーとジャネットは丘を下って街へと向かった。途中で行商人や荷馬車がいくつも通り過ぎていくが、誰もふたりを気にも留めない。それだけふたりは堂々としていた。
しかし、ふたりの目的は商売でも観光でもない。まるで隣の家にあいさつに行くような気楽な雰囲気を持つのに反して、ふたりの心には悪意が満ちていた。
-
「ドゥドゥー兄さま、さっきの資料をちゃんと覚えたかテストしてあげますわ。わたしのターゲットはベアトリス・イヴォンヌ・フォン・クルデンホルフ、お兄さまのお相手は?」
「バカにするなよ。ぼくは物忘れはひどいが物覚えはいいんだ。ジャン・コルベールとかいう中年の男、そいつらを……殺せばいいんだろ?」
そこでドゥドゥーとジャネットは顔を見合わせて、不敵な笑みを交わし合った。
「さて行くか、ロマリアの坊主たちに、ぼくら元素の兄弟の仕事ぶりを見せてあげよう」
東方号再建を阻むために、ロマリアが送り込んだ暗殺者がふたりの正体であった。だが、ふたりはそんなことを他者にはまったく感じさせないのんびりした空気を漂わせて歩いている。
紛れもなく、このふたりは殺人に慣れたプロの仕掛人ということだ。自然体で日常に紛れ込み、前触れなくターゲットの前に現れて命を奪う。若いながらも、それだけのことをできるという計算と自信を内に隠し、ドゥドゥーとジャネットは街の雑踏の中に入り込んでいく。
ジュリオの命を受けて、ロマリアの放った刺客が何も知らないコルベールとベアトリスに迫りつつある。ガリアの北花壇騎士団に籍を置くという彼らの実力は折紙つきで、このままでは、日を置かずして死体がふたつ転がるのは確実かと思われた。
だが、暗殺計画の成功を確信するジュリオやヴィットーリオは極めて現実主義者であり、怜悧な思考を持っていたが、このハルケギニアのすべてを知り尽くしていたわけではなかった。だがそれは仕方がない。彼らの概念で言えば狭いであろうこのハルケギニアの大陸にも、人間以外にも無数の生物があらゆる場所に息づき、まだ解明されていない謎が数多く存在し、それらをすべて把握することなどはそれこそ神業に等しい。
問題は、平時であればなにも影響をもたらさなかったであろうそれらの要素が、現在の混乱したハルケギニアではどこでどう作用してくるかまったく読めなくなっているということであった。
そしてその危険要素は、実はすでに動き出し、それが教皇たちの用意した狂騒劇をある意味の喜劇に変えようとは、それこそ神ならぬ”神の代理人”を自称する彼らには想像の埒外であったのだ。
さて唐突だが、ここで物語はその時間軸を少し多めに戻すことになるのをお許し願いたい。
具体的には才人たちがティファニアをアーハンブラから救出して少し後、初代東方号が完成したあたりに巻き戻る。ここで才人たちがサハラ行きの使命を与えられ、それを妨害しようとするミミー星人の操るバラックシップ、アイアンロックスとの戦いにつながっていくのは少し懐かしい思い出である。
-
しかしここで、実はミミー星人の影に隠れて、同時にもう一組の宇宙人がラグドリアン湖に来ていた事実があった。
「ミミー星人よ、本当に我らはこの星の海洋調査をすればいいだけなのだな?」
「もちろんだとも、我々にとっても君たちの星の調査技術はありがたいし、君たちにとっても我々の武力の庇護はありがたかろう。なにせこの星には、かつて君たちの同胞をひどい目に合わせた地球人と同じ人間たちが住んでいるのだからね」
「ああ、あの生き物は本当に危険だ。姿かたちこそ我々に似ているが、奴らの心には悪魔が住んでいる」
その星人は、元々M78星雲のある次元に住む宇宙人で、ハルケギニアでの資源収奪をもくろむミミー星人に請われてやってきた。彼らの名はパラダイ星人、GUYSのドキュメントMACに記載のある星人で、ミミー星人やバルキー星人などと同じく水棲型の宇宙人だ。姿かたちは人間と大差はなく、かつては同族が地球に海洋調査のために訪れていたことがある。
ただ、彼らはミミー星人とは違って本来は平和的な種族で、メイツ星人やミラクル星人のように他の星を観察しに来ることはあっても、侵略行為に加担するようなことはない。
しかし、ヤプールを出し抜くことを目論むミミー星人は、自分の星の発展のために他の惑星の海洋調査データを欲していたパラダイ星人をそそのかした。あの地球と同じように、広大な海と豊かな自然を持つ惑星がある。そのデータが欲しくないか? と。
パラダイ星人たちは悩んだ。ミミー星人があまりいい評判を持つ宇宙人ではないことは聞いていたが、ミミー星人は巧みにヤプールとの関連性はごまかしており、ミミー星人も彼らと同じく海生型の宇宙人であるために話に信憑性があったからだ。
結果、パラダイ星人はあくまで海洋調査のみという条件での協力でハルケギニアに来訪することを決めた。むろん彼らはミミー星人への不信を拭い去ったわけではなかったので、派遣されたのは、専門の技術者一人とその助手ふたりだけに限られたが。
そして、彼らはミミー星人によって次元を超えてハルケギニアに来訪した。彼らの宇宙船は潜水艇にもなっており、海の底を自由に巡りながら海水の成分や生態系の分布、海底資源の有無などのデータが瞬く間に集まっていった。
ただ、パラダイ星人の技術者は、かつて地球を訪れた者たちが現地住民に迫害された経験から、この世界では一切陸上に上がろうとはせず、海中で秘密裏に惑星の海洋を調査した。
だが、技術者のそんな姿勢を、ふたりの若い助手は退屈そうに見ていた。
「ねえ先生、ちょっとでいいから陸に上がりましょうよ。これだけ海がきれいな星なんだから、きっと陸も素敵ですって」
「だめだ、何度も言っているだろう。以前地球という星に降りた我々の同胞は、うかつに陸に上がってしまったばかりに原住民に子供を殺されかけた。この星も文明は未開だが同種の人間が支配している。危険すぎるのだ」
「ちぇっ」
「仕方ないわよ、わたしたちはまだ見習いなんだもの。いつか一人前になったら、もう一度この星にやってこよう」
ふたりの助手は不満げであったが、許可が下りないのであれば仕方がない。パラダイ星人たちは宇宙船の中で紆余曲折ありつつも調査を続け、やがて満足すべき成果を得た。
-
だが、まとまった観測データを持って、ミミー星人の待つラグドリアン湖へ戻ったとき、ミミー星人は完全に彼らの期待に応えた。悪いほうに完璧なまでに。
「裏切ったなあ! ミミー星人」
バラックシップから放たれた魚雷を受けて沈み行く宇宙船の中で、パラダイ星人たちは怒りに震えたが遅かった。
観測データを伝送した瞬間、ミミー星人は本性を表した。立ち向かおうにもバラックシップの火力は強大で、たいした武装のされていない彼らの宇宙船ではとても太刀打ちできるものではなかった。
「やはり我々が愚かだった! あんな奴らを信用したばかりに。あんな奴を信用さえしなければっ! せ、せめて研究資料だけは、うおおぉぉっ!」
そう叫んだのを最期に、宇宙船のブリッジは魚雷の直撃を受けて大破し、直後に彼らの宇宙船はバラックシップからのとどめの魚雷を受けて爆発四散した。
強力な水中爆発が起こり、助手ふたりが資料の持ち出しをはかっていた研究ブロックも破壊されて、ふたりはラグドリアン湖の中へと投げ出された。
「ティ……ね、姉さん……」
「手を、離さないで……」
バラックシップの魚雷攻撃で湖水は滅茶苦茶にかき回され、ふたりはその中で上も下もわからず、ただお互いにはぐれまいとかばい合い続けた。このままでは、いくらふたりが水棲宇宙人であるといっても、濁流に放り込まれたハンカチのようになってしまっただろう。だが、ふたりが力尽きる直前に、魔力を帯びた水のカプセルがふたりを守るように包み込んだのだ。
『この単なる者たちは、この地に生まれたものではない……だが、邪なるものも感じぬ。よかろう……』
このラグドリアンに住まう主の加護を受けて、ふたりの宇宙人の子はゆっくりと安全な湖岸へと運ばれた。
-
やがて気がつき、ふたりは自分たちが置かれた状況を知る。
「助かったのね、わたしたち」
「そうだね……これからどうしよう?」
「見て、あそこに明かりが見える。きっと、人間という生き物の町だよ」
「行くの? 先生は、人間は信用するなって」
「行かなければ、わたしたちは飢えるだけ。それに、わたしたちは学者のはしくれだよ。人の言ったことを、はいそうですかと鵜呑みにして満足できる?」
「ふふ、こんな時なのになにか楽しそうだね。いいよ、わたしたちの歴史書はわたしたちで書きましょう……さあ」
ふたりは手をつなぎ、声をそろえて言った。
「「行こう」」
そしてふたりはラグドリアン湖畔の町のひとつにたどり着き、人間に紛れて生きていくことを選んだ。
この直後、ミミー星人はバラックシップとアイアンロックスを駆ってウルトラマンAと戦い、東方号の特攻で倒される。そうしてラグドリアン湖には平和が戻り、人々の心から次第にこの戦いの印象は薄れていき、現在に続くこととなる。
だがその間に、このふたりの宇宙人がどこで何をしていたのか? その答えが、これから少ししてから起こる事件で大きく羅針盤を動かすことになるのだ。
続く
-
今回はここまでです。久々登場のベアトリスたち、そして新規登場の元素兄弟、新編は彼らを絡めあいながら進めていきます。
本来ならこの話でメイン怪獣も登場させたいと思っていましたが、書いていたら長くなってしまいましたので先延ばしにしました。
さてそれはともあれ、物語にはイレギュラー要素が不可欠でありますので、この話にも目立つものや気づきにくいものも含めて、いろいろ伏線をうっておきました。気が向けば先読みでもしてみてください。
新しく話を始めるときは出だしが一番難しいので、次の話はそれなりに早くできると思います。いずれにしても、失踪だけは絶対にしないつもりです。
ハーメルンのほうでも3章までに入りましたので、よろしければそちらも来てください。内容は変わりませんが、ある方が挿絵を描いて下さいまして、怪獣好きなら一見の価値あるものばかりです。
では、また。
-
乙です!
-
乙です
この二組の兄弟(と姉妹?)がどう絡んでくるんだろうw
-
皆様、こんばんは。お久し振りです。
遅くなりましたが、よろしければまた23:20頃から続きを投下させてくださいませ。
-
ヴロックを倒した後もなおしばらく、ディーキンらは事態の収拾のために忙しく働かねばならなかった。
まず、事態を目撃した店内の客に対するフォローが早急に必要だった。
客にはタバサが自分のシュヴァリエの身分を明かし、王宮の命令でこの店に潜む怪物の調査をしていたのだ、という旨の説明をする。
使用人にはトーマスがオーナーの死を伝え、店の蓄えの中から幾許かの退職金を渡してやった。
残りの金は、おそらく後日王宮を通して、客たちに返金されることになるだろう。
そうして無関係な者たちをさっさと帰らせ、店を封鎖してから、次にこの惨事の後片付けに取りかかった。
最初に、タバサが仕事の完了を報告する際の証拠品とするため、骨と化したサキュバスの亡骸を回収する。
その際にディーキンはサキュバスの所持品を検分し、マジック・アイテムの類については戦利品としてもらっておいた。
それ以外の装飾品等は、店の売上金と一緒に後で王宮へ提出することにしてタバサに委ねる。
ディーキンはこの店にデーモンがいたことで、ますますガリアの王宮内にはデヴィルが入り込んでいるのでは、という疑いを強めていた。
デヴィルとデーモンは悪の頂点の座を争う宿敵同士であり、遥かな太古から血で血を洗うような争いを続けているのだ。
この店にデーモンがいることを知っていて排除させようとしたのだ、と考えてもおかしくはない。
仮にそうでないとしても、デーモンが遺していった品々をそのまま王宮に委ねてしまうのはよくないだろう。
不適当な人物の手に渡れば、どんな不幸の種になるか分かったものではない。
金は客たちに返金しなくてはならないが、不穏当な物品は引き渡さずにこちらで持っておくか、内密に処分してしまった方がいいはずだ。
それから、続けて奥の方の片付けに取り掛かった。
カジノの奥にあったいくつかの部屋の様子は、デーモンが美しい見てくれの下に隠していた、腐敗と堕落とを如実に表していた。
ある部屋には、退廃的・嗜虐的な娯楽に使うための器具や薬品、性的な征服を通して得たおぞましい戦利品のコレクション等が並んでいた。
ディーキンはそれらの物品をざっと検分し、明らかにいかがわしい物、悪の穢れを受けているような物はすべて処分していった。
そうではない物で利用できそうなごく一部の品物は、回収して持っておくことにする。
どこから調達したのか、『苦薬』と呼ばれる麻薬を抽出するための大がかりな機材が設置された部屋もあった。
激しい苦痛に苛まれている犠牲者から魔法的に抽出されるこの悪しき物質は、使用者に強烈な幸福感を与える極めて中毒性の高い麻薬だ。
当然、作成済みの薬と機材の類はすべて完全に破壊して、残骸まで含めて念入りに処分しておいた。
完全にデーモンに屈服して傀儡となった人々が、爛れた行為を行われるために一時的に拘束されている、牢獄のような部屋もあった。
あのサキュバスは、おそらくこれらの虜にした者や攫ってきた者を拷問にかけて、悪しき麻薬を作りだしていたのだろう。
囚われていた犠牲者の中には、件の麻薬に対する中毒症状を呈している者も何人かいた。
ディーキンは詮索されぬよう彼らに目隠しをした上で、招来呪文を用いて呼び出した来訪者に頼み、簡単な治療を施してやった。
その様子を見たほかの3人、特にタバサは、非常に興味を惹かれた様子だったが……。
最奥の倉庫は、特に悲惨な様相を呈していた。
そこには、わけのわからない体液に塗れたり、無残に痛めつけられたりした屍が、何体も押し込まれていたのだ。
おそらくはサキュバスが欲求不満を解消するために攫ってきた不幸な孤児や浮浪者、旅人等であろう。
カジノのオーナーであったというギルモアの遺体も、それらの屍に交じって転がっていた。
トーマスはその腐りかけた遺体の傍に跪いて手を握ると、静かに涙を流しながら彼らに詫びて、死者の魂の安息を祈っていた。
このカジノの店員として、責任を感じているのであろう。
ディーキンらもまた彼に倣って、しばし哀れな犠牲者たちのために祈った。
そうしてすべての部屋からデーモンの遺していった穢れの痕跡を完全に始末し終わったころには、既に夜明けが近い時間になっていた。
さすがに皆かなり疲れていたが、誰一人としてこの忌まわしい場所で一眠りしたいなどという者はいなかった。
用件が済み次第足早に店を後にすると、最後に全員で郊外の人気のない丘に、犠牲者たちの遺体や遺品を埋葬しに向かった。
ディーキンはバードとして、犠牲者たちのために鎮魂歌を奏で、いつになく厳粛な調子で祈りの言葉を朗誦した。
-
♪
公正なるティールよ
慈悲深きマイリーキーよ
温かきラサンダーよ
すべての善なる人の神々よ、どうか彼らを天上から見守りたまえ
御使いを遣わし、導きを与えたまえ
哀れな御魂が、死後もデーモンによって悩まされぬように
デヴィルが彼らを誑かさぬように
いと高く高潔なる御方、白金のバハムートよ
その輝ける翼に乗せて、御魂を浄土に疾く運び賜われ――――
……
♪
ディーキンはさらに、呪文でランタン・アルコン(燈火の聖霊)を呼んで、死者たちのために祈ってもらった。
招来された4体のアルコンは、呪文の効力が切れるまでの間ずっとその暖かな輝きで墓標を照らし、柔らかく音楽的な声で歌ってくれた。
その行為に、実際に何らかの効力があるというわけではない。
だが、天上界から聖霊がやってきて導いてくれたのだと思えば、犠牲者たちの御魂も少しは慰められるだろう。
この手の呪文に馴染みのないトーマスらは、驚きと感嘆の念を持って、その様子を見守っていた。
それを終えると、タバサは休む前に、王宮への報告をさっさと済ませてしまうことにした。
プチ・トロワへ赴き、ディーキンやトーマスのことは伏せて、正体不明の魔物が人々を誑かしていたのを始末したことを伝える。
それから、カジノで回収した金品や、これまでの勝ち金を預けてあるシレ銀行の鍵などを引き渡した。
イザベラはそれについて、特に詮索はしてこなかった。
実を言えば、彼女は既にカジノで騒動があったことについて、ある程度の報告は受けていたのである。
その内容は「カジノに現れた魔物と子供が戦った」「少年が魔物を始末した」というようなもので、タバサの報告と矛盾はしていなかった。
タバサ自身子供のような容姿であるし、男装もしていたので、ディーキンに関する話もタバサのものと混同されていたのだ。
仮にタバサ以外にも戦った者がいたという情報が流れていたとしても、カジノには貴族もいたのだからその中の誰かだと思った程度だろう。
そんなわけで、イザベラには特にタバサの報告を疑うべき理由もなかったのだ。
従姉妹が成功したのは面白くはなかったが、まあ自分は先だってその優秀な従姉妹にも勝ったのだと思えば、逆に優越感を感じられる。
それに時刻もまだ早朝なので、彼女を嬲って愉しむよりも、もう少し寝ていたかったというのもあるだろう。
イザベラの背後にいるラークシャサも、別段深く探りを入れようとは考えなかった。
この度の任務は、元々デヴィル側からの要請であった。
カジノにデーモンが潜伏している可能性があるのでそれを探らせ、可能ならば排除させろと言って来たのだ。
大方、邪魔者を始末した上で、そいつが築いたカジノをそっくり頂き、自分たちで利用しようという腹積もりだったのだろう。
だが、魔物騒動が起こったのでは店には当分客が寄り付かなくなり、そのまま利用するのは困難になったはずだ。
デヴィルどもの目論見が外れるのは彼にとっては愉快なことだったし、こちらの役目は果たしたのだから文句を言われる筋合いもない。
そうである以上、この上自主的に何かしてやる気などは毛頭なかった。
そうして、イザベラへの報告は特に問題もなく、ごくあっさりと済んだ。
-
当面の用件をすべて終えると、一行はようやく人心地がついた。
元の姿に戻ったシルフィードと一旦別れると、残った3人は休息のために、適当な宿で部屋を取る。
それから、眠る前に同じ部屋に集まって、トーマスの今後の身の振り方について相談をした。
「ねえ、トーマスさん。もしよかったら、トリステインに来ない?
あんたは手品が上手なんでしょ、それにナイフ投げとかもできるみたいだし、ハンサムだよね。
だからきっと、『魅惑の妖精』亭でディーキンと一緒に仕事をしたら、すごーく人気が出ると思うんだよ!
タバサも今はその近くの学校に通ってるから、お互いに会いに行きやすいしね」
「私も……、そうしてくれると嬉しい」
「……何から何までお世話になりましたのに、なおそのように気遣っていただいて……。
ありがとうございます、シャルロットお嬢様、ディーキンス様。いえ、ディーキンさん、でしたね」
トーマスは2人からの提案に控えめな笑みを浮かべると、深々とお辞儀をした。
ディーキンもシルフィードも、既にタバサからの信頼厚い彼に対しては正体を明かしていた。
しかし、彼は相手が貴族であろうと平民であろうと、あるいは亜人であろうと、それだけで態度を変えたりはしない主義のようだ。
もちろんディーキンとしては大変に嬉しいことであり、彼に対する敬意を新たにしていた。
シエスタの時と同様、様付けで呼ぶのは止めてほしいとだけは頼んでおいたが。
「私には、もはや身内もありません。かつて仕えたシャルル様にも、ギルモア様にも、とうとう何のご恩返しもできずじまいです。
大恩を受けたあなたと懐かしいシャルロットお嬢様のお役に立てるのであれば、喜んでまいりましょう」
それを聞いたタバサは僅かに、しかしはっきりと、嬉しそうな笑みを浮かべた。
懐かしい使用人に再会できたためか、普段よりも表情が柔らかい。
それから、トーマスとタバサはしばらくの間、思い出話などに花を咲かせて旧交を温めた。
ディーキンは彼らの話の邪魔をしないように静かに耳をそばだてて、様々な情報を知った。
タバサの本名がシャルロットといい、オルレアン家なる、非常に身分の高い貴族家の出であるらしいこと。
そのオルレアン家は、何らかの陰謀に巻き込まれて没落したらしいこと。
それにタバサとトーマスとの関係とか、昔遊んだ時の思い出話とか、その他にも色々な細かいことを……。
2人には積もる話があったし、ディーキンにとっても彼らの話は興味深かった。
とはいえ、今日はみな疲れている。
ある程度話して一区切りつくと、続きはまた翌日にして解散し、一行は各々の部屋に引き取って寝ることになった。
「ンー……、今日も楽しかったの」
ディーキンは自分にあてがわれた部屋に入ると、大きく伸びをした。
今日もまた、いろいろなことがあった。
犠牲者のことや、デヴィルの件などを考えれば、楽しかった、などというのは不謹慎だという者もいるかもしれない。
しかし、そんなことを言っていたらこの世の中は何ひとつ楽しむには値しなくなってしまうのだ、とディーキンは考えている。
コボルドの部族の洞窟で過ごした日々は辛く、恐ろしいものだった。
それでも時には楽しいこともあったし、多くの役に立つ教訓を学びもした。
今日のことも、それと同じだ。
初めて学院から大きく離れて別の国を見たし、トーマスという新しい友人とも知り合えた。
そしてデーモンを打ち倒して、その悪事を終わらせることもできた。
哀しいことがあったからと言って、良いことの方を喜んではいけないなどとは思わない。
とにかくここへ来てから、毎日が刺激的で、退屈しない日々が続いている。
-
ディーキンは、明日が来るのが心から楽しみだった。
自前の魔法の寝袋で眠るのが一番快適ではあるだろうが、せっかくなのであえて宿のベッドに横になってみた。
安めの宿なのでそんなに柔らかいわけでもなかったし、寝ている間にウロコや翼などで傷めないように気をつけもしなくてはならない。
しかし、何でも新しい物は試してみたいというのがディーキンの性分である。
「そういえば、ルイズはどうしてるかな……」
使い魔の仕事はラヴォエラに頼んで来たし、何も心配はいらないだろう。
だが、仮にも“主人”である彼女を放って、勝手に出てきたのは申し訳なかったと思っている。
それにラヴォエラにも、あまり長い間仕事を押し付けておくわけにもいくまい。
この国の上層部にデヴィルが入り込んでいるかも知れないというのは不安だが、現状では踏み入った調査をするのも難しそうだ。
任務とやらも終わったことだし、今はひとまず学院に戻ろう。
それからみんなに、念のためデヴィルに関する説明をして、注意を促しておこう。
タバサには、今後の『任務』の時には自分を必ず同行させてくれるように頼んでおいて。
それから……。
「ウーン、あとは……。
みんなに何か、お土産でも買って帰ろうかな?」
ベッドに寝転がって少しうとうとしながらそんな風に考えていたとき、部屋のドアがコンコンとノックされた。
ディーキンはベッドの上で身を起こして、ちょっと首を傾げると、外の人物に向かって呼びかける。
「誰? ディーキンに用事なの?」
返事の代わりにドアが僅かに軋んで開き、声の主が姿を現した。
「……タバサ?」
彼女はカジノで着ていた男装とヴロックに破かれたシュミーズとを脱ぎ捨てて、下着の上から宿に備え付けのナイトウェアを着ていた。
貴族が着るにしては質素なものだったし、若干ぶかぶかだったが、タバサは別に気にした様子もなかった。
窮屈な男装や、学院の制服で寝るよりはいいと思ったのだろう。
「もう少し、話したいことがある。……いい?」
ディーキンは、やや不思議そうに目をしばたたかせた。
話があるのなら、さっきトーマスと一緒にいた時にすればよかっただろうに。
何か、話し忘れたことでもあったのだろうか。
なんにせよ、別段断る理由もないので素直に頷く。
タバサはとことこと部屋に入って来ると、ベッドの脇、ディーキンの横の方に正座した。
そうすると、ベッドの上にいるディーキンよりも、いくらか目の高さが低くなる。
他人と同じベッドの上にずかずかと登っていかないのは、まあ当然のことだが……。
ディーキンにはそればかりではなく、何かあえてタバサが、自分をより低い位置に置こうとしているかのように思えた。
ゆえに、少し迷ったが、あえてベッドから降りずに彼女と応対することにした。
彼女はそのまましばらく、押し黙ったままだった。
どこかそわそわした様子でじっと俯き、時折ディーキンの方を上目遣いに見たりする。
なにか思い悩んでいるらしいことは察せられたので、ディーキンは彼女が話し出すまで、急かさずに待つことにした。
やがて、タバサは顔を上げてじっとディーキンの方を見つめると、重い口を開いた。
-
「……今日は、ありがとう」
「どういたしまして。でも、ディーキンはそんな、大したことはしてないと思うの。
それに、タバサにもずいぶん、危険なことをお願いしたりもしたし……」
「元々は私の仕事、私が危険を冒すのは当然。
あなたがいなかったら、私はどうなっていたかわからない。
それに、トーマスも助けてくれた……」
タバサは自分の杖を捧げるように持って、深々と頭を下げた。
それから、またしばらく押し黙ってしまう。
彼女は、ここまで来たものの、どうしても話す決心がつかずに悩んでいた。
どんな任務でも恐れずためらわないタバサにも、躊躇することはあるのだ。
自分がこれからしようとしている頼み事は、聞き入れればガリア王家を敵に回しかねない危険なことだから。
そうであっても、彼が決して断らないであろうことはよく分かっていた。
彼なら、物語の中の英雄のように自分を救ってくれたこの人なら。
だからこそ躊躇するのだ。
ここまで世話になっているこの人に、この上そんなことを頼んでもよいものかと。
これが自分一人のためのことなら、決して頼まないだろう。
だがこれは、大切な身内のためでもあるのだ。
それでも後ろめたさを感じて、なかなか切り出すことができないでいた。
(……ウーン)
ディーキンはどうしても決心がつかない様子のタバサを見て、内心で考え込んだ。
思うに、彼女には何か、自分に持ちかけたい頼みごとでもあるのだろう。
しかし、明らかに躊躇っている様子だ。
彼女の性格からして、おそらくは危険なことなのでこちらの身を案じているか、あまりに図々しいとでも思って遠慮しているのか……。
もちろん自分はそんなことを気にしないが、こちらから遠慮なく話せなどといっても逆効果でしかないだろう。
ここは大人しく、彼女が話す気になるまで待つことにしよう。
そう、思っていたのだが……。
この分では、こちらからなんとかして水を向けた方がいいかもしれない。
ディーキンはひとつ咳払いをしてタバサの注意を引くと、じっと彼女の顔を見つめて、真面目な調子で話し始めた。
「オホン……。ねえ、タバサ。
タバサは、もしかしてディーキンのことを信じてくれてないの?」
「! ……そんなことは、ない」
「うん、タバサにそんなつもりがあるなんて思わないよ。
でも、ディーキンは冒険者なの。冒険者の間で信頼するっていうのは、危険を分かち合ってくれることだよ。
ボスがよく、そう言ってるの」
「……」
-
ディーキンはベッドから降りると、押し黙ったタバサの手を取った。
そうしてから、無邪気そうな笑顔を浮かべて見せる。
「だから、タバサがディーキンを信じてくれるなら、ちゃんと話してほしいの。
どんな危険なことでも、大変なことでもね。
それともタバサは、ディーキンがタバサに隠し事をしてても、それを話してほしいとも思ってくれないの?」
――そんな調子で、しばらく<交渉>を続けた結果。
タバサはようやく、ディーキンに自分の望みを打ち明けることを決心してくれたようだった。
「……わかった。だけど、その前にひとつ教えてほしい。
その答え次第では、私の頼み事は意味がなくなる。その時は、このことは忘れると約束して」
「ンー、そう? わかったの。
ディーキンはボスに誓って、頑張って忘れるの。自分に催眠術とか記憶を消す呪文とかを掛けてでも」
微かに頬を染めたタバサは、深々と頭を下げてひとつ深呼吸をすると、質問を始めた。
彼の言う催眠術や記憶を消す呪文とやらにも興味はあったが、そんなことを聞くのはまた今度だ。
「……質問は、あなたがカジノで私や客の傷を治す時に呼びだした、亜人のこと」
「亜人? ……アア、ケルヴィダルのこと?
あの人たちは、亜人じゃなくてガーディナルっていうんだよ。ラヴォエラみたいな天使に近い種族らしいの」
ガーディナルは天上の諸次元界に住まい、中立にして善の属性を代表する、獣人めいた姿をしたセレスチャルの一種別である。
ケルヴィダルは山羊のような角や蹄を持つ、サテュロスに似た姿をしたガーディナルの一種だ。
タバサはあの獣人めいた姿をした存在が天使の仲間だと聞いて、少なからず興味を惹かれた。
だが、今聞きたいのは種族に関する話ではない。
「……そのケルヴィダルというのは、麻薬の中毒になった人でさえ癒していた。
どんな毒でも、治すことができる?」
タバサの望みは勿論、叔父によって自分の母が飲まされ、正気を失わされた毒の効力を消し去って、彼女を救うことだ。
これまでどんな水の秘薬を用いても、母の陥った狂気を癒すことはできなかった。
だが、フーケとの一件の際にディーキンは、ブララニとかいう名のエルフめいた姿の存在を呼び出した。
それが自分の治癒魔法がまるで効かなかった傷をたちまち塞いだのを見たとき、タバサは一抹の希望を抱いたのである。
その希望は、先程カジノでディーキンが呼び出したまた別種の獣人めいた存在、ケルヴィダルの力を見て、ますます高まった。
それはただ触れただけで自分が魔物から受けた深手をたちまち塞ぎ、麻薬中毒に苦しむ患者をも癒してみせたのである。
果たしてディーキンの答えは、タバサの望み通りのものだった。
彼はあっさりと首肯して、何でもないことのように言った。
「うん、できると思うよ。
ケルヴィダルはどんな毒でも病気でも、ただ角で触るだけで治してくれるの」
-
苦薬(液状の苦痛):
特別な呪文やアイテムを使用することで、苦悶する犠牲者から苦痛の本質を抽出したもの。
見た目はねっとりして赤みがかった液体であり、摂取した者にしばらくの間激しい悦びを感じさせ、より魅力的にする。
しかしながら、この悪しき物質は通常の麻薬を遥かに超える極めて高い中毒性を持ち、その禁断症状は言語を絶する苦しみである。
悪の属性を持つ来訪者たちは、この物質を熱心に追い求めているという。
ティール、マイリーキー、ラサンダー、バハムート:
いずれもD&Dの神格。
ティールは「秩序にして善」の上級神。地球の北欧神話体系からフェイルーンにやってきた戦神で、“もぐり”の神々の一柱である。
マイリーキーは「中立にして善」の中級神。森の守護者で、かの名高いドリッズト・ドゥアーデンの信仰する女神としても有名である。
ラサンダーは「中立にして善」の上級神。太陽神で、若々しい活力と創造性、新たな誕生を祝福する強大な神格である。
バハムートは「秩序にして善」の下級神。プラティナム・ドラゴン(白金竜)と呼ばれ、善属性の竜族の神格を代表する高潔な神である。
アルコン:
アルコンは「秩序にして善」の属性を代表する来訪者の一種別である。
外見は天使のような者や獣人のような者、光球状の者など様々だが、いずれも荘厳な美を感じさせる。
ランタン・アルコンは死せる義人の魂が生まれ変わった最低次のアルコンであり、進化すればより偉大なアルコンになれるという。
なお、グノーシス主義におけるアルコンは低級な霊的存在であり、蒙昧にして傲慢な偽神だが、D&Dのアルコンは純粋に善の存在である。
ガーディナル:
ガーディナルは「中立にして善」の属性を代表する来訪者の一種別である。
いずれも獣と人との特徴を併せ持った姿をしているが、同じような姿をしたある種の亜人や獣人よりも、遥かに高貴に感じられる。
彼らはとても親切で、言葉を持たぬ獣とも意志を疎通させることができ、触れただけで傷ついた者を癒す力を持っている。
-
今回は以上になります。
また、できるだけ早く続きを投下していきますので、次の機会にもどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、失礼しました(御辞儀)
-
乙です
-
D&Dのことは解らんのだが、混沌のディーキンが秩序のアルコン呼んでいいんかのう(メガテン脳)
-
>>710
まず、本作におけるディーキンは設定上混沌ではありません(バードは秩序ではいけないが、混沌である必要はない)
原作での彼の属性は「混沌にして善」→「真なる中立」と変化しております
今作では「中立にして善」である(ボスがパラディンなので、その影響を受けて善に戻った)と設定しています
また、対立属性の呪文が使えないという制限は信仰呪文を使うクレリック等には適用されますが、ウィザードやバードなどの秘術呪文使いには特に関係ありません
-
すいません、善に戻ったを、元の属性(混沌善)に戻ったと読み違えてました
ありがとうございます
-
こんばんは。焼き鮭です。今回も投下します。
開始は20:17からで。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第七十七話「風の竜のともだち(前編)」
凶悪怪獣ギャビッシュ 登場
エズレ村のミノタウロス事件の際に、グレンファイヤーがシルフィードの正体を知っている
ということが発覚した。今一度確認するが、シルフィードはただの風竜ではない。本名をイルククゥと
言い、人間の間では絶滅したと言われているがその実隠遁して生き延びている風韻竜の子供なのだ。
イルククゥはタバサのコントラクト・サーヴァントの呪文に導かれて、彼女の使い魔となった。
しかし、その事実を何故グレンファイヤーが知っていたのか。それにまつわる話には、
魔法学院の夏季休暇期間中に起きたある事件が関わっていた……。
夜のトリステインの森の一つ。その上空を、ジャンボットが飛行している。しかし普通に
飛行している訳ではなかった。彼は、自身と同等のサイズの巨大怪獣を抱えている。
『むんッ!』
「ピィ――――――――!」
無人の森の上に強行着陸するジャンボット。その際に巨大怪獣が放り出され、木々の上に叩きつけられた。
「ピィ――――――――!」
青い毛皮に覆われ、真っ赤な両眼を持つ、凶暴な面構えの怪獣が立ち上がる。その顔面からは、
おぞましいほどの悪意がにじみ出ていた。
怪獣の名はギャビッシュ。とめどない破壊衝動と狡猾な頭脳を併せ持つ危険な宇宙怪獣であり、
これに襲われた星はあまりにも大きな被害が発生してしまう。実際、このハルケギニアでも
人の街を積極的に狙い、住民をわざと巻き込む形で彼らの命を盾にして思う存分暴れ回ろうと
していた。しかしそこにジャンボットが駆けつけ、ギャビッシュが反応する間も与えずにこれを
捕獲し、こうやって無人の土地に運ぶことで卑劣な策略を無効化したのだ。
『ここならこちらも存分に戦える! 行くぞ、ならず者怪獣!』
正義の心をたぎらせたジャンボットはビームエメラルドで先手を打った。
だが緑色のレーザーはギャビッシュの赤い目に吸い込まれ、口からジャンボットへと送り返された!
「ピィ――――――――!」
『むッ、光線を反射する能力を持ってるのか! ならば格闘戦だ!』
はね返されたビームエメラルドを盾で防いだジャンボットはすぐに戦い方を切り換える。
ぐっと両の拳を握り締めて、ギャビッシュへと接近していく。
「ピィ――――――――!」
だがギャビッシュに肉弾戦をするつもりはないようだ。口から針状の光線を吐いてジャンボットを攻撃。
ジャンボットは足止めされる。
『ジャンナックル!』
しかしこれしきで追い詰められるジャンボットではない。素早くロケットパンチを飛ばし、
ギャビッシュの頭部に命中させた!
「ピィ――――――――!」
大きく仰け反ってよろめくギャビッシュ。その隙にジャンボットは押し込もうと、再び踏み込んでいく。
が、その時にギャビッシュの長い尾が頭上まで持ち上がり、その先端から電撃光線が辺り一面に発せられた!
『ぐッ!』
強烈な一撃が連続して爆発を引き起こし、ジャンボットの視界が一瞬さえぎられた。
そして晴れた時には、ギャビッシュの巨体が影も形もなくなっていた。
『何ッ、しまった! 逃げられたか!』
ギャビッシュは光線反射や光線発射の能力の他に、いざという時に逃避するテレポートの
超能力も備えている。自分が敵う相手ではないと見るや、すぐに逃走して姿をくらますのも、
ギャビッシュの狡猾さの一面である。
-
ジャンボットはレーダーも使って捜索したが、ギャビッシュは既にこの付近からいなくなっているのか、
反応は全くなかった。最早ここには現れないだろう。
『あの怪獣は、野放しにしておくほどに危険度が高まる。早く見つけ出さなければ! 仲間たちにも
協力してもらおう』
そう判断したジャンボットはジャンバードへと変形し、一旦衛星軌道上へと引き返していった。
一夜明けて、トリステイン魔法学院近くの森の中。そこが普段のシルフィードのねぐら。
タバサに呼ばれないときは、ここを中心に遊んだり、使い魔仲間と話し合ったりして日々を
過ごしているのだ。
しかし今日のシルフィードは憂鬱そうだ。岩の上に腰掛け、前足で器用に頬杖を突いている。
はぁ、とため息まで吐いた。
「さっきは哀しかったのね……」
思わず声に出してから、はっと気がついて慌てた顔で辺りを見回す。
しゃべっちゃった!
心の中で、そう呟く。
風韻竜の子供、シルフィードは普通の竜と異なり、言葉を操ることが出来る。しかし言葉を
話すところを人に見られたら、正体が一発でバレてしまう。それを防ぐために、タバサは上空
三千メイル以上の場所以外での、シルフィードの発声を禁じているのだ。同時に、この周辺での
人間への変身も禁止している。勘の良い知り合いに、一緒にいるところを見られたらシルフィードの
正体に気づかれてしまうかもしれないからだ。とにかく、タバサはシルフィードの正体が
露見しないように気を遣っている。
それを破ったら大目玉だ。シルフィードはどうか周りに誰もいませんように、と願いながら
見回していたが……。
「……」
振り向いたその先に、木々の間から半身を出してこちらに視線を送っているグレンの姿を見とめた。
(い、いるのねー!?)
ガビーン! とショックを受けるシルフィード。彼は確か、グレンファイヤーがその身の中に
宿ったウェールズという人間。それがどうしてこんな場所に? 一体シルフィはどうしたらいいの!?
と混乱するシルフィード。
しかしふと落ち着きを取り戻す。まだ自分の声を聞かれたとは限らない。もしかしたら
彼の耳には届いていなかったかも……と、一縷の望みにかけたが、
グレンはこちらにつかつかと歩いてきて、こう言ってきた。
「おいおいどうしたよ、えぇと、シルフィード。アンニュイな空気醸し出して、挙句『哀しかった』だって?
何か嫌なことでもあったのか?」
(バッチリ聞かれてたのねー!)
再びガビーン! とショックを受けるシルフィード。それでも最後の抵抗とばかりに、
そっぽを向いてしらを切ろうとしたが、
「おーい、返事しろっての。お前さっきしゃべってたじゃ……」
とグレンが言うので、無視できずに慌ててその口を塞いだ。これ以上ややこしいことになるのはごめんだ。
観念したシルフィードははぁ……とため息を吐いて、口を開く。
「あの……シルフィがしゃべってることに驚かないの?」
まずはそう問い返した。いくら使い魔でも、動物が人語を話すようになるのは極めて稀なことだ。
普通なら竜が口を利くことに驚かないはずがないのだが、グレンはそんな様子が微塵もない。
そのことにグレンは、ポカンとした表情で質問を返した。
「えッ、普通はしゃべらねぇもんなのか? そういや、竜が言葉話してるとこって見たことねぇな」
「……し、知らなかったのね?」
唖然としてしまうシルフィード。それくらいは常識であることは、シルフィードだって知っている。
まぁ、グレンはハルケギニアの人間ではないので、ハルケギニアの常識は通用しないのかもしれないが。
-
「まぁな。竜っていうくらいだし、言葉ぐらいは話せてもおかしかねぇって思ってた。怪獣にも、
しゃべれる奴はいるしな」
「しゃべれる怪獣もいるのね……!? そっちが驚きなのよ」
「ってぇなると、シルフィード、お前は普通の竜じゃねぇってことだよな」
聞かれて、シルフィードは今度こそ近くに人がいないことを確認してから、開き直ったような
態度でグレンに答えた。
「そうなのね! シルフィのほんとの名前はイルククゥ。人間はいなくなったと思ってる
古代の幻獣、韻竜の眷属なのよ! そこらの竜とは格が違うのね」
「へー、そうだったのか! お前ってすごい奴だったんだな!」
称賛されて、シルフィードは何だか誇らしい気持ちになり鼻高々となった。思えば、人間たちの
都合で普通の風竜の振りをし続ける毎日で、ずっと窮屈な思いをしていた。韻竜は本来気高い
生き物なので、そんな思いをするのはストレスが溜まる。
「そうなのよそうなのよ! シルフィはすごいのね! 飛ぶ速さだって鳥なんかとは比べものに
ならないし、精霊の力も使えるのね! 姿を変えるのだって、ほらこの通り!」
「おぉー! やるじゃねぇか!」
すっかりいい気になって人間への“変化”まで披露し、二人で盛り上がる。
しかしはたと我に返り、グレンにお願いした。
「グレン、シルフィが風韻竜ってことや、言葉を話せるってことは誰にも言わないでほしいのね。
これが知られたら、お姉さまの使い魔をやっていられなくなるのね」
その頼みを、グレンは快く引き受けた。
「分かったぜ! こいつは俺とお前の、男と男の約束だな!」
「シルフィは女の子なのね……」
と突っ込むシルフィードであった。
ともかく約束を交わしたところで、グレンが話を戻した。
「それでシルフィード、お前何でさっき暗い顔してため息吐いてたんだ? ここであったのも
何かの縁だ。相談くらいは乗るぜ」
「……実は……」
シルフィードは己の内に抱えた重い気持ちを吐き出すように、今朝からの出来事を紅蓮に打ち明けた。
シルフィードが朝目を覚ますと、森の中で五歳くらいの小さな女の子とばったり出くわした。
苺やキノコを採りに来たようであったニナという少女は、恐ろしい竜の姿を前にしても物怖じせず、
人懐っこく話しかけてきた。それが何だか嬉しくてシルフィードも少しつき合ったが、ニナは
森の中に籠を忘れていった。それを届けに、彼女の村まで行ったシルフィードだったが、村の人間に
見つかってしまい大騒ぎになってしまった。その上ニナが、他の人々の自分を恐れる様子に
感化されて、泣き出してしまったのだ。せっかく仲良くなれたのに……と、シルフィードは
それがショックだったのだ。
グレンはその話を聞いて、したり顔でうなずいた。
「なるほどねぇ……。見た目が厳ついってのは何かと不利だよな。俺だって、チーム内の人気は
ゼロやミラーナイトに取られがちでちょっと悔しい思いしてるんだよ。あいつらイケメンだからなぁ」
イケメン、と言われても、シルフィードには違いがよく分からなかった。宇宙的な美的センスは、
彼女にはまだ早かった。
「よっしゃ、そういうことなら俺が一肌脱いでやろうじゃねぇか! 要は、村の奴らがお前を
恐がらなくなりゃいいんだろ?」
「でも、どうするのね?」
「なぁに、簡単なことだぜ。俺がお前のことを、メイジの使い魔で危険なことは全然ない、
すっげぇ大人しい奴って弁解するのさ。誤解が解けりゃ、そのニナって子もお前のことを
もう怖がったりはしねぇだろ」
おお! と一瞬喜んだシルフィードだったが、すぐに思い直して断った。
「気持ちは嬉しいけど、やっぱり遠慮するのね……」
「え? 何でだよ」
「どんなに言葉で説明しても、人間はシルフィみたいのは本能で怖がる。それはどうしようも
ないことってのは、シルフィだって知ってるのね。たとえニナが怖がらなくっても、シルフィと
一緒にいたら、あの子が村で仲間外れになるかもしれないのね……。シルフィのせいで
そんなことになったら、申し訳ないの」
-
シルフィードはニナのために身を引くつもりであった。本当はあの子と友達になりたいのだが……
その気持ちを抑えつけるのだ。
「シルフィード……お前って結構大人なんだな」
「そうなのね。お姉さまはしょっちゅうシルフィをお叱りするけど、シルフィだって色々と考えてるのね」
寂しそうなシルフィードだが、本人がこう言う以上は、グレンにはどうすることも出来ない。
そっとしておくのが関の山であった。
考えとは裏腹に落胆を隠せないシルフィードは、それを紛らわすようにグレンに尋ね返した。
「ところで、グレンはこんなところで何やってたのね?」
「ああ、それだそれだ! 実はちょっと大変なことになっててな。ちょうどいい、お前にも
注意をしておくぜ」
グレンはそう前置きして、自身の目的を話した。
「昨晩、焼き鳥の奴がある怪獣と戦ってな」
「焼き鳥?」
「ジャンボットの仇名だぜ。あいつは認めねぇんだけどな。それは置いといて、その怪獣が
この辺りに逃げ込んだみてぇなんだ。そいつを捜してたって訳だ。多分こんくらいの大きさの、
青い毛の奴なんだが、見てねぇか?」
グレンはジェスチャーで、両腕で抱えられる程度の大きさを示した。
「ううん、見てないのね。というか、そんなちっさい奴、わざわざ追いかける必要あるの?」
「いや、見た目で騙されちゃ駄目だぜ。そいつは化けの皮を被ってるだけだ。ほんとの姿は
俺たちと同じくらいの大怪獣で、しかもすげぇ凶暴なんだよ。小さな姿に化けんのも、
逃げると同時に無害な生き物の振りして、人のいるとこに潜り込んで暴れようって魂胆からだ」
「うッ、そんなずるい怪獣もいるのね……」
か弱い存在を装って人を騙し、集団の内側に入り込んでから破壊活動を始める……その狡猾さは、
説明だけでも想像がついた。
「ここには学院がある。今は休暇中だが、人はいるんだろ? そこに侵入しやがったらえらいことだ。
もし青い生物を見つけても油断しねぇで、敷地内には絶対入れるな! ってお前からもみんなに
警告しといてくれ」
「だからシルフィは、人の前ではしゃべられないのね……」
突っ込むシルフィードだが、今の話は放ってはおけない。タバサには事情を説明して、
学院全体に警戒してもらうようにしよう、と行動の方針を決定するのだった。
シルフィードとグレンが出くわす少し前……ニナの暮らす村。
ニナは母親に散々説教を食らって、しょぼんとうなだれていた。竜のそばなんかに行っちゃいけない、
と怒られたのである。そうこうするうちに、ニナは地面に転がっていた籠を見つめた。
「あ、あたしのかごー」
中にはぎっしりと蛙苺が入っている。シルフィードが運んできて、騒動の内に置いていったものだ。
「かご、竜さんが持ってきてくれたんだ」
ニナは立ち尽くした。置き忘れてきたことに気づいたのは、家に帰ってきてすぐのことだった。
「……ママがいうとおり、ほんとに怖い生き物なのかな」
わからない。幼いニナにとって、母親の言葉は絶対である。でも……、今朝見たシルフィードは、
そうは見えなかった。
ニナが悩んでいると……、彼女の元にどこからか、ひょこひょこと小動物が近づいてきた。
「あれ? この生き物……何だろう?」
小動物を目にしたニナは首を傾げた。全く見たことのない生物だった。犬でも猫でもない。
強いて言えばネズミに似ているが……青い毛のネズミなど、ニナは聞いたこともなかった。
その小動物はブルブルと震えている。弱っているようであった。
-
「あなた、どうしたの? 具合が悪いの? それとも、怪我したの?」
ニナは小動物のことを心配し、自分のところで介抱してあげようと思い立った。
母親は竜を、身体が大きく力が強いので、とても恐ろしい生き物だと言っていた。ならば、
身体が小さく力も弱そうなこの生き物は、家に連れて帰っても大丈夫だろう。
「おいで、家で手当てしてあげるね」
そう決めたニナは小動物を抱え、家まで運んでいった。その道すがら、村の人たちが小動物に目を留める。
「まぁ、あの生き物は何かしら? 見たことないわ」
「でも大人しそうで、安全みたいね。それにかわいい顔をしてるわ!」
「さっきの竜とは大違いだな。貴族さまがたにも、ああいう生き物を使い魔にしてもらいたいぜ」
家に帰ったニナは、母親に小動物の世話をする許可をもらう。
「ママ、この子弱ってるみたいなの。うちで看病してあげてもいい?」
「え? 何かしら、その生き物……」
母親も初めは訝しんだが、すぐに小動物の愛らしい顔立ちとうるうるした瞳に気持ちをほだされた。
「……まぁ、危なくはないみたいね。いいわよ。それどころか、そんなかわいい生き物なら
うちで飼ってもいいわ!」
「やったぁ! ありがとう、ママ!」
ニナは喜んで、小動物をテーブルの上に乗せる。
「きみ、これからニナの友達だね! 待ってて、お薬持ってくるから」
ニナは傷に効く薬草を探しに、小動物の前から離れた。
……その途端に、小動物はニタァ……と、邪悪な笑みを口の端に貼りつけた。
-
今回はここまでです。
あかん。
-
いつも乙です!
-
皆様、お久し振りです。
よろしければ、また21:40頃から続きを投下させてくださいませ。
-
ディーキンはタバサから彼女の願いと大まかな事のあらましとを聞くと、あっさりと助力を承諾した。
タバサに深々と頭を下げられて、忠実な従者のような礼をとられたのにはいささか困ったが……。
ひとまず頭を上げてもらい、一眠りして体を休めた後、トーマスやシルフィードも含めて全員で彼女の実家へ向かおう、と取り決めた。
そうしてから、ディーキンは寝る前に、事前にいろいろと現地での方針を練っておこうとタバサに提案する。
力を貸すこと自体には何のためらいもないが、頼まれた仕事の重大性について軽く考えているわけではない。
下手なことをすれば、タバサやその母親をはじめ、自分の周囲にいる人々の身の安全が脅かされることになるかもしれないのだ。
となれば、そうそう暢気に構えているわけにもいくまい。
彼女が同意してくれたので、早速確認しておきたいことを順に質問し始めた。
「ええと、タバサのお屋敷には、今は見張りとかはいるの?」
「いない」
「じゃあ、スパイが紛れ込んでたりとかは?」
「しない。家には今、母様の他には昔からの執事が一人いるだけ。
彼の忠義は保証する」
「ンー……、魔法で監視とかもされてない?」
「ない」
タバサはディーキンのそれらの質問に、明確に即答した。
自分の家のことなのだから、変化があれば気付かないはずがない、という自信を持っているのだろう。
それから続けて、自分の意見を述べた。
「……だから、あなたが母を救ってくれても、それがすぐに王家に知られることはないはず。
私はすぐに母と執事のペルスランとを、どこか安全な場所に連れていく。
危険なお願い。だけど、母さえ救ってさえくれればそれ以上はあなたたちに迷惑が掛からないように、なんとかしてみる……」
「ウーン……」
ディーキンは、しばし眉根を寄せて考え込んだ。
タバサは優秀なメイジであり、その見る目は十分に信頼のおけるものだ。
彼女がそう言うのなら、本当に監視はされていないのかもしれない。
しかし……、絶対にそうだと断言できるものだろうか?
いかにタバサが優秀でも、彼女にとってフェイルーンの技術が未知のものであり、しばしば想定外であることは既に実証されている。
ハルケギニアには存在しないフェイルーンの呪文を用いた監視には、彼女も気が付けないかもしれない。
そして、ガリア王家内部にデヴィルが存在している疑いがある以上、そういった呪文が用いられている可能性は十分にあるのだ。
たとえそうでなくとも、ハルケギニア有数の伝統と力を持つというガリア王家に、どんな未知の魔法技術があるかわかったものではない。
タバサにも、そしてディーキンにも気がつけないような代物が存在していたとしても、何ら不思議ではないはずだ。
それに、本当に監視の目などは無く、すぐには露見しないとしても、流石に定期的な視察くらいはしているだろう。
となれば、タバサの母が正気に戻ったり館からいなくなったりすれば、即時ではないにせよ、遠からず露見することは避けられない。
それどころか、フェイルーンの呪文を向こうが使える可能性を考慮するならば……。
どこへ隠れたとしても、《念視(スクライング)》や《クリーチャー定位(ロケート・クリーチャー)》で見つかってしまう恐れがある。
タバサも、それに彼女の母親や身の回りの人間も、だ。
気が付いた時点で、誰がやったのかということをガリア王家は調査し始めるだろう。
真っ先に嫌疑をかけられるのは、当然ながらタバサのはずだ。
それを逃れるには、彼女自身も学院から姿を消して、どこかに身を隠しでもするしかない。
あるいは、ガリアからの刺客を真っ向から迎え撃つかだが、いずれにせよ非常に危険が大きいと言わざるを得ない。
-
タバサとて、それは承知の上であろう。
その上で、周囲の者に迷惑が掛からないように「なんとかする」と言っているわけだが……。
それは自信というよりは、強がり、ないしは悲壮な決意だという方が近いだろう。
とにかく母を救えさえすれば、その後は自分は父の仇と刺し違えてでも、とでも思っているのか?
いずれにせよ、ディーキンにとってはタバサの案をそのまま素直に受け入れるのは危険なように思えた。
自分が頑張って対処法を用意することもできなくはあるまいが、様々なマジックアイテムこそあれど、バードの身では少々心もとない。
現在ではサブライム・コードになるために、より深く魔法の勉強をしている最中とはいえ。
最悪、ボスたちに助力を求めるなどして、なんとかできないこともないだろうが……。
「……ねえエンセリック、あんたも聞いてたでしょ。どんなことに気を付けておいたらいいと思う?」
何かと愚痴の多い元魔術師にも話を振ってみた。
また文句を言われることだろうが、大事なことなのだから相談相手は多いほうがいい。
「あー、そうですね。いざという時に備えて私の手入れをもっと頻繁にすることをお勧めします。
あと、戦いのときはしっかり握って、思い切り振り回してくださいね」
「ンー、そう? ありがとう、じゃあそうするよ」
「どういたしまして、それでは――」
そんなとぼけたやり取りをしただけで終わりにしようとする漆黒の剣を、タバサが黙って杖で小突いた。
「……何をするのですか、お嬢さん」
「真面目な話」
「私は真面目に言ったつもりですが……。
やれやれ、どいつもこいつも、どうして剣なんかに有益な助言ができると思うんですかね?」
エンセリックはひとつ溜息を吐いた後、投げやり気味に付け加えた。
「……そうですねえ、ダークパワーの宿っていそうな黒っぽい剣の私なんかに聞くよりも、神様にでもお伺いしたらどうですか?
あなた方のやることが上手くいきそうかどうか、神様に神託でもなんでもお頼みになればいいでしょう!」
それを聞いたタバサは、むっとしたように僅かに顔をしかめた。
こっちは真剣だというのに、またふざけたことを……、と思ったのだ。
しかし、ディーキンの方は得心がいったような顔で頷いた。
「オオ……、確かにそうなの。
こういう場合はまず、神様に聞いてみるのもいいかもしれないね」
「そうでしょう。どんなにくそったれな神でも、剣よりはマシですよ。おそらくはね」
いささか困惑したような様子を見せるタバサをよそに、ディーキンはスクロールケースを探り始めた。
すぐに一枚の巻物を取り出すと、集中しやすいように一旦タバサの傍から離れてそれを広げ、長い詠唱を始める。
「《アルラウ・ゼド・ディーキン……、ルエズ・デルファウリ・デルファウルト・イオ――》」
「……彼は、何を?」
タバサは途方に暮れて、エンセリックに説明を求めた。
「はあ……、さっきの話を聞いておられなかったのですか、お嬢さん?
言ったでしょう、神託ですよ。あの詠唱からすると、どうやら相手は竜族の主神、イオのようですね」
「神託……」
そう呟くと、タバサはじいっとディーキンの様子を見つめた。
どう見ても彼が詠唱に集中する様子は真剣そのもので、声をかけることも憚られる。
目の前の漆黒の剣も、答えるのも面倒そうなやる気のない態度ではあるが、嘘や冗談を言っているようには思えなかった。
しかし……。
-
「……本当に、そんなことが?」
タバサは半信半疑といった様子で、ディーキンとエンセリックとを交互に見つめた。
ハルケギニアでは始祖ブリミルに対する信仰が盛んだが、司祭が始祖から力を授かるというようなことはない。
魔法を使う司祭はいる。だが、それはその司祭がメイジだからであって、彼らの魔法は系統魔法とまったく同じものである。
始祖のお言葉を聞いたと主張する者は時折出るが、それが真剣に受け取られることは滅多にない。
彼女は、ディーキンのすることはもちろん信頼している。
しかし、タバサのこれまでの常識では、神託に基づいて行動するなどというのは茶葉占いや星座占いの結果を信じるのと同じようなものだ。
気休め以上のなにかではなく、そんなことに大事の方針を真剣に託そうなどというのは、およそ馬鹿げた話だった。
「まあ……、確かにあなたがたのお国では、そういうことがないというのは伺いましたがね……」
エンセリックは、うんざりしたような様子で溜息を吐いた。
フェイルーンにおいては、敬虔なるクレリックが神から力や言葉を授かれることは子どもでも知っている常識である。
そんなことを一から説明するのは、実に面倒だった。
「彼が神の眷属たる天使を呼び出して頼みごとを聞いてもらったことは、すでにあなたも知っているでしょうに。
天使を呼べるのならば、神託を授かることもできるとは思いませんか?」
「…………」
ここへ来る前に学院で見たラヴォエラのことを思い出して、タバサは押し黙った。
そう言われてみれば、確かにその通りだが……。
「まあ、論より証拠です。いいから黙って見ておいでなさい、あと数分もあれば済みますよ」
タバサは少し考えた後、黙って頷いて一旦自分の疑問を引っ込め、ディーキンの詠唱を見守ることにした。
「《――ルエズ・ガルア・ズガ……、シーイール・ディア!》」
ディーキンが10分にも及ぶ長い詠唱の最後の音節を紡ぐと同時に、スクロールの文字が一瞬強く輝き、煙を残して消滅する。
その芳しい香の匂いのする煙を吸い込んだディーキンはしばし入神状態となり、神との精神的な交信が形成された。
神の存在を感じたディーキンがスクロールから顔を上げると、目の前には雲突くばかりに大きな竜の影が姿を現していた。
正確に言えば、それは彼の心の中にのみ存在するものであったが、決してただの幻覚ではなかった。
その影は、巨竜かと思えば次の瞬間には細身の翼竜のそれとなり、ふと気がつけば猫のように小さな妖精竜のシルエットに変わっている。
これこそすべての竜族の相を持ち、それを守護するとされる偉大なる竜族の主神、イオの顕現に間違いなかった。
いつの間にか周囲も安宿の部屋ではなくなり、眩い財宝に覆い尽くされた、竜族の宝物庫に変わっている。
ディーキンは再び顔を伏せると、まずは感謝の意を伝えた。
『調和の竜、大いなる永遠の転輪、影を呑む者……、一にして九なる竜族の創造主、偉大なるイオよ。
この度の呼びかけに答えてくれたことに、ディーキンは感謝してるの』
イオの影は、時に重々しく低く響き、時に子どものように高くなる奇妙な声で、それに答える。
『我が一族の末子よ、愛おしき者よ。
仰々しい挨拶をするには及ばぬぞ、汝の得意ではなかろう。
早々に願いを言うがよい、あまり長くはそなたに時間を割いておられぬのでな』
ディーキンはちょっとお辞儀をすると、目当ての質問を神に伝えた。
『ディーキンはこれからタバサと一緒にお屋敷に行って、タバサのお母さんを助けようと思うの。
それって上手くいくかな、どんなことに気をつけたらいいと思うか教えて』
それを聞いたイオの影は、心なしか、少し笑ったように思えた。
ややあって、回答が伝えられる。
『――――いかな人間の王とて、地獄の悪魔とて、どうして竜族の宝物庫に及ぶほどの守りを成し得ようか。
竜族の詩人たる汝は既に、十分な対策を知っておるはずだ。
……そうよな、さしあたっては赤竜フィロッキパイロンの宝を奪わんとした、不埒なる三匹のオークの逸話を思い出すがよいぞ――――』
-
それで、神との交信は終わりだった。
ディーキンは目の前のイオの影が薄らぎ、その存在が急速に自分の精神から離れて行くのを感じた。
次の瞬間にはもう、神の影はすっかり消え失せて、ディーキンは元の部屋の中で白紙になったスクロールを握りしめていた。
「どうやら、終わりのようですね。
《神託(ディヴィネーション)》の首尾はどうでしたか?」
もう声をかけてよいものかどうかと迷うタバサの横で、エンセリックが先に質問をした。
「うん……。イオは、ちゃんと答えてくれたの。
ディーキンたちは、『赤竜と三匹のオーク』のお話を参考にしたらいいってさ」
その後の寝るまでの時間は、概ねディーキンがタバサらにその物語を披露して、解釈について考えることに費やされた。
♪
あるところに、三匹のぐうたらオークの兄弟がいた
母さんオークは無駄飯食いの三匹をとうとう家から叩き出して、自活しろと言った
三匹の兄弟は、不満たらたら
けれど手柄を立てれば自分たちも見直されると考えた兄弟は、大胆な計画を立てた
なんと近隣で有名な赤竜のフィロッキパイロンの巣穴から、宝物を盗んでこようっていうのさ
最初に一番上のお兄さんオークが、ドラゴンが熊を食べに出かけた隙に、巣穴に忍び込んだ
彼はこう考えた。「盗んじまえばお終いさ。見られなきゃ、誰が取ったかなんてわかりっこないもんな」
彼はでっかい宝石のたくさんついた像を盗み出して、うんしょうんしょと引っ張っていった
けれどドラゴンは戻ってすぐに、像がなくなっていることに気が付いた
彼は怒って巣を飛び出すと、空の上からあたり一帯を見回した
そうして重たい像を一生懸命運んでいるオークに気がつくと、一飲みに食べてしまった
次に次男のオークが、フィロッキパイロンが生意気な真鍮竜を追いかけている隙に、巣穴に忍び込んでいった
彼はこう考えた。「兄貴はデカすぎるのを盗んだからばれたんだ。ちっこいのを盗めばいい」
そこで小さな宝石や金貨を宝の山のあちこちからちまちまあつめてポケットをいっぱいにし、巣穴を悠々と立ち去った
けれど何日か経ってから宝物を数え直したドラゴンは、数が足りないのにちゃんと気が付いた
とても怒った彼は呪文を使って、すぐになくなった宝物の場所を探し出した
こうして次男も、ドラゴンに引き裂かれて食べられてしまった
最後に三男のオークが、慎重にフィロッキパイロンのことを調べ上げた
彼はこう考えた。「疑われたらおしまいだ。幸いあいつは目ざとく宝を集めてるが、その価値には詳しくないらしい」
そこで仲間に芸術品の精巧なレプリカをいくつか作ってもらった彼は、ドラゴンの巣穴に忍び込んで、そいつを本物と取り換えた
ドラゴンは数が変わっていないので、本物の宝が偽物と変わった事には気が付かなかった
けれど何年も何年も経って、もう安心と思った彼は、酒を飲んだ夜にそのことをぺらぺらと自慢してしまった
彼の成功をねたむ告げ口オークが、そのことをこっそりドラゴンに教えた
火山みたいにおこったドラゴンは、三男のいるオークの集落にやってくると、みんなまとめて焼き殺して食べてしまった
こうして結局、三人の兄弟も、母さんオークも、告げ口オークも、みんないなくなってしまったんだってさ
……
♪
-
ディヴィネーション
Divination /神託
系統:占術; 4レベル呪文
構成要素:音声、動作、物質(香とその神に相応しい捧げものを最低25gp分)
距離:自身
持続時間:瞬間
術者はこれから1週間以内に達成しようとする目的や起きる出来事、活動等について神に質問をし、有益な助言を得ることができる。
ただし、術者の属するパーティがその情報に従って行動しなかった場合には状況が変化し、神託が役に立たなくなる可能性もある。
この呪文で得られる助言は短いフレーズ1つだけの簡潔なものか、もしくは謎めいた詩や言葉にならない前兆のような形をとる。
助言の内容が正しい可能性は、基本的には70%+術者レベルごとに1%(最大で90%)である。
ダイス・ロールの結果失敗したとしても、術者には呪文が失敗したということはわかる。
ただし、誤情報を与えるような何らかの特殊な魔術等が働いている場合は除く。
この呪文を同じ内容に関して何度も試みたとしても、得られる結果は最初に試みた時と同じになる。
--------------------------------------------------------------
短いですが、今回は以上になります。
それでは、またできるだけ早く続きを書いていきますので、次の機会にもどうぞよろしくお願いいたします(御辞儀)
-
乙ですー
-
乙
-
皆さんこんばんわ。ウルトラ5番目の使い魔34話投下準備できましたので始めます。
-
第34話
水妖精騎士団
海凄人 パラダイ星人 登場!
『疑わしきと見れば殺し、目ざわりと見れば滅ぼす』のがロマリアの真実だと、人はひそやかにささやく。
聖戦を狙うロマリアのために暗躍するジュリオは、真実を知って帰国を目指す銃士隊と水精霊騎士隊の一行に吸血鬼エルザを差し向けるが、これは失敗した。
しかし一方で、ジュリオはトリステインに残る銃士隊と水精霊騎士隊のことも忘れてはいなかった。彼らは個々の戦力ではたいしたことはないが、チームワークでそれを補って、これまで数々の怪獣や宇宙人を倒してきた。さらに現在では東方号を有し、もはやその影響力を軽視することはできない。
そう、彼らのこれからの動向は、世界をどう動かすかわからない。それを嫌い、ロマリアはジュリオからガリアのシェフィールドを介して刺客を送り込んできた。
刺客の名は元素の兄弟。兄ドゥドゥーと妹ジャネットのふたり組で、才人たちとほぼ同じ若さの少年少女であるにも関わらず、ただならぬ雰囲気を持つガリアの北花壇騎士の一員だ。
ターゲットは、東方号のメインエンジニアであるコルベールと、そのパトロンであるベアトリス。このふたりがいなくなれば東方号は鉄くずと化し、水精霊騎士隊と銃士隊は頭数は残っても、最大の戦力を失って大きく弱体化する。
そうなると、あのMATがバット星人によって全メカニックが破壊されたために、隊員のほとんどが残っていても終に再建できなかった例が再現されることになりかねない。
危機が迫っている。このままでは世界の未来が危ない。
しかし、ベアトリスは美少女だからまだいいとして、コッパゲの首に世界の未来がかかっているとなると、なにかアホらしい感じがしてきてしまう。
いや、毛根の神に愛されているか否かはこの際置いておこう。ハゲていて世の中の役に立っている人もいっぱいいるからして。
それよりも、本格的に今回の物語に入っていく前に、もう一つ前置きをしておこう。
異変があったとき、人が後に思い返すと、「あのときは朝から雲行きが怪しかった。あれは前兆だったのかもしれない」というようなことを言う。
そう感じたのならば何かしらアクションを起こせばよかろうものだが、人は日常に慣れると少しくらいの変化では動じなくなってしまうのだろう。
-
コルベールとベアトリスの命を狙った暗殺者が港町にやってきたこの日も、表面上は何事もなく始まった。ただ、暗殺者たちが街に入ったのに前後して、ふと空を見上げたある姉妹が、あるものに気づいたことを除いたら。
「ねえティア、空を見て。なにかが空から降りてくるよ」
「見えてるよティラ。へえ、ドラゴンに乗った騎士たちね。ずいぶん物々しい様子だけど、こんな街になんの用かしら」
「さあ、けどわたしたちには関係ないでしょうね。それよりも急ぎましょう、ティア。皆さんを待たせたら失礼よ」
「むー、ティラが言い出したくせに、ずるいなあ。じゃあさティラ、今日はどっちが早く着けるか? フフ……」
「「競争ね!」」
街の石畳に、軽快な靴音が響いて遠ざかっていく。彼女たちの少し上には、街に影を下ろしながら降下してくる騎竜の羽音が響いていたが、もう彼女たちがそれに気を向けることはなかった。
むろん、これですむはずもなく、数時間後に彼女たちは自分たちがなにげなく見過ごしたこのことを思い出すことになる。ただ、神ならぬ身の民にとって、なにげない変化から未来を予見しろというのは無理難題に違いないのだ。
増してや、ある日突然に見も知らぬ相手から命を狙われているなどということが予見できたら、それはもはや人外の域にいる者と言っていいだろう。
今日この日も、ベアトリスとコルベールは昨日までの延長として今日を迎えた。むろん、自分の命を狙う者がこの街に入っているなど、思うはずもない。
さて遅ればせながら、そろそろこのあたりで今回の物語の主道に入ろう。
時は、ベアトリスが潜水艦伊-403でコルベールと談話してから、ざっと一時間ほどしてからとなる。
ベアトリスは修理・改修の途中である東方号を視察し、現場責任者であるコルベールと話し合った。そして一旦休憩をとろうと、この街で拠点にしている宿に帰ってきたのだが、そこで彼女は少々落胆することになった。
「ただいま……ん、エーコたちはまだ戻ってないの?」
「はい、エーコ様たちから伝言をお預かりしています。暗くなる前には戻る、とのことですので。それまでのお手伝いは私どもが承らせていただきます」
「はぁ、そう……」
メイドからの報告を受けて、ベアトリスは「またか」とため息をついた。メイドの、お疲れでしたら熱いお茶を淹れましょうか? という言葉もろくに頭に入ってこない。
実はこのとき、ベアトリスはある悩みを抱えていた。それは、コルベールにも話したとおりにエーコたちのことなのだが、最近の彼女たちのある行動が悩みのタネだった。
「あの子たち、また特訓に行ってるのね。無茶してないといいけど……」
ある日突然のことであった。エーコたちが「姫殿下にお世話になってばかりでは申し訳ないです。今度はわたしたちが強くなって姫殿下をお守り申し上げます!」と言い出したのだ。
そして彼女たちは日々出かけて行っては特訓に励んでいる。それはいい。向上心があるのは大変けっこうなことなので、ベアトリスも最初は喜んでいた。そう、それだけならばよかったのだが……
-
ベアトリスは自室に戻ると、もう一度ため息をついて椅子に腰掛けた。もしエーコたちが戻っていたら、四人でティータイムにでもしようと思っていたけれども、ひとりでは食欲も湧いてこない。
「エーコ、ビーコ、シーコ、わたしのために頑張ってくれるのはうれしいけど、わたしにとってあなたたちがいてくれることが何より大事なのよ……」
ツインテールに伸ばした髪をいじりながら、ベアトリスはあのときのことを思い出した。超獣ユニタングと化したエーコたち姉妹をヤプールの手から救い出したとき、大切な人を失う悲しみと痛みを知った。それから今日まで、彼女たち十姉妹は人間として何事もなく過ごしてきた。ベアトリスとしてはそれだけでもう十分だったのだけれど、あれ以来エーコたちは前にも増してベアトリスに懐いてしまった。自分たちから特訓を言い出したのもその表れだが、忠誠心豊富な彼女たちは最近になってベアトリスの思いもよらないことを考え付いたのだ。
それは、ベアトリスにとって突拍子もないものだった。最初はすぐにやめさせようと思ったのだが、言われてみると自分にとって将来役立つことにつながるので、現在は黙認していた。ただ、理屈と感情は別である。
「わたしの側近は貴女たちだけで充分と思ってたけど……でも、ねえ……はぁ」
ベアトリスはつぶやきながら、何度目になるかわからないため息をついた。今頃、エーコたちははりきって”あれ”をやっているのだろう。
困ったものだ。今後のことで、考えなくてはいけないことは山のようにあるというのに、これでは手が足りない。やはり、エーコたちの言うようにするべきなのか……いや、でも数だけ増やしたところで。
思い悩むベアトリスは、やけっぱちな気持ちでベッドに飛び込んだ。そして気晴らしにと思って、ベッド脇に積み上げてあった本の一冊を手にとって広げる。それは『召喚されし書物』と呼ばれる希少な種類の書籍で、どこで誰が書いたのかはわからないが、その精巧な絵やハルケギニアのものとは懸け離れた描写からコレクターの間では人気がある。
「『リードランゲージ』……ヤー……マイマスター……うふふふ」
あらゆる文字を解読できるコモンスペルを唱え、ベアトリスは本に見入った。どうやらそれは絵でつづられる娯楽作品のようで、遠い異国のある伯爵が主人公の物語。ベアトリスはその中に登場する執事がお気に入りのようだった。
しかし、ベアトリスはこのとき無理にでもエーコたちの下に乗り込んでいかなかったことを後悔することになる。それも、この後ほんの少しして起こるとは、ベアトリスは知るよしもなかった。
さて一方、ベアトリスが思い悩んでいるとは露知らず、エーコたちはベアトリスの想像したとおり、特訓に汗を流していた。
「よーし、じゃあ今日も姫殿下のために気合入れていくわよーっ!」
エーコの声が空き地に響き、続いてビーコやシーコの「おーっ」という掛け声が続いた。
ここは工場街にある資材置き場で、現在は物資がなく空き地となっている。割かし広く、学校のグラウンドほどの広さがあるそこで、エーコたちは姉の指南を受けて戦いの特訓をしていたのだ。
『ブレット!』
「遅いよ! 杖を振るときはとにかく素早く。かっこなんてどうでもいいから相手に向けるんだ!」
十姉妹の五女ユウリの叱咤する声が響き、エーコたちは汗を流して杖を振り続けた。この街に来る前にはアルビオンで傭兵稼業をしていたというユウリの指導は激しく苛烈で、エーコたちは実の姉妹にも容赦のない指導に、汗をぬぐう間もない。
それを見て、七女ティーナと四女ディアンナは妹たちに同情したようにつぶやいていた。
-
「いやあ、ユウリ姉さん気合はいっちゃってるねー。昔っから、体を動かすことだけは得意だったから、エーコたちかわいそー」
「魔法学院に通っていた頃なんか、学院の馬を五頭も乗りつぶして、あげくに修学旅行の馬車を三台も事故らせて、貴族の娘なのにデストロイヤー・ユウリなんてあだ名をもらったくらいですものねぇ」
「うんうん、あれでトリステイン中の騎馬業者から出入り禁止を食らって、お父さまが平謝りに駆け回ったことは忘れられないわぁ。アタシはお腹抱えて笑ってたけど」
赤毛が目立つユウリの指導は、ティーナやディアンナの入っていく余地もないくらい過激で、ときたま女性とは思えない罵声なんかも混ざっていた。この訓練の厳しさは、銃士隊のそれと比べてもひけはとらなかったろう。
「え、エア・ハンマー!」
「遅いっ! そんなんじゃ実戦じゃ魔法を使う前に蜂の巣だよ。まずは素振り百回、かかれっ!」
「はっ、はいい!」
エーコたちは姉の怒声に、腕が痛くなりながらも杖を振り続けた。
が、なぜエーコたちがここまで過酷な訓練を続けてるのであろうか? その理由は、実は水精霊騎士隊にあった。
知ってのとおり、この港町は東方号の母港である。つまり東方号を使っている水精霊騎士隊の少年たちも、この街には慣れ親しんでいてベアトリスともよく顔を合わせている。
ロマリア行きが中止して引き返してきた際、水精霊騎士隊の一部はギーシュに率いられてロマリアを目指したが、残りは東方号とともに帰還してきた。その後、東方号の修理をしながら訓練を続けていたのだが、ある日に修理状況を視察に来ていたエーコたちに対して、水精霊騎士隊の少年の一人がこんなことを言ったのだ。
「修理の視察ねえ。ご覧のとおりさ、毎日毎日、少しでも早く直そうとみんな奮闘しているあの音が、一リーグ離れていたって聞こえるだろ? それをわざわざ見に来るなんて君たちも暇だね。ぼくらなんか、今日も厳しい訓練を続けているっていうのに。まあ、しょうがないか、ぼくらの肩にはトリステインの将来がかかってるけど、君たちはクルデンホルフ姫殿下のお茶汲みをしてれば安泰なんだろ? そんなことより、よかったら後でいっしょにお茶でもどうだい」
そいつは訓練の疲れから来たストレスでか、深いことは考えずに嫌味を言ったのだろうが、これがエーコたちの逆鱗に触れた。
以前とは違い、一度離反して自分たちを救ってくれたベアトリスに対する彼女たちの忠義は本物だ。その自分たちの忠義を侮辱されたことは、主君であるベアトリスを侮辱されたことに他ならないからだ。
エーコたちは激怒した。そして軽口を叩いた太っちょなそいつは、茶色の悪魔と黄色の鬼神と緑色の死神によって、豚のような悲鳴をあげてボロ雑巾のようにされたあげくに犬の餌にされた。なお、この件に関して水精霊騎士隊からの抗議などは一切ない。隊長ギーシュの、レディには常に優しくあれ、レディを傷つけるものはすべからく我らの敵だというモットーが正しく履行された結果であった。
しかし戯れ言をほざいた豚をつぶしても、エーコたちの怒りは収まらなかった。豚に対してではない。そんな侮辱をされて、心の一部ではそれを認めざるを得なかった自分たちの弱さを自覚してしまったがために、自分自身に対して怒っていたのだ。
「わたしたちが弱いままじゃ、また姫殿下の名誉に傷がつけられるかもしれない。ビーコ、シーコ、わたしたちは姫殿下に救われて以来、わたしたちがどうすれば姫殿下のお役に立てるか考えてきた。今、その答えが出たわね!」
「ええ! 下品な男たちなんかに姫殿下は任せられないわ。なら、わたしたちがあいつらより強くなるしかないじゃない!」
「なら特訓ね。貧乏貴族のグラモンの部隊なんか、わたしたちの前を歩かせたりしないわ。姫殿下はいずれクルデンホルフを継いで、世界を統べるお方。その手足は最強じゃなきゃいけないのよ!」
-
こういう具合で、エーコたちの中に水精霊騎士隊へのライバル意識が芽生えたのである。
そして彼女たちは、あちこちで様々な経験を積んできた姉たちに教えを請うことにした。姉たちも、ベアトリスに対してはまだ負い目を感じていたので罪滅ぼしになればとこれに飛びつき、こうしてエーコたちは今日まで自分を磨いてきた。その努力はすばらしいもので、普通なら三日も持たないであろう猛訓練を続けてきている。今では水精霊騎士隊の少年たちともたいした差はないだろう。
また、姉たちは様々な分野で活動してきたので、エーコたちに与えられるものは戦闘技能以外にも数多くあった。
例えば、ある日はユウリの都合が付かなくてディアンナが教えることになったのだが、彼女が教えるものはもちろんユウリとは違っていた。
「では、今日は私があなたたちにハルケギニアの交易を教えてあげるわ。よーく聞きなさいよ、それでなくともあなたたち三人は、お勉強の時間になると寝息を立ててたんだから」
「はーい、頑張りまーす。あーあ、次は歩くお小言百科のディアンナ姉さんの番か。長い一日になりそう」
「対話術と言いなさい。一流の貴族には一流の外交能力も必要なの、それにあなたたちもクルデンホルフの一翼を担っていくなら、世界の情勢について知らないと話にならないわ。特に、ゲルマニアの商人たちの狡猾さはトリステインの比じゃないわ。騙されて野良犬同然に落とされた貴族なんて星の数ほどいるんだからね」
ディアンナはゲルマニアで、とある商業ギルドに潜り込んでいたので世界情勢に詳しかった。また、三女キュメイラは医者見習いをしていたし、ティーナはエーコたちより子供っぽく見えるが、小柄で身が軽いことを生かしてラ・ロシェールで港湾作業員をしていた。平たく言えば、入港してきた船を桟橋に固定したりマストの上げ下げを手伝う係である。こうして、様々な分野で活動することで、ハルケギニアの社会を知りたがっていたヤプールに情報を渡していたわけだが、スパイでなくなったからといって経験まで消えることはない。皮肉なものだが、人生とはどこで何が役に立ってくるかわからないものである。
エーコたちはこうして、将来ベアトリスの役に立ちそうなことはなんでも吸収していった。人間は目標を見つけると強い。アホぞろいの水精霊騎士隊が強いのも、女王陛下のために尽くそうという一念を持っているからだ。
ただし、熱意と努力というものは必ずしも正しいほうへ行くとは限らない。
「よーっし、今回はとりあえずここまでだ。水飲んでいいぞお前たち」
「ふぁ、ふぁーい」
ユウリの特訓がようやく終わり、三人はクタクタになって息をついた。まだ寒い季節なのに滝のように汗が出て気持ちが悪い、三人は魔法で水を作って飲み、頭からかぶって汗を流した。
「し、死ぬかと思ったわ」
「ひゃあん冷たいっ! もうっ、加減してよ、下着までビチョビチョじゃない」
「すぐ乾くよ。姫殿下のところに、汗臭いまま帰るわけにはいかないでしょ。透けて困るものも持ってないことだし」
「ちょっとビーコ、それどういう意味かしら?」
そんなエーコたちを、姉たちは暖かい目で見守っていた。
-
本当に平和だ。世界には危機が迫っているが、今の自分たちのここには平和がある。家を失い、両親を失ったあのときは、まさかまたこんな平穏が来てくれるとは思えなかった。
それもみんな、ベアトリス・イヴォンヌ・クルデンホルフ、あの小さな体で大きな器のお姫様のおかげだ。自分たち姉妹はあの方に大きすぎる借りがある、借りっぱなしではいけない。恩返し、そう恩返しをせねば貴族の矜持に関わる……
そのとき、彼女たちのいる広場に複数の足音が響いてきた。
「ちょうど終わったところみたいね。ほら、みんな連れてきたわよ」
「あっ、姉さんたち。もう、遅いよ」
それは姉妹の次女セトラの声だった。その隣には、キュメイラと六女イーリヤもついている。
だが、足音はそれだけではない。なんと、姉妹たちに続いて十人近い少女たちがやってきたのだ。
「おはようございます、先輩方。我ら水妖精騎士団総勢十一名、ただいま参上つかまつりましたわ」
「よく来たわ。よーっし! みんな、整列! 傾聴! また新しい顔も見えるわね。ようこそ、そしてよろしく。わたしが団長のエーコよ、わたしたち水妖精騎士団はあなたたちを歓迎するわ。いっしょに、トリステインの淑女の未来のために戦いましょう」
エーコが肩まで伸びたサイドテールを揺らしながら宣言すると、少女たちも拳をあげて歓声をあげた。
”水妖精騎士団(ウィンディーネ)……”
これが、彼女たち一団の名前である。そう、これこそがベアトリスが頭を悩ませている真の理由であった。なんと、エーコたちは自ら新しい騎士団を作り出そうとしていたのだ。
団員はエーコたちの姉妹を除いて、現在総勢十一名。皆エーコたちと同じくらいの少女で、この街に勤めている軍人や役人の娘たちである。もちろん全員がメイジであり、エーコたち姉妹がそれぞれ集めてきて、現在も団員は絶賛募集中だ。
しかし、なぜエーコたちはこのような無謀なことを始めたのだろうか? そしてなぜ、こんな無謀なことに十人以上の参加者が集まっているのだろうか? その原因は、実はまた水精霊騎士隊にあったのである。
「団長、よろしくお願いします! 団長たちの噂はかねがね、あの破廉恥な水精霊騎士隊の男を成敗なされたとか」
「聞くところによると、空中高く放り上げて街灯上に吊し上げ、木っ端微塵になされたそうですね。それを聞いたとき、胸のすくような気持ちがいたしましたです」
「なにせ、あの水精霊騎士隊の男たちの軽薄さときたら、ひどいものでしたね。でも、エーコさんたちのお話を聞いて勇気が出ました。あの野蛮な水精霊騎士隊をやっつけましょう!」
水精霊騎士隊への恨み言が機関銃のように少女たちの口から飛び出してくる。実は、水精霊騎士隊の少年たちは時間があると、女の子に声をかけてまわるため、少女たちは彼らのしつこさにうんざりしていたのだ。彼らは年齢的には思春期真っ只中の青少年であり、さらにギーシュの影響で女性に対して大胆になっていた。
「美しいお嬢さん。少しぼくと散歩でもしませんか? お花でも摘みながら、お互いについて語り合いましょう」
こんな具合に誘ってくるのだがら、女の子のほうとしてはいい迷惑としか言いようがない。ギーシュのモットーが、今度は悪いほうに働いた結果がこれだった。
-
さらに隊長ギーシュの不在もこれに追い討ちをかけた。普通ならば行き過ぎる前に、フェミニズムの塊であるギーシュや、常識人でやや奥手のレイナールがブレーキ役となるが、ふたりともロマリアに行っていていない。大人たちも、コルベールは東方号にかかりきりで、アニエスは頻繁にトリスタニアに出かけていて、ミシェルもいない。歯止めがなくなった少年たちは、「どうせ隊長もロマリア美人を相手にいい思いをしてるに違いない。だったらぼくらも隊長に従ってゆこうじゃないか」と、身勝手な解釈をしたのだった。
つまり一言で言えば、「水精霊騎士隊、被害者の会」である。その気もないのに口説かれて辟易していた少女たちはエーコたちの呼びかけで団結し、今ではついに騎士団を名乗るほどメンバーが増えている。そもそも”水妖精騎士団”という名前も、水精霊騎士隊に当てつけたものであった。
「聞きなさい、男たちは女を下に見ているけど、このトリステインは女王陛下の治める国。白百合の国を、汗臭い男たちなんかに任せておいていいと思うかしら?」
「いいえ! 白百合のごとき女王陛下は、蝶のごとき妖精がお守りするべきです!」
「水精霊騎士隊の隊長、ギーシュ・ド・グラモンは女癖の悪いことで有名なグラモン元帥の息子よ。今はロマリアに行ってるけど、そんなのが帰ってきたらわたしたちの身がどうなるかわかったものじゃないわ。わたしたちの身を守るのは、誰だと思う?」
「はい! わたしたちの身を守るのはわたしたち自身です」
ギーシュにとってはとんだとばっちりである。
「よく言ったわ。わたしたちの力で、水精霊騎士隊をぎゃふんと言わせてあげましょう。そうすれば、クルデンホルフ姫殿下もお認めになられて、公式な騎士団へ昇格するのも夢じゃないわ。さあ、特訓特訓! 着いてきなさい、あなたたち」
エーコに続いて、少女たちも掛け声を一斉にあげて答えた。少女たちは、こんな街では友達もろくに作れず、寂しい思いをしていたので同じ志を持つ仲間が増えるのはうれしかったのだ。
彼女たちは、寄せ集め所帯ながらも本気だった。本気で、水精霊騎士隊と戦って倒して取って代わろうとさえ思っていたのだ。ベアトリスが頭を痛めるのも当然と言えるだろう。しかしベアトリスがそのことをエーコたちに咎めると、将来ハルケギニアを統べようと志している人が自前の騎士団のひとつも持っていなくてどうしますか、と言われると手持ちの人材の少なさを嘆いていたのも事実なのでそれ以上強くも言えないありさまだった。
と、そこへ、広場の入り口から、やや調子っぱずれな声が響いてきた。
「やっほーっ! 先輩ー、おっそくなりましたぁ」
「ティア、遅刻したのにそれじゃ失礼よ。申し訳ありません、エーコ様、ビーコ様、シーコ様」
「ティラ、ティア!? あなたたち、また来たの」
広場の入り口から駆け込んできて、三人の前で止まったふたりの少女を見て、エーコたちは肩を落として困った様子を見せた。
-
その二人は、年のころはエーコたちと同じか少し上くらいに見えて、二人とも新春の若草のような鮮やかな緑色の髪を持っている。ただ、ぱちりと開いた瞳と整った顔立ちの美少女であったが、なんと二人はまったく同じ容姿をしていた。つまり双子である。
ただ、見分けられないかと言えばそうでもなく、ティアと呼ばれたほうは髪が肩までと短く、ティラのほうは腰まで伸びている。また、雰囲気もティアのほうがどこかふてぶてしいが、ティラのほうは小さな丸眼鏡をかけていて、少し幼げな様子を感じられた。衣装はふたりとも、ふたりの髪と同じグリーンの光沢を持つ、スリットスカートをしたチャイナドレス風のものを着ていた。
二人はエーコたちの前に堂々と立つと、困惑している新入りの少女たちに向かって堂々と宣言した。
「はじめまして、わたしはティラ」
「わたしはティア」
「「わたしたちは、エーコ姉さまたちの一の家来です」」
胸を張りながらそう言ってのけたふたりを見て、集まった少女たちはぽかんとするしかなかった。
しかしエーコたちはそうはいかない。ビーコが仕方なさそうに、ティラとティアに言った。
「ティラ、ティア、何度も言ってるでしょう? 平民は騎士団には入れないのよ」
「またまたぁ、ケチケチしないで入れてくださいよ。わたしたちとエーコ様たちの仲じゃないですか。ねえティラ」
「そうですわ。わたしたちはエーコ様たちに大きな恩を感じているのです。それとも、わたしたちにはもうお飽きになりましたの? 行きずりの関係だったのですか。うっうううぅ」
「そっ、そんなことないったら。泣かないでティラ、あなたたちはわたしたちの大切な友達なんだから」
「「ほんと! やった、だから大好き! わたしたち、エーコ様たちのためならなんでもやりますわ!」」
「だからわたしはあなたたちには別に……もう、どうしてこうなっちゃったのかしら」
頭を抱えて、ビーコはどうしたものかと首を振った。
このティラとティアという姉妹と出会ったのは、今からざっと二ヶ月ほど前にさかのぼる。
ある日、エーコたちはいつものように工場を見回っていると、騒ぎが起こっているのを耳にした。ただのケンカであれば官憲の仕事であるので触らずにゆくところだが、どうも異端審問だの宗教裁判だのと危険な単語が聞こえてきたので、慌てて駆けつけると、工場の人間たちにティラとティアのふたりが囲まれて、街の神父に弾劾されているところだった。
「ちくしょう、なんでブリミルとかいう奴を褒めなきゃ飯も食えねえんだよ。クソッタレが」
「では両名とも、反省のつもりはないということですね。仕方ありません、ロマリア宗教庁の名の下に君たちふたりを異端者とみなし、死刑を」
「待ちなさい!」
エーコたちは死刑判決が出される直前で割り込み、神父から事情を聞いた。簡単にまとめると、工場で働いている少女ふたりが昼食時の食堂で神父がおこなう始祖ブリミルへのお祈りに対して暴言を吐いたのが原因だという。
-
それが、ティラとティアだった。エーコたちはふたりからも言い分を聞くと、異端審問を中止させてふたりを引き取った。異端は大罪であり、エーコたちのやったことはかなり危険な行為だ。しかし、ティラとティアが身寄りがなく、ふたりだけで働きに出てきていると聞いたとき、エーコたちはとても見捨てて行くことはできなかった。
「いい、あなたたち。どんな田舎から出てきたかは知らないけど、始祖ブリミルへの侮辱は大罪なの。今回は世間知らずということでかばってあげられたけど、次はないわよ。気をつけなさい」
「は、はい。ありがとうございます。はぁ……なんてお優しい」
「うっうっ、人間にも、こんないい奴がいるんだなぁ。決めた! あたしらの星じゃ、恩を受けたら必ず返すのが決まりなんだけど、この命、あんたたちのために使わせてもらうよ!」
こういう具合に、すっかりと懐かれてしまったのである。正直、ありがた迷惑ではあったけれども無下にすることもできず、簡単なことを手伝ってもらったりしているうちに少しずつ気心も知れてきた。魔法は使えないそうなので平民には違いなく、仕事をまかせてよいかどうかは最初疑問があったけれど、ティラもティアも想像以上に利発で働き者で、たいていの仕事は一度教えればすぐに覚えた。
これは思わぬ拾い物だと、エーコたちが評価を改めるのには時間はかからなかった。過去はあまり語りたがらなかったが、それは自分たちも同じなので無理に聞くことはしない。それに、ふたりとも少々変わっているところはあっても、変わっていることに関しては自分たち姉妹も似たり寄ったりなので気にしなかった。
「ティラ、ティア、あなたたちすごいわね。まるで学者か医者だったみたい。ほんと、あなたたちみたいな子がなんでこんなところで下働きしてたの?」
「そうですね……実はわたしたちは、ある学者の先生についてこちらに来たんですけど、その先生が亡くなって、それで帰るあてもなくなってしまって」
「そうだったの。よければ送る手はずを整えてあげましょうか? あなたたちはもう充分働いてくれたし、クルデンホルフの名義でなら、ハルケギニアのどこへでも旅券を作ってあげられるわよ」
「いやいや、命を救われたお礼をこの程度でなんてもったいない。帰っても、満足に恩も返せずに帰ったりしたらこっちがどやされますって!」
「でも、ご家族や友人が心配してるんじゃ」
「「まあそう遠慮なさらずに!」」
うまくはぐらかされてしまったような気がしたが、こうして今日までティラとティアはエーコたちといっしょにこの街で過ごしてきた。やがてエーコたちの姉妹もティラとティアのことを知るようになり、いつしか二人も姉妹の中に入ってきたかのように親しく交流するようになってきた。
とはいえ、仕事に役に立つかどうかと戦いで強いかは別である。エーコたちが作ろうとしている騎士団は、本気で水精霊騎士隊に対抗するための武道派集団である。魔法を使えるか使えないかということで、どれくらい戦いにおいて違いが出るかということをよく知っているエーコたちは、身分関係なくできた友人を危険な目に合わせたくはなかった。
そのことは、もう何度もティラとティアには説明した。しかしふたりは聞く耳を持たず、今日まで押し問答が続いている。
「はぁ、しょうがないわね。今さら帰れというのもなんだし、あなたたちは魔法は使えないし。なにか、やりたいこととかある?」
「水泳! わたしたち泳ぐのとっても得意なんです。みんなで泳げばきっと楽しいよ!」
「却下! まだ寒いのにみんな風邪ひいちゃうわよ。もう、どうしようかシーコ?」
騎士団に参加する気満々で、帰るつもりなどさらさらないティラとティア。ビーコが困った様子で助けを求めると、シーコは少し考えるそぶりをしてから自分のかばんを取り出した。
-
「んーん……そうだねえ、じゃあ今日は趣を変えて勉強会ということにしようか」
「勉強会?」
「うん、姫殿下が最近『召喚されし書物』を愛読してるの知ってるでしょ? 殿下が読み終わった本を持ってきたから、これをみんなで読みましょうよ」
シーコがかばんをひっくり返すと、どさどさと本が転げだしてきた。
「悪くないわね。あ、でもリードランゲージはみんな使えるけど、それだとティラたちが読めないんじゃない?」
「それは大丈夫、ティラたちにはわたしが読んであげるから」
「シーコ、あなた最近ティラたちに甘くない? というより最初から二人が来るのを見越してたでしょ」
「えへへ」
髪の色が同じ緑で似ているからか、末っ子で妹ができてうれしいからなのか、シーコはこのふたりと特に仲がよかった。
とはいえ、すでに空気が特訓向きではなくなっているのもある。見ると、ユウリやティーナら姉たちも、それでいいんじゃないか? というふうにわくわくした顔をしている。ほかの少女たちも同様だ。召喚されし書物とは、それだけハルケギニアでは贅沢な娯楽なのである。
そうと決まれば、わっと少女たちは本に群がった。それぞれ好きな本を手にとってリードランゲージを唱え、思い思いに楽しみはじめる。
本はいずれも絵で物語を追っていくものであったが、作者は異なっているようで内容は様々であった。海賊の少年が世界の海を冒険するものや、メガネをかけた力持ちの少女がむっちゃんこな騒動を起こしていくものなど、どれもハルケギニアではありえないようなストーリーと描写が多感な子供の心をぐっと引き込んできた。
なお、シーコとティラたちは「せっかくだから見敵必殺の精神が学べるものにしましょう。最近姫様が読んでるこれとか、これなんてどう?」と、三人して吸血鬼や眼鏡のデブや神父が仲良く戦争する本や、妖怪首おいてけや眼帯親父や男女が国捕りする本を熱心に読んでいた。
読書会の様相となった水妖精騎士団の面々は、笑ったり興奮して叫び声をあげたりしながら、読み終わった本を交換しながら楽しい時間を過ごした。こうした面では、彼女たちも年頃の少女そのものであった。
その端で、セトラやキュメイラは自分たちも好きな本を読みながら、妹たちに新しい友達が出来ていっていることをうれしく思っていた。たとえ、集まった動機は少々不純でも、若者とは元来そうしたものだ。それに、なんであろうと目標を持ってそのために努力しているというのはすばらしい。
しかし、姉たちはエーコたちの成長を快く思いながらも、同時に自分たちの教えられることへの限界も感じ始めていた。
-
「ユウリ、どう、最近のエーコたちの育ち具合は?」
「悪くないよ、もうそこいらのごろつきよりはよっぽど強いんじゃないかな。けど……」
「けど?」
「あたしの戦い方はあくまで我流だからね。ケンカに強くはできても、エーコたちが求めてる騎士団としての戦い方は教えられないんだ。どっかに、実戦経験豊富で集団戦も得意なメイジがいればいいんだが、あたしらにそんなのを雇う金なんてねえし」
「そうね、みんなもそろそろエーコたちに教えられることがなくなってきてるし、これ以上の成長を見込むならプロの誰かに頼むしかないけど、あの子たちはけっこうプライドが高いから、知らない人間に素直に教えを受けるかどうか」
難しいわね、とキュメイラとユウリはため息をついた。
それぞれの思惑は異なれど、楽しい時間を過ごす少女たち。だが、そんな彼女たちに、大変な危険が迫りつつあった。
少女たちの和む広場に、ガチャガチャとうるさい鉄の足音を響かせて入ってくる大勢の影。少女たちがあっけにとられて見上げる前で、無作法な侵入者たちのひとりが嘲るように言った。
「こんにちは、可愛らしいお嬢さんたち。よろしければ、私どもと楽しいお時間でもいかがかな?」
重い鉄の鎧を着込んだたくましい重装騎士の一団の乱入に、少女たちの間に戦慄が走る。しかし、エーコたちはその騎士たちが身につけている紋章がクルデンホルフのものだということに気づき、目の前に現れた男たちの名を苦々しげにつぶやいた。
「空中装甲騎士団……」
そして同じ頃、ベアトリスも予期せぬ客を前にして怒りを覚えていた。
「なんですって……? もう一度、言ってみなさい」
「ははっ、我ら空中装甲騎士団一同、ベアトリス殿下の護衛のためにはせ参じました。本日よりは、我らを手足のように使い、存分に大事をなせとの当主様よりのご命令です」
目の前にひざまづいて頭を垂れる騎士たちを見下ろして、ベアトリスは「お父様め、余計なことを……」と奥歯をこすらせた。
空中装甲騎士団。それはクルデンホルフ公国の有する竜騎士の大隊で、実力はハルケギニアでも五指に入ると武勇が知れ渡っている。
当然、ベアトリスにとっても誇るべき勇者たちなのだが、今回は事情が異なる。空中装甲騎士団は確かに強いが、裏を返せばそれだけの軍団であって融通がきかない。護衛にしては大げさすぎるし、権威を示すにしても周り中が貴族だけの魔法学院ならまだしも、この街では平民への余計なプレッシャーになってしまう。
恐らくベアトリスの父、クルデンホルフ公国王は辺境で努力している娘への親心として空中装甲騎士団を送ったのだろうが、今のベアトリスに必要なのは戦闘集団ではない。様々な事態に柔軟に対処できる小回りのきく人材なのだ。空中装甲騎士団では助力どころか足手まといになってしまうだろう。
「必要ないわ。わたしは今のままでもじゅうぶんに仕事を勤めてる。あなたたちは帰還してクルデンホルフ本国の防衛につきなさい」
-
最初が肝心だと、ベアトリスは不要の意思を断固とした口調で伝えた。しかし、相手も壮齢に達した歴戦の騎士団の指揮官、簡単には引き下がらない。
「そのご命令は聞けませぬ。我々は当主様直々のご命令を受けております。常に姫様を警護し、あらゆる脅威からお守りしろとのこと。聞くところによると、姫様は先日暴漢に襲われてお怪我をなされたとのこと、ご心配なさるお父上のお気持ちもお察しください」
これはもちろんヤプールに騙されていたときのエーコたちの姉妹に負わされた傷のことである。しかしベアトリスは恨みに思ったことはないし、傷自体もすぐに治して口外も避けてきた。しかし、どこからか漏れて本国に伝わってしまったらしい。
「そのことは心配いらないわ。たいした傷を負わされたわけじゃないし、何事をも無傷で済ませられると思うほど子供じゃないつもり。危険に近づくのも勉強のうち、お父様のお気持ちはうれしいけど、わたしは信頼できる部下は自分で集める。お父様の手を借りるつもりはないわ」
「いえ、あなた様はまだお若い。どんな狡猾な輩に騙されるか、まだ世間の厳しさをわかっておりませぬ。しばらくは、忠義に疑いのない我らをお使いくださいませ。姫様につこうとする害虫は、我らがすべて排除いたしまする」
「大きなお世話よ。わたしにはもう、エーコたちが……まさかあなたたち! エーコたちに」
「あのような没落貴族の子弟なぞ、信用がおけませぬ。今頃は、泣き喚きながら化けの皮をはがされておりましょう」
「っ! あなたたちっ! エーコ、ビーコ、シーコ!」
ベアトリスは惰眠をむさぼっていたことを後悔した。ドアを蹴破るようにして駆け出すが、エーコたちが特訓場所に使っている広場はこのホテルから急いでも三十分はかかる場所にある。
間に合うか、間に合って!
体裁も考えず、ホテルから飛び出して必死に走るベアトリス。その頭上には、ホテルの屋上から飛び立った竜騎士が、どんなに急いでも遅いよとでも言う風にゆっくりと飛んでいた。
だが、事態はここで誰もが予想もしなかった方向へと進もうとしていた。
エーコたち、仮称水妖精騎士団に対して、逃げ場を塞ぐように広場の入り口に布陣する総勢三十名の空中装甲騎士団。彼らはエーコたちへの嘲りを隠そうともせず、高圧的に要求を突きつけた。
「つまり、金輪際ベアトリスさまに近寄るな。さもなければ痛い目にあってもらう、ということですね?」
「そうさ、クルデンホルフの財産からこれまでいくらかすめとってきた? あいにくだが、これからは真の忠義を持った我々が姫殿下をお助けする。わかったか、薄汚いこそ泥ども」
ぶつけられる罵声に対して、エーコたちは表情を変えずに受け止めた。だがエーコ、ビーコ、シーコの心には怒りの炎が激しく燃え始めていた。
こそ泥? こそ泥と言ったか? ふざけないでもらおう。わたしたちはこれまで、金子を目当てにあの人といたことは一度たりとてない。
しかし空中装甲騎士団は人数だけでもエーコたちの倍近くもいる余裕からか、エーコたちの心の機微を察しようともせずににやけ笑いを続けている。エーコたち姉妹以外の少女たちは、はじめて体験する恐ろしげな男たちの空気に怯えて後ろで震え上がっていた。
-
張り詰める空気。しかしそれを破ったのは、ひとりの少女のせせら笑う声であった。
「ウ、フフフ、クックククク……」
「む? 小娘、なにがおかしい!?」
「ティア!?」
その場の全員の目が、ふてぶてしく笑う緑色の髪の少女に向けられた。
「笑える冗談ね。あんたたちは自分たちの半分くらいの相手に鎧をつけて現れるような臆病者の軍隊で、わたしたちはハルケギニア最強の軍集団を目標にして集った精鋭たち。肥えた体を包み隠さなくては人前にも出られないようなロートルが、真の忠義とはねぇ」
「な、なんだと小娘! まだ子供だと思って甘い顔をしてたらつけあがりおって!」
挑発するティアに、いきり立つ空中装甲騎士団の男たち。がしゃがしゃと鎧を鳴らし、鈍器にもなっている杖を握り締めて威圧する。そのプレッシャーに、怯えていた少女たちはさらに縮こまった。
空中装甲騎士団としては、この威圧だけで女子供の集まりなどたちまち降参してしまうだろうと考えていた。が、その期待は雄雄しい叫びによって打ち砕かれた。
「水妖精騎士団、杖を取りなさい!」
エーコの凛々しい声が広場に響き渡り、恐怖に怯えていた少女たちの耳も揺さぶった。
「え、エーコさん!?」
「わたしたちが間違ってたわ。水精霊騎士隊をつぶして、ハルケギニア最強の騎士団を目指すなら、こんなところでつまずいてられないもの。わたしたちの目の前に立ちふさがる障害は叩いて潰す! 逃げも隠れもせず、正面から押し潰し、粉砕する! さあ杖をとりなさい! あなたたちは狗か? 豚か? それとも人間か?」
茶色い髪を振り乱しながらエーコの放った激が、怯えていた少女たちから恐怖心を薄れさせていった。
そうだ、こんな理不尽な脅迫に屈するわけにはいかない。ここで戦わなかったら、一生逃げたという足かせを引きづったまま生きることになる。仲間たちが戦おうとしているのに逃げたら、もう二度と貴族と名乗れない。
震えながらも杖をとって前に出た少女たち。年若くても、彼女たちもまた誇り高いトリステイン貴族の血を受け継いでいた。
ユウリやディアンナたちも笑いながら杖を抜いている。二十人近い少女が臨戦態勢に入り、その恐れを知らぬ様子は歴戦の騎士たちをもたじろがせるものがあった。
対峙する空中装甲騎士団と水妖精騎士団。空中装甲騎士団は、思ってもみなかった少女たちの反抗に驚きながらも、それでも虚勢を張って杖を向けて通告してきた。
「お嬢さんたち、もう冗談ではすまないぞ。我々空中装甲騎士団に杖を向けたこと、たっぷりと後悔させてやる。泣いて謝っても許さん! 遺言でも考えておけ」
「遺言ね、じゃあせっかくだし先に聞いておいてもらおうかしら? ティラ、ティア」
-
杖を向けられたシーコが、ティラとティアを連れて一歩前へ出る。そして彼女たちは空中装甲騎士団に対して、”遺言”を歌うように読み上げていった。
「小便は済ませたか?」
「神様にお祈りは?」
「部屋の隅でガタガタ震えて命乞いをする心の準備はOK?」
これが決定打になった。いきり立って、杖を振り上げてくる空中装甲騎士団。対するは、実戦経験皆無の水妖精騎士団。
「シーコ、なに? 今の台詞」
「さっき読んだ召喚されし書物に載ってたの」
「うん、とりあえず女の子が言う言葉じゃないね」
呆れた様子のビーコと、いたずらを成功させたように茶目っ気に微笑むシーコも戦闘態勢に入り、ティアとティラもうれしそうに笑う。
「あっはは、ケンカですねケンカだね。楽しくなってきたなあ」
「でもテレポートとかを使っちゃだめよ。さあ、恩返しの絶好のチャンスね」
そして、騒ぎを少し離れた場所から楽しげに見守っている、黒い服の少女がひとり。
「うっふっふふ、見ものですわ見ものですわ。こんな面白そうなものが見れるなんて、今日はラッキーね。お仕事はこの後にしましょっと」
事態はひたすらに混迷を深めていく。果たして、最後に立っているのは誰なのだろうか……
続く
-
今回は以上です。ちと調子に乗ってややネタ分多めでお送りいたしました。
ベアトリスかわいいですよねベアトリス。21巻で出番があればいいのですが。ツインテは大好物です。
パラダイ星人のふたりは引っ掻き回し要員として思いついたのですが、キャラ立てしていったら今後の重要な要素の柱としても有効になってきたのでしばらく出すつもりです。
ちなみにパラダイ星人は原作では鋭い爪を持った星人ですけど、この話の中では手袋をして隠しているということで補完してください。
本来はこの回で主役怪獣を出すはずだったのですが、ちと長くなってしまったので次回にまわします。なお、キングパラダイではありません。
あとジャネットのファンの方々すみません。
年内にもう一回は投稿したいと思ってますが、ガルパン劇場版をまた観に行かなきゃいけないしなあ。
今年はアニメが豊作な年でしたね。原作が完結したら、いつしか完全な形でのゼロ魔アニメが見たいものです。
ではまた。次回はシリアスにいきます(たぶん
-
乙です!
-
こんばんは、焼き鮭です。今回の投下をさせてもらいます。
開始は21:57からで。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第七十八話「風の竜のともだち(後編)」
凶悪怪獣ギャビッシュ 登場
ジャンボットが取り逃がした凶悪怪獣ギャビッシュの行方を追うグレンが見たのは、
シルフィードがしゃべっているところ。これによりグレンは、シルフィードが伝説の
風韻竜であることを知ったのだが、彼女の正体を公言しないという約束を取り交わしたことで、
シルフィードの秘密は守られることとなった。
そのシルフィードは、ちょうど悲しい経験をしたところであった。森の中で小さな女の子、
ニナと知り合ったのだが、彼女の村の人たちが恐ろしい竜の姿のシルフィードを拒むので、
ニナもシルフィードを恐れてしまったのだ。せっかく友達になれそうだったのに……と、
シルフィードは落ち込んでいた。グレンが取り成そうとも提案したが、シルフィードはニナの
これからのために身を引くことを決めたのだった。
シルフィードはそれから、グレンのギャビッシュ捜索を手伝う。だが、悪魔のような怪獣の魔の手は、
既にハルケギニアの人間に忍び寄っていたのであった。そう、他ならぬニナの元に……。
シルフィードは背の上にグレンを乗せ、上空から森を見下ろしていた。シルフィードが尋ねかける。
「でも、小さくなれる怪獣をこんな空の上からで、捜し出せるのね?」
小動物のようなサイズになれる怪獣を見つけ出すのは、地上からでも至難の業というのは容易に想像がつく。
それなのに空から捜して、発見できるのだろうか。地上には木々に茂る葉しか見えないのだが。
だがグレンは自身ありげに答えた。
「そこんところは大丈夫だぜ。怪獣のパワーの波長は焼き鳥が記録した。空からでも、近くまで行きゃあ
どんだけ小さくなろうと、その波長から居場所を探知できる。だからお前は、この辺をとにかく飛び回って
くれりゃそれでいいのさ」
「ふーん? よくわかんないけど……怪獣は確かにこの辺にいるのね?」
「テレポート能力があるとはいえ、手負いの状態じゃ遠くへは逃げれないはずだ。絶対近くに
いるはずなんだが……とにかく、早えぇとこ見つけ出さなきゃなんねぇぜ。発見が遅れりゃ遅れるだけ、
危険の度合いが増してく手合いだからな……」
そう話し合いながら森の上を飛び回っていくシルフィードとグレン。
そしてニナの村の近くまで差し掛かった。
「あッ、あの村は……」
先ほどのことを思い出して一瞬悲嘆に暮れるシルフィード。しかしその時に、グレンが叫んだ。
「やべぇ! 怪獣はあの村の中だ!」
「えぇッ!?」
その言葉の直後に、一軒の家が突然内側から破られ、青い毛皮の大怪獣が飛び出してきた!
この怪獣の正体は当然ギャビッシュだ!
「ピィ――――――――!」
「うわあああぁぁぁぁぁぁぁぁぁッ!?」
村の人たちは、いきなり出現した怪獣に度肝を抜かれ、大慌てで逃げ惑い出した。
「くっそ、遅かったか! 誰かあいつに捕まってねぇだろうな……!」
グレンは冷や汗を垂れ流し、超感覚で人質の有無を探る。
出来ればいてほしくなかったが、残念ながらギャビッシュの右眼の奥に子供の姿があることを
捉えてしまった。
「まずいぜ、もう小さな子供が奴の目の中に閉じ込められてる……!」
「小さな子供!? まさか……!」
シルフィードは最悪の想像をした。そしてその想像も的中した。
破壊された家から逃げ出していた女性の叫びが聞こえたのだ。
「ああ! あんな小さな生き物が怪獣だったなんて……! ニナが、ニナがあいつに捕まった!」
顔面蒼白になるシルフィード。やはり、ギャビッシュに捕まった子供とはニナのことだったのだ。
-
「ピィ――――――――!」
ギャビッシュは村の破壊は行わず、代わりに進行方向を魔法学院のある方へと向けて森に踏み込む。
「もっと人質を増やして、誰からも攻撃されねぇようにするつもりか!」
そんな悪行を許してはならない。だが、ニナが目の中に囚われている以上、ギャビッシュに
攻撃することが出来ない。
戸惑うグレンたち。と、そこにジャンバードが大空から駆けつけてきて、ジャンボットに変形し
ギャビッシュの前に立ちはだかった。
『待て! ここから先へは行かせんぞ!』
ジャンボットは早速ギャビッシュに飛びついて進行を食い止めるが、攻撃は加えない。
彼も人質がいることに気がついているのだった。
「ピィ――――――――!」
それをいいことに、ギャビッシュは容赦なくジャンボットを攻め立てる。鋭い牙で肩に噛みつき、装甲を砕く。
『ぐわぁッ!』
ひるんだところを爪で切り裂き、突き飛ばして尻尾の先端からの電撃光線を浴びせた。
『うぐわぁぁぁぁッ!』
防戦を余儀なくされるジャンボット。このままではやられるのも時間の問題だ。
「ど、どうにかニナちゃんを助けられないの!?」
泡を食って問いかけるシルフィード。それに対し、グレンは険しい表情で告げた。
「方法は一つだけだぜ……」
「あるのね!? 早く教えて! シルフィードも力になるのね!」
もう会わないと決めたが、こうなっては話は別だ。何としてでもニナの救出に尽力する所存だ。
そうしてグレンが、その方法を語った。
「焼き鳥の転送光線で俺たちがあいつの目の中に入り込んで、ニナを連れて脱出するんだ!」
「そんな単純なことなのね? だったら早く……!」
「だが入る時はよくても、脱出する時が問題だぜ。目の中から飛び出すんだから、文字通り奴の
目と鼻の先に出るんだ。とんでもなく危険だ」
ギャビッシュも馬鹿ではあるまい。人質を救い出したら、その瞬間に目先の彼らに襲いかかるはず。
対するグレンたちは、どうしても抜け出た瞬間は無防備にならざるを得ない。
「下手したら、命を落とすことだってあり得るぜ。シルフィード、お前それでもやれるのか?」
「……!」
問われて、一瞬返答に窮するシルフィード。怪獣の恐ろしさは彼女ももう知っている。
グレンの言葉が確かな現実になり得るものであることは、重々理解している。
いくら何でも、そこまでする必要があるのだろうか? ニナは今日会ったばかりの子供。
本当ならシルフィードとは何の関わりもないのだ。命を賭すほどの価値があるのだろうか。
「……やるのね!」
それでも、シルフィードはそう答えた。
「本気だな?」
「うんッ! ニナちゃんはちょっと会っただけだし、言葉も交わせないけれど……シルフィの
ともだちなのね! ともだちは大事なものだって、お姉さまもそう思ってる! 命がけでも
助けるには、十分なのね!」
「よぉし分かったぜ! 絶対に俺たちでニナを救い出すぞッ!」
シルフィードの回答を気に入ったグレンは、すぐに行動に移った。ジャンボットの転送光線の
範囲内に入り、呼びかける。
「焼き鳥! 俺たちを奴の目の中に送ってくれ! 人質を救出する!」
『ジャンボットだ! って、それどころではないな! 頼んだぞ!』
もたもたしている暇はない。ギャビッシュがこちらの意図に気がつく前に、ジャンボットの
転送光線がグレンとシルフィードを包んで、一気にギャビッシュの目の奥へと二人を送り込んだ。
-
飛び込んでいったギャビッシュの眼球の中では、ニナがめそめそと泣いていた。
「怖いよぉ、ママぁ……」
そこにゆっくりと近寄っていくグレンたち。シルフィードが鳴き声を出す。
「きゅい」
「え……?」
振り返ったニナはグレンと、シルフィードの存在を確かめる。
「あなたは……さっきの竜さん? どうしてこんなところに……」
「こいつ、シルフィードは君を助けにここまで来たんだぜ」
と教えるグレン。それを聞いて、ニナは泣き止んでシルフィードの顔をまじまじと見つめた。
人間の感覚からしたら、厳つくて恐ろしい竜の顔。しかし、今のニナはその瞳の中に、
温かい優しみを見出していた。
「竜さん……ありがとう……」
ニナはシルフィードの首にそっと抱きつき、つぶやきかけた。
「きゅい……」
シルフィードは目をつむり、小さく鳴く。
しかし今は穏やかな時間を過ごしている暇もないのだ。
「ニナちゃん、礼を言うのはまだ早いぜ。ここから脱出だ! さぁ、シルフィードに乗るんだ」
「うん!」
グレンがニナを抱え上げてシルフィードの背の上に乗せ、シルフィードにはこう囁きかける。
「シルフィード、心の準備はいいな? ここから出たら、一気に森の中に飛び込んで隠れるんだぜ!」
「きゅい!」
グレンの指示に、決意を固めた面持ちでうなずくシルフィード。先ほども説明したが、
ギャビッシュが目の中で行われていることに気がつかないはずがない。脱出した瞬間に、
彼らに牙を剥いてくるはず。シルフィードはそれから逃げ切らないといけないのだ。
大変危険なことだ。
それでも、シルフィードはそれをやる覚悟があるからこそ、ここに来たのである。
「よし……行けぇッ!」
グレンの合図で、二人を乗せたシルフィードが一直線に飛び立った!
ギャビッシュの水晶体と角膜をぬるりとすり抜け、シルフィードが外の世界に脱け出した!
そこは当然ながら、ギャビッシュのすぐ眼前。
「ピィ――――――――!」
この瞬間に、ギャビッシュがシルフィードたちに食らいつこうと首を伸ばす!
「危ねぇッ!」
「きゅいい!」
あわや食い殺されるかというところで、シルフィードは急降下した。その甲斐あって、
すんでのところでギャビッシュの牙から逃れられた。牙はガチン、と空を切る。
ギリギリ攻撃をよけられたが、ギャビッシュはすぐに追撃を行おうとする。
『させんぞッ!』
しかしジャンボットがすかさず飛びついて、追撃を阻止した。彼のお陰で、シルフィードは
ぐんぐんと森に近づいていく。
「いいぞ! あと少しだぜ!」
興奮して声を張り上げるグレン。このまま森に紛れてニナとシルフィードを逃がせば、
そこからはギャビッシュを一気に仕留めてくれる。
「ピィ――――――――!」
『ぐわッ!』
だがギャビッシュも甘くはなかった。長い尻尾を横から叩きつけてジャンボットを弾くと、
シルフィードめがけ針状の光線を吐き出す!
「きゅいぃ!」
必死に光線をかいくぐるシルフィードだが……避け切れずに、針の一本が胴体をかすめた!
-
「きゅいー!」
「シルフィードッ!」
「竜さん!?」
シルフィードはバランスを崩し、森の手前、村の入り口の付近へと不時着した。
「シルフィード! おい! しっかりしろ!」
「竜さん、しっかりしてー!」
シルフィードが最後まで力を振り絞ったお陰で、背の上のグレンとニナに負傷はなかったが、
その代わりにシルフィード自身の息が絶え絶えだ。グレンが慌てて応急手当てを行い、ニナが
必死に呼びかける。
「ピィ――――――――!」
ギャビッシュは冷酷無情にそこへ攻撃しようとする。が、
『やめろぉッ!』
体勢を立て直したジャンボットの鉄拳が突き刺さり、殴り飛ばされた。
『この卑劣漢め! 貴様は最早万死を免れんぞ! ジャンファイトだ!』
小さな少女を人質にし、更に彼女を命がけで救出した竜を撃ち落とすような悪質な怪獣への
義憤にジャンボットは燃えていた。そしてギャビッシュとの間合いを詰め、格闘戦を行う。
「ピィ――――――――!」
応戦するギャビッシュだが、人質が助けられた以上はジャンボットも遠慮がない。相手の鋭い爪を
鉄の拳が弾き返し、ギャビッシュを何度も殴り飛ばす。自慢の牙で噛みつこうとしても、顎を掴まれ
大きく投げ飛ばされた。
「ピィ――――――――!」
肉弾戦では分が悪いと見てか、ギャビッシュが尻尾を持ち上げて先端から電撃光線を放射しようと構えた。
『させるものか! ジャンブレード!』
しかしそれより早く、ジャンブレードを出したジャンボットが跳ぶ。そして刃が一閃し、
ギャビッシュの尻尾を切断した!
切り落とされた尻尾が地面に落下し、ビタンビタンと跳ねる。
「ピィ――――――――!?」
ここに至って、ギャビッシュは最早勝ち目なしと見たか、なりふり構わず背を向けて全力の逃走を始める。
だが、今更そんな真似を許すジャンボットではない。ジェットで飛んでギャビッシュの前方に
回り込み、すかさずとどめの光線を撃ち込む。
『ビームエメラルド!』
緑色の光線はギャビッシュの胸に直撃! ギャビッシュの全身は青い炎に包まれ、そのまま完全に燃え尽きた。
こうして卑劣極まる凶悪怪獣は天誅を受けたのであった。
しかしギャビッシュを倒せても、地に伏せたシルフィードは目を開かなかった。
「うえーん! 竜さーん!」
伏したままピクリとも動かないシルフィードに覆い被さり、ニナはわんわんと泣きじゃくる。
そこに、怪獣が倒されたことで戻ってきた村人たちが集まる。
「その竜は、今朝の……」
「俺は見たぜ。ニナちゃんは、その竜が怪獣から救い出したんだ」
「でも、どうして竜がそこまでして……」
ざわつく村人たちに、グレンが説明する。
「その竜、シルフィードは、ちょっとの間だがニナちゃんと仲良くしたんだ。そのニナちゃんを
見捨てることは出来ねぇと、危険をかえりみずに怪獣に立ち向かってったんだよ」
それを聞いて、ニナの母親が一番ショックを受けた。
「ああ、うちのニナのためにそこまで……。あんな仕打ちをしたってのに、申し訳ない気持ちでいっぱいだわ……」
ニナの母親を始めとして、村人たちは次々とバツの悪い表情となった。
「こいつは竜だけど、心優しい奴だったんだな……」
-
「わたしたちは見かけだけで判断して、いい竜を追い出して、悪魔を呑気に受け入れた……。
なんて愚かだったんだろうね……」
「この竜には感謝してもし切れない。本当に、ありがとう……」
心から反省した村人たちは、せめてシルフィードの優しさと勇敢さを称えようと、一斉に黙祷を捧げた。
「うう、竜さん、こわがってごめんなさい……。竜さぁん……」
ニナもまた謝罪し、シルフィードの死にさめざめと涙を流したのだった。
……現在のシルフィードが生きているのだから、ここで死んでいるはずがない。
シルフィードは単に意識を失っていただけで、数時間後にしっかり目を覚ましていたのだった。
「きゅーい!」
「わぁ、たかーい! すごーい!」
ニナを乗せて宙を舞うシルフィード。ニナは肌で風を感じ、きゃっきゃっと楽しそうに笑う。
あの事件を経てシルフィードは村の人たちに受け入れられ、ニナとも本当に友達になることが出来た。
言葉を交わすことは出来ないものの、暇な時はともに遊ぶような関係になったのであった。
本来の生息地から遠く離れた場所に召喚されて、タバサといない時は孤独であることが
多かったシルフィード。しかしもう孤独ではなくなった。大事な友達が出来て、シルフィードは
とても気持ちよさそうに空を自在に飛んでいる。
その様子を地上からながめたグレンもまた、快活な笑顔を浮かべていたのであった。
-
以上です。
今年の投下はあと一回で終わりそうです。
-
乙です
そういえばギャビッシュって複数体いる怪獣でしたね。ダイオリウスやゾンバイユとかもうろついてるしダイナ世界の宇宙は修羅の国ですな
-
皆様、お久し振りです。
よろしければ、20:20頃からまた、続きを投下させてください。
-
一通りの話し合いを終えた後、ディーキンはさらにもう少し作業をした。
まず、《神託(ディヴィネーション)》で得た情報について皆と話し合い解釈して立てた、いくつかの仮説を確認する必要があった。
そのためにもう一度スクロールケースを探り、今度は《交神(コミューン)》の呪文を使用する。
この呪文を用いれば複数の質問に対して神から明確な回答を得られるが、その質問は原則二択で答えられるような形でなくてはならない。
したがって、まずは《神託》でヒントを得た後に、それに基づいて、質問するべき事項をいくつかに絞り込んだのである。
タバサは《神託》の時と同様やや不審そうにはしていたが、ディーキンのすることなのだから確かだろう、と納得してくれたようだ。
その質問の結果に基づいて、タバサと別れた後にディーキンは再度考えをまとめ、さらにいくつかの仕込みをした。
そうしてから、ディーキンはようやく寝床に入った。
ひと眠りして目を覚ました後、タバサとディーキンはトーマスにも事情を説明した。
それから軽く食事をしてシルフィードと合流した一行は、竜の姿に戻った彼女の背に乗って、一路ラグドリアンへと向かう。
ラグドリアン湖はガリアとトリステインの国境沿いに広がる、ハルケギニア随一の名勝と名高い大きな湖だ。
その一帯は古くから、ガリア王家の直轄領になっているのである。
しばらくの空の旅の後に、その美しい湖が見えてきた。
タバサはシルフィードに指示すると、ひとつの大きな屋敷の前に彼女を降り立たせる。
そこが、彼女の実家だった。
旧い、立派なつくりの大名邸である。
門に刻まれた紋章は交差した二本の杖、そして“さらに先へ”と書かれた銘。
それはまごうことなき、ガリア王家の紋章であった。
タバサの父、オルレアン大公シャルルは先王の第二王子であったのだから当然のことだ。
しかし、その紋章には大きな罰点の不名誉印が刻まれている。
それはこの家の者が、王族でありながら現在はその権利を剥奪されている、ということを意味していた。
トーマスはしばし沈痛な面持ちでその紋章を見つめながら、かつて仕えた名家の没落を悲しんでいた。
ディーキンもまたじっとその紋章を見つめて、先刻タバサから聞かされた彼女の身の上話を思い返していた。
タバサの祖父が命を落とした後、王位を継いだのは先王の長男であり、タバサの伯父でもあるジョゼフだった。
長男が王位を継ぐのは通例に倣えば当然のことであり、本来何も怪しむべき点はない。
しかし、国内の多くの貴族は、その決定に戸惑いを見せたという。
長男のジョゼフは貴族の証である魔法もまともに使えず、そのため陰で嘲笑され、暗愚と揶揄されていた男だった。
対して、タバサの父でもある次男のシャルルは若くして四系統すべてに精通し、頭脳も明晰で人柄も良く、多くの者から慕われていた。
そのため多くの者は、先王は後継として第二王子の方を選ぶに違いないと思っていたのである。
-
この意外な決定に、不信感を露わにする貴族も多かった。
しかもその後、まもなくして、彼らの疑いを決定的にするような事件が起こった。
先王の死から僅か十日ばかりの後に、シャルルは暗殺されたのである。
それもジョゼフに招かれて参加した狩猟会の途中に、魔法ではなく、下賤な毒矢で射抜かれて命を落としたのだった。
当然シャルル派の貴族たちはジョゼフによる謀殺であることを確信し、怒りの声を上げた。
しかしタバサによれば、彼らは反乱の企てをタバサの母であるオルレアン公夫人に持ちかけたものの、彼女は応じなかったという。
夫に続いて自分と娘もジョゼフによって呼び出された時、彼女は娘が飲まされようとした毒の杯をその手からもぎ取って、自ら仰いだ。
夫人は、国を二つに割って戦を起こすようなことは望まず、ただ一人残された娘の身の安全だけを願ったのである。
その結果、彼女は謎めいた毒の効力によって心を壊され、今も屋敷の寝床に伏せたまま、悪夢の中を彷徨い続けている。
そしてタバサは、その夫人の嘆願によって命だけは助けられたものの、身分を剥奪され、危険な任務を押し付けられることになった。
断ることはできない、そうすれば自分と母との身の破滅を招くだけだから……。
その話をタバサから聞かされた時のディーキンの率直な感想は、人間の貴族もドロウみたいなことをするんだな、というものだった。
典型的なドロウの社会、たとえばアンダーダークの大都市メンゾベランザンなどでは、そうした家系内での争いは日常茶飯事なのである。
ドロウたちの崇める主神ロルスは、『デーモンウェブ・ピット(蜘蛛の巣地獄)』と呼ばれる次元界を治める女神だ。
その教義は極めて女尊男卑的なもので、ロルスに仕える司祭は必ず女性でなければならず、彼女らは女神によって互いに争わせられる。
ロルスは忠義よりも野心を好み、他のいかなる神格にもまして、自身に仕える者たちを永遠の試練にあわせようとするのだ。
彼女は自分に仕える者たちが男を女と対等の存在と見たり、慈悲や愛情、平和を求める心などを抱くことを一切許容しない。
そうして男たちが踏みつけられ生贄に捧げられる様を見て、また強者が弱者を間引く果てない裏切りの連鎖を見て、狂える女神は狂喜する。
ロルスに仕える尼僧たちは一人の例外もなく、位階を登るには目上の者を後ろから刺すしかないと心得ている。
もちろん、目下の者が同じことを自分にしかけてこないはずはないことも。
しかもそのような狂った教義の毒は、尼僧のみならずドロウの社会全体を蝕んでいる。
覇権を求めて互いに争い合うのは、尼僧でない女たちの間でも、身分の卑しい男どもの間でも変わらないのだ。
家族の間でさえ、それは同じだ。
ドロウの親子の間には愛情などはなく、互いに不快な競争相手であり、家系が滅びぬために許容している必要悪でしかない。
妹はその地位を上げるために、姉を謀殺しようとする。
長姉は母長の力が衰えて家系の権力が衰退する前に代替わりをしようと、母親の背中を刺す機会を伺う。
そして、自分自身がそうやって支配権をもぎ取ってきた母親は、娘たちが自分の命を狙わぬはずがないことをよく心得ている。
もちろん、父や息子たちの間にも、まったく同じことが言える。
かの名高いドリッズト・ドゥアーデンの物語でもその旨は語られていたし、仲間のナシーラもいろいろと昔の話を聞かせてくれた。
彼女は元々、今は滅びてしまったメンゾベランザンのとある貴族家の末娘だったのだ。
家系の支配権を握るために母や姉たちを排除する計略を弄んだことは、彼女自身にも一度ならずあったという。
ナシーラがそれを実行に移さなかったのは、彼女が弱かったからでも善良だったからでもなく、ただ自分が魔術師だからというだけだった。
ドロウ社会の支配階級は尼僧であり、魔術師が公然とその上に立つことは許されないのである。
仮に家系内の敵をすべて打ち破れたとしても、他の家系から睨まれては生き残るのは難しいからという、ただの打算と妥協の結果だ。
-
彼女らの基準から見れば、タバサの語った境遇ですら、十分に恵まれている部類に入るのだろう。
ドリッズトは父親のザクネイフィンという男からは愛され、心を通わせていたそうだが、それは極めて稀な幸運だったらしい。
事実、母親の方とは対立し、家系を捨てて決別した後には命を狙われたことも度々あったという。
両親から愛されて育つことなど、ドロウにとっては贅沢極まる夢物語なのだ。
当のディーキン自身とて、別段幸福な境遇で育ったわけではない。
幼少期から主人や仲間たち、あるいは異種族に命を脅かされたことは数知れないし、特に家族から愛されて育ったというわけでもない。
というよりも、そもそもコボルドは、親子関係も含めて家族という間柄をほとんど重要視していないのである。
ディーキンにも、おばあちゃんと呼んでそれなりに慕っていたコボルドはいた。
だが、彼女は部族で子育てを生業としていた年配者だったために皆からそう呼ばれていただけで、ディーキンの実祖母ではない。
ディーキンは自分の兄弟姉妹が誰なのかも明確には知らないし、それどころか両親が誰かということさえも、はっきりとは知らないのだ。
もしかしたらディーキン自身にも息子や娘がいるかもしれないが、それさえも確実には分からない。
一応、コボルドには、自分と血縁の近い個体を嗅ぎわける嗅覚は備わっている。
だから、誰が自分の家族なのかといったことは、ディーキンにも一応推定することくらいはできる。
しかし、実際のところその感覚は、単に近親間での意図せぬ交配を避けるために備わっているというだけなのだ。
普通のコボルドにはそれを使って家族を捜し、絆を育もうなどという気はさらさらない。
一般的にコボルドは繁殖期に複数の異性とつがい、その結果として産み落とされた卵はすべて同じ孵化場に集められる。
どの個体から生まれたコボルドもみなそこで孵化し、同じ部族の一員となるのである。
コボルドは“部族”の単位で生活する種族であり、“家族”という単位はほとんど意識に上ることさえないのだ。
そうした習慣についてディーキン自身にはあまり思い入れはないが、そうはいってもそれを当然とする環境で育ってきたのも事実である。
人間のような種族が持つ“家族愛”というものには好い印象は持っているものの、正直あまり実感はわかなかった。
だからといって、タバサの苦しみを軽んじる気などはもちろんディーキンにはない。
家族との愛情を育んだ経験こそないが、好きな人を理不尽に失う悲しみや怒りならばよく知っている。
互いに愛し愛されていたからこそ、両親を襲った不幸に強く心を痛め、憤りを感じるのは当然なのだということは理解できる。
(ウーン……、ナシーラがタバサの話を聞いたら、なんていうかな?)
彼女は今はドロウの善なる女神イーリストレイイーの教えに感銘を受け、過去の生き方を捨てて同族たちを救おうと頑張っている。
とはいえ、冷酷な魔術師にして暗殺者であった頃の習慣や考え方も根強く残っているのだ。
彼女はタバサに同情し、同族たちと同じように、その不幸な境遇や憎しみの檻から救い出してやろうとするのだろうか。
それとも、大して過酷でもない環境で悲壮ぶる小娘だと冷たく笑って、厳しく突き放すのだろうか。
いずれにせよ、彼女ならばタバサに、なにがしかのよい影響を与えてはくれるのではないだろうか。
一度会って話をしてもらいたいものだとは思ったが、彼女は今、アンダーダークと地上とを往復して忙しく活動する日々を送っている。
大した用件でもないのに、おいそれと呼びつけるわけにはいくまい。
ディーキンは小さく頭を振ってとりとめのない考えを振り払うと、門をくぐって家へと向かうタバサの後を追った。
-
タバサが帰還しても、当然ながら出迎えはなかった。
彼女は事前に帰省する旨を伝えていないし、現在この屋敷には正気を失った彼女の母と、ただ一人残った忠実な老僕しかいないのだから。
それでもトーマスがかつての使用人としての忠義を示し、彼女のために進み出て呼び鈴を鳴らそうとした。
しかし、タバサはそれを手で制すと、自ら家の扉を開けて、客人たちを中に招き入れる。
この時、ディーキンは魔法による監視や見張りの存在の心配はしていなかった。
昨夜の《交神》による質問の中のひとつで、この館には現時点では恒久的な監視や見張りが存在しないことは既に確認済みだった。
ややあって姿を現した執事のペルスランにタバサが事情を説明すると、一行は屋敷の客間へと案内された。
ディーキンが《変装帽子(ハット・オヴ・ディスガイズ)》を外して本来の姿を晒すと、最初は非常に驚かれたが……。
タバサとトーマスの説明でじきに納得すると、正体が亜人だからこそ治療の成功を期待できると思ったのか、老僕は目を輝かせた。
ペルスランは居間で寛いだ一行にワインや菓子を勧めながら、恭しく礼をする。
トーマスとディーキンも、それぞれに挨拶を返した。
「いやはや! このペルスラン、もう何年もの間、これほど嬉しい日はございませんでした。
お嬢さまのおっしゃるとおり、奥さまが本当に治られるのならば……。
いや、たとえそれが叶わなかったとしても、お嬢さまが昔懐かしいあのトーマスと、お友達とを連れてこられただけでも!」
「ありがとうございます、ペルスランさま。
同じガリアの空の下に住みながら、長い間ご無沙汰をいたしました」
「はじめまして、おじいさん。
そうだよ、ディーキンはディーキン、詩人で冒険者で、タバサの友達だよ」
一通りの挨拶や四方山話などが済むと、タバサはディーキンを促して、いよいよ母親の元へ案内しようとする。
しかし、ディーキンはそれを手で制すると、ペルスランの方へ向き直った。
「すぐにお母さんを治しに行ってあげたいけど、ちょっと待ってね。
ええと、ペルスランさん。ちょっと、お願いしたいことがあるんだけど……」
「は……、なんでございましょうか?
費用や礼金のことでしたら、当家にはもはや財貨もあまり残されてはおりませぬが、可能な限り」
「イヤ、それはいいの。お金は、ちょっとはかかるかもしれないけど、どうか気にしないで」
そうしてひとつ咳払いをすると、ディーキンは奇妙な要求を伝えた。
「ディーキンが欲しいのはね、おじいさんの―――」
-
コミューン
Commune /交神
系統:占術; 5レベル呪文
構成要素:音声、動作、信仰、経験(100XP)、物質(聖水ないしは邪水と香)
距離:自身
持続時間:瞬間
術者は自分の神格、ないしはその代理人と交信し、単純な「然り」か「否」で答えられる質問をすることができる。
一言だけの回答では誤解や神格の利害に反する結果を招きかねない場合には、代わりに短文での回答が与えられる場合もある。
行なえる質問の数は術者レベル毎に1つまでであり、与えられる解答は、質問をされた存在の知識の及ぶ限りでは正しいものである。
神格と言えど必ずしも全知ではないが、他の神格やそれに準じるほど強大な存在が故意に隠蔽している事柄以外は大概わかると思ってよい。
もし質問の答えがわからない場合には、「定かならず」という回答を与えられる。
--------------------------------------------------------------------
短いですが、今回は以上になります。
前回から大分間が空いてしまいまして、申し訳ありませんでした。
またできるだけ早く続きを書いていくようにしますので、次の機会にもどうぞよろしくお願い致します。
それでは、失礼しました(御辞儀)
-
おつです
-
こんばんは、焼き鮭です。今年最後の投下をさせてもらいます。
開始は02:08から。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
幕間その六「父と師匠」
二面凶悪怪獣アシュラン 登場
「ピッギャ――ゴオオオウ!」
「イヤァーッ!」
M78ワールドのある惑星の衛星上で、宇宙怪獣に真紅の戦士が立ち向かっていた。
怪獣は鬼のような形相の人型怪獣であるが、肉体の両面にそれぞれ赤い顔と青い顔を持った、
表裏の概念がない非常に特異な体型をしている。その名は凶悪宇宙怪獣アシュラン。高い力と頭脳を
兼ね備えた恐るべき大怪獣である。
そして真紅の戦士は、獅子座L77星の王子であった宇宙空手の達人、猛き戦士のウルトラマンレオだ!
レオはここの惑星で、暴力に物を言わせて好き放題に星の住民たちを苦しめていたアシュランを発見し、
衛星に追い詰めて一対一の勝負をしているところなのであった。
「デイッ! イヤァッ!」
レオの十八番、宇宙空手の手刀や蹴りがうなりを上げてアシュランに決まっていく。だがアシュランは
前後を頻繁に入れ替えることで受けるダメージを分散するので、なかなか倒れない。
「ピッギャ――ゴオオオウ!」
そして隙を見て両目からの怪光線を発射する!
「イヤァッ!」
レオはバク転で怪光線を回避するが、アシュランは続けざまに口から火炎放射を繰り出して追撃。
レオはアシュランの後方に回り込んでいって火炎から逃れようとするものの、そうするとアシュランの
反対側の顔から火炎が放たれる。
アシュランはただ破壊力のある怪獣ではない。前後の顔が360度をカバーする、全方位に
隙のない堅牢さを誇るのだ。この特性には、さしもの一流の戦士レオも苦戦を強いられる。
「ウゥッ!」
火炎攻撃でダメージを負うレオの様子を、遠くの衛星の大地からウルトラマンメビウスが目撃した。
彼は今回、レオとともにこの周辺の宙域に派遣されてきたのだ。
『レオ兄さん!』
思わず救援に駆けつけようと身を乗り出したメビウスだが、その肩をウルトラセブンが掴んで制止する。
『待て、メビウス。アシュランは狡猾な怪獣だ。ウルトラ戦士が複数になったら、すぐにでも
逃げ出してしまうだろう』
『ですがセブン兄さん、いくらレオ兄さんでも、一人でアシュランには……!』
アシュランは並みのウルトラ戦士の力をもはるかに超える大怪獣だ。事実、かつてレオは
別個体のアシュランと戦ったことがあるが、その時は彼だけでは全く勝ち目がなく、ジャックの
助力を得て初めて倒すことが出来たのだった。
だが狼狽えるメビウスに、セブンは言い聞かす。
『レオを信じて、見ていろ』
その言葉に応えるかのように、追い詰められつつあったレオの動きが変わる。彼の反撃だ!
「デェイッ!」
右腕に赤い輝きを発生させると、光球に変化させて素早く投げつけた! レオの光線技、エネルギー光球だ!
「ピッギャ――ゴオオオウ!」
エネルギー光球は見事アシュランの赤い面の命中。それの引き起こす爆発が、アシュランに
無視できぬ大きな負傷を与えた。
アシュランは青い面を前にして負傷部分を隠すが、その時にレオが走り、跳躍!
「ダァッ!」
アシュランの頭上を跳び越えて赤い面の方に回り込み、鋭い拳の突きをお見舞いした。
「ピッギャ――ゴオオオウ!」
負傷した顔面を殴られ、アシュランも耐えられずに動きが止まる。そこにレオは連続ハイキックを
入れていき、アシュランをきりきり回転させる。
-
アシュランがグロッキー状態になったところで、レオが再び高く跳んだ!
「イヤァーッ!」
アシュランの真上できりもみ回転し、足が赤熱化するとそのまま急降下! かつてセブンの
課した特訓の元に開発した、きりもみキック!
回転キックは無抵抗のアシュランの脳天に突き刺さった。前後に顔を持つアシュランも
頭上だけはお留守であった。
「ピッギャ――ゴオオオウ!!」
アシュランは両方の口から黄色い血をダラダラと垂れ流し、バッタリと倒れて大爆発。
こうしてまた一つ、宇宙の悪が散って命ある星が守られたのだった。
『レオ兄さーん!』
レオがアシュランを討ち取ると、メビウスとセブンが彼の元へ駆けつける。
『お見事でした、レオ兄さん! あのアシュランを一人でやっつけるなんて!』
『うむ、また一段と腕を上げたな、レオ』
肩を叩いて健闘を称えるセブンに、レオは笑って答える。
『情けないところを見せたら、またあなたにどやされてしまいますからね。昔のあなたは、
それはもう厳しかった』
『ははは、言うようになったじゃないか』
互いが地球を守っていた時代を思い出して朗らかに笑い合うレオとセブン。
と、その時に、セブンが不意に顔を上げた。
『む……』
『どうしました、セブン兄さん?』
メビウスが尋ねると、セブンは宇宙の彼方を見つめたままつぶやいた。
『今、確かにゼロの気配が……ゼロの光の波動が感じられた』
『えッ!?』
驚くメビウス。しかしその声音は、前回ゼロの気配の消失を聞いた時とは異なる、喜びの響きだ。
レオもまた告げる。
『俺も感じました、ゼロの光を。セブン兄さんの言葉の通り、ゼロは再び立ち上がったようですね』
実はこの瞬間が、バルキー星人の前に絶体絶命だった才人が復活したゼロに変身した瞬間であった。
二人の戦士、ゼロの父と師匠はそれを感じ取ったのだった。
メビウスが嬉々としてうなずく。
『ゼロがよみがえった……! これでもう安心ですね!』
『ああ。私はこの時が来るのを信じていた』
と言うセブンを、レオが茶化す。
『そう言う割には、ずっと心配そうだったじゃないですか。どこかそわそわとしていて』
『むッ。レオ、お前こそ弟子の安否が気にかかってたように見えたぞ』
咎めるようなセブンの言葉だが、口調は明るい。こんなことを言い合えるのも、二人が
安心し切ったからであり、また二人の仲の良さがあるからこそだ。
『それはまぁ、ゼロは手塩にかけて鍛え上げた弟子ですからね。気にもなります。全く、あんなに
手を焼かされた奴もいない。修行中は、本当にはねっかえりの強い奴でしたからね』
『そう言うお前にも、私は何度も手を焼かされたものだがな』
『あれ、そうでしたっけ? すいませんが、よく覚えてませんね』
今では偉大なウルトラ戦士のレオも、恩師のセブンの前だとありし日の若々しい青年のような態度だ。
メビウスは何だかそれが新鮮に感じられた。
『それはともかく、ゼロは立派な戦士に育ってくれました。今手合わせをしたら、俺も勝てるかどうか
自信がありません。さすがはあなたの息子だけあります、セブン兄さん』
『ゼロが立派になってくれたのも、お前のお陰だ、レオ。お前に託して正解だった。感謝している』
この星系の恒星の光が差し込む中、向かい合って言葉を交わすセブンとレオ。その様子は、
かつて二人が地球の平和を守ることを誓い合った時の構図によく似ていた。
-
その様を目の当たりにしたメビウスは、二人の間の固く熱い絆を自身も感じて、感動を覚えていた。
『……しかし、ゼロが復活したからといって安心ばかりしていられない。怪獣の被害はまだ続いてるし、
マイナスエネルギーの原因も未だ不明だ。私たちの戦いは、まだまだこれからと言える』
『はい。師匠として、ゼロには俺も負けていられません』
『僕も頑張ります! ゼロが向こうの宇宙で頑張ってるように、この宇宙の平和をこの手で
守ってみせます!』
セブンの言葉に、レオとメビウスはそれぞれ気概を表明した。セブンはそれに固くうなずく。
『うむ! では私たちの力を必要としてるところへと向かおう! デュワッ!』
三人の戦士が衛星の大地を蹴って宇宙に飛び立ち、またはるかな戦いの旅路へと戻っていったのだった。
-
短いですが、ここまで。次からは来年です。
それではよいお年を。
-
乙です。アシュランって強豪のはずなのにザラブ星人が解説しているウルトラ怪獣大百科ではボロクソに言われてたのを覚えてます
では来年また、よいお年を
-
失礼します。
よろしければ21:00頃から、また続きを投下させてください。
-
ディーキンは怪訝そうにしながらも自分の要求を聞き届けてくれた老僕に礼を言うと、いよいよタバサと共に夫人の元へ向かうことにした。
トーマスもまた2人に同行を申し出たが、タバサは首を横に振る。
「あなたが会っても無駄。
今の母さまには、あなたのことはきっとわからない」
「……ですが!
そうだとしても、私にも奥様のために何か、少しでもできることがあれば……」
「駄目」
タバサは食い下がるトーマスに対してきっぱりと拒絶の意思を示すと、再び首を横に振った。
「あなたにまで、母さまのあんな姿は見せたくない。
母さまも、元に戻った時にあなたに見られていたとわかったら、きっと嫌だと思う」
それから、悲しそうに項垂れるトーマスの手をそっと取るとほんの僅かに、しかしはっきりと微笑んで見せた。
「ごめんなさい、でも、母さまが元に戻られたら、その時にこそ会ってあげてほしい。
ペルスランやあなたが今でも傍にいてくれていると知ったら、きっと喜ばれるはずだから……」
「お嬢様……」
トーマスは感極まったのか少し涙ぐむと、タバサの手を握り返して力強く頷いた。
「……わかりました。このトーマス、無力ではありますが、せめて始祖にご加護をお祈りしております」
それから、ディーキンの方にも向き直って深々と御辞儀をする。
「どうかお嬢様と奥様のことをよろしくお願いいたします、ディーキンさん」
ディーキンは2人のやり取りをじっと見て、嬉しそうに目を細めたり、さらさらとメモをとったり、していたが……。
トーマスに頭を下げられると、手を止めてしっかりと頷いた。
「もちろんなの。ディーキンは、いつだって全力を尽くすよ!」
ディーキンはタバサに先導されて、彼女の母が寝かされている部屋へと向かっていた。
人がいないのだから当たり前だが、どこもかしこもシーンと静まり返って薄暗い。
それでも、埃が積もったり蜘蛛の巣が張ったりしているような場所はなく、手入れが行き届いて綺麗なものだった。
この屋敷を管理する使用人が今はたった一人しかおらず、しかもそれが年老いた執事であるという点を考えれば、これは大したことだろう。
あのペルスランという老僕の誠実さと、この家系に対する忠義の高さとがうかがわれた。
やがて、タバサは屋敷の最奥にある部屋の扉の前で足を止めた。
一応コンコンと扉をノックしてみたが、返事はない。
いつものことだ。
-
タバサは構わずに、扉を開けて中に入った。
「……アー、勝手に開けちゃって、申し訳ないの。
ディーキンはちょっとだけ、奥さんのお部屋にお邪魔するね?」
少し首をかしげたディーキンは、そう言って頭を下げておいてから、タバサに続いて中に入った。
室内にいるという哀れな夫人をおびえさせないために、あらかじめ《変装帽子(ハット・オヴ・ディスガイズ)》を被り直しておく。
部屋は、広々として立派なつくりだった。
元々はおそらく、貴人の私室らしい豪奢な内装の部屋だったのであろう。
だが、今となっては煌びやかな調度品も、柔らかいカーペットも、美麗なタペストリもない。
古びて痛んだベッドと、椅子とテーブル以外には家具のひとつもなく、なまじ大きい分だけ余計に殺風景だった。
心を壊したこの部屋の主が暴れて痛めてしまうのを懸念して、殆ど物を置かないようにしてあるのだ。
季節は春とはいえ湖から吹く風は冷たいので、この部屋の主の体に障らぬようにとの配慮から窓も閉め切られ、カーテンが引かれている。
そのために室内は薄暗く、空気が重苦しく淀んでいるように感じられた。
この部屋の主であるタバサの母親、オルレアン公夫人は、ベッドの片隅にうずくまっていた。
壊された心を蝕む悪夢からくる心労のためなのか、あるいはそれと併せて病などにも侵されているのか、彼女はひどくやつれていた。
タバサと同じ鮮やかな青髪は、手入れもされずに痛んで伸び放題で、まるで幽鬼のようだ。
娘の年ごろから見ても実年齢はおそらく三十代の後半程度なのだろうが、たっぷり二十は老けて見える。
それでもなお、元はさぞや気品のある美しい女性だったのだろうという面影が、微かに見て取れた。
夫人はまるで乳飲み子のように、抱えた人形をぎゅっと抱きしめて、おびえた目で闖入者たちの方を見つめている。
彼女はやがて、わななく声で問いかけた。
「……だれ?」
タバサはすっと彼女に近づくと、深々と頭を下げる。
「ただいま帰りました、母さま」
しかし狂気に侵された夫人は、彼女のことを自分の娘だと認めることはなかった。
目を爛々と光らせて、刺々しく吐き捨てる。
「下がりなさい、この無礼者が!」
実の母からそのような言葉を浴びせられても、タバサは身じろぎもせずに、黙って頭を垂れ続けた。
内心でどれだけ傷ついていようと、それを顔に表すことはない。
「わかっているわ、王家の回し者でしょう。わたしから、シャルロットを奪おうというのね?
誰があなたがたに、可愛いシャルロットを渡すものですか!」
夫人はそう言って、抱きしめた人形にしきりに、愛おしげに頬擦りをした。
毒薬によって心を病んだ彼女は、その人形を自分の娘であるシャルロットだと思い込んでいるのだった。
元々は彼女自身が娘に買い与えたもので、幼い頃のシャルロットはそれにタバサという名前を付けて、妹のように可愛がっていたものだ。
その名前が、現在本物のシャルロットが名乗っている、タバサという偽名の由来なのである。
何度も何度もそのようにして頬を擦りつけられたのであろう人形の顔は今や摩耗して破れ、綿がはみ出ていた。
-
「………」
タバサはゆっくりと顔を上げると、悲しげな笑みを浮かべた。
それは、母の前でのみ見せる表情だった。
母が心を病んでから随分と長い間、それだけが彼女の唯一の表情だったのだ。
キュルケと友人になってからは多少なりとも感情を顔に表すこともあったが、それもごく稀な出来事でしかなかった。
しかし、ディーキンと知り合ってからは色々とあって、タバサも僅かながら表情を崩すことが多くなってきた。
そして今日は、もし予定通りに事が運んだならば、彼女にとって最高の日となるはずだった。
(きっと、うまくいく……)
そうなってくれれば、こんな表情を浮かべるのもきっと最後になることだろう。
そのことを思うと、タバサの胸を満たす悲しみは消え、代わりに期待と不安とが入り混じった感情が胸中に渦巻いた。
この人なら、きっと母さまを救ってくれる。
私の勇者に、なってくれる。
タバサは不安を打ち消すように自分にそう言い聞かせると、すっと後ろに下がって、ディーキンの傍らに並んだ。
それからもう一度、頭を深々と下げる。
「母さまを救ってくれる、勇者をお連れしました。もう、悪夢も終わります。
あなたの夫を殺し、あなたをこのようにした者どもの首も、いずれ私がここに並べてごらんにいれます――――」
タバサから紹介されたディーキンはしかし、その言葉を聞いてやや顔をしかめると、じっと夫人の方を見つめた。
今のは少々、不穏当な発言であるように思えたのだ。
ディーキンの懸念したとおり、夫人は実娘のその言葉を聞いても喜ぶどころか、一層敵意を強めたように見えた。
彼女は砕けた心の理解の及ぶ範囲で、今でも必死に、自分と娘に纏わり憑く実体のない悪夢と戦い続けているのだった。
「ああ、おそろしいことを……、この子がいずれ王位を狙うだろうなどと、誰がそのようなことを!?
あの呪われた舌の、薄汚い宮廷雀たちにはもううんざり! わたしたちはただ、静かに暮らしたいだけなのに……。
下がりなさい! 下がれ!!」
夫人は金切り声をあげると、実の娘にテーブルの上のグラスを掴んで投げつけた。
タバサはそれを、避けようともしなかった。
ただ黙って、自分のために心を壊した母からの暴行を受け入れようとする。
しかし、投げられたグラスがタバサの頭に当たる前に、ディーキンがぴょんと彼女の前に飛び出した。
彼はそれを器用に空中でキャッチすると、床に降り立つ。
「はい。いい道具を、どうもありがとう」
ディーキンはなおも怯えて喚き続ける夫人ににっこりと微笑みかけると、グラスを掲げてちょこんと頭を下げた。
それから、そのグラスを使って、即興の芸を披露し始める。
くるくると体の周りを回しながら、別の手持ちのグラスも一緒に取り出して、お手玉のようにして遊んでみせたり。
-
それらのグラスを楽器に仕立てて、簡単な音楽を演奏して見せたり。
さいころなどの小さな小物をどこからともなく取り出したり、そうかと思えばぱっと消してみせたり……。
トーマスなどと比べれば技術的には拙いが、ディーキン自身の話術や見せ方の上手さと相まって、余興として十分に楽しめるものだった。
しばらくそんな芸を見せた後、一区切りしたあたりでディーキンは御辞儀をすると、グラスをテーブルの上に返却した。
「どう? さっきはちょっと、こっちのお姉ちゃんが怖がらせてごめんなさいなの。
ディーキンたちはただちょっと、お姉さんと娘さんのために、いろいろな芸を見せに来たんだよ!」
(彼は、一体何を?)
タバサは、早速治療に取り掛かるのかと思いきや、唐突に芸などを始めたディーキンを、しばし戸惑ったように見つめていた。
だが、ふと自分の母親の方に注意を向けると、唖然とした。
これまで、人が現れればきまって怯え、人形をしっかりと抱き締めて、出ていけと叫ぶばかりだった母が。
誰であれ近づいたりすれば、金切り声をあげて暴れ始める母が……。
ぼうっとした様子ではあったが、途中からディーキンの芸を黙って、じっと見つめだしたのだ。
笑顔や拍手、賞賛の言葉こそなかったけれど、グラスを返すために彼がベッドの脇のテーブルに近寄ったときにも怯えることはなかった。
タバサのそんな驚きをよそに、ディーキンはテーブルの傍で、しげしげと夫人の顔を見つめていた。
「ンー……、お姉さんはきれいな人だね。
でも、ちょっと髪とかが傷んでるみたいだよ。この部屋って、鏡はないの?」
そんなことをいいながら、さっと手鏡を取り出して、夫人に自分の顔を見させてやる。
《内なる美(イナー・ビューティー)》の呪文焦点具に使用している高価な品で、高貴な身分の女性が使っても恥ずかしくない代物だ。
夫人は、鏡に映る自身のやつれた顔を、黙ってぼんやりと見つめた。
ディーキンはその様子をしげしげと観察してから、おもむろに声をかける。
「ねえお姉さん。ディーキンは芸人だから、お芝居の扮装に必要なお化粧とか髪の手入れにも詳しいんだよ。
よかったら、お姉さんの髪も手入れしてあげるの。きっと、すごくきれいになると思うな!」
無邪気そうにそう言ってから、ディーキンは夫人の様子をじっと観察して、怯えたり拒絶したりする気配がないのを確かめた。
それから、断りを入れた後にベッドの上にのぼり、彼女の手を引いてゆっくりとそこから降りさせて、椅子に座らせる。
「ウーン……。ねえタバサ、もっと大きな鏡はないかな?
ちっちゃな手鏡だと、お姉さんに自分のきれいな姿をちゃんと見てもらえないからね!
アア、それと、ディーキンが乗るための踏み台も、あると嬉しいんだけど……」
タバサは自分の母親と同じくらいぼうっとした様子でディーキンのすることを眺めていたが、そう声をかけられて、はっと我に返った。
夫人に頭を下げて一旦部屋から退出すると、すぐに手近の別室から、姿見と踏み台とを運んでくる。
タバサには、ディーキンがどうしてさっさと魔法を使って母の治療をせずに、こんなことをし始めたのかはよくわからない。
実の娘である自分を差し置いて、心を失った母に受け入れられているらしい様子にも、心中穏やかでない部分はある。
それでも、母の様子がこれまでになく穏やかなのは確かで、希望に胸が膨らむ思いがした。
(今は、あの人を信じよう)
質問などは、すべてが済んでからゆっくりとすればいいのだ。
-
タバサは、そう自分に言い聞かせた。
「ありがとうなの。じゃあ、今からディーキンは、お姉さんの美容師だからね!」
ディーキンはタバサが運んできてくれた踏み台に登ると、早速夫人の髪の手入れに取り掛かった。
迂闊に鋏などの刃物を見せては夫人が怯えて暴れるかもしれないので、とりあえず髪は切らずに櫛で梳っていく。
その際に細かい枝毛などは、密かに自前の鋭い爪の先で挟んで、ちょいちょいと切っておいた。
それから、ディーキン愛用のビターリーフ・オイルを香油として塗って、束ねて整える。
ディーキンの見立てでは、夫人の様子からしてなんとなくだが、彼女がその香油の匂いに若干心を動かされているように感じられた。
コボルドが身嗜みを整えるのに使うこのオイルの匂いは、はしばみ草というこちらの世界の食品に似ているのだが……。
そのあたりになにか、昔を思い起こさせるような部分でもあったのだろうか?
たとえば、彼女の好物だったとか。
(ンー……、まあ、今は関係ないかな?)
ディーキンはひとまず深く詮索するのは避けて、続けて彼女の顔に化粧を施してやることにした。
冒険者用の変装用具セットの中から化粧品類を取り出して、夫人の顔にあれこれと塗ったり、白粉をはたいたりしていく。
他人の、それも人間の女性の髪や顔の手入れなどをするのはさすがに初めてだったが、なかなか上手くやれていた。
《なんでも屋》としての器用さと、《即興曲(インプロヴィゼイション)》の呪文の恩恵。そしてディーキンの基本能力それ自体の高さ。
それらを組み合わせてやれば、このくらいは朝飯前なのである。
もちろん、呪文を使うところを見られれば、彼女に警戒されてしまう恐れがあった。
だが、ディーキンほどの術者ともなれば、そうそう気付かれずに呪文を発動する術くらいは心得ているものだ。
そうして一通り手入れをすませた頃には、夫人は見違えるほど美しくなっていた。
以前よりも髪が伸び、頬がこけ、皺も増えてはいるものの、かつてのオルレアン公夫人を思わせる姿であった。
その上にさらに《内なる美》の呪文を掛けることも考えたが、呪文の影響に晒された彼女を怯えさせる恐れがあるので、当面は差し控えた。
いくら呪文の発動自体は悟られずに行なえても、他者にかける呪文では抵抗されて気付かれる可能性があり、よりリスクが高まる。
「へっへっ。お姉さん、すごくきれいになったの。どう?」
ディーキンは大きな姿見を夫人の目の前まで動かして、自分の姿をしっかりと見させてやった。
夫人はしばらく、ぼうっと鏡に映った自分の姿に見入っていたが……。
やがて微かながら、確かに笑みを浮かべた。
「……! 母さま?」
それを見たタバサは、母が正気に戻ったのかと慌てて傍に駆け寄り、彼女に呼びかけてみる。
しかし、夫人は実の娘が近寄ってきたのに気が付くと、怯えたように身を竦ませてしまった。
それでも、いつものように、叫んだり暴れたりすることはなかったが……。
「ねえタバサ、申し訳ないとは思うけど、あんまり焦らないで。
それに、お姉さんを怖がらせちゃダメだよ?」
-
ディーキンはそういうと、怯えた夫人の肩を優しくたたいて大丈夫だと宥めながら、仕上げに爪の手入れをしてやった。
小さいとはいえ刃物を使って切るので、夫人の緊張を解いてからと思い、最後に回したのである。
短く切った後、仕上げに自分も爪の手入れに使っているやすりで軽く磨いて手入れを終えると、ディーキンは台から降りて御辞儀をした。
今切ったばかりの爪や枝毛などをしっかりと小袋に入れて保管し、退出する。
「それじゃ、ディーキンとタバサは一度失礼するね。
今度またお邪魔して別の芸をお見せするから待ってて、お姉さん」
「……ありがとう」
ひとまず休憩のために手近の空き部屋に入って椅子に腰を下ろすと、タバサはディーキンに深々と頭を下げてお礼を言った。
タバサの正面の席にちょこんと座ったディーキンは、きょとんとして首を傾げる。
「ン? ディーキンはまだ、お母さんの治療も何もしてないよ?」
「毒を飲んでから、母さまがあんなに穏やかだったことはない。
それに、母さまは綺麗になって、笑っていた……」
母が、満面の笑みではなくても、微かにでも笑顔を浮かべたことなど、心を失ってから一度でもあっただろうか。
少なくとも自分は見たことがない。
(そう言えば、自分もこの人と話すようになってから、少し笑えるようになった気がする)
彼の『主人』であるルイズも、最近は不機嫌そうな刺々しい態度を取ることが、めっきり減ったように思える。
きっと彼には、周りの者の気持ちを和ませ、心を開かせる力があるのだろう。
それが、心を失ったはずの母にさえ通じたということなのか。
これまでどんな魔法をもってしても元に戻せなかった母の心を、僅かにでも癒したとするなら。
それはある意味では、魔法よりも強い力だとさえいえるのかもしれない。
それにしても、まだよく分からない点も多い。
タバサはひとまず礼を言い終えると、今度は先程から疑問に思っていた事柄について質問してみた。
どうして、すぐに治療をせずに、手品師や美容師の真似事をしただけで部屋を出たのか。
どうして、自分でさえ受け入れてくれない母に、彼は受け入れられたのか。
どうして、……。
ディーキンは少し考えると、それらの疑問に対して順に答えていった。
「ええと、まず、タバサのお母さんに怖がられないようにお話した、っていうことについてだけど……。
ディーキンは普通に、相手を怖がらせないようにするにはどうしたらいいかなって考えて、反応とかをみながらやってただけだよ。
別に何も、特別なことはしてないの」
「でも……」
母さまは、私のことは怖がる。
-
実の娘である私を受け容れてくれないのに、どうして初対面であるあなたを。
タバサは胸の中にもやもやした激しい気持ちを抱えたまま、問い詰めるような、訴えかけるような目で、ディーキンを見つめた。
そのことを直接口に出せなかったのは、先日身勝手な嫉妬で彼を傷つけたことを恥じているからだ。
ディーキンはちょっと首を傾げてから、遠慮がちに口を開く。
「ウーン……、たぶん、タバサの場合はお母さんに話しかける、そのやり方があんまりよくなかったんじゃないかな?
ディーキンが見た感じではそう思った、っていうだけだけど……」
「……私のやり方が、よくない?」
「そうなの。ええと、たとえば……、お母さんは今、タバサが自分の子どもだってことが分からなくなってるんでしょ?
つまり、見ず知らずの人がいきなり部屋に入ってきたってことなの。
なのに、その知らない人からいきなり『母さま』なんて呼ばれたら、びっくりしちゃうんじゃないかな。
それに『あなたの前に首を並べにくる』とか、そんなことを言われたら誰だって怖いでしょ?」
「……」
「それから、お母さんは、ええと……。『宮廷雀にはうんざり』だとか、そんなふうなことを言ってたよね。
それはきっと、周りの人たちに裏切られて毒を飲まされたからそう思ってるんだと思うの。
だから、なんていうか“貴族やその取り巻きを思わせる”ような態度で話しかけたら、余計に警戒するんじゃないかな、って」
タバサやペルスランを受け容れないのも、きっと彼女らが夫人を高貴な身分の貴族として扱うせいだろう。
ディーキンはそう思ったから、夫人の前ではそういう堅苦しい礼儀作法とは程遠い、いつも通りの人懐っこい話し方をしていたのだ。
「あとは、きっと暴れるせいでちゃんとお世話ができなかったんだと思うけど、すごくぼろぼろの格好だったよね。
物を置いておいたら危ないからだとは思うけど、家具とかも全然なかったし、薄暗いし……。
そんな酷い恰好のままで、あの部屋にずっといさせられたから、余計に“自分は酷い扱いを受けてる”って思ったんじゃないかな?」
だから、ディーキンはまずは芸を見せて彼女の警戒を解き、姿見を部屋に運ばせて、髪などの手入れをしたのである。
グラスを正確に狙った場所へ投げられるくらいには自由に体も動くのに、ベッドに寝たきりにさせられている様子なのも気になった。
ゆえに手を引いてベッドから降りさせ、自分の脚で椅子まで歩いて座るように誘導した。
ただ独り善がりに自分の世話を押し付けるのではなく、夫人の反応を見て喜んでいるかどうかを確かめながら、色々と試行錯誤したのだ。
その結果、久し振りに人間らしい扱いを受けられたと感じた夫人は、気持ちを解して笑顔を見せてくれた。
少なくともディーキン自身が理解している限りでは、さっきやったのはただそれだけのことである。
「タバサは、優しい人だよ。さっきも、トーマスさんのことを思いやってるのがすごく伝わってきたの。
ペルスランさんも、こんな広いお屋敷に一人で頑張って、きっと真面目でいい人なんだと思う。
でも、2人とも昔のお母さんのことをよく知ってるから、逆に今のお母さんのことをちゃんと見れてないところもあるんじゃないかな?」
在りし日のオルレアン公夫人は、優しく美しく、聡明な人物であったという。
心を病んでやつれきった現在の姿からでも、その面影が窺えたくらいだ。
だからこそ、かつての彼女をよく知っている2人には、今の彼女の姿を認められないところがあるのだろう。
心のどこかで、おかしくなってしまった今の夫人には何もわからない、何をしても無駄だと思い込んでしまっているのだ。
それゆえ毒の影響を取り除くことだけが重要で唯一の解決策だと考え、今の彼女に快適に過ごしてもらおうという配慮に欠けている……。
彼女の身の安全には配慮しながらも、居心地の良さや精神的な健康は重視していないあの私室の様子を見て、ディーキンにはそう思えた。
対してディーキンは、かつての夫人の姿については何も知らない。
-
知っているのは、毒で判断力を失ったために周りのものすべてに怯えながらも、なおも娘のために懸命に敵の影と戦おうとする女性の姿。
哀れな中にも気高い強さを保っている、現在の彼女の姿だけだ。
夫人の思考力が完全に失われていないことも、ただ虚心に彼女の様子を観察すれば明らかだった。
判断力や認識力に欠陥こそあれど、ちゃんとした言葉を話しているし、誰かが部屋に入ったこともわかっていたのだから。
タバサやペルスランは今の夫人の状態を受け容れられないから、今でも彼女のことを母と呼び、公爵夫人として扱った。
現在の彼女の理解や気持ちを考えてそれに合わせようとはせず、ただ彼女の身の安全だけを第一に考えた。
一方ディーキンは、今の夫人の状態をそのまま受け容れた。
彼女に何がわかって何がわからないのか、どんな気持ちなのかを理解しようと努めた。
同じように心から夫人のことを思いやって行動した両者の間になにか違いがあるとしたなら、それは技術とかの問題ではなくその点だろう。
ディーキンはその事を、タバサになるべく詳しく、丁寧に説明してやった。
「……そう。そうなのかも、しれない……」
タバサはディーキンの説明を聞くと、しばらくじっと俯いて物思いに沈んだ後、ぽつりとそういった。
確かに、言われてみれば自分たちの母への対応には、いささか問題があったように思う。
今の母にはどうせ何もまともにはわからないのだと、高をくくっている部分もあったかもしれない。
指摘されてみれば単純なことだが、自分もペルスランもそんな世話には不慣れで、周りに助言をしてくれる人物も誰もいなかった。
そのために、長い間思い至らなかったのだ。
ただでさえ毒に苦しめられている母に、杜撰な扱いをしてなおさら辛い思いをさせていたのかと思うと、胸が締め付けられる。
もっと早く気づいていれば、自分にも母の苦しみを和らげてあげることができたかもしれないのに……。
ディーキンはタバサの沈み込んだ様子を見て少々居心地悪そうにした後、体を伸ばして慰めるようにポンポンと彼女の頭を撫でた。
「その、タバサもこれからお母さんのために、何かしてあげたらいいんじゃないかな。
お母さんを治すにはまだもう少し、時間がかかるからね」
「……? 時間が、かかる?」
タバサはそれを聞くと、顔を上げて不思議そうに目をしばたたかせた。
毒の治療は、あの奇妙な姿をした亜人だか天使だかを呼び出して、角で触れてもらうだけで終わりではないのか?
そういえば、それについての質問にはまだ答えてもらっていなかった……。
しかし、タバサがもう一度それについて質問する前に、ディーキンが彼女の疑問に対する説明を始めた。
「アア、いや。治療自体はきっと、すぐ終わると思うの。
だけど、お母さんを治す前に、治った後のための“身代わり”を用意しておかないとね。
それには少し、時間がかかるんだよ」
そう言いながら、ディーキンは机の上に、それに必要となるはずのいくつかの品物を並べ始めた。
それは、先程ペルスランに対して奇妙な要求をして譲り受けた、彼の爪や髪の毛が入った小袋。
今しがた夫人の世話を見たついでに手に入れた、彼女の爪や枝毛の入った小袋。
そして、インク瓶に似た形状をした、奇妙な小さいボトルであった……。
-
インプロヴィゼイション
Improvisation /即興曲
系統:変成術; 1レベル呪文
構成要素:音声、動作、物質(一対のさいころ)
距離:自身
持続時間:術者レベル毎に1ラウンド
術者は運命の流れを自分の方に引き寄せ、流動的な“幸運プール”を利用できるようになる。
ゲーム上ではこの“幸運プール”は様々な作業の成功率を上げるために、自由に使えるボーナス・ポイントの形をとる。
プールの総量は術者レベル毎に2ポイントであり、自身の攻撃ロール、技能判定、能力値判定の結果を向上させるために任意に使用できる。
ただし1つの判定に与えられる幸運ボーナスの上限は、術者レベルの半分までである。
使用したポイントはプールから消え、呪文の持続時間が過ぎた時点でまだポイントが残っているなら、残量はすべて失われる。
たとえば、20レベルバードがこの呪文を使用したとすると、最初の“幸運プール”は40ポイントである。
続く20ラウンドの間、このバードは各種の判定にポイントが許す限りの範囲で、最大で+10までの幸運ボーナスを得ることができる。
それは攻撃の命中判定でも、扉を打ち破るための【筋力】判定でも、あるいは<魔法装置使用>や<はったり>などの技能判定でも構わない。
この呪文はバード専用である。
---------------------------------------------------------------------
今回は以上になります。
またできるだけ早く続きを書いていきますので、次の機会にもどうぞよろしくお願いいたします。
それでは皆様、よいお年を……(御辞儀)
-
乙です
こういう機敏やら
ファイターやパラディン、ウィザード、クレリックとは違った活躍がバードにはありますね
-
おつです
前話が前々話から3週もかかってたので、今回がいつものペースで来るとは思ってなかった
-
皆さんこんばんわ、ウルトラ5番目の使い魔、35話。今年最後の投稿を始めます
-
第35話
死闘! 神よ、乙女たちのために泣け
海凄人 パラダイ星人
古代怪獣 キングザウルス三世 登場!
空中装甲騎士団と水妖精騎士団。互いのプライドを賭けた戦いが今、始まろうとしていた。
空中装甲騎士団は、百戦錬磨の重装騎士四一名。
対する水妖精騎士団は、エーコたち姉妹九人とこの街の貴族の少女たち十三人、それにティラとティアを足して二十四人のほとんどが素人集団。
普通に考えれば、どちらが勝つかなどは戦う前から子供でもわかる。だが、戦力の多寡だけで勝負が決まるなら誰も戦ったりはしない。
人間は勝敗以前に、戦わねばならないことがあるから戦う。男も女も関係なく、譲れない意地というものはある。
たとえ殺し屋が近くに潜んでいたとしても、そんなことは知らない。たとえ世界の危機だとしても、そんなことは関係ない。
宣戦の布告はとうに済んだ。
よろしい、ならば戦争だ!
「うおぉぉぉぉぉっ!」
「いやあぁぁぁぁーっ!」
獣の吼えるような声とともに、戦いの幕は切って落とされた。空中装甲騎士団は威勢をつけるために、水妖精騎士団は恐怖に打ち勝つように叫び、それぞれ得意とする魔法を放つ。
『ファイヤー・ボール!』
『エア・ハンマー』
『氷の矢!』
炎、風、氷が左右から乱れ飛んで相手を襲う。メイジとメイジの戦いは、一撃一撃が致命傷に繋がる威力を持つだけに、小細工よりも単純な力勝負に向いて派手だ。つまりは先手必勝、集団戦ではこれが特に顕著となる。
しかし、今回の互いの第一撃はどちらも有効打にはならなかった。
空中装甲騎士団は、自分たちに向けられた魔法をすべて立ったままで受け止めた。火も、風の刃も氷のつぶても鋼鉄の鎧にはじかれて空しく落ちていく。彼らは重い鎧をまとっているために素早くかわすといった芸当はできない代わりに、その鎧は魔法で強化された特別製であり、ドットクラスの魔法程度では打ち抜くことはできなかったのだ。
一方、水妖精騎士団に向けられた魔法は、彼女たちの前に張り出した風の壁によって方向を狂わされて、すべてあらぬ方向に飛び去るか外れて埃を舞い上げるかに終わった。
「さっすが姉さんたち!」
シーコが感激で歓声をあげた。今の風の壁はキュメイラとディアンナの仕業だ。この二人は攻撃に参加せずに、最初から防御に徹するつもりで待っていた。空中装甲騎士団が「女子供に本気を出せるか」と、まだ舐めていたのもあるが、ラインメイジ二人分で作られた風の防壁はそう簡単には突破されはしない。
互いの初太刀はそれぞれかわされ、相手にはいささかのダメージもない。
-
この状況に対して、空中装甲騎士団のとる手段は簡単だ。単に、キュメイラとディアンナの張る風の防壁を突破できるくらいに強力な魔法を打ち込めばそれでいい。それで、水妖精騎士団の隊列はズタズタになって勝負は早くも決まるであろう。
しかし、そうはさせじと猫のように飛び出した娘たちがいた。
「なにっ!?」
「ウェンディ・アイシクルは唱えさせないよ」
一瞬で距離を詰め、空中装甲騎士団の足元に現れたのはユウリとティーナだった。兜で視界が限られていて、特に足元が見えにくくなっていた空中装甲騎士団はふたりに反応するのが遅れ、その一瞬のうちにふたりの放った魔法が炸裂する。
『ライトニング!』
『エア・ハンマーだよ!』
至近距離からの電撃魔法と圧縮空気の弾丸の炸裂が男たちをしびれさせ、数人まとめてドミノ倒しに吹っ飛ばした。手が届くほどに近づけば魔法耐性の鎧だからとて受けきれず、鎧の隙間から見下ろす空中装甲騎士団員の目に、不敵に笑うユウリとティーナの顔が映った。
「この、餓鬼め!」
「トロいお前らが悪いんだろ、ウスノロ」
「ウィヒヒ、そうら、よそ見してていいのかな?」
空中装甲騎士団が激昂して、足元のふたりに気をとられたその隙に、次の攻撃は迫っていた。
下から来たなら次は上から、男たちが下に注意を向けた一瞬に、跳躍して頭上から襲い掛かるエメラルドの矢。
「「えいやーっ!」」
ティラとティア、ふたりのダブルキックが空中装甲騎士団員の顔面に直撃し、だるまのように周りの団員を巻き込みながら転がした。
そのままふたりは空中で一回転し、重さを持たない羽根のように地面に降り立つ。ふたりの緑碧玉のような髪が舞い、ふたりの身につけているグリーンのスリットスカートのドレスが優雅にたなびいた。
目を丸くする空中装甲騎士団。当然だ、完全武装のメイジの騎士に、素手で真っ向から挑んでくる人間など非常識にもほどがある。
それは水妖精騎士団の面々にしても同様で、エーコやシーコたちもティラとティアがまさかこんな無謀な行動に出るとは思っていなかったので、止めることもできずに飛び出していくのを見守っていたのだが、結果はこのとおりあっさりと騎士ひとりを昏倒させてしまった。
しかし、虚を突かれた空中装甲騎士団は、目の前で余裕げにたたずむふたりの少女をそのままにしてはおかなかった。相手が丸腰の少女であるにも関わらず、杖を向けて魔法を放とうとする。が、そのスペルを唱えきるよりも速く、ティラとティアは空中装甲騎士団の隊列に飛び込んでいった。
「な、速いっ!?」
ティラとティアの瞬発力は空中装甲騎士団や水妖精騎士団の想像をはるかに上回っていた。瞬く間に間合いがなくなり、ひとりの騎士に足払いをかけて転ばせる。さらに隣にいた騎士のマントを左右から掴むと、ふたり同時に思いっきり引っ張って引き倒してしまった。
-
「うわぁぁっ!?」
転倒させられた騎士は鎧の重さが仇になってすぐには起きられない。元々空中装甲騎士団の鎧はドラゴンに騎乗して戦うことを想定しており、地上で着て戦うようにはできていないのだ。
転ばされてもがく騎士の背中を踏みつけて、ティラとティアはにこりと友達にあいさつをするようににこりと笑う。
「「いらっしゃい?」」
「この、小娘たち!」
「よ、よせっ、味方に当たる!」
激昂して魔法を放とうとした騎士は、同士討ちを恐れた仲間に止められて慌てて呪文を止めた。だが、その隙をついてふたりは跳んでいた。
ティラとティア、ふたりは鏡合わせのように同時に跳ねて、ひとりの騎士の顔面にふたり同時に膝蹴りを食らわせた。鎧の隙間から鼻先を叩き潰され、鼻血を出しながらまたひとり騎士が倒れる。
さらに、ふたりは倒れ掛かった騎士を踏み台にして、断崖を駆け上がる鹿のように再度跳ねていた。騎士たちの頭上でティラとティアのグリーンの髪とドレスが舞い、まるで宙空で人魚が跳ねているかのような美しさに、騎士たちは一瞬それに見ほれてしまったほどだ。そして空を背にして一回転し、風にたなびいたスリットスカートからしなやかな脚が伸びて空を斬る。
「あ、白、し……」
その光景をラッキーにも正面から見れた騎士は、鼻血を出そうとしたところで強制的に意識をカットされた。落下しながら放たれたティラとティアの蹴りが彼の頭の左右から同時に炸裂し、脳に許容限界を超える衝撃が加えられてしまったのだ。もっとも、痛みをほとんど感じずに沈められたという点で彼は同僚たちより幸運ではあった。思い切り頭を叩かれたショックで、気を失う直前に見た光景を忘れてしまったことが少々不運ではあっただろうが。
「あいにくね」
「わたしたちは」
「「自分の安売りはしてないのよ」」
倒れた騎士を踏み台にして、騎士たちを見下ろしながらティラとティアは歌うように告げた。騎士たちは、丸腰であるにも関わらずあっというまに五人もの騎士を倒してしまったふたりの少女の気迫に圧倒されて手が出せない。
そして、誰より驚いていたのはエーコたちである。
「あ、あの子たちが、あんなに強かったなんて」
最初は、無茶なことはやめて逃げてと叫ぼうとしたが、ティラとティアの身のこなしはエーコたちの想像を軽く超えていた。あの俊敏さ、あの跳躍力は銃士隊の隊員たちのそれに匹敵するか、もしくは上回っているだろう。姉妹ゆえに完璧に息が合っていることも含めて、プロの戦闘集団であるはずの空中装甲騎士団が完全に手玉にとられている。
魔法の使えない平民だと思っていた。人懐っこいばかりの田舎者だと思っていた。学者の卵で、つかみどころがないけれど明るく元気なだけのただの娘だと思っていた。しかしそれは一面だけしか見ていなかった。ティラとティア、あのふたりは強い。格闘技の心得があるのかどうかはわからないが、あの身のこなしは常人のものではない。いや、人間離れしているとさえ言ってもいいと感じた。
-
「人間離れ……まさか」
ビーコはふと、自分たちにも覚えのある”あること”を思い出した。まさか、もしかしたら、そんな……
しかし、戦いは不安に浸る余裕さえも与えてはくれなかった。いくらティラとティアが活躍しても、空中装甲騎士団はまだ三十人以上もいる集団だ。これ以上、たかが平民に舐められては沽券に関わると、同士討ちの危険もかまわずに一斉にふたりに襲い掛かってきた。危ない! いくらふたりが俊敏でも、四方八方から魔法を撃たれたら逃げ場がない。
が、頭に血が上った彼らは自分たちの隊列に潜り込んでいるのがティラとティアだけではないことを忘れていた。
「バカにつける薬は」
「ないってね、ヒヒッ」
至近距離から放たれる魔法のつぶてと飛び交う悲鳴。ユウリとティーナの魔法攻撃が炸裂し、鎧で守りきれない箇所を切り裂き、叩き付けた。その隙に、ティラとティアは安全圏に跳んで逃れ、四人は視線を交し合った。
「ありがとうございます。さっすがお姉さま方!」
「ククッ、お前たちはなんとなくあたしたちと似た匂いを感じたんでね。なにかやらかしてくれると思ったけど、おもしろい、おもしろいじゃん!」
「いいねえ、楽しいのは大好きだよ。あんたたち気にいったよ、さあ、もっと遊ぼうよ!」
「もう、ティアに合わせるとすぐ荒事になるんだから。まあいいわ、エーコさまたちに仇なそうとする無頼者にはきついおしおきが必要ですものね」
おとなしそうに見えたティラもその気になればけっこう過激らしい。そういえばさっきもえげつない台詞をノリノリでしゃべっていたが、こういうタイプが実は一番怖いかもしれない。
四人の娘に隊列をめちゃくちゃにされて、空中装甲騎士団はすでに統率のとれた動きは不可能になっていた。しかもそこへ、ディアンナに指示された水妖精騎士団が魔法攻撃を撃ち込んで混乱を助長した。いくら堅固な鎧をまとっていたとて、受けるつもりでいるのといないのとでは耐えられる強さがまるで違う。またも数人が倒されて、ついに空中装甲騎士団の戦闘可能人数は水妖精騎士団よりも少し多い程度まで下がった。
だが、彼らもこのままおめおめと苦杯を飲むつもりはなかった。相手が少女たちだからと手加減していたのもここまでだと、指揮官らしき男が叫んだ。
「総員、隊列を解いて個々に戦え! 空中装甲騎士団前進、我らの敵に地を舐めさせよ!」
その命令で、混乱していた空中装甲騎士団に秩序が戻った。彼らはそれまでの、無理に隊列を維持しようしていたのをやめてバラバラになって攻め入ってきた。杖を構え、鎧を鳴らしながら水妖精騎士団へと迫ってくる。彼らの兜のすきまから覗く目の鋭さに、少女たちはついに空中装甲騎士団が本気を出してきたことを悟った。
-
「男たちの中にも少しはできるのがいたようね。水妖精騎士団前へ! 迎え撃つわよ」
「はいっ!」
少女たちもときの声をあげて前進する。ユウリやティラたちの活躍が、戦いにはまったくの素人の彼女たちにも勇気を与えていた。
しかし、水妖精騎士団がまがりなりにも有利に戦えたのもここまでだった。
互いに魔法を唱え合い、再び幾多の炎や水や風や土の弾丸が交差する。空中装甲騎士団はそれらをすべて鎧と魔法で受けきったが、水妖精騎士団のほうはそうはいかなかったのだ。
「きゃああっ!」
「う、あっっ、痛い、痛いよおっ」
「カレン、ユミナ! 大丈夫、しっかりして!」
数人が魔法を受けて倒されてしまった。最初に魔法攻撃を受けたときは空中装甲騎士団はきちんと陣形を組んで一斉攻撃をしてきたので、キュメイラとディアンナの魔法でそらすことができたが、今度は個々人がバラバラに魔法を撃って来た為にすべてを防ぎきることができずに取りこぼしが出てしまったのだ。
しかも、これが実戦を積んで鍛えた騎士であれば少しくらいの負傷には耐えて戦い続けられただろうが、完全な素人である彼女たちは傷の痛みに耐えられなかった。
すぐにキュメイラが駆け寄って水魔法で治療をする。だが少女たちは初めて味わう実戦の痛みに怯えて暴れ、言い聞かせてもなかなか治療が進まない。
そこへ、空中装甲騎士団の指揮官がすごみの利いた声で告げてきた。
「よくも調子に乗ってくれたな小娘たち。子供の遊びと手加減していたが、もう容赦はしないぞ。お前たちに、戦場の恐怖というものをたっぷり味わわせてくれる。覚悟するがいい!」
明白な宣戦布告であった。空中装甲騎士団はすべて、水妖精騎士団を打ちのめすつもりで杖を握り締めている。これがギーシュなどであれば、女性に手を上げるとは男の風上にもおけないなどとと言うだろうがそうではない。実戦において、女性の傭兵や騎士などが少数にせよ存在することは常識だ。それらと対峙したときに、いちいち手を抜いて戦っている余裕などはなく、もたもたしていたら自分が殺されてしまう戦場においては愚行というほかはない。
これが、本物の戦争を生き抜いてきた人間の空気。その威圧感に、新米の少女たちは怯えて、半べそになってすでに戦意を失ってしまっている。
エーコたちも、相手が本気を出していなかったからこそ戦えたことを思い知って冷や汗を流した。まずい、このまま真っ向から戦えば、勝機は万に一つもない。
ところが、このまま戦わずして水妖精騎士団が瓦解するかと思われたとき、悠然と声をあげた者がいた。
「だからどうしたの? 鎧ダルマさんたち」
「し、シーコ?」
突然、目を伏せて重々しくつぶやいたのはシーコだった。その挑発げな声色に、ビーコははっとしてシーコを見た。いけない、今この男たちを刺激しちゃ危険だわ、と。
-
しかしビーコの懸念は斜め上の方向で裏切られた。シーコは顔を上げて、まるで狂信者のように殺意をみなぎらせた目で叫んだのだ。
「我らはベアトリス姫殿下の代理人。我らの使命は、姫様に仇なす愚者を、その肉の最後の一片まで根絶やしにすること。有象無象の区別なく、わたしの杖は許しはしないわ!」
「あ、この子また何か変なのに影響されてるわ」
盛大にたんかを切ったシーコに、ビーコは「だめだこりゃ」とつぶやいた。シーコは姉妹の中で一番好奇心旺盛だけれども、なにかと流行とか本とかに影響されやすい。これはたぶん、さっき読んでいた召喚されし書物の影響だろう。その証拠に、ティラとティアが「よく言ってくれました!」とばかりに後ろで黄色い声をあげている。ついでにユウリとティーナも笑いながら手を上げている。あなたたちこの短期間で仲良くなりすぎでしょ! と、エーコやビーコは思うのであった。
空中装甲騎士団はシーコの啖呵を負け惜しみと思って高笑いしている。だが、シーコのこの無謀に思えた一言が姉妹の闘志に火をつけた。
「そうね、地獄を味わってきたのは軍人さんたちだけじゃないものね」
「一度は悪魔に魂を売った鬼子の手管、お行儀のいいつもりの兵隊さんたちにお見せしましょう」
イーリヤ、セトラもあらためて杖をとって身構える。復讐鬼として生きていたあの頃に比べたら、このぐらいのことなどピンチのうちにも入らない。
エーコとビーコも、まったく今日はついてないわねとぼやきつつも攻撃呪文のスペルを唱えだす。どのみち逃げるつもりも降参するつもりも最初からない、形成不利なんて考えるまでもなくわかっていたこと、困難を乗り越えていくことができなければ騎士団を名乗ることなど永遠に不可能だ。
道がないなら切り開く、戦意は完全に蘇った。
「あああああああーっ!」
少女とは思えない絶叫を放って、魔法がふたつの騎士団のあいだを交差する。
が、今回の激突は一方的な結果に終わった。
「ううっ、い、痛ぁっ」
「しっかりしなさい、ビーコ、シーコ!」
完全武装と無防備、その差はやはり大きかった。空中装甲騎士団は今回もほぼ無傷なのに対して、エーコたちはいずれも傷を負っている。
ビーコの額からつうと血が流れてえりを赤く染めた。エーコの左手が服ごと凍りつき、凍傷になる前に無理矢理引きちぎった。
セトラ、ディアンナたちもそれぞれ衣服や髪を傷つけている。さきほどまで元気だったユウリ、ティーナらやティラ、ティアも今度は全部は避けきれずに傷を負っている。
「ははっ、あーあ、この服はお給金を溜めてやっと買ったのに、ひどいなあ」
「今さら後悔しても遅いぞ。我々を愚弄した罪は、もはや万死に値する。子供の騎士ごっこが調子に乗ったむくいだ。もう謝っても許さんぞ!」
激昂して放たれた魔法弾がティーナを襲い、かばったユウリごと吹き飛ばす。ふたりは広場に積んであった資材に突っ込んで、崩れてきた材木などに全身を強打された。
-
「「このっ! おふたりをよくもっ!」」
ティアとティラが怒って飛び掛るも、今度はふたりの動きも相手に読まれていた。身軽さを活かして、相手の死角から攻撃をかけようとしたふたりの前へと魔法弾が打ち込まれ、避けようとしたところへさらに別の攻撃が加えられては避けようがない。
ティアは左手に火傷を負い、ティラは腹を空気の塊に強打されて胃液を吐いた。
「ふん、平民がでしゃばるからだ。いくら速かろうと、あれだけ見せられれば我らには充分だ。風と共に駆ける竜騎士の視力をあなどるではないわ」
ティラを助け起こしているティアを見下ろしながら、空中装甲騎士団員が冷徹に言い捨てた。
やはり、強い。さっきの攻撃でティアとティラの動きの癖は完全に読まれていた。これでは今後、いくら奇襲を仕掛けようとしても成功はしまい。
だが、空中装甲騎士団はこれでおさめるつもりなどはさらさらなく、さらに魔法をぶつけてきた。避ける以外にたいした防御手段のない姉妹とティア、ティラに次々魔法が当たり、たちまちのうちに彼女たちはボロボロにされていく。
セトラ、ディアンナ、キュメイラが血を流して荒い息をついている。ユウリとティーナはそれぞれ片腕が折れたらしく、だらりと片腕を垂らしながらもう一方の腕でかろうじて杖を持っていた。エーコ、ビーコ、シーコにしても大なり小なり傷を受けている。水魔法での治療も焼け石に水でしかない。
どころか、事態は悪化の一途を辿った。エーコたちのダメージは増える一方なのに対して、空中装甲騎士団の負傷者たちは水魔法で治療を受けて戦線に復帰して復讐戦を挑んできた。いつの間にか、空中装甲騎士団はほとんど開戦時の戦力を回復してしまっている。
勝負はほぼついたようなもの。空中装甲騎士団の指揮官は、ひざをついて倒れかけているエーコたちを見下ろしながら笑った。
「これまでだな、痛いか? 苦しいか? だがそれは罰だ、身の程を知るがいい。ふっはっははは!」
まるでなぶり殺しだった。空中装甲騎士団は、一時の小細工で倒されることはないというふうに高い地力を見せ付けて、大きな壁として水妖精騎士団の前に立ちふさがっている。
しかし、エーコたちの誰も倒れることはない。何度打ちのめされようとも、そのたびにひざを突きながらでも立ち上がってくる。
「つぅ……シーコ、大丈夫?」
「なんの、このくらいの痛み、あのときの痛みに比べたらなんてことないって」
シーコはそう言って、あのときのことを思い出すように、今ではもう影もなくなってはいる腹の傷跡に手を当てた。
戦いはまだこれから。しかし、勝機はこのままでは万に一つもない。それでも立ち上がろうとする彼女たちに、空中装甲騎士団はしだいにじれて、怒鳴りつけてきた。
「もういい加減にしろお前たち! 勝ち目などないのがわからんか。命まで奪うつもりはないが、これ以上長引くと取り返しがつかんことになるぞ、あきらめろ!」
もう勝敗は決まったも同然、なのになぜ立ち向かってくる。純粋な軍人である彼らには、彼女たちの折れなさの理由がわからなかった。
それに、エーコたちのやられ様を見続けていた水妖精騎士団の少女たちも、ついに耐え切れずに叫んだ。
「も、もうやめてください先輩方、それ以上戦ったら死んじゃいます! もういいじゃないですか。降参しましょう。謝ったら許してくれるって言ってるじゃないですか」
-
「そうです! しょせんわたしたちなんかに騎士団なんて無理だったんです。男の人に勝つなんて無理です。せめて逃げましょう!」
少女たちは戦いの恐怖に怯えきっていた。無理もない、経験のない人間が血しぶきの飛び散る様を見れば誰でも足がすくむ。
だが、エーコたちはフッと笑うと楽しげに言った。
「勝ち目がない? あきらめる?」
「降参? 謝る?」
「無理? 逃げるですって? 冗談じゃないわね」
三人ともすでにズタボロだ。しかし三人の目はまったく死んでいない。
「勝ち目がないからって何だっていうの? 一生、勝ち目のある戦いだけしていけると思うの?」
「あきらめてどうなるっていうの? 価値のない明日につないでなんになるっていうの?」
「無理っていうのはね、わたしたちがあきらめるということを言うのよ。それにね、わたしたち……ふふふ、ふっふふふ……」
低い笑い声が漏れた。そして。
「楽しいのよ、こんなときなのにわたしたちとっても楽しい!」
「ええ、わたしたちは戦ってる。姫様のために、自分たちのために、みんなでいっしょに!」
「これが楽しくなくてなんだっていうの? あっはっははは!」
高笑いが響き、少女たちは唖然とし、空中装甲騎士団はあっけにとられた。
狂したのか? いや、エーコたちは正気だ。正気で、弱いほうが強いほうを笑い、道理に強理を持って貫こうとしている。
さらに、エーコは千切れたツインテールを揺らしながら少女たちに告げた。
「あなたたちはどうするの? ここで頭を下げて一生負け犬の屈辱を背負って生きるか、それともわたしたちに続いて下品な男たちを泣かすか、好きなほうを選びなさい」
それだけ告げると、エーコたちは答えを待たずに杖を握り締めて前へ出た。
ユウリにセトラ、姉妹たちも皆それに続く。そして、その光景を見て、ティアとティラはうれしそうに笑うのだった。
-
「かっこいいなあ、やっぱ人間ってすごいよ、すげえよ、素晴らしいよ」
「やはり、あの方々についてきたのは間違いではなかったわね。さあ行きましょう、わたしたちが受けた恩を返すのはこれからです」
薄汚れた緑色の髪をかきあげてティアとティラも構えをとる。
戦いはこれからだ。
杖を握り締めているだけがやっとのありさまでありながらも、なおも向かってこようとする少女たちの姿は、歴戦の空中装甲騎士団の背中にも冷たい汗を流させる。彼らはエーコたちが辿ってきた道のけわしさと、そこで得てきたものの重さを知らない。
たった十人足らずの少女たちが、プロの軍人を気圧している。その光景に、水妖精騎士団の少女たちは、うまく言葉に表すことはできないものの、なぜか胸がぐっと締め付けられるものを感じ始めていた。
「わたしたちは、水妖精騎士団……」
遊びでつけられたはずだった名前が、汚してはならない軍旗のように思えてくる。
戦いは野蛮なもの……だけど、戦わないと守れないものもある。
だが、エーコたちがどんなに気力をふりしぼっても、空中装甲騎士団の鎧には彼女たちの牙は通らず、彼らが手を緩めることはない。
このまま戦いが長引けば、なにか悪いことが起こる。空中装甲騎士団は長年の勘からそう感じ出した。
「部隊長、これ以上長引いて騒ぎが衆目につくようなことになれば……」
「やむを得ぬな、我らの名に傷が付くことだけは避けねばならぬ。かくなるうえは手足をへし折ってやってもかまわん。身動きをとれないようにして病院に叩き込んで終わりだ!」
「はっ! そして、みじめな様になった小娘たちを目の当たりにすれば姫殿下もご自分の甘さに気づかれることでしょう。彼女たちには可哀想ですが、生贄になってもらいますか」
じれた狼が我慢の限界を超えて、ついによだれを垂らして牙をむき出した。
加減を抜いた凶悪な魔法のスペルが流れ、家一軒を吹き飛ばせるほどの魔力が溜まっていく。
それでも、エーコたちには引く道はない。避ける力も防御するだけの力も残っていない彼女たちは、残った力のすべてを攻撃に向けようと呪文を唱える。たとえそれが、相手の攻撃の前に吹き飛ばされてしまうそよ風の吐息だったとしても。
だがまさにこのとき、彼女たちのいる広場に向かって、一対の足音が近づきつつあったのだ。
「ハァ、ハァ、ま、間に合って、間に合ってっ!」
息を切らしながら、ベアトリスはフラつく足を叱咤して走っていた。
ホテルを飛び出してからここまで、途中で何度か魔法で飛んでショートカットしてきたがもう限界だ。しかし間に合わねばという一心で、とにかくここまで急いできたのだ。
-
支援ってこっちでもいるんだっけ?
-
空中装甲騎士団とやり合ってはエーコたちのお遊びなどひとたまりもない。なんとしてでも止めなくてはという思いで、必死にここまで走ってきて、ようやく騒動の音とともに件の広場が見えてきた。
けれども、ベアトリスの眼に飛び込んできたのは、今まさに魔法を放とうとしている空中装甲騎士団とエーコたちの姿だった。
いけない! ドットメイジのベアトリスにも、あんな魔法を受けたらエーコたちが無事ではすまないのはわかる。止めなくては! だが、どんなに走っても広場に駆け込むにはあと十数秒はかかる。大声を出して止めようにも、全力で走ってきたせいで喉が涸れて声が出ない。
「だめ、間に合わないっ」
絶望がベアトリスの胸を包んだ。あとまばたきを数回もすれば、エーコたちは恐ろしい魔法によってズタズタにされてしまうだろう。
わたしのせいだ、全部わたしの。エーコたちの危険な遊びを、怒鳴りつけてでもやめさせていればこんなことには。
だが、ベアトリスの目に惨劇は映らず、耳にエーコたちの悲鳴が聞こえることはなかった。
強力な空気の弾丸が飛び込んできて炸裂し、猛烈な風圧でもって空中装甲騎士団を十数人まとめてふっ飛ばしたのである。
「見てられませんわ見てられませんわ見てられませんわ」
轟音と、空中装甲騎士団の悲鳴が響く中で、広場につぶやくような少女の声が流れた。
その場にいた全員の視線が声のした方向に注がれる。そして、資材の山の上から羽根が舞い降りるようにふわりと一人の少女が広場に降り立った。
”誰だ?”
全員の思考がそこで固定された。少女の顔に見覚えがある者は一人もおらず、しかし少女は白いフリルのついた黒のドレスを優雅にひらめかせ、鋭い碧眼で場を見渡している。
敵か、味方か? だが今の魔法は間違いなく空中装甲騎士団を狙ったものだ。ならばと、空中装甲騎士団のひとりが声を荒げた。
「貴様、何者だ? なぜ我々の邪魔をするか」
「別に。わたくしはただの通りすがりの者ですわ。ちょっと退屈しのぎに散歩してたんですけど、おもしろそうな香りがしたので見物してましたの。いいですわね、わたくしとしたことが久しぶりに胸を熱くしてしまいました。あなたたち、いいものを見せてくれてありがとうね」
少女はそう言うと、エーコたちに向かって笑いかけた。エーコたちは唖然としながら、「あ、どうも」と言い返すことしかできない。
-
が、それで空中装甲騎士団がおさまるわけはない。
「貴様、杖を持っているなら貴族であろうが、遊びで戦争にしゃしゃり出て、ただですむと思うなよ」
「あら、わたしは貴族ではありませんわ。まあ、どちらでも同じことですが、心配はご無用、これでも些少は腕に覚えがありますの。さて、楽しませてくれた礼といってはなんですけど、少女騎士隊の皆さん、助太刀させていただきますわ」
「えっ、ええええぇっ!?」
エーコたちだけでなく、ティラやティアや少女たちも仰天した。
「いっ、いやそんな。どこの誰とも知れない、無関係な人を巻き込むわけには!」
「心配は無用と言いましたわよ。それに、関係ないというなら、同じ女として下品な殿方が高笑いして幕が下りるのは不快ですもの。観客としては少々強引にでも脚本の変更を願いますわ。むしろ感謝してほしいくらいです、わたしがタダで杖を振るうなんて、めったにないことですのよ」
少女はにやりと笑い、エーコたちの下へ歩み寄ると杖を振って治癒の呪文を唱えた。すると、傷だらけだったエーコたちの体がみるみるうちに元通りになっていく。
「す、すごい。すごい強さの治癒魔法だわ! あ、あなた何者? 貴族でないってことは傭兵? いや、でも」
「ふふっ、そんなこと今はどうでもいいじゃないの。そんなことより、これであなたたちも戦えるでしょう? あなたたち、腕はまあまあだけど戦い方は素人ね。特別サービスで教えてあげるわ、勝ったもの勝ちの戦場の戦い方というものをね」
少女はそう言うと、杖を真っ直ぐに空中装甲騎士団に向けた。それは宣戦布告の証、お前を倒すという意思表示だ。
ここまで来たらもはや空中装甲騎士団も見逃しはしない。シーコは、不敵な笑みを崩さない少女に向かって確認するように問いかけた。
「あ、あなた、わたしたちの味方でいいのね」
「ええ、そう思ってくださいな。でも、あの数を片付けるのはちょっと面倒ね。お兄様はどっかに行っちゃったし、あなたたちも働いてもらうわよ」
「あ、当たり前よ! これは元々わたしたちの戦いだもの。あなたは、え、ええっと……」
「ジャネット、そう呼んでちょうだい。じゃあ、勝ちにいきましょうか!」
ジャネットが杖を振り上げると、エーコたちも身構える。空中装甲騎士団も、ジャネットがただ者ではないことを見抜いて体制を立て直した。
空中装甲騎士団vs水妖精騎士団。ジャネットという予想外の乱入者を加えて、戦いは最終局面を迎えようとしていた。
-
その光景を、ベアトリスは呆然として見守っている。
「なに、なにがどうなっちゃってるの? これからどうなるのよ!」
訳がわからない。しかし、この戦いを決して見逃してはならない、ベアトリスの中の何かが強くそう訴えかけていた。
人の運命の糸は互いに絡み合い、人生と歴史という布を織り上げていく。その模様は複雑怪奇で、時にいびつで時に美しく、そして常に変化を続けて同じ形をとどめない。
止まることなく運命の糸をつむぎ続ける時の女神の機織り機。この機織り機は、動き続けながら運命の糸を無限に取り込んで色彩を深めていく。
そして、織り込まれる糸は時として、出来上がる布の柄を一気に変えてしまうこともある。その特別な糸は、すでに機織り機に取り込まれ、生地の裏側にまで編みこまれていた。
それは、ロマリアから遠く離れたトリステインで、今を去ること二ヶ月ほど前に遡る。
ハルケギニアの列強の中で、もっとも小さな”小国”トリステイン。だが ハルケギニアには、まだまだ未開の土地が数多くあり、トリステインもこの例外ではない。
地球でいえばヨーロッパ地方と似た土地に、ガリア、ロマリア、ゲルマニア、トリステインの四国がひしめき、これに浮遊大陸であるアルビオンが存在して、およそ六千年の間この状態を堅持してきた。
しかし、六千年という時間を持ってしても、人間はハルケギニアのすべてを知り尽くしているというわけではなかった。
ブリミル暦六二四三年の今もってなお、ハルケギニアには人間を寄せ付けない山岳、密林地帯が残り、地図に空白を生んでいる。
だがなぜ誰も未開の土地を切り開かないか? 探検しようとしないのか? それらの原因の多くは、人間が敵わない強さの亜人や幻獣の巣になっているというもので占められる。オーク、トロル、ドラゴン、ないし未知の食肉植物や毒虫などなど。それらに阻まれて、勇敢な冒険家や探検家が次々に未帰還になるうちに、ハルケギニアのあちこちには人間が足を踏み入れてはいけない暗黒地帯が残されたのだ。
ただそれらの中にひとつ、凶暴な亜人も有毒な生物も棲んでいないのに、暗黒地帯として人が近寄らない地方がある。
それはトリステイン北西部の小さな山間部。一見、これといった危険もないように見える岩山がつらなるこの地方には、奇妙な伝説があった。
『その山に決して近寄ることなかれ。もし足を踏み入れたら、山の悪魔に取り付かれる。山が見えるところに住んでもいけない。悪魔は夜な夜なやってきて生気を吸っていき、最後には全身の力が奪い取られたあげくに血を吐いて死に至ることだろう』
これだけならば、よくある田舎の迷信と笑い飛ばすこともできよう。しかし、この山の伝承を笑った者で無事で済んだものはいなかった。
-
タブーを笑い、山の近くに家や村を作って移り住もうとした者は、いずれもしばらくして原因不明の病魔に犯された。症状は、全身がだるくなり、やがて体の毛が抜け落ちたり皮膚の色が変わったりしながら衰弱していき、そのまま死に至るというもので、まさに悪魔に生気を吸われたとでもしなければ説明できない恐ろしいものであった。
今ではこの山は『悪魔の住む山』として、近づこうとする者は誰もいない。
だがもしも地球の医者や科学者がこの話を聞けば、その山にはなにがあって、なにが原因で病が引き起こされたのか気づいたに違いない。山にあるものは悪魔などではなく、ある希少な鉱物であることに。
それは使い方を誤れば世界を滅ぼす武器にもなる。しかし正しく使えば人間を星の海にも導くことの出来る素晴らしいエネルギーにもなり、科学特捜隊が宇宙ビートルに使用したハイドロジェネレート・サブロケットエンジンにも応用されている。
ただ、まだ使用方法を知らないハルケギニアの人々にとっては悪魔と変わりなく、未来のために眠らせておくべき大切な資源であるべきだった。
しかし、そっとしておけば何事も起こさないはずだった『悪魔の住む山』を、突如として激変が襲ったことによって、ハルケギニアの運命に少なからぬ影響がおよぼされることになる。
ある日、『悪魔の住む山』を含む一帯を巨大な地震が襲った。
マグニチュードは九を軽く超えて測定不能。岩山からは何十トンもあろうかという巨岩が軽石のように転がり落ちる激震に、周辺の森の木々は倒れ、動物たちは逃げ惑った。
が、地震はこの激変のほんの前兆に過ぎなかったのだ。激震の中で、標高五百メイルの山が地面に沈み込むようにして低くなっていく。そして、猛烈な土煙が舞い上がって晴れた後には、山々が連なっていた景色は消えてなくなり、山は地底に大きく沈み込んだ盆地と化してしまっていたのだ。
これはいかなる天変地異の仕業か? いや、これは人災である。この時期、まだ記憶に新しい火竜山脈の大陥没を覚えていることだろう。シャプレー星人の操るギラドラスによって、ハルケギニア全土の地下に埋蔵されている風石が奪い去られたために、支えを失った地殻が山岳部などの重いところから崩壊を始めた、この『悪魔の住む山』もその影響を受けたひとつだったのだ。
『悪魔の住む山』は完全に崩落して、もはや跡形もない。しかし、地の底に沈んだ盆地となり、どんな生物も生き残ってはいないだろうと思われたその岩海がうごめきだし、信じられない事態が起こった。無数の岩石を弾き飛ばしながら、地中から二本の長い角を頭に生やした巨大な四足歩行の恐竜が姿を現したのである。そいつは鈴の音に似た甲高い鳴き声を放ちながら、太くたくましい足で大地を踏みつけて地上に全貌を現した。青い体の背中には一列のヒレが生え、長い首と長い尻尾を生やした胴体を合わせた全長はなんと百五メートルにも及ぶ。
この怪獣の名はキングザウルス三世。かつてはウルトラマンジャックと戦い、一度はジャックを完敗に追い込んだ強力な大怪獣だ。
だがなぜこの山にキングザウルス三世がいたのか? それがこれから始まる事件の原因にもつながっていく。
地上に現れたキングザウルス三世は、ゆっくりと辺りをなにかを探るかのように見渡すと、やがてひとつの方向を定めて向きを変えた。そして強靭な首と足を使って地面を掘り返すと、あっというまにまた地底へと潜っていってしまったのである。
その光景を見ていた者は誰もおらず、このことは人間たちにとっては忌まわしい魔の山が消えたという朗報だけに終わった。真相を知るのは、神のみである。
そして、時間はその時計の針を現代に戻して、場所を次の物語の舞台へと移す。
続く
-
おつです
-
こんばんわ、なんとか今年中に投稿しようと思ってたらほんとうにギリギリになってしまいました。
>>789さん、こちらでは支援はいらないようですがお気遣い感謝します。
ともあれ、2015年も応援ありがとうございました。2016年もまたよろしくお願いします。
果たして来年中に完結できるかなあ。いや、新刊も2月に出ますしファイトですね。
今度の怪獣はかなり人気あるほうだと思うので、頑張って書きます。といっしょにパラダイ星人のふたりもよろしく!
では皆さん、よいお年を!
-
乙
いろいろとダメな姉妹ベネ!
そしてあけましておめでとう
-
あけましておめでとうございます、焼き鮭です。新年一発目の投下を致します。
開始は23:07から。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第七十九話「少年シュヴァリエ」
甲冑星人ボーグ星人 登場
トリステイン王国の飛行船用の港町、ラ・ロシェールの桟橋に今、ロサイスから飛んできた
軍船が接舷した。タラップが下ろされると、パーカーを着て剣を背負った一人の少年が一番に降りてくる。
「んー! 久々のトリステインだ! 色々危ない目を見たけど、無事に帰ってこれたんだなぁ」
背筋を伸ばしながら感慨深く発した少年は、誰であろう平賀才人。その後にはグレンが続く。
「いやぁ、ほんと無事でよかったぜ。見つかるまでめっちゃ心配したけど、これでひと安心ってもんだ。
なぁ焼き鳥」
『私の名前はジャンボットだ!』
グレンに続いたのはシエスタ。その腕輪からジャンボットがいつもの抗議の声を上げた。
「サイトさん、わたしたちようやく、みんなそろって学院に帰れるんですね!」
シエスタの嬉しそうなひと言にうなずいた才人は、最後に降りてきたルイズに呼びかける。
「ルイズ、またお前の使い魔としてよろしくな」
「……」
だが、ルイズはつんと不機嫌そうに澄ましたままだった。才人は呆れたように頭をかく。
「お前なぁ、まだ機嫌損ねてるのかよ。テファとは何もなかったって言ってるだろ? ほんとだって」
ティファニアの名前を出すと、ルイズは口を開いて苛立ちの声を出した。
「どうかしら!? 実際何もなかったとしても、あの“胸っぽいなにか”に触りたいとか
ずっと思ってたんじゃないの? あんたってああいうの好きそうだものね!」
「胸っぽいなにかって……」
未だにコンプレックスを爆発させているルイズに、才人たちはほとほと参った。
才人と再会した時のルイズは、筆舌に尽くしがたいほどに喜び感涙まで流したものだが、
世話になっていたティファニアを紹介すると態度が一変。彼女のあまりにも大きな胸に
過去最大のショックを受け、何故かティファニアに逆ギレし、更には彼女の胸に才人が
どぎまぎしていることに目敏く気づいて八つ当たりをしでかすなどと大暴れだった。
お陰で一瞬でも生じていた才人との甘い空気は完全に霧散してしまったのだった。
ルイズにとっては、ティファニアがハーフエルフでしかも自分と同じ“虚無”の
担い手だということよりもそっちが重要なようであった。
そんなこんなでへそを曲げっぱなしのルイズであったが、残っている理性で才人らに呼びかける。
「それに、学院に戻るにはまだ早いわよ。先に姫さまの御許まで行かないと。姫さまも、
そのために迎えのフネを寄越して下さったんだから」
「ああ、そうだったな。姫さま、俺に用件って何だろうな」
才人たちは話しながら、彼らを待っている送迎用の竜籠の元へと向かっていった。
冷凍怪獣軍団とバルキー星人の襲撃を退けた才人は、ルイズと再会。そして再び彼女と
契約を交わし、“虚無の使い魔”に立ち返った。その際、ルーンが以前と同じ左手に現れたことに
デルフリンガーが異様に安堵していたが……。
激戦があったこともあってしばらくウェストウッド村で休息を取るはずだったが、グレンが
アンリエッタに才人の生存を伝えると、彼女から才人に話したいことがあるという連絡が来たのだ。
それで才人たちは、アンリエッタの回した送迎船に乗ってアルビオンをあとにした。
この際、『外の世界を見たい』と言っていたティファニアを才人が誘ったのだが、彼女は
ウェストウッド村の身寄りのない子供たちの世話をしなくてはならないと、その話を断った。
いつかは、ティファニアも自由に外の世界を見て回れる日が来るのだろうか……。
-
ともかく、こうして才人、ルイズ、グレン、シエスタの四人はトリステインに帰国したのであった。
四人を乗せた竜籠がトリスタニアに到着し、一行が王宮入りすると、出迎えたのはアニエスだった。
「よく来てくれた、ミス・ヴァリエール、グレン。そしてよく生きていたな、ミス・ヴァリエールの使い魔」
「アニエスさん! お久しぶりです」
サウスゴータ以来のアニエスと顔を合わせ、才人は頭を下げて挨拶した。その顔を見た
アニエスは、ほぅ、と息を漏らす。
「少し見ない内に、随分とたくましくなったようだな」
「え? そうでしょうか」
「それくらい、見ればわかる。すっかり戦士の顔つきになったな」
「だろぉ〜? この俺がつきっきりで指導したんだからな! そりゃ当然ってもんよ!」
ピッと自分を指差して、胸を張って自慢するグレン。それにアニエスは苦笑を浮かべる。
「どうやら苦労したみたいだな。さぁ、陛下は執務室でお待ちだ。案内しよう」
アニエスのあとに続いて、一行は執務室へと向かう。アニエスが扉をくぐると、アンリエッタへと
深く一礼する。
「陛下、ミス・ヴァリエールの使い魔の少年をお連れしました」
そのあとに執務室へと入ると、すぐにそこが王宮に相応しくないほどに寂しい光景であることに
気がついた。家具はほとんど何もなく、執務用の机は古ぼけたライカ欅のもの。他には書架が一個、
隅にぽつんとあるのみと、王冠を被ったアンリエッタがいなければ、誰もここが女王の執務室とは
思わないであろう。
ルイズが不安そうに辺りを見回すと、アンリエッタが説明する。
「ああ、家具はすべて売り払ってしまったの。びっくりした?」
「ざ、財産だけでなく、ですか……?」
「しかたがないの。あの戦争で、国庫はからっぽになってしまったから……」
アンリエッタは、ルイズの手をとった。
「ルイズ、元気になってよかった。わたくしはあなたに、使い魔を奪いかねなかったこと、
いえそれ以上にあなたを死地に追い込んだことを改めてお詫びせねばなりませんね」
「そんな……あんなことになったのは姫さまのせいではないではないですか」
ルイズが慰めるが、アンリエッタは首を振る。
「いえ……、わたくしの責任です。わたくしは、戦争というものを……侵略者と戦うということを
甘く考えていたのです。本当に、あなたたちが生きていてよかった。ごめんなさいルイズ。なんと言って
お詫びすればよいのか……」
「姫さま、どうぞお気になさらないでください。このルイズ・フランソワーズ、陛下に一身を
捧げております。己の死もそこには含まれています。ですから……」
抱きしめあっておいおいと泣くルイズとアンリエッタ。才人は、俺の死もそこに入ってるのかよと
心の中で突っ込んだ。
ひとしきり泣くと、ルイズが伝える。
「姫さま……、恐ろしい事実をお耳に入れねばなりません」
「まあ! 恐ろしいですって! どうしましょう! いいえ、聞かねばなりませんわね。
わたくしはすべてを耳に入れねばなりません。恐ろしいことも、心をつぶしてしまうような
悲しい出来事も……、さあ、話してくださいまし」
ルイズはもう一人の虚無の担い手、ティファニアに出会ったことを語った。
「あなたの他にも、虚無の使い手がいるのですか? なんということ。そのものを早く保護しなければ」
ルイズは首を振った。
「彼女はひっそりと暮らすことを望んでおります。その呪文は身を守るのに適しているし……、
できうることなら、かの地でそっとしておいてあげたいと思います」
「そうね……、この地が安全とは限りませんわね……。わかってルイズ。己のものにしたい
わけではないの。ただ、わたくしは“虚無”を誰の手も触れぬようにしておきたいだけなのです。
自分の目的に利することはもう望んでおりません」
アンリエッタは、ルイズの“虚無”の存在が、自分に少なからずアルビオン侵攻を決意させた
ことを知っていた。
-
「わかっていてなお、力を持つということは、分を超えた野望を抱きやすいものです。わたくしは
そのようなことが二度と起こらぬよう、注意するつもりです。また、他人にそれをさせるつもりも
ありません。ああ、触らぬに越したことはないわね。その方がそう臨むのであれば、そっとしておいて
さしあげましょう。ほんとうに。ええ……」
ルイズは続けて告げる。
「虚無の担い手ですが……、察するに王家の秘宝の数だけ……、つまり四人いると思いますわ」
「なんということでしょう! 始祖の力を担うものが四人とは!」
「その中に、虚無を悪しき目的で用いようと考えるものがいないとは限りません。仮にまだ
姿の見えない虚無の担い手が、侵略者の残党と手を結んだりなどすれば、脅威の度合いが一挙に
はねあがるものかと思われます」
アンリエッタはルイズをじっと見つめた。
「安心して、ルイズ。最早これ以上、外敵の好きにはさせません。……で、あるならば、
なおさら必要がありそうですわね」
「必要?」
アンリエッタはルイズから離れると、今度は才人を見つめた。
「使い魔さん。わたくしはもう存じています。あなたが、わたくしたちの救い主、ウルトラマンゼロなのですね」
「え!? ど、どうしてそのことを……」
「状況から推察いたしましたわ」
見るからに動揺する才人に苦笑したアンリエッタは、一つ頼む。
「すみませんが、ウルトラマンゼロのお声を聞かせてはいただけないでしょうか」
才人は困ったようにウルティメイトブレスレットに視線を落としたが、それがチカチカと
瞬いたので、ゆっくりと持ち上げた。
『アンリエッタ姫さん、こうして言葉を交わすのは初めてだな。その通り、才人はこの俺、
ウルトラマンゼロと一体なんだ』
ゼロが言葉を発すると、アンリエッタは王冠をかぶった頭を何度も下げ始めた。
「ありがとうございます。何度お礼を言っても足りません。本当にありがとうございます。
あなた方は英雄です」
「そ、そんな……、ゼロはともかく、俺は英雄なんて呼ばれるようなことはしてないですよ」
「いいえ……、あの地獄絵図の最中に、飛行機械で敵に立ち向かうあなたの勇姿があったからこそ、
皆が勇気づけられたのです。あなたの活躍がなければ、最悪わたくしたちは皆殺しにされ、世界は
終わっていたかもしれません」
そんな風にアンリエッタに頭を下げられ、才人は恐縮した。同時に、今まで感じたことのない
喜びを感じた。女王さまに認められる、なんて、日本にいたら考えられないことである。
ここでグレンがニッと笑って発言した。
「これでアンリエッタ姫さんも、正真正銘、秘密を共有する仲間ってわけだな!」
「こんなわたくしがウルティメイトフォースゼロの仲間などと、身に余る光栄です」
グレンに笑いかけられたアンリエッタはほんのり頬を赤らめた。
「んじゃ、ここで改めて俺たちの自己紹介をしようか」
と言うグレン。そのために、シエスタも連れてきたのだ。
彼女の腕輪のランプを通してミラーも呼ぶと、ウルティメイトフォースゼロの四人が名乗りをあげる。
「アンリエッタ姫さま、私は鏡の騎士、ミラーナイトと申します」
『私は鋼鉄の武人、ジャンボットです』
「俺が炎の戦士、グレンファイヤーな!」
『そして俺がウルトラマンゼロ! ここにはいないジャンナインと合わせて、宇宙警備隊
ウルティメイトフォースゼロ! ハルケギニアを狙う宇宙のワルをやっつけるために来たんだ!』
それからゼロたちは、自身らの素性や目的などを詳しくアンリエッタに伝えた。遂にウルティメイトフォースゼロの
確かな事実を知ったアンリエッタは、感極まって四人へ再び頭を下げた。
「そんなに遠くの世界から、わたくしたちのために……。何と感謝の気持ちを申し上げれば
よろしいのかもわかりません……」
-
『いいんだよ。宇宙の平和は俺たち自身の願いだ。アンリエッタ姫さんも、どうか平和の
実現のために頑張ってほしい』
「はい! わたくし、この身とこの魂を祖国トリステインとハルケギニアの大地の安寧のために
捧げる決心を改めて固めましたわ」
熱い思いを瞳にたぎらせたアンリエッタは、才人に告げる。
「それで、ウルトラマンゼロとして日々戦ってくださっているあなたにせめてものお力添えと、
ささやかながら感謝の気持ちとして、用意したものがあります。受け取ってください」
アンリエッタが差し出したのは、黒地のビロードのマントであった。小さく青い百合紋があしらわれ、
胸元には銀色の五芒星が燦然と輝いている。
それを見たルイズが、口と目を大きくあけた。
「“シュヴァリエ”のマントじゃない! ということは姫さま……サイトに“シュヴァリエ”の
称号授与を!? サイトを貴族に取り立てるおつもりですか!?」
「わッ!? す、すごいです! サイトさんが、貴族に!?」
シエスタもあっと驚いた。トリステインでは、ゲルマニアと違ってメイジでないいわゆる
『平民』が貴族の位をいただくことは、アンリエッタ以前の治世ならばあり得なかったことだ。
才人自身は、ことの重大さがよく飲み込めておらずにきょとんとしている。
「でも姫さま、どうしてサイトに“シュヴァリエ”の称号を……」
「侵略者の行いはあまりに姑息です。これから先、何の権限も持たない平民の身分では侵略者の
影を追う際に動きづらい時があるかもしれません。それ故の計らいです。この騎士のマントが
あるだけで、トリステインで行動できる範囲がぐんと広がります。戦時の彼自身の貢献も、
騎士叙勲の名誉を授けるに相応しいものです」
アンリエッタは改めて才人と向かい合う。
「お願い申し上げます、使い魔さん……いえ、サイトさん。あなたとゼロのお力を、これからも
わたくしたちハルケギニアの民にお貸しください」
才人はやっと、アンリエッタの自分への用件と、その重要さを理解した。ルイズやシエスタの
反応を見ても、ただごとではないことがはっきりわかる。
しかしルイズがアンリエッタに抗議した。
「姫さま、でもサイトを貴族にするなんて、認められませんわ!」
「どうしてかしら? トリステインで平民が貴族になる例は、既にアニエスがありますよ」
「サイトとアニエスは違います! サイトは元々トリステインの民ではありませんし、この世界の
人間でもないんですよ! そんな人間を貴族にしていいんですか?」
「彼に貴族の資格がない、とすれば、王国中の貴族から領地と官職を取り上げなければいけなくなるでしょう」
「でも、サイトはわたしの使い魔で……」
「ええ。もちろん、そのことは変わりません。貴族になれば、あなたのお手伝いもやりやすくなるはず。
違って?」
「でも、でも、わたしの“虚無”とウルトラマンゼロのことは秘密のはずじゃ……」
「もちろん、それは秘匿します。サイトさんが“ガンダールヴ”であり、ウルトラマンゼロだということは、
これまで通り一部の人間のみの機密です。彼は今までどおり“武器の扱いに長けた戦士”として振る舞って
もらいましょう」
そう言われては、もうルイズは反論できない。しかしアンリエッタは更に説得する。
「ルイズの他にも“担い手”がいるならなおさらあなたを今までとおりにしておくわけにはいきません。
名実共に騎士となり、ルイズを守っていただくことにいたします」
そうまで言われてはしかたがない。ルイズは頷いた。
「わかってくれたのね。嬉しいわ、ルイズ」
続いて才人に向けて、アンリエッタは水色の水晶があしらわれた杖を掲げた。
「略式ですが……、この場で“騎士叙勲”を行います。ひざまずいてください」
女王の威厳がこもったアンリエッタのその言葉に、才人は思わずひざまずいてしまった。
才人が目をつむり、頭を伏せると、右肩にアンリエッタの杖が乗せられた。そしてアンリエッタが
騎士叙勲の詔を唱える。
-
「我、トリステイン女王アンリエッタ、この者に祝福と騎士たる資格を与えんとす。高潔なる魂の
持ち主よ、比類なき勇を誇る者よ、並ぶものなき勲し者よ、始祖と我と祖国に、変わらぬ忠誠を……
いえ、他所の人間に、わたくしたちへの忠誠を誓わせるわけにはいきませんわね。詔の一部を変えます」
「姫さま」
思わずルイズが口を開いた。そんな騎士叙勲、聞いたことがない。
「いいのです。頼んでいるのはわたくしなのですから。わたくしは彼に請うて、騎士になっていただくのです」
アンリエッタは再び厳粛な顔になり、言葉を続けた。
「高潔なる魂の持ち主よ、比類なき勇を誇る者よ、並ぶものなき勲し者よ、汝の魂の在り処、
その魂が欲するところに忠誠を誓いますか?」
「……誓います」
「よろしい。始祖ブリミルの御名において、汝をシュヴァリエに叙する」
アンリエッタは、才人の右肩を二度叩き、次に左肩を二度叩いた。これで才人は騎士に叙されたのだ。
叙勲式が終わり、才人がマントを試しに羽織ると、シエスタらがわっと歓声を上げた。
「お似合いですよ、サイトさん! サイトさんがシュヴァリエなんて、夢のように素敵です!」
『うむ、なかなか様になっているな』
「マントが似合うような男前になったのも、俺の手腕だからな!」
「はいはい」
『へへッ、親父やレオのマント姿を思い出すな』
グレンたちがわいわい盛り上がる一方で、ルイズは複雑な気分だった。
才人が他ならぬアンリエッタに評価されたのが嬉しくないわけではないが、シュヴァリエなんかに
なってしまったら、今より女の子が寄ってくるのではないかなんて不安があるのだ。シエスタより
強力なライバルが現れたら、女の子としての魅力“ゼロ”の自分が勝てるんだろうか? などと
憂鬱になってしまう。
それだけではなく、才人はいずれ自分の世界に帰らなければならないはずだ。それなのに
騎士になんてなってしまって、いざ帰る時に未練が湧いたらどうするつもりなの? とも思っている。
それより何より、仮に才人がシュヴァリエとしてこの地に残ると考えて、喜びがこみ上げてきたのが
一番の理由なのであった。
そういう風にルイズが悶々としていたとき……。
ドンッ!!
「!? 何事かしら……!」
いきなり執務室の外から激しい爆音が響いてきたので、アンリエッタたちは一瞬にして
楽しげな雰囲気が吹っ飛び、緊張に包まれた。
「確かめて参ります」
早速控えていたアニエスが飛び出していこうとしたが、それより早くに銃士隊の隊員が一人、
執務室に駆け込んできた。
「失礼いたします! 非常事態です!」
「何が起きた!」
アニエスの問いに、隊員は早口に答える。
「王宮の一画で爆発が発生しました! 何者かに爆発物を仕掛けられたものと思われます!」
「爆発物だと……!?」
「まさか、また侵略者の破壊工作かしら……」
アンリエッタがつぶやき、才人たちは一瞬互いに目を合わせる。
刹那、才人は殺気を感じた!
「ッ!」
才人の身体は、考えるよりも早く、デルフリンガーを抜いていた。反射神経のみで動いていた。
グレンの指導の賜物だ。
そしてデルフリンガーで、電光のような速度で斬りかかってきた銃士隊員の剣を受け止めていた。
「えッ!?」
-
まさかの銃士隊員が才人を攻撃したので、ルイズたちは衝撃を覚えた。
攻撃の瞬間に能面のように生気のない表情となった銃士隊員は、全く動じずに二撃目を
仕掛けようとしたが、才人の切り上げが彼女の剣を弾き飛ばした。それでもなお才人に
襲いかかろうとする銃士隊員を背後からアニエスとグレンが捕まえ、床に抑えつける。
「貴様、これは何のつもりだ! もしくは侵略者の変装か!?」
アニエスの怒号に銃士隊員は何も答えず、二人を振り払おうとする。恐ろしい力であったが、
グレンの怪力により抑え込むことが出来た。
「すげぇ力だ……! 人間のパワーじゃねぇぜ!」
「ですが、星人の変身という訳でもないようです」
ミラーのひと言に同意するジャンボット。彼はセンサーで銃士隊員の状態を突き止めた。
『うむ。彼女は生身の肉体ではなくなっている! 何者かにサイボーグにされ、操られているのだろう』
『フッフッフッフッフッ……その通りだ』
突如として第三者の声が響き、執務室に宇宙人がテレポートで侵入してきた! 全身を甲冑で
覆っているように見えるが、正真正銘の生身である。
『ボーグ星人かッ!』
ゼロの指摘を肯定する宇宙人……ボーグ星人。
『如何にも、私は元宇宙人連合の一人、ボーグ星人。ウルティメイトフォースゼロ、貴様らを
抹殺してこの星を我々のものとする!』
ボーグ星人は堂々と宣戦布告する。才人がシュヴァリエに叙勲されてすぐに、新たな敵の
攻撃が始まったのだ!
-
以上です。
今年遂に待望のゼロ魔の新刊が刊行されますし、ペース上げていこうかと思います。
-
皆様、明けましておめでとうございます。
よろしければ、21:30頃からまた続きを投下させてください。
-
「身代わり……」
タバサは、ディーキンの言葉に僅かに首を傾けて、しばし考え込んだ。
だが、じきに思い至る。
「あの御伽噺?」
「そうなの。神様のお話によると、身代わりがあればしばらくはばれずに済むみたいだからね!」
タバサはやや当惑げに、机の上の品々とディーキンの顔とを、交互に見詰めた。
彼には、これらの品物から本人の身代わりとなるような何かを作り出せる能力もあるのだろうか。
そのような用途に用いられそうなもので、タバサの知識の範囲内で真っ先に思いあたるのは、スキルニルと呼ばれる魔法人形だった。
血を一滴垂らすだけでその者と寸分たがわぬ姿に化け、魔法的なものを除けば殆どの能力をも複写することができる、という代物だ。
非常に有用なマジックアイテムだといえるが、製法は既に遺失しており、新たに作られることはない。
だが、古い遺跡から見つかることは稀にあるし、伝統ある王家や貴族家の中にはこの品を所蔵しているところもある。
古代の王の中には多数のスキルニルを用いた戦争ごっこに興じていた者が何人もいたらしく、ある程度の数は現存しているのだ。
彼がスキルニルと似たような品を所有している、もしくはその作り方を知っているとしても、さほど不思議ではないだろう。
(そのために、爪や髪の毛を……?)
血の代わりに爪や髪の毛を用いて本人そっくりに化ける魔法人形、というのはありえそうに思えた。
ただ、スキルニルは一度作れば永続的に動き続けられる、というような代物ではない。
動かすための燃料として、製作時に『土』の精霊力の結晶である“土石”が組み込んであるのだ。
当然、力の強いスキルニルほど燃料切れも早くなる。
メイジが自分の魔力を注ぎ込んで維持することもできるが、その場合は操作する者が常に傍に居なくてはならない。
したがって、永続的な身代わりとして用いるのには向いていないといえる。
その他には、精巧に作られたガーゴイルでも、同様の役目がこなせるかもしれない。
ハルケギニアにおけるガーゴイルは、傍で操作せずともある程度の自由意志を持ち、自律的に動けるゴーレムの仲間だ。
優秀な『土』の使い手であれば、外見が人間とそっくりなガーゴイルを作ることも可能だろう。
作成時に自分の精神力を注ぎ込むだけではなく、土石を用いることで、稼働時間を延ばすことができる。
スキルニルのように元となった人間の技能を再現するのに力を消費しなくてよい分、長持ちさせることができよう。
ただ動いて話せる程度で、何も特殊な能力を持たないものであれば、大きめの土石を用いれば数十年でも稼働させ続けられるかもしれない。
彼はそういった、ガーゴイルに相当するようなものを作ろうとしているのだろうか?
それも、あり得なくはないかもしれない。
彼の用いる、ハルケギニアの常識を遥かに逸脱した呪文やマジック・アイテムの数々には、既に何度も驚かされてきたのだから……。
そこまで考えて、タバサは小さく溜息を吐いた。
(……きっと、考えても無駄)
これまで、彼は常に自分の予想を裏切り続けてきたではないか。
ならば結局のところ、こんな推測の試みは虚しいものでしかないのではないだろうか?
これまでに私の得てきた知識や常識は彼には通用しないと、既に十分証明されているのだから……。
タバサはそう結論してあれこれ考えるのを止めると、素直にディーキンのすることを見守ろうと決めた。
母の命運がかかっているというのに不謹慎だとは思うが、なんとなくワクワクする。
そういえば幼いころ、トーマスが手品を披露してくれる前にも、こんな気持ちになったものだった。
-
(それが、彼の狙い?)
ふと、そんな考えが頭を掠めた。
昨夜は彼と一緒に話し合ったものだが、こんなことをする予定だとは聞かされていない。
情報はぎりぎりまで味方にも伏せておいた方が安全だというような、慎重な思惑もあったのかもしれない。
しかしどちらかというと、内緒にしておいてびっくりさせようという子どもっぽい悪戯心の方が彼には似合うような気がした。
もしくは、その両方なのかもしれないが……。
いずれにせよ、私のためを思ってのことで、悪意に基づく行為でないことだけは確かだろう。
そう考えると、タバサは妙に嬉しいような気分になって、微かに口元を緩めた。
そんな彼女の思惑をよそに、ディーキンは机に並べた品物の中から、まずは小さなボトルを手に取った。
それから、部屋の天井にちらりと目をやる。
「……ウン、この高さなら問題ないね」
ディーキンはそう呟くと、手の中のボトルを大事そうに握りしめて、目を細めた。
これは、ラヴォエラがボスから預かってきてくれた品物の中に入っていたものである。
最初それを見た時は驚いて、これは何かの間違いで混ざったのだろう、早く送り返さなくては、と思った。
極めて貴重な物だし、自分が用意してくれるように頼んだ品々の中には入っていなかったからだ。
しかし、ラヴォエラはボスがディーキンのことを案じてそれを渡すように言ったのだ、と言った。
大きく文化の違う異界で、これがあれば非常に有用なはずだから、と。
ボスは他にも、旅の間に手に入れた貴重なマジック・アイテム類をいくつも、ラヴォエラに託して贈ってくれていた。
断りもいれずに突然旅に出た自分のために、ここまでしてくれるとは。
ボスの寛大な気遣いに、ディーキンは改めて感動した。
ディーキンはしみじみとその事を思い返しながら、勿体ぶった仕草でひとつ咳払いをする。
そして、おもむろにボトルをこすり始めた。
その動作に応じて、たちまちボトルが彼の手の中で振動しはじめる。
あわせてボトルの口から、煙がもくもくと立ち上りだした。
それを見て、タバサは咄嗟に杖を握り直した。
が、ディーキンが落ち着いた様子なのを確認すると、すぐに警戒を解く。
(これは一体、何?)
タバサがそんな内心の疑問を口にするより先に、変化が起こった。
立ち上った煙がぐるぐると渦を巻いて集まり、ぼんやりとした人型の形状を取り始めたのだ。
やがて煙が晴れると、その中からひとつの人影が現れた。
「……!」
それを見たタバサは、驚きで僅かに目を見開いた。
その人物は、立派な口髭と長い顎鬚を生やし、肌浅黒く頑強な体つきをした、中年の男性のような姿をしていた。
頭にはターバンを巻いており、エキゾチックな衣類や、高価そうな装身具類を身につけている。
そこまでなら、ロバ・アル・カリイエ(東方)のどこかの地方からやってきた貴人か富商だとでも言えば通りそうな身なりだった。
しかしながら、この人物の背丈は見上げるように高く、タバサの優に2倍はある。
明らかに、普通の人間ではない。人種の違いや個体差などで説明のつく範囲を超えていた。
-
「巨人……?」
その男はタバサの呟きを聞き咎めると、哀れむような目で彼女を見下ろした。
『私はジャイアントなどではないぞ、定命の者よ。
お前の無知の程度を推し量って、それを私に対する侮辱であると捉えることは差し控えるがな』
穏やかな調子だが、大きく轟くような声が、タバサの頭上から降り注いできた。
いや、それは実際には、彼女の頭の中に直接響いたのである。
巨大な人影は、それからディーキンの方にも目をやると、勿体ぶった仕草で2人に向かって御辞儀をした。
次いでその声が、2人の頭の中に轟く。
『そちらのコボルドには改めて言うまでもないだろうが、名乗らせて頂こうか。
私はヴォルカリオン・アーセティス、王家の血をひく有力なジンだ。
ジンは誇り高き魔人(ジンニー)の一種族であり、決して野卑な巨人(ジャイアント)の仲間ではないということも付け加えておこう』
「お久し振りなの、ジンのおじさん。
じゃあディーキンも、言うまでもないだろうけど名乗っておくね。
ディーキンはディーキン、竜族の血を引く愉快な詩人のコボルドで、バードで、冒険者で、今は使い魔もやってるよ」
「……私は……、タバサ。『雪風』のタバサ。
貴族で、メイジをやっている」
ディーキンが丁寧にお辞儀を返したのを見て、タバサも慌てて自己紹介をして頭を下げた。
それから顔を上げると、またまじまじと目の前の巨大な人物を見つめる。
「魔人……の、王族?」
いわゆる“高貴な魔人”に関する御伽噺ならば、ハルケギニアにもある。
もちろんタバサは、今の今まで魔人が実在するなどとは思っても見なかったが。
それらは、古い壺の蓋を開けたり、指輪やランプをこすったりすると、中から出てきて……。
(そして、願いを……)
そんなことを考えていたところへ、またヴォルカリオンから声が送られてきた。
『ふむ。王族だというのは、誤解を招く恐れがあるかもしれんな。ジンであれば誰でも、何らかの形で王家の血筋をひいているものだ。
私の家系はとても尊敬されているのは確かだが、権力の座からは遠いのだ。
ジンの社会における私の地位をお前たちの階級社会に当てはめてあらわすなら、私は貴族の類ではない』
それから、咳払いをして付け加える。
『……それと、新顔のお嬢さんのためにあらかじめ言っておくが。
私は、定命の存在の3つの《望み(ウィッシュ)》を叶えるようなことはせんからな!』
いままさにそんな期待を少しばかりしていたタバサは、思わず僅かに顔をしかめた。
ヴォルカリオンはそれを見ると、腕組みをして小さく鼻を鳴らす。
『ふん、おまえたち定命の者は妙な先入観から、我々に会えばいつでも願いを叶えてもらえるはずだと信じているようだがな……。
残念だろうが、そう都合よくはいかんぞ。
第一、どうして我々が出会ったばかりの他人の願いを、さしたる理由もなく気前よく叶えてやらねばならんと思うのだ?
私としても、いちいち初対面の相手から願いを言われるのにはもううんざりしておる!』
-
「……」
タバサは、少しばかりばつの悪い思いがしてヴォルカリオンから顔を逸らすと、問い掛けるようにディーキンの方を見つめた。
願いを叶えてもらうためにこの魔人を呼んだのではないとするなら、一体何のために?
ディーキンはタバサの視線に対して少し悪戯っぽい笑みを返すと、ヴォルカリオンの方に向き直った。
「それで、ヴォルカリオンさん。
これからはディーキンとも取引をしてくれるっていうのは、本当なの?」
ヴォルカリオンはその問いに対して、鷹揚に頷いた。
『コボルドという種族が、尊敬を受けるようなものではないということは知っておる。
長年商人として活動をしてきた私としても、正直に言ってコボルドの顧客というのは初めてなのだ。
だが、ドロウどもから私の召喚の瓶を取り戻してくれた解放者であり、今や良き顧客でもあるあの“カニアの英雄”の紹介とあればな。
……ああ、もちろんお前に渡した瓶の代わりに、彼にもすぐに新しい瓶を用意する手筈になっておるから、心配は無用だぞ』
それを聞いて、ディーキンは嬉しそうにうんうんと頷いた。
自分がこの瓶を預かったせいでボスに迷惑がかかるのではないかと思っていたが、そうでないのなら一安心だ。
しかも、自分とボスの両方がヴォルカリオンを呼び出せるということになれば、彼に伝言などを頼むこともできるだろう。
そうすれば、今後は連絡をとろうと思うたびにラヴォエラを召喚したりする必要もなくなるはず……。
そう考えていたところへ、タバサが口を挟んだ。
「……商人?」
どうやら今のヴォルカリオンのテレパシーは、彼女にも送られていたようだ。
ヴォルカリオンは、ひとつ頷いてそれに答えた。
『いかにも。私は、強力で貴重なアイテムを扱っている次元間商人でな。
様々な世界を歩き回り、すばらしい品々を有り余るほど集めて、厳選した少数の客に売っているのだ。
顧客は、商品を見たい時にはいつでも召喚の瓶をこすって、私をどこの世界からでも呼び出してよいということに取り決めてある』
タバサはそれを聞くと、首を傾げて考え込んだ。
つまり、この魔人は目の前の瓶の中に入っていたのではなく、どこかの世界からこの瓶で召喚されているということか。
それにしても……。
「魔人も、お金を使うの?」
タバサの素朴な問いに、ヴォルカリオンは少し首を傾けた。
『ふむ……。使うことがあるのかと問われれば、その通りだと答えるしかないな。
我ら魔人も、時と場合によってはお前たち定命の種族と同様、金を使って取引をすることはある』
それから、口髭を弄りながら付け加える。
『ただ、私の商売に関して言えば、金自体よりもそれが象徴するものをより重視している。
ゴールドは定命の者にとって貴重で、手放すには犠牲が伴う。
つまり私の扱う品物には価値があるから、買うには代償を伴うということで――』
そこで少しの間言葉を止めて、適切な説明の仕方を考え込んだ。
『――言うなれば、金を渡せば犠牲の価値、おまえたちにとっての価値が、私へと移ることになるのだ。
とても複雑な話だから、完全に理解してもらえると思ってはいないがな』
-
「えーと。とにかく、必要なお金を払えば、普通のお店と同じに商品が買えるってことだよね?」
ディーキンが横から口を挟んで、簡潔にまとめた。
『まあ、そういうことになるな。
結局のところ、お前たちにとって重要なことは、アイテムの値段は私が決めるのであって交渉の余地はないということだけだろう』
「わかったの、ディーキンはあんたから値切ろうとは思わないよ。ボスだって、値切ったりはしないからね」
『よろしい。それから、わかっているだろうが、私が呼び出しに応じるのは最大で1日に3回までだ。
その回数以内なら、私がその時点でどの次元界のどんな場所を探検していようと、瓶を使えば呼びかけには一瞬で応えよう』
「大丈夫、ディーキンはしっかり覚えてるよ」
『後は……、くれぐれも私の瓶を、不埒な輩に奪われないように気を付けてもらいたい。
ハラスターのような不注意な顧客は、もう御免こうむりたいのでな!』
この“ジンのボトル”は、元々はかのアンダーマウンテンの大魔道士、ハラスターが所有していたものである。
ヴォルカリオンは他次元界から商品を呼び出すことができ、瓶を使うことで彼を召喚して、それらの在庫を見せてもらうことができるのだ。
ボスは、ディーキンらと共にアンダーマウンテンを旅していた時に、倒したドロウの一人がこの瓶を所有しているのを発見した。
おそらく、ドロウたちがハラスターを捕えた時に、彼から奪い取ったのであろう。
ヴォルカリオンは顧客にする気もないドロウたちからしつこく瓶を使って呼び出されていたらしく、解放したことに大変感謝していた。
その返礼として、彼はボスを自分の顧客の一人に加えたのである。
わざわざ他次元界からやって来てくれる手間賃を取られているのか、彼の店の品物は概して相場より高めだし、買い取りは安めだ。
それでも、ヴォルカリオンは瓶をこすりさえすればほとんどどこにでもやって来てくれるので、商品の売買に大変役立ってくれた。
アンダーマウンテンでも、アンダーダークでも、九層地獄でも、ボスは幾度となく彼の店の世話になっていたものである。
『ハラスターがあれほど不注意だとわかっていれば、召喚の瓶を作ることに絶対に同意しなかったのだがな……。
だが、“カニアの英雄”は良い客だ。彼との取引では、私も相当な利益を上げることができたよ。
彼からは、ハラスターが死蔵していた貴重な宝物や、九層地獄下層部の珍品なども、数多く仕入れることができたからな』
ヴォルカリオンは満足そうに顎鬚をさすりながら、目を細めた。
『お前も、そうなってくれるものと期待しているぞ。
この物質界のことは私も知らなかった、まだ足を運んだことがない地だからな。
他の世界では見られぬような品物が見つかれば、私の店にどんどん売りに出してくれ。高値で買い取ろう』
「オオ、それは嬉しいの。
じゃあさっそく、こっちの世界で見つけたものがいくつかあるんだけど……」
ディーキンは背負い袋の中から、先だってカジノで回収した品物をいろいろと取り出し始めた。
それらの中には、フェイルーンにはない、この世界で作られた器具や薬品、マジック・アイテムなどの類が含まれている。
タバサは得心がいった思いで、その作業の様子を眺めていた。
なるほど、彼がこの魔人を呼び出したのは不用品を売却し、身代わりを作るだのといった作業に必要な品物を買い入れるためか。
「……私も、何か用意してくる」
タバサはそう言って小さく頭を下げると、部屋の外へ向かおうとした。
ペルスランに事情を伝えて、この屋敷の中から金になりそうなものを集めてこようというのだ。
-
彼は自分や母のために力を貸してくれているのだから、必要な費用はこちらも可能な限り捻出するべきだろう。
それにあのカジノでも、彼はデーモンとやらと戦うために、巻物などを消費した様子だった。
おそらくその分を買い足す必要もあるのだろうし、あれも自分の仕事を手伝ってくれた結果なのだから、こちらが負担するべきだ。
王族の権利を剥奪されて以来、この屋敷にはそれほど大したものは残っていない。
残ったものにも祖先から受け継いだ縁のある品々が多く、本来ならば売り払ったりするべきではない。
しかし、この人の力になるため、母を救うための手助けとするためならば、きっと祖先たちも許してくれることだろう……。
「ンー……、」
ディーキンはタバサを止めるべきだろうかと、少し悩んだ。
確かにこのところ、普段ならば仲間に任せているような事でも自分でこなさねばならなくなったこともあって、出費はかさんではいる。
とはいえ、まだまだ余裕はあるし、金欠で困っているというほどではない。
だから、タバサに無理に金を捻出してもらう必要は、ないといえばないのだが……。
しかし彼女の気持ちを考えれば、自分も母親のために何かしたいと思うのは当然だろう。
無理に引き留めても、かえって彼女の思いを無下にすることになる。
そう思ったディーキンは、素直に申し出に甘えることにしてタバサを見送った。
それから、ヴォルカリオンの方へ向き直る。
「それじゃ、タバサが用意してくれてる間に、在庫を見せてもらえる?」
『もちろんだ。ただし、金を払うまでは手を触れないようにな』
ヴォルカリオンがそう言って、さっと手を一振りすると、たちまち周囲の様子が一変した。
がらんとした室内が、どこからともなく出現した、眩いばかりの魔法の品々で埋め尽くされたのだ。
展示棚に広げられた数々のスクロールに、戸棚に並べられた色とりどりのポーション。
かさ立てのような容器に詰め込まれたロッド、ワンド、スタッフ。
鎧掛けには大小さまざまな鎧が飾られ、台の上には手入れの良い武器がずらりと陳列してある。
他にも、外套、籠手、手袋、長靴、魔除け、首飾り、指輪、鞘、聖句箱などなど、あらゆる種類の魔法の品々が揃っていた。
ボスがこの店で売買を行うのを何度も目撃していたので、ディーキンにとっては既に見慣れた光景だ。
最初の時には、目を丸くしてはしゃいだものだったが。
(イヒヒ……、タバサが戻ってきたら、驚いてくれるかな?)
そんな悪戯っぽい思いを胸に、ディーキンはゆっくりと品物を見て回った。
まずは、タバサの母親や執事のペルスランの身代わりを作るため、《似姿(シミュレイクラム)》の呪文が必要になる。
とはいえ、最低でも2人分で2回使う必要があるわけだが、はたして在庫があるだろうか。
もしも足りなければ、《望み》か《奇跡(ミラクル)》あたりで代用することも考えねばなるまい。
あるいは、必要な呪文を使ってくれそうな来訪者を招請するか、だ。
それに、いずれ身代わりがばれた時に見つからないようにするための方策も、できれば用意しておきたい。
理想は露見するほどの時間が経つ前に、この問題の根を絶ってしまえることだが……。
あとは、これまでに消費したスクロールなども買い足しておかねばなるまい。
これからデヴィルを相手にすることも予測される以上、《次元界移動拘束(ディメンジョナル・アンカー)》などの呪文は必須だ。
(ええと、他に必要そうなのは……。手持ちのお金は足りるかな?)
ディーキンは、入用な品物を優先度順にさらさらと羊皮紙に書き出しながら、費用の計算をしていった……。
-
ジンニー(魔人):
ジンニーは地水火風の元素界に住む精霊めいた来訪者であり、いくつかの種族がある。
風のジン、火のイフリート、水のマリード、地のダオ、そして物質界に住み四元素すべてから成るジャーンである。
彼らの一部には、御伽噺に語られるように、定命の存在の願いを叶える力を持っている者もいる。
ジン(風の魔人):
風の元素界に住むジンは、混沌にして善の気性を持つジンニーである。彼らは自在に空を飛び回り、その身を竜巻やガスに変じられる。
また、透明化したり、幻覚を作り出したり、飲食物やワインを生み出したりすることができる。
永続する植物性の物質を無から作り出したり、一時的になら宝石や貴金属等の様々な品物を作り出したりすることもできる。
彼らの100人に1人は“高貴なるジン”であり、同族以外の存在の3つの《望み(ウィッシュ)》を叶えてやることができる力がある。
ただし、一般的に彼らがそうするのは、誰かに捕えられて解放と引き換えに奉仕を約束した場合だけである。
ジンのボトル:
NWNに登場する、特殊なマジック・アイテム。
使用することでほぼどんな場所でもジンの次元間商人であるヴォルカリオンを召喚し、商品の売買をすることができる。
ヴォルカリオンがしてくれるのは基本的には商取引だけで、戦闘への参加などはしてくれない。
----------------------------------------------------------------------
今回は以上になります。
出来るだけ早く続きを書いていきますので、本年もまた、よろしくお願いいたします……(御辞儀)
-
おつです
-
亀ですいませんがウル5の人、ウルゼロの人も含めて乙です
-
こんばんは、焼き鮭です。今回も投下をさせてもらいます。
開始は2216からで。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第八十話「君はウルトラマンゼロだ」
甲冑星人ボーグ星人
熔鉄怪獣ツルギデマーガ 登場
執務室に侵入してきたボーグ星人に対し、才人、ルイズ、アンリエッタ、アニエスはそれぞれの
得物を手にした。皆臨戦態勢に入り、ボーグ星人を強くにらむ。
『ボーグ星人……宇宙人連合が壊滅したってのに、このハルケギニアの侵略をやめないってことかよ』
問いかけるゼロ。宇宙人連合はヤプールの消滅により、まとめる役割がいなくなったことで
自ずと解散となった。だが先日才人を急襲したレギュラン星人やバルキー星人のように、
連合がなくなっても侵略をあきらめない者が少なからずいるようだ。
『フッフッフッ、当然だ。ヤプールは元よりこの宇宙に来るために利用しただけ。奴を葬ってくれて、
むしろお前たちに感謝してもいいくらいだ。この星をいただくための一番の邪魔者がいなくなったのだからな』
そう語るボーグ星人。ヤプール自身がそうだったが、宇宙人たちもヤプールに対して利用価値以上のものを
見出していなかった。連合など所詮、利害の一致だけの薄っぺらい結束だったのだ。
「けッ! 相変わらず侵略者ってのは胸くそわりぃ性格だぜ」
グレンが吐き捨て、ミラーがボーグ星人に指摘する。
「私たちを抹殺するつもりとのことですが、この女性を利用した奇襲が失敗しておいて、
あなた一人で私たち全員を相手にするつもりか?」
ウルティメイトフォースゼロは全員が一流の戦士。才人もまた強くなった。そこにルイズたちもいる。
どう考えても、ボーグ星人単体に勝ち目などない。
しかしボーグ星人は余裕の態度であった。
『フッフッフッフッ、お前たち全員に私と戦う暇があればの話だ』
「何?」
『先ほど、私が仕掛けた爆弾が炸裂しただろう』
前置きをして、ボーグ星人は恐ろしいことを説明し出した。
『それの何倍もの威力がある時限プレート爆弾を八個、この王宮の至るところに仕掛けた。
一つだけでも王宮を吹き飛ばすのに十分な威力を、八個だ!』
その言葉にギョッと驚愕する才人たち。
『フッフッフッフッ、一個でも逃したら何人の人間が死ぬだろうなぁ? フッフッフッフッフッ……!』
脅迫の文句を言い残したボーグ星人は窓へ飛び込み、ガラスを突き破って外へと逃走した。
「待ちやがれ、この野郎!」
それを追いかける才人。
「サイト!」
ゼロはルイズらに言いつける。
『俺たちはボーグ星人を倒してくる! みんなは手分けして爆弾を回収して、爆発を阻止してくれ!』
「頼んだぜ! デュワッ!」
才人は窓から外へ飛び出すと同時に、ウルトラゼロアイを装着した。
残された執務室の者たちは、アンリエッタを中心に行動を起こす。
「こうしてはいられません! いつ爆発するかも分かりません、役人や使用人たちは直ちに
王宮外へ避難させ、兵士を総動員して爆弾を捜索しましょう!」
「陛下も避難して下さい! 総指揮はわたしが行います」
アニエスが申し出たが、アンリエッタは首を横に振った。
「いいえ、人の上に立つ者が逃げるのは常に最後です」
「陛下……了解しました!」
「ルイズとウルティメイトフォースゼロの皆さまは、ゼロを助けてあげて下さい」
アンリエッタはそう言ったが、ミラーたちは次の通りに返す。
「いえ、ボーグ星人の言葉が真実とは限りません。八個以上の数が仕掛けられてる恐れもあります。
王宮中をくまなく探すには、私たちの力が必要となりましょう。私たちも協力します」
-
「ボーグ星人ならゼロとサイトに任せときゃ大丈夫だぜ! あいつらが負けるもんかよ!」
『うむ。私たちはゼロとサイトを信頼している!』
「姫さま、わたしも手伝います! 人手は一人でも多くあるべきでしょう」
「わ、わたしもジャンボットさんと一緒に!」
五人の言葉を受けて、アンリエッタは固くうなずいた。
「分かりました。では、皆さまのお力をわたくしたちトリステインにどうかお貸し下さい!」
「おうよッ!」
グレンが代表してうなずき返し、一同は直ちに爆弾捜索に取りかかっていった。
外へと逃走したボーグ星人は、城下町の真ん中で巨大化を果たす。
その直後に変身したウルトラマンゼロもまた巨大化。ボーグ星人と向かい合って宇宙空手の構えを取った。
「あッ! 侵略者がまた現れたぞ!」
「それに……ウルトラマンゼロも!」
トリスタニアの民たちはボーグ星人出現に驚く以上に、久々のゼロの勇姿に大きく沸き上がった。
「ゼロは生きてたんだ! よかった!」
「また私たちを救って下さるのね! ああ、ゼロさま!」
「ゼロー! 頑張ってー!」
「侵略者なんてやっつけろー!」
ゼロの生存を知った人々は歓喜し、こぞってゼロに熱い声援を送る。それを一身に受けるゼロは、
勇んでボーグ星人に立ち向かう!
『俺のこのカラータイマーが輝く限り、ハルケギニアはお前みたいな連中の好きにはさせないぜ!
行くぜッ!』
『ふんッ! 来るがいい!』
ゼロとボーグ星人双方が踏み出し、格闘戦を開始した!
「ジュワッ!」
ゼロの先制の拳を腕一本で防御するボーグ星人。ボーグ星人は見た目の通り、全身が甲冑並みに強固。
生半可な打撃では少しのダメージにもならない。
頑丈な肉体が生み出すのは防御力だけにあらず。ボーグ星人のカウンターのパンチは文字通り鉄拳で、
打たれたゼロの頬がジンジンと痺れる。
『ぐッ! せぇいッ!』
だがゼロはダメージをぐっとこらえ、突き出されたボーグ星人の腕を捕らえて素早く背負い投げを決めた。
地面に叩きつけられるボーグ星人だが、打たれ強さもなかなかのもので、すぐに起き上がる。
そこからボーグ星人はゼロに向けてパンチのラッシュを繰り出す。しかしゼロは全てさばき切り、
鋭い掌底を相手の胸の中央に入れてボーグ星人を吹っ飛ばした。
武術には『気功』というものがある。体内の力の流れを制御して、効率よくパワーを発揮したり
相手に一層のダメージを与えたり出来るのだ。宇宙空手の達人たるゼロも気功を扱える。それにより、
今の掌底から生じた衝撃をボーグ星人の肉体の内側へと行き渡らせたのだ。体表は鉄のように強靭な
ボーグ星人も、体内まで頑丈とはいかず、無視できないダメージを受けて一瞬ふらつく。
格闘戦で劣勢のボーグ星人は、頭部の中央のトサカから細いレーザーを発射した!
「シャッ!」
だがゼロは即座にウルトラゼロディフェンサーを展開し、レーザーを防御。バリアを消すと
間髪入れずにエメリウムスラッシュをお返しして、ボーグ星人を撃つ。
よろめいたボーグ星人だが、押されているというのに焦りを見せずに言い放った。
『フッフッフッ、聞きしに勝る実力だな、ゼロ。ボーグ星一の戦士である私をこうも容易く
追い詰めるとは。やはり、アレを用意しておいて正解だった』
『アレ、だと?』
『真の勝負はここからということだ。さぁ、出てこい!』
-
ボーグ星人の呼び声に応じるように、ゼロの背後の地面が下から一直線に切り裂かれ、
裂け目が広がって巨大怪獣がせり上がってきた!
「グバアアアアアア! ギャギャギャギャギャギャ!」
以前にグレンファイヤーが倒した怪獣、デマーガと同種。しかし両腕からは長大な剣が生え、
両肩からも反り返った禍々しい刃が伸びている。全身から発せられる威圧感も、デマーガよりも
ひと回りもふた回りも大きい。
『そいつはツルギデマーガ。ヤプールが強化改造を施し、リザーブしていたのを私がいただいたのだ。
さぁツルギデマーガよ、ウルトラマンゼロを八つ裂きにしてしまえ!』
「グバアアアアアア! ギャギャギャギャギャギャ!」
ボーグ星人の命令でツルギデマーガが咆哮し、ゼロに向かって突き進み始める。
「シェアッ!」
ゼロはツルギデマーガに向けてゼロスラッガーを投擲。だがふた振りのスラッガーはデマーガの
腕の剣に難なく弾かれてしまう。
「デェヤッ!」
スラッガーを戻したゼロは次にワイドゼロショットを発射。が、デマーガが振るった剣によって
真っ二つに切り裂かれてしまった。
『くッ、伊達に剣がある訳じゃねぇってか……!』
必殺技が二連続で破られたゼロが舌打ちする。
「グバアアアアアア! ギャギャギャギャギャギャ!」
今度はツルギデマーガの攻撃する番だった。口から熔鉄光線を発射! あまりに膨大な熱量で、
大気が歪むほどであった!
ゼロはウルトラゼロディフェンサーで防御しようとしたが、熔鉄光線はバリアをも溶かして
ゼロを弾き飛ばした!
『ぐわあぁぁッ!』
「グバアアアアアア! ギャギャギャギャギャギャ!」
投げ出されたゼロに詰め寄っていったツルギデマーガが斬撃を振るう。両手にスラッガーを
逆手に持ったゼロが受け止めようとするが、ツルギデマーガの凄まじい剣圧に押されて防御を崩され、
剣をその身に食らう。
『うぐわぁぁぁぁぁッ!』
剣は深々とゼロの身体を切り裂き、ゼロは一旦後退を余儀なくさせられる。
『つぅッ……何てパワーだ……!』
ツルギデマーガを警戒するゼロだが、そこにボーグ星人が飛び蹴りを仕掛けてきた!
『うわッ!』
『フッフッフッフッ、私がいることも忘れるんじゃないぞ!』
掴みかかってくるボーグ星人を対処している間に、ツルギデマーガが接近してきて剣を薙いでくる。
「グバアアアアアア! ギャギャギャギャギャギャ!」
『ぐッ……!』
その攻撃をどうにかかいくぐるゼロだが、ツルギデマーガに意識が向いている隙をボーグ星人に
狙われ、みぞおちに鉄拳をもらった。
『ぐはッ!』
ボーグ星人とツルギデマーガに挟み撃ちにされたゼロは、一転して窮地に立たされてしまった。
カラータイマーが赤く点滅し出す。
「あった! これで四つ目だな……」
王宮では、グレンたちによる爆弾捜索が大急ぎで行われていた。たった今グレンが四個目の爆弾を、
回廊に飾られている絵画の裏から見つけ出す。発見された爆弾は随時、ミラーが解体して信管を抜いていく。
だがここで、彼につき添うアンリエッタが窓からゼロの苦戦を目撃し、両手で口を覆った。
「グレン、ゼロが危険な状態に陥ってます!」
「何ッ!?」
「侵略者は怪獣も出してます!」
グレンは新たに出現したツルギデマーガの姿を確認し、ギリッと歯噛みする。
「そうか、爆弾で俺たちを抑えつけてる間に二対一でゼロを倒そうって作戦だったんだな……」
-
「グレン、あなただけでもゼロを助けに行ってあげて下さい! いくらゼロでも、一人だけでは……」
魔法衛士隊も爆弾の捜索に駆り出されているため、現在のゼロは孤立無援の状況だ。
焦るアンリエッタはグレンにそう要請したのだが、
「いいや、ゼロは一人なんかじゃねぇぜ」
「え?」
グレンがそう返したので、思わず変な声を出してしまった。
グレンは力強い表情で、こう告げる。
「ゼロにはサイトの奴がついてる。サイトはアルビオンで、男として見違えるぐらいに成長したんだ。
それは鍛えた俺がよく知ってる。あいつがゼロの力になってくれるぜ!」
『ぐっはぁッ!』
ゼロはツルギデマーガとボーグ星人の同時攻撃で吹き飛ばされ、背中から地面に叩きつけられた。
彼を見下ろしてボーグ星人が豪語する。
『フッフッフッフッフッ! たとえお前とて、このヤプールの秘蔵のツルギデマーガと私を前にして、
たった一人では勝ちの目はない!』
だが、なおも立ち上がったゼロは言い放つ。
『俺は、一人じゃねぇんだぜ……!』
『何だと?』
そしてゼロは、己の内の才人に呼びかける。
『才人、俺は知ってる。俺が眠ってる間に、お前は前よりもずっとずっと強くなったってことを。
意識がなくとも、お前の頑張りは俺にしっかりと伝わってたぜ』
『ゼロ……』
『お前のその強さと勇気が、俺にも力をくれる! 才人、俺と協力してくれ! 一緒に俺たちの、
みんなの未来を切り開こうぜ!』
『ああ、もちろんだ!』
ゼロと才人は今、心を重ねる。
『何をごちゃごちゃ言っている! ツルギデマーガ、早くやってしまえッ!』
「グバアアアアアア! ギャギャギャギャギャギャ!」
業を煮やしたボーグ星人にけしかけられ、ツルギデマーガがゼロに迫っていく。恐るべき切れ味の
凶刃がゼロに向けて振るわれる……!
「フッ!」
しかし、ゼロは二本の指でその刃をはっしと止めた!
『な、何だとぉ!?』
それまでツルギデマーガに手も足も出ていなかったゼロが、突然剣を受け止めたことに
衝撃を受けるボーグ星人。ツルギデマーガはより凶暴になって両腕の剣を滅茶苦茶に
振り回し出したが、ゼロは全て見切り無駄のない動きでかわし切った。
『とぉうッ!』
ツルギデマーガが疲労で動きの鈍ったところで、ゼロはひねりをつけながら相手の頭上を
跳び越えて背後に回り込み、尻尾を抱え込んだ。
『でりゃあああぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁッ!』
「グバアアアアアア!」
そこからジャイアントスウィング! ツルギデマーガの巨体が軽々と宙を舞い、真っ逆さまに
地表に落下した。
『おのれぇッ!』
まさかのゼロの盛り返しに焦りを覚えたボーグ星人が背後から突撃をかけたが、すかさず
放たれた後ろ蹴りで返り討ちにされた。
『ごはぁッ! ど、どういうことだ……あれだけのダメージを受けながら、動きに磨きが
かかっただと……!?』
混乱するボーグ星人。そこには、才人の存在があるのだ。
今の才人とゼロは一心同体。ゼロは才人の影響を受ける。才人の心が弱まればゼロは力を
発揮できなくなるが、逆に才人の心の高まりがゼロに一層の力を与える。
-
才人はグレンの鍛錬によって心身ともに見違えるほどに鍛えられ、戦士の風格を得た。
また、ポール星人の仕掛けた試練を乗り越えたことで、大きな勇気がその胸に宿った。
彼の鍛え込まれた熱い魂がゼロの精神とシンクロし、彼の実力を以前よりも一段も二段も
高く引き上げているのだ!
ゼロは才人へ呼びかける。
『才人、お前の強さが俺に流れ込んでくるのが分かる。お前と一緒であることで、俺はもっと
強くなっている! 俺たちはもっと高みへ行けるぜ!』
『ああ! 俺も前よりずっと、お前が近くにいることを感じるよ、ゼロ!』
『相棒たち、俺のことも忘れるなよ!』
デルフリンガーが声を上げた。
『もちろんだぜ。デルフ、お前も一緒に戦おうぜ!』
ゼロはスラッガーとデルフリンガーを結合し、ゼロツインソードDSを作り上げてツルギデマーガへと
肉薄していく。
「グバアアアアアア! ギャギャギャギャギャギャ!」
ゼロツインソードDSと斬り結ぶツルギデマーガだが――その途端に、腕の刃が粉々に砕け散った!
「グバアアアアアア!?」
武器を破壊されたことで大きく狼狽えるツルギデマーガ。先ほどまでの勢いが嘘だったかのように、
ゼロによって追い詰められていく。
デルフリンガーが叫ぶ。
『相棒、ガンダールヴの力は心の震えで引き出される! その力も、ゼロに影響してるんだぜ!
ガンダールヴのウルトラマン、ウルトラマンのガンダールヴ! へへッ、こりゃ無敵の組み合わせだぜ!』
『その通りだな! 行こうぜ、ゼロ!』
『おうよッ! プラズマスパークスラッシュだぁぁぁッ!』
ツインソードDSを真正面に構えたゼロが、一直線にツルギデマーガへと飛んでいく!
「グバアアアアアア! ギャギャギャギャギャギャ!」
ツルギデマーガは熔鉄光線を吐き出してゼロを撃ち落とそうとしたが、ゼロは先ほどとは逆に、
熔鉄光線を真っ二つに切り裂きながら直進していった。
「セェェェヤァッ!!」
そしてツルギデマーガも一刀両断! ツルギデマーガは壮絶な大爆発を起こして消え去った!
『なぁぁッ……! お、おのれぇぇぇぇぇッ!』
切り札のツルギデマーガを討ち取られたボーグ星人は、最早自棄になってゼロスラッガーを
戻したゼロへ殴りかかっていく。が、拳を易々と止められて当て身で迎え撃たれた。
『ぐふぅッ!』
『うりゃあぁぁッ!』
ゼロは更にボーグ星人の背後を取り、ゼロドライバーを決めた! ボーグ星人は脳天から
大地に打ち据えられる。
『ごふぅッ……!』
『さぁ行くぜ! フィニッシュだぁぁぁ――――――――ッ!』
一足飛びで距離を取ったゼロは、スラッガーをカラータイマーに接続してゼロツインシュートを発射!
ちょうど起き上がったボーグ星人は、光の奔流に呑み込まれる!
『うぎゃあああぁぁぁぁぁぁぁぁぁッ!? こ、この力は何だ!? その強さはどういうことなんだッ!
お、お前は何なんだぁ……!』
『ウルトラマンゼロ! 俺の、俺たちの名前だッ!』
颯爽と背を向けるゼロ。それと同時に、ボーグ星人は爆裂して紅蓮の炎を遺した。
ゼロが逆転勝利を収めた頃、グレンたちも八個の爆弾全部を発見し終えていた。
「これで全部みたいだな……。他にも爆弾がなくてよかったぜ」
「爆弾も解体し終えました。これでもう安心ですよ」
もう爆発の恐れがないことが分かり、ルイズたちはほっと胸を撫で下ろした。だがアニエスは
もう一つ、心配があった。
「しかしわたしの部下が、敵の手で機械にされたままだ。あれは元の人間に戻れるのだろうか……?」
それについては、ジャンボットが答える。
-
『大丈夫だ。私の設備があれば、彼女を本来の生身の状態に戻すことも可能だ。後で彼女を
引き取ろう。一日もあれば治せるはずだ』
「私も手伝いましょう。アニエスさん、すぐにあなたの部下をお返ししますよ」
「かたじけない……!」
ジャンボットとミラーに頭を下げたアニエスは、安堵して微笑みを浮かべた。
王宮の問題が片づいたところで、変身を解いた才人が戻ってきた。
「みんな、敵はやっつけたぜ! そっちも解決したみたいだな」
「サイトさん! よかった、ご無事だったんですね!」
シエスタとアンリエッタが才人の無事の帰還に喜びを見せた。ゼロはミラーたちに告げる。
『今回の勝利は才人がいてこそだったぜ。こいつの勇気が俺に力をくれたんだ』
「そうですか。やりましたね、サイト」
『君はもう立派な戦士だ! 実に素晴らしい』
ミラーとジャンボットに称賛されて、才人は照れくさそうにはにかんだ。
「俺も誇らしい気分だぜ! なぁ、ルイズもそうだろ? 何たってお前さんの使い魔なんだしな」
グレンが呼びかけると、ルイズは若干つんけんとした態度で才人に告げる。
「まぁ、姫さまから賜ったシュヴァリエの称号に恥ずかしくない程度には頑張ったんじゃない?」
「むッ、何だよ、その言い草。もっと他に言うことないのか? よく頑張ったわねーとか、
すごいわサイトーとか」
ルイズのぶっきらぼうな言葉に顔をしかめる才人。
「調子乗るんじゃないわよ。全く、あんたってすぐそうなるんだから」
鼻を白けさせたルイズだが……すぐにやんわりと表情を緩めて、才人に言った。
「……お帰りなさい。これからも、改めてよろしくね、サイト」
「……ああ。こっちこそよろしくな、ルイズ」
一瞬面食らった才人は、すぐに同じように微笑を見せて返答した。
その背にかかったマントが、どこか誇らしげに翻った。
-
以上です。
次回から新章です。
-
乙です!
-
皆様、お久し振りです。
よろしければ、9:55頃からまた続きを投下させてください。
-
タバサがディーキンらを連れてオルレアンの屋敷へ戻ってから、2日目の晩のこと。
屋敷の最奥、オルレアン公夫人の部屋では、最後の仕込みが行われていた。
「じゃあ、申し訳ないけどあんたはいつもベッドの上に居て、おかしくなったままのフリをしててね。
それと何かあったら、すぐにディーキンに連絡を入れて。わかった?」
「はい、心得ておりますわ」
先刻やっと完成した《似姿(シミュレイクラム)》のオルレアン公夫人が、ディーキンの指示に従順に頷く。
ディーキンはウンウンと頷くと、続けてもう一体のシミュレイクラムにも指示を伝えた。
「それから、あんたはこの人の世話をするフリを続けて。屋敷の掃除とかも、これまでどおりにちゃんとしてね」
「はい、しかと心得ました」
ペルスランのシミュレイクラムも、畏まってお辞儀をする。
これらの似姿は、粗雑な型どりをした雪や氷の像に本人の体の一部を入れ、影術による半実体の幻影を重ねて作られた複製品だ。
像を製作するにあたってはタバサにも協力を要請して、一体あたり半日以上の時間を費やして作った力作である。
2体とも本物そっくりで、本物の着衣を譲り受けて着込んでおり、ちょっとした知り合い程度ではまず見分けがつかないだろうと思われた。
夫人の方のシミュレイクラムには、必要があればすぐにディーキンに連絡を入れられるような細工もしておいた。
これで、万が一査察などの結果偽装が露見したとしても、直ちにその事を知って対策を取ることができるだろう。
「……うん。これで、しばらくは大丈夫だと思うの」
ディーキンは満足そうに笑みを浮かべて仲間たちの方を振り向くと、丸々一昼夜以上にも渡った作業の完了した旨を伝えた。
「ありがとうございます。あなたには何から何まで、よくしていただきました。
この御恩はいずれ必ずお返しします。杖に誓って……」
先程治療を受けて正気を取り戻した本物のオルレアン公夫人は、ディーキンに対して臣下のように恭しく跪いて、礼を述べた。
まだ頬などはこけたままだったが、その目にはすっかり知性と生気の輝きが戻っている。
彼女にしがみ付くようにして寄り添っていた、嬉し泣きに泣き腫らした赤い目をしたタバサも、母親に倣った。
そして主らの後ろに控えた、ペルスランとトーマスも。
「えーと……。別に、冒険者仲間とかでは普通のことだからね。
あんまり気をつかわないで?」
ディーキンは、ちょっと困ったように頭を掻いた。
もちろん、彼女らが本心から感謝してくれているのはわかるし、それは嬉しい。
それに、貴族として払わねばならぬ礼儀というものがあるのだということもわかる。
だが正直に言って、このくらいであまり大げさなお礼をされても逆に居心地が悪いのだ。
それは、他人からそんな態度で接された経験がろくにないから、というのもある。
しかしそうでなくとも、冒険者内では心を病んだら治してもらうとかは、ごく普通のことなのである。
ディーキンとしては、できれば今回かかった経費を負担してもらえると嬉しいな、という程度の気持ちだった。
その経費にしても、タバサが屋敷の骨董品等をヴォルカリオンに売りに出して、いくらかは既に負担してくれている。
売ったのが大切な先祖伝来の品々であっただろうことなども鑑みれば、これ以上何かしてもらうのはかえって申し訳ないくらいだ。
シルフィードだけはそんな堅苦しい人間の作法には従わず、代わりにそこらをぴょこぴょこと跳ねまわって喜びを体で表していた。
そういう自然な感謝の方が、ディーキンとしても気が楽だった。
「きゅいきゅい! お姉さまのお母さまがよくなられて、良かったのね。
これからはお姉さまも、危ないことなんかせずに、心安らかにお過ごしになれるわ!」
「…………」
礼を終えて、改めて母に寄り添い直したタバサは、自分の使い魔のそんな様子を温かい目で見つめながらも……。
心の中では、そうはいかないのだ、と考えていた。
-
自分は、母とペルスラン、それにトーマスの当面の住処と安全を確保したら、また元通りの生活に戻らなくてはならない。
ガリアからの呼び出しにも今まで通り応じて、危険な任務もこなしていかなくてはならないのだ。
今、急に自分が生活の仕方を変えて、王家からの呼び出しにも応じなくなれば、敵に異変を知らせるようなものである。
一度ガリア王家に自分の叛逆を悟られたら、いつまでも逃げおおせられるとは思えないし、周囲の人々にも危険が及ぶだろう。
せっかくのディーキンの配慮も、すべて無駄になってしまう。
できることならこの懐かしい人たちと共に、また退屈なほどに穏やかで幸福な、昔のような日々を過ごしていきたかった。
だが、ままならぬことである。
母は救ったが、父の復讐はまだ終わってはいない。
それに、一度冷徹な戦いの世界に慣れた自分が、いまさら何も知らなかった小娘の頃の生活に、完全に戻ることなどできようか。
自分はもう、子どもではないのだ。
(でも……)
でも、もう少しは、この安らぎに身を委ねていてもいいだろう。
母の腕を甘えるように抱き寄せ、母から優しく抱き返される幸せをしみじみと噛みしめながら、タバサはそう考えた。
・
・
・
-------------------------------------------------------------------------------
・
・
・
――――タバサは、ラグドリアンの湖畔に立つ屋敷の中庭で、家族と一緒に和やかな時を過ごしていた。
優しい父と母がテーブルを囲み、楽しげに料理を摘みながら談笑している。
そしてタバサ自身は、いやシャルロットは、二人に見守られるようにして、人形の『タバサ』を相手に絵本を読んで聞かせていた。
絵本のタイトルは『イーヴァルディの勇者』、ハルケギニアでも一番ポピュラーな英雄譚だった。
幼い頃、母はむずかる自分を寝かしつけるために、枕元でよく本を読んでくれたものである。
自分は特にこの本が大好きで、何度も何度もせがんで読んでもらった覚えがあった。
そのうちに興味は別のものに移り、読んでもらうことも、自分で開くこともなくなった。
だが、自分に読書の楽しみを最初に教えてくれたのは、この『イーヴァルディの勇者』だったといっていい。
この本を読むのは、もう何年振りだろう。
(何年振り?)
シャルロットはそこで、はたと気が付いた。
(これは、夢)
ああ、そうか。
自分は今、夢を見ているのだ。
今の自分は、もう家族と幸せに暮らしていた幼い少女ではないのだった。
そう気がついて、改めて自分の姿を見てみると、もう自分はシャルロットではなかった。
トリステイン魔法学院の制服に身を包んだ、『雪風』のタバサがそこにいた。
顔を上げると、傍らにはもはや人形はなく、机を囲む両親の姿ももうなかった。
そうだ、あんな風に温かい笑顔を浮かべる父は、もうどこにもいない。
そして母も、あの恐ろしい毒杯を口にして……。
(……?)
いや、違う。
なにかがおかしい。
-
自分の手の中には、まだ『イーヴァルディの勇者』の本があった。
『雪風』のタバサは、こんな本は読まない。
けれど、確かに読まないのだろうか。
自分がこの本を読むのは、本当に何年か振りだっただろうか。
いいや、つい最近にも読んだことがあったはずだ。
あれは一体、どこでだったか……?
(あれは……)
確か、そう、この屋敷で。
母さまに……。
「まあシャルロット。ずっと一人で本を読んでいたの?」
背後から、懐かしい声がした。
振り向くと、そこにいたのは確かに母だった。
屋敷から今出て来たばかりで、先程よりも少し年を重ねてやつれたようには見えるけれど、変わらぬ温和な笑顔を浮かべていた。
「母さま……」
「そんな風に一人で寂しそうにしていないで、もうすぐお友達が来るのでしょう。
ふふ、それとも、男の子のことでも考えていたのかしら?」
そうだ、自分は母を治療してもらうために、“あの人”と一緒にこの屋敷へきたのだった。
そして治療の準備が整うまでの間、あの人の作業の手伝いをする合間に、母にこの絵本を読んで聞かせたのだった。
それで母が元に戻ることはなかったけれど、話を聞いている間は終始穏やかで、読み終わったときには、私に笑顔を向けてくれさえした。
その後、あの人は母をすっかり治してくれて、今ではまた、こうして笑顔を……。
「奥さま、お嬢様のお友達の方々がお見えになりました」
執事のペルスランが屋敷の奥から姿を現し、そう言って頭を下げた。
傍らには、トーマスも一緒にいる。
2人とも、嬉しそうな笑顔を浮かべていた。
「今日はお嬢さまとお友達とのパーティのために、とっておきの手品を用意して参りましたよ」
その時、中庭にシルフィードが降り立った。
「お姉さまのお友達を連れてきたのね!」
自慢げにそう言う使い魔の顎を優しく撫でてやると、シルフィードは嬉しそうにきゅいきゅいと鳴いて、目を細めた。
次いでシルフィードの背から、学院の仲間たちが次々と姿を現す。
ルイズやシエスタが、花束や菓子の包みを渡してくれた。
キュルケが、いつものようににっこりと笑って、自分を抱きしめてくれた。
タバサは、自分の心の中が氷が解けたように暖かくなってゆくのを感じた。
そしていつの間にか、“あの人”がやって来ていた。
「お招きにあずかって、ディーキンは本当に光栄に思ってるの」
傍らの、先程まで人形を座らせていた椅子に座って、タバサの顔をじっと見上げている。
タバサははにかんだ笑みを浮かべて、彼から目を逸らした。
抱えていた『イーヴァルディの勇者』の絵本が、手からすべり落ちた。
そして、ささやかなお茶会が始まった。
学院の友人たちが和やかに談笑し、母とペルスランが傍らで見守る。
トーマスが手品を、ディーキンが歌と物語を披露する。
どこまでも優しく、温かい夢が続いていった。
-
(私は、仕えるべき勇者を見つけたのだろうか)
椅子の上に立ち上がるようにしてリュートを鳴らし、勇ましい英雄の物語を語るディーキンの姿を見つめながら、タバサはふとそう思った。
だがそう思ったことは、実のところ、これが初めてではないのかもしれない。
思えばタバサは何度も、彼こそが自分にとっての『イーヴァルディ』なのではないかと、心のどこかで考えていたような気がした。
彼に一方的に戦いを挑み、そして過ちに気が付いた時に。
あの恐ろしいデーモンに追い詰められ、そして救われた時に。
彼が心を病んだ母を笑わせ、そして癒してくれた時に……。
幼い頃のタバサは、何度も夢見た。自分を助けてくれる勇者が、いつか現れないだろうか、と。
タバサは勇者ではなく、勇者に助けられる姫になりたいと願っていた。
自分の手を引いて、幸せながらも退屈な日常から自分を連れ出してくれる勇者をこそ、かつてのタバサは求めていたのだ。
ならば、今の自分も心のどこかで、かつてと同じことを夢想していたのだろうか。
退屈な日常からではなく、過酷な運命から、自分を救い出してくれる勇者を求めていたのだろうか。
そんな勇者の幻想を求めるのではなく、自ら戦わなければならないことを、自分は知った。
自分が『雪風』のタバサになったあの日に、今は亡き一人の狩人の女性が、その事を自分に教えてくれた。
それでも、心のどこかでは、未だにそんな弱い幻想、姫願望を……。
自分をじっと見つめるタバサの視線に気が付いたのか、ディーキンは彼女の方に顔を向けた。
にっこりと笑い返すと、演奏を終えて楽器を置き、とことこと近寄ってくる。
「ねえタバサ、もしかして待ちきれないの?
だったらそろそろ出かけるの!」
拍手をしようとしていたタバサは、まじまじとディーキンを見つめ返す。
「……出かける?」
「そうなの。無限の彼方へ、さあ行くの!」
ディーキンはタバサの手を取って、屋敷の外の方へ向けてくいくいと引っ張った。
「む、無限の彼方……?」
タバサはわけがわからなかったが、所謂“もののたとえ”なのだろう、と判断した。
「その、何を……しに?」
「ンー? そりゃもちろん、タバサが望んでることだよ!」
「私の、望んでいること……」
タバサは少し考えた。
「……、父さまの復讐をしに行く、ということ?」
それを聞いたディーキンは、ぴたりと足を止めると、顔をしかめてふるふると首を横に振った。
「復讐? タバサは英雄なの!
英雄は、ただの復讐なんかには興味ないの!」
「でも、私は」
「デモもストもないの。ディーキンたちは、もっと英雄らしいことをしに行くんだよ!」
「英雄らしいことって……」
タバサは、また考え込んだ。
ふと、先程取り落とした、『イーヴァルディの勇者』のことを思い出す。
-
「……悪い竜を退治する、とか?」
「オオ、それはなかなかいいね。
ンー……、でもディーキンは、竜を退治するより、竜とお話をして仲良くなって、改心させる英雄の方が好きかな」
それから、少し首を傾けて。
「ええと、例えば……。ここにはほら、タバサのお父さんがまだいないじゃない。
お父さんを探して連れ帰りに行くっていうのは、どうかな?
叔父さんを殺すよりは、いいんじゃない?」
タバサはそれを聞いて顔を曇らせると、首を横に振った。
「……それは、無理」
「お母さんは戻ってきたのに?」
「無理」
ディーキンは、また目を閉じてかぶりを振った。
「無理だとか無駄だとか言った言葉は聞き飽きたし、そんなの英雄には関係ないの。
やるか、やらないかなの。無理っていうのはないんだよ!」
タバサは困惑した様子で、まじまじとディーキンの顔を見つめた。
自信に満ちて、きらきらと輝く目……。
「……本当に?」
「輝いた瞳には不可能がないの。
みんながついててくれれば、英雄にはなんだってできるの!」
ディーキンは、タバサの後ろを指差した。
そこには、いつの間にかすっかり出かける準備を整えたキュルケたちの姿があった。
誰の顔にも、疑いのない自信に満ちた、明るい笑顔が浮かんでいる。
それを見ていると、本当に何でもできそうな気がしてきた。
この人と、この温かい人たちと、一緒なら……。
・
・
・
-------------------------------------------------------------------------------
・
・
・
「――――さま。お姉さまってば、居眠りしてらっしゃるの?」
シルフィードの声で、タバサははっと目を覚ました。
体を起こしてきょろきょろと周りを見回すと、そこはオルレアンの屋敷の中庭ではなく、雲海を下に見下ろす遥かな上空だった。
寝惚けた頭が、冷たい夜風で急速に覚醒していく。
「大分お疲れみたい、大丈夫なのね?」
「大丈夫」
心配そうなシルフィードにそう返事をして、気遣いのお礼にぽんぽんと背を撫でてやった。
タバサは屋敷でディーキンたちと一旦別れ、今は一人シルフィードに乗って、トリステインへと帰る途上だった。
作業の手伝いや母の世話等でろくに寝ていなかったため、ついうとうととシルフィードの背で微睡んでいたのだ。
-
シルフィードに母やペルスランなどが乗っているところを見られて疑いを持たれないようにと、念には念を入れて別行動にしたのである。
ディーキンは今、見つからぬよう慎重に他の皆を連れて、トリステインへと戻っているはずだ。
母とペルスラン、そしてトーマスには、ひとまず『魅惑の妖精』亭へ行ってもらうことにしている。
スカロンやジェシカは間違いなく協力してくれるし、絶対に他言したりはしないということは、ディーキンが力強く保証した。
もしかしたら、いずれキュルケなどにも協力を仰いで、また別の場所へ移ってもらうことになるかもしれないが……。
できれば、会いに行きやすいように学院から近い場所の方が、タバサとしても嬉しかった。
あの店なら学院からもそう遠くないし、身を隠すのにも好都合であろう。
自分も早く向こうで母たちと合流して、店のオーナーであるスカロン氏へお願いをして、手配を済ませよう。
それから学院へ戻って、欠席の件を教師たちに謝罪して、ディーキンの『主人』であるルイズにも、謝っておかなくては……。
それにしても、おかしな夢を見たものだ。
タバサは、思わず苦笑した。
(不愉快な夢では、なかったけど)
むしろ、とても温かい気持ちになれる夢だった。
後半は何だかおかしな話の流れになっていたけど、何だかつい、わくわくしてしまった。
姫君として勇者の訪れを待っているよりも、彼と、仲間たちと一緒に冒険をして回る方が、もっと素敵なことかもしれないと思えた。
(そんな日がいつか来てくれたら、いいな……)
タバサは、素直にそう思った。
けれど、いつまでも夢にばかりかまけているわけにもいかない。
タバサは気持ちを切り替えて、今度は母のことを考えた。
今後の安全などについて不安はまだあるけれど、母が元に戻ってくれたことが、まず何よりも嬉しい。
それに、心を壊した母が、最期に絵本を読んだ時に笑顔を見せてくれたことも嬉しかった。
母を癒したのは結局ディーキンだったが、自分も作業の手伝いはできたし、少しは母のために役に立てたと感じた。
(そういえば……)
タバサはそこでふと、母に絵本を読んでいた時に起きた、妙な出来事を思い出した。
タバサはディーキンの助言を考慮して、無理に娘として接するのを止め、母を穏やかな気持ちにする方法はないかと頑張って考えてみた。
いろいろ考えた末に、かつて母がよく読み聞かせてくれた『イーヴァルディの勇者』を読んでみよう、と思いついたのである。
そうして、母が自分にしてくれたように穏やかな調子で本を読み聞かせているうちに、彼女の様子に変化が現れた。
腕の中の人形と自分とを、困惑したように交互に見比べ始めたのだ。
もしかして、人形ではなく自分の方が娘かもしれないと、認識しつつあるのではないか。
そんな期待を抱いたタバサは、思い切って彼女に今一度、「母さま」と呼びかけてみることにした。
じきにディーキンが治療してくれるとはいえ、やはり自分の力で母にできる限りよくしたい、認められたいという思いは強かったのだ。
結果、母は、これまでのように怯えたり喚いたりはしなかったものの、妙な反応をした。
タバサの言葉にしばらくぼうっとした後、ふいに体を震わせて、ぽつりと呟いたのだ。
『……ジョゼット? ジョゼットなの? おお、なんということ……』
そして、手で顔を覆って泣き始めてしまった。
タバサは困惑して、一生懸命なだめてはみたが、泣き疲れて眠るまで手の施しようがなかった。
(ジョゼットとは、一体誰のことなのだろう?)
考えてみても、思い当たる相手はいない。
タバサは、答えの出ない問いに頭を悩ませながらも、トリステインへの帰路を急いだ……。
-
シミュレイクラム
Simulacrum /似姿
系統:幻術(操影); 7レベル呪文
構成要素:音声、動作、物質(雪か氷でできた対象の像と対象の体の一部、似姿のヒット・ダイス(HD)ごとに100gpの価値のあるルビーの粉末)、経験(似姿のHDごとに100XP、ただし最低でも1000XP)
距離:0フィート
持続時間:瞬間
シミュレイクラムはどんなクリーチャーであれ、そのクリーチャーにそっくりな幻を作り出す。
複製されたクリーチャーは半ば実在のものであり、氷と雪から作り出される。
複製はオリジナルとまったく同じように見えるが、この似姿は、本物の持つレベルもしくはHDの半分しか持たない。
そしてそのレベルもしくはHDに対応するヒット・ポイント(hp)、特技、技能ランク、クリーチャーの特殊能力を持つ。
術者は、自分の術者レベルの2倍より高いレベルもしくはHDを持つクリーチャーの似姿を作り出すことはできない。
術者は似姿がどれくらい本物に似ているか決めるため、呪文発動時に<変装>判定を行なわなければならない。
この似姿は常に術者の完全な命令下にあるが、テレパシー的な接続は存在しないので、他の何らかの方法で命令しなければならない。
似姿はそれ以上強力になる能力を持たず、レベルや能力を成長させることはできない。
hpが0になったり破壊されたりすれば、似姿は雪に戻り、即座に融けて無に帰す。減少したhpは、研究室で作業をすれば修復できる。
---------------------------------------------------------------------
今回は以上になります。
またできるだけ早く続きを書いていきますので、次の機会にもどうぞよろしくお願いいたします(御辞儀)
-
乙ですー
-
おつです
>氷と雪から作り出される
これがロマサガのシムラクラムですか
-
みなさんお久しぶりです。あけましておめでとうございます。
いや、今言うのかよ!って感じで申し訳ない。
ここのところ忙しく、これからしばらくも更新が滞りそうです。
そんな中、続きがなんとか完成したので、投下しようかと思います。
22時55分ごろから、よろしければ投下させてください。
-
ラ・ロシェールの町並みが灯りを灯し、人の出入りが静まる夜。
薄暗く狭い空間に、息を潜める気配が二つあった。
その二つの気配は、微動だにせず乱雑に置かれた荷物の物陰に蹲る。
頭上でゴトゴトと、足音が行き来するのが聞こえてきた。
ふと見上げると、そこには木で仕切られた天井がある。足音はその上を移動しているのだ。
しばしの間、呼吸が止まらんばかりに神経を尖らせ、足音の動向を窺う。
すると、やがて遠くへ行ったのか、足音が小さくなって聞こえなくなった。
「いったかい?」
「ああ」
二人の人影が、短く囁きあった。たがいに頷きあうと、二人ははぁ、と小さく息を吐いて喋りだした。
「まったく、こんなコソコソした旅行なんていつ振りかしら?まるで盗賊やり始めた頃みたいだよ」
「んなこと言やあ俺なんて初めてだぜ。こんなコソ泥みてえな真似はよ」
先程の緊張はどこへやら。その二人、長曾我部とフーケは木で仕切られた小部屋に足を投げ出して座り込んでいた。
小部屋は数十メイル四方の広さで、辺り一面にぎっしり中身の詰まった木箱や樽が置かれていた。
カビ臭い臭いとともに、つんと鼻を突く腐った卵のような臭いも漂ってくる。硫黄の香りだった。
ここは一艘の船の船室。アルビオン行きの連絡船に設けられた積荷を置く倉庫、その一つだった。
「はぁ、この船室ったら臭いし狭いし最悪じゃないのさ。これならレコン・キスタとやらに着いて行った方が良かったかしら?」
「あぁん?あの時監獄で助けた俺が悪いってか?」
フーケの言葉に眉をひそめながら、長曾我部が言った。それに対してフーケが笑いながら言う。
「冗談だよ。あんな胡散臭い連中についてたら、そのうち使い捨てられそうだしね。まあニオイは我慢するよ」
私みたいな美人が台無しだけどね、と付け加えるフーケ。そんなフーケを小突きながら長曾我部が笑った。
暗の使い魔 第十九話 『白の国を目指せ』
ラ・ロシェールで追っ手を撒いた長曾我部とフーケは、訳あってこの連絡船に忍び込んでいたのだ。
ことの始まりは三好三人衆から逃げ切った後である。
二人は一刻も早く追っ手を振り切るため、アルビオンへの密航を急いでいた。
そこでフーケは、官兵衛達に捕まる前に利用していた、ある『店』を利用することにした。闇のルートと情報を扱う店である。
その店はこの日、桟橋付近のボロい酒場の一室にあった。
日ごとに場所が変わるため、フーケのように裏の世界を知り尽くした人間でなければ縁のない店である。
フーケと長曾我部は、酔っ払いとならず者であふれたその酒場に足を踏み入れた。
バーにいた何人かの男が、ニヤニヤしながらフーケを見る。美女がこんな場所に訪れるのが珍しいのだろう。
しかしすぐ隣の碇槍を担いだ長曾我部に睨まれると、男達は慌てて視線をそらした。
「いつ来ても小汚い酒場だねぇ」
「そうかい?活気があっていいじゃねえか」
店内を見回しながら、長曾我部は薄く笑みを浮かべた。
二人は人目を避けるように酒場を抜け、二階のある小部屋に入る。
すると小汚いフードで顔を隠した痩せぎすの男が二人を迎えた。情報屋だ。
フーケはまずアルビオンへの船の密航船の有無、それと白い仮面の貴族について尋ねた。
懐の袋からエキュー金貨を、多めに取り出し情報屋に握らせる。
「まいど」
情報屋の男はこすずるい笑みを浮かべると、白仮面の目撃情報と船の状況を話し出した。
それによると、アルビオンの内乱のせいで、密航の為の船は現在手配できる状況ではないらしい。
そして白仮面は桟橋付近で出入りしており、何者かを探すそぶりをしているとの事だった。
さらに詳しい情報を、上乗せした金で得たフーケは表情を曇らせる。
「お手上げかい?あの仮面に見つからずにアルビオンへ渡りたいんだけどね」
アルビオンへ渡るには定期船に乗るしかない。しかし、どこで仮面が目を光らせているか分からない。
堂々と定期船に乗れば、即座に見つかり狭い船内で命を狙われることになるだろう。
「あの仮面をのしちまえばいいじゃねえか」
「バカだね、相手は組織だよ?アイツをどうにかした所で次の追っ手がやってくるだけじゃないのさ!」
それに今この港町にいる追っ手は、あの得体の知れない三人もいるのだ。
長曾我部の強引な意見に呆れてため息も出ないフーケ。彼女が腰に手をやり考える。その時だった。
「そんなあんたらのためにいい情報があるぜ?」
悩む二人を見て、情報屋の男が笑みを浮かべだした。フーケが情報屋に顔を寄せる。
「なんだって?」
「その仮面の旦那に見つからないで、船に乗り込める手段があるんだって」
-
それを聞いて、長曾我部とフーケは顔を見合わせた。情報屋が黄ばんでボロボロの歯を覗かせる。
「ただしちょいと値が張るぜい?なにせ、『仲介料』も含まれてるんでね」
「へぇ?」
フーケが興味を示したようにテーブルに身を乗り出した。その懐から、袋一杯の金貨を取り出しながら。
「でだい!あんだけ払っておいてなんだこの方法は!あの情報屋ッ、いつも以上に足元見やがって!」
「まあいいじゃねえか。これで何とか向こうに着くんだろう?」
隣でキリキリするフーケを嗜める長曾我部。
フーケ達は、情報屋と繋がりがある一人の船員の元へ案内された。
四十半ばで濃いひげの、大柄の男が二人を迎える。二人は、桟橋から遠く離れた、積荷を保管する倉庫へ案内された。
そこにはいくらかの積荷が保管されており、船員はそれらすべてをアルビオン行きの連絡船に積み込む監督だという。
そしてその船員の監督する船が、丁度あさって出港する予定だったのだ。
用意された空き樽に乗り込む二人。なにやらかび臭いニオイがしたが、背に腹は変えられない。
すでに情報屋から金を受け取っていた船員は、その樽に蓋をして確認済みの旨を告げる札を張ると、他の積荷と一緒に船へと運び入れた。
そうして二人は、泥臭いながらも密やかに船に乗り込むことに成功したわけである。
「おいフーケよ」
「なんだい?」
狭い船室の中、足を投げ出したままの姿勢で座り込んだ長曾我部が、不意に呟く。それをフーケが顔を見ずに聞き返した。
「この船。こいつァ空飛ぶってのは本当かい?」
「しつこいね、またその話かい?そりゃそうだよ、アルビオンへは飛ばないと行けないからね」
フーケが、何を当然な事をといわんばかりの表情で彼をみやる。
「空飛ぶ船、ね。まあそのアルビオンとやらが『空』にあるのはいいとしてよ、こいつは一体どんな原理で飛んでんだ?」
まさか、落っこちたりしねえよな?と落ち着かない様子で言う男に、フーケは呆れながら言った。
「なんだいアンタ、そんな事も知らないのかい?『風石』を使ってるんだよ。そいつがある限り落ちるわけないじゃないのさ」
『風石』すなわち風の力のこめられた魔法石だ。それが船底にいくつも取り付き、風を吹かして船を浮かしている。
ハルケギニアの人間であれば、知らぬものなどいない常識だ。
それを一から説明しなければならない事に、彼女はうんざりした。
「全く、どこの未開の地から来たんだか。アンタ本当にハルケギニアの人間かい?」
それを聞いて、長曾我部が思わず声を荒げる。
「だぁからよ!日ノ本の四国から来たって何度いわせりゃあわかりやがる!俺はこの訳わかんねえ田舎の――」
その時、フーケははっとした顔でその口を塞いだ。
口元を手で押さえられ、元親も思わず押し黙る。頭上を乾いた足音が通り過ぎていくのが聞こえた。
足音が遠くへと行く。
それを確認したフーケは、押さえていた手をどけながら、長曾我部を睨みつけた。
だがそんな視線を意に介さず、長曾我部は手を広げて悪びれもせずに言う。
「コソコソすんのは俺の性に合わねえってんだ」
フーケの細い手が元親の頭をはたく。スパン!といい音が鳴った。
フーケは切なげな気持ちになって虚空を見つめる。そしてため息をつくと、チラリと長曾我部を見た。
長く通った鼻筋に、強い意志を思わせる瞳。
顔半分を覆う紫の眼帯に目をつぶれば、中々の男前である。
顔はいいんだけどねぇ、とぼんやり考える。
しかし、その分熱血で大雑把なのが長曾我部である。彼ほど隠密に向かない男はいないだろう。
正直、この船に乗り込むまでに何度騒ぎを起こしそうになったことか。
衛士やレコンキスタの刺客に狙われるたびにフーケは思うのだった。
なんでアタシこんな奴と一緒に脱獄したんだろう、と。
成り行きもあった。しかしフーケはなによりも、チェルノボーグで見せた、この男の得体の知れない力に興味があったのだ。
-
一瞬で石壁を吹き飛ばし、焼き尽くしてみせた男の槍技。
こいつと共に居れば、少なくとも並みの追っ手には遅れを取るまい。自分も安全に行動できようものだ。
それに牢屋でのこの男の口ぶり。どうにもあの天海や黒田官兵衛を知っているようだった。
もしかしたら、あの天海とやらに『礼』をする機会にめぐり合えるかもしれない。
そう考えると、まあ一緒に行動するしかないか、と彼女は諦観せざるを得なかった。
再び深いため息をつくフーケ。それを見て声をかける長曾我部。
「どうした?なんか気に病む事でもあんのかい?」
「誰のせいだと思ってんだい」
正直もう一発はたいてやりたい気分になったフーケだが、思いとどまる。
下手に騒いで見つかったらことだ。船が出港するまでの時間もある。
彼女は、座ったままの姿勢で静かに目を閉じた。
朝の出航まで睡眠をとるつもりなのだ。
隣でなにやら物思いにふける長曾我部を背に、寝転がる。と、その時だった。
ガクン!と一瞬、謎の浮遊感が二人を襲った。
「な、なんだ一体?」
いきなり落ちるような感覚を味わった長曾我部があわてて言う。フーケも身を起こし周囲を見回す。
部屋全体が、いや船そのものが揺れ動いている。そしていつのまにか、部屋の外が掛け声と足音で騒がしくなっている。
一体どうしたことか、と長曾我部は立ち上がった。
「おいおい!まさか、落ちる予兆だってんじゃあ――」
「バカだね。そんなんじゃないよこれは」
フーケが彼の服をつかんでそれを制す。彼女は落ち着いた様子で言った。
「どうやら、出航したみたいだね」
船の動きにより、身体がよろめく。長曾我部はドスンと座り込むと、落ち着き無く辺りを見回しながら言った。
「出航?随分早いじゃねえか、まだ真夜中だろ」
「そうだね、あの船員の話じゃあ出るのは朝方のはずだけど……」
二人は首をかしげながら、かなり早い船の出航を怪しんだ。
「怪しいね……。ちょっと待ってな」
フーケは立ち上がると、倉庫の出口に近づく。その急な行動にオイ、と呼び止める長曾我部。
しかし彼女は、扉の向こうに人の気配が無い事を確認すると、静かに倉庫を出た。
長く続く通路に、甲板へと続く階段が見える。船員は航行の為、ほとんどが甲板に出ているようだ。
彼女は猫のように素早く、気配を隠して階段に駆け寄る。そして階段の裏側に回ると、息を殺して階上の様子を窺いはじめた。
「アルビオンにはいつ着く?」
「明日の昼過ぎにはスカボローの港に到着しまさあ」
ワルドと船長が会話をする。それをよそに、官兵衛は船の舷側から遠ざかるラ・ロシェールの灯りを見下ろしていた。
隣にはルイズがいる。彼女は落ち着いてはいるが、どこか不安な様子を隠せずにそこにいた。
おそらく桟橋に残してきたキュルケらが心配なのだろう。
官兵衛達はあの後無事船に乗り込み、船長との交渉の末に船を出航させた。
出航してそれほど時間は経っていないが、ラ・ロシェールはすでに雲の遥か下だ。追っ手の心配はないだろう。
しかしキュルケ達が無事かどうかはわからない。
ルイズは唇を固く結んでいたが、しばらくすると官兵衛に話しかけた。
「カンベエ……」
「何だ?」
ルイズのおずおずとした声に、官兵衛はゆっくりと首を向けた。
しかし、官兵衛の視線に、ルイズは言葉を途切れさせた。
何を話したらいいだろうか?任務の事か、仲間の心配か、それとも――
そこまで考え、ルイズは官兵衛に言わなければならない事を思い出した。
謝るべき事があった。あの時、宿屋で怒りをぶつけた事を。気を遣ってくれた官兵衛に怒鳴り散らした事を。
意を決したように彼を見上げる。
ひとまず危機が去った今だからこそ、言わなければならない。
しかし、ルイズがその気持ちを言葉にしようとした、その時。
-
「二人ともいいかな?」
不意にワルドが話しかけてきた。官兵衛がワルドの方を向く。
「船長の話では、ニューカッスル付近に陣を配置した王軍は、攻囲されて苦戦中のようだ」
「成程な。お目当ての皇太子は?」
「わからぬ、生きてはいるようだが……」
官兵衛とワルドが会話を始める。二人とも、宿でのいざこざとは無縁のように話を続けていた。
ルイズは仕方なく二人の会話に入る。
会話は、スカボロー港に着いてからどう動くか。敵の動向にどう注意するか。ウェールズ皇太子との交渉をどうするか、といった内容だった。
一通りの打ち合わせが終わると、官兵衛は手ごろな場所に座り込み、目を瞑る。
やがて間を置かずに、官兵衛は寝息を立て始めた。
「ちょっと……」
ルイズは慌てて話しかけようとした。会話が終わるなり、彼に宿での事を詫びようと思っていたからだ。
ゆすり動かそうと彼の目前に座り込むルイズ。しかし彼女のそんな行動は、目前で無防備に眠る彼の様子に遮られた。
思えば彼もここに来るまでに、かなりの襲撃を掻い潜ってきた。ひどく疲れていたのだろう。
そんな自分の使い魔の安息を遮る事はできない。
「カンベエ……」
ルイズは彼を起こさないよう、ゆっくりとその隣に座る。
真横から彼の寝顔を覗き込みながら、彼女はじっと考えた。
あの宿で、官兵衛に言った事。自分がしてしまった過ちを。
官兵衛からしたら訳のわからない癇癪であっただろう。
ワルドとの確執を問いただされ、それを詫びたと思えばあの騒ぎだったのだから。
『あんたみたいなのが居るせいで私は結婚に踏み切れないんだわっ!』
なんてひどい言い様だろう。自分を守ってくれ、今回の旅にも何も言わず着いてきてくれた使い魔に対して。
「(貴族、いいえ人として恥ずべき事だわ)」
しかし彼は、そんな自分にも関わらず、追っ手相手に戦ってくれた。こんな我侭な娘に命を張ってくれたのだ。
そう思うと、彼女は胸が詰まるような気持ちだった。
ルイズは、すっかり寝入った官兵衛の横顔を見つめながら呟く。ポツリと。
「ありがとう」
大空を疾走する船の上。その言葉は吹き荒れる風にさらわれた。
この場の誰にも聞こえないだろう、微かな言葉。
だが今はこれで十分、というよりこれが精一杯。
いつか、そう遠くないうちに伝えよう。この言葉を、気持ちを。
甲板にはいつの間に乗り込んだのか、ワルドのグリフォンが大人しく鎮座しており、二人のそんな様子を見つめていた。
翌朝、官兵衛は甲板の隅に寝転がり、船上を吹き荒れる風に肌をなでられていた。
「アルビオンが見えたぞーっ!!」
その掛け声に目を覚ました官兵衛は、眠い目を擦りながら辺りを見回した。
船の外には、真っ白い雲海が広がっている。青空と強い風が、肌寒さを感じさせる。
すっかり夜は明けており、爽やかな朝の空気を胸に吸い込んだ。
「アルビオン?とうとう着いたのか?」
官兵衛は伸びをしながら、何気なく空を見上げる。そして、その方向に浮かんだ巨大なソレを見て、言葉を失った。
「な、何だ、ありゃあ……!」
頭にかかっていたもやが跡形も無く吹き飛ぶ。ポカンと口が空いて閉まらない。
彼にとって目の前の光景は、それ程までの衝撃だった。
それは、雲の合間にのぞく巨大な陸地。
雲海に巨大な影を落とし、空を旅する大陸そのものだった。
「あれが――」
「そう、あれが浮遊大陸・アルビオンよ」
いつの間にか隣に立つルイズが、官兵衛を見上げて言った。
「どう?驚いたでしょ」
「ああ。こんな光景が存在するとはな……」
巨大という表現が陳腐に聞こえるほど、それは圧倒的な存在感を示していた。
黒々とした岩肌、その上には山脈が連なり、大陸の端から滝が流れ落ちる。
滝の上には大河が流れるのだろう。
ルイズの話では、大河から流れ落ちる滝が霧を作り、大陸の下半分を覆うのだそうだ。
その雄大な様からついた呼び名が『白の国』
白の国を覆う霧は、恵みの雨となってハルケギニアに恩恵をもたらすらしい。
-
呆然としていた表情が、見る見るうちに感動で塗り替えられる。
日ノ本ではまず見られない神秘の光景に、彼はしばらくの間見惚れていた。
官兵衛が感動に打ちひしがれていたその時、鐘楼に上った船員が大声をあげた。
「右舷上方の雲中より船が接近!」
官兵衛とルイズは急いでその方向を見やる。なるほど、そこには確かに一艘の船があった。
こちらより二倍も大きい、重厚な船である。それが真っ直ぐにこちらに向かってくるのが見えた。
「いやだわ、アルビオンの貴族派かしら?」
ルイズが不安そうに船を見上げた。
船長がすぐさま船員に指示を飛ばす。
あれがアルビオンの貴族派なら話は簡単だ。この船は貴族派のために積荷を運び、商売しているのだから。
しかし船員が手を振っても、相手から返答が無い。船長が妙に思っていると、船員が青ざめた顔で言った。
「あの船は旗を掲げていません!空賊です!」
船長の顔も蒼白になる。
「なんだと!このタイミングで!」
「間違いありません!内乱に乗じて活動が活発になってると聞きます!」
船長は急ぎ全体に指示を飛ばす。取り舵いっぱい、空賊船から逃げ切れ!と。しかし遅かった。
いかづちのような轟音を立てて、一発の砲弾が交易船を掠めた。黒金の弾が、ぶおん!と風を切り、目前の雲を突き抜ける。
雲を吹き飛ばした大砲の威力に、船全体が緊張した空気に包まれた。そして。
「う、うああ……」
船長はうめき声をあげる。
自分らの目と鼻の先。そこにはいつの間にか、無数の砲口がこちらを睨んでいたからだ。
こちらの船がうろたえる間。漆黒の空賊船は、恐るべき速度で接近していた。
敵船から四色の旗が上がる。停船命令だ。
「船長!どうしましょう!?」
「ぐう……」
額を手で押さえながら、船長は決断をせまられた。
武装が無い訳ではなかった。しかし相手は方弦二十門の大砲が並ぶ軍艦。
真横につかれ、いつでも貴様らを粉々にしてやる、とも言うほど相手は攻撃手段を構えている。
逃げることも、抵抗することも不可能。
船長は、隣で船を操作しているワルドに視線を送る。
いや、もしかしたら、このスクウェアクラスの貴族様ならば無数の大砲などものともしないのでは?
彼こそが、この状況を切り抜ける唯一の突破口では?
船長は子犬のようにワルドを見つめた。しかし、帰ってきたのは非情な答えだった。
「僕はこの船を浮かすので手一杯さ。あきらめたまえ。」
首を振るワルドに船長は絶望する。
そして船長は、船員に停船を指示すると、小さく諦めた口調で「これで破産だ」と呟いた。
こちらの船が停止して黒船がピタリと張り付いてから、船が制圧されるのに時間は掛からなかった。
銃や弓を構えた賊がこちらに狙いを定める。鉤つきのロープがこちらに投げられ、それを伝って男達が続々と乗り込んできた。
ルイズが怯えた様子で官兵衛の影に隠れる。
しかし官兵衛はというと、船が賊の襲撃にあったのが自分の不運のせいだと思い、申し訳なさそうに頭を抱えていた。
全部で数十人程の男達が、交易船を踏み荒らす。次々と船員が捕まり、やがて船長が連れてこられた。
賊の中から一際派手な格好の男が進み出て、船長の前に立つ。どうやらこの男が、空賊の頭らしい。
「おめえが船長かい」
「そうだが……」
交易船の船長をじろりと眺めながら、賊の頭は尋ねる。
「船の名前と積荷は?」
「トリステインのマリー・ガラント号。積荷は硫黄だ」
頭はそれを聞いて笑った。賊達もニヤニヤと薄気味悪く笑みを浮かべる。
「よし、船ごと全部買った。料金はてめえらの命だ」
頭は愉快そうに大笑いすると、今度はルイズとワルド、そして官兵衛の一行に向き合った。
「よう、貴族のお客とは珍しい。奴隷まで引き連れて物見遊山かい?」
「だれが奴隷じゃ」
官兵衛はそっと呟いた。ルイズの顎を持ち上げながら、頭は言う。
「おめえ中々別嬪だな。俺達の船で使ってやってもいいぜ?」
下卑た笑みを浮かべる賊達。しかしルイズはその手をぴしゃりと跳ね除けると頭を睨みつけた。
頭は笑みを崩さず言う。
「中々いい度胸じゃねえか、だがそれもいつまでもつかねえ?」
頭は背を向けると、賊に命じてルイズ達を連行させた。
「こいつらは大事な人質だ。身代金がたんまりもらえるだろうさ」
-
ルイズ達は、黒船の一船室に放り込まれた。ワルドとルイズは杖を、官兵衛はデルフリンガーを取り上げられている。
官兵衛はともかく、ルイズとワルドはもうそれだけで手も足も出ない。杖を取り上げられたメイジは無力なのであった。
「はぁ、ここに来てツキに見放されたか……」
官兵衛は鉄球に座り込んで、俯いていた。もうじき目的地に到着だというのになんという事か、と。
見るとワルドは興味深げに置かれた積荷を物色。ルイズは床にうずくまって膝を抱えていた。
よほど恐ろしいのか、時折肩を震わせているルイズ。
それはそうだろう。慣れない船旅に、度重なる襲撃、そして挙句空賊のお出ましと来たものだ。
歳若い娘にはとんでもない苦痛に違いない。
「おいご主人」
官兵衛はルイズの隣に移動すると、静かに座り込んだ。ルイズが顔を上げる。
官兵衛が前を向いたままで喋りだした。
「ま、あれだ。こうなった以上なるようになるしかない。小生が言っても説得力は無いが、天運を信じるこったな。
それに小生はともかく、人質のお前さんらは下手な真似はされんだろう。貴族様なわけだからな」
「カンベエ……」
膝を抱えていたルイズがそんな官兵衛を見た。
「だからしゃんとしろ。重要な任務を背負ってるお前さんが震えてちゃあ、締まらないだろうが」
その言葉に、ルイズの瞳に強い光が宿る。
そうだ、官兵衛の言うとおりしっかりと気を持たなければ。
これは姫様直々の依頼、そして祖国の命運を握っているのだ。
ルイズはグッと唇を噛むと、顔を上げた。
その時船室の扉が開かれ、一人の男が現れた。
「おい、おまえらに聞きてえ事がある」
やせぎすの男が、三人を見回しながら質問する。
「おまえら、もしかしてアルビオンの貴族派かい?」
ルイズとワルドは答えない。官兵衛も、相手の質問の意図が見えないうちは、口を閉ざした。
そんな三人の様子を見て、男は続ける。
「おいおいだんまりじゃあわかんねえよ。だが、もしそうだったんなら悪かったな。俺らは貴族派と対等に商売させてもらってる立場でよ。王党派に与する輩を捕まえる密命を帯びてるのさ」
「なんですって?」
ルイズが思わず聞き返す。
「どうなんだい?おまえらは貴族派かい?もしそうだってんなら港まで送ってやるぜ」
やせぎすの男はじっと三人を見据えた。しばしの間が空く。
どう出るべきか、と官兵衛は思考をめぐらす。
ここで貴族派と答えれば、たやすく港へと着け、さらには連中の襲撃を免れる隠れ蓑になりうるかもしれない。
逆に王党派と答えれば、自分らの命運は尽きる。捕らえられた人質のまま、悪くて命を奪われかねない。
いずれにせよ任務など遂行出来なくなる。ここは賢く、立場を偽るのが正解だろう。しかしルイズは。
「バカ言わないで!私達は王党派の使いよ!だれが薄汚い反乱軍なものですか!」
彼女は男を睨みつけると、正々堂々と言い放った。
「アルビオン王室はまだ負けてないわ!だから正当な王室は王党派よ!私達はそこに大使として赴くの!だからそれ相応の待遇を要求するわ!」
「おいおい!」
官兵衛はルイズの肩をたたいて言った。
「正直すぎるぞ!」
官兵衛が声を荒げる。しかしルイズは官兵衛を睨みつけると言った。
「こいつらに嘘ついて生き延びるくらいなら、死んだほうがマシよ!」
官兵衛は深くため息をついた。
-
一通り話を聞いた賊の男は、そんな二人の様子を見て笑った。
「正直は美徳だが、お前らタダじゃあすまないぞ?頭に報告してくる。それまでゆっくり考えるんだな」
バタンと扉が閉められた。あとに残った三人は、静かになった空気の中、立ちすくんだ。
「おいご主人。ひとつ聞くが、お前さんの答えで小生らが破滅するかもしれない。あれはそういう覚悟の上での言葉か?」
「当然よ!」
毅然としてルイズが言う。
「私は貴族よ!誇りと引き換えに生きながらえるなら、喜んで死を選ぶわ!」
「それで小生や婚約者が死んでも、か?」
「……そうよ」
それを聞いて、ルイズは一瞬黙ったが、やがて強く頷いた。
「それに私は諦めないわ。地面に叩きつけられる瞬間まで、ロープが伸びると信じるわ。あんたもワルドも死なせない、そう信じて!」
「そうかい……」
官兵衛はそれだけ言うと、ドカンとその場に座り込んだ。その顔に表情は無く、何かを考え込んでいるようであった。
「いいぞルイズ、流石は僕の花嫁だ」
ワルドはルイズの肩を叩いて言った。
その言葉に、ルイズは複雑な思いを抱きながら、顔をしかめた。
やがてしばらくすると、扉を開けて先程の男が現れる。
「頭がお呼びだ」
三人は言われるがままに導かれて、船室を出た。
「……状況はどうだい?」
「ああ、まだここはバレちゃいないよ」
硫黄の香りが立ち込める船室内で、二人の男女が囁き合った。
商船が空賊に占拠されてから、何時間が過ぎただろうか。
フーケはその手に杖を、長曾我部は碇槍を担ぎながら、占拠された『外』の様子を窺っていた。
「しかし、こんな状況で賊船に出会うとは。とことんついてないね」
フーケが肩をすくめながら言う。
せっかくレコンキスタの追っ手から逃れ、快適とはいかないがわずかな空の旅を楽しんでいる所。
そうしたら今度は空賊の襲来ときたものだ。
まったく、あの学院で捕まってからろくな事がないではないか。
どこかで厄でもうつっただろうか。そんな事をボヤキながら、フーケは長曾我部に向き直った。
「これからどうするんだい?」
今は見つかっていないとはいえ、この狭い船の上じゃあ見つかるのは時間の問題である。
早いうちに手を打たないと面倒だ。
「なあ、どうするんだって!」
フーケが語調を強めた。
しかし長曾我部は、それに対してなんの反応も返さなかった。
フーケが妙に思い、彼の肩を叩く。
「ちょいとアンタ、なんだい渋い顔して。腹でも痛いの?」
「ち、違げえ!ちょいと気になることがあってよ」
慌てて顔を上げた長曾我部の言葉に、フーケも繰り返した。
「気になること?」
「ああそうさ」
長曾我部はふう、と息を吐くと、後ろに詰まれた積荷にどすんと腰掛けた。
「アイツら……あの空賊ってやつらだがよ、どうにも妙だ」
「妙?」
フーケが首をかしげる。妙、どこかおかしなところがあるだろうか?
この戦時中、空賊が船を襲うのは日常茶飯事だ。先程聞こえたが、貴族の連中らしき一行も人質にとらわれたらしい。
金目当ての賊らしい手段だ。別段おかしいところは無い。
「別に普通じゃないかい?あの連中の何が気になるってのさ」
「仕草よ」
フーケの言葉に、長曾我部が即座に答えた。
-
「仕草?」
フーケもそれを繰り返した。
「俺はこっちに来てまだ日も浅ぇ。よくわからねえ常識も多い」
やや間をおきながら、長曾我部はゆっくりと語る。
「だが俺だって長年海賊の長やってきた身だ。一目見りゃあそいつらがカタギなのかそうでないのかくらい良くわかる」
その瞳に一つの確信を抱きながら。
「でだ!」
語調を強め、くいと顔を上げる。
「あいつら、賊にしちゃあ変だぜ。まるで全員新米みたいだ」
長曾我部は、迷い無くその言葉を発した。
「ほう?」
「どう思うよ、フーケさんよ?」
長曾我部の言葉にフーケはややあっけにとらわれていた様だが、彼女も即座に思考を巡らす。
しばしの黙考。それと同時に、長年盗賊に身をやつしてきた彼女自身の勘が、頭を抜ける。
「なるほど、ねえ……」
突如空に現れた、賊徒ども。しかしそれが上っ面の皮で覆われてるとしたら。
その理由は?正体は?
ここまでで、彼女は一つの可能性に辿り着く。そして。
「もしかしたら、面白いものが見れるかもねぇ」
「どういうことだ?」
フーケの眼が、猛禽類のごとく釣りあがった。
「いいかい?これからアタシが言うように動くんだ。そうしたら活路が開けるかもしれないよ?」
フーケは長曾我部と顔を合わせると、ニヤリと唇の端を傾けて見せた。
ルイズ、官兵衛、ワルドは、豪華なディナーテーブルが備えられた、広い船室に案内された。
扉を開き中に入る。すると十数人の空賊が突っ立った中心に、甲板で見た派手な格好の頭が座っていた。
どうやらメイジらしく、水晶のついた杖を片手にじっとこちらを見据えている。
「頭の前だ、挨拶しな」
痩せぎすの男に小突かれるも、ルイズは敵意をあらわに頭を睨みつける。それを見て、頭は歯を覗かせて笑った。
「ガキだが、気の強い女だな。悪くねえ。さてと、名乗りな」
頭がルイズに促す。しかし彼女はそれを無視して言う。
「大使としての扱いを要求するわ!でなければあんた達なんかと、一言だって口をきくもんですか」
そういうと、室内にいた全員が笑った。頭が言う。
「王党派と言ったな?奴らに何の用だ。あいつらは明日にも消えちまうぜ?」
「あんたに言うことじゃないわ」
ルイズは毅然とした態度を崩さない。頭はさらに続ける。
「貴族派につく気はないかね?あいつらはメイジを欲しがってる。礼金をたんまりもらえるぜ?」
「死んでも嫌よ」
ルイズの手が小刻みに震える。堂々としたように見えて、彼女は怯えていた。
これから起こる事の恐怖に。自分らが死ぬかもしれないという想像に。
しかしルイズは前を向いて、頭を睨みつける。決して怯えの表情を表に出さない。
官兵衛は、隣でそんな彼女の態度を見ていた。全く、小娘が無理しやがって、と。
そして、そろそろいいか、と官兵衛はルイズを押しのけた。
「カンベエ?」
「そろそろ茶番は終いにしないか?」
官兵衛が気だるげに言う。その言葉に、頭の目の色が明らかに変わった。
「なんだと?」
頭が驚いた様子で言う。官兵衛が続ける。
「考えてみりゃあ不自然だった。貴族派と対等な空賊が、貴族派のための商船をわざわざ襲い、人質を取るなんざな。それに――」
周りの空賊も、なにやら落ち着きがなくなっている。
「お前さんらは、小生の知る賊とは随分違う。動作の端々に規則正しさが見受けられる。
本物はもっと粗雑で、統率も取れてない」
ルイズもその言葉に呆気にとられる。
-
「つまりはお前さんらは、貴族派でも空賊でもないってこった。正体は、小生が言うよりお前さんらからバラした方が、格好がつくんじゃないか?」
そういうと、官兵衛はニッと笑った。
それに呼応するかのように、頭も杖をおさめ歯を覗かせる。
「ハハハ!まいったな。まさかこうも容易く見破られようとは!」
頭が大声で笑い出す。心底愉快そうに、口を空けて。
ルイズはまだ思考がついていかないらしく、頭の豹変に首をかしげている。
「失礼、貴族に名乗らせるならばこちらから名乗らなければな」
その言葉に、周囲の賊が一斉に直立する。まるで軍隊のように。
頭は黒髪を剥ぐ。付け髭をはがし、眼帯を取り払う。するとその変装の下から、凛々しい金髪の青年が姿を現した。
「私はアルビオン王立空軍大将、本国艦隊司令長官……、といってもすでにこのイーグル号しか存在しない無力な艦隊だがね。
それよりはこちらのほうが通りがいいだろう」
そういうと青年は、威風堂々と名乗った。
「アルビオン王国皇太子、ウェールズ・テューダーだ」
ルイズは驚き目を見開いた。ワルドもほうと興味深げに皇太子を見つめる。
官兵衛は、自分の推測が当たっていた事がわかり、薄く笑みを浮かべた。
ウェールズはにっこりと魅力的な笑みを浮かべると、ルイズらを席に招いた。
ウェールズ達が空賊を装っていた理由、それは貴族派の補給路を断つためだった。
貴族派に気取られぬよう変装し、空賊になりすましていたのだ。
そして、ルイズらを試したのは、まさか国外に王党派の味方がいるとは思っていなかったかららしい。
その為、ああまでして自分らを見極めようとしたのだ。
ウェールズにそんな事情を一通り説明されても、ルイズはポカンとしているだけであった。
いきなり目的である皇太子に出会った為、心の準備が出来てなかったのだ。
「アンリエッタ姫殿下より密書をことずかって参りました」
ワルドが進み出て、優雅に頭を下げる。
「ふむ姫殿下からとな?きみは?」
「トリステイン王国魔法衛士隊、グリフォン隊隊長、ワルド子爵。そして――」
ワルドが一礼すると、ルイズと官兵衛を皇太子に紹介する。
そして一通りの挨拶の後、ルイズは懐から密書を取り出した。
ウェールズが受け取ろうと歩み寄るが、ルイズはおずおずと皇太子に尋ねる。
「あの、本当に本物の皇太子様?」
ルイズの言葉に笑いながらウェールズは言う。
「僕は正真正銘、ウェールズだよ。なんなら証拠をお見せしよう」
そう言うとウェールズは、自分の薬指に嵌っていた指輪を外し、ルイズに手に光る水のルビーに近づけた。
すると、ふたつの指輪の宝石が共鳴し、虹色の光を振りまいた。
「その指輪はアンリエッタの水のルビー。そして僕の指輪はアルビオン王家に伝わる風のルビーだ。
水と風は虹を作る。王家の間にかかる虹さ」
「大変失礼をばいたしました」
ルイズは慌てて頭を下げ、手紙を差し出した。
ウェールズは愛しそうに手紙を見つめると、花押に接吻した。
そして封から手紙を取り出すと、真剣な表情でそれを読み出した。
「姫は結婚するのか?あの愛らしいアンリエッタが。私の可愛い……、従姉妹は」
ワルドが無言で肯定の意を示す。ウェールズは最後の一文まで手紙に目を通すと、微笑んだ。
「了解した。姫は、あの手紙を返して欲しいとこの私に告げている。なにより大事な姫から貰った手紙だが、姫が望むならそうしよう。」
ルイズの顔が輝いた。
「しかしながらあの手紙は手元には無い。ニューカッスルの城にあるのだ。少々面倒だが、ニューカッスルまでご足労願いたい」
ウェールズはそう言うと、乗組員に指示を飛ばした。空賊の変装を取っ払った乗組員は、きびきびとした動きで部屋を出ようとした。その時だった。
-
「そいつは困るぜ!!」
どおん!と、突如轟音とともに船室の扉が吹き飛んだ。
「何だ!?何事だ!!」
「殿下をお守りしろ!」
船員が即座にウェールズを囲む。
ルイズはいきなりの出来事に顔を覆った。ワルドは素早く身を翻し、弾け飛んだ扉の破片から身を守る。
そして官兵衛は。
「お、おいおい。冗談だろ?」
目の前に現れた人物を、口をあんぐり空けて見ていた。
吹き飛んだ扉と、その跡に燃え盛る炎が辺りに煙を撒き散らす。火を消せ!と怒号を飛ばす船員。
それに目もくれず、その男は煙の中から姿を現した。
紫の上着をたなびかせ、肩に担いだ巨大な槍を光らせたその男は、ウェールズを見据えた。
「急ぎのところわりぃがよ、この船は俺達が貰うぜ」
槍をぶん回し、風で煙を払う。その男の姿を見て、官兵衛は声を荒げた。
「なんでお前さんがここにいる!西海!」
官兵衛の目の前には、四国・鬼ヶ島の鬼とうたわれた武将、長曾我部元親が立ちはだかっていた。
今回は以上になります。
遅くなりましたが、本年もよろしくお願いします。それでは。
-
乙です
-
ウルゼロの人乙
デルフにも出番があるのがうれしい
あと両手が剣の怪獣ときたらまずバギラを思い浮かべるのは俺だけじゃないはず
-
こんばんは、焼き鮭です。今回の投下をします。
開始は22:07からで。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第八十一話「ウルトラマン高校生」
月の輪怪獣クレッセント 登場
「……サイトさん、サイトさん」
「う〜ん……」
「サイトさん、起きて下さい。もう朝ですよ」
……シエスタの呼ぶ声で、俺は目を覚ました。
うっすらと開けた目に飛び込む景色は、俺の部屋のもの。
……え? 俺の部屋?
「おはようございます、サイトさん」
寝転がっている俺の顔を上から覗いているのは、声の主のシエスタ。
「お、おはよう、シエスタ。……っていうか、どうしてシエスタが俺の部屋に?」
俺が尋ねかけると、シエスタは呆れたように返答した。
「もう、毎朝、起こしに来てるじゃないですか。じゃないとサイトさん、いつも遅刻するんですから」
「毎朝? えーと……いつから?」
「いつからって、いつの間にか……ですよ? えーと中学校の時にはもう習慣になってましたね」
「中学校?」
ちょっと待て。俺、シエスタとそんなに長いつき合いだったっけ? それに……シエスタの
格好はどういうことだ?
「シエスタ……。何で俺の学校の制服なんて着てるの?」
そう、シエスタは俺の学校のブレザー姿なのだ。いつものメイド服はどこ行ったんだ?
「何でって、これから学校に行くんだから、制服を着ているのは当たり前でしょう?」
え? シエスタが、俺の学校に……? シエスタの職業はメイドじゃあ……。
あれ……でも、言われてみれば、シエスタが俺の学校の生徒というのも、違和感がないような
気がしてきた……。うーん……。
「おかしなサイトさん。もしかして、悪い夢でも見たんですか?」
首をひねる俺に、シエスタはクスッと笑ってそう聞いた。
「悪い夢っていうか……俺、剣と魔法の異世界に召喚されたはずなんだけど……」
と言うと、シエスタにますます笑われた。
「それが夢じゃなきゃ、何なんですか? サイトさんが異世界に召喚されるなんて、現実に
ある訳ないじゃないですか」
「い、いや、でも……」
戸惑う俺。あんなにはっきりと現実感があるのが夢だなんて……。特に、俺を召喚した
あのピンク髪のかわいい……。
……あれ? 何て名前だったっけ……。全然思い出せない……。
……いや、思い出せないんだったら現実じゃあないよな。あれは長い長い夢だったんだ!
うん、ここが現実! そうに決まってるじゃないか! 俺の部屋が現実じゃないなんてことが
ある訳ないよ!
「い、いや、ごめん。変な夢見たから混乱してたみたいだ」
「ふふ、ならよかった」
シエスタの笑顔が安堵のものに変わった。
「ごめんなシエスタ、心配かけちゃって」
「いいえ。それより、早く起きて支度して下さい。一緒に登校する幼馴染を遅刻させる気ですか?」
幼馴染……。そうだ、生まれてからずっと一緒の幼なじみだよな、俺とシエスタは。
こうして毎朝シエスタに起こしてもらって、一緒に高校に登校して、授業受けて……。
これが俺の日常なんだよな。
……でも……何か違う……ような。
って、そんなこと考えてる場合じゃない! 急がないと、本当に遅刻だ!
制服に着替えた俺は、シエスタと一緒に学校へと走っていた。
「ほら、シエスタ、早く行こうぜ。遅刻しちゃう!」
-
「はぁ、はぁ……。さ、サイトさんが早く起きてくれれば、走らなくてもいいのに……」
それは、まぁ……その通りか。すまんシエスタ、俺の幼馴染に生まれたんだから、諦めてくれ。
「あ、サイトさん」
ふと足を止めたシエスタが、横手の公園を見やった。
「見て下さい、あの公園。子供の時、よく一緒に遊びましたよね」
「ああ、そうだな」
懐かしいなぁ。小さい時に、よく遊んだ公園だ。もちろんシエスタとも一緒に……。
……一緒だったよな? その時の情景が、よく思い出せないんだが……。
疑問を抱いていると、シエスタがこんなことを言った。
「ねえ、サイトさん……。わたしたち、この街でずっと一緒に過ごしてきたんですよね」
「あ、ああ。そうだよな」
「小学校も中学校も、高校だって同じ……。だから、これからも一緒ですよね、わたしたち。
大人になっても……ずーっと……」
一緒……。そうだよな……こんなことを女の子が言ってくれるからには、そうだったに
決まっているよな。わざわざ嘘を吐く必要があるはずないしな。
「一緒なんじゃないかなぁ。シエスタが俺の幼馴染をやるのが嫌になっちゃったら、そこで
終わりだろうけど」
からかい気味に言うと、シエスタは急に大声を出した。
「嫌になんかなりません!!」
「わッ!? じ、冗談だって今のは。びっくりさせるなよ」
「冗談でも、そんなこと言わないで下さい!」
「ご、ごめん。そんなに怒らないでくれよ。なッ、なッ?」
必死にシエスタをなだめる俺。まさかこんな過敏な反応するとは思わなかったなぁ……。
と、俺がシエスタの方に意識を向けていたら……。
「あ、サイトさん危ない!」
「え?」
シエスタが叫ぶので、振り向くと……セーラー服の小柄な女の子がこっちに向かって走ってきた!
「遅刻遅刻ー! 転校初日から遅刻なんて最悪だわー!」
「うわぁッ!?」
俺はその女の子に激突される!
「きゃあッ!?」
「いててててて……」
女の子の勢いがすごかったので、お互い尻もちを突いてしまった。
「いったぁーい……」
「サイトさん、大丈夫ですか!?」
「ああ、俺は大丈夫だけど……」
シエスタの手を借りながら立ち上がると、ぶつかってきた女の子に目をやる。いい体当たり
かましてきやがって……何だこいつ。
ピンク色の髪の、顔はかわいらしい女の子……。あれ? どこかで見覚えがあるような……
それに、どことなく親近感を覚えるような……。
いやいや、そんなまさかな。こんな、ひと目見たら忘れられないような美少女、どこかで
会ってたら忘れる訳がないや。
「おい、危ないじゃ……」
「ちょっと、あんた! こんなところで何ぼーっと突っ立ってんのよ!」
俺が文句をつけようとしたら、先に女の子から怒鳴られた。
「へ?」
「ああもう! グズね! 紳士たるもの、女性が走ってきたら道を開けなさいよ!」
あんまりな物言いに、俺もついむかっ腹が立ってしまった。
「な、何なんだよ、お前! 前も見ないで走ってたのはそっちだろ!」
「何よ! 道の真ん中に突っ立ってるあんたが悪いんじゃない!」
「悪いのはお前だッ! 俺のこと見えてたんだろ、避けるくらいしろッ!」
-
女の子と口論する俺だが、女の子は苛立ったようにそれを打ち切った。
「あーもう、こんなことしちゃいられないの! 遅刻しちゃうんだから〜!」
「あ、おい、待てよ!」
「あんたに構ってる時間はないの! もう、遅刻遅刻ー!」
女の子は俺の制止を振り切って、嵐のように去っていった……。俺はそれを呆然と見送る……。
「……何だったんだ、あいつ」
「……すごい女の子でしたね」
シエスタも呆気にとられている。
「まぁ、そんなことは置いといて、俺たちもそろそろ急ごうぜ。大分時間食っちまったよ」
「そ、そうでしたね。行きましょう、サイトさん!」
気を取り直して、学校へ向けて走っていこうとした、その時……!
「ギイイイイイイイイ……!」
「ん?」
上の方から、何かのうなり声のようなものが聞こえた気がした。その方角を見上げると……。
空の彼方の一画が唐突にスパークし、雷が集まって巨大怪獣が出現した!
「ギイイイイイイイイ!」
「う、うわぁぁぁッ!? 怪獣!?」
全身灰色の皮膚だけど首元だけ白い三日月模様があり、まるでツキノワグマみたいだ。
顔には真っ赤な二つの目玉と、三本の牙が出っ歯みたいに裂けた口からはみ出している……!
かなり凶暴そうな雰囲気だ!
通信端末には、月の輪怪獣クレッセントとある。けど……地球圏の怪獣は全部倒されて、
もう出現しないんじゃなかったのか!? それがこんないきなり……!
『才人、怪獣の出現だ!』
ん? いきなり、誰かの声が耳に……いや、脳内に直接届いた。
目を落とすと、左腕の手首にごてごてとした銀色のブレスレットが嵌まっている! うわッ!?
こ、こんなのつけていたっけ……!?
『ぼやぼやしてる暇はないぜ。変身だ! 怪獣と戦うぜ!』
声はそのブレスレットから発せられているみたいだ。って……変身!? それってまさか……。
昔の地球では、怪獣に襲われて人間がどうしようもないピンチに陥った時、助けてくれる
大恩人がいた。奇跡のような力で怪獣に立ち向かい、俺たちの先祖の命を救ってくれていた
光の巨人……ウルトラマン!
まさか、俺にウルトラマンになれって言ってるのか!? このブレスレットは!
「お、おい、待ってくれよ! いきなりそんなこと言われても……心の準備って奴が! そもそも、
どうしてよりによって俺がウルトラマンに!?」
『なーに言ってんだよ、お前。俺たちは前から一心同体じゃねぇか。そう、お前の命が失われそうになって、
俺が融合することでつないだあの時から』
ええッ!? お、俺の命が失われそうになっただって!?
「そ、それっていつ、どこでのことだよ! 記憶にないぞ!?」
『いつ、どこってそりゃあ……あれ? いつ、どこで起きたことだったっけ……? 何で思い出せねぇんだ?』
ブレスレットの声にも分からないことみたいだ。おいおい、そりゃないだろ。そんな重大な
ことを忘れるなんて……。
『いや、今はそんなことどうでもいいぜ。さぁ、早くこのウルトラゼロアイを装着して変身するんだ!
いつもやってることだろ! ……確か』
ブレスレットのランプ部分から出てきたのは、青と赤と銀色のサングラスみたいなものだった。
あれ? これを見た途端……混乱していた頭の中が、急にクリアになった気分になった。
これを身につけることが、これまでで一番しっくり来る動作のような……。
俺はほぼ無意識に手を伸ばし、眼鏡を掴むと流れるような自然な動きで顔に張りつけた。
「デュワッ!」
その瞬間、俺の身体が光に包まれ、青と赤と銀色の巨人の姿に変貌していった!
巨人になった俺が怪獣クレッセントの前に着地する!
-
『よぉっし! ウルトラマンゼロ、出撃だぜッ!』
ウルトラマンゼロ……!
ああ、そうだよ。どうして忘れてたんだ。ウルトラマンゼロ……それが俺たちの名前じゃないか。
俺たちは今日まで、いくつもの戦いを一緒に乗り越えてきた! ……はずだ! 何故かその戦いの
日々は思い出せないけど……そうだと心が訴えている!
『よし、行こうぜゼロ! 力を合わせよう!』
『へへッ、ようやく調子が出てきたみたいだな。オーケーだ才人! 始めようぜぇッ!』
下唇をぬぐったゼロが、クレッセントにぶつかっていく!
「ギイイイイイイイイ!」
クレッセントは太く鋭い爪が生えた手の平を振るって、ゼロに攻撃してくる。この一撃を
もらったゼロが、ズザザザッ! と押し戻された!
『くッ、なかなかのパワーじゃねぇか』
『大丈夫か、ゼロ!』
『あったり前よ! 戦いはまだ始まったばっかりだ! おおおッ!』
気合いを入れ直して、ゼロは再びクレッセントへ肉薄していった!
「ギイイイイイイイイ!」
クレッセントは腕を振り回してくるが、ゼロは宇宙空手の動きで相手のパワーを巧みに受け流す。
そうして隙を作ったところで、首筋に速いチョップを見舞った。
「セアッ! ダァッ!」
「ギイイイイイイイイ!」
チョップからのローキックでクレッセントをひるませ、そこに相手の体幹に強烈な横拳をぶち込む!
「シェアァッ!」
「ギイイイイイイイイ!」
今度はクレッセントが押し出され、打たれたところを抑えて苦しんだ。
『その調子だ、ゼロ!』
『おう! どんどん行くぜ!』
ゼロは勢いに乗ってクレッセントを更に追い詰めようとしたが……クレッセントは途端に
両目から赤い熱線を発射して反撃してきた!
「ギイイイイイイイイ!」
『おわぁッ!』
かなり威力のある熱線だ! 流石のゼロも、その攻撃は耐え切れない!
「ギイイイイイイイイ!」
クレッセントは更に熱線を撃ち続けて、ゼロを激しく攻め立てる! ゼロが熱線と爆発に
あおられて苦しめられる!
ああ、カラータイマーも点滅を始めた!
『しっかりしろ、ゼロ! お前はあんな奴にやられるような奴じゃない! そのこと、俺がよく知ってるぜ!』
『ああ……その通りだ! まだまだぁッ! ここから反撃だッ!』
ゼロはわずかな攻撃の隙間を突いて、バク転の連続で熱線から逃れた! クレッセントは
追いかけて熱線を撃ってくるが、その時にはゼロも態勢を立て直していた。
『うらぁッ!』
クロスした腕で熱線を防御! これに動揺したクレッセントへ、アクロバティックな側転の
連続で懐へ飛び込む!
『せぇぇぇぇぇぇいッ!』
そこからの首投げが決まった! クレッセントは大きく宙を舞って地面に叩きつけられた!
「ギイイイイイイイイ!」
『おしッ! そろそろフィニッシュと行くぜぇッ!』
クレッセントが持ち直さない間に、ゼロが必殺光線の構えを取る! 左腕をまっすぐ左へ
伸ばしてから、右腕と合わせてL字のポーズを取る!
「シェアァーッ!!」
発射されるワイドゼロショット! この攻撃がクレッセントに直撃する!
-
「ギイイイイイイイイ!!」
ワイドゼロショットを浴びせられ続けたクレッセントの動きが完全に停止し、そのまま前のめりに倒れた。
ゼロの勝利だ! ゼロの勇姿が太陽の輝きに照らし出される!
『へッ、俺たちに勝とうなんざ、二万年早いぜ』
『やったな、ゼロ! やっぱりゼロは強いな!』
『これはお前の力でもあるんだぜ。俺たちの勝利なんだ!』
ゼロの言ってくれた通りだ……。俺も最近は頑張って、ゼロの力になっている。俺たち二人には、
向かうところ敵はいないぜ!
けど、勝利で浮かれていたら……突然目の前が急速にぼやけてきた。
いきなり何だ!? 何が起きているんだ……。
……才人が目を覚ますと、そこは豪奢なベッドの上だった。隣には、いつものようにルイズの寝顔。
「……ん、あれ……」
おもむろに身体を起こす才人。ぼーっ……とした眼差しで、辺りを見渡す。そこは、見慣れた
ルイズの部屋だ。
「……ああ、アルビオンから魔法学院に帰ってきたんだった……」
「お目覚めかい、相棒。けど今朝はいつにもまして寝ぼけてるみたいじゃねえか」
壁に立てかけたデルフリンガーが話しかけてくると、才人は彼に告げた。
「いやぁ、久しぶりに故郷の夢を見てさ……しかもそれが、妙に現実感のある夢だったんだ。
ルイズがセーラー服着てたことくらいしか思い出せないんだけど……」
「へぇ? 今になってホームシックって奴かい、相棒? それとも、嬢ちゃんにセーラー服
着せたい願望があるとか。あの時は楽しそうだったもんな」
「や、やめてくれよ。ちょっと思い出したくない……」
才人が以前のことを思い返して辟易していると、ウルティメイトブレスレットからゼロが声を上げた。
『才人、怪獣の出現だ!』
「何だって!? 本当か! ……ん?」
すぐに反応したかに見えた才人だが、不意に怪訝な顔になる。
『ぼやぼやしてる暇はないぜ。変身だ! 怪獣と戦うぜ!』
「……」
『場所はそう遠くないところみたいだな。直接飛んでいくぜ! ……って、おい。聞いてるのか?
まだ寝ぼけてるのかよ』
才人がぼんやりとしているので、ゼロが呆れた。すると才人はゼロに尋ねかける。
「なぁ……こんなやり取りをどこかでやらなかったか? しかもつい最近」
『なーに言ってんだよ、お前……ん? 俺も何か既視感があるな……。はて、どこでこんなことを
言ったんだったか……』
ゼロも不思議に思って、一瞬黙る。が、すぐに我に返った。
『いや、今はこんなことしてる場合じゃないぜ。才人、すぐに出発だ!』
「あ、ああ、そうだったな。行くぞ、デルフ」
ベッドから飛び降りた才人がデルフリンガーを背負う。それから、まだスヤスヤと眠っている
ルイズにそっと呼びかける。
「行ってくるな、ルイズ。すぐ戻るから」
それからブレスレットから出てきたウルトラゼロアイを装着し、ウルトラマンゼロへの変身を行う!
「デュワッ!」
青と赤の光は窓から外へと飛び出していき、大空で巨人の勇敢の戦士の姿へと変化する。
『よぉっし! ウルトラマンゼロ、出撃だぜッ! ……これも言ったことある気がする』
ゼロは怪獣出現の現場に急行しながら、そうぼやいた。
-
ここまで。
ということで、今回から「夢魔が紡ぐ夜風の幻想曲」編です。
-
皆様、お久し振りです。
今回は短いのですが、よろしければ21:20頃からまた続きを投下させてください。
-
「はあ……」
ある日の夕方、トリステイン魔法学院の自室で、ルイズは溜息を吐いていた。
ルイズの『使い魔』であるディーキンが、彼女の知らぬ間にタバサと一緒に出かけてから、もう3日以上も経っている。
無断で勝手な行動をとったことについては、何かと事情もあり、ディーキンにも考えあってのことだと、不承不承認めてはいる。
そもそも彼は自分の正式な使い魔ではないのだから、という思いもあった。
時間についても、異国であるガリアへ赴き、そこでタバサと一緒に何らかの任務を引き受ける以上は相応にかかるだろうと理解している。
まず3日や4日はかかって当然だし、仕事の内容いかんによっては、一週間以上かかったとしてもおかしくはない。
とはいえルイズは、一刻も早くディーキンに戻って来てもらいたいものだと思っていた。
彼が留守の間に、彼女の方でもいろいろと面倒な問題が持ち上がっていたのだ。
「どうかしたの、ルイズ。溜息を吐いて……。
人間の身体のことはよく分からないけど、どこか具合が悪いのかしら?」
問題の大きな原因である天使(エンジェル)、『使い魔代理』のラヴォエラが、彼女の気も知らずに的外れなことを言ってくる。
心底心配そうに優しく自分の背中をさする彼女を、ルイズは肩越しに軽く睨んだ。
(あんたのせいで気苦労してるのに決まってるでしょ!)
……と、言いたいのは山々だが、そう言ってみたところで彼女に通じるとは思えない。
そのことは、この数日でルイズにも身に染みてよく分かっていた。
別に、ラヴォエラの使い魔としての働きぶりが悪かったわけではない。
彼女は引き受けた仕事を、いつでも真摯に務めてくれた。
ルイズの同行させたいところにはどこにでもついて来てくれたし、頼めば何でもちゃんとしてくれたのである。
天使にこんなことを頼んでいいのだろうかと、ルイズの方がかえって躊躇するような雑務でも、嫌な顔ひとつせずに引き受けてくれた。
ただ、ラヴォエラは何といっても天使であった。
天使はその魂の隅々まで完璧に善に染まった存在であり、決して嘘をついたり、相手を騙したり、盗みを働いたりはしない。
そのように高潔で信が置けるがゆえに、経験豊かな天使は極めて優れた交渉役ともなり得る。
だが、生憎とラヴォエラはまるで経験不足な若い天使で、人間の社会の常識にも酷く疎く、あまり融通も利かなかった。
その点において、彼女はディーキンとは大きく違っていたのである……。
-------------------------------------------------------------------------------
ルイズが初めて使い魔の代理としてラヴォエラを伴って食堂へ行ったとき、当然ながらその主従は、周囲の注目を集めた。
一応、ラヴォエラは「天使だなんていったら騒ぎになって面倒なだけだから」とルイズに頼まれて、人間のメイドの姿に変装していた。
周りの人間を欺くのか、と難色を示すラヴォエラを説得するのに多少の時間はかかったが、シエスタも手伝ってくれたのでどうにかなった。
アアシマールのシエスタには、天使の考え方と人間の考え方の両方がよく分かるため、交渉役には最適だったのである。
とはいえ、それで周囲の注目を一切受けずに済むかといえば、当然ながらそんなことにはならない。
使い魔の代理などという話は前代未聞だし、それが通常使い魔になるとは考えられない人間となれば、尚更のことである。
ルイズもそのくらいは勿論承知していたが、それでも天使だなどと、普通に考えて荒唐無稽なことをいうよりはマシだろう、と思っていた。
いっそしばらくの間使い魔を連れて歩かないのはどうかとも考えたが、その場合でもどうせ遠からず詮索は受けるだろう。
ディーキンはあちこちで顔を売って人気者になっているので、いなくなれば理由を聞かれないはずがない。
ゆえに、いっそ天使だという一点のみを伏せて、ディーキンはしばらく出かけていて彼女が使い魔代理だと正直に言う方がいいと結論した。
せっかく代理をよこしてくれたのに部屋に閉じ込めておくというのも、ディーキンとラヴォエラに申し訳ないことだろうし。
-
結果として、周囲から注がれる好奇の視線の中でルイズはかなり居心地の悪い思いをしたが、そればかりでは済まなかった。
それらの視線の中には、非常に意地の悪い性質のものも、いくつか含まれていたのである。
それは、生徒らの中でも殊更強くルイズを蔑み、長い間嗤いものにし続けてきた連中からのものであった。
最近彼女が召喚した奇妙な亜人の使い魔がやけに人気者な上、ルイズの評判も上がったために手を出しにくく、不満を募らせていたのだ。
その使い魔が今はおらず、代わりにやってきた代理とやらはどう見ても平民の使用人。
となれば、これは彼らにとって絶好の機会であった。
「やれやれ、あの使い魔にはとうとう逃げられたらしいね。
まあ、『ゼロ』にしてはよく持ったじゃないか!
おまけに、その代わりに平民のメイドを使い魔だなどと言い張って持ち出す度胸には恐れ入ったよ!」
と、挑発の口火を切ったのはヴィリエ・ド・ロレーヌ。
ルイズの同級生であり、『風』系統の高名なメイジを何人も輩出した名家の出身で、自身も風のライン・メイジだ。
その事を傲慢なまでに誇り、家格や実力で劣る他者を蔑む態度が鼻につく男子生徒だった。
「そうそう、大したもんじゃないか!
さては例の盗賊退治の時のお手柄も、実はその話術の成果かい?」
「その口の上手さなら、将来はさぞやいい政治屋になれるぜ!」
何名かの意地の悪い生徒がロレーヌに追随するように声を上げて、ルイズを囃し立てる。
「あんたたちがそう思うのは自由よ」
ルイズは半目で彼らを睨むと、さらりとそう返しただけで、後は無視を決め込んだ。
こと風においては間違いなく当代最強のメイジを身内に持つルイズからしてみれば、ロレーヌの増上慢はむしろ滑稽なだけであった。
おまけにこの男は、入学直後に自分よりも秀でた風の使い手であるタバサに決闘を挑んで無様に返り討ちに遭い、学院中に恥を晒している。
そんなわけで、ルイズは彼からの嘲りなど、ほとんど意に介したこともないのである。
しかし、彼女の傍に控えている使い魔代理は、そうはいかなかった。
ラヴォエラはロレーヌの言葉を聞いて不審そうに首を傾げると、彼の傍に歩み寄って話しかけた。
「ねえ、あなた、どうしてそんなことを言うのかしら?
私は確かにディーキンから代理を頼まれてここに来たのだし、彼はルイズから逃げ出したりなんかしないわ」
ルイズと、少し離れたところで給仕をしていたシエスタとが、ぎょっとして彼女の方に目をやる。
キュルケは逆に、これはまた面白いことが起きそうだと目を細めていた。
案の定、ただの平民だと思い込んでいたラヴォエラからの思いもよらぬ反論に、ロレーヌはたちまち憤慨し始めた。
「平民ごときが貴族に対して、何だその態度は!
さすがにゼロの雇った平民だけあって、常識もゼロだと見えるな!」
しかし、人間の社会自体に疎い、ましてやハルケギニアのそれなどまったく知らないラヴォエラは、ますます困惑するばかりだった。
「ええと……、その、つまり、私の態度がいけなかったのね?
じゃあ、どういう話し方で、あなたにルイズが嘘を言っていないとわかってもらえばよかったのかしら?」
ラヴォエラはむしろ、穏やかに話を進めたいと思って純粋に質問をしただけだったのだが……。
ロレーヌには、この非常識な言動は明らかな挑発か侮辱だとしか思われなかった。
「……どこまでもそうして舐めた態度をとるつもりか。
いいだろう、そういうつもりならば、望み通りお前に礼儀を教授してやろう!」
ラヴォエラに対して杖を突き付けるロレーヌの前に、慌ててシエスタが割って入った。
「お、お待ちください、貴族様!
その、この方は、まだこの辺りに不慣れなもので……、」
しかしながら、シエスタが出て来たことは、かえってロレーヌの怒りの炎に油を注ぐ結果となった。
彼は、平民の分際で先日ギーシュとの決闘に勝ったこのメイドのことも、内心気にいらないと思っていたのだ。
厳密に言えば引き分けということになってはいるが、実質的にはシエスタの勝ちであることにはギーシュ自身も含めて誰も異論はなかった。
-
「ふん、最近は生意気な使用人が増えているようじゃあないか!
メイド風情が、たかだかドットのメイジにまぐれ勝ちしたくらいで調子に乗るなよ。
この際、あの不甲斐ないギーシュに変わって僕が、お前にもついでに……」
「待ちたまえ!」
そこで、今度はギーシュが席から立って、ヴィリエに薔薇の杖を突き付けた。
その目には、爛々と怒りの炎が燃えている。
先の決闘以降、ギーシュはシエスタに対して、身分の差を超えた敬意を示すようになっていた。
「ロレーヌ、これ以上その女性と僕とを侮辱する気ならば、僕も君の相手になるぞ!」
「……ちっ。平民などに肩入れを……」
ロレーヌは忌々しげにギーシュを見て、舌打ちをした。
たかがドット・メイジのギーシュなどに負ける気はないが、そのギーシュを負かしたメイドと一緒となると、少々面倒かも知れない。
万が一にも負けたくはない、一年の時のような恥をかかされるのだけは嫌だった。
しかしそこで、先程ロレーヌに同調してルイズを囃し立てていた生徒らが立ち上がった。
「ロレーヌ、相手の人数が多いようじゃないか。僕も加勢しよう」
「それなら、僕も参戦させてもらおうかな」
ロレーヌは彼らと、にやりと意地の悪い笑みを交わした。
彼らはいずれもロレーヌの悪友で、それぞれ火のライン・メイジと、土のドット・メイジだった。
「よおし、これで3対3ってわけだ。公平だし、文句はないよなあ?」
同じ土メイジ同士でギーシュを足止めしている間に、殺傷力に優れる風と火の呪文でメイド2人を始末する。
その後は、3対1でギーシュを滅多打ちにしてやるまでだ。
これなら負けるはずがない。
「ま、待ってください。私たちは決して、貴族様に挑もうなどとは……」
「ちょっと待ちなさいよ、ロレーヌ! 決闘は禁止でしょう!」
シエスタとルイズが、それぞれ声を上げる。
彼女らは、なんとか問題を大きくせずに事を収めたいと願っていた。
しかしそこで、ラヴォエラの鋭い声が上がった。
「いいでしょう、邪悪な者たちめ!
あらぬ言いがかりで他人を傷つけようというのなら、私があなたたちを成敗してあげるわ!」
見れば、先程の穏やかな様子とはうって変わって、鋭く吊り上った目でロレーヌたちを睨み、彼らに指をビシッと突き付けている。
これではもう、到底決闘は避けられそうにもない。
ルイズは、なんで来て早々こんな面倒なことを起こしてくれるんだという気持ちで頭を抱えていた。
一方シエスタは、天使という存在についてより詳しく理解しているがゆえに、ルイズよりもなお一層危機感を募らせていた。
なんとか穏健に対処してくれるよう、彼女を説得しなくてはという焦りで、額に冷や汗をかいている。
ラヴォエラは明らかに、あまりに悪意のあるロレーヌらの態度を見て、彼らに《悪の感知(ディテクト・イーヴル)》を試したのであろう。
そうしておそらくは、彼らが悪の存在であることを確かめてしまったのだ。
力の及ぶ限り悪しき者と戦い、それを打ち倒すことは天使の重要な務めのひとつであると、シエスタはよく知っていた……。
-
今回は以上になります。
また、できるだけ早く続きを書いていきますので、次の機会にもどうぞよろしくお願いいたします……(御辞儀)
-
おつ
-
乙
善の来訪者も大変だw
-
こんばんは、焼き鮭です。今回の投下をします。
開始は18:18からで。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第八十二話「ハルケギニアの剣豪」
古代怪獣ツインテール
地底怪獣グドン
マスコット小怪獣デバン 登場
「グギャ――――――!」
「グオオオオオオ!」
早朝のトリステインのとある草原。普段は平穏な空気が流れる土地だが、現在は二大怪獣と
それに挟まれたウルトラマンゼロがそびえ立っており、強い威圧感が草原を覆っていた。
怪獣の内の片方、逆立ちしたエビのようなものはツインテール。そしてもう片方、両腕がムチ状に
なっているのがグドン。グドンはツインテールを捕食することで有名な怪獣だ。現在も、草原に
出現したツインテールを追って現れたのである。
当然ツインテールも、黙って食われたりはしない。必死の抵抗をして、グドンと激しい生存競争を
繰り広げていたのだが、その移動しながらの争いが人里にまで降りかかりそうになったため、ゼロは
駆けつけて怪獣同士の対決に割って入ったのであった。
「グギャ――――――!」
「グオオオオオオ!」
「シャッ! シェアッ!」
ツインテールとグドンは乱入者ゼロを互いに敵と見なし、襲いかかっていく。前後から二大怪獣に
迫られるゼロだが、少しもひるまずに二体同時に相手取る姿勢を見せた。
二怪獣のそれぞれの触手を巧みにいなすと、後方のツインテールに後ろ蹴りを入れ、正面のグドンには
拳打を叩き込んだ。鋭い打撃を食らった怪獣たちはよろよろと後退する。
「グオオオオオオ!」
しかしひるんでいたのはわずか一瞬の間だけだ。怒り狂ったグドンは勢いを強め、更に速い
ムチさばきをゼロに振るう。
「フッ!」
そのムチ攻撃もかいくぐるゼロだったが、
「グギャ――――――!」
背後から忍び寄ったツインテールに対応できず、ふたまたの尻尾が首に絡みつき、また足首を
噛みつかれた。
「グゥッ!」
身体の弱い部分を同時に狙われては、さすがのゼロも苦しい。しかもツインテールに
掴まっているところに、グドンのムチが容赦なく飛んできて激しく打たれる。
「ウオォォッ!」
前後から攻撃を受け続け、ダメージが蓄積される。カラータイマーも点滅し出した。ピンチのゼロ!
「デヤァッ!」
だがこのままで終わるゼロではなかった。ムチの攻撃の合間に素早くエネルギーを電撃に変換し、
全身から放った。ボディスパークだ!
「グギャ――――――!」
「グオオオオオオ!」
突然の電撃攻撃をもらったツインテールとグドンの動きが停止した。そして解放されたゼロは、
狙いをツインテールの方へ向けた。
「デュワッ!」
ビームランプからエメリウムスラッシュを発射! 緑色の光線はツインテールに直撃し、
一撃で粉砕する。
「グオオオオオオ!」
その背後から迫り来るグドン。だがゼロはすかさず振り返り、相手のムチをはっしと掴んだ。
「セェェェェェイッ!」
気合い一閃、ムチごとグドンの巨体をスイングし、草原の上に投げ飛ばす! 大地に横たわる
グドンに、ゼロはとどめの一撃!
-
「シャッ! シェアァッ!」
ワイドゼロショットが見事グドンに決まった。グドンは爆散し、草原は静けさを取り戻す。
「ジュワッ!」
危ない場面もあったが、無事に二大怪獣を倒すことが出来たゼロは、空に飛び上がって
魔法学院へと帰還していった。
その後の昼時、ルイズら学院の生徒が授業中の間、才人は中庭でデルフリンガーを素振りしていた。
アンリエッタにシュヴァリエの称号を授かってから、身体を鈍らせないようにこうした訓練を日課に
加えたのである。
「相棒、今日は一段と力が入ってるじゃねえか。一体どうしたんだい?」
素振りをされているデルフリンガーが、才人のいつもとの違いを察して尋ねかけた。それに才人は
こう答える。
「いや、さっきゼロが背後からの攻撃を食らって危なくなっただろ? それって、俺の身体が
知らず知らずの内に鈍ったからじゃないかって思ってさ……」
二対一のハンデがあったとはいえ、いつものゼロなら背後からの攻撃もかわせたはずだ。
それを避けられなかったというのは、自分に問題があったからではないかと才人は考えたのだ。
だが、それにゼロが告げた。
『才人、さっきのはお前は関係ないぜ』
「えッ、そうなのか?」
ではその理由は何なのか。ゼロは答える。
『何だか、思ったよりも身体が動かなくってな……どうも、疲れてたみたいなんだよ』
「疲れてたって……ゼロが?」
『ああ、俺としても不思議だ。体力はちゃんと回復してたはずなんだが……。そう、ちょうど
直前に一戦やったぐらいの疲労感があった』
直前に一戦……? それを聞いた才人は、何かを思い出しそうな感覚を覚えた。何を思い出し
かけているのか……自分は何を忘れたのか……どうにもはっきりしない。頭に靄がかかっているような……。
悶々としていた才人だが、以前よりも鋭敏になった感覚が、突如攻撃の気配を察知した!
「!?」
咄嗟に振り返ってデルフリンガーを盾にする。
「やああッ!」
その刃が、迫ってきた白刃を受け止めた!
白昼堂々の襲撃! しかし才人はそれよりも、剣を振るってきた相手の格好に驚かされた。
「なッ……! な、な、何だこいつ!?」
何と、「和風」という言葉も存在しないハルケギニアで、「袴」を纏っているのだ。しかし
日本人という訳でもない。人種自体は、金髪の典型的な白人タイプの少女だ。何ともミスマッチな服装だ。
「この不意打ちを受け止めたか。気配は完全に消したつもりだったが」
「だ、誰だ! 何のつもりだよ、これは!」
一瞬面食らってしまったが、我に返った才人が襲撃者の少女に問うた。
「いきなり失礼した。少し、お前の剣の腕を確かめたくてな。サイトとやら、お前の腕はなるほど、
なかなかのもののようだ。しかし、男なら白刃取りをせんかッ!」
「……はぁ?」
いきなりの訳の分からない発言に、才人はまたも面食らった。
「アンリエッタの話を聞く限りでは、お前はかのサムライの国の者らしいが……わたしの見込み違いか?」
更に少女の口からは、ハルケギニアではまず聞かないはずの単語が出てきた。
「ち、ちょっと待て! サムライ? 今、サムライって言ったよな!?」
よく見れば、少女の剣はハルケギニアで広く用いられている西洋剣ではない。明らかに片刃の、
日本刀であった。
「ま、まさか……お前、日本を知ってるのか!?」
-
「ほほう。その反応、やはりお前はニホンから来たのか」
「じゃあ、あんたも向こうの世界から来た人なのか!?」
そう思った才人だったが、少女は不思議そうに顔をしかめた。
「向こうの世界?」
「……違うのか?」
「いや、わたしはニホンの者ではない」
「けど、あんたのその格好とかサムライとか、この世界のものじゃないだろ?」
「この格好などは、わたしの師匠から授かったものだ」
「師匠?」
先ほどから変わった言動をする少女。ここでようやく名前を名乗る。
「ああ、申し遅れたな。わたしはクリスティナ・ヴァーサ・リクセル・オクセンシェルナ。
クリスと呼んでくれ。アンリエッタもわたしをそう呼ぶ」
「……アンリエッタ? さっきもそう言ってたけど、まさかそれ、女王さまのこと?」
「他にいるか?」
「えええええ!」
仰天する才人。今や一国の女王のアンリエッタを呼び捨てにするなど、一体どんな身分の者が
出来るのだろうか。ルイズだってそんなことは出来ない。
「彼女は古くからのなじみだ。互いに名を呼び合う仲でな、問題ない」
「なじみ? 仲?」
「先日、久しぶりに会った際にお前のことを聞いてな。魔法を扱えない平民で、シュヴァリエの称号を
与えられたそうではないか。それでお前の主人ともども、会いたいものだと思っていた。会えて嬉しいぞ、
サムライのサイトよ!」
「さ、侍って……」
才人は苦笑いする。「侍」など、何世紀前の身分だろうか。
「それで、えーと、クリス? お前はこの学院に、俺やルイズに会いに来ただけ?」
問いただすと、クリスという少女は語る。
「いや、わたしは明日からこの魔法学院に転校する予定なんだ。アンリエッタに口利きしてもらってな」
「え、転校?」
才人は思わず虚を突かれた。今の時期は、日本の学校制度で言うならば三学期に相当する。
そんな時期に転校してくるなんて、普通はないことだろう。このハルケギニアでもそのはずだ。
「奇妙だと思うだろうが、ちょっとした家の事情があってな」
「はぁ、そういうものなのか……」
「ともかく、明日からよろしく頼むぞ、サイトよ」
「よ、よろしく……」
色々と突拍子もない少女、クリスのペースに呑まれっぱなしの才人であった。
ここでようやく気になっていたことを尋ねる。
「ていうかさ。この学院に入るからには、クリスも貴族で魔法使いなんだよな」
「一応な。系統は風、二つ名は『迅雷』だ」
デルフリンガーも問いかけた。
「おめえさん、メイジなのに剣だけを使うのか? 変な奴だなぁ。俺も初めて見るな」
「デルフが初めて見るんじゃ、歴史上初に近いんじゃないか?」
「だなぁ。いや相棒、こいつはほんとうに変な奴だよ」
デルフリンガーが何度も「変」と言うと、クリスは気分を害したように反論した。
「失礼だな、人を変だと何度も。わたしはサムライだ、故に魔法などに頼らず剣を使うのは当然!
サイトならわかろう? この気持ちが」
「はぁ……」
そう言われても、才人は別に侍ではないので、そういう気持ちはよく分からなかった。
と話していたら、才人の視界ににゅっと奇怪な生物が割り込んだ。
「キュー!」
「どわッ!? 何だこいつ!? びっくりした……」
銀色の肌でたらこ唇の、何とも形容のしづらい見た目だ。地球上のどの生き物にも似ていない。
宇宙生物だろうか。
「ああ、それはわたしの使い魔だ。名をデバンという」
-
「デバン? 変わった名前だな」
「どうもこの音の響きを、自分の名前と認識してるみたいでな」
「キュー、キュー」
ひょこひょこ動くデバンの姿に、ゼロが独白した。
『こいつは確か、異次元の小型怪獣の一種だったな。前に魔神エノメナを倒したことがあったが、
こいつはその能力を打ち消すことが出来る奴だったはずだ』
「キュキュキュキュキュー!」
ひょうきんなデバンの動きに、才人は思わず笑いを噴き出した。
「あははは! こいつ、濃い顔だけど結構かわいいな」
「かわいいだけでなく、とても賢いぞ? サムライの従者らしくあれと言っているからな」
「へー、サムライの従者ねぇ」
一時デバンと戯れる才人。しかし、クリスはアンリエッタを呼び捨てにするほどだから、
かなり身分が高いはずだが、気さくでなじみやすい性格だ。学院の無駄に偉そうな貴族の
数々とは大違い。
と、才人はそう思ったのだが……。
「さて、サイトよ。いまから学院を案内してくれ」
「えッ、いまから!? それよりさ、さっきチラッと言ったクリスの師匠って誰なのか教えてくれよ!」
「それは、おいおい話す。とにかくいまは案内をしてくれ。明日に備えデバンと適当に見て
回るつもりだったんだが、せっかくお前に会えたのだしな。行くぞ、サイト」
クリスとデバンは有無を言わせずに本塔の方に歩いていく。
「おいッ! そんな、いま話してくれよ! それに俺、いまは訓練中……!」
才人がいくら呼び止めても、クリスは立ち止まらなかった。
先ほどの不意打ちといい、こういう強引なところは貴族だなぁ、と才人は感じたのであった。
それから才人はクリスに魔法学院の設備などを説明して回る。と言っても、案内役の才人が
半ば引っ張られるようであったが。
「ここが庭。結構広いけど、覚えられそう?」
「ああ、心配無用だ。もう大抵覚えた」
「へー、記憶力いいんだな。俺、広すぎて覚えるの大変だったのに」
「広いか? 一国を代表する魔法学院ともなれば、この程度は当然だろう」
クリスと会話する才人は、ふと尋ねかける。
「……あのさ。クリスのその言葉遣い、変わってるよな」
「ブシの言葉はこうなのだろう? 会得するのに苦労したぞ」
「いや、そんなしゃべり方をする人は物語の中くらいにしかいないけど」
今の地球では、クリスのように固い話し方をする人はまずいない。若者は大体砕けた口調だ。
しかし今の才人の言葉に、クリスはショックを受けたようだった。
「な、なんだと!? ニホンではブシがチョンマゲを装備し剣一本で身を立て、いずれセップク
するのが誇りなのだろう!?」
「……えーっと」
思わず言葉をなくす才人。いつの時代のことを話しているのだろうか……というより、
それを差し引いてもどこかおかしい。まるで外国人のエセ日本観だ。
「まあその、細かい点は置いといて。武士にも色々あるんだよ、時代は流れるしさ」
「むう……。セチガライ、とはこういうことを言うのか?」
「……そうだけど。そんな言葉、よく知ってるな」
若干呆れる才人だった。本当に、クリスはどこの誰から日本を教わったのだろうか。
「でもさ、武士の心までは失ってないと思うよ。義理人情に厚い人はまだまだいるしな」
「そのようだな。サイトを見ていればわかるぞ」
「へ? 俺?」
「アンリエッタはお前を、主人への忠義に厚く、心優しく、かつ腕の立つ使い魔だと言っていた」
-
「え、え? そうなんだ、お姫さまが俺のことをそんなに……」
アンリエッタからそこまで高評価されていたことに、才人は思わず照れた。
そうしていると、クリスが才人へ礼を告げた。
「案内をありがとう、サイト。お陰で明日からの生活への心配が少なくなった」
「……」
「どうした? 口が開きっぱなしだぞ」
才人は文字通り、開いた口がふさがらなくなっていた。
「いや、その、使い魔にお礼を言う貴族は初めてかなーなんて思って」
トリステインの貴族は、大体がプライドの塊だ。才人もシュヴァリエとなったが、それでも
同等とは見られていないのがほとんど。平民の成り上がりが、と僻みを受けることも少なくない。
「お前はわたしの使い魔ではないだろう? それに、わたしにとってお前は友だ」
「……とも?」
才人が呆気にとられていると……聞き覚えのある声音の、怒鳴り声が響いてきた。
「サイトー!」
「わッ!?」
「何事だ?」
駆けてきたのは、案の定ルイズであった。
「この、ののの、野良犬! ささささ、盛りのついた、いい、犬ー!」
顔を合わすなり、ルイズはいきなり罵倒してきた。
「は、はあ!? なんだよ、走ってきていきなり!」
「聞いたわよッ! つつつ、使い魔のくせにいい度胸してるじゃない! 女の子連れて学院内を
散歩なんて! デ、デ、デートなんて! しかも、ま、また、む、む、胸が大きい女の子だし……」
「でーとぉ!?」
ギョッとする才人。確かに、傍目から見ればクリスと一緒に学院内を回っていたのは、
デートと取れるかもしれない。恐らく、ギーシュかモンモランシー辺りが吹聴したのだろう。
「そ、そんなんじゃねーよ」
才人がどうにか誤解を解こうとしていると、クリスが口を挟んできた。
「おい、サイト。これは誰だ?」
「こここここ、これ!? 貴族に向かってこれですって!?」
「いや、ルイズ。この子も貴族なんだって」
才人が必死になだめていると、ルイズの名を聞いたクリスが問い返す。
「ルイズ? では、これがお前の主、ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエールか」
「そ、そう」
「サイトー! あんた、こんな得体の知れない相手のわたしのことをベラベラしゃべったの!?」
「しゃべってない! 落ち着けって! いいか、この子はな……」
どうにも機嫌の悪いルイズに説明しようとした才人だが、またもクリスが口を開く。
「わたしとサイトは剣を交えた仲。つまり、好敵手と書いて友だ」
「まままま、交えた仲!?」
ルイズは顔を白黒させた。
「おい! なに考えてんだよルイズ! 交えたのは剣だよ剣! そう言っただろ!」
妙な誤解の解けないルイズを説得して、変な関係ではないことを分かってもらうのに、
才人はしばしの時間を費やすことになるのであった。
クリスがオクセンシェルナという国の姫という身分であることが分かり、更に仰天することに
なるのはまた別の話なのであった。
-
今回はここまで。
存在を取って代わられ、哀れガレット。
-
乙でした
-
乙です
-
皆様、こんばんは。
よろしければ、20:55頃からまた続きを投下させてください。
-
「それじゃ、僕らはヴェストリの広場で待ってるぞ。今さら逃げようなんて思うなよ!」
ロレーヌらがそう言い捨ててヴェストリの広場へ向かって行った後、シエスタはあわててラヴォエラの元へ駆けつけた。
決闘の準備をすると言い訳をしてから、彼女をルイズと一緒に自分の部屋へ引っ張り込んで説得にかかる。
もちろん、ラヴォエラが負ける心配などはまったくしていない。
そうではなく、彼女がロレーヌたちを悪だからといってあまり手酷く成敗しすぎるのではないか、ということが心配なのだ。
天使は基本的には慈悲深い存在だが、一度悪しき者への怒りを燃え上がらせれば容赦なき破壊の化身ともなる。
自分よりも色濃く天使の血を引く祖母を間近で見て育ったシエスタは、その事をよく知っていた。
相手は悪しき心の持ち主であり、実際にも悪意ある行動をとって、他人の心身を傷つけようとしたのである。
パラディンであるシエスタとしても、善悪という面から見れば懲らしめられるのは当然だとは思う。
しかしながら法や秩序という面から見ると、当然ながら悪人を懲らしめてはい一件落着、というわけにはいかないのだ。
まあ、ラヴォエラの態度にも問題はあったとはいえ、向こうから挑んできた以上は返り討ちにしても咎められることはないだろうが……。
貴族相手に重傷を負わせたり死に至らしめたりすれば、さすがにそうもいくまい。
天使であるラヴォエラ自身はそんなお咎めなど気にもしないだろうが、ルイズらに迷惑がかかる。
だから、なんとか穏便に事を運んでくれるように説得をしなくてはならない。
ディーキンがいればきっと簡単に彼女を納得させてくれたのだろうが、今は留守を任された自分がどうにかしなくては……。
ルイズにはシエスタほどの危機感はなかったが、とはいえなるべく穏便に事を運んでくれるようラヴォエラを説得したいとは思っていた。
メイジ3人を相手に遠慮なく戦ったりしたら、正体がただの平民などではないことが知られてしまうだろう。
そうなれば、『使い魔でもない危険な亜人を学院に連れ込んだ』と非難されるかもしれない。
彼女は天使だなどという、戯言めいた説明がそう簡単に通るとも思えないし。
しかし、やってみるとこれがなかなか大変だった。
「シエスタ、あなたはパラディンなのでしょう?
どうして、悪人を懲らしめるのがいけないなんていうの?」
「いえ、その。いけないというわけではないんです。
ですが、なんといいますか、人間の社会の規律的な問題がですね……」
「向こうから戦いを挑んできたのに、立ち向かってはいけないの?」
「け、決闘はこの学院じゃ禁止されているのよ!」
シエスタとルイズの説明に、ラヴォエラはまばたきをして首を傾げた。
「よくわからないけど……。
では、あの人たちをどこかに訴えて、法的に有罪にして処罰してもらえばいいのかしら?」
「あ……、いえ、あの方々は貴族でいらっしゃいますから。
たぶん、訴えても有罪にはならないかと……」
シエスタが困ったような顔をしてそう言うと、ラヴォエラは美しい眉を吊り上げて憤慨した。
「まあ、なんて邪悪な! ここでは悪意をもって無辜の人々の心身を傷つけようとした者が、罪に問われずにのさばるというの!?」
「じゃ、邪悪って……。それは思うところは私にもあるけど、ちょっと言いすぎじゃない?」
ルイズはラヴォエラのナイーブな反応に戸惑いながらも、なんとか穏便に対処する必要性を彼女に分かってもらおうとした。
「その……、なんていうかあいつらは、私たちの社会では高い身分にあるのよ。
あいつらがやられるのには同情しないけど、あなたがあまりひどく痛めつけると、ディーキンにも迷惑がかかるだろうし……」
「そんなことないわ。ディーキンは英雄だもの、悪人を懲らしめる時に、そんなリスクは気にしないわ」
ディーキンのことを信頼しきった真っ直ぐな目でそう言い切るラヴォエラを見て、ルイズは顔をしかめた。
-
「あ、あなたがあんまり派手に暴れるとね、私にも体面とかが……」
ラヴォエラはそれを聞いて、不思議そうに質問をした。
「ルイズは、善を成すことよりも自分の体面を保つことのほうが大事なの?
あなたは善い人のはずよ、どうしてそんな利己的なことを?」
人間のような種族の不完全さにまだ不慣れな天使である彼女には、ルイズの訴えは理解しがたいものだったようだ。
純粋なる善の存在である天使は、善のためなら自分の不利益など気にしないのが当たり前だし、裏表のある態度などもまず取らない。
善行をするにあたっては、その見返りはおろか、感謝の言葉ひとつ期待する事もない。
そして俗世に疎い彼女は、天使でなくとも善に属する者はすべからくそうであって、それが普通のことだと思っているのだ。
おまけに彼女が一番よく知っている人間はディーキンのボスで、パラディンである彼は、そんな彼女の考えを滅多に裏切らない人物だった。
経験を積んだ天使の中には、善を成す時ですら悪から離れられない定命の民の賤しい性質を知って、すっかり失望してしまう者もいる。
そのような者は、冷たく超然とした態度を持って、それらの種族と接するようになる。
人間のような種族の間でしばしば語られる、“高潔だが傲慢で冷酷な天使”のイメージは、主としてそうした者たちが形作ったものだ。
一方で、その不完全な性質の中に、自分たちのような完全性とはまた違う種類の高潔な精神を認めるようになる者もいる。
善に結び付けられたセレスチャルとは違う、本来は善にも悪にも偏っていない種族が、善を成そうとすることの意味を理解するのだ。
そのような者は、時に躓き迷いながらも懸命に正しい道を歩もうとする力弱い種族に敬意を覚え、時には深い愛情を抱くようになる。
シエスタのようなアアシマールも、そうして地上の種族に惹かれた心優しき天使を祖として生まれたものなのだ。
ラヴォエラは、今のところそのどちらでもないといえるだろう。
地上に来て初めての任務で希代の英雄に救われた彼女が、この後人間に失望するようになることはまずあるまい。
かといって、彼女はまだ定命の種族に対して深い愛情を抱けるほどに彼らのことをよく理解しているというわけでもなかった。
若々しい好奇心と生まれ持った熱意の赴くままに、世界と向き合い出したばかりの段階なのだ。
「……う、う〜」
責めるでもなく、ただ純粋な問いを投げてくるラヴォエラに、ルイズは何を言っていいのやらわからなくなってしまった。
そんな彼女の代わりに、天使というものについてよりよく理解しているシエスタが口を挟む。
「その、つまりですね。確かに悪を懲らしめるのは大切ですが、迷惑が掛かる人もでてきますよね?
もちろん、先生やミス・ヴァリエールは必要な犠牲であれば受け容れてくださるとは思いますが、それがなければもっと善いでしょう?」
「うーん……。それは、そのとおりね」
「ですよね! ミス・ヴァリエールが言われたかったのは、そういう、もっと良いやり方があるということなんですよ!」
ようやく手掛かりをつかんだと見たシエスタは、その線で一生懸命に説明を続けた。
確かにあの貴族たちは今は悪意に満ちているが、人間なのだから良心もあるはずだし、まだ若い。
少しだけ懲らしめた後は説得して正しい道に引き戻す方が、ただ徹底的に叩きのめして終わるよりもずっといいはずだ。
悪人のまま死ねばその魂は地獄や奈落で苦しむが、改心すれば浄土で永久の安らぎを得られるのだから……。
「ラヴォエラさんなら、きっとできると思うんです!
先生も、『悪い竜を倒す英雄より、友だちになって悪事を止めさせる英雄の方がもっと偉い』っておっしゃってましたわ!」
熱意を込めてそう言うと、ラヴォエラはあっさり納得したらしく、目をきらきらさせていた。
「そう……そうよね! さすがはパラディンね、あなたのお陰で目が醒めたわ!
私、頑張ってあの子たちを正しい道に引き戻してみせるわね!」
-
まったくもって、単純なものである。
シエスタは、これで最悪の事態は避けられただろうと、ほっと溜息を吐いた。
世慣れていない天使の心を動かすには、利害だの体面だのを説くよりもこういう話の方がいいはずだという考えは当たっていたようだ。
「おい、いつまで準備に時間をかけてるんだ。
なにをブツブツ喋ってるのか知らんが、そろそろ出てこいよ!」
部屋の外で、見張りのために残ったロレーヌの悪友の一人が乱暴にドアを叩いて声をかけてきた。
「もちろんよ、善を成すのは早いほどいいものね。今いくわ!」
そう言って勇んで部屋の外に向かおうとするラヴォエラに、ルイズが慌てて釘を刺した。
「シ、シエスタの話でわかってくれたとは思うけど、あんまり派手なことはしないでよ。
あなたがすごいのは今朝の話でちゃんと理解してるから、天使の力を見せびらかすみたいな戦い方はしないでちょうだい。
出来るだけ平民の戦士みたいな戦い方で……、相手に怪我をさせないで、なるべく目立たずに勝ってよね!」
その言葉を聞いたラヴォエラは、また不思議そうに首を傾げた。
「もちろんよ。私、自分の生まれつきの力を見せびらかしたいなんて、思ったこともないわ。
ねえ、私って、そんなことで威張るなんていう傲慢の罪に塗れるようなことをするほど、悪い人に見えるのかしら?」
そういって、腰に差した鎚鉾を示す。
これで戦うから安心して、ということだろう。
「ご、傲慢の罪……?
い、いや、分かってればいいのよ!」
いちいち大げさなことを真顔で、いたって自然に口にするラヴォエラに、ルイズは何だかまた不安になってきた。
善良で清らかなのはわかるが、どうも天使の感覚というのは人間のそれとは相当にずれがあるらしい。
(この天使に任せといて、本当に大丈夫なのかしら……?)
とはいえ、シエスタとギーシュだけでメイジを3人も相手にするのは難しいだろうし、彼女以外に頼れる相手もいない。
キュルケは手出しをする気は無さそうだったし、自分が名乗りを上げたところで勝つのは難しかっただろう。
ルイズは胸に一抹の不安を抱えながらも、それ以上どうする術もなく、ラヴォエラとシエスタの後に続いて決闘の場へ向かった……。
・
・
・
結論から言えば、ラヴォエラは確かに約束を守った。
彼女は変身を解いて天使の正体を現しはしなかったし、ロレーヌらをこっぴどく痛めつけたりも、派手な魔法を放ったりもしなかった。
でも目立った。
異常なほど目立った。
ラヴォエラはまず、決闘が始まるや否やロレーヌら3人に説教を始めた。
悪事を行なえば魂が永遠の救済から外れるだの、善行を成せば必ずや報いがあるだの……。
平民がメイジを相手に怯える様子もなく、いきなり説教である。
初っ端から物凄く目立っていた。
-
当然ながら、ロレーヌらがそれで感動して戦いを止めたりなどしようはずもない。
ロレーヌはまた挑発か侮辱の類だと解釈して激昂し、残る2人は怖じ気づいた平民の命乞い代わりの戯言だと考えて嘲った。
そして、ロレーヌの『エア・カッター』と、彼の悪友の『ファイアー・ボール』が、返答の代わりにラヴォエラを目がけて飛んできた。
ラヴォエラはそれらの攻撃を避ける間もなく、まともに食らったように見えた。
しかし、彼女の身体に当たる寸前に、呪文はまるで水滴のように弾けて掻き消えてしまったのである。
ロレーヌらは驚愕して、さらに『ウィンド・ブレイク』、『エア・ハンマー』、『フレイム・ボール』などの攻撃呪文を乱発した。
だがそれらの呪文も、ことごとくラヴォエラの身体を傷つけることなく、霧散して消えていく。
彼女の持つ生来の超常能力、《防御のオーラ》によるものであった。
そこへ、残る1人が作り出した3体の青銅製のゴーレムが向かってきた。
ギーシュのワルキューレよりも出せる数は少ないようだが、身長2メイル以上もある屈強な男の姿をしている。
呪文は効かずともゴーレムの拳ならばあるいは、と望みをかけたのであろう。
ギーシュがワルキューレを作り出して食い止めようとするよりも先に、ラヴォエラが自分から進んでそちらの方へ向かって行った。
相手がゴーレムならば武器を使って戦う限りは遠慮なくやっていいだろうと、張り切って自前のメイスを構える。
振るわれたゴーレムの腕を掻い潜り、懐へ素早く飛び込んだ彼女は、その得物を思いきり叩き込んだ。
ゴシャア! ……と金属が潰れる大きな音が響き、ゴーレムの巨体が一撃でひしゃげて吹き飛んでいく。
ごく平凡な体躯の人間の女性の外見からは、信じられないようなパワーであった。
アストラル・デーヴァの筋力はライオン以上で、どんな姿に変身していようともその身体能力は変わらないのである。
彼女はそのまま素早く残り2体のゴーレムにも飛び掛かって立て続けにメイスを振るい、ほんの数秒の間に粉砕して土に還してしまった。
自分たちの呪文がことごとく通じず、ゴーレムも粉砕されたのを目の当たりにしたロレーヌらは、完全に怯えきって戦意を喪失した。
ラヴォエラは確かに約束の通り、相手を痛めつけることなく勝ったのである。
シエスタとギーシュは殆ど呆気にとられていただけで、何をする暇も、またその必要もなかった。
さて、その一部始終を見ていた観客たちは、当然のごとくざわざわと騒ぎ始めた。
「……お、おい。あの子に当たった呪文が全部消えてったぞ、一体どうなってんだ?」
「ルーンを唱えてる様子はないし、杖も持ってない……。まさか、先住魔法か?」
「で、でも。確か先住魔法だって、詠唱や身振りは必要だって……」
「おまけになんだよ、あのパワーは。武器の達人だとかそういう問題じゃねえぞ、オーク鬼かよ!」
「あのメイド、実はエルフの魔法戦士とかなんじゃないのか!?」
ルイズは、それを見て頭を抱えた。
おそらく彼女としては、『約束通り武器だけで戦ったし傷つけずに勝ったわ、目立ってないでしょ?』というつもりなのだろうが……。
もうどうしようもないくらいデタラメに目立っている。絶対後で事情聴取される。
お前のような平民がいるか!
そんな周囲の騒ぎや嘆きを他所に、キュルケただ一人だけが、楽しげに眼を細めて拍手を送っていた……。
-------------------------------------------------------------------------------
-
(元はといえば、あの時あんたが目立ちまくったのが、今回の問題の始まりだったのよ……)
ルイズは事の経緯を思い返しながら、心配そうに背中をさすってくるラヴォエラをじとっとした目で睨んだ。
あの決闘の後、当然の成り行きとして教師に呼び出され、オールド・オスマンの前で事情を説明し……。
とりあえず、エルフの魔法戦士などという剣呑な存在でないことだけは皆の前で学院長に保証してもらい、どうにか騒ぎは収まった。
ではなんなのか、という話については、学院長が『まあ、天使のようなモノかのう?』などと冗談めかして誤魔化していた。
ラヴォエラは決闘の後、宣言通りにロレーヌらを改心させようと頻繁に彼らについて回り、説法などを聞かせているようだ。
今のところは“バケモノめいた恐ろしい相手”に付きまとわれて生きた心地もしないようで、改心どころではなさそうだが。
シエスタの使用人仲間の間では、ラヴォエラは『我らの天使』で通っている。
怪我人や病人が出た時に治してやったり、永久に燃え続ける炎のような灯りをプレゼントしたりした結果、そう呼ばれるようになったのだ。
どうせ人外の力を持っていることは知られてしまったのだから、正体はともかく力は今更隠してもしょうがないと、ルイズも容認していた。
そんな感じで、決闘以降はどうにか大きな騒ぎもなく過ぎて来たのだが……。
しかし、やはり目立ち過ぎてどこかから情報が広まっていたものか、つい先程王都の方から手紙が届いた。
その手紙の内容が、今し方ルイズに溜息をつかせた悩みの源だった。
『ルイズへ
今度の虚無の曜日にそちらへ行きます。
その時に、あなたの召喚したという亜人だか天使だかを私に見せなさい。
エレオノール・アルベルティーヌ・ル・ブラン・ド・ラ・ブロワ・ド・ラ・ヴァリエール』
王都トリスタニアの王立魔法研究所で、研究員として働いている上の姉が来るというのである。
ルイズは、昔から何かと厳しい上の姉のことが苦手だった。
エレオノールがやってきたときに、ディーキンが戻って来ていてくれさえすれば、問題はないだろうと思えた。
あの子なら、きっとうまくやってくれるはずだ。
しかし、その時にディーキンがまだ戻っていなくて、ラヴォエラが彼女と会ったら……。
何か問題が起こりそうな気しかしない。
(ディーキン、早く戻って来なさいよお……)
ルイズはもう一度溜息を吐くと、ベッドに突っ伏して枕に顔を埋めた。
結論から言えば、ルイズの望み通り、ディーキンは翌日にはルイズの元へ帰ってきた。
しかしながら、ラヴォエラはディーキンと入れ替わりですぐに元の世界へ戻るということは拒否した。
ロレーヌらを改心させないうちは還るわけにはいかない、というのである。
かくして、ラヴォエラはこの後もなおしばらくの間、ハルケギニアに留まる事になったのだった……。
-
《防御のオーラ(Protective Aura)》:
エンジェルが常時身に纏っている、自分や仲間を守る周囲半径20フィートの超常の力の場。
悪の存在による攻撃に対して、このオーラの範囲内にいる者はACに+4の反発ボーナスとセーヴィング・スローに+4の抵抗ボーナスを得る。
また、範囲内にいる者に対する魅惑や強制の精神作用効果、および憑依の試みは自動的に妨げられる。
善ではない招来された存在は、このオーラに守られた者から攻撃されない限り、オーラの範囲内に入り込むことができない。
加えて、このオーラの範囲内や範囲内にいる者に影響を及ぼそうとする、呪文レベルが3レベル以下のすべての呪文は無効化される。
このオーラは解呪され得るが、エンジェルは自身の次のターンに、ただそうしようと思うだけで即座に再稼働させることができる。
---------------------------------------------------------------------
今回は以上になります。
できるだけ早く続きを書いていきますので、次の機会にもまたどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、失礼しました……(御辞儀)
-
otudesu
-
お前のような平民がいるかw
-
up乙
-
乙
いやあ、どんなややこしい事態になるかとても楽しみ…
げふん、ルイズが心配だw
-
こんばんは、焼き鮭です。今回の投下をします。
開始は20:14からで。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第八十三話「才人の秘密」
羽根怪獣ギコギラー 登場
「あー、今日は疲れたなぁ……」
夜、才人はルイズの部屋で大きなため息を吐きながらぼやいた。本日は朝から二大怪獣と
戦ったと思えば、突然学院にやってきたクリスに振り回されてヘトヘトであった。
一方で、ルイズは不機嫌そうな様子であった。
「……ルイズ、まだ怒ってんのか?」
「お、怒ってなんかいないわ!」
「怒ってるじゃん。まだクリスのこと気にしてるのか?」
才人に指摘されると、ルイズは若干ムキになる。
「そんなわけないでしょ! そ、そういうあんたこそッ! クリスのこと、そんなに気になるの!?」
「気になるっていうか、何だかとんでもないことになりそうだなーって思うだけだよ。何せ姫君だろ?
しかも、ちょっと変わってるしさ」
「そうね。王女自ら留学なんて驚きだわ。どんな事情があるのかしら……」
その意見には、ルイズも同感であった。
「まぁとにかく、俺は疲れたしもう寝るわ。おやすみー」
「ええ、おやすみ」
才人とルイズは並んでベッドに入る。疲れ気味の才人は、すぐに眠りに落ちていった……。
……怪獣クレッセントをやっつけた俺とゼロ。そして俺たちはどうにか学校に間に合うことが出来た。
「はぁ……はぁ……。何とか遅刻しないで済んだみたいだな……」
「もう、毎朝毎朝ギリギリですよ……」
苦言を呈してくるシエスタ。そ、そう言われると耳が痛い……。
でも、何だかんだで間に合っただろ? しかも、怪獣と一戦交えたにも関わらずさ。割と時間に
余裕あるんじゃないかな? ……っていうか、ありすぎな気もする。あれから大分時間が経ったような
感覚があるんだよな。一日分くらい? いや、それは時間経ちすぎか……。
なんて思っていたら、俺たちの後から校門をくぐってくる人たちがいた。それも、片方は先生だ。
「あッ、あの先生はウチの担任じゃないか。名前は……」
何て名前だったっけ……。担任の名前が出てこないって、俺ってそんな記憶力悪かったかな……。
「そうそう、矢的先生! 矢的先生と一緒にいる奴は誰だ?」
矢的先生は外国人の生徒を一人連れていた。ぽっちゃりとした体格……オブラートに包まずに
言うとデブだ。まるでマリコルヌみたいだな。いや、マリコルヌ以上だ。
シエスタが俺の疑問に答えた。
「確か、オリヴァンという男子ですね。何でも、ここ最近登校していなかったそうです」
「登校拒否って奴か。外国からの留学生なのに、世知辛いな」
「多分、それで先生が迎えに行ったんでしょうね」
俺は矢的先生とオリヴァンとかいう男子に注目する。
「……先生、ぼく、やっぱり学校に行くの嫌だよ。みんなぼくをいじめるんだ……」
オリヴァンはかなり弱気で、びくびくとした奴だ。あんな態度じゃあ、いじめっ子に目を
つけられるのも無理はないだろうな。
先生はそんなオリヴァンに言い聞かす。
「オリヴァン、勇気を出すんだ。勇気を出してぶつかっていけば、みんなの見る目も変わるよ。
人間、誰だって勇気を持ってる! オリヴァンにだってもちろんあるとも。それを表に出すのは、
何も難しいことじゃないさ」
「でも……」
説得されてもオリヴァンがうじうじしていたら……先生はいきなりその場で逆立ちをした。
-
「見ろ、オリヴァン。こうしてると、地球を支えてる気分になるんだ。地球をしょって立つ!
いやぁ、地球は重いが、出来ないことじゃないぞ。これに比べたら、人にぶつかっていくことなんて
簡単なもんさ」
先生が説いていると、校舎から一人の男子が先生たちのところへ向かっていった。……高校生と
いうより、中学生みたいな背丈だなぁ。
「先生、クラスを代表してオリヴァン君を迎えに来ました」
「おぉ塚本、ありがとう。ほら、オリヴァン、お前を心配してくれる人だってちゃんといるんだぞ。
お前は一人じゃない!」
「オリヴァン君、教室に行こう。みんな待ってるよ」
先生と塚本という男子の二人の説得で、オリヴァンもようやくうなずいた。
「……うん」
……先生って大変なんだなぁ。でも矢的先生は困った奴にも体当たりの指導をして、いい先生だ。
っと。俺たちもそろそろ教室に行かないとな!
俺とシエスタは降車の中へ入っていき、下駄箱で上履きに履き替えた。
「それにしても、今朝ぶつかってきた子は何だったんだろうなぁ。ぶつかってきて、謝りもせず
行っちまうなんて、失礼な奴だったが」
「でも、かわいい子でしたよね」
「それはまぁ、そうだったけど……」
シエスタのひと言に、つい同意する俺。見た目だけなら、俺の好みのど真ん中なんだけどなぁ……。
と思っていたら、シエスタがこっちをじっと見つめているのに気づいた。
「シエスタ、どうした?」
「……前から思ってたんですが……サイトさんは、ああいう小さな女の子が好きなんですか?」
「ぶはッ!」
シエスタが変なことを言うので、思わず噴き出してしまった。
「いきなり何言ってんの!? 別に俺は小さな女の子がタイプとかじゃなくて……」
弁解しようとしたら……いきなり背後から誰かに飛びかかられた! 更にふくよかな胸に
頭が押しつけられる!
「ダーリーンッ!! おはよう!」
「うわッ!? キ、キュルケ!」
今飛びついてきたのはクラスメイトのキュルケだ。俺を「ダーリン」なんて呼んで、毎朝
抱きついてくる……んだったかな。個人的にはそうであってほしいが。
「もう、キュルケさん! 毎朝毎朝……! サイトさんから離れて下さい!」
「あら、いやよ。あたしの中のダーリン分が空っぽなの。だ・か・ら、ダーリン分を充填しなくちゃ!」
抗議するシエスタに、キュルケは訳が分からん理屈を並べた。ダーリン分って何だ。俺はサプリメントかッ。
うお、本気で息が苦しくなってきた……! さすがに命の危機があるので、俺は力尽くで
キュルケから離れる。
「あん、ダーリンったら。無理矢理離れたりしちゃ、ダメ」
唇を尖らせるキュルケ。その後ろには、眼鏡をかけた小柄な女の子が控えている。同じく
クラスメイトのタバサだ。口数少なくて、何を考えているのかよく分からない。
「もう、キュルケさんったら! サイトさんをぎゅーってしていいのは、幼馴染であるわたしだけなんですッ!」
シエスタはシエスタで、こっちも訳が分からん理屈をのたまっていた。そんなの、されたことないけど……。
「全く、二学期になっても毎朝毎朝、よくも飽きずに同じことやれるわね、あなたたち」
通り掛かった金髪縦ロールの女子が呆れ気味に言った。モンモランシーだ。
その彼氏のギーシュもやってくる。
「みんな、おはよう! 爽やかな朝だね! まるで、このぼくのように!」
-
「……ギーシュ。お前はどこの世界でも変わらないな」
「どこの世界でも? 何を言ってるんだ、きみ?」
ギーシュにツッコまれた。あれ、内から沸き上がった台詞をつい口に出してしまったが、
俺は本当に何を言っているんだろうか。
「そこのあなたたち! いつまでも廊下でたむろしてないで、早く体育館に移動して下さい。
始業式始まりますよ。もう、二学期になっても相変わらずなんだから」
朝から騒々しい俺たちに、クラス委員長の春奈が呼びかけてきた。いっけね、もうそんな時間か。
俺たちは雑談を打ち切って体育館へと移っていって、始業式に出席したのだった。
「みんな、始業式でも話があったように、今日から二学期が始まるぞ。全員、夏休み中は元気でいたかな?」
始業式が終わると、教室でホームルーム。矢的先生は本当に熱血さが全身から溢れ出ている先生だなぁ。
「それで、二学期最初の授業と行く前に、みんなに一つお知らせがある」
ん、お知らせ?
「実は今日から、このクラスに新しい友達が加わることになった。つまり転校生だ!」
おお、転校生とは。俺の前の席のギーシュが、女の子か!? と興奮して隣のモンモランシーに
たしなめられた。
「早速紹介しよう。さぁ、入ってきてくれ!」
矢的先生が廊下に向かって呼びかけると、扉が開かれて転校生という子が教壇に上がってきた……
って、あの子は!?
「し、失礼しますッ!」
あの子は、朝ぶつかってきた女の子じゃないか! う、嘘だろぉ!? 同じクラスになるなんて、
どこのラブコメ漫画だよ!
「ル、ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエールです。ルイズって呼んで下さい」
長い名前だな……。まぁ、このクラスの奴らも大概長いのが多いけど。ここは日本のはずだよな?
……まぁ、いいか。
「この度、父の仕事の都合でこの街に引っ越してきました。まだ分からないことだらけなので、
色々教えて下さい」
かなりしおらしいな……。朝とはまるで別人だ。日頃からあれだけ大人しければ……。
ん、日頃から? あいつの日頃なんて知らないだろ、俺。おかしいな、妄想癖に目覚めたのか?
矢的先生がルイズの紹介をする。
「ルイズ君のお父さんは外交官をされていて、今回、お仕事の都合で転校してきたんだ。
みんな、仲良くするんだぞ」
「はいはい、先生! 手前どもにどうぞお任せあれ!」
小気味よく返事をしたのは、通称落語。博士、スーパー、ファッションの四人組でよく行動している
クラスメイトだ。……あいつらも塚本同様、高校生というよりは中学生っぽいんだよなぁ。
「さて、ルイズ君の席だが……平賀の隣がちょうど開いてるな。そこに座るといい」
「はい」
げ! こっち来るのかよ……。こういう時って、どんな顔をすればいいんだ? とりあえず、
ギーシュを見習って無駄に爽やかな感じで、朝のことなんて気にしてませんよー的に振る舞おう……。
そう決めた俺は、こっちに近づいてきたルイズに、爽やかな感じで話しかけた。
「よ、よよよ、よう」
駄目だった! 思いっきりどもったよ! 爽やかさ、微塵もなかった!
「ああああああああ!! あんたは!?」
俺のことに気づいたルイズは大声を上げた。それで矢的先生が笑う。
「何だ、平賀はもうルイズ君と友達だったのか。それならちょうどいい。平賀、お前がルイズ君に
色々教えてやってくれ」
ええッ!? 何か先生に変な誤解をされている!
「俺がですか!?」
「こんな奴にですか!?」
-
ルイズが如何にも不満げに言い放った。俺の台詞を真似するんじゃないよ!
「はっはっはっ! 息もぴったりだな」
先生、勘弁して下さいよ! どこを見ればそう見えるんですか!
ルイズはきっと俺をにらんでくる。
「あんた、何でこんなところにいるのよ!」
「何でって、ここの生徒だから当たり前だ!」
言い返してやったら、ルイズはとんでもないことを言い出した。
「……やめなさい。そ、そそそそ、即刻、た、退学しなさいッ!」
「む、無茶苦茶言うなぁ!」
「命令よ! 退学なさいッ!」
「断るッ!」
「二人とも、その辺にしなさい。ルイズ君、席に着いて」
口喧嘩する俺たちを先生がたしなめた。
「でもッ!」
「席に着くんだ。授業が出来ないだろう?」
「矢的先生の言う通りですよ、ルイズさん。学生は勉強が本分です。平賀君と何があったか
知りませんが、お話は授業の後にして下さい」
博士も諭した。あいつは俺とは大違いの優等生だな。
「……はい」
やっと静かになったルイズは、しぶしぶと俺の隣の席に腰掛ける。くっそー、これから
こいつが隣なのかよ……。どうしてこうなるんだか……。
そうして二学期最初の授業が始まったのだが……途中で、外に異常が発生した!
「ギャオオオオオオオオ!」
「!? 今の音は……!」
突然、窓の外から飛び込んできた咆哮の音に教室は急激に騒然となった。そして外を見やると、
「ギャオオオオオオオオ!」
空の彼方から、真っ赤な眼をした青黒い怪獣が、腕と一体化している翼を広げて滑空しながら
こっちへと迫ってくるところだった! 顎の皮膚がだらりと下に伸び、顎髭のようになっている。
端末で調べると、あれは羽根怪獣ギコギラーという奴のようだ。かなり凶暴な性質の怪獣だ!
くそッ、今日は何て日だ。一日に連続して怪獣が現れるなんて! ……同じ一日だよな?
何故か自信がないんだが……。
「きゃああッ! 怪獣だわ!」
「うわああああッ!」
ファッションとスーパーが悲鳴を上げる。それを皮切りに教室内に騒乱が起こった。
他のクラスも同様だろう。
「みんな、落ち着くんだ! 避難訓練の時のことを思い出しながら、慌てず順番に避難するように!」
矢的先生が慌てる皆を鎮め、テキパキと指示を出してクラスを避難させていく。大分手慣れた様子だ。
先生、こういうの慣れてるのか?
『才人……!』
「ああ……!」
けれど俺は隙を見て、こっそりと皆の間から脱け出していった。もちろん、ゼロに変身して
ギコギラーを迎撃するためだ!
人気のないところを見つけてそこへ駆け込むが、念のためにキョロキョロ周囲を見回して、
周りが完全に無人であることを確認した。
『才人、確かに誰もいないだろうな?』
「ああ、大丈夫だ。ちゃんと確かめた」
『分かってると思うが、くれぐれも変身するところは見られないようにな。お前がウルトラマンに
変身するって誰かに知られたら、俺は地球にはいられなくなっちまうんだ』
-
「ああ。……?」
今のゼロの言葉に、俺は首をひねる。
『どうした?』
「いや、もう割と色んな人に知られてるような気が……」
『何言ってんだ、そんなことあるもんかよ。色んな人って誰だよ』
そう言われると……思い浮かんでこないな。どうしてそんなことを思ってしまったんだろうか……。
『おかしなこと言ってねぇで、変身だ! ギコギラーはもうすぐそこまで来てるぜ!』
「ああ、そうだったな! よし、行くぜ!」
ゼロに促されるまま、俺はウルトラゼロアイを装着して変身を行った!
「ジュワッ!」
俺から変身したゼロは、地上に降り立ったギコギラーの前に颯爽と立ちはだかる!
「ギャオオオオオオオオ!」
『ギコギラー、俺が来たからには、地球には指一本手出しさせねぇぜ!』
宇宙空手の構えを取ったゼロは、猛然とギコギラーに飛びかかっていった。
「ギャオオオオオオオオ!」
「シェアッ!」
ギコギラーの打撃をいなし、反対にチョップ、蹴り上げ等の猛襲で弱らせる。そして隙を見て
首投げを仕掛けた! 格闘の技量ではやっぱりゼロに軍配が上がる。
「ギャオオオオオオオオ!」
しかしギコギラーも怪獣の意地で、負けていない。翼を大きく羽ばたかせて、突風を巻き起こした。
『うおッ!』
さすがのゼロも風をいなすことは出来ず、姿勢が崩れる。そこを突いてギコギラーが地を蹴り、
飛びながらの両足蹴りを見舞った!
『ぐあッ!』
「ギャオオオオオオオオ!」
かなりの重量のあるキックに、ゼロは手痛いダメージを受けた。大きな翼を有するギコギラーは
飛行能力に優れる怪獣。そのため、どっしりとした体格に似合わぬ身軽な動きが出来るんだ。
重量とスピード、一見すると相反する要素を兼ね備えていることがギコギラーの強みだと、俺は分析した。
ギコギラーはまたフライングキックを繰り出してくる。今度はかわしたゼロだが、
『うッ!』
長い尾が首に巻きつき、ギコギラーに引きずり回されてしまう!
『ぐわぁぁぁッ!』
「ギャオオオオオオオオ!」
地面との摩擦で苦しめられるゼロ。どうにか尾の拘束から逃れるも、そこに口からの熱線を
叩き込まれて大ダメージを食らった。カラータイマーが赤くなる。
『ぐっはぁッ!』
『ゼロ、頑張れ! 俺も力を貸すぞ!』
ギコギラーの猛攻撃に追い詰められるゼロを応援する俺。更に念を込めて、ゼロに力を与えるぜ。
これが少しはゼロのパワーになってくれればいいが……。
『助かるぜ、才人。気合いが戻ってきたぜ!』
よし! ゼロの身体に力がみなぎってきた! ここから反撃の狼煙を上げるぜ!
ギコギラーはまた翼を羽ばたかせて突風を起こそうとするが、ここまででギコギラーの
手持ちの札はあらかた見た。もうお前の攻撃は、ゼロには通用しないぜ!
「セアッ!」
額のランプから緑色のレーザーが照射される。エメリウムスラッシュだ!
素早い光線の一撃がギコギラーの翼を撃ち、羽ばたきを阻止した。
「ギャオオオオオオオオ!」
ひるんだところでゼロは一気に相手の懐に飛び込み、みぞおちに強烈な横拳を突き入れた!
「セェェイッ!」
「ギャオオオオオオオオ!」
殴り飛ばされたギコギラーはかなりのダメージを負ったはずだ。この勢いで倒せるはずだ!
-
だがギコギラーは再度飛翔し、今度は全身を使った突進を繰り出してきた! 危ない、ゼロ!
『なぁに、これぐらい! おおおぉぉッ!』
ゼロのブレスレットが閃光を放ったかと思うと、ゼロの体色が真っ赤に染め上げられた!
『ストロングコロナゼロッ!』
超パワータイプの戦士に二段変身したゼロは、ギコギラーの突進を真っ向から受け止めた!
そして回転を加え、大空高くに放り投げる!
『ウルトラハリケーンッ!』
「ギャオオオオオオオオ!」
竜巻の勢いで頭上へ吹き飛んでいったギコギラーに、とどめの必殺技がぶち込まれる!
『ガルネイト、バスタァァァーッ!!』
真っ赤な噴火のような光線が刺さり、ギコギラーは空中で瞬時に爆散した! やった、ゼロの大逆転勝利だ!
『すげぇぜ、ゼロ! やっぱりゼロは強いな!』
『へへッ、これは俺たちの力だぜ。俺たち二人の力がありゃ、そんじょそこらの奴に後れは取らねぇよ』
嬉しいことを言ってくれるゼロ。だけど……二人、に何か違和感があるな。ここにもう一人が
加わっていたような……。いや、人? だったっけな?
変な疑問を抱いていたら、また視界が急激にぼやけてきた! くそッ、一体何だっていうんだ……!
「……んッ、ふあぁぁ……もう朝か……」
……朝が来て、才人は今日もルイズのベッドから起床した。
「んー……今日もまた地球の、日本の夢を見たような……。でも、どんな内容だったかな……」
はて、と頭を傾げる才人だが、夢のことは忘却の彼方にあり、どんなに首をひねっても
思い出すことはなかった。
-
今回はここまで。
矢的先生!
-
おつ
-
皆様、こんばんは。
よろしければ、また22:20頃から続きを投下させてくださいませ。
-
ここは、トリステインの王都・トリスタニアの王立魔法研究所(アカデミー)の一室。
ルイズの姉・エレオノールは、研究用のフラスコに入れた紅茶が沸くのを待ちながら、いらいらしたように机を指先で叩いていた。
彼女が苛立っているのは、最近態度が気に入らない婚約者のせいでもなければ、上から命じられた退屈な研究もどきの作業のせいでもない。
末の妹が召喚したという使い魔に関して、外部から入ってきた情報が問題なのだった。
「まったく、亜人だか天使だか知らないけれど……」
どうしてそんな重要な話を、さっさと自分に知らせなかったのか。
ようやく魔法が成功して使い魔が召喚できたというその一事だけでも、最も傍にいる身内の自分に知らせてきてもよさそうなものだ。
ましてや、そんな変わった使い魔が召喚されたなどという重要事を知らせようともせぬとは。
「この私に恥をかかせるつもりなのかしらね、あのおちびは……!」
普段研究に没頭していて市井の話には疎い部類の自分の耳にまで、その噂が届いてきた、ということは……。
王宮の中にも、もう既に知っている者がいるかもしれない。
ここは調査の命令が王宮側から来るよりも先に、自分の方でさっさと済ませておくべきだろう。
いざ問い合わせが来たときに、身内の使い魔に関してなにも把握していませんでしたなどというのでは、恥晒しもいいところだ。
(それに……)
あまつさえ、妹やその使い魔を妙な事に利用されでもしては、という心配もあった。
なんでもアンリエッタ王女は、近いうちにゲルマニアとの同盟のため、かの国の皇帝の元へ嫁ぐ予定になっていると聞く。
よりにもよってあんな野蛮な成り上がり者どもの国へ、伝統あるトリステインの王族が……、という思いはエレオノールにもあった。
だが、様々な状況を考えればいたしかたのないことらしいとも理解している。
浮遊大陸の『白の国』アルビオンでは、レコン・キスタと名乗る勢力が王権の打倒とハルケギニアの統一を宣言して革命を起こしている。
そして、既にアルビオンの王家を追い詰め、勝利を目前にしているのだという。
彼らの掲げる大義から推して、アルビオンを制圧した後には地上にある他の国家にも、遅かれ早かれ牙を向けてくるだろう。
その時に、真っ先に目標になるであろう至近の国はこのトリステインだ。
そして、小国に過ぎぬトリステイン一国の戦力では、到底アルビオン王家を滅ぼせるほどの戦力を持つ相手に太刀打ちできる見込みはない。
だから、そうなる前に王女を嫁がせることで、強い力を持つゲルマニアと軍事同盟を結んでおく必要がある、というわけだ。
聞くところによると、レコン・キスタの首魁であるクロムウェルとかいう男は、伝説の『虚無』の使い手だと主張しているのだという。
そのことが、王権の打倒という不遜な行いをするにあたって、彼らが掲げる大義名分のひとつであるらしい。
始祖が用いたという伝説の虚無が使える以上、始祖が認めているのは遠い末裔でしかない王族ではなく自分たちなのである、ということか。
にわかには信じ難い話だが、それで大勢の者がついてくるということは、その男は確かに虚無だと思えるような力を持っているのだろうか?
そのあたりの事情が、エレオノールの不安をなおさら強めているのだった。
「……天使、ねえ」
エレオノールはそう呟いて、壁にかけられた一枚の絵を眺めた。
それは、ハルケギニアの大地に降臨する始祖と、それを支える天使たちの姿を描いた宗教画だった。
始祖ブリミルにまつわる神話の一場面、『始祖の降臨』を描いたものだ。
「天使は神の御遣いであり、天より降臨した我らの始祖を導き、守護した存在……。本当なのかしらね?」
神話の真偽はともかくとしても、もし仮に、天使が今現在このトリステインに降臨しているということになれば。
それは、始祖の加護が今もなお王権の側にあるということの、強力な証拠となり得るのではないか?
ならば、もしもルイズの呼び出したという天使が、『本物』だったならば。
あるいはそうでなくとも、少なくとも本物だと言い張れそうな程度に珍しく強力な能力を持つ、亜人か何かの類であったならば……。
この切羽詰った状況で、王宮の者たちがそれを利用せずに、ルイズとその使い魔を放っておくなどということがあり得るのだろうか?
-
それは、ある意味では歓迎すべきことなのかもしれない。
レコン・キスタを打倒し、このトリステイン王国の命脈を保つことは、言うまでもなくエレオノールとて大いに望んでいる。
長年魔法を使えず、蔑まれ続けてきた末の妹にとっても、大きなチャンスだといえるかもしれない。
だが、そのために大事な妹を戦争沙汰に巻き込み、危険な目に遭わせることになるかもしれぬとなれば……。
そうそう安易に、肯定することはできなかった。
「はあ……、まったく、あの子はいくつになっても世話が焼けるんだから」
エレオノールはひとつ溜息を吐くと、ぶつぶつと愚痴をこぼした。
普段は厳しい態度で接してはいるが、エレオノールは自分なりに妹たちのことを大切にしているのである。
魔法の研究者としての道を志したのも、元々は上の妹の病弱さと下の妹の魔法が使えないのを何とかしてやりたいと思ってのことだった。
幸いにして、今、姫殿下と枢機卿は、皇帝を訪問するためにゲルマニアへと赴いているはずだ。
王宮でも最重要の人物であるこの2人の耳には、今回の話はまだ入ってはいまい。
とにかく、虚無の曜日になって仕事から解放され次第、まずは研究員としてではなく姉としてルイズを訪問する。
そうして自分の目で真偽のほどを確かめ、状況を判断することが先決だろう。
その結果が何でもなければそれでよし、もしそうでなければ、それから改めて王宮への報告をどうするかなどといったことを検討しよう。
エレオノールはそう結論すると、丁度沸いた紅茶を携え、気持ちを切り替えて仕事に戻っていった……。
-------------------------------------------------------------------------------
ディーキンとタバサが学院に帰還した、その日の夜。
学院の授業が終わると、ルイズ、キュルケ、タバサ、シエスタは揃って王都へ出かけ、『魅惑の妖精』亭の一室に集まった。
もちろん、今回の件について情報を交換し合い、共通理解を図るためだ。
オルレアン公夫人も同席している。
ちなみに、ラヴォエラは学院で留守番である。
今頃はまた、ロレーヌらに説法を聞かせてでもいることだろう。
ディーキンはといえば、ルイズから席を外す許可を得て、久し振りに酒場の方で詩歌などを披露していた。
かねてからの約束通り、学院長秘書あらため“新入りのきれいな大妖精さん”のミス・ロングビルと共演して大盛況を博しているようだ。
なんだか面白そうだと興味を持ったシルフィードも、人間に化けてそのお手伝いしていた。
ルイズらは、ロングビルが学院長秘書という立派な役職を捨て、このようないかがわしい趣の酒場で働き出したことに驚いていたが……。
きっと詮索してはいけない事情があるに違いない、と解釈して、それについて本人に問い質すようなことはしなかった。
タバサだけはその事情を立ち聞きして知っていたのだが、元より彼女が口外などしようはずもない。
トーマスはディーキンに進められたとおり、早速ディーキンの演劇の幕間に手品の披露をしている。
ディーキンやロングビルが助手を務めて、客からの評判も上々のようだ。
ペルスランは、酒場で一般の客に交じって飲んでいる。
長年ただ一人で仕事をし続けてきたのだから、今夜くらいは仕事から離れてくつろいでほしいと夫人から勧められたのだった。
「ふうん、まさかあなたが、ガリアの王族だったなんてね。
それに、よく何日も外出してたのには、そんな事情があったなんて……」
タバサの境遇を聞いたキュルケは、感心したようにそういうと、うんうんと頷いた。
シエスタは、流石は私の先生だと、ディーキンの功績に感動しているようだ。
-
ルイズはといえば、まずタバサの身分に驚き、次いでその話に心を動かされ。
それから、自分のパートナーであるディーキンの功績が誇らしいような、立場がないような、複雑な気持ちになり……、と忙しかった。
「……でも、それはまあ、無理に聞く気はなかったけれど。
私にこれまでなんにも教えてくれなかっただなんて、水臭いわね」
「ごめんなさい」
「別に、謝らなくてもいいけど……」
キュルケは、母親の傍らでしおらしく頭を垂れるタバサの姿を、微笑ましげに眺めやった。
(この私にも内緒にしていたことを、ディー君には教えるだなんてね)
それはもちろん、彼が母親を治せる手段を持っていたから、というのもあるだろうが……。
それにしても、一年ほどの付き合いになる自分にも教えなかったことを、この内向的な友人が一月にも満たない付き合いの男に教えるとは。
おまけにタバサの彼に対する雰囲気が、出かける前とは明らかに違っている。
もちろんそれについても、母親を救ってくれた恩人に対して態度が変わるのは当たり前だろう、ともいえるが……。
何というか、距離が近くなった感じがする。しかも時々、ちらちらと彼の方の様子を伺っている。
この、他の人間すべてに対して無関心なように見えた友人が、だ。
(これは微熱なんてもんじゃないわ、相当ぞっこん惚れ込んでるわね)
と、キュルケは以前からの確信をより確かなものにしていた。
タバサの親友と自負している身としては、自分を差し置いて、といった悔しさのようなものも少しはある。
だが、タバサやディーキンを見守る目はあくまで優しい。
キュルケは、振る舞いこそ奔放とはいえ、大切な友人の幸せを心から祝福できる人間なのだった。
「シャルロットに知らない間にこんなに大勢お友達ができていたなんて、嬉しいわ。
皆さん、どうかこれからも、娘のことをよろしくお願いします」
オルレアン公夫人が微笑んで頭を下げる。
「ええ、もちろん」
「はい、御夫人。こちらこそ、光栄ですわ」
キュルケは朗らかに会釈し、ルイズは丁寧に一礼して、その言葉に応える。
「わ、私のような平民が、王族の方からそのような……」
自分に対してまで頭を下げられたことに、シエスタが恐縮してその十倍くらいぺこぺこと頭を下げ返した。
それを見てルイズは苦笑し、キュルケはからからと笑う。
タバサも、微かに顔を綻ばせていた。
5人の女性たちはそのまま、しばし和やかに歓談して時を過ごした。
-
・
・
・
「それにしても、酷いわね!
王族ともあろう者が、身内に対してそんな仕打ちをするなんて……」
ルイズが紅茶とクッキーをつまみながら、ぷんすかと腹を立てた様子でそういった。
だいぶ打ち解けてきて、話題がそういったデリケートな内容に及んだのだ。
キュルケも、それに同調する。
「まったくね……。
しかも、そんな仕打ちをしておきながら、面倒事が起こるたびに始末を押し付けるだなんて!」
普段は悠然とした微笑みを湛えている顔に、その系統に相応しい炎のような怒りの色が浮かんでいた。
そこでシエスタが、努めて明るい声で口を挟んだ。
「でも、先生のお陰でこうして夫人もお元気になられましたし。
これでもう、シャルロット様が危険なお仕事をされる必要もないですわ!」
シエスタも、もちろん少なからぬ義憤を感じてはいる。
だが、せっかくの和やかな雰囲気を壊して、ようやく元に戻ったばかりの夫人に早々にまた辛い思いをさせるのもどうか、と思ったのだ。
しかし、それを聞いたタバサは、静かに首を横に振った。
「そうはいかない。私が命令に従わなくなれば、王室から疑いがかかる」
タバサは、何か言いたそうな曇った顔で自分を見つめてくる傍らの母に対して心苦しく思いながらも……。
半ば決別するようにきっぱりと、深々と頭を下げた。
「申し訳ありません、母さま。
ですが、王室の敵どもを討たない限り、いつまた私や母さまの身が脅かされるかもしれません。
シャルロットは、父さまの仇を討つまでは戦い続けると、杖に誓いを立てました」
「シャルロット……」
オルレアン公夫人はそれを聞くと、悲しげに呻いて首を横に振った。
そして、愛娘の体をぎゅっと抱き寄せる。
「いいえ、復讐などを考えてはなりませぬ。
私は母として、あなたが国を2つに割きかねない戦いを起こすところなど、見たくはありません」
「母さま……」
「そもそも、シャルルがジョゼフ殿下に討たれたなどという証拠がどこにあるのです?」
「……え?」
タバサは、思いがけない言葉に、戸惑ったように母を見上げた。
「いえ、仮にシャルルが、間違いなくジョゼフ殿下に討たれたものだとしても……。
あの人にもその原因が、罪がなかったなどと申せましょうか」
そうしてオルレアン公夫人は、タバサがこれまで思ってもみなかったような話を語り始めたのだった……。
-
短いですが、今回は以上になります。
またできるだけ早く続きを書いていきますので、次の機会にもどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、失礼しました……(御辞儀)
-
皆さんこんにちは。ウルトラ5番目の使い魔36話投下準備できましたので始めます。
-
第36話
五十万エキューの転成
海凄人 パラダイ星人
古代怪獣 キングザウルス三世 登場!
「小娘が、確かに並のメイジではないようだが、貴様一人で我ら空中装甲騎士団三十人を倒せると思っているのか?」
「ええ、確かに普通にやりあえばわたくし一人では敵わないでしょうね。でも、今のあなた方なら話は別ですわ。教えてあげるから光栄に思っていいわよ、刈り取られる快楽というものを」
ハルケギニア最強格の竜騎士団を、ひとりの少女が笑っている。
彼女の名前はジャネット。ガリア北花壇騎士の中の一団、通称元素の兄弟のひとり。コルベールとベアトリスの暗殺の命を受けてこの街へとやってきたが、偶然エーコたちと空中装甲騎士団の戦いを目の当たりにして気まぐれを起こし、エーコたち水妖精騎士団に味方するために飛び入ってきた。
しかし完全武装の兵団を相手に、いかにも戦闘に不向きそうなドレスをまとった少女がどうやって勝とうというのであろうか。ジャネットは傍らに立つエーコに視線を向けると、命令するように言った。
「あなたがリーダーね。そういうわけだから、わたしの言うとおりに動きなさい。そうしたら勝たせてあげる」
「なっ! 突然現れて、あなたいったい何様のつもりなの? わたしたちは姫様以外の命令を受けるなんて」
「勝ちたいの? 負けたいの? 嫌ならわたしは帰るけど?」
「う、お、お願いします……」
「よろしい、素直な子は好きよ」
ジャネットは無邪気そうな笑みを浮かべると、教師が生徒を褒めるときのように優しくうなづいてみせた。
しかし、次の瞬間には小動物を見下ろす猛禽のような鋭い視線となってエーコたちを見返してきた。
「あなたたち、戦い方は素人だけどこういう場面ははじめてじゃないようね。ただまあ、あなたたちはいいけど、そっちでまだ腰を抜かしているカカシたちはねえ?」
見ると、エーコたちの後ろでは水妖精騎士団の少女たちが、まだ決心がつかないというふうに震えていた。
だが無理はない、どんなに頭に思っても、戦いはつらいもの、怖いもの、痛いものだ。今日はじめてそれを知ったばかりの彼女たちを責めるのは酷でしかない。ただし、人生とはその繰り返しでもあるのだ。
「あなたたち、あなたたちみたいなのでも、今は人手が足りないから手伝いなさい」
「えぅ、で、でもわたしたちみたいなのじゃあ」
「大丈夫よ、わたしの言うとおりにするだけでいいから。わたし、これでも結構強いほうだから、悪いようにはしないわ」
ジャネットの誘いにも、少女たちは迷っているようだった。それも無理はない、相手は自分たちより少し年上に見えるだけの少女で、身なりからして戦うようにはとても見えないからだ。
だが、敵を無視して悠然と少女たちと話しているジャネットに対して、空中装甲騎士団は怒りで答えた。
-
「貴様、我々をなめているのか!」
騎士のひとりが放ったウェンディアイシクルの氷弾がジャネットを襲った。あのタバサも得意としている水と風の強力な攻撃魔法、高速で鋭くとがった氷の弾丸を複数同時に撃ち出して敵を打ち据える。普通の人間が食らえば、よくて大怪我、下手をすれば死に至る。
だがジャネットは避けるそぶりも見せずに、唯一腕を上げて顔をかばうだけで、氷の弾丸のすべてをその身で受け止めてしまった。
当然、声にならない悲鳴が少女たちからあがり、エーコやティアたちも思わず顔をしかめた。蜂の巣だ……あれではとても、と、誰もが思った。が。
「ひどいわねえ、レディの会話に割り込むなんて男の風上にも置けないわ」
「なっ、なんだとお!」
空中装甲騎士団から驚愕の声が響いた。なんと、ジャネットに当たったウェンディアイシクルは、そのすべてがはじき返されるか砕け散ってしまって、一本たりともジャネットに傷を与えたものはなかった。ドレスにすら破れ目もついていない。
ジャネットは体に残った氷の破片を手で払って、にやりと笑って見せた。凶暴な、強者が弱者を見下すときの侮蔑しきった目である。
「いっ、いったい何をした貴様?」
「別に、たいしたことじゃないわ。魔法が当たる直前に、当たるところに『硬化』をかけただけよ。大抵の攻撃なら、これでどうにでもできるわね」
簡単そうに言っているが、それが理論上はともかく現実的には不可能に等しい神業なのはここにいるほぼ全員がわかっていた。なぜなら、魔法は詠唱をはじめてから発動して効果を得るまでにどんなに鍛えても時間差が生じ、ジャネットの言うようにやろうとしても、硬化が働く前に氷の弾が刺さってしまっていることだろう。車に例えれば、空走距離も制動距離もなく停車しろと言っているに等しい。こんな真似は、空中装甲騎士団の猛者たちでさえ、できない。
しかし、ジャネットはいともたやすくその神業を成功させてしまった。
何者なんだ、この女は!? ティラとティアを除く、メイジの心得のある全員がそう思って戦慄するが、ジャネットは気にした風もなく少女たちに言った。
「さて、これでわたしのことは少しは理解してくれたでしょ。もう一度だけ聞くわよ、杖をとる? それとも汗臭い男たちに頭を下げて逃げ帰る?」
ジャネットの問いかけに、少女たちはあどけなさの残る顔に、ぐっと決意を込めて立ち上がった。
「やります、勝たせてください」
「ふふ、いいわ、あなたたちのその表情すごくいい。じゃあ、パーティをしましょう。楽しくね」
楽団の指揮をとるようにジャネットが杖を振り、水妖精騎士団はついに全員が集合した。
対峙するふたつの騎士団。だが、ジャネットの存在におじけずく空中装甲騎士団を見かねてか、空から数騎の竜騎士がドラゴンに乗って降り立ってきた。
-
「なにをしているか、こんな子供らを相手に!」
「こっ、これは軍団長殿!」
それはベアトリスの元にやってきていた空中装甲騎士団の指揮官だった。兜の中からのぞく壮年の顔立ちには威厳が溢れ、カイゼル髭を伸ばした風貌は一目で強そうと誰もが感じた。
彼らはドラゴンから降り立つと、自ら先頭に立って杖をかざしてきた。指揮官が帰ってきたことで、空中装甲騎士団も士気を取り戻す。
こんな相手に、どうやって勝てというのか? 少女たちの問いかけに、ジャネットは楽しそうに微笑んで言った。
「そう緊張した顔しないでいいわ。パーティはほら、楽しくやるものよ? 震えた唇からは心に響くソナタは出てこないの。歌うように奏でるように、魔法はハートよ、それがすべての基本だからね」
「そんなの子供でも知っているわよ。そんなことより、わたしたちのつたない魔法で、どうやってあの人たちに勝つのか、早く教えてよ!」
「慌てない慌てない、あの騎士さんたちは親切にも竜騎士の一番の武器であるドラゴンから降りて戦ってくれる人たちよ。むしろ勝ってあげなきゃ失礼なんだから」
そう、これまでまがりなりにも水妖精騎士団が空中装甲騎士団とやりあえている理由はそれが大きかった。重い鎧は高い防御力を誇るが、地面の上では重石に等しく、動きが大きく制限されてしまう。重装備はドラゴンに乗って飛び回っていればこそ、その真価を発揮できるのだが、彼らは女子供を相手に竜を使えるかと、自らのプライドにこだわって竜を呼ぼうとはしなかった。
もしも、彼らがドラゴンに乗って空から攻めてきたら水妖精騎士団にはどうあがいても勝ち目はなかったであろう。が、そんなことをすれば嫌でも人目について、女子供をドラゴンに乗っていじめる騎士団という不名誉な噂が広がってしまうのは間違いない。
水妖精騎士団にとって、唯一有利な点はそこで、空中装甲騎士団は自重で思うように動けず、魔法をぶっ放つ砲台のようにしか戦えない。しかし、それでも歩兵が戦車に挑んでいくような無謀さである。もちろんバズーカのような便利な武器は持っていない。
にも関わらず、ジャネットは余裕だ。いったいどこからそんな余裕が出てくるというのだろう?
「いい? これからあなたたちにいくつかレクチャーしてあげる。それが全部できたら、必ず勝てるわ」
「は、はい。で、でも、あっ!」
「お前たち! いつまでごちゃごちゃしゃべっているか!」
ジャネットの余裕の態度に空中装甲騎士団はしびれを切らした。いっせいに杖をこちらに向けて呪文を唱えてくる。数十人のメイジの本気の攻撃を受けたらジャネットはよくても、ほかの少女たちはひとたまりもない。とっさに、キュメイラとディアンナが防御の魔法を使おうとしたが、ジャネットはそれを軽く制して。
-
「いい? 勝利のためにレッスンその一、戦いというものはね」
「そんなこと言ってる場合じゃ! うわぁぁっ! 来る、来るわっ!」
「戦う前から始まってるのよ」
その瞬間、空中装甲騎士団の周辺の地面が爆発した。白い煙がもうもうと立ち上がって、あっという間に空中装甲騎士団を包み込む。
「うぉわっ!? なんだ、このガスは」
「見えない、なにも見えない。おのれ、姑息な真似を!」
視界を完全に奪われてしまった空中装甲騎士団は身動きを封じられてしまった。すぐさま風魔法を使って煙を吹き飛ばそうとするが、煙はなんらかの細工をされているようで、空中装甲騎士団にまとわりついてなかなか離れない。
白い煙の塊になってしまった空中装甲騎士団を見て、ジャネットはくすくすと笑い続けている。その様子を見て、ユウリが感心したように言った。
「へぇ、あれはあんたの仕掛けかい?」
「ええ、あなたたちの前に顔を出す前にちょっとね。もっとも、遠隔錬金のちょっとした応用だからたいしたものじゃないけど」
いや充分にたいしたものである。離れた場所にあるものに錬金をかけるのは相当高位のメイジでなければ難しい上に、空中装甲騎士団にまったく悟られず、さらに時間差で効果を発動させるなど普通は考えられもしない。
が、ジャネットはそこで表情を引き締めると、エーコたちを向いて告げた。
「さて、ここからが問題よ。あの煙も、そう長くは持たないわ。その間に、あなたたちの魔法で一発ガツンとお見舞いしてやるのよ」
「そ、そんなこと言ったって! わたしたちの魔法じゃあ、全員でいっせいに撃ったって効き目がないのは見てたでしょ!」
「ただ一斉に撃てば、ね。あなたたち、賛美歌詠唱って知ってる?」
「さ、賛美歌詠唱って、あなた!」
エーコや、その名を知っていた者が驚いたのも無理はない。それは確かに強力な攻撃方法だが、とても素人にできるようなものではない。名前の意味がわからずにきょとんとしている少女が尋ねてくると、セトラが額に汗を浮かべて説明した。
「ロマリアに聖堂騎士という精鋭騎士団がいるのは知っているでしょう。賛美歌詠唱は、彼らが使う合体魔法の通称よ。その威力は、小さな城を崩すほどだと聞いているわ」
「そ、そんなすごいものがあるんですか。あ、でも聖堂騎士団の必殺技ということは、もしかして」
「そう、普通のメイジに使えるような代物じゃないわ! 選び抜かれた精鋭が、さらに血を吐くような鍛錬の後にはじめて使える極意と聞くけど、そんなもの私たちに使えるわけがないじゃない」
「うふふ、心配しなくても、そんなお行儀のいいものをやってもらおうなんて思ってないわ。言ったはずよ、魔法はハートだって。魔法はね、ハートの持ちようでどうにだってなるの、それこそドットがいきなりスクウェアになれるくらいにね」
そんな無茶な、と誰もが思った。魔法の威力が精神に左右されるのは常識だが、それとて限度がある。大抵は長い鍛錬と経験で少しずつ格を上げていくもので、一生をライン以下のクラスで終わる者も少なくはない。それをみんな知っているのに、このド素人の集団にいきなりスクウェアクラスのことをやれというのか。
-
「でたらめだわ! 魔法の常識にまるっきり反してる」
「そんなことはないわよ。あなたたちこそ、メイジの持つ底力を甘く見てるわ。あなたたちの知ってるそこらのメイジなんて、本来の魔法の力のほんの一部しか使えてないんだから。じゃ、やり方を教えるけど簡単よ。みんなで心の震えを最大にして同時にひとつの魔法を放つ、それだけ」
簡単に言ってくれるが、方法を説明されただけでできるならば誰も苦労はしない。第一、心の震えを最大にしろと言ったってどうすればいいのか? 十数人もが心の震え、すなわち怒りや悲しみなどの感情を最大に高められるような「何か」がそうそうあるわけがない。
しかしジャネットは困惑するエーコたちに向かって、人差し指をぴんと立てて言った。
「まだわからないの? あなたたちは一体なにで集まってきた団体だったのか、心をひとつにする絶好のネタがあるじゃないの」
「あたしたちの……って、ええーっ!」
今度は全員がびっくり仰天した。このメンバー、水妖精騎士団が集まった理由と言えば。
「あっ、あなた! いったいいつから見てたのよ!」
「けっこう前からよぉ、あなたたちが汗を流してるところも、集まって召喚されし書物を楽しんでるとこもね。仲良きことは美しいわね、もう食べちゃいたいくらいだわ。特に、馬鹿な男に負けたくないって心意気は気に入ったわよ。実はわたしにも出来の悪い兄がいるんだけど、フォローにはいつもいつも苦労してるの。たまにはターゲットじゃなくてヘマした兄を撃ちたくなることもあるわあ。だから、あなたたちの男に対する憤りは理解できるつもり。その怒り、思いっきりぶつけてみたいと思わない?」
まるで悪魔のささやきのようなジャネットの問いかけに、少女たちはごくりとつばを飲み込んだ。
確かに、確かに、あの破廉恥きわまる水精霊騎士隊を完膚なきまで叩き潰してやりたいとは思っていた。そういえば、魔法の練習をしているときも、あのふざけた連中をへこましてやりたいと考えながらやっていたときは調子がよかったが、まさかそんなことで。
「わかってきたようね。レッスンその二、怒りは大切よぉ、怒りは人の心を一番燃え上がらせてくれるの。さらにレッスンその三、友達は大切にしなさい。火はひとつずつでは小さくても、集まれば大きな炎になるわ」
そう言うとジャネットは、自分の杖を少女たちの前にかざした。
それは、この杖に集えという合図。少女たちは息を呑み、それぞれの杖をジャネットの杖にかぶせるように合わせていった。
「そう、それでいいわ。後はわたしに合わせて呪文を唱えて、心の震えを高めながら魔力を高めていくのよ」
「けど、心の震えを高めるなんてどうしたら」
「簡単よ、嫌がるあなたたちに無理矢理迫ってきた破廉恥な男の顔を思い出しなさい。目をつぶって、あの顔に思いっきりパンチしたいと念じ続けなさい。その怒りが、そのまま力に変わるわ」
「わかりました……やってみます!」
少女たちは決意した。エーコたち三人を加えて、水精霊騎士隊に恨みを持つ少女たちの目に火が灯る。
-
だが、ジャネットは少女たちを見渡すと、底冷えのする声で言った。
「ただし、最後にひとつだけ言っておくわ? 杖はわたしが構えるわ、呪文もわたしが唱えましょう。魔力を合わせ、波長を整えて狙いを定め、号令もわたしが出してあげる。それでも……勝つのはあなたたちの意思よ」
「意思……」
「そう、どうして六千年ものあいだメイジが支配者でいれたと思う? それは魔法が意思の力をそのまま強さにできたからよ。亜人、幻獣、メイジ殺し、そんな限界を前にして、それでもあきらめを踏破できたときに魔法は無限の力を生み出してくれる。あなたたちにそれができるかしら?」
ジャネットの問いに、少女たちは無言のうなづきで応えた。
自分たちにどこまでできるかはわからない。だが、目の前のジャネットというメイジは、それらの大言を吐くだけの実力を有している。後はただ、実行あるのみ。
にこりとジャネットは笑い、しかるのちに表情を引き締めた。
「じゃあやるわよ。系統も実力もバラバラなあなたたちの魔力を、わたしが集めてひとつにするけど、これには少しばかり時間がかかるのよね。そういうわけだから、そっちのお姉さんたち、よろしくね」
軽くウインクをしながら合図されると、セトラやユウリ、ティーナたちはやれやれといった様子でうなづいた。
「仕方ないわね。まあ、私たちはオンディーヌの坊やたちに特に恨みはないし、時間を稼いであげるわ」
「あたしはこっちのほうがいいぜ。つるむのは元々性に合わねえからな、勝手に暴れさせてもらうよ」
「エーコたちのサポートが第一でしょ? 血の気の多い姉を持つと妹は苦労するよ。さあて、お姉ちゃんがんばっちゃうぞ」
呪文を唱えているあいだのエーコたちに手を出させまいと、姉たちは杖を持って身構える。
空中装甲騎士団を包んでいる煙幕も、そろそろ晴れる。そうなったら、怒りに燃える連中は傘にかかって攻め込んでくるだろうから、わずかな人数で死守しなくてはならない。これはまたいい塩梅の無理難題だ。
だが、白煙が晴れて真っ先に頭を出した空中装甲騎士団員のの見たものは、自分に向かって飛んでくる靴の裏であった。
「でありゃぁぁっ!」
「ぐばはっ!?」
間の抜けた声とともに、顔面にキックの直撃を受けた騎士がぶっ飛ばされた。
「ティラ、ティア!」
「皆さん、わたくしたちをお忘れとはひどいですわ」
「戦う意思を持っているのはメイジだけじゃないってことを見せてやるぜ。こっちはまかせてくれよ! この身に代えてもあんたらに指一本触れさせはしないぜ」
-
「ふたりともありがとう……でも、無理はしないで!」
シーコの叫びに、ティラとティアはこくりとうなづくと、戦いの渦中へ入っていった。ふたりのグリーンの髪と衣装が華麗に舞い、まるでエメラルドの星が飛び交っているように見える。
だが、空中装甲騎士団も今度は杖に『ブレイド』をかけて迎え撃ってきた。これでは、いくら身のこなしが軽くても、素手のふたりが圧倒的に不利だ。
長くは持たない。ティアのスカートの端が切り裂かれてちぎれ、ティラの髪の数本が切られて舞う。
それでもティラとティアはひるむことなく空中装甲騎士団の足止めをしてくれている。あの心意気に応えなければ貴族ではない、いいや女じゃあない。
煙幕が切れ、ついに激突する空中装甲騎士団と、ティラ・ティアを含めた姉妹たち。戦況は最初から圧倒的に不利で、姉妹たちはかなわず倒されていくが、覚悟を決めた人間は強い。倒れながらも杖を振って食い下がり、一秒でも時間を稼ごうとしてくれた。
そしてその間に、エーコたちは魔力を少しでも集めるために念じ続けた。
「ダス・ウィー・オンジュー・ウィス・アル・リィティロス……」
「まだよ、もっと強く、深く念じなさい。あなたたちが男に言われたことを、あなたたちが言われたことを思い出して」
エーコたちの脳裏に、水精霊騎士隊の少年たちにナンパされたときの記憶が蘇ってくる。
あのぎらぎら光った目、荒い息遣い、今思い出しても虫唾が走る。
嫌だというのにしつこく言い寄られて、肩に手を置かれたときは本当に気持ち悪かった。壁際に追い詰められて迫られたときは泣きたくてたまらなかった。
むろん、水精霊騎士隊の少年たちは少女たちに乱暴しようなどと考えていたわけではないが、ギーシュほど女性の扱いに慣れていない彼らの態度はねちっこくてしつこく、初心な少女たちから嫌悪感を買ってしまうばかりだったのだ。
だがそれはそれ、少女たちは自分が受けた体験を思い出して感情を高め、魔力を込めていく。しかし、この程度ではまだ足りない。
「まだよまだ! もっと強く、思い出すだけじゃなくて想像しなさい。その男たちに体を触られることや、あなたのお友達の貞操が危機にさらされることとかね」
ジャネットの言うがままに、少女たちはさらに怒りをつのらせていった。
じわじわと、感情の高まりと共に魔力が増大していく。その高ぶりを感じて、ジャネットは自分も興奮のるつぼに身を焦がしていた。
”いいわぁ、この子たち、やっぱりわたしの見込んだとおりの素質を持ってる。ぞくぞくするような怒りや憎しみや嫉妬の波動! それになんて一生懸命な顔をするのよ、濡れちゃいそうなくらい可愛い可愛い可愛いわぁ。欲しい、この子たちをみんなわたしのお人形にしたい! でもだめよ、まずはわたしが約束を守らなきゃね。このくらいの感情じゃあまだ勝てない。あと少し! あと少しなにかで底上げしなきゃ、もっとこの子たちの憎悪をあおる何かがないかしら”
よだれを垂らしたい欲求を抑えながらも、ジャネットは冷静に魔法をコントロールしていた。魔法力は順調にたまりつつあるが、これではまだスクウェアスペルに毛が生えた程度に過ぎない。空中装甲騎士団を一発で倒すには、あと一歩、なにかで魔力をブーストしてやる必要がある。彼女たちの感情を、文字通り爆発させる何かが必要だ。
-
”もう余裕もないことだし、こうなったらこの子たちの心を少々えぐる言葉を使ってでも、感情を高めてもらおうかしらね”
暗殺者であるジャネットにとって、言葉も立派な武器である。人の心を翻弄し、古傷を呼び起こして狂わせるくらいお手の物だ。ましてやこんな小娘たちの心を操るなど簡単である。
だが冷たい笑みを浮かべ、言葉を選んだジャネットが口を開こうとした、そのときだった。
「きゃああぁっ!」
「ティラ! ティア!」
ついにブレイドの一撃を受けて、ティラとティアが吹き飛ばされてしまった。剣となった魔法の杖での攻撃で、ふたりともそれぞれ片腕を大きく傷つけて血を流している。
「く、くっそぉ……ティラ、ティラっ」
「うぅぅ……エーコさまたち、ご、ごめんなさい」
そして、傷ついて動くことも出来なくなったティアとティラに空中装甲騎士団が迫る。
「バカめ、平民のくせに貴族に逆らうからこうなる。覚悟しろ虫ケラめ、その両手両足を砕いてくれるわ!」
兜の下で残酷な笑みを浮かべて、空中装甲騎士団員は恐ろしい凶器となった杖を振り上げた。ティアとティラは、互いにかばいあいながらももう逃げる力は残っていない。
危ない! ユウリやディアンナたちはそれぞれ別の騎士団員と戦っていて動くことができない。だが、まさに杖が振り下ろされようとした、そのとき。
「……許さない」
「許さない」
「許さない!」
巨大な魔力の波動が放たれて、それを感じ取ってしまった空中装甲騎士団の動きがびくりと止まった。
今の、魔力は!? スクウェア? いや、それ以上? 困惑する空中装甲騎士団の耳に、三人の少女、エーコ、ビーコ、シーコの血を吐くような声が響いてきた。
-
「よくもわたしたちの大事な仲間の、私たちの大事な友達を傷つけたな!」
「虫ケラと呼んだか彼女たちを、お前たちここから生きて帰れると思ってんじゃないわよ」
「許さない、許さない、絶対に許さないから!」
これまでとは比べ物にならないほどの怒りの波動が魔力に変わり、彼女たちの杖を通してジャネットの杖に集まっていく。その力の巨大さには、ジャネットすらも予想外だったと愕然とした。
「なっ、なんて力なのよっ! くっ、これ以上はわたしのほうが制御しきれない。ええい、撃つわよあなたたち!」
「行って!」
「撃って!」
「砕いて!」
限界を超えた魔力が収束し、ジャネットはもはや魔法として具現化することもできなくなったその魔力の塊をそのまま撃ち出した。
振り下ろされた杖から巨大な光の弾が飛び出し、空気を切り裂き、砂塵を巻き上げながら空中装甲騎士団に向かう。
「なんだこの魔法は!? さっ、散開をっ! 間に合わない、うわぁぁーっ」
光は怒涛のまま空中装甲騎士団を飲み込んでいった。その壮絶な光景を、とっさに飛びのくことに成功したセトラやキュメイラ、ティラとティアを抱えて退いていたティーナとユウリは呆然とした様子で見ていた。
魔力の塊は、魔法という形を与えられずに、ただ怒りのままに飛んで空中装甲騎士団を打ちのめした。火でも風でもなく、ただ相手を倒したいという意思そのものが現実の衝撃となり、屈強な騎士たちの鎧を貫通し、その身と精神を文字通り叩きのめしたのだ。
光芒が収まった後で残ったのは、広場の土の上に横たわる空中装甲騎士団の死屍累々。皆気絶しているか弱弱しくうめき声を漏らしているだけで、立っている者はひとりも残ってはいなかった。
瞬き一つする間に激変してしまった光景に、水妖精騎士団の少女たちも、ジャネットですらもしばし呆然としてその場に立ち尽くした。
「やった、の?」
あの鬼のように恐ろしかった空中装甲騎士団がひとり残らず倒れ付している。魔法にすべての感情の力を注ぎ込んで、怒りも憎しみも空白となってしまったエーコたちは、目の前の光景が信じられずに動けなかったが、それを喜色に満ちたユウリの叫びが打ち消した。
「やったの? じゃねえよ、お前たちはやったんだよ。お前たちの魔法で、空中装甲騎士団に勝ったんだよ!」
「やった……勝った? 勝った……やった、勝ったんだぁーっ!」
その瞬間、少女たちの大歓声が広場にこだました。皆が抱き合い、手を叩いて喜び、自分たちが大事を成し遂げたことに感涙していた。
もう一度、いや何度でも確認しよう。彼女たち水妖精騎士団は、あの空中装甲騎士団に勝ったのだ。
その中で、唯一ジャネットだけがいまだ呆然として、自分の想像を上回る結果を認め切れていなかったが、後ろからぽんと肩を叩かれて我に返った。
-
「ジャネットさん」
「えっ? あ、な、何かしら」
「すみません、疲れてるでしょうけどティラとティアの傷が深いの。治してください」
「あ、うん、わかったわ」
呆けていたところに声をかけられて、ジャネットはほとんど言われるがままに杖を振って回復魔法を唱えた。
治癒の光がティラとティアの傷を包み、ふたりの傷がみるみるうちに癒されていく。そして全快すると、ティラとティアはエーコ、ビーコ、シーコと抱き合って喜んだ。
「ティラ、ティア、治ったのね。大丈夫? まだ痛くない?」
「もう平気です。ひゃあ、やっぱ魔法ってすごいっすねえ。おっとと、それよりも、勝利おめでとうございます!」
「いいわよそんなの、あなたたち、無茶しないでって言ったのに。ほんとに危ないとこだったじゃない」
「申し訳ありません。けど、わたしたちにできるのは体を張ることだけですので」
「なに言ってるの! シーコの言うとおりよ。あなたたちにもしものことがあったらどうしようかと……いい、あなたたちふたりはもうわたしたちの大事な友達なんだからね!」
「「はい、ごめんなさい。エーコさま、ビーコさま、シーコさま……」」
ティラとティアの瞳からつうと光るものが流れて、彼女たちのエメラルドグリーンのドレスに濡れたしみを作った。
エーコたちや、彼女たちの姉は、それを暖かく見守っている。もう、大切な人を失うのはたくさんだ。あんな悲しい思いは二度と味わいたくはない。
水妖精騎士団の少女たちも、平民の仲間の無事を心から喜ぶエーコたちを見て心を決めていた。この人たちなら命を預けられる、この人たちならついていけると。
そして、ジャネットはそんな様子を見て、自分が見立て違いをしていたことにやれやれと心の中でため息をついていた。
”まずったかしらねぇ……怒りに狂わせて、男をいたぶる楽しみに目覚めさせてあげようと思ったけど……この子たち、今どき珍しい、他人のために一番強く怒れるってタイプねえ”
ジャネットは、そんなさわやかな笑顔で自分を見ないでよとエーコたちの視線をそらして首を振った。
こんなことなら、寄り道なんかしないでさっさとターゲットを始末しに行けばよかった。ジャネットは、さてこの場からどうやって逃げ出そうかと思案をめぐらせた。
ところが、そこへカンカンに怒った少女の怒鳴り声が響いてきた。
-
「エーコ! ビーコ! シーコ!」
「えっ! あっ、ひ、姫殿下ぁ!」
とっさにかしこまるエーコたちの前に、ツインテールをなびかせて、大股でベアトリスがやってきた。そしてベアトリスは、エーコたちの「い、いつから見てたんですか?」という問いを無視すると、三人の顔にそれぞれびんたを浴びせかけた。
「このバカ! 空中装甲騎士団に喧嘩を売るなんていったいなに考えてるの! まかり間違えば取り返しのつかないことになっていたじゃない! あなたたちをクビにする気なんかわたしにはないんだから、あなたたちは適当に頭を下げておけばよかったのよ」
「す、すみません。けど、わたしたちにも姫殿下の家臣としての誇りが」
「それがなんだっていうの! そんなものなくたって、あなたたちに代えられる人なんてどこにもいないのよ。また、あなたたちがいなくなったら……あんな悲しい思いを、もう二度とわたしに与えないでよ……」
怒りながらも、最後は涙を流しながらベアトリスはエーコたちに詰め寄っていた。
その涙に、エーコたちはようやく、自分たちが家族を失った悲しみと同じ悲しみをベアトリスも感じてくれていたことを悟った。
「姫様、すみませんでした」
「う……わ、わかればいいのよ。これからは気をつけなさい……ごほん! それはともかく、あの空中装甲騎士団を倒すなんてたいしたものね」
「えっ、あ……いや、それは。わたしたちじゃなくて、そちらの」
エーコたちは慌てて、ベアトリスの前にジャネットを引き出した。
ベアトリスは涙を拭き、毅然とした様子でジャネットの前に立った。対してジャネットも、不敵な様子を見せてベアトリスの前に進み出る。
「ベアトリス・イヴォンフ・フォン・クルデンホルフよ。この度は、わたしの部下を救ってくださって感謝するわ。お名前をうかがってもよろしいかしら」
「お初にお目にかかります、クルデンホルフ姫殿下。わたしのことはジャネットとお呼びくださいませ。助太刀のことでしたらお気になさらずに、傭兵稼業のかたわらの、ただの気まぐれでありますゆえに」
第一声はそれぞれあいさつで済ませた。ベアトリスはジャネットの前に、大貴族らしく胸を張って尊大そうに構えている。先ほどの泣き顔を見ていたジャネットからしたら笑止の極みであるのだが、ジャネットの心は別の歓喜で震えていた。
”うふふ、まさかターゲットが自分からしゃしゃり出てきてくれるとはねえ。なんてわたしはついてるのかしら!”
そう、ジャネットの本来の目的はロマリアの依頼でベアトリスを暗殺することにあったのだ。その標的が、こともあろうに今現在自分の目の前に無防備に立っている。
こんなチャンスは二度とない。周りの小娘たちなど、自分の力ならば蹴散らすのは簡単だ。いやむしろ、目の前で恩人と思っていた相手に主君を殺されたときのこの子たちの顔はどんなものかしらとぞくぞくしてくる。
さあ、相手が油断している今のうちに、杖を振ってこの娘の心臓を串刺しにする。それですべて終わりだ。
-
ジャネットは口元に浮かびそうになる笑みをかみ殺しながら、杖を振ろうとベアトリスを正面から見据えた。だがベアトリスはそれより一瞬早く、ジャネットも予想もしなかった速さでジャネットに飛びついてきて。
「気に入ったわ! あなた、わたしのものになりなさい!」
「は、はぁぁぁぁっ!?」
突然の命令に、さしものジャネットも意味がわからずに奇声をあげてしまった。だがそれも当然だ、周りで見ているエーコたちも何を言い出すんだと目を丸くしてしまっている。
しかしベアトリスは極めて真面目な目で、ジャネットをぐっと見つめて続けた。
「あなたの強さ、さっきの戦いでしっかりと見せてもらったわ。それだけの力を野に置いておくなんてもったいない! クルデンホルフの、いいえ、このわたしの直属の騎士として雇ってあげる。そして、エーコたちを、水妖精騎士団を鍛え上げてほしいの!」
「えっ、えええっ!?」
「ちょ、姫さま! 急になにを言い出すのですか……って、姫さま、今、水妖精騎士団と……もしかして」
「そうよ、あなたたちの戦いぶりも見せてもらったわ。まがりなりにも、空中装甲騎士団を倒すとは見上げたものね。なにより、その敢闘精神は他に変えがたいものと感じ入ったわ。よって今日ここで、あなたたちをわたしの直属騎士団として任命します。異論がある者はここから去りなさい!」
ベアトリスの宣言に半瞬遅れて、歓喜の大合唱が少女たちのあいだから上がった。エーコたちは自分たちの努力がベアトリスに認められたという喜びで、この街で集まった少女たちは、飛ぶ鳥も落とす勢いで成長していくクルデンホルフの臣下ならば両親も喜んでくれるだろうし、自分の将来も安泰に違いないと。
しかし、ベアトリスは歓喜にむせぶ少女たちに一喝するように告げた。
「ただし! あなたたちがまだ安心して見てられないひよっこだということも事実よ。よって、水妖精騎士団の名前は仮称としてわたしが預かります。この名前を公に名乗りたければ、全員が一人前の騎士として腕を上げることね。そのための教官なら、今ここで用意してあげたから!」
そうしてベアトリスは、ジャネットの肩を掴んで前に引き出した。
「よろしくお願いします! ジャネット先生、いえ教官殿!」
「えっ、ええっ! えええええええええーーっ!」
少女たちから一斉に敬礼されて、ジャネットはうろたえるしかなかった。
エーコたちには異存があるはずがない。そんじょそこらのクラス高だけの二流メイジならいざ知らず、ジャネットの実戦仕込の圧倒的な実力は全員が見てきた。これほどの強さを学べるならば、文句なんかあろうはずがないではないか。
だが勝手に話を進められたジャネットはそうはいかない。なにがなんだかわからないうちに雇われて教官にされてはたまったものではない!
-
「ちょ、ちょっとあなた! いくら大貴族だからってそんな勝手に人をどうこうしていいと思ってるの!」
「もちろんわかってるわ。けど、わたしは欲しいと思ったものは必ず手に入れる主義なの。そしてわたしはいずれクルデンホルフの名の下に、ハルケギニアのすべてを手中に収める女。つまり、どうせあなたもいずれはわたしの手の中に入るってわけ。早いも遅いも同じなら、早いほうがいいと思わない?」
「餓鬼の夢に付き合う気はないわよ」
「あら? あなた意外と人を見る目がないわね。でもいいわ、必ずあなたをはいと言わせてあげるわ。逃がさないわよ、フフフフ……」
「ああっもう! 話が通じない! もういいわ、もう知らないわ。こうなったら教えてあげるけど、わたしはさるところの依頼であなたをころ」
「五十万エキューでどう?」
殺しに来た……と、言いかけたジャネットの言葉はベアトリスの一声で封じられた。
なに? 今、なんて言われたの? ありえない数字が聞こえたような気がしたけど……
しかしベアトリスは、目を白黒させているジャネットに追い討ちするように言う。
「年間契約金五十万エキューであなたを雇うわ。これ以上の額を提示できる貴族がいるっていうなら、わたしが直々に話をつけてあげる。もちろん、契約期間中の仕事によってはそれぞれ上乗せするわ。どう?」
どう、と言われても金額がすごすぎて正直頭がついてこない。普通、自分たちが依頼を受けるときの相場は十万エキューが最低クラスであるが、そうそう都合よく仕事が舞い込むわけではないので自分ひとりで稼げる額は年間ざっと三十万エキューがせいぜい。今回のロマリアからの依頼にしても兄と二人で二十万エキューである。しかも、仕事ぶりによってはさらに増額してもいいというのだ。
「わ、わたしには三人の兄がいて、わたしの勝手で仕事を決めるわけには」
「なら、あなたの兄さんたちにもそれぞれ同額を払うわ。それでも納得してはもらえないかしら?」
「えっ、三人分も同額というと、全員合わせて……二百万エキュー!?」
ケタがひとつ飛んでいることに、さしものジャネットも腰を抜かしかけた。すごい、それだけあればダミアン兄さんも説得できるかもしれない。
-
しかし額がすごすぎることに、慌ててビーコが口を差し挟んだ。
「ひ、ひ、姫様! いくら姫様でも、二百万エキューなんて大金を用意するなんて!」
「わたしは市井のアパルトメントに移るわ。それから、わたしの馬やドレスや宝石類なんかも最低分だけ残して売り払いなさい。そうそう、わたし名義の別荘があったけど、あれを処分すれば百二十万エキューにはなるでしょう」
「そ、それでは姫様が下級貴族と変わらないご生活に……」
「だからなに? こんな鉄と煙だらけの街であんなもの持ってても役に立たないわ。心配いらないわよ、ジャネットほどのメイジが四人もいれば一年に二百万エキュー以上を稼げる仕事をわたしが見つけてくるわ。なにより、あなたたちが何年後かにジャネットと同じくらいに強くなれば、それこそ一秒に一万エキューを稼いでくれるようになってくれるでしょ?」
これは先行投資よ、そのためなら一年や二年を貧しい暮らしをすることになるなんて問題にもならないわと、ベアトリスはエーコたちを黙らせてしまった。
その様子に、少女たちや、誰よりもジャネットはベアトリスへの評価を改めていた。
”このお姫様、ひょっとしたら数年後に本当に化けるかもしれない”
決断力がある、先を見通している、なによりも器がでかい。もしかしたら、この小さな少女の手のひらに、本当にハルケギニアが収められる日が来るかもしれないと、そんなとてつもない空想が少女たちの頭をよぎった。
「さあ、わたしはカードを切ったわ。次はあなたの番よ、契約を受け入れる? それとももっと値を吊り上げてみる?」
「……確約はできないわ。わたしたちの決定権は、長男のダミアン兄さんが握ってる。けど、あなたが始祖と杖にかけて誓ってくれるなら、わたしが全力でダミアン兄さんを説得してみる」
「了解したわ、あなたの望み、聞き入れましょう」
ベアトリスはそう言うと、常備している誓紙に契約内容とサインを書き込んでから、魔法のインクで拇印を押した。
これで、契約は相手が呑んだら正式なものになる。そしてこれを破ったら始祖への反抗とみなされて教会で裁かれることとなる。
受け取ったジャネットは、心の中でニヤリと笑った。ロマリアからの依頼は破棄することになるが、それを補って有り余るほどのものを得れた。傭兵としての信頼など、正規で雇われることに比べたら気にする必要はない。
「契約成立ね。よろしくジャネット、歓迎するわ」
「まだ決まったわけじゃないって言ってるでしょ。ダミアン兄さんの説得は、正直あまり自信がないんだから。でもまあ、あなたの度量には正直感心したわ。そう、有能な人材はひとりでも多いほうがいいってやつかしら?」
「違うわ、欲しいのは有能な人材じゃない。あらゆる人材なのよ」
そう言うと、ベアトリスは手を広げて、その場にいる全員を抱きかかえるように手を広げた。
「世界は広い、世界を統べるには、十や二十の才能じゃとても足りないわ。有能な人材ももちろんいるけど、無能な人間は無能であるからこそ役立てられる場所がある。なにもできない人間は、誰もやったことがないことをやらせることができる。わたしに害をなそうという人間がいたら、それを処分するための人材を育てるエサにできるわ。もちろん、わたしのために役立とうという人間には、相応の仕事をくれてあげる」
-
「つまり、どんな人材でも使いこなしてみせると、そういうわけですか」
「覚えておきなさい。この世に、無能な部下なんてものはいないのよ。無能な上司ならいるけどね」
ベアトリスは、その場にいる全員の顔をひとりずつ見つめていった。エーコたちや少女たちには無言で、エーコの姉妹たちにはこれからもよろしくねと声をかけ、最後にティアとティラに目をやって。
「あなたたちも、見事な働きだったわ。よければ、これからもエーコたちを支えてもらえるかしら」
「い、いいのかよ? 大貴族さまが、あたしらみたいなのを」
「どこに邪魔する理由があるっていうの? 言ったでしょ、あらゆる人材が欲しいって。それに誰より、エーコたちがあなたたちを必要としてるわ。だからよろしく頼むわね」
「はい、わたしたちでよければ、なんなりと」
「そこまでかしこまらなくていいわよ。エーコたちの友達なら、わたしの……その、わたしとも、と、友達になってくれる?」
「「喜んで!」」
そう叫ぶと、ティアがベアトリスに抱きついて、慌ててティラが引き離す騒ぎになった。
まったく……わずか一年足らずでよくも自分の周りがにぎやかになったものだとベアトリスは思った。エーコ、ビーコ、シーコの三人から始まって、エーコたちの姉妹、今度は水妖精騎士団にジャネット。彼女たちのおかげで、一年前の自分では知らなかったいろいろなものを知れた。そしてそれも、エーコたちに絡みついていた呪われた鎖を断ち切ってくれた、あの風来坊の……いつか、また会いたい。
だがそのとき、エーコたちの魔法を受けて伸びていた空中装甲騎士団がようやく起き上がってきた。
エーコたちのあいだに緊張が走る。しかしベアトリスはエーコたちを手で制すると、指揮官のもとに歩み寄って言った。
「空中装甲騎士団、ハルケギニア最強の名に恥じない勇猛な戦いぶり、褒めてつかわすわ」
「ぐぐっ、お戯れはおやめくだされ。せめてお笑いくだされ、お叱りくだされ。我ら一同、クルデンホルフの名を敗北によって辱めたこと、万死に値すると覚悟しております。かくなるうえは、この一命を持って」
「お黙りなさい!」
びくりと、ベアトリスの一喝によってその場が凍りついた。
「負けたことが恥ずかしい? そりゃそうでしょうよ。あなたたちは竜の子をトカゲと思って狩りに出かけた大馬鹿者ですもの。かくいうわたしも、この子たちの資質を見誤っていたことが恥ずかしいわ。でもだから何? 墓石にハルケギニア一の大馬鹿者ここに眠るとでも刻んでほしいの? して欲しければそうするけど、慢心しきって小娘ごときに負けた未熟者がどうすればいいか、あなたたちに戦いを教えた人はそんなことも教えてなかったの! 男でしょ」
「ぐっ、ぐぐ……姫様、叶うことならば我らに名誉挽回の機会をくだされっ! 我ら一から己を鍛えなおし、あらためてハルケギニア最強の名を得たいと存じます」
-
「ならさっさと行きなさい! 今日のことは見なかったことにしてあげるから、その代わりに今の百倍強くなるまでわたしの前に顔を出すんじゃないわよ!」
「はっ、ははぁっ!」
空中装甲騎士団は頭を下げると、全員ほうほうの体で広場から飛び出していき、やがて飛び立ったドラゴンが遠くの空に消えていくのが見えた。
これですべて終わった……広場には少女たちだけが残り、皆が新しい道を見つけた喜びに顔を輝かせている。
だが楽観はできない。空中装甲騎士団も、次に会うときには今とは比べ物にならない屈強な騎士団に生まれ変わっているであろう。そのときまでに自分も強くなっておかなくては、少女たちは胸を熱くするのだった。
そしてジャネットは、これからどうやってこの子たちを鍛えようかと想像していた。人形にできないのは惜しいが、この子たちを自分好みに育て上げていくのもそれはそれでおもしろい、なにより楽しみながら大金が手に入るのだ。
だが、なにか忘れてるような……ジャネットは、奥歯にものが挟まっているような嫌な感じをぬぐいきれなかった。
と、そのときである。爆発音が響き、建物の屋根越しに火柱が上がったのが見えたのは。
「なっ、なによ! じ、事故?」
「違うわ、今のは炎の攻撃魔法の音よ。あっちは、港の南の桟橋あたりね」
「桟橋って、最近ミスタ・コルベールがよく行ってるとこじゃない」
「あ、ドゥドゥー兄さんのことすっかり忘れてたわ……」
これはまずい、もしミスタ・コルベールが手際よく始末されたら全部が台無しだ。
「まったく、ふだん仕事遅いくせにこんなときだけターゲットに行き着くんだから……っとにもう!」
あのバカ兄貴を止めないと大変なことになると、ジャネットは港に向かって駆け出した。
しかし、人間同士で争っているそのうちにも、自然からの危機は迫りつつあったのだ。
街外れの小高い丘から土煙が立ち昇り、その中から這い出てくる巨大な影。
「かっ、怪獣だぁぁーっ!」
近くを通りかかった商人の悲鳴が響き、完全に地上に姿を現したその怪獣、キングザウルス三世は鈴のように吼えると街に向かって進撃を始めた。
だがなぜキングザウルスはこの街に現れたのだろうか? いったい何を狙っているのだろうか? 事態はひたすらに混迷に向かって加速し続けている。
続く
-
今回はここまでです。
地獄のさたも金次第。1月中に投下しようと思っていたのですが間に合いませんでした。
それからキングザウルス三世の活躍に期待してた人すみません。都市破壊シーンは次回に伸ばします。
いよいよ今月はゼロ魔21巻の発売日ですね。ネフテスに乗り込んだ東方号がどうなるのか、ネフテスから脱出した才人たちの行く先は。
今からいろいろ期待が大きいです。
では、原作を楽しみにしながら、私も次はできるだけ早くできるよう頑張ります。
-
ふたりともおっつおっつ
-
乙! なんて銭闘力だ……!
-
こんばんは、焼き鮭です。今回も投下します。
開始は20:18からで。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第八十四話「再会の姫」
地殻怪地底獣ティグリス 登場
剣と魔法の世界ハルケギニアで、侍の格好をした奇妙奇天烈な姫君、クリスティナ・ヴァーサ・
リクセル・オクセンシェルナがトリステイン魔法学院にやってきた翌日。クリスは正式にルイズらの
クラスに編入を果たした。生徒たちは当然ながら、見たこともない出で立ちで、デバンという奇怪な
生物を使い魔にしているクリスに奇異の目を向けていた。
そして同日、クリスはアンリエッタへと、トリステインの魔法学院への留学に際して便宜を
図ってもらったことの礼を言うために、トリスタニアの王宮へと向かうこととなった。そして
王宮までの案内兼護衛役として、アンリエッタと特に親しい間柄のルイズと才人が同行することとなった。
そういうことで現在、ルイズたち一行はトリスタニアへと足を運んでいた。
「ああ、クリス! それにルイズと、サイトさんも! 来てくれたのね!」
王宮のアンリエッタへのお目通りが認可され、彼女の私室で対面すると、アンリエッタは
弾んだ声を出して一行を歓迎した。
「アンリエッタ女王陛下もご機嫌麗しく。お目通り感謝致します」
「ふふッ! そんなに畏まらなくていいのよ。いま、ここにはわたくししかいませんもの」
クリスが恭しく頭を下げると、アンリエッタはおかしそうにそう言った。
「改めて、ようこそ、トリステイン王国へ。歓迎するわ、わたくしのお友達、クリス」
「……ははッ!」
アンリエッタが「友達」と呼ぶと、クリスもおかしそうに笑った。
「そうだな、小うるさい皆もいないし堅苦しいことは抜きにしよう。アンリエッタ、この度は
本当に世話になった。お陰で学院での生活も不自由なく送れる」
「いいえ、わたくしは何も。あなたの人徳よ」
クリスとアンリエッタが対等に言葉を交わす様子を目の当たりにして、クリスの後方に
控えるルイズがぽつりとつぶやいた。
「クリス、ほんとに姫さまのご友人だったのね……」
すかさず才人が突っ込む。
「何だルイズ、信じてなかったのか?」
「まぁ、正直に言うと、半信半疑だったわね。だって、姫さまとクリスのイメージは、今一つ
結びつかなかったんだもの」
「へぇ。ま、気持ちは分からなくもないけどな」
かく言う才人だって、クリスがアンリエッタの友と自称してから、こうして直に二人の関係を
目にするまでにわかに信じられなかった。絵に描いたようなファンタジーのお姫さまのアンリエッタと、
クリスはある意味で対極だったのだから、本心から信じられないのも無理のないことなのかもしれない。
クリスからお礼を告げられたアンリエッタは、次にルイズと才人の方を向いた。
「ルイズ、わたくしの元までクリスを連れてきてくれたこと、感謝します。わたくしから
改めて紹介するけれど、クリスはわたくしの数少ない対等な立場のお友達なの。留学中、
どうかクリスのことをお願いするわね」
「は、はい! 姫さま、ご安心下さい。不肖ルイズ・フランソワーズ、どんな時もクリスティナ・
リクセル姫のお力になることを姫さまに誓います」
ルイズはその場に片膝を突いて頭を垂れ、アンリエッタに約束した。
だが肝心のクリスは、ルイズにこんなことを言う。
「ルイズ、わたしのことはクリスでいい。学院では身分に関係なく、ともに魔法を学ぶクラスメイト
なのだからな。あそこでは、わたしはただのクリスだ」
「ふふッ、ルイズ、そうしてあげてちょうだい。クリスは見て分かるかもしれないけれど、
格式ばったことが嫌いなのよ」
「し、承知致しました。では……クリス、困ったことがあったらわたしに相談しなさいね。
出来る限りなら力になるから」
「ああ! こちらこそ、どうかよろしく頼む」
クリスがルイズに笑顔を向けていると、アンリエッタは最後に才人へ向き直った。
「サイトさんも、ここまでクリスを無事に連れてきてくれてありがとうございます」
-
「いやぁ、俺は今回何もしてないですよ」
一緒についてきただけなのにお礼を言われて、才人は少々照れくさくなった。
それにしても、今のアンリエッタはどこか楽しそうだと才人は思った。戦後はかなり影を
背負った様子であったが、現在は年齢相応の少女らしさが窺える。
実際に、アンリエッタは語る。
「わたくし、数日前から今日のこの時間をとても楽しみにしていたの。ルイズとクリス、
二人のお友達と語り合えるなんて。こんなに嬉しいことはないわ」
「もったいないお言葉です、姫さま」
「いいのよ、ルイズ。あなたもクリスのようにもっと気を抜いてちょうだいな」
「そ、そんな! 姫さまを相手にそんなこと出来ません!」
とルイズが言うと、クリスがツッコミを入れた。
「おや、ルイズ。わたしも王族なのだが?」
「あ、あなたは学院ではただのクリスだって自分で言ったじゃない! だからよ!」
「ははは! 冗談だよ、冗談」
「あらあら! 二人はもうすっかり仲良くなったのね」
ルイズとクリスのやり取りにアンリエッタがおかしそうに笑うと、クリスがアンリエッタに告げる。
「そうだ! アンリエッタ、サイトは本当にサムライだったよ」
「そうなの? わたくしには、あなたのお話を聞いてもよく分からなかったのだけれど……」
やはり、トリステイン人のアンリエッタには『侍』の概念がよく理解できなかったようだ。
「サムライに会えただけでも、この国に来た甲斐があったよ。本当にありがとう、アンリエッタ。
お前がわたしをサイトに、そしてルイズに引き合わせてくれたのだ」
「あなたの役に立てたのなら嬉しいわ、クリス」
クリスとアンリエッタが話していると……突然アニエスがノックもなしに部屋に飛び込んできて、
開口一番に報告した。
「ご歓談中失礼致します、陛下。このトリスタニアに怪獣が一体、まっすぐに接近中です!」
「――詳しく教えて」
アンリエッタは瞬時に女王の顔となり、アニエスに求めた。
トリスタニアに接近中という怪獣の現在地、トリスタニアからの距離を教えてもらい、
銃士隊が運んできた遠見の鏡でその姿を確かめる。
『グアァ――――――!』
果たして、鏡に怪獣の容貌が映し出された。二本の角を頭部から生やしたトラのような怪獣であり、
ルイズたちのやってきた魔法学院のある方角からちょうど真逆の方向から四足歩行で一歩一歩城下町に
近づきつつある。双眸は何故か半分しかまぶたが開いていない。
「地殻怪地底獣ティグリスっていう怪獣か……!」
才人が通信端末で怪獣の情報を引き出した。
「現在の移動速度から計算しますと、半刻に満たない時間で怪獣はトリスタニアに侵入することでしょう」
「わかりました、即刻対処致しましょう。ルイズ、サイトさん、一緒に来て下さい」
「承知致しました、姫さま」
アンリエッタがルイズと才人を連れて部屋から出ていこうとすると、クリスが呼び止めた。
「アンリエッタ、お前自ら指揮を執るのか?」
「ええ。国を守ることこそが王族の第一の役割ですもの」
「そうか、すっかり立派な女王になったな……。では、わたしに何か出来ることはないだろうか?
友として、どんなことでも力になるぞ」
クリスはそう申し出たのだが、アンリエッタはゆっくりと首を横に振った。
「大丈夫よ。これでも怪獣を相手にする経験は豊富なのだから。気持ちだけ受け取るわ。
だからあなたはここで吉報を待っていてちょうだい。ありがとう、クリス」
「分かった……。アンリエッタ、ルイズもサイトも、無理はしてくれるなよ!」
クリスの激励を受けながら、アンリエッタたちは部屋を出た。アニエスたち銃士隊を先に
作戦会議室に行かせると、才人とゼロがウルトラ戦士として意見をする。
-
「姫さま、ティグリスの対処は俺たちに任せてくれないか。データによると、ティグリスは
凶暴性のない、地底で大人しく生活してる怪獣だっていうんだ」
『地上に出てきたのには何か理由があるはずだ。俺たちがあいつを止めてみせるぜ!』
平和を守るために凶悪な敵と戦いながらも、一つでも多くの生命を助けたいと願うウルトラ戦士として、
悪性のない怪獣が傷つけられることは望ましくない。才人とゼロは、ティグリスと人間が無用な衝突を
しないようにする考えであった。
アンリエッタも彼らの気持ちを汲む。
「分かりました。ではこの一件は、あなた方に託します。どうかわたくしたちのみならず、
怪獣のことも助けてあげて下さい」
「頑張ってね、サイト、ゼロ!」
「ああ! それじゃ行くぞ! デュワッ!」
ルイズの声援を受けながら、才人はウルトラゼロアイを装着。光となって王宮から飛び出し、
ティグリスの迫る方角へと一直線に飛んでいった。
そして接近するティグリスを発見すると、ウルトラマンゼロの巨大な姿でその面前に着地する。
『よっしゃ! 止まれ、ティグリス!』
降り立ったゼロは早速ティグリスの首周りに組みつき、これ以上の進行を止めようとする。
「グアァ――――――!」
だがティグリスは怪力を発揮し、ゼロを払いのけた。
『うわッ!』
ティグリスは地底深く、常に四方八方から強烈な圧力を受ける環境下で長い時を過ごす生物。
その影響で、肉体は実に強固に出来上がっている。その身体から生じるパワーはかなりのものだ。
単純な力では、ゼロをも上回る。
しかしゼロは無用な暴力は振るわない。しりもちを打ってもすぐ立ち上がり、今度はティグリスの
尻尾をむんずと掴んだ。
『せぇぇぇぇいッ!』
「グアァ――――――!」
ゼロもまた怪力を発揮して、腰をひねってティグリスを街の反対方向に投げ飛ばした。
これでティグリスを街から大分引き離すことが出来た。
が、ティグリスはなおもトリスタニアへの接近を続けようとする。その様子を観察して、
才人がゼロに呼びかけた。
『ゼロ、何だかあいつ、様子が変じゃないか?』
『ああ……俺もちょうどそう思ったところだ』
ティグリスは一心不乱にトリスタニアを目指している。ゼロが止めようとすると抵抗するが、
それ以外の時はゼロのことがまるで目の中に入っていないようだ。
目といえば、ティグリスの視線はどこか虚ろだ。まっすぐ前を向いていないようにさえ見える。
正気ではないのではないだろうか?
『正気じゃないなら、目を覚まさせてやろうぜ!』
ゼロの身体が青く輝き、ルナミラクルゼロへと変身した。そして、
『フルムーンウェーブ!』
手の平からティグリスへ淡い光の粒子を浴びせかける。浄化技、フルムーンウェーブ。
対象の覚醒効果もあるのだ。
「……グアァー?」
フルムーンウェーブの効果は無事に発揮され、ティグリスは半開きだったまぶたがパッチリと開いた。
そして辺りを不思議そうにキョロキョロ見回す。自分がどうして地上にいるのか、分かっていない様子だ。
「グアァ――――――」
やがてティグリスはクルリと半回転して、来た道を静かに引き返していった。このまま元いた
地底の世界に帰っていくのだろう。
『これでティグリスは大丈夫だな。だが……』
-
あっさりとティグリスを帰らせたゼロだが、釈然としない気持ちを抱えていた。先ほどまでの
ティグリスは、明らかに不自然な状態であった。どこかの誰かが、何らかの目的でティグリスを
操ってトリスタニアにけしかけようとしたのだろうか。だが何のために? ティグリスがあまりに
簡単に正気に戻ったのも逆に腑に落ちないし、ティグリスを操作した誰かがいるとするなら、
何故この状況に至っても一向に姿を見せないのか。一体何をしようとしていたのか? 手掛かりが
なさすぎて、全く答えが見つからない。
結局ゼロは、空へ飛び立って才人に戻って王宮に戻る以外に出来ることがなかった。
ティグリスを元の生息地に戻した後、ルイズ、才人、クリスの三人も学院へ帰還することとなった。
帰りの馬車の中で、クリスが口を開く。
「最後は忙しなくなったが、無事アンリエッタへの挨拶も済んだ。これで正式に学院での生活が始まるな」
彼女に才人が言う。
「クリス、ほんとに姫さまと仲いいんだな。あんなに楽しそうな姫さま、久しぶりに見た」
それに対し、クリスはこう返す。
「アンリエッタが喜んでいたのは、ルイズにわたしを紹介できたからだと思うぞ?」
「え?」
ルイズは一瞬虚を突かれたかのような顔になった。
「ルイズにわたしを託すことはアンリエッタの、ルイズへの信頼の証だ。わたしとアンリエッタは
友人ではあるが、国というしがらみからは抜け切れない。しかし、ルイズにはそれがないのだから」
「……そうね」
クリスの言葉に、ルイズは若干感心させられた。
「わたしも、アンリエッタのあんな笑顔は久しぶりに見たな。正直、友人を最高の笑顔に
出来るルイズが羨ましいよ」
正面から持ち上げられ、ルイズは気恥ずかしさを覚える。
「な、何言ってるのよ。姫さま、あなたに会えたことだってすごく喜んでらしたじゃない!」
才人はクリスを次のように評した。
「クリスってさ、何て言うか、素直だよなぁ。そういうことを簡単に言えちゃう辺りが」
「そうなのか? 師匠もよくそう言っていた。お前は素直だから色々教え甲斐があると」
クリスが「師匠」の単語を出すと、才人があっと思い出す。
「あ! そうだよ! クリスの師匠のこと、教えてくれよ!」
「ニホンから来たっていうサムライの人?」
聞き返すルイズ。
「そうそう! 詳しく教えてくれ!」
才人がせがむと、クリスは遠い目をしながら語り始めた。
「師匠か……。名はニシキダ・コジューロー・カゲタツ。ここではない世界からこちらに
迷い込んだと言っていた。モノノケ……要するに魔物を退治しながら流浪する旅人だったそうで、
これまで首の前後に顔を持つ鬼、マトーなる悪しき呪術師、心中した男女が化けて出た怨霊などを
退治したという。真実なのかどうかは、わたしにも分からないが」
ニシキダ・コジューロー・カゲタツ……。名前の響きは確かに日本風である。現代日本では
廃れた「諱」があるということは、本当に侍だったのか。さすがに端末に情報はなかった。
「なぁ、サイト。ニホンはどこにあるんだ? 師匠が言っていた通り、異世界にあるのか?」
「えッ、あー、その……すっごい遠くにあるんだ。ここからずーっとずーっと東の、ロバ・アル・カリイレ。
俺はそこからルイズの魔法で召喚されたんだ」
異世界のことをあまり言い触らされても困るので、才人はいつものように「はるか東方から
やってきた」設定を使った。
「むむう……。ロバ・アル・カリイレは幻とも言われる地。だから師匠は『異世界』という
表現をしたのかもしれないな。……おっと、すまん。師匠の話だったな」
「その師匠って人とは、どうやって出会ったんだ? 旅人ってことは、俺みたいに召喚された
訳じゃなかったんだろ?」
「ああ。十年ほど前、師匠は我が国にふらりと立ち寄った。そして、とある森の中で魔物に
襲われていた幼い日のわたしを助けてくれたのだ。迅雷のような速さで剣を抜き、あっという間に
魔物を斬り捨てた姿は、とにかく鮮烈だったな……」
クリスは幼き日のヒーローを、熱い口調で説明した。
-
「わたしは彼に礼をするため、身分を明かし城に招こうとした。が、彼はわたしの身分を知っても
名誉や金を要求せず、更には名乗らずにその場を立ち去ろうとしたのだ。その姿は……わたしに
とっては衝撃だった」
当時を思い返しているのか、クリスの瞳はキラキラと輝いている。
「王族であるわたしに取り入ろうとする者は掃いて捨てるほどいる。だが、その正反対な態度を
取った者は師匠が初めてだった。彼は何故そのように振る舞えるのか、わたしは不思議でたまらず、
素直に尋ねた。『褒美が欲しくないのか』と。すると師匠は、『モノノケを退治することが拙者の
使命。拙者の見出したブシドウ。拙者にとってはこれが当たり前のこと故に、見返りなど求めんのさ』
と答えたのだ」
「へええ〜! 格好いいなぁ」
クリスの説明の中の、カゲタツの『武士道』に才人はいたく感心した。
「わたしは彼をそのように突き動かす『ブシドウ』というものを知りたくて、半ば無理矢理城に招き、
彼が説くサムライの生きざまに感動し、自分を弟子にしてほしいと願った訳さ」
「じゃあその人、まだクリスの国にいるのか?」
才人の問い返しに、クリスは否定する。
「いや……わたしが大きくなったある日に、この剣を残して忽然と姿を消してしまったのだ。
恐らくは、また魔物退治の旅に出たのだろう。その後どうなったのか……今はどこにいるのか、
故郷のニホンには帰れたのか、何も分からない。師匠ほどの剣の腕ならば、滅多なことは
ないとは思うのだが……」
――クリスのあずかり知らぬことだが、カゲタツ……錦田小十郎景竜はその後、ネオフロンティアスペースの
日本に帰還し、そこで天命を全うした。しかしその霊が、封印を破られて復活した二面鬼・宿那鬼を再度
封じるために現世に蘇ったことは、別の話である。
「別れの挨拶と感謝の気持ちを伝えられなかったことは残念ではあるが……わたしは師匠のお陰で
己の生き方を決められた。そして師匠の教えてくれた『ブシドウ』をこの生ある限り全うしようと誓ったのだ」
クリスは己の師匠を思い返しながら、精一杯の感情と熱意を込めながらその思いを宣言した。
ルイズたちが魔法学院に帰還している頃に、トリステインの空の一画でも、学院を目指す
風竜の影があった。
タバサとシルフィードである。トリステイン・ゲルマニア連合とアルビオンの戦争時に、
キュルケにくっついてトリステインから離れていたのだが、戦争も終わったので久々に学業に
復帰するために一路学院へと向かっているのである。
その旅路の中で、シルフィードがふとつぶやいた。
「それにしてもお姉さま、さっきの任務はすごい肩透かしだったのね」
実はタバサの学院帰還は、もう少し後になるはずだった。ツェルプストー家に滞在していた時に
任務が一件飛び込んできて、それを達成してからのはずだったのだが……いざ任務先に赴いたら、
頼まれたことが既に解決されていたので、予定を切り上げたのである。
「不登校児の貴族の子を学院に通わせるようにするなんて、どうなっちゃうのかシルフィちょっと
楽しみでもあったけれど、その子の家の門を叩いたちょうどその日に、えーっと、何て名前だったっけ?
……そうそう、オリヴァンって子が自分から学院に通うようになったなんて。とんだ無駄足だったのね。
まぁ、お姉さまが楽できたからそれでいいんだけど」
シルフィードが勝手にまくし立てることを、タバサはいつものように本を読みながら聞き流す。
「でもあの子、急に意見を翻したみたいで、一体どうしたのかしら? 昨日までは相変わらず
だったそうだけど、ひと晩経ったらすっかり変わったなんて。どんな夢を見たのかしら? それに、
何で逆立ちの練習してたのね? 謎なのね。きゅい」
シルフィードがいくらしゃべっても、タバサはまるで関心を持たない。終わったことに
これ以上首を突っ込むつもりはないと、態度が物語っていた。
シルフィードも肩をすくめ、それ以上不登校児の件には触れずにまっすぐ学院の方向へと飛んでいった。
-
ここまで。
景竜はどこにでもいる。
-
乙です
-
皆様、お久し振りです。
よろしければ、21:10頃からまた続きを投下させてください。
-
オルレアン公夫人の語った話は、タバサにとっては大きなショックだった。
伯父への復讐心を燃やすにあたって、自分がこれまで信じてきた前提には、大きな誤りがあると伝えられたのだ。
ジョゼフは、父であるオルレアン大公に家族を殺すと脅迫することによって、王位を諦めるよう迫った。
そして、優秀で人望の厚い弟に託された王の座を簒奪した。
その後、脅迫が明るみにでることを恐れたジョゼフの手の者によって父は暗殺され、大公家は反逆者の汚名を着せられた……。
これまでタバサはそうに違いないと確信してきたし、シャルル派の貴族たちのほとんどもそれを信じているはずだ。
だが、母によれば、ジョゼフは王位の簒奪などしてはいないのだという。
「葬儀の後にリュティス大司教が読み上げた遺言の中で、先王はジョゼフ殿下を次の国王に指名していました。
それだけでなく、私はシャルル自身の口からはっきりと聞いたのです。『父上は崩御の間際に、後継者を兄上に決められたよ』と」
「そんな、はず……! 伯父にやましいことがないのなら、どうして父さまが……」
必死の面持ちでそう問い掛けてくる娘の頭を優しく撫ぜながら、夫人はそっと首を横に振った。
「それは、私にもわかりません。
ジョゼフ殿下……、いえ、ジョゼフ陛下が、本当にシャルルを暗殺したのかどうかということも――――」
夫人は一旦言葉を切ると顔を伏せて、悲しげに溜息を吐いた。
「それに……、反逆者と呼ばれるに値するような咎が、シャルルにまったく無かったかどうかということさえも、です」
「え……?」
タバサは、一瞬意味が分からずに目をしばたたかせ……、次いで、耳を疑った。
父が、あの優しく誰からも認められ慕われていた父が、本当に反逆者なのかもしれないと?
「……どうして!? 父さまには、反逆をするような理由なんて……!」
「あの人は、王の座を欲しがっていました。
それも以前から、ずっと。渇望しているといってよいほどに……」
「……! そんな……」
タバサは顔を歪めて、いやいやをするように首を振った。
聡い彼女には、この話の先がなんとなく見えてきたのだ。
娘のそんな姿を見て、夫人も辛そうに首を振って少し躊躇ったが、先を続けた。
「……あの人の名誉のためにも黙っておこうと考えていましたが、そうもいかないようです。
シャルルは王に選ばれたいがために、自分の評価を少しでも高めようと、ひたすらに魔法の腕を磨いていました。
まっとうな努力をするだけではなく、いろいろと怪しげな薬や儀式にまで手を出したり、古代の魔法具を求めたりもしていたようです。
それに人脈やお金を使って根回しをして、大臣たちを味方につけたり。
家臣たちをたきつけて、ジョゼフ殿下の評判を貶めるように画策したり……」
タバサは、俯いて苦痛に耐えるようにぎゅっと目を瞑り、何かを否定するように首を横に振っていた。
-
彼女ももう、子どもではない。
どんなに非の打ちどころのないように見える人間でも、御伽噺の中の英雄や聖者とは違うのだということくらいはわかっている。
けれど、あの優しい父が、思い出の中でいつまでも清らかだった父が、実は権力の座に執着していたのかと思うと……。
それでも、耳を塞ぐことはしなかった。
自分が聞いておかなければならない話であることはわかっていたから。
「私にも話してはくれませんでしたが、何やらいかがわしい者たちとも、ずいぶんと付き合いがあったようですし……。
あの人が実際に反乱の相談をしていたとしても、不思議には思いません。
事実、あの人が亡くなった後、あの人を立てる大勢の貴族たちが早々に私の元へ押しかけて、決起を促してきました。
シャルルが関知していたかどうかまではわかりませんが、少なくとも彼らは先王の崩御の直後から既に挙兵の準備をしていたのでしょう」
夫人はそこで、困惑したように顔を見合わせているルイズらの方に向けて、少し頭を下げた。
それから、改めて体を震わせている愛娘の方に向きあう。
「シャルロット……。もし、あなたがジョゼフ陛下を討つなどということをすれば、私たちの母国はどうなるのです。
今のガリアの情勢を、はっきりとは知りませぬ。ですが、国が2つに割れ、多くの血が流れることは間違いないでしょう。
私は、それを避けるためにあの毒杯をあおいだのですよ?」
タバサは、はっと顔を上げて、母を見つめた。
「私はシャルルにも、平和と、私たち家族皆の安らぎを大切に考えてくれるようにと願いました。
でも、あの人は王の座を諦めてはくれなかった。
シャルロット、あなたまであの人の後を追うようなことをしないで。復讐など考えず、私と静かに暮らしましょう」
「母さま……」
静かに泣く母に抱きしめられたまま、タバサはしばらくの間、ただ呆然と立ち尽くしていた……。
・
・
・
-------------------------------------------------------------------------------
・
・
・
酒場での講演を終えたディーキンは、ルイズらの待つ部屋へ戻ると、事の次第を聞かされた。
オルレアン公夫人は席を外し、トーマスやペルスランと別室で話をしている。
忠実な従者たちにも、事の成り行きを自分の口から伝えておかなくては、という考えからだ。
シルフィードはたらふく飲み食いして、暢気に酒場で居眠りしていた。
「うーん……、ディーキンにはあんまり難しいことはよくわからないけど、わかったよ。
それで、タバサはどうするつもりなの?」
ひととおりの話を聞き終えたディーキンは首を傾げて、俯いて物思いに沈んでいるタバサにそう問い掛けた。
-
「……私は……」
「タバサ、その、あなたのお父さまの方にも否があったかもしれないっていうのは、私も信じたくないことだけど……。
復讐は何も生まないし、夫人の言われたとおりだわ。親子2人で、静かに暮らすべきよ」
ルイズが口を挟んで、そう提言する。
「もしもあなたがそれを望むのなら、ゲルマニアの私の屋敷の方に来てくれれば、お母さまもあなたも安全に匿ってあげられるけど……」
キュルケはルイズの提案に沿ってそういいながらも、必ずしも賛成ではない様子だった。
ルイズの言葉は正論かも知れないが、綺麗事だ。
そんな綺麗事で、簡単に復讐の炎が鎮まるものなら世話はないだろう。
確かに夫人の言葉には考えさせられる点はあった。
だが、どんな事情があったにせよ、タバサの父を殺したのがジョゼフなら仇であることには変わりないのだ。
仮にそうでなくとも、タバサの母親に心を壊す薬を飲ませ、姪であるタバサに危険な任務を押し付けたのは間違いない事実ではないか。
向こうに非がないなどと、どうして言える?
なのに大切な親友が、そんな目に遭わされた恨みも晴らせずに、連中の目を怖れてこそこそと隠れ続けながら生きることになるなんて!
夫人の願いを無下にしたくはないものの、その辺りがキュルケにはどうにも納得できなかった。
「その、ミス・タバサが私的な復讐をされるのには賛成できませんけど、悪には報いがあるべきです。
本当のことを確かめて、罰されるべきところがあるなら、法に則って罰を受けるか、贖罪を果たされるべきだと思います。
難しいことだとは思いますけど……」
シエスタは遠慮がちに、しかしはっきりした意思を込めてそう提言すると、ディーキンの方を見た。
彼女は、できればタバサには母親と静かに暮らしてもらって、自分たちでそれを成すことはできないか、と考えていた。
ガリアの国王を相手に一介の平民が、なにを夢のようなことをと誰でもいうだろう。
しかしディーキンやラヴォエラが協力してくれるのなら、きっとできるはずだとシエスタは信じている。
よしんばそうでなくても、パラディンにとっては、目標の困難さはそれを成すことを断念する言い訳にはならないのだ。
「私は……、わからない。どうしたらいいのか……」
皆の視線が注がれる中、タバサは珍しく、そんな弱音のような事を口にした。
それから、ちらりとディーキンの方を伺う。
「……あなたは、どう思うの?」
この人は、私が復讐心に駆られて人を殺すところを見たら、どう思うのだろうか。
人に頼って匿ってもらい、ひたすら隠れ続ける安息への逃避の道を選んだら、どう思うのだろうか。
そして、もしこの人に失望され、軽蔑の目で見られでもしたら、私は何を思うのだろうか。
今まで誰も頼らずにやってきた自分が、そんな人の顔色を窺うような気持ちを抱いていることに、タバサは愕然とした。
急に自分がひどく弱く、頼りなくなってしまったように感じる。
ちょうどその時にディーキンと視線が合って、タバサは慌てて目を逸らした。
-
「ンー……、どうしたらいいかって聞かれても、本当のことがまだよくわかってないから何とも言えないの」
ディーキンはそう答えた後、なぜか少し躊躇してから付け加えた。
「うーん、ただ……。ディーキンも昔、ママの復讐をしたことがあるからね。
だから、タバサが相手をものすごく憎くて、復讐を諦められないっていう気持ちはよくわかるよ」
ディーキンの口から出た思いがけない言葉に、しばらくの間、皆戸惑ったように顔を見合わせた。
この人懐っこい亜人は、憎しみだの復讐だのとはまったく無縁な、天真爛漫な存在だとばかり思っていたのだ。
「ちょ、ちょっとディーキン。それって本当?
あんたが昔、母親の復讐をしたなんて話、ぜんぜん聞いてないわよ?」
ルイズが全員を代表してそう質問した。
「本当なの。ディーキンは嘘なんてつかないの。でも、ディーキンのお母さんのことじゃないよ?」
「え、だって……。あんた今、ママって言ったじゃない」
「えーと……、だから、ママはママなの。お母さんじゃないよ。
ルイズは、耳の調子が悪いの?」
「……?」
「ママはね、ディーキンが昔立ち寄った村の酒場の、太った女主人なの。
村人が彼女のことを“ママ”って呼んでたから、ディーキンもそう呼んでたんだ」
「あ、ああ……。なんだ、そういうことね」
得心がいって頷くルイズをよそに、ディーキンはしみじみと、その時のことを思い返していた。
クロマティック・ドラゴンの間には、“血のごとき甘み、火炎のごとき手ごたえ、金よりも珍しきこの遊び”という言い回しがある。
ディーキンは長い間その言葉の意味がよくわからなかったが、あの時、初めてわかった。
その言い回しが表わすもの……、噴き上がるように熱く、それでいて冷血で甘い復讐の味というものを、初めて実感したのだ。
「ディーキンはそのとき、実際に冒険をするために雇われたの。初めて、一人だけでね。
あんまり楽しいお話じゃないけど……、聞いてもらえる?」
ディーキンはそう言うと、珍しくリュートを手に取らず、芝居がかった演出も無しに、話をし始めた。
ボスとの最初の旅は、最終的には世界の危機を救うまでのものになった。
それだけの旅に同行したにもかかわらず、ディーキンは自分がまだ冒険者ではないことを、彼と別れて痛感した。
あの時の自分はまだ、『ボスのお供』にしか過ぎなかった。
一人では、何もできなかったのだ。
比べれば、これからする話はまったく大したものではない。
色々と辛いこともあったし、今思い返せば恥ずかしいこともしていた。
成し遂げたこともごく小さなものでしかなく、自慢げに語れるような手柄話ではない。
だから、リュートの演奏付きの叙事詩形式で語るようなこともしない。
それでも、あれこそが正真正銘、自分の初めての『冒険者』としての仕事だったことは確かだ――――。
-
短いですが、今回は以上になります。
またできるだけ早く続きを書いていきますので、次の機会にもどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、失礼しました……(御辞儀)
-
おつです
-
初めまして。
最近になってゼロ使を読んだ新参者ですが、投稿させて頂きます。
バイオハザード6よりレオン・S・ケネディを召喚。
時系列としてはバイオ6の数か月後となります。
投稿は25分頃より始めたいと思います。
-
闇がある。
何処までも広がっているかのような、深い闇。
まるでこの国のようだ、と男は思う。
数か月前に起きた世界規模のテロ事件。被害者の総数は15万人ともそれ以上とも言われ
ている。標的の一つとなったアメリカもまた、大統領と7万人の国民を失った。
全てを飲み込むような目の前の暗闇は、まるでアメリカの、いや、この世界の行く末を
暗示しているようではないか。
――だとすれば、まだ希望の光は残ってるって事か。
フラッシュライトの小さな光が、男の眼前を照らし出していた。
そうだ。まだ大統領と志を共にした、自分達が残っている。そして、世界各地で同じ理
想を目指して戦っている盟友達がいる。
「だからこそ――その光を遮るこいつらを放ってはおけない。そうだよな、アダム……」
大統領であり友であった男に語り掛けながら、男――レオン・S・ケネディは、光の中
に浮かび上がった影へと、静かに銃口を向けた。
BIOHAZARD CODE:Zero
大統領の死による混乱が続く中、情報部が入手したテロリストの潜伏情報。その情報が
久方振りの休暇をどのように過ごそうかと思案していたレオンの元に伝えられたのが、全
ての始まりだった。
――俺はトム・クルーズじゃないんだがな。
休暇を邪魔されるのはいつもの事だ。もはや諦めてはいるものの、次に休暇が取れるの
はいつの事になるのだろう……そう思うと、一言ぼやかずにはいられなかった。
「――泣けるぜ」
本来であれば、テロリストの制圧は大統領直轄のエージェント組織『DSO』――Divisio
n of Security Operationsに所属するレオンの仕事ではない。しかし、テロリスト達がB.
O.W.を所持しているとなると話は別だ。
B.O.W.――Bio Organic Weaponと名付けられたそれは、核兵器以降に誕生した最悪の非
人道的武器であり、使用はもちろん所持でさえも国際法で禁じられている。
B.O.W.を根絶し、バイオテロの脅威から国家を守る。それこそが、DSO所属のエージェ
ントの使命であると同時に、バイオテロによって人生を狂わされたレオンにとっての存在
意義でもあった。
テロリストのアジトとして利用されていた、今は使われていない地下水道。光の届かぬ
暗闇の中、レオンはその最悪の兵器と対峙していた。
筋肉組織だけでなく、脳すらも剥き出しとなった異形の肉体。長い手足の先についた鋭
い鉤爪。カメレオンのような長い舌。舐めるもの――リッカーと名付けられたその生物兵
器が、かつては人だったなどと誰が信じられるだろうか。
辺りに散乱している肉片は、テロリスト達のものだろう。
馬鹿な事を、と思う。B.O.W.は人の手に負えるようなものではない。奴等が敵も味方も
関係なく、全てを奪っていく光景を、レオンは嫌になるほど目にしている。
黒板を引っ掻いたような不快な叫び声が、レオンの意識を呼び戻した。
軽く舌打ちし、構えていたAK-47のトリガーを絞る。分間600発の弾丸がリッカーの体を
撃ち貫いた。
-
しかし、身を裂かれながらも、リッカーは怯まない。体を素早く左右に揺らし、器用に
致命傷を避けながら、両手両足でレオンの元へと素早く這い寄ってくる。
レオンは知っている。この悪魔の使いを地獄へ送り返すには、脳髄を破壊する以外に方
法がない事を。
銃口が獲物の頭部を捉えたと同時に、リッカーの逞しい後肢が地面を蹴った。
死を目前にしながらも、レオンは冷静だった。
上半身を引き、テロリスト達を解体した鉤爪の一撃を寸前で躱す。そのまま仰向けに倒
れ込んだレオンの頭上を、勢い余ったリッカーが飛び越えた。
逆境が瞬時にして好機へと転じる。
レオンは目の前にある獲物の無防備な腹部に、ありったけの弾丸をお見舞いした。
これには流石のリッカーも無事ではいられなかった。真っ黒い血液を撒き散らしながら
転がるように着地すると、レオンから距離を置こうと駆け出す。
邪魔だと言わんばかりに、レオンはアサルトライフルを地面に転がした。弾倉が空にな
っている。周りには複数の空になった弾倉と、二体のリッカーの骸が転がっていた。
――調子に乗って、サービスしすぎたか。
すかさずサイドアームへと手を伸ばす。
右太腿のレッグホルスターに収められているH&K VP70では力不足だ。体の向きを反転さ
せながら起き上がると同時に、黒のレザージャケットの下、左脇のショルダーホルスター
から拳銃を引き抜き、そのまま膝射の姿勢をとる。
一分の無駄もない、流れるような動きだった。
その手で握られているのは、カスタム10インチ銃身付きのデザートイーグル50AE。ハン
ドキャノンの異名を持つ、イスラエル製の大口径オートマグナムもまた、新人警官時代か
らの愛用品だ。
約20メートル先を駆けるリッカーの後頭部に照準を合わせる。
後は引き金を引けば――――
瞬間。辺りは眩い光に包まれた。
Chapter.1
「何でよ……何で出てこないのよ……」
辺り一面に広がる豊かな草原の真ん中で、ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・
ラ・ヴァリエールは一人途方に暮れていた。
ハルケギニア大陸の西方に位置する小国、トリステイン王国。その中に存在するトリス
テイン魔法学院の二年生へと進級するルイズ達が、試験も兼ねて初めに行う儀式、それが
『春の使い魔召喚の儀式』だった。
メイジの手足となる使い魔を召喚するだけでなく、使い魔の能力により主の今後の属性
を固定し、専門課程へと進む為の神聖かつ重要な儀式。
その日はルイズにとって、汚名を返上する絶好の機会となるはずだった。
昨日もクラスメイトに宣言したばかりだ。私を馬鹿にした奴等全員でも及ばない、神聖
で美しく、そして強力な使い魔を召喚してみせると。
呪文を唱え、杖を振る。それで使い魔が呼び出される。決して難しい事ではない。現に
ルイズより先に儀式を行った級友達は、使い魔の能力の差異はあれど、一人の例外もなく
儀式を成功させている。
それなのに。
のどかな風景に場違いな爆発が巻き起こる。
――まただ。
そう、ルイズが何度杖を振っても爆発が起きるだけで、使い魔となるべき生物は現れる
気配すらない。
「どうした、ゼロのルイズ! また失敗か!?」
嘲笑が浴びせられる。気が付けば召喚を終えていないのはルイズ一人となっていた。
その声につられて笑った生徒は半数程度か。残りの半分は、後何度同じ光景を見せられ
なければならないのかと、もはや呆れて物も言えないといった様子だ。
悔しさから、グレーのプリーツスカートの裾を握る。
-
見れば爆風を間近で浴び続けたせいで、スカートのみならず、白いブラウスも黒いマン
トもボロボロである。桃色がかったブロンドの髪も、透き通るような白い肌も煤で汚れて
しまっている。
自分の惨めな姿に涙が零れそうになり、ルイズは慌てて天を仰いだ。
しかし、諦めるわけにはいかない。私は由緒正しき名門中の名門、ラ・ヴァリエール公
爵家の三女なのだ。
震える手で杖を構え直すと、もはや何度唱えたかも分からない呪文を唱える。
「宇宙の果てのどこかにいる我が僕よ! 神聖で美しく強力な使い魔よ! 私は心より求め
訴えるわ! 我が導きに応えなさい!!」
今までにも増して大きな爆発。
爆風で巻き上げられた土煙により、視界が遮られる。
辺りから生徒によるものであろう溜息が聞こえた。
――また、失敗なの……?
「お、おい! 何かいるぞ!!」
「嘘っ、ゼロのルイズが成功したの!?」
もう召喚を行う気力もない。精も根も尽き果て、項垂れていたルイズであったが、周囲
の反応に慌てて顔を上げる。
確かに、土煙の中に黒い影のようなものがゆらゆらと動いている。
――ほ、本当に成功した!?
影は主を認識したのか、低い姿勢でルイズに向けて歩を進め始めた。
生徒達の好奇の視線が影へと集中する。
ゼロのルイズが呼び出した使い魔。きっと矮小な生物に違いない。それともまさか、本
当に強力な使い魔が――?
「あ、あれが、ルイズの使い……魔……?」
ようやく影が土煙の中から姿を現した時、その場の空気は凍りついた。
ハルケギニアの子供達が醜悪な生物と聞いて思い浮かべるのは、狂暴で野蛮なオーク鬼
だろうか? それとも、ファンガスの森に住むという合成獣だろうか?
少なくとも、この場にいた子供達は例外なく認識を改める事となった。
どのような生物も目の前の異形――リッカーと呼ばれていた生物に比べれば可愛いもの
だと、心からそう思った。
いや、ただ一人だけ、例外が存在した。
「あ、あなたが……私の使い魔、なのね」
ルイズは泣き笑いの表情を浮かべ、ゆっくりと自分の使い魔へと近付いていく。
気持ちが悪くないわけではない。それでも、この生物は自分の呼び掛けに応えてくれた
のだ。それが嬉しかった。
「ほぉら見てごらんなさい! 私の言った通りだったでしょ!? そりゃ火トカゲや風竜も
凄いわよ? でも、こんな使い魔、見た事ある!?」
自分を馬鹿にしていた級友達を振り返り、高らかに勝利宣言をしてみせる。
もっとも、それに対する反応は何一つ返って来なかった。
凄いと言えば凄いのかもしれない。しかし、あれを使い魔にしてもよいと言われたら、
果たして自分は嬉しいだろうか?
考えれば考えるほどどう反応すればいいか分からず、彼等はただただ呆然としていた。
唯一リッカーだけが、主のあげた騒音に反応した。
不快そうに首を回すと、ルイズに向け、大きく口を開く。
「お、おい!」
「へ?」
高速で射出されたそれは、もはや舌ではなかった。
当たれば肉を裂き、骨を砕く、肉色の槍。
後ろを向いているルイズには何が起きているのか分からない。いや、正面を向いていた
生徒達でさえも、咄嗟の事に声をあげる事しか出来なかった。
そんな中、青い髪の小柄な少女だけが、状況を冷静に判断していた。
自分の身長ほどもある長い杖を一振りすると、不可視の風の槌がリッカーを横殴りに弾
き飛ばす。エア・ハンマーと呼ばれる魔法だ。
-
「ちょっと、タバサ!?」
彼女の隣にいた赤毛の少女が驚いたように声をあげた。
生徒達の中では有数の実力者である彼女をもってしても、瞬時に目の前の状況を理解す
る事は困難だったようだ。
「あれは、危険」
タバサと呼ばれた少女は短く呟く。
理由は分からない。しかし、あの生物を見た瞬間に直感した。
あれは、この世界にいてはならないものだ。
吹き飛ばされたリッカーは空中で一回転し体勢を整えると、着地と同時に跳躍した。
――まずい。
子供達の引率者であるジャン・コルベールは慌てて杖を構える。タバサと赤毛の少女も
危険を感じ取り、怪物に杖を向けた。
直後、タバサは自分の読みがまるで甘かった事を痛感する。
先程放った渾身の魔法は、怪物に致命傷を与えていないどころか、動きを制限するにも
至っていない。唯一開いたルイズとの距離も、その驚異的な跳躍力の前では時間稼ぎにさ
えならなかった。
「あ……」
三人に遅れて怪物の方に向き直ったルイズは、ようやく目の前の生物が友好的でない事
を理解した。死は既にルイズの目と鼻の先まで迫っており、その鋭い鉤爪は今まさに振り
下ろされんとしている。
殺される――――
反射的に、目を瞑る。それが無力なルイズに出来る小さな、唯一の抵抗。
暗闇の世界に、轟音が響き渡った。
生暖かい液体が肌を伝う。
目を閉じていても、それが血だという事ははっきりと分かった。
これが死か。
痛みを感じる間もなかったのは、不幸中の幸いだったのかもしれない。でも、贅沢を言
うなら、心臓を一突きにされた方がよかった、と思う。
母や二人の姉譲りの美貌は、魔法の才能がない自分にとっての数少ない自慢だった。頭
が潰れた死体を見て、皆は私だと分かってくれるだろうか。
いや、もうそんな事を考える必要もないのだ。
ああ、父さま、母さま、姉さま、ちいねえさま。先立つ不孝をお許し下さい――
――? あれ?
どこか釈然としないものを感じ、恐る恐る潰れた頭部へと手を伸ばす。
ぬるぬるとした不快な感触。しかし、真っ二つに裂かれたはずの頭は、意外にも綺麗な
球形を保っている。
目も鼻も口も、元あった位置にちゃんとある。それどころか、傷口らしきものさえ何処
にも見当たらない。
――私、生きてる……?
ゆっくりと瞳を開く。
まず飛び込んできたのは、真っ赤に染まった自身の両手。そして、その先に横たわる、
血溜まりに浮かぶ自らの使い魔の姿。
剥き出しの脳に穿たれた大きな穴を見て、ルイズは自分を濡らしているのがこの生物の
血液だと理解した。
――誰がやったの?
この場で一番の実力者であろう引率の教師は、杖を構えたままの姿勢で固まっている。
コルベールだけではない。そこにいた皆は同じ様に一点を見つめ、立ち尽くしていた。
ルイズも我知らず、皆の視線を辿る。
あれは先程自分がサモン・サーヴァントを行い、使い魔を呼び出した場所ではないか。
――何か、いる。
-
先程の恐怖がフラッシュバックし、ルイズは思わず体を強張らせた。
それは、人間の男性だった。
見た事のない黒い衣服に身を包んだ、金髪の男性。片膝をつき、その両手には銀色に鈍
く光る奇妙な形の銃が握られている。
鋭い碧眼が真っ直ぐにルイズを捉えていた。
――何が起きた。
激しい光に包まれ、レオンは眼を細めた。
光がリッカーの前方に集束していく。
そこに現れたのは強い光を発する鏡――としか言いようのない物体だった。
何の前触れもなく現れた鏡に、リッカーは気付いていない。この生物は露出した脳髄が
眼球の部分までせり出している為に、目が見えないのだ。
いや、仮に視覚能力を有していても、突然すぎる障害物の出現に反応出来たかどうか。
ぶつかる――レオンがそう思った瞬間、リッカーはまるで魔法のように姿を消した。
鏡の中に吸い込まれた。そうとしか説明しようのない状況に、レオンは考えるよりも先
に駆け出していた。
恐れも迷いもなかった。
B.O.W.を世界から根絶する。これ以上奴等によって苦しむ人間を増やさない。その目的
だけが彼を突き動かしていた。
後には静寂と闇だけが残された。
受け身を取りつつ回転し、片膝をつき、姿勢を整える。
おびただしい土煙によって視界は完全に塞がれているが、空気の流れから、自分が室外
に出た事だけはかろうじて理解出来た。
――奴はどこだ?
瞬間。突風がレオンの横を通り抜け、土煙を晴らす。
開かれた視界に飛び込んできたのは、桃色の髪の少女と、少女に向かい爪を振り上げる
仇敵の姿だった。
レオンは一瞬の躊躇もなく、引き金を引く。
ハンドガンの中でも最大級の威力を誇る.50AE弾はリッカーの脳髄へと吸い込まれ、少
女の頭上を抜けていった。
数秒の後、少女は目を開いた。
少女の無事を確認し、レオンは安堵する。
「な、ななな……」
少女の可愛らしい唇がわなわなと震える。あんな化物に襲われたのだ。無理もない。
驚かせてすまない。怪我はないか?
そう声を掛けるよりも早く、少女の口から発せられたのは、レオンにとって思いもよら
ない言葉だった。
ルイズは混乱していた。
サモン・サーヴァントを行ってから僅か数秒の間に起きた様々な出来事は、彼女の情報
処理能力のキャパシティを大きく超えていた。
ようやく皆を見返せたと思った。嬉しかった。涙が出そうになった。
次の瞬間には、死を覚悟した。怖かった。皆ともう会えないかと思うと、悲しかった。
そして、目を開けたら、これだ。
結局何が起きたのか、まるで理解が追い付かない。あれこれ考えるうちに様々な感情が
ない交ぜになり、そして、爆発した。
「――何すんのよ、私の使い魔に!!」
それは異様な光景だった。
ボロボロの服を着て、体中を赤く染めた少女が、突然現れた男に向かい怒鳴り声をあげ
ている。しかも、その少女は男が救ったはずの少女ではなかったか。
-
これにはレオンも流石に面食らったものの、怒鳴られた事自体は問題ではなかった。
B.O.W.の根絶、彼はそれを自分に与えられた使命だと思っている。決して称賛を求めて
やっている事ではないのだ。
問題は彼女が放った言葉、その内容だ。
使い魔、と少女は言った。まるで魔女か何かのような言い方が気になったが、その言葉
が意味するものは一つしかない。
「お前がリッカーを操っていたのか!?」
思わず声に怒気が孕む。
確かにレオンは、人間がB.O.W.をコントロールする術を知っている。それが同時に、文
字通り人である事を捨てる結果になるという事も。
少女は一瞬怯んだ様子を見せたが、再びレオンを睨みつける。
「そ、そうよ! 何回も……何回も失敗して、ようやく成功したのに……」
怒りとも悲しみとも付かぬ表情で、う〜〜と唸る少女を尻目に、レオンは素早く周囲を
見渡した。
土煙のせいで今まで気付かなかったが、黒いマントを羽織った子供達の集団に取り囲ま
れている。
――今から楽しいハロウィンパーティー……ってわけじゃないよな。
そう、レオンを囲んでいるのは子供達だけではない。子供達一人一人の傍らには、およ
そこの世のものとは思えない異形の存在が寄り添っていた。
尾に炎を灯した大蜥蜴。浮遊する巨大な目玉。中にはドラゴンとしか呼びようのない生
物までいる。
その光景に、レオンはかつてヨーロッパの辺境の村で関わった事件、その黒幕である集
団を思い浮かべていた。
ロス・イルミナドス教団。
あらゆる生物に寄生し、異形の怪物へと変える寄生体『プラーガ』を用い、世界征服を
企んだカルト教団。
レオンの手によりその野望は潰えた。しかし、生き残りがいないとも限らない。
デザートイーグルを握る手に力を込める。
しかし、子供達は戸惑いの表情こそ浮かべているものの、こちらに対する敵意は感じら
れない。それは異形の獣達についても同様であった。
――B.O.W.ではないのか?
「あー……少しよろしいですかな」
どうにも食い違っている様子のレオンとルイズを見かねて、コルベールは口を挟んだ。
「ミス・ヴァリエール、とりあえずあなたは顔を拭きなさい」
どこから取り出したのか、濡れたタオルをルイズに差し出す。体中に血の雨を浴びてい
る事を思い出したルイズは、慌ててタオルを受け取ると、顔を拭い始めた。
レオンはこの場にいるおそらく唯一の成人を、ねめつけるように観察する。
黒いローブに禿げ上がった頭という出で立ちは、否が応にもロス・イルミナドスの神父
を連想してしまう。
「ええと、私はコルベールと申します。あなたのお名前を伺ってもよろしいですかな」
コルベールの柔らかな物腰に、レオンの警戒心が僅かに緩む。
確かに、話を聞かなければ何も始まらない。
「レオン……レオン・スコット・ケネディだ」
「では、ミスタ・ケネディ。まずは彼女……ミス・ヴァリエールを救っていただき、あり
がとうございました」
予想外の感謝の言葉にレオンは呆気に取られた。ルイズはルイズで、ようやく状況が飲
み込めたのか、バツの悪そうな表情を浮かべている。
「ミス・ヴァリエールが先程の獣とあなたを呼び出したのは事実です。しかし、あの獣を
操っていたのは彼女ではありませんぞ。まだコントラクト・サーヴァントを行っておりま
せんからな」
そうでしょう? と水を向けられたルイズは、う……と声を漏らし、口を噤んだ。
確かに、使い魔としての契約を行っていない以上、あの怪物はまだルイズの使い魔とな
ったわけではない。
しかし、レオンが反応したのは別の個所だった。
「ちょっと待ってくれ。俺を、呼び出した……?」
-
それはつまり、あの鏡はこのヴァリエールと呼ばれる娘が作り出した物だという事か?
レオンは再度冷静に、自分の置かれている状況を確認する。
豊かな草原と、その先に見える城のような石造りの建築物。少なくとも、自分の記憶の
中にこのような風景は存在しない。
自分は一瞬のうちにまるで異なる場所へと“呼び出された”。さらに、周りを囲む存在
するはずのない生物達……
レオンの頭に最悪の想像がよぎった。
「ミスタ・コルベール、やり直しを要求します! 私の使い魔……候補が死亡した以上、
それは当然の権利のはずです!」
しかし、そんなレオンの思考は、ルイズの怒声によって掻き消される。
「それは駄目だ、ミス・ヴァリエール」
「どうしてですか!?」
「何故なら、君が呼び出した使い魔はまだ生きている」
「なっ……」
ルイズは驚愕の表情を浮かべたまま、ゆっくりと振り返った。レオンの怪訝そうな瞳と
視線がぶつかる。
「まさか……この平民を使い魔に……?」
「そうだ。君も知っての通り、春の使い魔召喚は神聖な儀式。好む好まざるに関わらず、
彼を使い魔にするしかない。例外は認められない」
状況の把握の為に、言い争う二人を静観していたレオンだったが、聞き捨てならぬ発言
に流石に口を挟もうとする。
「待て。誰を使い魔にするだと? 俺を無視して話を進め――」
「ああ、もう! 静かにしてっ!!」
レオンは険しい表情でルイズを眺めていたが、やがて諦めたように肩を竦めた。
警戒を解くわけにはいかないが、どうやら彼等は自分の敵というわけではないらしい。
少なくとも、今すぐに何かをされるという事はなさそうだ。
ならば、情報が何もない今、しばらくは成り行きを見守るしかない。
そんなレオンの事など目に入らない様子で、ルイズは俯いてぶつぶつと一人何かを呟い
ていた。
――平民を使い魔に? そんな話、聞いた事がないわ。前代未聞よ……
それも、決して良い意味での前代未聞ではない。目の前の平民は、自分が宣言した神聖
で美しく強力な使い魔からは大きくかけ離れた存在なのだ。
このままでは、また皆に馬鹿にされてしまう。ゼロのルイズには平民の使い魔がお似合
いだとか何とか。
ほら、現に今だって――
「は、はは……き、聞いたか? ルイズのやつ、平民を使い魔にするらしいぜ……」
「あ、ああ。ゼロのルイズにはお似合い……だよな……」
しかし、ルイズの予想に反して、生徒達の反応は控えめであった。
呼び出された男は、確かにただの平民のはずだ。
しかし、服の上からでもはっきりと分かる鍛え上げられた肉体が、猛禽類を思わせる鋭
い目つきが、何より、引率の教師ですら止められなかった得体の知れない怪物を、一撃の
もとに葬って見せたという事実が、子供達に嘲笑を浴びせる事を躊躇わせていた。
「ねえタバサ、彼、平民にしてはなかなかイケてない?」
赤毛の少女――『微熱の』キュルケは隣にいる友人に囁いた。
長身。健康そうな褐色の肌。洗練されたプロポーションから漂う大人びた色気。ルイズ
とは何もかも対照的なこの少女は、他の生徒とは異なる視点からレオンを観察していた。
見ればあの平民は背も高く、なかなか精悍な顔立ちをしている。まばらに生えた不精髭
が顔を覆っているが、逞しい体と相まって、それはそれでワイルドだ。奇妙な服装にさえ
目を瞑れば、名のある騎士といった感じだろうか。
――あら、珍しい。
自分から声を掛けておきながら、キュルケは意外そうに友人を見つめた。
普段であれば、何が起きようと我関せずという感じで読書に勤しんでいるタバサが、そ
の手に開いた本から顔を上げているのだ。
-
しかし、キュルケはタバサの視線の先にまでは気を回さなかった。
彼女の視線はレオンではなく、その少し手前――血溜りに浮かぶリッカーへと向けられ
ていた。
間違いなく、死んでいる。死んでいるはずである。
しかし、今なお拭い去れない、この嫌な予感は何だろうか。
そんなタバサとは違い、ルイズは自分を襲った怪物の事など、すっかりと忘れていた。
正確には、今現在彼女の頭の中にあるのは『この平民を使い魔にして良いのか否か』、
それだけである。この一大事に他の事を気にしている余裕なんてない。
目の前の平民に対する自分の想像とはいささか異なる周囲の反応に、ルイズはうむむと
考える。
これ以上食い下がったところで、ルールだの伝統だのを持ち出され、拒否される事は目
に見えている。
それならば……
ルイズは改めて、不服そうに自分を見下ろしている平民を熟視した。
軍人というわけではなさそうだが、体の鍛え方からして、戦闘を生業としている人間な
のは間違いないだろう。主を守るという使い魔の役割は一応こなせそうだ。
というか、気が動転して怒鳴ってしまったが、先程もあの怪物から守ってもらったんだ
った。
――農民や商人じゃないだけ、まだマシか……
ルイズは一人頷くと、覚悟を決め――それでも未だ不機嫌そうな表情のままで――自分
の使い魔候補を見上げた。
「しゃがみなさい」
「……いったいどういうつもりだ? せめて状況を説明しろ」
「いいから! 背が届かないじゃない!」
レオンは諦めて、言われた通りに膝をつく。
相変わらず状況は飲み込めないが、そんな中でも一つだけ分かった事があった。この少
女は我儘だ。しかも、かつて自分が救った大統領令嬢が可愛く思えるレベルの。
そのような事を考えていると、突然少女の左手に顎を固定される。
「おい」
「か、感謝しなさいよね。貴族にこんな事されるなんて、普通は一生ないんだから……」
嫌な予感がする。しかし、まさかとも考える。
このような展開になる予兆など、どこにもなかったはずだ。
「我が名はルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール。五つの力を司
るペンタゴン。この者に祝福を与え、我の使い魔となせ――」
――俺の悪い予感はだいたい当たるんだ。
唇に柔らかな感触を感じながら、突然の事に思考停止に陥りかけた頭で考える。
悪い予感というのは語弊があるかもしれない。しかし、レオンには自分の半分も生きて
いないであろう少女に唇を奪われ、喜ぶような趣味はない。
「……終わりましたっ!」
レオンがそのような失礼な事を考えているとは露知らず、ルイズはレオンを突き飛ばす
ようにして、前屈みになっていた上体を起こした。
頬が赤く染まっている。ファーストキスだった。
しかし、レオンはレオンでそんな事情など知る由もない。あまりにも理不尽な扱いに抗
議の声をあげようとしたその時、
「っ……!?」
レオンの左手の甲を焼けるような痛みが走った。
「おい、いったい何を……!」
「使い魔のルーンが刻まれてるだけよ。すぐ終わるわ」
言葉にならないレオンの問いに、苛立たしげにルイズが答える。
その言葉通り、痛みは数秒の後には嘘のように引いていた。
-
レオンは訝しげに左手を視線の先に掲げる。いつの間にか、異国の文字のようなものが
手の甲に浮かび上がっていた。
「ふむ、コントラクト・サーヴァントは一度で成功したようだね。それにしても、これは
……何とも珍しいルーンだな」
いつの間に隣にいたのか、コルベールがレオンの左手を覗き込んでいた。
そこに刻まれたルーンの形状をメモ用紙にスケッチし終えると、どうやら満足したらし
い。何の説明もないまま踵を返すと、子供達に教室に戻るよう促し始めた。
「……刻むなよ」
取り残されたレオンは、呆れたように呟いた。
レオンはエージェントとなってから、多少の事では動じなくなっていた。日常的に異形
の怪物と戦っているのだから、当然と言えば当然だろう。
しかし、そんなレオンも、目の前の光景には言葉を失った。
コルベールを視線で追ったその先で、子供達が一人また一人と宙に浮かんでは、城のよ
うな建物に向かい飛び去っていくのだ。
――本当に、俺の悪い予感はよく当たるんだ。
段々と小さくなっていく子供達を仰ぎ見ながら、レオンは自嘲気味に唇を歪めた。
また一つはっきりした事がある。先程頭によぎった最悪の想像は、決して勘違いではな
かったという事だ。
この世界は、自分のいた世界ではない。
ドラゴンが存在し、人間が空を飛ぶ世界――
「……何よ? 何か言いたい事でもあるわけ?」
気が付けば、草原にいるのは自分とこの我儘な少女だけとなっていた。
不機嫌そうな口調とは裏腹に、困ったような表情を浮かべている。彼女自身もこの妙な
使い魔をどう扱っていいか、まだよく分からないのだろう。
「言いたい事、か……」
言いたい事も尋ねたい事も山のようにある。しかし、いったい何から尋ねたものか。
しばらく考えていたレオンだったが、やがて諦めたように左手に刻まれた紋章へと視線
を落とす。そして一言だけ、もはや口癖になりつつある台詞を呟いた。
「――泣けるぜ」
-
今回の投稿は以上となります。
今後は週一程度のペースで投稿出来ればと思っております。
至らぬ点もあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いします。
-
新人おっつおっつ
-
バイオおつおつ
リッカーが使い魔じゃなくてよかった
-
新人さん大歓迎
まとめサイトにも話を載せるといいぞ
-
乙
新人さんが来るとか嬉しい
-
皆様、こんばんはです。
よろしければ、また20:00頃から続きを投下させてください。
-
「あれは……ボスとした最初の冒険が終わって、彼と別れた後だから……。
まだ、ウォーターディープに着く前のことだね」
ディーキンはルイズらの聞き入る中で、静かに自分の『冒険者としての最初の仕事』の話を語り始めた。
「旅行中に夜になって、小さな人間の村へ着いたの。
その時、ディーキンはとてもお腹がすいてたから、その村に入ったんだ――――」
-----------------------------------
「ううう……」
ディーキンは崖の上からその小さな村の灯りを眺めながら、もうずいぶん長いこと躊躇していた。
まるで神経質な鼠のように、不安げに何度も、きょろきょろと周囲を伺っている。
まだ決心が固まらないうちに村の人間に見つからないか、心配なのだ。
少し前までは、こうじゃなかった。
あの“ボス”と共に偉大な冒険を終えて、少しく自信を持っていたものだった。
もう少し堂々と、人間の前に出ていってみたことも何度もある。
けれど、彼と別れて一人で旅をしてみて分かった。
英雄なのは、あくまでもボスだったのだ。
自分は決して英雄でもなければ、強くもなかった。
人間の前に出ていっては追い回される、そんな経験を何度もした。
逃げずにあくまで粘ってみようという根性も、彼らに対抗しようという勇気も、自分には出せはしなかった。
そのせいで、この頃は挑戦してみようとする気持ちからして、すっかり挫けてきていたのだ。
けれど、自分の小さな胃袋がまたグーグーと鳴って、しまいにきりきりと痛んでくるに及んで、ディーキンもついに覚悟を決めた。
「このままじゃ、飢え死にしちゃうし……。
ディーキンは、行くしかないってことだよね……」
前の夜に、大きなクマに荷物を荒らされて、とっておいた食べ物をみんな食べられてしまったのだ。
レンジャーでもない自分が、この寒い季節に野外での狩りや採集だけで凌ぐのは、土台無理な相談だった。
実際には、本気を出せば自分でも、クマくらいは追い払うことができたかもしれない。
でも竦み上がってしまって、とても立ち向かう勇気はなかったのだ。
食べ物を取られた仕返しくらいで、悪気もないただの動物を傷つけたり殺したりする気が起きなかった、というのもある。
だがどちらかといえば、そのことを言い訳にして自分を正当化していた、というほうがより正しいだろう。
「……アア、ディーキンはどうして、食べ物を作る呪文を覚えておかなかったのかな……」
《お祭りの御馳走(フェスティヴァル・フィースト)》の呪文かなにかを自分が使えれば、こんなことをしなくても済んだのに……。
ふとそう考えて、自分の挑戦心がすっかり萎えてしまっているのを改めて自覚する。
ディーキンは、ひどい自己嫌悪に襲われた。
自分は、ボスやご主人様がいなくてはなんにもできない、まったくの弱虫だ。
とにかくひたすら頭を下げて回って、余り物の一皿でももらえれば恩の字だ。
それが駄目なら、家畜の餌のいなご豆でもなんでもいい。
食べ物さえもらえればすぐに村から出て行くと言おう、馬小屋でもいいから寝かせてくれとまでは求めるまい。
ディーキンは頭の中で何度も頼み方を検討し直しながら、おずおずと村の方へ降りていった……。
-
-----------------------------------
「それで……。ディーキンはおそるおそる酒場の扉から中をのぞいて、食べ物をなにかくれないかって聞いたの。
そしたら、太った人間の女の人が顔を出して、『いいけど、そんな寒いとこにいないで入りなよ』って言ってくれたんだ!」
ディーキンはどこか遠くを見るような目をして、しみじみとその女性のことを話し始めた。
「本当に変だったよ。ディーキンはおかしな気持ちだったの。
だって、ディーキンを中へ入れてくれて、たくさん食べさせてくれて、部屋まで用意してくれたんだもの。
たぶん、彼女はコボルドを見たことがなかったし、いろんなお客の相手をしてきたからかな……。
とにかく、ディーキンのことをあんまり奇妙だとは思わなかったみたい」
「へえ、ディー君は運が良かったのね」
「うん。ディーキンはママみたいな人に会えて、とても運が良かったよ!
後から酒場に入ってきた人は頭にきてたけど、太った女主人が話して、その場を収めてくれたんだ。
ママがディーキンのことを、『何言ってんだい、この子は紳士だよ。紳士に失礼じゃないか』って言ったんで、みんな落ち着いたの」
その時の気持ちを思い出して、ディーキンは照れたように頬を掻いた。
「ディーキンは初めてそんな風に言われて、すごくくすぐったい感じだったな……。
ママは1人で宿を経営してたんで、ディーキンは1週間程泊まって仕事を手伝ったんだ。
彼女はディーキンに親切にしてくれて……、『息子のことを思い出すよ』って言ってくれたの」
ディーキンが幸せそうに“ママ”の事を話すのを聞いているうちに、ルイズはふと、下の優しい姉のことを思い浮かべた。
「ふうん。いい人に会えて、よかったじゃない」
「うん、とってもね。ディーキンは、そのまま留まって、ママを手伝おうかとさえ思ったよ。
英雄にはなれなくなるけど、それでもいいかなって……」
そう出来ていたら、自分は今頃、その小さな村の酒場のちょっとした名物にでもおさまっていたかもしれない。
それはそれで悪くない人生だったに違いないと、今でも思う。
嬉しそうに話していたディーキンは、そこで急に、話すのをやめて黙り込んだ。
しばらくして、俯いたままぽつりと呟く。
「……でも……、それは叶わなかった」
ぽろぽろと涙が溢れてディーキンの顔をつたい落ちるのを見て、ルイズらは皆びっくりした。
彼が泣くなんて、想像もできなかったのだ。
「ある晩、オオカミが……、村にやってきたの。
ママは……、その時、外にいて……。
オオカミに、殺されちゃった……」
ディーキンは声を絞り出すようにしてそう言うと、ようやく自分が泣いていることに気がついて、ぐしぐしと頬を拭った。
残念ながら当時のディーキンには、女主人を生き返らせる手段は何もなかったのである。
もちろん、蘇生の秘跡を行なえるような司祭も、その小さな村にはいなかった。
「ディーキンは、その時眠ってたの。
ママが外にいることなんか、ちっとも知らなかった……」
まだ少し震える声で、ディーキンは話を続ける。
「……最初、村の人たちは、ディーキンがママを殺したんじゃないかって思ったの。
でも近くでよく見たらオオカミのしわざだってわかって、村長は『オオカミを殺しにいった者に金を出そう』って提案したんだ。
だけど、村人は誰も買って出なかった。オオカミは大きいし危険だってね。……だから、ディーキンが志願したの」
-
ディーキンの声は、最後の方になるにつれて、次第に強張っていった。
戸惑いながらも、ディーキンを慰めようと彼の頭に手を伸ばしかけていたルイズは、その顔を見て……。
ぎょっとして、凍りついたように動きを止めた。
他の皆もまた、ディーキンの表情に気がつくと、ひどく衝撃を受けた。
その時のディーキンの顔は、まぎれもない怒りと憎悪の感情に歪んでいたのである。
「悲しかったけど、怒りもあったの。ママがあんな死に方をするなんて、許せない!
だからオオカミの洞窟をみつけて……、一匹残らず、皆殺しにしたんだ!」
-----------------------------------
――――あそこだ。
ディーキンは、いつになく険しい目で、岩肌にぽっかりと空いた洞窟の入り口を睨んだ。
怒りのあまり、先程ママの遺体を目にした時の胸の潰れそうな悲しみや引き裂かれるような絶望は、すっかり心から消えていた。
「あそこにいるやつらに、ママを殺した報いを受けさせてやる……!」
憎々しげにそう吐き捨てると、真っ直ぐに洞窟へ向かう。
村に入る時に感じていたようなためらいや恐怖は、今は微塵も無かった。
ディーキンは明かりもつけずに、躊躇なく暗い洞窟の奥へと突き進んでいった。
暗視能力を持つコボルドには、そんなものは要らないのだ。
おそらく、夜目が効き、嗅覚も鋭いオオカミたちは、自分の侵入をすぐに察知するだろう。
縄張りへの侵入者を排除しようと、集団でこちらを取り囲んでくるだろう。
だが、それがなんだ?
あちらから向かってくるのなら、皆殺しにするのには好都合ではないか。
ただ、それだけのことだ。
ただの動物であるオオカミには、ものの善悪を判断するような能力はないのだ。
別に悪気があって彼女を殺したわけではないだろう。
この寒い季節で、彼らとて生き延びるために必死だったのに違いない。
だが、だからどうしたというのだ?
奴らが自分の恩人を殺した仇であることにはなんの違いもないではないか。
悪気の有無など、こちらの知った事か!
(……きた……!)
怒りのためかいつになく研ぎ澄まされた五感は、暗視の範囲にオオカミを捕えるよりも先に、その接近を感知した。
いくつもの唸り声、足音、獣の匂いが、洞窟の岩肌の向こうから迫ってくる。
怒りに歯を食いしばり、憎しみに目を吊り上げる。
武器のスピア(槍)を握る手に、力がこもる。
距離を保ってまずは飛び道具で攻撃しようとか、呪文を使おうとか、まきびしを撒いておこうとか……。
そんな理性的な思考は、感情の爆発の前に一切消し飛んでいた。
ややあって、ついに最初のオオカミが曲がり角から姿を現したとき、ディーキンは雄叫びを上げて突進した。
-
「ウォォオオオオォォッ!!」
まったく隠密性などを考慮しない、その突然の怒号に晒されたオオカミは一瞬怯んで立ち竦んだ。
そして、体勢を整え直して迎え撃つ間も、かわす間もなく、次の瞬間にはもう脳天を串刺しに刺し貫かれて絶命していた。
ディーキンの怒りがそのまま形となったような、まさに会心の一撃だった。
しかし、もちろんオオカミは、その一匹だけではない。
後続のオオカミたちは、先手の一頭がいきなり突き殺されたことに多少は怯んだようだが、さすがに野生の獣である。
すぐに気を取り直して散開し、ディーキンが死体から槍を引き抜くころには、すっかり彼を包囲し終えていた。
先程屠ったのはどうやら一番の下っ端ゆえに先頭を歩かされていた奴らしく、残りのオオカミどもはどいつもこいつもそれより大きかった。
だがそれを見ても、ディーキンの心に恐怖心はいささかも沸き起こってこない。
それどころか、ますます怒りと憎悪で心が煮え滾り、血が沸き立っているかのように体が熱くなってくる。
(この、ちっぽけで下等なケダモノどもめ!)
なぜか、そんな思いが心をよぎった。
少なくとも、ディーキンより小さなオオカミなどは一匹もいないというのに。
オオカミたちの数は、全部で十匹以上。
彼らは唸り声を上げながら包囲の輪をじりじりと狭め……、ついに一斉に飛び掛かってきた。
ディーキンは、すかさず正面から来る一頭の前に槍を突き出し、突進してきたところを串刺しにして迎撃してやった。
肩のあたりを貫かれて苦しんでいるオオカミをそのまま堅い岩の床に叩きつけて槍を捻り、止めを刺す。
その間に四方から、残りのオオカミたちが襲い掛かってきた。
ごく柔らかいコボルドのウロコやなめし革の鎧程度では、オオカミの鋭い牙を完全には防ぎきれない。
体に一頭のオオカミの牙が食い込み、鈍く熱い痛みが走った。
だがその痛みも、今のディーキンを怯ませる役には立たない。
ただ、煮え滾る怒りの炎に油を注いだだけだ。
ディーキンは完全にオオカミの体を貫いた槍を抜くのは諦めて手放し、代わりに腰からショート・ソード(小剣)を引き抜いた。
それで、自分の腰の辺りに噛み付いているオオカミの頭を力任せに突き刺す。
しかし、コボルドの非力ゆえに一撃ではそのオオカミは死なず、痛みに身悶えしながらもさらに激しく食らいついてきた。
「ぎっ……!」
ディーキンは敵に対する憎しみと、自分の非力さに対する苛立ちとで唸った。
そのオオカミの頭から剣を抜き、角度を変えて今度は顔の正面から二度突き込んで止めを刺し、自分から引きはがした。
その間に、また残りのオオカミたちが食いついてくる。
ディーキンはその攻撃を受けて傷つきながらも、一匹ずつ血にぬめる小剣で仕留めていった。
しかし、残りのオオカミの数がついに4匹にまで減った時。
一体のオオカミがディーキンの足に食いつき、そのままバランスを崩させて、地面に引き倒すことに成功した。
起き上がる間もなく、それとはまた別のオオカミがディーキンの上に飛び乗って、押さえつけてくる。
獣の熱い吐息と滴る涎に、ディーキンは顔をしかめた。
そのオオカミの牙が自分の喉笛に食らいつくのを、間一髪小剣を間に差し込んで阻止し、そのまま喉の奥を貫いてやった。
死んだオオカミの重たい屍を押しのけた瞬間、息つく間もなく今度は足を噛んだオオカミが自分の上にのしかかってきた。
しかもその拍子に、オオカミの喉の奥から溢れ出してきた大量の血で手が滑り、小剣を手放してしまう。
新しくダガー(短剣)を抜こうにも、体勢が悪い上にオオカミに押さえ込まれていた。
ディーキンがその時に感じたのは、恐怖でも絶望でもなく、ただより一層の怒りと憎しみだけだった。
そのオオカミの欲望にぎらつく目を、憎しみを込めて真っ向から睨み返してやる。
-
「グルルウゥ、……!?」
口の端から涎をこぼしながら、興奮して狂ったように唸っていたオオカミは、その途端に怯えたように身じろぎした。
まるで、ドラゴンにでも睨まれたかのように。
慌ててディーキンの上から降りて逃げようとしたが、ディーキンはそいつの首に腕を回して、ぎりぎりと締め上げた。
「……ディーキンは、すごく怒ってるの。
たぶん、あんたを締め殺してやりたいんだよ……!」
しかし、コボルドの細腕では、なかなか絞め殺すことができない。
ディーキンは口を大きく開くと、そのオオカミの喉笛にくらいつき、力の限り噛みしめて、牙を深く深く埋めてやった。
オオカミはごぼごぼと血の泡を吹きながら、しばらく身悶えしていたが、やがて動かなくなる。
そいつの死体を放り捨てて起き上がると、勝てぬと悟った残る2匹がキャンキャンと情けなく鳴いて踵を返し、逃げ出そうとした。
「逃げるな! このちっぽけな犬コロめ!」
ディーキンは無意識にそう吠えて、懐から短剣を抜くとそのうちの一頭に投げつけた。
「ギャンッ!?」
短剣は狙い違わず、そいつの後ろ脚を捕えて切断した。
不具となったオオカミの哀れな苦鳴が響く。
ディーキンは脚を失って悶え苦しむそのオオカミに歩み寄ると、新しい短剣を引き抜いて止めを刺した。
それから、最後の一頭を追って洞窟の外へ向かった。
戦いの興奮が少しく引いて、麻痺していた痛みが全身を苛み、失血で傷口が冷えてきていたが、足取りはまだしっかりしている。
洞窟から出て周囲を見渡すと、遠くのほうに、慌てて崖を逃げ下ってゆくのが見えた。
ディーキンは冷たい目で、黙ってその無様な負け犬の姿を見据えると、ゆっくりとクロスボウを取り出してボルトを装填し……。
-----------------------------------
あの時の気持ちを思い出すと、ディーキンは今でも体が震える。
身を引き裂かれるような絶望と悲しみ。
煮え滾るような怒りと憎しみ。
初めて自分一人の力で冒険をやり抜いたという、達成感と喜び。
そして……、そればかりではない。
間違いなくあの時の自分は、獣どもの血と臓腑に塗れて、邪悪な衝動、昏い愉悦と興奮を覚えていた。
その証拠に、あの日を境に自分は赤竜になる夢を見るようになり、ドラゴン・ディサイプルとしての修行を考えるようになった。
体の中に眠っていた、地上で最も邪悪な竜族の血が目覚め始めたのだ。
「あの時のディーキンは、ぜんぜん弱くて。牙がいっぱい体に食い込んで、あやうく死にかかったけど……。
それでも、ディーキンはオオカミをみんな殺して、気分がよかったよ。
ママの復讐をして、真の冒険者になったと思ったの。村長も、約束通りに報酬を支払ってくれたもの」
「……っ、」
一瞬、ディーキンの顔が怒り狂う獰猛な火竜か、冷酷な爬虫類のそれのように見えて、タバサは我知らず身を竦ませた。
-
そんな表情を彼が浮かべていることが、信じられない。
その表情は自分に向けられたものではないとはわかっているのに、なぜかひどく怖かった。
命懸けの任務でさえ、怯える事など滅多にないこの自分が……。
もしもそれが自分に向けられたものだったら、私は絶望のあまり、引き裂かれるより先に死んでしまうのではないか。
そんな愚にもつかないような考えさえ、心をよぎる。
(私も、復讐のことを考えている時は、あんな顔をしているの?)
だとしたら、その顔を彼にも見られていたことになる。
そう考えると、ひどい自己嫌悪に襲われた。
「今思うと、そんなことで偉いことをしたつもりになってたなんて、恥ずかしいけどね……。
ディーキンは、ルイズたちにだから話したの。みんなには、内緒にしといて」
ディーキンはそう言って、きまり悪そうに頬を掻いた。
幸いにも、その後ほどなくしてディーキンは、ウォーターディープでボスと再会することができた。
そのとき、ディーキンはこの初めての冒険の話を彼にも聞かせた。
少しばかり手柄顔をして、自慢げに。
彼は、自分が復讐の念に駆られて悪でも何でもない動物たちを虐殺したことを少しも責めなかった。
感心しないというような態度さえ見せなかった。
ただ、ママのことを悼み、よく頑張ったなと言って、自分を労ってくれた。
しかし、また彼と旅をして、彼を傍で見るうちに、自然と自分の憎悪に駆られた復讐の行為は誤っていたと悟るようになったのだ。
別に、あのオオカミたちを殺したこと自体が誤っていたとは思わない。
人間を襲って味を占めた彼らは、また別の村人を襲う可能性も高かっただろうから。
だが、ボスなら決して、憎悪に駆られてそれをしはしないだろう。
彼が自分の憎悪ために復讐に走るなど、到底考えられない。
自分は彼に憧れていたはずなのに、殺し合いなど好きではなかったはずなのに、どうしてあんなことをしてしまったのか……。
あの時ほど、自分が英雄の器ではないと痛感したことはなかった。
彼の高潔な生き方に再び接することができなければ、いずれは邪悪な赤竜の血の衝動に飲まれて墜ちてしまっていたかもしれない。
それでもなお、たとえ英雄にはなれなくても、自分は旅を続けたいと思った。
自分は詩人であり、冒険者であるから。
そう思えたあの時に初めて、自分は本当の意味で『冒険者』になったのかも知れないな、とふと思った。
「その……、それで、その後は、どうなったのですか?」
シエスタが、おずおずと質問した。
「うん……。その後、ディーキンは村を出て、ウォーターディープに向かったの。
オオカミを殺したからって、村人がディーキンのことを本当に信頼してくれるわけじゃないもの。
それに、もうママもいないしね……」
彼女のいない村は、それまでのように温かくは感じられなかった。
あの村は、既に自分の居場所ではなくなっていたのだ。
「彼女のことで、ディーキンはボスを思い出したの……。ボスがいなくて、あれほど寂しいと思ったことはなかったよ。
いい仲間が一緒じゃないと、旅はとっても大変なんだってことがわかったの。
それは、ディーキン自身が努力しないってことじゃないけどね」
だから、今のタバサにもきっといい仲間が傍にいてやることが必要なのだと、ディーキンはそう信じていた。
ただ、それを口には出さなかった。
あの時のボスも、きっとそうだったに違いないから――――。
-
フェスティヴァル・フィースト
Festival Feast /お祭りの御馳走
系統:召喚術(創造); 2レベル呪文
構成要素:音声、動作
距離:近距離(25フィート+2術者レベル毎に5フィート)
持続時間:2時間
術者は、良質な食糧およびエール、ビール、ワインなどの酒類を創造する。
この呪文によって作り出された酒によって、酩酊状態の悪影響が出ることはない。
なお、創造される飲食物の量は術者レベル毎に人間1人の1日分相当であるが、呪文の持続時間内に消費されなければ駄目になってしまう。
----------------------------------------------------------------------
今回はここまでになります。
またできるだけ早く続きを書いていきますので、次の機会にもどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、失礼しました……(御辞儀)
-
おつおつ
-
こんばんは、焼き鮭です。今回の投下します。
開始は21:43からで。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第八十五話「泣くな失恋怪獣」
硫酸怪獣ホー 登場
……ウチのクラスにルイズが転校してきてから、一日が経った。第一印象が最悪だったんで、
一時はどうなることかと思ったが……ルイズはきついところはあるけれど、意外と気さくで
人当たりのいいところがあって、案外すぐ打ち解けられた。いやぁよかった。どうしてかそれと
前後してシエスタが妙に不機嫌になっているが……。
何はともあれ今日も登校すると……校舎の玄関口で、そのルイズが一人の男子といるところを
目撃した。あいつは、確か……同じクラスの、中野真一って奴だったっけな?
ルイズは中野に対して、バッと頭を下げた。
「ごめんなさい!」
何故か謝られた中野は、思いっきりショックを受けているようだった。
「そ、そんな!? ルイズさん、せめてもう少し考えてくれても……!」
「えーと、何て言うか……わたし、あなたをそういう風には見られないんです! だから……
ほんと、ごめんなさい!」
もう一度謝ったルイズが校舎の中へ逃げるように駆け込んでいく。何だ何だ?
「そんなぁ……ルイズさ〜ん……」
置いていかれる形になった中野は、ガックシと肩を落としうなだれた。
呆気にとられる俺とシエスタ。これってまさか……。
「朝から賑やかなことだな」
と言いながら俺たちの元に現れたのはクリスだ。
……あれ? クリスって……この学校にいたっけ? 昨日はいなかったような……。
まぁいいや。俺はクリスに何事だったのかを尋ねる。
「クリス」
「ああサイト、おはよう」
「おはよう。クリス、今さっきルイズと中野が何やってたのか知ってるか?」
「ああ。あの男子が、ルイズに自分とつき合ってほしいと告白をしたんだ」
告白! 俺とシエスタは目を丸くして驚いた。
「しかし、あの様子ではきっぱりと断られたみたいだな。かわいそうに」
「ナカノさん、ルイズさんは転校してきてまだ一日なのに、大胆ですねぇ……」
シエスタが呆けながらつぶやいた。確かに、大胆というか急ぎすぎって感じはするな。
「彼の気持ちがそれだけ真剣だったのだろう。真剣な気持ちに時間は関係がないことと、
師匠も言っていた」
クリスはそう語った。弓道部主将にして剣の達人でもある、女侍といってもいいクリスの師匠……
どんな人なんだろう。
ん? つい最近教えてもらったんじゃなかったっけ? でも、記憶には全然ない。また何か
変な思い違いをしてるのかな、俺……。
俺たちが話している一方で、中野は依然として肩を落としながらトボトボと校舎の中に入っていった。
その背中からは哀愁が漂っている……。確かにかわいそうだが、俺たちに出来ることなんてないよな。
せめて、早く失恋から立ち直ってくれることを祈ろう。
おっと、授業が始まる時間が近づいてきた。俺たちも教室に行こう。
教室に入り、授業が開始される寸前に、ルイズが俺に呼びかけた。
「ちょっと……」
「ん? ああ、また教科書持ってきてないのか?」
俺はまだルイズが教科書をそろえてないのかと思ったが、そうではなかった。
「違う! ……これッ!」
と言ってルイズが俺に突き出したのは、布にくるまれた箱型のものだった。
「何だこれ?」
「これは……その……あの……!」
「あの?」
「お、お、お、お弁当よ!」
弁当? どうしてそんなものを、こんな時間に出すのか。
-
「そうか、弁当か。随分でかいな。こんなに食ったら太るぞ」
「わ、わたしのじゃないもん!」
「じゃ、誰の?」
「あ、あ、ああああんたに決まってるでしょ!」
……え?
「俺の? 弁当? お前が?」
「か、勘違いしないでよね! た、ただ、昨日、道でぶつかって謝りもしないままだったから……。
ほ、ほんのちょっぴりだけ悪かったなって! だから、お詫びの気持ちよ、お詫びの! ほ、ほんとに
そ、それだけなんだからね!」
弁当……。女の子が俺に弁当を……。
俺は思わず教室の窓を開け放ち、青空に向かって叫んだ。
「神様ー! 生きててくれてありがとおおおおおお!! 僕は幸せで――――――す!」
「えぇッ!?」
驚くルイズ。周りの奴らもこっちに振り向いていた。
「ど、どうしたの? 平賀くん、何をやってるんですか?」
「ああ、またサイトが変なことしてるだけ。気にしたら負けよ」
目を丸くしている春奈に、モンモランシーがそう答えていた。変なことで悪かったな!
この感動を表現するには、これくらいのことはしないと駄目だったんだよ!
「ちょっと! 恥ずかしいじゃない! どうして空に向かって雄叫び上げるのよ! みんな見てるわ!」
慌てふためくルイズに、俺は熱弁する。
「だって、弁当だよ? 手作り弁当だよ!?」
「そ、そうだけど! は、恥ずかしいからやめてよ!」
「お、俺、女の子に弁当もらうのなんて……。う、う、生まれて初めてで……。うっうっうっ……」
感動のあまり、俺は嗚咽を上げて泣きじゃくってしまった。
「ち、ちょっと泣かないでよ。こんなことくらいで……」
「いやいや、男子高校生三種の神器には、一生縁がないと思ってたから……」
「三種の神器?」
「女の子の手作り弁当、バレンタインデーの本命チョコ、誕生日プレゼントの手編みセーター!
この三つを称して、三種の神器と呼ぶのですッ!」
誰が呼んでいるのかは俺も知らんが、ともかく俺の中ではそうなっている!
「ああッ、今日は最高の日です。お父さん、お母さん。俺を生んでくれてありがとう!」
「ふ、ふーん。よく分からないけど、そんなに喜んでもらえるならよかったわ」
俺の感動ぶりに、ルイズは満更でもなさそうに言った。
「はッ!? そ、そうか、そうだったのか!?」
「え?」
「ちょっとこっちに来てくれ、ルイズ」
「こっちにって……! もうすぐ授業始まっちゃうってば! サイト!?」
教室じゃ何なので、俺はルイズを屋上まで連れていった。
「ごめんよ、ルイズ。君の気持ちに気づかないままで……」
「さ、サイト? な、な、何真面目な顔して……」
戸惑い気味のルイズに、俺は尋ねかけた。
「お前、俺のこと好きなんだろ?」
「なッ!?」
「だから今朝、中野からの告白を断った。そうだろ?」
そうか、そういうことだったんだな……。俺のことが好きだったから、中野の気持ちには
応えられなかったんだな。
「ち、違うもんッ! あれは……!」
「そんな言い訳いらないさ。さあ、ルイズ……!」
「サイト……」
腕を広げた俺の顔を、ルイズはじっと見つめて……。
ドゴォッ!
「バカッ!」
-
「ぐがッ!」
お、俺の股間に膝蹴りが決まった……。
「ぐおおおおお……! お、俺の股間の夢工場が……!」
「だ、誰があんたをす、す、好きなのよ!? 全く笑えない冗談だわ!」
苦悶にあえぐ俺に、ルイズは真っ赤になりながら怒鳴りつけてきた。
「一つ教えてあげる! 冗談も過ぎると命取りになるの! 分かった!?」
「……勉強になりました……」
「全く! 馬鹿なこと言ってないで、教室に戻るわよ!」
「ふぁい……」
すっかり怒ってしまったルイズは、早足で屋上から中へ戻っていった。く、くそう……
少し焦りすぎたか……。もっと落ち着いてから質問すればよかった……。ああ、すっげぇ
痛い思いをしてしまった……。
反省しながら俺も教室に戻ろうとした時……扉の陰に春奈とシエスタがいることに気がついた。
あんなところで、授業が始まる前に二人は何をやっているんだ?
「……見ましたか、ハルナさん?」
「ええ、しっかりと。これは……由々しき問題ですね。何とかしなければ」
……な、何をやってたんだ? まさか……さっきの俺とルイズのやり取りをこっそり見ていたんじゃ……。
異様な威圧感のあるシエスタたちに対して、俺は知らず知らずの内に怖気づいていた。
教室に戻ると……中野がとんでもなくショックを受けたような顔をしていて、次いで俺に
一瞬恨めしい視線を向けた。
げッ……そ、そういえばルイズに振られた張本人がいるんだった……。さっきの、俺が手作り弁当を
もらうところを目撃したに決まっているよな……。き、気まずい……。
俺は針のむしろにいるような気分になりながらも、その日の授業を受けたのであった。
そして夜遅くに、自室にいたところにゼロに呼びかけられた。
『才人! 外で何か異常が起きてる!』
「えッ、何だって!? 本当か!?」
『外を見てみろ!』
促されて、窓を開け放つと、俺の住む街に怪しい霧が掛かっていることに気がついた。
「霧……? 今日は晴れだぜ……?」
『ただの霧じゃないぜ。マイナスエネルギーの異様な高まりを感じる……。こいつはマイナス
エネルギーの実体化だ!』
マイナスエネルギー……! 俺も話には聞いたことがある。人間の怒りとか嫉妬とか、
負の感情から生じる良くないエネルギーだとか。あのヤプールのエネルギー源でもある。
このマイナスエネルギーが高まると、怪獣が出現しやすくもなるらしい。
ということは……。俺の嫌な予感は的中してしまった。
街に漂う霧に投影されるように青い怪光が瞬くと、一体の巨大怪獣の姿が不気味に浮き上がったのだ!
「ウオオオオ……!」
「あいつは……!」
まっすぐ直立した体型にピンと立った大きな耳、手の甲は葉っぱのような形状で、腹には幾何学的な
模様が描かれている。生物というよりは、何かの彫像みたいだ。そして二つの目から、何故か涙をこぼしている。
データには、硫酸怪獣ホーとある!
「またまた怪獣か……! 行こうぜ、ゼロ!」
俺は怪獣と戦うために変身しようとしたが、それをゼロ当人に止められた。
『待て、才人! あの怪獣、まだ実体って訳じゃないようだぜ!』
「えッ? どういうことだ?」
『奴はマイナスエネルギーの結晶体の怪獣みたいだが、肉体が完全に固形化してないんだよ。
いわば中間の状態だな』
と言われても、俺にはよく分からないが……。
-
と、その時、怪獣ホーの姿が一瞬揺らぎ、あの中野の姿が見えたような気がした。
「今のは中野……!?」
『俺にも見えたぜ。気のせいとか幻とかなんかじゃねぇ。あの怪獣はどうやら、中野真一の
負の感情が中核になってるみたいだ!』
な、何だって!? 中野の感情は、怪獣になるまで大きかったのか……! というかそうなると、
ホーの出現の原因の半分は俺ってことになるのか!? 俺があいつを尻目に、ルイズから弁当を
受け取ったりしたから……。
さすがに中野の感情の化身を闇雲に倒すのは目覚めが悪い。ホーの核があいつっていうのなら、
中野を説得して怪獣を消し去ろう!
「中野に、怪獣を消すように説得をしなくちゃ!」
『ああ!』
俺は遮二無二部屋を飛び出し、中野の家の方へと大急ぎで走っていった。ホーにまだ暴れる
様子はないが、いつまで続くかは分からない!
しかし中野の家にたどり着く前に、夜の街の中で肝心の中野を発見した。何故か、矢的先生と一緒にいる。
「真一、聞こえるか? あの怪獣の鳴き声は、お前の声だ! 夢の中でお前が作ってしまった怪獣だ!
憎しみや悲しみ、マイナスの感情を吸収して、あそこで泣いてるんだ!」
先生は中野に向けてそう告げた。先生もホーの正体を見抜き、俺よりひと足先に中野を説得して、
怪獣から解放しようとしているのか? 民間人のはずの先生が、そんなことまでするなんて……。
そんなにも生徒のことを考えているのだろうか。
話がややこしくならないように、俺は物陰にこっそりと隠れながら話の行方を見守る。
そして矢的先生は、中野に対して語り出した。
「愛しているから、愛されたい。愛されなければ腹が立つ。でも、本当の愛ってそんなちっぽけな
ものなのか? 人のお返しを期待する愛なんて、偽物じゃないかな」
……矢的先生……。
「想う人には想われず! よくあることだぞ。先生だってそんなことあったよ」
「先生も?」
「うん。……故郷にいた頃、本当に好きな女の子がいてなぁ、その子のためなら、何でもしようと思った。
その子、楽器欲しがってたんだ。先生どうしても買ってあげたくてさ、必死になってバイトした! だけどな……
二ヶ月目にやっと手に入れた時には、遅かったよ。その子には、新しい恋人が出来てたんだ。悲しかった……。
悔しかった。憎かったよ! だけどな、先生そのままプレゼントしたよ! その楽器が、先生の本当の心を、
鳴らしてくれると思ってな。それで終わりだよ……! 今はもう懐かしい思い出だ」
先生に、そんな苦い思い出があったんだな……。
『……何だ? どこかで聞いた話のような……』
何故かゼロが首をひねっていた。
自分の過去を話した先生は、改めて中野に呼びかける。
「真一、あの怪獣を作った醜い心が、お前の本当の気持ちなんて先生思わないぞ。今にきっと
お前にも分かる!」
しかし、中野は、
「分からないよ! 俺、憎いんだ! 悔しいんだよぉーッ!!」
その絶叫に呼応するように、とうとうホーが完全に実体化して暴れ始めた!
「ウアアアアアアアア!」
地団駄を踏むように行進して、近くの建物を薙ぎ倒す!
「くそッ、結局こうなっちまうのか……!」
『仕方ねぇ! 才人、怪獣を止めるぜ!』
「ああ! デュワッ!」
俺は街を守るためにゼロアイを装着して、ウルトラマンゼロに変身した!
『やめろ、ホー!』
巨大化したゼロはすぐさまホーに飛びかかっていって、押さえつけて街の破壊を食い止めようとした。
「ウアアアアアアアア!」
けれどホーは暴れる勢いを止めようとしない。その両眼から涙がボロボロと飛び散り、
一滴がゼロの手に落ちる。
-
途端に、ゼロの手がジュウッと焼け焦げた!
『うおあぁッ!? あぢッ、あぢちちちッ!』
反射的にゼロは手を放してしまう。
『ゼロ、ホーの涙は硫酸なんだ!』
『くそッ、何て迷惑な奴なんだ……!』
「ウアアアアアアアア!」
ホーはわんわん泣きわめき、辺り一面に硫酸の涙をまき散らす! 何て危険な!
『や、やめろ! くそぉッ!』
阻止しようにも、涙の勢いは雨あられで、ゼロも容易に近づくことが出来ない!
そして涙の一滴が、ホーを生み出した中野にまで飛んでいく!
『あッ……!』
「危ない真一ッ!」
それを助けたのは矢的先生だった。けど中野の身代わりに、先生が肩に硫酸を浴びて火傷を負ってしまう。
「先生……俺のために……!」
「そんなことより……怪獣を見ろ……! 奴は、ルイズの家の方に向かってる……!」
何だって!? 確かに、ホーはどこかに移動しようとしているように見える。まさか、
ルイズを殺そうってのか!? くそッ、それだけは絶対にさせるものか……!
「お前の潜在意識が、怪獣をルイズのところに行かせるんだ! お前は本当にルイズが憎いのか!?
いいのかそれで!」
先生は大怪我を負ってもなお、中野を説得しようとしていた。矢的先生……!
「本当にそれでいいのか!? 真一ッ!」
先生の呼びかけに……中野も遂に応えた。
「消えろー! お前なんか俺の心じゃない! 消えろーッ!!」
中野は自分の憎しみを捨てた!
「ウアアアアアアアア!」
……けど、ホーは消えない! それどころか、ますます凶暴になって暴れ狂う!
『ど、どうしてなんだ!?』
『ホーはもう、あいつの心から離れて独立した存在になっちまった! こうなったからには、
倒す以外にないぜ!』
くっそぉ……! だったら、とことんまでやってやるぜ! 俺たちは気持ちを重ねて、
ホーに立ち向かう!
『おおおおおッ!』
「ウアアアアアアアア!」
今度は硫酸にもひるまず、正面から間合いを詰めて打撃を連続で入れていく! が、ホーは
ゼロの身体を掴んで軽々と投げ飛ばした!
『うッ!』
「ウアアアアアアアア!」
地面に打ち据えられたゼロに馬乗りになったホーは、両手の平で激しくゼロを叩く。
『ぐッ……! 調子に乗るなッ!』
自分の上からホーを振り払ったゼロだが、起き上がった瞬間にホーの口から放たれた火炎状の
光線をまともに食らってしまった!
『ぐああぁッ!』
痛恨のダメージを受けるゼロ! カラータイマーもピンチを知らせる!
『今の光線の威力……何てパワーだ!』
『人の心から生じたマイナスエネルギーを直接吸収して、力と憎しみが膨れ上がってるってところか……!』
マジか……! 人間の憎しみは、それだけのパワーになるってことなのか……! 同じ人間として、
恐ろしい気分になる……。
『だからこそ、負ける訳にはいかねぇぜ! とぉあッ!』
勇んで地を蹴ったゼロは、そのままウルトラゼロキックをホーにぶち込んだ! この必殺キックは
さすがに効いたようで、ホーに大きな隙が出来る。
-
「シェエアッ!」
そこにワイドゼロショットが発射される! 直撃だ!
「ウアアアアアアアア……!」
しかし、ホーはワイドゼロショットを食らっても倒れなかった! ほ、本当にとんでもない奴だ……!
『だが、こいつで今度こそフィニッシュだぁッ!』
ゼロはひるまず、ゼロツインシュートを豪快に放った!
「ウアアアアアアアア!」
それが遂に決まり手となった。ホーの全身が赤い炎のように変わり果て、身体の内側から
輪郭の順に飛び散って完全に消え失せた。
やった……! ゼロの勝ちだ。ゼロは恐ろしい、人間の憎しみの心にも勝ったんだ……!
……今日もまた、才人は覚醒して身体を起こした。
「……本当の、愛……」
またしても夢のことはほとんどを忘れ去ってしまった才人だが……誰かが熱く語った
「本当の愛」についての内容だけは、記憶に残っていた。
そして日中、
「こらぁーサイトッ! あんたまた、わたしの見てないところでメイドとイチャイチャしてたそうね!
しかも今度はクリスともだそうじゃない! この節操なしの犬! 一辺教育し直してあげようかしら!?」
ルイズはまた何か変な誤解をしたようで、怒り狂って才人に詰め寄ってきた。いつもの才人なら、
彼女の怒りから逃れようと必死に言い訳を並べていることだろう。
だが、今の才人は違った。
「なぁ、ルイズ」
「な、何よ? 今日はいやに落ち着き払って……どうしたっていうのよ? 何か変よ」
「愛しているから、愛されたい。愛されなければ腹が立つ……。本当の愛って、そんなちっぽけな
もんじゃないだろう?」
困惑したルイズに、才人は夢で覚えた言葉を、すました態度で告げた。
「人のお返しを期待する愛なんて、偽物。お前もそう思わないか?」
ふッ、決まった……と言わんばかりに、格好つけた様子でルイズと目を合わせる才人。
果たして、ルイズの反応は、
「……知った風な口を利くんじゃないわよぉッ!」
余計に怒らせて、ドカーンッ! と爆発をお見舞いされた。
「ぎゃ―――――――――ッ!!」
「ふんッ! どこでそんな言葉覚えてきたんだか……!」
ツカツカとその場を離れていくルイズ。後には、黒焦げになった才人がバッタリと倒れ込んだ
姿だけが残された。
「ど……どうしてこうなるんだ……」
ピクピク痙攣した才人は、そうとだけ言い残して力尽きた。
-
以上です。
人の真似をしようとしても、大抵は上手くいかないもの。
-
こんばんは。
よろしければ15分頃から続きを投稿させて頂きます。
-
「夢……じゃなかったようだな」
藁束の中で目覚めたレオンは、辺りを見回し、溜息を吐いた。
必要最低限の家具しかない殺風景な室内は自分の部屋と似ていなくもないが、そこに置
かれているアンティーク風のタンスやベッドは、明らかに自分の趣味ではない。
何よりベッドの中では、今もこの部屋の主がすやすやと寝息を立てているではないか。
部屋の隅に敷かれた藁束。それが使い魔であるレオンの現在の寝床だった。
申し訳程度に与えられた毛布から這い出ると、女物の下着がその手に触れる。そういえ
ば昨夜、自分の主となった少女に洗濯しておけと渡された気がする。
使い魔の役割は、主人の目となり耳となる事。そして、主人の望むものを見つける事。
昨夜そう説明を受けたレオンだったが、本来ならば可能なはずの視覚・聴覚の共有は何
故か二人の間では行う事が出来なかった。
この世界についての知識を持たないレオンには、主の望むもの――例えば秘薬など――
を見つける事も難しいだろう。
結局、レオンに与えられた役目は、護衛を除けば掃除、洗濯、その他雑用という、使い
魔というよりは使用人のようなものだった。
二度目の溜息と共に下着を床に放り投げ、ベッドの中で未だ夢心地の我が主を眺める。
桃色がかったブロンドの長髪に、磁器のように白くきめ細かい肌。
――黙ってさえいれば、可愛いんだがな。
出来ればこのまま眠っていてもらいたいが、そういうわけにもいかない。レオンは彼女
の使い魔として、与えられた任務を遂行しなければならないのだ。
毛布をそっと剥ぎ取ると、体を揺すり、驚かさないよう極力優しく声を掛ける。
「朝だぞ、眠り姫。起きろ」
「ふぇ……? ああ、おはよ……って、あんた誰よ!?」
身を守るように毛布を引き寄せ、寝惚けた声で怒鳴る主の姿を見て、レオンは三度目の
溜息を吐いた。
「泣けるぜ」
Chapter.2
「確認だけど……あんた、本当に別の世界から来たのよね」
朝に弱いのか、レオンの手を借りて着替えを終えたルイズは――ルイズに言わせれば、
それも使い魔の仕事らしいが――ふらつきながらも何とか椅子に腰掛けた。
寝惚け眼を擦りながら、昨日の記憶を一つ一つ辿っていく。
「ああ、ジョン・カーターの気持ちがよく分かったよ」
「誰よそれ……」
「俺の元いた世界の有名人さ。火星の大元帥だ」
レオンは昨夜見た、夜空に赤と青、二つの月が浮かぶ奇妙な光景を思い出していた。ど
うやらこの世界では月は二つあるものらしい。火星にも衛星は二つ。いつもの軽口のつも
りだったが、意外な一致にうすら寒いものを感じる。
一方のルイズは聞いた事のない単語を並べられ、頭に『?』マークが浮かんでいる。不
満そうな視線を受け、レオンは苦笑とともに突飛な想像を振り払うと、テーブルの上にPD
Aと二挺の拳銃を並べた。
それらを除けば、レオンの所持品はジャケットの下に着込んでいた、動きを阻害しない
程度の軽量のボディアーマー、拳銃の予備マガジンが二本ずつ、手榴弾と焼夷手榴弾が各
一個のみである。
「ふーん。本当、不思議なアイテムよね」
昨夜も全く同じやりとりをしたにも関わらず、ルイズは何が楽しいのか、スノーノイズ
しか映らないPDAを興味深げに弄っている。
壊すなよ、と注意しようかとも思ったが、電波の届くはずのないこちらの世界では使い
道もないだろう。
-
「確かに、ハルケギニアにはないものだって事は認めるわ。そっちの銃も」
仕組みを説明されたところでルイズにはちんぷんかんぷんだったが、ハルケギニアの技
術力で同じ物を作るのは不可能だという事だけはかろうじて理解出来た。
それは銃についても同様で、ハルケギニアでは未だに火縄銃やマスケット銃といった単
発式の銃が主流なのである。
「こっちも確認するが、元の世界に戻る方法は――」
「ないわ。少なくとも、私は知らない」
もはや何度目か分からない溜息を吐く。
本来であれば、サモン・サーヴァントはハルケギニアの生物を呼び出す魔法だ。決して
異世界間を繋ぐ魔法ではなく、何故レオンが呼び出されたのかはルイズにも分からないと
いう事だった。
また、サモン・サーヴァントは使い魔を一方的に呼び出すだけの呪文で、元に戻す呪文
は存在しない。試しにもう一度使ってみようにも、使い魔が死ななければ再度使用する事
は出来ないという。
つまりは、お手上げという事だ。
「あ、そうだ。聞き忘れてたけど、あんた元いた世界じゃ何してたの?」
「そいつは難しい質問だな」
途方に暮れているレオンの事などお構いなしに、期待と不安が入り混じった視線が向け
られる。仕方なく思考を中断し、何と説明すべきか考える。
大統領直轄のエージェント組織に所属していたと言っても、ルイズに理解出来るはずが
ない。ハルケギニアの国の多くは王制国家であり、そもそも大統領とは何かという講義か
ら始めなければならない。
かといって、国で一番偉い人間に全ての行動を容認されていたと正直に説明する事も躊
躇われた。そんな肩書はこちらの世界では何の役にも立たない。それならば、わざわざい
らぬ期待を抱かせる事もない。
「警察官だった。こっちの世界では衛兵みたいなものか」
「へえ! 衛兵だったの!」
ルイズの瞳が輝いた。昨日は農民や商人じゃないだけマシだと自分に言い聞かせたが、
衛兵なら上出来じゃないか。
しかし、そんなルイズの期待は、次の一言で打ち砕かれる。
「ああ、一日だけな」
「あんた見かけによらず根性ないのね……」
ルイズはレオンに負けず劣らず大きな溜息を吐いた。
まさか配属初日に勤務地となる街が消滅したなどという考えに至るはずもない。レオン
だって、今でも長い夢を見ているのではないかと思う事がある。永遠に覚めない悪夢を。
「で、それからは何してたの? まさか無職とか言わないわよね……?」
「それからの仕事は害虫駆除みたいなものかな。デカいゴキブリや蜘蛛に寄生虫。依頼が
あればどこでも駆けつけますってやつだ」
おどけたような口調でそう説明すると、最後に一言、レオンは僅かに顔をしかめつつ付
け加えた。
「例え数か月ぶりの休暇の真っ最中でもな」
今度はルイズが顔をしかめる番だった。
一日で衛兵を辞めて害虫駆除業者に就職なんて、何という転落人生だろう。確かに戦闘
を生業にしてはいるが、まさかその相手が虫だとは。そんな見かけ倒しの駄目男が私の使
い魔なのだ。
――か、考え方を変えるのよ。この平民はあの凄い銃のオプション。そう、あの銃が私
の使い魔なのよ。
必死に言い聞かせている自分が虚しくなり、ルイズは頭を抱えた。
そんなルイズの思いなど知る由もなく、ある意味ドラゴンよりも危険な害虫との戦闘を
生業としてきた男は、決意を新たにしていた。
今こうしている間にも、元いた世界ではバイオテロが発生しているかもしれない。B.O.
W.による新たな被害が出ているかもしれないのだ。
自分は何としても元の世界に戻らなければならない。その為の方法をこの少女が知らな
いのであれば、自分で探せばいいだけだ。
-
レオンはこれまで、どのような理不尽な運命にも抗ってきた。そのスタンスは例え異世
界にあっても何ら変わる事はない。
二人が部屋を出ると、ちょうど隣の部屋から一人の少女が姿を現した。
トリステイン魔法学院は全寮制だ。ならば、この少女も学院の生徒なのだろう。
「おはよう、ルイズ」
「……おはよう、キュルケ」
にこやかに挨拶をする級友に、ルイズは明らかに嫌そうに返事をする。
レオンもこのキュルケと呼ばれた少女には見覚えがあった。確か昨日、自分とルイズを
取り囲んでいた生徒の一人だ。
炎のような赤い長髪と褐色の肌、胸を強調するように着崩した制服が目立っていた為、
記憶に残っている。
「ご機嫌よう、ミスタ・ケネディ」
気が付けば、キュルケの視線はレオンへと向けられていた。彼女もレオンの事をよく覚
えていたらしく、人懐こい笑みを浮かべている。
「名前を憶えていてもらえたとは光栄だな。ええと……」
「キュルケ・アウグスタ・フレデリカ・フォン・アンハルツ・ツェルプストーよ」
「……噛みそうな名前だな」
クスリと笑ったキュルケの体から、不意に力が抜ける。慌てて支えようとしたレオンの
腕は、柔らかな感触に包まれた。
「キュルケと呼んで」
「あ――――っ!!」
ルイズの絶叫など聞こえないかのように、レオンの腕にしなだれかかったまま、キュル
ケは囁く。
「ああ、逞しい腕……ゼロのルイズなんかの使い魔にしておくには勿体ないですわ。どう
かしら。ルイズの使い魔なんかやめて、私の騎士になってくれませんこと?」
「そうだな。君がカルト教団に誘拐された時は、真っ先に駆けつけるよ」
「まあ、嬉しい! 約束よ!」
何をわけの分からない事を言っているんだ、こいつらは。ルイズは半ば呆れながら、キ
ュルケの頭とレオンの肩を掴み、二人を引き離した。
「ちょっとー、何するのよヴァリエール」
「黙りなさい、ツェルプストー!! こいつは私の使い魔なのよ! あんたの使い魔はそっ
ちでしょうが!」
ルイズが指し示す先には、レオンが昨日B.O.W.と間違えた、真っ赤な蜥蜴が鎮座してい
た。その体は虎ほどの大きさがあり、尾の先には燃え盛る炎が灯っている。
「ええ、そうよ。火竜山脈のサラマンダー、フレイムよ。いいでしょー? 好事家に見せ
たら値段なんかつかないほどのブランドものよー?」
得意気に胸を張るキュルケとその使い魔を見て、ルイズは思わず拳を握り締めた。
ハルケギニアでは『メイジの実力をはかるには使い魔を見ろ』と言われている。
ただの平民とサラマンダー。それは魔法の才能のない自分とトライアングルメイジであ
るキュルケとの実力差を、何よりもはっきりと表していた。
「あ、ああそう! それはよかったわね! だったら、ただの平民なんて相手にする必要な
いじゃない!!」
「あら、勘違いしないで、ルイズ。私は使い魔として彼に興味があるわけじゃないの。一
人の男性として、彼を愛しているの。彼が欲しいのよ」
あまりにもストレートな告白に、ルイズは言葉を失ってしまう。
「それにね、彼は確かにあなたの使い魔かもしれないけど、意思だってあるのよ。彼が誰
を選ぼうと、あなたがとやかく言う事じゃないわ」
「だ、騙されちゃ駄目よ! この女はただ惚れっぽいだけなの!」
「そうね……人よりちょっと恋ッ気は多いのかもしれないわ。でも、仕方ないじゃない。
私の二つ名は『微熱』。松明みたいに燃え上がりやすいんだもの」
キュルケは寂しそうに首を振った。潤んだ瞳が、上目遣いにレオンを見つめている。
「それでも今、私の中にいるのはあなただけ! 信じて、ミスタ・ケネディ! あなたが颯
爽と現れ、あの怪物を退治した時、私の体は炎のように燃え上がったの!」
キュルケは恋愛に関しては百戦錬磨だと自負していた。事実、自分に言い寄られて動揺
を見せない男など、これまで一人もいなかった。
だからこそ、キュルケがレオンの言葉を理解するには、少しばかり時間を要した。
-
「ああ、俺も体が燃え上がりそうだ。お互い少しそいつから離れた方がいいみたいだな」
レオンの視線の先、口から炎を迸らせながら不思議そうに首を傾げるフレイムの姿を見
て、キュルケはようやく自分の魅力が通用しない男がこの世に存在する事を知った。
彼女にすれば渾身の告白を袖にされた形だが、レオンの軽口と、使い魔の大柄な体に似
合わぬコミカルな仕種に、思わず吹き出してしまう。
「ご心配なく。『火』属性の私には涼しいくらいですわ。もしかして、火トカゲを見るの
は初めて?」
「そうだな。10メートルのワニとなら遊んでやった事があるんだが」
「まあ、ステキ! そのお話、詳しく聞かせてくださいません? よろしければ今夜、ベッ
ドの中で……」
瞬間、凄まじい殺気を感じてレオンは視線を移した。自分の主がその小さな体を小刻み
に震わせながら、無言で二人へと杖を向けている。
「まあ、怖い。ではミスタ・ケネディ、今夜お待ちしていますわ」
大袈裟に震えてみせると、キュルケは軽やかな足取りで去っていった。角を曲がる際、
レオンにウィンクする事も忘れない。
「……あんた、まさか行くつもりじゃないでしょうね」
既に誰もいなくなった曲がり角へと視線を向けたまま、ルイズはボソリと呟いた。
「魅力的なお誘いだが、あいにく火遊びは趣味じゃなくてね」
「ならいいけど……」
肩を竦めるレオンを、ルイズは横目で睨み付ける。
「いいこと。確かにあんたが誰と付き合おうとあんたの勝手だわ。でも、キュルケだけは
駄目なの」
そもそも、そんなつもりは最初からないんだが……と、レオンに弁明する暇も与えず、
ルイズは続ける。
「そもそもキュルケはトリステインの人間じゃない。隣国ゲルマニアの貴族よ。そして、
ラ・ヴァリエール家とキュルケのフォン・ツェルプストー家の領地は国境挟んで隣同士!
戦争のたびに戦ってきた! 殺しあってきたのよ!!」
話しているうちに興奮してきたのか、ルイズは堰を切ったように捲し立てる。
気が付けば、ルイズの先祖がキュルケの先祖に恋人を奪われただの、婚約者を取られた
だのと、戦争と関係ない話にまで発展している。
二人の脇を笑いながら通り抜けていく子供達の視線が痛い。
「OK、分かった。微熱の二つ名が示す通り、彼女の家は罪作りな家系って事だ」
「そうよ! だからヴァリエール家の物はもうこれ以上、例え小鳥一匹でも取られるわけ
には――」
「二つ名と言えば、ゼロっていうのが君の二つ名なのか?」
いたたまれなくなったレオンは、何とか話題を変えようとした。その方法はいささか強
引ではあったが、意外にもルイズは言葉を詰まらせる。
「まあ……そんなところよ。今は、ね」
ルイズは目を伏せたまま踵を返すと、そのまま無言で歩き出した。先程までの熱が嘘の
ようだ。
――あまり気に入ってはいないようだな。
彼女の態度は気になったが、とにもかくにも目的は達したのだ。レオンはその二つ名に
ついて、それ以上言及する事をやめた。
しかし、その名の由来はすぐに分かる事となる。
トリステイン魔法学院の学院長室は、五つの塔に囲まれた本塔の最上階にある。
他の部屋と比べ、一際重厚なつくりの室内。しかし、その中央に横たわる生物は、およ
そその部屋に相応しいとは思えなかった。
剥き出しの皮膚。だらりと伸びきった長い舌。同じく剥き出しの脳に穿たれた穴から、
この生物が生命活動を停止している事は誰の目にも明らかだ。
にも関わらず、その死骸が今にも動き出しそうな威圧感を醸し出しているのは、腐敗防
止の為にかけられた固定化の魔法だけが原因ではないだろう。
学院長秘書のミス・ロングビルは、恐怖と不快感からその理知的な顔を歪めた。
「で……君はこの生物をどうしろというのかね?」
この部屋の主である学院長オールド・オスマンは、顔の下半分を覆い隠す長く白い髭を
撫でながら、もう一人の闖入者を眺めた。
-
招かざる客――奉職20年の中堅教師、コルベールの主張はこうだ。
このような生物はどの図鑑にも載っていない。即刻王室の研究機関に引き渡すべきだ。
もっともな意見である。しかし、王室の腰の重さを嫌というほど理解しているこの老人
は、どうにも気が進まずにいた。
報告をしたところで、「いずれ確認に向かう故、それまで先方で保管されたし」などと
適当にあしらわれ、放置されるのが目に見えているのだ。
それならば、いっそ『炎蛇』の二つ名を持つ目の前の教師が焼却してくれれば、どれだ
け楽か。
「誰かが大トカゲか何かの皮を剥いだんじゃろう。他愛もないイタズラじゃよ」
「このような巨大な脳を持つトカゲがいるとすれば、間違いなく新種でしょうね」
ロングビルの冷静な指摘に、オスマンはますます顔をしかめる。どうにも自分は数か月
前に採用したこの秘書に、あまり好意を持たれてはいないようだ。
もっともそれは、退屈凌ぎに彼女の尻を撫でたり、使い魔のネズミ――モートソグニル
を利用してスカートの中を覗き見たりするオスマンの完全なる自業自得なのだが。
「ではコルベール君、君はズバリ、この生物は何だと考えるね?」
「キメラ……ではないかと」
表情を強張らせるコルベールを見て、オスマンはわざとらしく溜息を吐いた。予想して
いた通りの回答だった。
キメラとは数年前にガリア王国の一部貴族がファンガスの森で研究を行っていた、人造
合成獣の総称である。この神をも恐れぬ所業は、研究者自身がキメラによって殺害される
という呆気ない幕切れを迎えた。
今では生み出されたキメラ達も、あらかた狩り尽くされたと聞いているが……
「確かにのう……未だにそんな馬鹿げた研究を続けておる者がおるなら、放ってはおけん
わのう」
腕を組んで、瞳を閉じる。いかにも何かを考えているというポーズ。しかし、そう簡単
に妙案が浮かべば苦労はしない。
それでも数秒の後、オスマンは何とか一つの提案を捻り出す事に成功した。
「おお、そうじゃ。こやつと一緒に呼び出されたというミス・ヴァリエールの使い魔。彼
ならこの生物について、何か知っているのではないかね?」
「そう言われれば、この生物を何とかという名で呼んでいたような……」
「まずは、その使い魔君から話を聞いてみてくれ。どうするかはその後でよかろう」
何の事はない、ただ問題を先送りにしただけなのだが、コルベールはあっさりとその提
案を受け入れた。
コルベールがわざわざこの不真面目な学院長の元へと足を運んだ理由は、この生物の処
遇を訪ねる為だけではない。むしろ、もう一つの用件の方が本題であったからだ。
「それともう一点……オールド・オスマンに見て頂きたいものがあるのですが」
「なんじゃ、まだあるのか」
不満を隠す様子もなく、心底鬱陶しそうな顔と声音でオスマンは答える。
その態度は手渡された『始祖ブリミルの使い魔たち』と題された歴史書を見ても変わら
ない。それどころか、今更何の役にも立ちそうにない古臭い文献を見せられた事で、その
表情には呆れが加味されている。
しかし、続いて差し出された一枚のメモを見た瞬間、オスマンの目の色が変わった。
昨日、コルベールがレオンの左手に浮かび上がったルーンをスケッチしたものである。
「……ミス・ヴァリエールの使い魔に聞かねばならん事が増えるかもしれんな」
その場の誰にも聞こえない程度の声でそう呟いたオスマンは、厳しい表情でロングビル
に退室を促した。
――これでゾンビでも出れば完璧なんだがな。
散乱する瓦礫を拾い上げ、レオンは苦笑した。
彼が立っている魔法学院の教室は、惨憺たる有様だった。割れた窓ガラスから吹き抜け
る風が砂塵を舞い上げ、大学の講義室のようなその室内には、粉々に砕けた椅子や机、生
徒達のものであろうノートが散らばっている。
まるでバイオテロにあった、トールオークスのアイヴィ大学だ。
あの時と違うのは、真実を知る為に教会まで走り回る必要がない事と、惨劇の首謀者が
逃げも隠れもせず、目の前に立っている事だろう。
本塔にある『アルヴィーズの食堂』で、スープとパン二切れというあまりに質素な“使
い魔用の”食事を終えたレオンは、学生達が受ける授業への同席を命じられた。
-
どうやらこの授業は使い魔のお披露目も兼ねているらしく、教室内はさながら動物園の
ようだった。こんな状態で授業になるのかと心配になったが、予想に反して使い魔達は皆
大人しくしている。
「契約したら使い魔は主人の言う事を聞くようになるのよ。あんたは違うみたいだけど」
ルイズが不満げに説明してくれる。なるほど、それも魔法の為せる業なのだろう。
元の世界に戻る為にも、まずは自分を呼び寄せた魔法というものについて知る必要があ
る。そう考えるレオンにとって、一年次の復習を兼ねたこの授業は渡りに船だった。
紫のローブと帽子という、いかにも魔法使いという服装に身を包んだふくよかな中年の
女性教師、『赤土』のシュヴルーズ曰く、この世界の魔法には火・水・土・風、そして今
は失われし『虚無』の五つの系統が存在する。
この世界の魔法は、レオンの世界でいう科学技術に相当し、例えば金属の生成や加工、
石を切り出し建物を建てるといった事までが、シュヴルーズの属性でもある『土』系統の
魔法を使えば可能となる。
メイジのレベルは、魔法の系統を足せる数によって『ドット』『ライン』『トライアン
グル』『スクウェア』とクラス分けされる。シュヴルーズも含め、魔法学院の教師クラス
となると、三系統を足せるトライアングルメイジがほとんどとの事だ。
基本的な説明を終えたシュヴルーズは、次いで土属性の基本である『錬金』の魔法を披
露し、石を一瞬で真鍮へと変えてみせた。
世の錬金術師達が永きに渡り追い求めてきた奇跡が、誰でも使える基本中の基本だと知
り――もっとも金の生成となると、スクウェアクラスの力が必要らしいが――レオンは魔
法の持つ力に、内心舌を巻く。
そして、事件は起きた。
シュヴルーズは錬金を実演する生徒の代表として、ルイズを指名したのだ。
「ルイズ、やめて」
キュルケを始めとする生徒達の制止を振り切り、ルイズは教室の前へと歩を進める。
その表情には緊張の色こそ滲んでいるが、実に堂々たる態度である。レオンには生徒達
の懇願の意図が分からなかった。
「ミス・ヴァリエール、錬金したい金属を強く心に思い浮かべるのです」
優しく微笑むシュヴルーズに頷き返すと、ルイズは机に置かれている石に向けて杖を構
えた。真剣な表情でルーンを唱え、勢いよく杖を振り下ろす。
瞬間、眩い光と共に目の前の石は――――爆発した。
――なるほど。魔法の成功確率が『ゼロ』か。
子供達の反応を見るに、彼女が魔法を使おうとする度に、あの爆発が起きているのだろ
う。教室を破壊した罰として課せられた後片付けを手伝いながら、レオンはゼロと呼ばれ
た少女へと視線を向けた。
レオンに背を向けて床を掃くその小さな肩が、心なしか震えているように見える。
「ルイズ」
肩がビクッと跳ねた。
思わず声を掛けたものの、レオンも二の句が継げずにいる。魔法の存在しない世界から
来た自分が慰めの言葉を掛けたところで、彼女に届くとは思えなかった。
やがて気まずい沈黙に耐え兼ねたように、ルイズが口を開いた。
「……これで分かったでしょ。私がゼロって呼ばれてるわけ」
絞り出したような、か細い声。それでも、一度溢れ出した感情は止まらない。
「笑っちゃうわよね。魔法も使えないくせに、貴族だなんて言って、あんたにも偉そうに
して……これじゃ、平民の方がまだマシだわ」
「おい、俺は別に……」
「あんたも嫌よね。才能も成功確率もゼロのご主人様なんて。いいわ。キュルケの所でも
何処でも行きなさいよ。あの子、トライアングルだもん。ゼロの私と違って、元の世界に
帰る方法だって探してくれるわ」
これまでの生意気な態度からは想像も出来ない、自嘲めいた物言い。
爆発が起きた時、子供達は口々にルイズを罵った。彼女は学院に来てから、いや恐らく
それ以前から、ずっと虚勢を張ってこうした状況に耐えてきたのだろう。
誰からも期待される事も、認められる事もなく、ただ一人耐え続けてきたのだろう。
-
「ゼロってわけでもないと思うがな」
ルイズの動きが止まる。レオンからはその表情は窺えない。
「爆発が起きた。俺からすれば立派な魔法だ」
脳がその言葉を認識するよりも早く、ルイズは体がカッと熱くなるのを感じた。
馬鹿にされている。メイジだけでなく、使い魔である平民にまで蔑まれている。
情けない表情を見られないように背を向けていた事も忘れ、ルイズは使い魔を振り返る
と同時に叫んでいた。
「何がっ……何が魔法よ! あんなのただの失敗じゃない!! ……いいえ、その通りね。
私に使える魔法なんて、どうせあの失敗だけよ。ゼロのルイズだものね……!」
怒りに任せ感情を吐き出すルイズを、レオンは黙って見つめていた。そして、彼女が荒
れた息を整えるだけの時間を空け、おもむろに口を開く。
「なら、もし君の目の前に怪物に襲われ、助けを求める人がいたらどうする? 君はゼロ
だからと見て見ぬふりをするのか?」
ギリ、とルイズの歯が軋む。この使い魔は何処まで私を馬鹿にすれば気が済むのだ。
悔しさから、ルイズは再び声を荒げる。
「そんなわけないじゃない! 私は貴族よ! 貴族が敵に後ろを見せるなんて、ありえない
わ!! ……それでもっ!」
ルイズの瞳からは、間際で堪えていた涙が溢れ出していた。
使い魔に馬鹿にされた事が悔しいのだろうか。それとも、自分が現実から必死に目を背
けていると気付いてしまった事が悔しいのだろうか。ルイズにもよく分からなかった。
「それでも……あんたに言われなくても、本当は分かってるわよ……ゼロの私に出来る事
なんて何もないって……」
分かってはいた。分かってはいたが、考えないようにしていた。自分はいずれ魔法が使
えるようになるのだから。それでも、心の何処かではいつも思っていた。自分は一生魔法
なんて使えないのではないかと。
涙でぼやけた視界に、不意に何かが飛び込んで来た。
反射的に受け止める。レオンが自分に向かい、先程拾い上げた瓦礫を放ったのだと気付
くには、少しの時間を要した。
意図が分からず、ルイズはレオンを濡れた瞳で睨み付ける。
「これだけの爆発が起こせるなら、どんな奴でもフッ飛ばせるさ」
出会った時と同じ様に、青い瞳が真っ直ぐにルイズを見つめていた。
誰しもが望んだ力を手に入れられるわけではない。
鳶色の瞳を見つめながら、レオンは一人の少女を思い出していた。
マヌエラ・ヒダルゴ――エージェントとなったレオンが南米の某国で出会った少女。少
女は不治の風土病の治療の為、t-Veronicaと呼ばれるウィルスを投与されていた。
ウィルスを適応させるには、多くの人間の命を犠牲にする必要がある。そして適応出来
なければ、理性を持たぬ怪物と化す。
全てを知ったマヌエラは、人としての死を望んだ。
それでも彼女は、最終的にはウィルスによって得た力を使い、窮地に陥ったレオン達を
救うという道を選択した。
――死ぬべき人間など一人もいない。それに、犠牲となった少女達の為にも、君には生
きる義務がある。
あの時、レオンはマヌエラにそう告げた。それは、彼女に人として生きて欲しいという
レオンの願いでもあった。
しかし、あの時パートナーとして背中を預け、そしてあの任務により道を違えた男――
後に自分とレオンを『コインの表と裏』と称した男は、こう思ったはずなのだ。
――お前は残酷だ、レオン。彼女には誇りを与えるべきだ。新たな生命体としての。
レオンは今でもそれが正しいとは思わない。人としての死を望んだマヌエラは、人とし
て生きるべきだ。しかし、あの男の考えが全て誤りだと言い切る事が出来るだろうか。
人間であろうとする彼女の心も、彼女がレオン達を救う為に使った力も、彼女以外の誰
にも否定する事など出来やしないのだ。
――本当に、俺達はコインの表と裏だな、クラウザー。二つを足して、ようやく正しい
答えに行き着くなんて。
-
だから、自分はあの時、本当はこう告げるべきだったのだ。
「その力は君が望んだものではないだろう。それでも、それは確かに君の力だ。誰かを救
う事が出来る力だ。それをゼロにするかどうかは、君が決めればいい」
唖然とした。
小さい頃から駄目だ駄目だと言われ続けてきた。ヴァリエール家の面汚しだと陰口を叩
かれていたのも知っている。父も母も、もはや自分には何の期待していない。
そんなルイズにとって、爆発はただの失敗の証でしかなかった。
何も言えず、ただただ立ち尽くすルイズの視線の先に、レオンは左手を翳す。サモン・
サーヴァントの成功の証であるルーンは、光の加減のせいか、僅かに輝いて見えた。
「それに、俺を呼び出してこいつを刻んだのは君だろ。勝手に呼び出されて、勝手に暇を
出されちゃ、たまったもんじゃない」
微笑みを向けられ、ルイズは慌てて視線を逸らした。
「……な、何も知らないくせに、適当な事言わないでよ」
ルイズに同情や慰めをくれる者も中にはいた。次姉が本心から自分を心配してくれてい
る事も知っている。
それでも、今のルイズに出来る事があるなどと言う者は一人もいなかった。
――本当に……
言いたい事だけ言って、いつの間にか片付けを再開している使い魔の姿を、横目でチラ
リと見やる。
――本当に、私にも出来る事があるのかな。
それが分かれば、こんな自分の事でも、少しは好きになる事が出来るのだろうか。
――なんて……何、使い魔の言葉なんかに感化されてんのよ、私。
決闘だ、と喚き立てるクラスメイト――ギーシュ・ド・グラモンを眺めながら、ルイズ
は数時間前の自分を激しく後悔した。
ようやく片付けを終えたルイズは、遅めの昼食をとるために一人食堂を訪れていた。
レオンは学院内を見て回りたいと席を外している。先程取り乱した姿を見せてしまった
為に、ルイズを気遣い一人にしてくれたのかもしれない。
後でコックに言って、彼の分の昼食を取っておいてもらおう。少なくとも、朝食よりは
マシなものを。
「君の軽率な行動のおかげで二人のレディの名誉が傷ついた! どう責任を取るつもりだ
ね!?」
食堂に似つかわしくない怒声が響き渡り、ルイズは不快そうに顔を上げた。
その声の主には見覚えがある。金色の巻き髪。フリルのついた小洒落たシャツ。ルイズ
の級友でもある、ギーシュだ。
それなりに整った容姿と軍の元帥の息子という肩書から、彼を慕う女子は少なくない。
しかし、そのキザで見栄っ張りで移り気な性格の為に、彼を避けている女子もまた少なく
はなく、ルイズも後者だった。
ギーシュの前では黒髪の給仕――確かシエスタという名だった気がする――が何度も頭
を下げている。彼女が何かヘマでもしたのだろう。そう珍しい光景でもない。
ルイズとしては厄介事に関わるつもりはさらさらないのだが、興奮したギーシュがあま
りにも大声で喋るので、事の顛末が嫌でも耳に入ってしまう。
発端は彼が落とした小瓶をシエスタが拾った事だった。
ギーシュは知らぬふりをしたが、彼と一緒にいた友人が、その小瓶の中身を同じくルイ
ズの級友であるモンモランシーの香水だと気付いてしまった。
ちょうどその場に現在ギーシュが必死にモーションをかけている一年生のケティという
少女とモンモランシーがいたのが運の尽き。哀れ二股がバレたギーシュは二人の女性に愛
想をつかされ、先程の発言へと繋がったようだ。
――何よ、それ。無茶苦茶じゃない。
ルイズは呆れてしまった。
それでも、普段のルイズであれば無視をして食事を続けていたかもしれない。しかし、
その時、ルイズの頭の中には使い魔の言葉が甦っていた。
-
こんな自分にも出来る事がある。
だからこそ、ルイズはつい立ち上がり、余計な口出しをしてしまったのだ。
「あ、あの……?」
突然現れ、無言のままつかつかと二人の間に割って入ったルイズに、シエスタは怯えた
瞳を向けた。
椅子に腰掛けたままのギーシュも、この少女の目的が分からず、ただ呆然とルイズを見
上げるしかない。
「……? いったい何だと言うのだね、ゼロのルイ――」
「馬っ鹿じゃないの? そんなの、完全にあんたの自業自得じゃない。貴族が八つ当たり
してんじゃないわよ、みっともない」
時が止まった。遅れて周りにいた彼の友人達からドッと笑いが起こる。
「ゼロのルイズの言う通りだ! お前が悪い!」
「ルイズが『ゼロ』なら、お前は『二股』のギーシュだな!」
ピシリ、とギーシュは自分の体にひびの入る音が聞こえた気がした。よりにもよって、
ゼロと呼ばれる落ち零れに笑いものにされるなんて、彼には耐え難い屈辱だった。
それでも、この時のギーシュはまだ、かろうじて冷静さを保っていた。
「は、はは……君は何か勘違いをしているようだな。だいたい君は一部始終を見ていたわ
けではないだろう。それなのに口を挟むなんて貴族として……」
「あんた、声がでかすぎるのよ。あんたの二股はもう、ここにいる全員に知られてるわ」
慌てて周囲を見回す。様子を見守っていた者達が、自分の首の動きに合わせて視線を逸
らせていくのが分かった。生徒だけでなく給仕の平民の中にさえ、口元に手を当て、笑い
を堪えている者がいる。
怒りと羞恥からギーシュの顔は真っ赤に染まっていた。
「き、き、君は言いがかりをつけるだけでは飽き足らず……我がグラモン家の名まで汚そ
うというわけか……!」
「はあ? だから、それもこれも全部あんたが――」
ガタンと椅子を倒し、ギーシュは立ち上がった。驚いて一歩下がったルイズの鼻先に、
手にしていた薔薇の造花を突きつける。
「け、け、け……決闘だ――!!」
「け、決闘って、あんた本気で言ってるわけ? だいたい貴族同士の決闘は……」
「ああ、禁止されている。しかし、君は僕を侮辱したのだ。これで君が詫びを入れないと
言うならば、僕の名誉を回復するには、もはや決闘しかあるまい」
ルイズは後悔していた。
しかし、だからといって詫びを入れるつもりなど毛頭ないし、こうなった以上、シエス
タを見捨てて立ち去るなどという選択肢が彼女の中に存在するはずもない。
――決闘? 上等じゃない!
ルイズはマントの下の自分の杖へと手を伸ばす。
先程使い魔にも言われたばかりじゃないか。自分の爆発の力は戦闘に使える。ギーシュ
はメイジのランクとしては最下級のドットメイジ。勝てない相手ではないはずだ。
――でも……本当に爆発が起こせるの?
しかし、ルイズの手は杖に触れる寸前で止まってしまう。
彼女は気付く。自分が決闘は疎か、魔法を使った戦闘らしい戦闘をした事がない事に。
そもそも、ルイズは自らの意志で爆発を起こした事など一度もないのだ。
もし爆発を起こそうとして、何も起きなければ――その時こそ、自分は本当のゼロにな
ってしまう。
心に灯った火が萎んでいくのを感じる。
10年以上もの間、浴びせ続けられた否定の言葉は、少女から自分を信じる力さえ奪い去
っていた。
無言のまま俯いてしまったルイズを見て、ギーシュは内心でほくそ笑んだ。
-
ギーシュだって、禁止されている決闘を行うような馬鹿な真似をするつもりはない。し
かし、自分に恥をかかせたこの少女をただで帰すわけにもいかない。
――相手はあのゼロのルイズだ。ここまで脅せば、きっと謝ってくるに違いない。それ
を快く許してやり、度量の広さを見せつける。ああ、何と完璧な作戦なのだろう。
周囲の者がギーシュの度量をどう評価するかはともかく、全ては彼の目論見通りに進ん
でいた。そのはずだった。
「――なるほど、貴族同士の決闘は禁止か。勉強になるよ」
不意に、ルイズの背後から聞き覚えのある声が響いた。彼女にはその声が、とても懐か
しいもののように聞こえた。
ギーシュの余裕に満ちた表情が、忌々しいものを見たかのように歪んでいく。
「こっちに来てまだ日が浅いものでね。ついでに教えてくれないか? 貴族と平民が決闘
した場合はどうなるのか」
ルイズが振り向いた先には、不敵な笑みを浮かべる使い魔の姿があった。
-
今回の投稿は以上となります。
なるべくこのくらいのペースで続けられるよう頑張ります。
-
乙です
-
割とどうでもいいシーンをざっくり飛ばしてるのいい感じだと思う
あと、使い魔が何らかの理由で食堂にいなくって、ルイズが止めたからって
ギーシュがルイズに挑むのってたまにあるけど、これはちゃんとわかってポーズでやってるのがいいな
本気でルイズとやろうってのはいくら何でもアレだよなあ
-
こんばんは、焼き鮭です。今回の投下をさせてもらいます。
開始は20:00から。
-
ウルトラマンゼロの使い魔
第八十六話「怪獣は動く」
不動怪獣ホオリンガ 登場
トリステインの一地方の、小さな農村。背景に野山が並ぶ、のどかな空気が流れる平和な土地である。
ここの畑の一つを耕している農夫に、通り掛かった農夫仲間が呼びかける。
「おーい、今日はいい天気だっぺなぁ〜」
「ああ、そうだっぺなぁ。ほんに畑仕事日和だっぺ」
鍬を振るう手を一旦止めた農夫が、仲間と立ち話をする。
「それにしても、戦争が終わってからほんに平和になったっぺなぁ。重くなる一方だった税金も
軽くなって、はぁ〜、まさに女王陛下さまさまだっぺぇ」
「ほんとになぁ。ウチの兵隊に出ていった息子も無事帰ってきたし、ひと安心だっぺよ」
「……けど、ここのところは刺激的なこともすっかりなくなって、何だか退屈だっぺよ。
来る日も来る日も変わり映えのない畑仕事ばっかり。ここらで何か面白いことでも起こらんもんだっぺかな」
「おいおい、そんな贅沢なことを言うもんじゃねぇっぺ。何をおいても、平和が一番! 今度の戦争で
それがよく分かったろうよ?」
「まぁ、そうだどんけどな」
アハハハと朗らかに笑い合う農夫たち。こんな風に他愛ない話で楽しめるのも、平和である証だ。
しかし、ふと背景の山々に目を向けた農夫が、訝しげに目を細めた。
「んん〜……?」
「おい、どうしたっぺ?」
「なぁ……何か、山が多くないっぺか?」
「はぁ?」
おかしなことを言う農夫に、仲間はすっとんきょうな声を上げた。
「何を言うっぺか? 山が多いって……そんなことあるはずなかろうて」
「いやいや、あそこ! いつも見てる景色と、今日はなーんか違う気がするっぺよ!」
農夫が指差す方向に、仲間も顔を向けた。
「そうかぁ? 気のせいだろうよ。落ち着いて考えろよ。山が増えるなんて、いくら何でも
ある訳ねぇっぺ」
「けんど……」
もう一度山地に視線を送った農夫が、ギョッと目玉を剥いた。
「お、おい!」
「あん?」
「今、山が一つ動いたっぺ!」
その言葉に、農夫仲間はとうとうおかしくなったのかと心配になった。
「おめぇ、頭大丈夫っぺか? 山は生き物じゃねぇど。動くかよ」
「け、けど、あれ!」
農夫がしきりに指を差すので、仲間はやれやれと肩をすくめ、指の先へと視線を戻した。
そして彼も、表情を驚愕に染めることになった。
「な、な、な……なぁぁぁぁ――――――――――――!?」
「や、山が動いとるだよぉぉぉぉぉぉ――――――――――――!!」
二人が目撃したのは……野山と野山の間から、「山のような何か」がズズズズ……とゆっくり
移動している現場であった。
毎度お馴染みのトリステイン魔法学院、寮塔のルイズにあてがわれた部屋。
「なぁルイズ……クリスのことなんだけどさ」
「何よ、いきなり改まって」
才人が神妙な面持ちで、ルイズに話を振っていた。
ちなみに二人が座っている場所は、畳の上。そして囲んでいるのはちゃぶ台。何故西洋風文化の
世界のハルケギニアに、こんな不釣り合いのものがあるかと言うと、先日復学したタバサが
持ち込んできたところを発見した才人が、日本にいた頃を懐かしんで譲ってくれるように
頼み込んだからだ。タバサの方も、畳とちゃぶ台をどうしようか少し悩んでいたというので、
快く受け取ることが出来た。そしてルイズの部屋に運び込み、以前寝床にしていた藁を敷いていた
部屋の隅に設置し、才人のスペースにしたのであった。
-
しかしタバサがどういう経緯でこんなものを手に入れたのかはよく分からなかった。
里帰りしていた時に、色々あったみたいだが。
それはともかく、才人はまだ椅子を使わずに直接座ることに慣れていない様子のルイズに言った。
「今日もクリス、独りぼっちだったな。話しかける奴は、俺らだけだった」
「……そうね」
コクリと、ルイズは小さく首肯した。
クリスが学院に編入してから数日が経過していたが、クリスは現在のところ、ルイズと才人以外に
全然友達が出来ていなかった。それどころか、誰も近寄ろうとしない。やはり、クリスの格好や言動、
振る舞いが他と違いすぎるから敬遠されてしまっているようだ。
この状況を、才人は苦々しく思っているのであった。
「クリスのこと、どうにかならないかな。あいつ、時々突拍子もないこと言ったりやったりもするけど、
根は真面目でいい奴なんだぜ。それなのに、腫れ物みたいに扱われるなんてひでぇよ」
この才人の意見に対し、ルイズも渋い顔をしながらも返答する。
「気持ちは分からなくもないけど……貴族って、多分あんたが思ってる以上に閉鎖的なものなのよ。
自分たちにとっての変わり種は、そうそう受け入れようとは思わない……。わたしだって色々と苦労したものよ」
経験談を語るルイズ。確かに、会ったばかりの頃のルイズは周りから「ゼロ」と軽んじられ
半ば仲間外れにされていて、大変そうだったと才人は思い返した。現在はほぼ対等の立場と
なっているが、それは『虚無』に目覚めたことでコモン・マジックを扱えるようになってから……
貴族にとっての「普通」になってからようやくのことだった。
「他にも、貴族社会のしがらみのこともあるわ。その点においては、クリスが他国の王女だと
いうのが一番のネックになってるのよ」
「他国の王女だってのが問題って……他の国の留学生ならタバサとかキュルケとかがもういるし、
何よりクリス、自分のことは王女と思わなくていいって言ってたじゃんかよ」
「クリス自身がそう言ってても、周りが同調するとは限らないわよ。むしろ、クリスに賛同する
者の方が圧倒的に少ないでしょうね。本人がどう言おうとも、周囲はどうしても彼女を「王女」、
つまり「一つの国そのもの」として見るわ。それに親しくしようとするのは、他国に取り入ろうと
してると見られてしまうって訳。そんなマイナスイメージがついたら、貴族社会で苦しい思いを
することになるでしょうね。……「他国の貴族」と「他国の王女」じゃ、その点が大きな違いなのよ。
そしてその意識を変えるのは、所詮一生徒と成り上がり貴族には無理難題よ」
憮然とした才人に、ルイズは諭した。
「何だよ、それ。くっそ、貴族ってのはいちいちめんどくさいな……」
大きなため息を吐いた才人は、論点を変えながら話を続ける。
「でも、俺たち姫さまから、クリスのことをよろしく頼まれただろ。それを反故にするのか?」
アンリエッタのことを出されると、ルイズはうッ、と息を詰まらせた。
「そんなつもりじゃないけど……だからって、具体的にどうしようってのよ。たとえば、
あんたの世界だと転校生はどんな風に扱われるの?」
聞かれて、才人は答える。
「俺の世界じゃ、そもそも身分の違いなんてもんはないし……転校生が来たら、仲良くしようって
歓迎するもんだよ。クラスのみんなで、パーティーとかもするんだぜ」
そう言ったら、ルイズが食いついた。
「パーティー? ……なるほどね。それ、なかなか悪くないじゃない」
「え?」
「貴族の世界も、親交を深める手段として最も用いられるのはパーティーを開催することだわ。
一対一だと変な勘繰りをされるかもしれないけど、不特定多数と平等に接すれば、他意があると
思われる可能性は少なくなるでしょうね」
ルイズの言うことは才人には少し難しかったが、同意してくれているということだけで十分であった。
-
「そっか! ルイズがそう言うんだったら、その方向で行こう! クリスを中心に、学院でパーティーだ!」
張り切る才人だが、ルイズはそのことで違う問題を挙げた。
「でも、パーティーをやるとして、今度はその内容をどうするかを考えないといけないわよ。
何せ、普通のパーティーじゃクリスがまたいらないことを言って、せっかくの席をぶち壊しちゃう
かもしれないし。それに、パーティーするなら少なくとも広間が必要よ。そこを貸してもらう
許可が下りるかしら」
「うッ……まだそんなに問題があるのかよ」
嫌になってくる才人だが、ここで閉口していては先に進まない。
「それじゃまずは、どんなパーティーにするかの案を……」
と言いかけた時に、ゼロがいきなり声を発した。
『話の途中ですまねぇが、一旦そこまでにしてくれ。才人、怪獣がこっちに近づいてるぜ!』
「えッ!? マジかよ!」
途端に才人とルイズは身を強張らせた。
『嘘言うもんかよ。気配が異様に静まってるからなかなか気づけなかったが、一度捕捉すりゃ
はっきりと分かる。もう結構近いとこまで来てるようだ』
「そうか……分かった。どんな奴か知らないが、放っとく訳にはいかないよな」
気配が異様に静まっている、というのが奇異であったが、そこを考えるのは後からでもいい。
才人はさっと立ち上がる。
「怪獣の接近を止めないとな。ってことでルイズ、行ってくるぜ」
「頑張ってね、サイト」
壁に立てかけていたデルフリンガーを背負った才人を、ルイズはひと言だけ告げて応援した。
「デュワッ!」
ウルトラゼロアイを装着すると、ゼロへ変身した才人が光に包まれながら学院から飛び出していった。
才人が変身する少し前、タバサはシルフィードに跨って学院から飛び出し、学院に接近しつつある
怪獣の姿をひと足先に確認していた。直前に空の散歩をしていたシルフィードが、たまたま発見して
彼女に報告していたのだ。
「お姉さま、あれなのよ! ホントに、小山が動いてるみたいでしょ? きゅいきゅい!」
シルフィードが指す先にいるのは、動く小山……と思わせるような、重量級の怪獣であった。
二つの真ん丸とした目玉に、青い胴体からはいくつもの触手を伸ばしている。そして口に相当する
部分には、黄色い花をちょこんと生やしている。それがズズズズ……とゆっくりと学院の方向へと
移動している。
花があることから想像がついたかもしれないが、この怪獣は動物型ではなく植物型。名をホオリンガという。
そしてタバサは、以前に書籍でこのホオリンガの姿形を目にしていた。
「あの怪獣は……トリステインの一地方の伝承を纏めた本の挿絵にあった怪物と瓜二つ」
「お姉さま、あの怪獣のことを知ってるのね?」
シルフィードの問い返しにコクリとうなずくタバサ。
「……確か、現れた場所から一歩も動かずに、土地に栄養を与えた後に山に変貌するという。
その地方では、自然の神として信仰されてたこともあるとか」
「山に変わる? どういうことなのね?」
「そのままの意味らしい」
「……よく分からないけど、そんなシルフィにも分かることが一つあるのね」
シルフィードは地上のホオリンガへと視線を落とした。
「一歩も動かないって、あの怪獣は明らかに動いてるのね。おかしくないかしら?」
「……わたしにも、そこはよく分からない」
そう話していたら、ゼロが現場に到着した。実体化した彼はホオリンガの前に着地して、進行を妨害する。
『待ちな! これ以上は学院には近づかせねぇぜ! そこで止まれ!』
手の平を向けて高々と告げるが、
「キュウウゥゥゥイ!」
-
ホオリンガはまるで聞き入れた様子がなく、速度を保ったまま前進し続けている。それを見た
ゼロが舌打ちした。
『聞いちゃいねぇか。……って言うか……』
ゼロはホオリンガの眼に注目した。おぼろげにしか光が灯っていない。
『どうも正気じゃなさそうだな。……この前のティグリスもそんな感じだったな……立て続けに
そんなのが現れるとは、やっぱり何か恣意的なもんがあるのか……?』
一瞬考え込んだゼロだが、すぐに意識をホオリンガに戻す。
『とりあえず考えるのは、こいつを正気に戻して元の居場所に帰してからだ!』
向かってくるホオリンガに飛びかかっていくゼロだが、ホオリンガはティグリスの時とは異なり、
自発的にゼロに攻撃を仕掛ける。
「キュウウゥゥゥイ!」
胴体から生える長い触手がいくつもうごめき、ゼロへと伸びていった!
『おっと!』
しかしさすがはゼロ、複数の触手を難なく回避。だがホオリンガも諦めず、しつこく触手を振り回す。
『よッ! はッ! とッ!』
正面からの突きを、首を傾けてよけ、袈裟に振るわれたものはくぐり、足元を狙った横薙ぎは
軽く跳び越える。巧みな身のこなしだ。
『へへッ、今度はこっちの番だぜ!』
そろそろ反撃しようとするゼロ。だがその瞬間に、ホオリンガの花から大量の黄色い花粉が噴き出した!
『うわっぷッ!?』
ゼロは突然の花粉をもろに浴びてしまった。それにより、
『は、はぁっくしッ! べっくしッ! く、くそぉ……!』
花粉が呼吸器を刺激し、くしゃみが止まらなくなる。いくら身体を鍛えようとも、こういうものは
どうしようもない。
くしゃみのせいでろくに身動きが取れなくなっていると、地面から触手が突き出てきて、
ゼロの四肢を拘束して空中に持ち上げた!
「キュウウゥゥゥイ!」
『うおわッ!? くぅッ……!』
ホオリンガは捕らえたゼロをそのままギリギリと締め上げる。苦痛にうめくゼロだが、
もちろんやられたままではいない。
『しょうがねぇ……ビリッと行くが、勘弁してくれよ!』
意識を集中し、ツインテールに浴びせたような電気ショックを身体から発した。電撃は触手を通じ、
ホオリンガ本体を痺れさせた。
「キュウウゥゥゥイ!」
『よし、今だ!』
ホオリンガが停止している隙に、ルナミラクルゼロへ変身。素早く浄化技を放つ。
『フルムーンウェーブ!』
光の粒子を浴びて、ホオリンガの触手がダラリと垂れる。そして二つの目玉に青い輝きが灯った。
「キュウウゥゥゥイ……」
ホオリンガは辺りを見回すと、クルリと反転して来た道をそのまま引き返していった。
ホオリンガはもう大丈夫。このまま元々の場所へ帰り、自らの栄養を土壌に与えて野山の一つになり、
自然と一体化するその時を待つ、本来の生態を取ることだろう。
その日の夜、才人は学院の中庭を散策しながら頭をひねっていた。
「う〜ん……クリスのためのパーティー、どんな内容にしたらいいかなぁ……」
ホオリンガ出現で中断していたパーティーの考案を続けているのだが、どうにもいい案が
一向に浮かんでこないのだった。それで気分転換を兼ねて散歩しているのだが、やっぱり
良い考えは出ない。
「先生たちから場所を借りれるかって問題もあるけど、まずはそこを決めないと、どうしようもないよな。
けど、普通じゃないパーティーってどんなんだ? そもそも俺、普通のパーティーってのがどんなもんかも
よく知らないし……」
-
と思い悩んでいたら、背後から声(?)を掛けられる。
「キュー」
「ん?」
振り返ってみると、そこにいたのはクリスの使い魔、デバンだった。
「デバン。お前、こんなところで一人で何やってるんだ? クリスの傍にいなくていいのかよ」
思わず尋ねかけた才人だが、すぐに苦笑する。
「って聞いても、人の言葉なんて話せないか……」
「そういう君も一人じゃないの。お互いさまだね」
そう思った矢先に、返事が来た。しかもかなり渋みのある声。
「……えええええええええ!? デバン、今しゃべったのお前か!?」
「うん、私がしゃべったよ」
「お、お前、しゃべれる怪獣だったのかよ!」
「いや、元々は人の言葉は話せなかったよ。これはお嬢と契約した影響だね」
お嬢というのは、言うまでもなくクリスのことだろう。
「けど、しゃべれるんだったら何でいつもは『キュー』なんて鳴いてるんだよ」
「それはあれだよ。私はお嬢のマスコットだからね。それが渋い声でしゃべっちゃダメでしょ。
女の子の夢が壊れちゃう」
「マスコットって、そんな濃い顔でよく言うな……」
若干呆れた才人であった。
「まぁそれはいいや。で、お前は俺に何の用だ?」
「ああ、そうだったね」
デバンは気を取り直して、才人に聞き返す。
「今、お嬢のためのパーティーがどうとかって話してたけど、どういうこと?」
「聞いてたのか。実はな……」
才人は、クリスが学院で孤立しているのを気に掛けていること、それをどうにかする手段として
パーティーを立案中であることを説明した。すると、デバンはジーンと感動する。
「ウチのお嬢のことをそんなに考えてくれるなんて……君ってすごくいい子だねぇ。さすが、
お嬢が見込んだサムライだよ! うん、実に素晴らしい!」
「いやぁ、それほどのことじゃないさ」
称賛されて少し照れた才人だが、デバンは声のトーンを変えてこんなことを語り出した。
「でも、実はお嬢、この国には勉強をするためだけに来たんじゃないんだよね。お嬢のことを
心配してくれてる君には話すけど」
「へ? クリス、留学生じゃないのか……?」
「表向きはそうなってるけどね、本命は別にあるのさ。お嬢は、ある使命を帯びてこの国に来たんだよね」
突然の重々しい話に、才人は目を見開いて驚く。
「使命って……」
「その使命を終えたら、すぐに国に戻ることになってるの」
「すぐに? そんなに早く帰らなくちゃいけないのかよ?」
「何せ王女だからねぇ。本当なら、そうそう国を空けてちゃいけないんだよ」
デバンの説明に、才人はクリスもアンリエッタ同様、色んな制約の下に生きているのだと
いうことを薄々感じた。
「それで国に帰ったら、ルイズと彼女の使い魔の君ならともかく、ここの学院の人々とは
もう二度と会うことはないだろうね」
「そんな……」
「そういうこともあって、お嬢自身周りと馴れ合う気がないんだよ。それに自分の立場ってのも
よーく分かってる。だから孤立してるんだよ」
デバンの言うことを、才人は受け入れがたかった。
「ホントにそれでいいのかよ……。クリスだって、一人ぼっちで寂しいんじゃないのか?」
「本心じゃそうかもしれないけど、すぐにお別れになるだろうからね。後が辛くなるのを考えると、
必要以上に仲良くなりたくないと考えちゃうのさ」
「けど……」
「サイトくん、君はお嬢を本当に心配してくれてる。それは私としても嬉しいよ。けど、お嬢の事情も
分かってあげてほしい」
-
そう言われては、才人に反論の言葉は見つからなかった。代わりに、デバンにこう尋ね返す。
「でも、そのクリスの使命って何なんだよ。この学院に、どんな用があるんだ?」
しかし、デバンからははっきりとした答えは得られなかった。
「そこまでは私からは話せないねぇ。何せ私はあくまで使い魔だ。そこまで重要なことを、
独断で教える訳にはいかない」
「そうか……」
「まぁ、お嬢はサイトくんを友達だと思ってる。君の力が必要だと思ったら、お嬢自らが話すさ」
それでデバンからの話は終わりであった。
「話、聞いてくれてありがとね。もちろん、このことはお嬢には秘密にしておいてね」
「言われなくても分かってるって」
「ありがと。じゃ、私はお嬢のとこ戻るから。キュー!」
最後にひと鳴きして、デバンはひょこひょこと中庭から離れていった。
「……すっげーギャップ、あの声……」
デバンの背中を見送った才人は、ふと考える。クリスの事情ももちろんのことだが、
一番気にかかったのはクリスの使命とやらだ。王女自らが果たさなければならないほどの
使命とは、一体どんな内容なのか。
あの気持ちの良いクリスのことだ、まさかトリステイン侵略などを考えているのではあるまい。
しかしそうでないのなら、わざわざ他国の学院に何をしに来たというのだろうか?
その答えは、どんなに考えを巡らそうとも出てくることはなかった。
-
ここまで。
まさかの畳とちゃぶ台がレギュラー化。
-
ウルゼロのかた、乙ですー。
そして皆様、お久し振りです。
よろしければ21:45頃から、また続きを投下させてくださいませ。
-
「ふうん。ディー君にもそんな経験があったのね。
ちょっと意外だけど、熱くなれる男の子って素敵だと思うわ」
そんな場違いに暢気な感想を漏らすキュルケを軽く睨んでから、ルイズは困ったように眉根を寄せてディーキンを見つめた。
「その……、あんたの経験したことはわかったし、私には、なんて言っていいのかわからないけど。
それじゃディーキンは、タバサが復讐を続けるべきだと思うの?」
ルイズとしては、何があろうと友人が身内と血で血を洗うような復讐を繰り広げるところなど見たくはなかった。
もちろん、その結果起こるであろう国家規模の戦争などは言うにも及ばない。
ディーキンなら、大切な自分のパートナーなら、きっとそれに賛同してくれると思っていたのだが……。
自分の経験から復讐に駆り立てられる気持ちもわかるといわれてしまうと、そんな経験のないルイズとしては言葉に詰まってしまった。
絶対に賛成ではないが、軽々しく否定するのもなんだか申し訳ないような気分になる。
「イヤ、ディーキンは別に賛成とか反対とかってわけじゃないの。
思うに、復讐をどうするかとかを決めるより先に、まずはもっと詳しく調べてみるのが最初なんじゃないかな?」
「もっと……詳しく?」
そう聞き返してきたタバサの顔を見つめて、ディーキンは頷く。
「そうなの。つまり……、タバサのお父さんや伯父さんが、実際にどんなことを考えて、何をやってたのかとかをね。
よくわからないのに決めつけて行動をしたら、取り返しがつかなくなるってこともあるでしょ?」
そう言ってから、ふと何かを思いついたように、リュートを手に取った。
「ええと、なんだかお話ばかりしちゃってるけど……。
ディーキンはひとつ、そういう事に関するお話を知ってるから、それをお聞かせしたいと思うの」
「え、また別のお話をされるのですか?」
話を終えたばかりのディーキンに、気を利かせて飲み物などを運んできたシエスタが、首を傾げた。
「そうなの。でも、今度はちっぽけなディーキンのみっともない体験談じゃないよ。ディーキンの昔のご主人様が大好きなお話。
バードは、いろんな説話なんかをお聞かせするのも仕事だからね。昔よくご主人様に聞かせてたの。
ディーキンは、あんまり好きってわけじゃないけど……」
「あんたの、昔の主人が好きだった話?」
ディーキンはルイズに頷き返すと、ちらりと周囲の反応を伺った。
どうやら皆、聞くことに意義は無さそうだと確認すると、咳払いをして演奏を交えながら語り始める。
「――――これは、遠い遠い、人間の王国の話なの。
そこには人間の王様がいたみたいだから、人間の王国って呼んでるんだけどね」
「とにかく、その国には王様を良く思わない人が大勢いて、その人たちが反乱を起こしたけど、王が彼らのリーダーを捕まえたの。
彼は、王様の従姉妹の貴族で、ええと……、名前を忘れちゃったけど、ジョージってことにしといて」
「王様は怒って、反逆者の名前をぜんぶ吐かせるために、彼を拷問しろって命令したの……。
卑劣で残忍な拷問執行人は、彼の足の指を切り落としたの」
「すごい痛みだったけど、彼は名前を言わなかった。
そこで、今度は指を切り落としたの。彼は金切り声を上げたけど、やっぱり同志の名前は言わなかった。
そこで、次は鼻を切り落とした。でも彼は話さなかった。
そこで、次は耳を切り落とした、その次は足を、それから、手を……」
-
そこまで話して、残酷な拷問の話にルイズやシエスタが顔をしかめているのを見て取ると、ディーキンは肩を竦めた。
「……アア、ディーキンもその気持ちはよくわかるよ。
だけど、前のご主人様はこんな趣向の話が好きだったの。信じられないよね?」
「あなたの主人は、悪意のあるドラゴンだったと聞いた」
タバサの言葉に、ディーキンは首肯した。
「そうなの。ご主人様は他にも、無力な乙女がドラゴンに食われるって話とか。
英雄がそれを止めようとするけど、やっぱり食われるって話とか。
勇敢な女騎士を倒して蹂躙して、屈服させて、助けに来た彼女の婚約者の前でいろいろして、最後は2人とも食べちゃうって話とか……」
「ふーん、なかなかいい趣味の御仁だったようね。
その最後のやつとか、今度私の部屋で聞かせてくれないかしら。
タバサも一緒に、どう?」
「……いい」
キュルケはむしろ楽しそうにそんなことを言って、ルイズにぎゃあぎゃあ文句を喚かれていた。
タバサやシエスタは、顔を赤くしている。
ディーキンは咳払いをして、話を戻した。
「エヘン。とにかく、彼は……。
ええと、彼の名前はなんだっけ。ラローシュだったかな?」
「ジョージ」
タバサが律儀に訂正する。
「そうそう、ジョージは……、どれだけ痛めつけられても、話さなかったの。
そこでようやく王様は、彼に一目置いたんだよ。勇敢だ、って。
彼のことを褒めて、反逆者ではあるがこれ以上苦しませないため、拷問をやめて一思いに殺してやるようにと命じたの」
「当然ね。それが、誇り高い貴族に対する扱いというものだわ」
少し胸を張ってそう言うルイズに、しかしディーキンは、いかにも悲しそうに軽く首を振って見せた。
「ああ、でも、それは間違いだったの……。
王様は、彼が本当に望んでいることが何かをわかってなかったし、ジョージも話せなかったんだよ」
怪訝そうにするルイズたちに対して、ディーキンは話を続けた。
「執行人が手斧を振りかざすと、ジョージは大声で叫んだの、『やめろ! 話すから!』って。
でも時すでに遅く……、手斧は振られて、彼は息絶えたの」
「…………」
「つまり、ジョージはただただ、殺されたくない一心で黙ってたの。
話したらそれきり殺されてしまうんだってよくわかってて、どんな痛みよりも死ぬ方が嫌だったんだね。
王様は彼のことを尊敬して、慈悲をかけてやろうとしたんだけど……、かえって彼の、一番望まないことをしてしまったんだよ」
-
何とも言えない顔をしている一同に向かって、ディーキンは質問した。
「この話の教訓は、何か分かる?」
顔を見合わせるルイズらに、ディーキンは指をぴっと立てて、先を続ける。
「わからない? つまり……。
『相手が怖じけづく前に、手斧でぶっ殺すのはNG』ってことなの」
「……は?」
「うーん……、いや、ディーキンの言い方が悪かったかもね……」
聞いて損したわ、というような顔つきになったルイズを見て、ディーキンは言い方を考え直した。
「……ええと、つまり。ディーキンが、何を言いたかったかっていうと。
本当に相手のことがわかってないうちは、どうするのが正しいかも判断できないってことなの。
このお話の王様みたいに、相手のことをよく知りもしないで、思い込みでうっかり殺しちゃってからじゃいろいろ手遅れでしょ?
死んだら生きられないし、相手に何か話そうと思っても、生き返らせない限りはどうにもならなくなるからね」
(……生き返らせる?)
タバサは、ディーキンの話し方に妙な引っ掛かりを覚えた。
生き返らせない限り? そんなことは、そもそもできないではないか。
(それとも……)
そこまで考えて、タバサははっとして頭を振ると、その思考を打ち消した。
自分は先日、シルフィードの上で見た温かくも奇妙な夢を思い出して、あらぬ期待を抱いているのだ。
彼は確かに、私の勇者かもしれない。
でも、ここは現実だ。御伽噺の世界ではない。
(夢を、見過ぎてはいけない)
「まあ、その妙な例え話はともかくとして。
それは、その通りでしょうね」
タバサの思惑をよそに、ルイズが頷いた。
「でしょ? だから、タバサはもっと詳しいことがわかるまで、様子を見るのがいいんじゃないかな。
復讐をするとかしないとかの前に、まずはもっと情報を集めるの。
冒険に出る前に情報を集めるっていうのは、冒険者の間でも基本だからね!」
そこへ、気を取り直したタバサが口を挟んだ。
「……あなたのいうことは、もっともなことだと思う。
だけど、どうやって調べるの?」
正しい知識を得ることが重要だというのは、暇さえあれば書物に目を通しているタバサにもよくわかる。
しかし、そうはいっても……。
母から聞いた話以外で、当時の父や伯父がどう考えてどう行動していたかなどを、果たして詳しく調べることができるだろうか。
当人たちに聞こうにも、父の方は既に死んでしまっているし、伯父から話を聞くことなどできようはずもない。
当時父の周囲にいた取り巻きたちを調べ上げて、話を聞きに行くという手もあるかもしれない。
しかし、それには時間もかなりかかるだろうし、第一彼らが潰えた反乱の目論見などを、いまさら正直に話してくれるものだろうか?
-
「そうだね。まず、タバサのお父さんがその頃に書いたものとか、何かお屋敷の方には残ってないの?」
「……わからない。処分されていなければ、父の私室にあるかもしれない」
「だったら、もしかしたらその中に手掛かりがあるかもしれないの。
タバサのお母さんからもう何日か、聞けそうなことを聞いてみてから、一度調べに戻ったらどうかな」
「わかった」
タバサはそう答えながらも、大したものは見つかるまいと考えていた。
反乱の疑いをかけられた父の私物や何かは、既に王宮側が一通り確認し、めぼしいものは回収してしまっているはずだ。
いまさら自分たちが調べ直しても、何も残ってはいないのではないか。
そうでなくとも、仮に反乱などを企てていたとしたら、あの賢明な父が私室にその明白な証拠などを残してはおくまい。
「あとは……。うーん、ディーキンの方にも、いろいろと考えはあるの。
でも、上手くいくかどうか、ちょっと考えてみてからだね」
真っ先に思い浮かんだのは、それこそタバサの父親を生き返らせて、彼の口から直接聞いたらどうか、ということであった。
死者の……、それも何年も前に死んだ者の蘇生など、ハルケギニアでは思いもよらぬことだろうが、フェイルーンではそうでもないのだ。
そうすれば確実に真相がわかるだろうし、タバサやオルレアン公夫人、ペルスランやトーマスらだって喜ぶのではないか。
生き返った後の政治的な問題等はいろいろとあるかもしれないが、将来の心配を言い訳にして目先の正しい行動をしないのは英雄ではない。
少なくとも、ディーキンはそう考えているし、“ボス”だってきっと同意してくれるはずだ。
しかし、ディーキンはそれとはまったく別の理由から、その案を実行するのは現時点では難しいだろう、と考えていた。
(タバサのお父さんが、ちゃんと生き返って来てくれればいいんだけどね……)
以前に自分が死んだ時のことを思い返す。
これまでにずいぶん死んだことがあるが、その度に何やらいろいろと奇妙な経験をしたものだ。
生き返ると死んでいた間のことは大概ぼんやりとしか思い出せなくなるのだが、はっきり覚えていることもいくらかはある――――。
-----------------------------------
一番最初に死んだときは、いつの間にか暗い洞窟の中にいて、目の前にコボルドの神・カートゥルマクが立っていた。
彼は何やら自分に対して説諭とも謝罪ともとれるような謎めいた事を述べた上で、元の場所に戻してくれた。
今となっては、邪悪な神であるカートゥルマクが、自身の教義に従わない者に対してそのようなことをしてくれるとは思えないが……。
あれは本物ではなく、自分の心が生み出した幻だったのだろうか?
-----------------------------------
-
アンダーダークでメフィストフェレスになすすべもなく殺された時には、気がつくと楽園にいて、天使に取り囲まれていた。
彼らはずいぶんとディーキンのことが気に入ったようで、ちやほやしてずっとそこにいるように勧めてくれた。
だが、元の世界にいるボスのことが心配でたまらなかったディーキンは、とてもそんな気持ちになれなかった。
『ディーキンが天国になんていられるわけないの。早くあっちに戻して!』
そんなことを言っていつまでもじたばた暴れているうちに、ようやくボスが呼び戻してくれて生き返れた。
まあ、暖かい天国から没シュートされて一転カニアの氷結地獄に行かされたのは、暴れたせいで天罰が当たったというわけではあるまい。
-----------------------------------
真っ暗な中で、なんだかよくわからない怒ったような男性の声が聞こえてきたこともあった。
『ジーザス! ファック! 半分以上残ってたディーキンのヒットポイントが、ファッ糞ドロウの急所攻撃であっという間に溶けちまった!
ま た ロードしてアンダーダークに潜り直しか!
まるで巨大な犬のクソだ、バッファローの下痢便を耳から流し込まれる方がマシだ!』
……そうしてなにがなんだかわからないうちに、強い力でずりずりと引きずり戻されるようにして生き返った。
-----------------------------------
――――ただ、いずれにしても。
いざ生き返るその時には、苦しく長い旅をしたような感覚を覚えた、という点では共通していた。
物質界の側で見れば蘇生はごく短時間のうちに終わるが、時間の感覚の異なる霊魂にとってはそうではないのだ。
生きている者なら、おおよそ誰しもが死にたくないと思うのは当然だ。
これまでのすべてに別れを告げて、生から死へ移行することは辛く苦しい経験であるに違いないと、誰もが教わらずとも感じている。
ならば、死者が懐かしい現世へ生き返れることを喜ばないはずがあろうか……と、考えるのは早計というものだ。
生から死へ移行するのが苦しいのと同様に、死から生へと移行することもまた苦しいことを、死者は直観的に感じとるものだ。
そして何度も生き返った経験のあるディーキンは、それが事実であることを身をもって知っている。
それどころか、後者の方が自然な世界の理に反している分、より一層苦しくさえあるのだ。
はたしてそれほどの苦しみに耐えてまで彼らが生き返りたいと思ってくれるか、というのが問題なのである。
死んでも成し遂げたいほどの目標を持っている生者が少ないのと同様、生き返ってでも成し遂げたいほどの未練がある死者も少ないものだ。
死んでから長い時間の経っている死者であれば、なおさらのことである。
時間が経つほどに死後の世界にも慣れていき、現世への執着も次第に薄まってくるのが普通だからだ。
何百年も前の英雄を蘇生させて助力を求めようといった試みは、そのために失敗することが多い。
過去の偉大な人物は、現在のことは現在の人々に委ねるべきだと考えているのである。
また、場合によっては死者の魂が既に分解されていたり、転生していたりするケースもあり、その可能性も時間が経つほどに高まる。
加えて、下位の蘇生呪文による復活は、上位の呪文によるそれよりもより一層苦しいものになる。
非常な苦しみを伴うがゆえに、生き返る際に力の一部分を失ってしまうことになるのだ。
そう言った力の喪失を引き起こさない、比較的苦しみを伴わぬ“完全な”復活は、最も強力な呪文によってのみ成し遂げられる。
-
死者の魂には事前に自分を生き返らせようとしている者の名前や属性がわかるし、その復活がどのくらい苦しいものになるかも概ねわかる。
そして死者の側が拒否すれば、どれほど強い力を持つ術者であろうと、蘇生の試みは決して成功させられない。
もし死者の意志に反して生き返らせるなどということができるのならば、世の中はとんでもないことになってしまうだろう。
たとえば、邪悪な支配者は既に死んだ敵でも生き返らせて捕え、満足して飽くまで、殺しては生き返らせて拷問し続けられるのだから……。
そのような死者の意思を無視した蘇生を行なえるほどの力を持つのは、神格だけなのだ。
そういった諸々の条件を踏まえた上で、ディーキンがシャルル大公を復活させようとした場合の成功率を考えると……。
普通に判断して、復活してきてくれる可能性は相当に低そうだと言わざるを得まい。
既に死んでから数年が経過しているというのに、いまさら苦しい思いをしてまで生き返りたいと思ってくれるかどうかがまず問題だ。
仮に彼が評判通りの善い人物で、何処かの天上の世界で安らぎを得ているのならば、なおさら生き返る気がしないだろう。
セレスチャルか何かの来訪者に、既に転生してしまっているという可能性もある。
おまけにいくら属性が善であっても、名前も知らないどこかの亜人に生き返らされるなんて、何があるか分からなくて応じる気になれまい。
無論、実の娘であるタバサや、妻であるオルレアン公夫人が蘇生を試みれば別だろう。
だが、彼女らには蘇生呪文を自力で唱えることも、スクロールやスタッフ等のマジックアイテムから発動することもできない。
そして蘇生の呪文は、世界の大きな法則に介入するがゆえに、神格に助力を願うにあたって捧げなければならない対価が非常に高い。
低レベルの蘇生呪文である《死者の復活(レイズ・デッド)》でさえ、5000gpもするダイヤモンドが必要になるのだ。
ディーキンの場合はスクロール等で使うので、実際にダイヤを用意するわけではないが、費用は自分で唱える場合以上にかかる。
かくも望みが薄いのでは、さすがに、僅かな可能性にかけて試してみようかという気にはなれなかった。
それでもいよいよとなれば、やってみるしかないかもしれないが……。
(やっぱり、タバサのお屋敷とかを調べるのが先だね)
現地で《伝説知識(レジェンド・ローア)》の呪文を使えば、何かわかるかもしれない。
調べたい場所はたくさんある、タバサの父の私室、彼が暗殺された現場、先王が遺言を残したという臨終の床……。
そして今、自分の荷物の中には、フーケ騒動の時に最後の切り札として使うつもりでボスから送ってもらったスクロールも入っている。
これを使えば、過去に何があったのかをより詳しく調べることも可能だ。
ただ、一枚しかないので使いどころをよく考えなくてはならない。
最悪の場合にはヴォルカリオンから買い足すこともできるかもしれないが、これはかなり高価で希少な品なのだ。
自分の所持金は無尽蔵にあるわけではない。
一体何を調べるのに使うのが最善か、それを見極めるためにもしっかり情報を集めなくては。
(それに、ボスに頼んでナシーラに連絡が取れれば、タバサのお父さんのこともなんとかなるかも……)
彼女はアンダーダークの大都市メンゾベランザンの魔法院(ソーセレイ)で修業した高位のウィザードで、多彩な呪文を心得ている。
その中には、ドロウ秘蔵の呪文書に記載されている、希少で強力な呪文も含まれているのだ。
特に、以前に“ママ”の魂が幸せかどうかを確かめるために、ナシーラに頼んで使ってもらったあの呪文。
あれがあれば、タバサの父親のこともなんとかなるかもしれない。
(なんにしても、明日からいろいろ調べたり、準備をしたりしなくちゃね)
それに、せっかくボスに頼んで必要になりそうな本や機材なども送ってもらったことだし。
そろそろ腰を落ち着けて、サブライム・コードとしての本格的な訓練にも取り掛かりたいのだが……。
(……やることがいっぱいあるね。
ウーン、ウォーターディープにいた時より忙しいかも……)
ディーキンはひとまず考えを打ち切ると、今夜の集まりをお開きにして、ルイズらと共に学院に戻って休むことにした。
-
今回は以上になります。
またできるだけ早く続きを書いていきますので、次の機会にもどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、失礼しました(御辞儀)
-
二人ともおつっす
>986
>王様の従姉妹
特に性別を表さない場合でも、「兄弟」と同じで、「従兄弟」じゃないかな?
-
>>993
ご指摘ありがとうございます、その通りですね。
直しておきますー。
-
次スレ立てていいんかな
-
あの作品のキャラがルイズに召喚されましたin避難所 3スレ目
ttp://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/otaku/9616/1456320335/
立てました。何か間違ってたらごめん。
-
たておつ
-
>>996
乙
-
モサキコ 、─- 、 ヽ `ヽ,,
ヽ '゙'""~ ヽ モサキコ
モサキコ ,ミ ´ ∀ ` ミ
ミ ミ,.,)┳(,.,.ミ モサキコ ,ハ,_,ハ
ミ. ┃ 'ミ ,:' ´∀`';
゙ミ ┃ ミ゙ ミ,;:.O┬O
((( ◎━ヾJ┻◎゙ ((( ◎-ヾJ┴◎
-
lミヽ、 _,,_,,_ノミ、
| ミ ,.:'"~ ~ヾ
ミ,∩ ´ □ `゚ l∩ ふあ〜
ミ'゙ミ ヾ ミ
ハ,_,ハ ミ, ` メ
,:' ´-``: ゞ, ~''∩ ∩ミ
ヾwj人jj人vvミ:.,0,,0彡w,,.jj从vv,W,,,,し',,从,,...U彡,wwノし〃
o
,, ,,_ _,,. O
,:''~_ミ-l ミ`,.-―-<ミ |
ハ,_,ハ ,: '~ ly' ヾ!
,:-` '; ミ ミ _ _ ミ
c' u ミ ミ .,:! 〜 ミ
ヾwj人jj人vv""ヾ),, w,,.jj从vv,W,,,,彡,,("~つ,,_,,⊂~,,彡ノし〃
|
|
|
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板