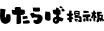レス数が1スレッドの最大レス数(1000件)を超えています。残念ながら投稿することができません。
一足先に魔法検定試験会場
-
>>995
同じように弾かれた男が、自由落下をかましながらもどうにか着地出来たのは、風による姿勢制御が間一髪で間に合ったおかげだろう。
「……馬鹿力だな」
最善を望めた状況でないに関わらずも、自身が放った一撃は相当な物だった筈だ。それも相手が剣を打撃武器として使うという加減を想定した上での蹴撃。
それがまさかこのような結果になるとは。骨にヒビでも入れられたかと思う衝撃を感じる右足に目をやりながら、男は低く呻いたものだった。
だが、それでもくつくつとなる喉と、抑えきれないような笑みがはっきりと浮かんでいた。
「だが、上等」
それは、相手の強さを認め、称賛すると同時に。それを乗り越えんとする自分を鼓舞するかのようなものだった。
とは言え、男も最前のように飛び跳ねるとはいかなくなったようだ。それに加えて先ほどの傷も癒えていない。状況としては芳しい物ではない事は
男もよく理解していたことだろう。
模擬戦ならば、いっそここいらで試合を中断……というのも選択肢としてはありなのだろうが、男はそれを良しとはしなかった。
ふぅと息を吐いて、未だ土煙に紛れる相手に向かって言葉を投げかける。
「……なぁ、死霊王の術ってのはよ。そんな小手先ばかりの術じゃあねぇんだろ?」
瞬間。渦巻くマナの奔流は、男が大魔術を使おうとしていることを砂埃の中にいるベルンにも否応なしに理解させる。
それが模擬戦にしては少々度を越したものである、ということもだ。だが、男の翠瞳は、一点の曇りもなく、正気である事も教えていた。
「だったらよ、そいつを俺に見せちゃあくれねぇか」
そう、模擬戦と言えども加減をしていたのであれば互いの実力を碌に測れもしない。それに加え、このお互いにダメージを負った状況下で力を抑えながら戦えば、泥仕合ともなりかねない。
ならばとトームが考えたのはこのような状況を一転させるような大技を駆使する、というもの。
見方を変えるのなら、ベルン程の実力者ならばこの一撃に耐え得る確信がこの男にはあるという事であった。
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板